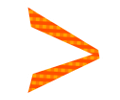<< 2:00~3:00




─────────────────────────────────
【3】
むかしむかし、とある山の麓にて。
一組の男女が、仲睦まじく暮らしておりました。
男の名は、荊尾 瀬渡(かたらお せと)。
生まれつき目の見えない男。
女の名は、荊尾 揺律音(かたらお ゆりね)。
鼠色の肌、深緑の髪。常人とは思えぬ見目の女。
そんな二人が住まう小屋には、いよいよもって人が来ません。
あの山には何かある。何かに憑かれた男がいる。化け物のような女がいる。
口さがない噂ほど広まるのも早いもの。
瀬渡と揺律音は、山の麓の小屋でふたりぼっち……
なので、とても幸せでした。
ふたりで山に入っては、瀬渡は揺律音に山の様々なことを教えました。
山の幸の在処、罠のかけ方、雨に降られた時の退避場所……。
一方の揺律音は、瀬渡の世話を焼くようになります。洗濯、食事、風呂の支度など。
と言うのも、瀬渡の“解る”範囲には何か偏りのようなものがあり……
特に料理の味が、ひどいとは言わないまでも、何か色々味が足りなかったのです。
そうして、お互いがお互いを補いながら、日が過ぎて行きます。
自分のことをとやかく言うことのない、自分に優しいひとが傍にいる。
他の人間など気にする必要がどこにありましょう。
山の麓に二人きり。慎ましやかながらも幸せな日々は、一日、一日と過ぎて行きます。
ある日。
瀬渡と揺律音は、同時に目が覚めました。
新月の夜。月の明かりがまるでない外は、真っ暗で。
朝日が昇るにはまだまだ時間がかかりそうな、そんな刻限。
「瀬渡さま」
「ああ。山に、誰かが入ったようだ」
不吉の象徴と吹聴されるこの山に、わざわざ踏みいる者がいたとして。
考えられる目的など、そう多くはありません。
まして揺律音はこの山に捨てられた身。あの時の不安は、恐怖は、未だに拭えず。
けれど、だからこそ。
「お前はここで、」
「いいえ瀬渡さま。わたくしもお供致します」
強い意思。
男を射抜く、蒼色の瞳。
「──分かった。では、行こう」
こうして男女はしっかりと手を繋いだままに、暗い山道を歩み、そして……
やはり置き去りにされていた老人を、無事見つけることができたのでした。
それから、似たようなことが何度もありまして。
麓の小屋は、いつしか二つになり、三つになり……
やがて小さな村のようになっていきました。
山に捨てられる者。
世を捨て、山に逃げてくる者。
いずれも訳ありの者ばかりでしたが、瀬渡と揺律音の二人は構わず受け入れます。
初めは二人を気味悪がった来訪者たちも、その心根と懐の広さに触れるにつれ、
やがて彼らに協力するようになっていきました。
となると、悪人も少なからず紛れ込む筈、なのですが。
不思議なことに瀬渡と揺律音の二人には、それが悪人だと分かっているかのようで。
性根のねじくれた人間を迎え入れることは、ただの一人もありませんでした。
山に潜み、村に財が無いか探ろうとした泥棒もおりましたが、
決まって崖から落ちたり、獣に襲われたりして、無事に山を出ることはなく。
二人に救われた者たちは、そのことを不思議に思いながらも、
ついぞ二人に尋ねることはありませんでした。
だってここにいる限り、平穏が得られるのですから。
わざわざ余計なことを知って、その結果帰りたくもない町に戻らなければ
ならなくなる、なんて絶対嫌だったのです。
世捨て人の村。
人の中にいられなかった者たちの村。
不思議なことに、そこには大きな争いもなければ
欲による奪い合いなども起こりませんでした。
皆、そういう“醜さ”を目の当たりにしてきた者たちだったので、
そういうものになりたくなかったのでしょう。
だから、ひとが増えても、村は穏やかで。
緩やかで。あたたかで。
それぞれの得意とする技で皆が、皆を支え。
そんな日々が、二年も過ぎたころ──
「やあ、旦那、めでてえなあ!」
「ほんにのう。よく、揺律音さまも頑張りなさって」
「名前は……決まったのか……?」
「お、お、お、おん、なの、こ、こ、こ、」
「ようけ泣くわあ。こら大物になりますえ」
村の面々に囲まれて。
布団に寝そべったまま、いとおしそうに『我が子』を撫でる揺律音。
その隣で、はち切れんばかりの笑みを浮かべた瀬渡は──
一同を見回すとひとつ、大きく頷いて。
「娘の名は、水渡里(みとり)。
水と里を渡すと書いて、水渡里だ」
この世に生を受けたばかりの赤子に。
長く語り継がれることになる名前を、授けるのでした。
─────────────────────────────────



ENo.101 イクコ とのやりとり

ENo.102 安里杏莉? とのやりとり

ENo.122 よつね とのやりとり

ENo.189 水野 杏梨 とのやりとり

ENo.216 ヒビキ とのやりとり

ENo.224 鳴 とのやりとり

ENo.260 貴登子 とのやりとり

ENo.273 闇 とのやりとり

ENo.382 イオリ とのやりとり

ENo.383 レオン とのやりとり

ENo.432 カンナ とのやりとり

ENo.513 十神 とのやりとり

ENo.582 リョウ とのやりとり

ENo.612 チホ とのやりとり

ENo.723 放課後探検部 とのやりとり

ENo.1072 フーコ とのやりとり

ENo.1104 刀崎 依良 とのやりとり

以下の相手に送信しました




闇(273) に ItemNo.9 白樺 を手渡ししました。
闇(273) から 松 を手渡しされました。











響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ItemNo.9 松 から射程3の武器『左天白陽・改』を作製しました!
⇒ 左天白陽・改/武器:強さ67/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
シェンラン(163) により ItemNo.10 爪 から防具『藍の羽織』を作製してもらいました!
⇒ 藍の羽織/防具:強さ67/[効果1]反撃10 [効果2]- [効果3]-
あかり(869) により ItemNo.6 右天黒月 に ItemNo.8 ねばねば を付加してもらいました!
⇒ 右天黒月/武器:強さ40/[効果1]闇纏10 [効果2]衰弱10 [効果3]-【射程2】
ルカ(857) とカードを交換しました!
デッドライン (デッドライン)

ブレイドフォーム を研究しました!(深度0⇒1)
アクアブランド を研究しました!(深度0⇒1)
ウォーターフォール を研究しました!(深度0⇒1)
エチュード を習得!
マーチ を習得!
コールドウェイブ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ミツフネ(161) は ネジ を入手!
詩穂乃(191) は ド根性雑草 を入手!
闇(273) は ネジ を入手!
闇(273) は 花びら を入手!
闇(273) は 羽 を入手!
ミツフネ(161) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
詩穂乃(191) のもとに ダンデライオン が軽快なステップで近づいてきます。
詩穂乃(191) のもとに キラービー がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
詩穂乃(191) のもとに 歩行石壁 が泣きながら近づいてきます。



闇(273) に移動を委ねました。
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 J-17(森林)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 J-18(森林)に移動!(体調12⇒11)
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- ミツフネ(161) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 詩穂乃(191) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 闇(273) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――















仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














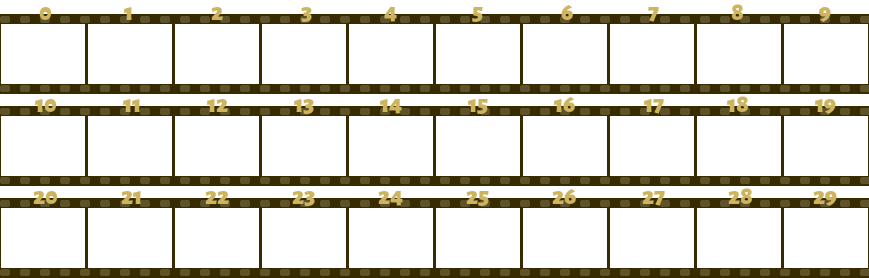





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



─────────────────────────────────
【3】
むかしむかし、とある山の麓にて。
一組の男女が、仲睦まじく暮らしておりました。
男の名は、荊尾 瀬渡(かたらお せと)。
生まれつき目の見えない男。
女の名は、荊尾 揺律音(かたらお ゆりね)。
鼠色の肌、深緑の髪。常人とは思えぬ見目の女。
そんな二人が住まう小屋には、いよいよもって人が来ません。
あの山には何かある。何かに憑かれた男がいる。化け物のような女がいる。
口さがない噂ほど広まるのも早いもの。
瀬渡と揺律音は、山の麓の小屋でふたりぼっち……
なので、とても幸せでした。
ふたりで山に入っては、瀬渡は揺律音に山の様々なことを教えました。
山の幸の在処、罠のかけ方、雨に降られた時の退避場所……。
一方の揺律音は、瀬渡の世話を焼くようになります。洗濯、食事、風呂の支度など。
と言うのも、瀬渡の“解る”範囲には何か偏りのようなものがあり……
特に料理の味が、ひどいとは言わないまでも、何か色々味が足りなかったのです。
そうして、お互いがお互いを補いながら、日が過ぎて行きます。
自分のことをとやかく言うことのない、自分に優しいひとが傍にいる。
他の人間など気にする必要がどこにありましょう。
山の麓に二人きり。慎ましやかながらも幸せな日々は、一日、一日と過ぎて行きます。
ある日。
瀬渡と揺律音は、同時に目が覚めました。
新月の夜。月の明かりがまるでない外は、真っ暗で。
朝日が昇るにはまだまだ時間がかかりそうな、そんな刻限。
「瀬渡さま」
「ああ。山に、誰かが入ったようだ」
不吉の象徴と吹聴されるこの山に、わざわざ踏みいる者がいたとして。
考えられる目的など、そう多くはありません。
まして揺律音はこの山に捨てられた身。あの時の不安は、恐怖は、未だに拭えず。
けれど、だからこそ。
「お前はここで、」
「いいえ瀬渡さま。わたくしもお供致します」
強い意思。
男を射抜く、蒼色の瞳。
「──分かった。では、行こう」
こうして男女はしっかりと手を繋いだままに、暗い山道を歩み、そして……
やはり置き去りにされていた老人を、無事見つけることができたのでした。
それから、似たようなことが何度もありまして。
麓の小屋は、いつしか二つになり、三つになり……
やがて小さな村のようになっていきました。
山に捨てられる者。
世を捨て、山に逃げてくる者。
いずれも訳ありの者ばかりでしたが、瀬渡と揺律音の二人は構わず受け入れます。
初めは二人を気味悪がった来訪者たちも、その心根と懐の広さに触れるにつれ、
やがて彼らに協力するようになっていきました。
となると、悪人も少なからず紛れ込む筈、なのですが。
不思議なことに瀬渡と揺律音の二人には、それが悪人だと分かっているかのようで。
性根のねじくれた人間を迎え入れることは、ただの一人もありませんでした。
山に潜み、村に財が無いか探ろうとした泥棒もおりましたが、
決まって崖から落ちたり、獣に襲われたりして、無事に山を出ることはなく。
二人に救われた者たちは、そのことを不思議に思いながらも、
ついぞ二人に尋ねることはありませんでした。
だってここにいる限り、平穏が得られるのですから。
わざわざ余計なことを知って、その結果帰りたくもない町に戻らなければ
ならなくなる、なんて絶対嫌だったのです。
世捨て人の村。
人の中にいられなかった者たちの村。
不思議なことに、そこには大きな争いもなければ
欲による奪い合いなども起こりませんでした。
皆、そういう“醜さ”を目の当たりにしてきた者たちだったので、
そういうものになりたくなかったのでしょう。
だから、ひとが増えても、村は穏やかで。
緩やかで。あたたかで。
それぞれの得意とする技で皆が、皆を支え。
そんな日々が、二年も過ぎたころ──
「やあ、旦那、めでてえなあ!」
「ほんにのう。よく、揺律音さまも頑張りなさって」
「名前は……決まったのか……?」
「お、お、お、おん、なの、こ、こ、こ、」
「ようけ泣くわあ。こら大物になりますえ」
村の面々に囲まれて。
布団に寝そべったまま、いとおしそうに『我が子』を撫でる揺律音。
その隣で、はち切れんばかりの笑みを浮かべた瀬渡は──
一同を見回すとひとつ、大きく頷いて。
「娘の名は、水渡里(みとり)。
水と里を渡すと書いて、水渡里だ」
この世に生を受けたばかりの赤子に。
長く語り継がれることになる名前を、授けるのでした。
─────────────────────────────────



ENo.101 イクコ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.102 安里杏莉? とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.122 よつね とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.189 水野 杏梨 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.216 ヒビキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.224 鳴 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.260 貴登子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.273 闇 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.382 イオリ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.383 レオン とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.432 カンナ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.513 十神 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.582 リョウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.612 チホ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.723 放課後探検部 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.1072 フーコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1104 刀崎 依良 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
ミトリヤ 「大丈夫? 疲れたら休憩しておやつ食べようよ! ……おやつって感じじゃないかもだけどさ」 |
| 「斯様な若年層ばかりに頼らねばならんというのは…… 如何せん、年長者としては、不甲斐無い所だ……」 |
闇(273) に ItemNo.9 白樺 を手渡ししました。
闇(273) から 松 を手渡しされました。
| 闇 「……木材が良く採れるな……」 |







対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 3 増加!
影響力が 3 増加!



響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ItemNo.9 松 から射程3の武器『左天白陽・改』を作製しました!
⇒ 左天白陽・改/武器:強さ67/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
 |
ミツフネ 「どうにか仕立ててみたが……さて、うまく使えるかな」 |
シェンラン(163) により ItemNo.10 爪 から防具『藍の羽織』を作製してもらいました!
⇒ 藍の羽織/防具:強さ67/[効果1]反撃10 [効果2]- [効果3]-
あかり(869) により ItemNo.6 右天黒月 に ItemNo.8 ねばねば を付加してもらいました!
⇒ 右天黒月/武器:強さ40/[効果1]闇纏10 [効果2]衰弱10 [効果3]-【射程2】
 |
あかり 「こ…こんな感じかな?」 |
ルカ(857) とカードを交換しました!
デッドライン (デッドライン)

ブレイドフォーム を研究しました!(深度0⇒1)
アクアブランド を研究しました!(深度0⇒1)
ウォーターフォール を研究しました!(深度0⇒1)
エチュード を習得!
マーチ を習得!
コールドウェイブ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ミツフネ(161) は ネジ を入手!
詩穂乃(191) は ド根性雑草 を入手!
闇(273) は ネジ を入手!
闇(273) は 花びら を入手!
闇(273) は 羽 を入手!
ミツフネ(161) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
詩穂乃(191) のもとに ダンデライオン が軽快なステップで近づいてきます。
詩穂乃(191) のもとに キラービー がものすごい勢いで駆け寄ってきます。
詩穂乃(191) のもとに 歩行石壁 が泣きながら近づいてきます。



闇(273) に移動を委ねました。
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 J-17(森林)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 J-18(森林)に移動!(体調12⇒11)
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- ミツフネ(161) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 詩穂乃(191) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 闇(273) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



水月大皇
|
 |
ヤーさんと愉快な仲間たち
|




チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



ヤーさんと愉快な仲間たち
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.161
小佐間 御津舟



─────────────────────
** 注意:彼らの異能は複写できない。 **
─────────────────────
■小佐間 御津舟(おさま みつふね)
身長170cm、体重そこそこ。
相良伊橋高校二年二組に通う生徒。
バイト先が潰れてしまったので、
新たなバイト先を探している。
住居はエクレールツクナミ305号室。
安里 杏莉(ENo.102)と付き合っている。
【異能】
『???』
彼の持つ唯一の異能。
以下の異能を正しい形で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
展開空間内の全ての形を認識する能力。
五感を封じられていても認識可能。
空間内にこちらから干渉することはできない。
『整流命繋(ミツナギ)』
命の持つ“流れ”を認識、把握する能力。
流れが歪んだり欠損したりしている場合、
これを正しい流れに寄せることができる。
『巫の誓約』
大切な人を喪ってはならない。
その手に戦うための力が無くとも。
────────────────────
■小佐間 美鳥夜(おさま みとりや)
身長150cm程度。胸はぜんぜんない。
チナミ区の実家に住む中学三年生。
なのにツクナミの兄の家によくいる。
考えるより先に行動するタイプ。
【異能】
『???』
彼女の持つ唯一の異能。
以下の異能を“本来と逆の形”で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
兄の異能と同じ。
『整流命繋(ミツナギ)』
兄の異能と同じ。
『茨の誓約』
その力で他者を殺めてはならない。
誰かが危険に晒されていたとしても。
────────────────────
■昏田 三(くらだ みすじ)
身長2m弱。体重すごくおもい。
屈強な身体、血の気の無い肌をした
明らかにその筋の人間にしか見えない男。
本職は綜合警備保障。副業は家庭教師。
通信教育も承ります。
【異能:流体加速】
液体を加速させる空間を作る。
加算ではなく乗算でかかるため、
元の勢いが強いほど威力も大きくなる。
【その他技能】
射撃術、近接戦闘術、符術、
特殊装甲型宅配車両からの制圧砲撃
────────────────────
■山本(やまもと)/
亜倉 右賢(あくら うげん)
身長180cmちょい。ひょろ長いおっさん。
常に白衣を着ている。うさんくさい。
阿久津機術研究所勤務。
【異能:流浪者】
自分の意思に関係なく世界を渡ってしまう。
きっかけや転移先など一切が制御できない。
【その他技能】
魔術、魔機混合具製作、話術
────────────────────
■繋譜音(ツフネ)
譜と音を繋ぐ者。亡霊。
────────────────────
■水渡里(ミトリ)
水と里を渡す者。アンジニティ。
────────────────────
** 注意:彼らの異能は複写できない。 **
─────────────────────
■小佐間 御津舟(おさま みつふね)
身長170cm、体重そこそこ。
相良伊橋高校二年二組に通う生徒。
バイト先が潰れてしまったので、
新たなバイト先を探している。
住居はエクレールツクナミ305号室。
安里 杏莉(ENo.102)と付き合っている。
【異能】
『???』
彼の持つ唯一の異能。
以下の異能を正しい形で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
展開空間内の全ての形を認識する能力。
五感を封じられていても認識可能。
空間内にこちらから干渉することはできない。
『整流命繋(ミツナギ)』
命の持つ“流れ”を認識、把握する能力。
流れが歪んだり欠損したりしている場合、
これを正しい流れに寄せることができる。
『巫の誓約』
大切な人を喪ってはならない。
その手に戦うための力が無くとも。
────────────────────
■小佐間 美鳥夜(おさま みとりや)
身長150cm程度。胸はぜんぜんない。
チナミ区の実家に住む中学三年生。
なのにツクナミの兄の家によくいる。
考えるより先に行動するタイプ。
【異能】
『???』
彼女の持つ唯一の異能。
以下の異能を“本来と逆の形”で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
兄の異能と同じ。
『整流命繋(ミツナギ)』
兄の異能と同じ。
『茨の誓約』
その力で他者を殺めてはならない。
誰かが危険に晒されていたとしても。
────────────────────
■昏田 三(くらだ みすじ)
身長2m弱。体重すごくおもい。
屈強な身体、血の気の無い肌をした
明らかにその筋の人間にしか見えない男。
本職は綜合警備保障。副業は家庭教師。
通信教育も承ります。
【異能:流体加速】
液体を加速させる空間を作る。
加算ではなく乗算でかかるため、
元の勢いが強いほど威力も大きくなる。
【その他技能】
射撃術、近接戦闘術、符術、
特殊装甲型宅配車両からの制圧砲撃
────────────────────
■山本(やまもと)/
亜倉 右賢(あくら うげん)
身長180cmちょい。ひょろ長いおっさん。
常に白衣を着ている。うさんくさい。
阿久津機術研究所勤務。
【異能:流浪者】
自分の意思に関係なく世界を渡ってしまう。
きっかけや転移先など一切が制御できない。
【その他技能】
魔術、魔機混合具製作、話術
────────────────────
■繋譜音(ツフネ)
譜と音を繋ぐ者。亡霊。
────────────────────
■水渡里(ミトリ)
水と里を渡す者。アンジニティ。
────────────────────
11 / 30
194 PS
チナミ区
J-18
J-18



































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 左天白陽 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 錆符 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 右天黒月 | 武器 | 40 | 闇纏10 | 衰弱10 | - | 【射程2】 |
| 7 | 野菜(?)炒め詩穂乃風 | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 9 | 左天白陽・改 | 武器 | 67 | 器用10 | - | - | 【射程3】 |
| 10 | 藍の羽織 | 防具 | 67 | 反撃10 | - | - | |
| 11 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 35 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 火行式改・甲 (ブレイク) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 火行式改・点 (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 水行式改・連 (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 水行式改・乱 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 御繋・常 (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 火行御繋・転 (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 火行式改・貫 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 水行式改・制 (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | 火行式改・一矢 (ストライク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| 水行式改・落水 (ウォーターフォール) | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| 水行式改・水鏡 (リフレクション) | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 土行式改・岩重 (フロウライフ) | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| 水行式改・刃砕 (コンテイン) | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| コールドウェイブ | 5 | 0 | 80 | 敵4:水撃&凍結+自:炎上 | |
| 水行式改・清流 (チャージ) | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 練3 | 水行御繋・流転 (アクアヒール) | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| 土行式改・吼虎 (ガーディアン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| 水行御繋・首咬 (アクアブランド) | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| 土行式改・破軍 (カウンター) | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
| 練3 | 火行式改・衝破 (イレイザー) | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| 練2 | 水行御繋・命脈 (チャクラグラント) | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 |
| 練3 | 火行式改・裂閃槍 (ハードブレイク) | 6 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 調息 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 調息 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 覚悟 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 覚悟 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 覚悟 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 構え (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 構え (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 揺律音の加護 (水の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
クリスマス (ペネトレイト) |
0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
|
『メリーさんの怪』 (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 練3 |
もっと身体に良い薬草料理 (ファーマシー) |
0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
|
デッドライン (デッドライン) |
0 | 100 | 敵列:闇痛撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]ストライク | [ 1 ]レッドショック |
| [ 1 ]ブレイドフォーム | [ 1 ]アクアブランド | [ 1 ]チャージ |
| [ 1 ]アイシクルランス | [ 1 ]ファイアボルト | [ 1 ]ウォーターフォール |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]イグニス | [ 1 ]グランドクラッシャー |

PL / きぬくろ