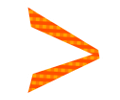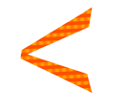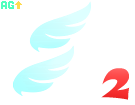<< 2:00~3:00




/04
"とじたせかい"――
双海の家系に流れる血と、血に由来する特異な力について祖父から初めて聞かされた時。
自然と頭の中に浮かんだ名前が、それだった。
代々、身の回りの物体に影響を及ぼす力を持って産まれること。
加齢に応じて力の大部分が変化しうること。
また精神面に強く影響を受けやすいこと。
言い渡された内容を掻い摘むと、その三点だった。
まだ術後間もないとはいえ電脳化したわたしには、祖父の話した内容は凡そ理解できた。
あの男
お父さんが自分を避けた一番の理由。
手を使わずに物を動かし、見もせずに何処に何があるか判別し。
人の持つ感情を読み取り、自分の想いまでも相手にぶつける。
その尽くを気味悪がったからこそ、"あれ"はわたしを部屋に閉じ込めた。
持たざる者なりに力の性質を知っていたが故に、広がることを恐れたのだ。
果たしてわたしの力は大きく歪んでしまった。
『お前など、生まれるべきではなかった』というただ一言が、心に深く突き刺さったからだ。
この力が精神状態によって変質しやすいのは、相手の言葉に含まれた感情を一切のフィルターを通さず直に受け取ってしまう所為だろう。
それが最大級の悪意・憎悪の塊であるなら、尚の事傷口は広くなる。
忘れようと必死になって、何重にも蓋をして、それでもある時突然思い出して消耗するくらいには。
"ミクスタ"との出会いこそあれ、念動力も千里眼も精神感応も、今では見る影もない。
一方で空間に対する認識には幾らか変化が生じた。
そこにあるもの。そこにはないもの。
そこにあるはずなのに、目には見えないもの。
目に見えているはずなのに、そこにないもの。
それらの違いを分かった上で、ありもしない虚像を作り出す。
そういった方向に進むことの良さを"ミクスタ"から学び、電脳化によって後押しを受けたのだ。
電脳技術がもたらした情報の共有化は、精神面に良い影響を与えたと言っていい。
広大なネットの海を泳ぐことで、自分に足りていなかった要素を補った。
わたしのように超常的な力を持った人間が周囲に多くないことを知り。
外部記憶と接続し、自分には許されなかったことの多くを疑似体験し続け。
さながら遅れを取り戻すかのように、膨大な情報を咀嚼する毎日を過ごした。
ネットとリアルの境が希薄になりつつある中で、わたしは"とじたせかい"の変質を目撃した。
ただ幻を作り出すだけの力が、その瞬間、不可逆的に書き換わる。
サイバーディープ・イロージョン
"侵食する電子の海"――
閉じた世界から抜け出た最初の力であった。
◆ ◆ ◆
"第一層。それは内と外とを隔てる大洋。"
◆ ◆ ◆
真っ先に気がついたのは、目の前に浮かぶ電子情報の欠片だった。
拡張現実などではない不可思議なデータ。
殊更に何の機能を実行するでもなく、ただそこに存在することを示すプロパティだけを持ち。
硝子めいた板状の破片が幾つか寄り集まって宙を漂い、きらきらと緑白色に光り輝いて。
それはわたしによって作り出されたものなのだ、と。
そう伝えんとして発光を繰り返したのち、いざ手で触れると途端に霧散する。
そこには大きな謎だけが残った。
中学入学当初は、環境の違いと電脳への注力で、交友関係を広げるのにひどく苦戦した。
ネットから流れ込む情報を処理するので手一杯であり、人付き合いに労力を割く余裕がなかったのだ。
年頃の学生が母譲りの白い髪を気にならないわけがなく、休み時間の度に代わる代わる声が掛かる日もままあった。
無愛想な返事は、彼ら彼女らにはウケが良かったらしい。
幸いにも距離を置かれることはなかったが、逆に縮められた相手が居たかと言うと些か怪しい。
春頃は、肉体の成長に対する受容と、変容した力の解明に躍起になっていた。
身体が両性の性質を併せ持つと言っても、基本となる部分は女性のものだ。
胸は徐々に膨らみ始め、皮下脂肪の増加でほんのりと肉付きがよくなり。
声や顔にも幾らか違いが表れ、とりわけ外性器には何よりも顕著で無視できない変化が訪れた。
有線通信の邪魔になるからと髪をばっさり切ったのは入学直前だったか。
お母さんの少し残念そうな顔は、今でもよく覚えている。
わたしも、お揃いでいることへの嬉しさと楽しさは確かに胸に抱いていたのだが。
すっかり髪を伸ばすという発想が頭から抜けてしまったようである。
いずれにせよ、世間一般の言う「女の子らしさ」から幾らか離れていったのは間違いない。
中学校での水泳の授業をどうするか、というのが自己の性を真剣に意識するようになったきっかけであった。
本来あるはずのない器官が備わっているだけでなく、同級生の――前の席で他の子と談笑する女生徒の肢体を目で追うことが増え。
否応なしに反応する"それ"を周りに悟らせてはいけないと、辛うじて働いた理性が危機感を抱かせもした。
余計なトラブルを招かない為に誤魔化す方法を全力で模索した結果、複数の発見を導き出した。
いつかの『電子情報の欠片』は初め宙に浮いていたが、物体や自分の体に貼り付けることも出来る。
その情報を書き換えれば、それは欠片でなく別のものとなって新たな機能を得る。
空中に映像を表示したり、スピーカーの代替としたり、凡そ電子情報としてやり取り可能なあらゆる物体を再現しうる。
それ自体に実体は無く、手で触れれば通り抜けてしまう。
風景写真を壁に貼り付けようと、それは壁以外の何物でもないし、通路上に壁の画像を投影しても前進すれば問題なく通過する。
つまり、見られると困るものに別のものを貼り付けて、視覚的に騙してしまえる力。
電脳技術を存分に活用してこそ本領を発揮する不完全な能力である。
これも『精神面に強く影響を受けた』一例かと言われると否定は難しい。
けれどそういった考えと試行錯誤が"電子の海"に関する気付きを与えたのだとすれば、この体も面倒事ばかりではないと思えた。
さしたるアクシデントにも見舞われず水泳の授業をやり過ごしたわたしは、より理解を深めるべく研究に取り掛かった。
外では必要以上に力を使わず過ごし、反面自宅に帰ってからはどこまで出来るのかを全力で検証する。
ふとした拍子に"何かの間違い"が起きてしまっては遅い。
この力が自己の手足の延長として有用であればあるほど、扱いには細心の注意を払う必要がある。
中学一年の秋。人間関係の構築に意識を向けるほどの余力が生まれ始めた頃。
クラスは元より、学校全体が"ある噂"で持ち切りになっていた。
曰く、この街のあちこちに現れる黒い靄が、人を怪物に変貌させる。
靄に触れたが最後、その者は二度と帰ってこない。
一度目を合わせれば、怪物はどこまでも追ってくる。
助かりたいなら決して一人で出歩くな、と。
ありがちな都市伝説の類いだと一蹴するのは簡単だ。
実際、生徒の殆どは怪訝な顔を浮かべていたし、わたしも半信半疑で聞いていた。
しかしここは情報の網が張り巡らされた電脳都市・海棠。
真偽を確かめる術には事欠かない街なのだ。
そうと決まれば、行動に移すのは早かった。
どこまで通用するかは定かでないものの、"電子の海"を用いた自衛手段は準備が出来ている。
最近目撃情報があった隣町、三椏の山間部を、単身噂を頼りに歩き回ることとなった。
暫くして、運良く――或いは運悪く、当たりを引いてしまった。
登山道の三叉路。行く手と帰り道、二方向を塞ぐ何かの影がある。
黒い靄。影の化け物。
わたしを待ち構えていた節すらあるそれは、一切の躊躇いもなく飛び掛かり。
影と自分とを遮るように、一本の棒が地面に突き刺さった。
棒を掴み取らんとして体の内側からすうっと現れ出たのは、緑白色の人型。
その鰐頭には覚えがある。半年前のあの夜のことは、ぼんやりとだが思い出せる。
"キベルネテス"――と、そう呼んだ記憶だけは、鮮明であるのに。
どうあれ、"鰐頭"はわたしを守ってくれた。
その点には信頼を寄せて、今度こそ逃げの姿勢に入る。
残された脇道。神社へと続く石畳の階段へ、真っ直ぐ駆け出して。
どういうわけか一瞬影の動きが鈍った様を見逃さず、ひたすらに上る。
"キベルネテス"は、贔屓目に見ても強かった。
獲物を振るえば影が削り取られ、たちまち形を保てず消えていく。
それでも数の多さを覆すには環境が適していない。
木々の合間、四方から次々と湧き出る影は限りを知らず。
また大振りの長物は木の幹や地面に触れ、乱雑に傷付けてしまう。
鳥居をくぐったところで、足がもつれ倒れ込む。
体力のない自分への恨み言ばかりが胸を満たして。
目撃者の末路、噂の顛末を想起して、いよいよ覚悟を決めたその時。
一条の光が降り注ぎ、靄もろとも、影の怪物はいなくなった。
「この山を一人で、とは関心しませんね。呑まれたらどうするつもりなのかしら」
有古山は天守神社。華やかな和装に身を包む一人の女性。
その名を雨森霖子。縦書きするな、が名乗り文句の巫女との出会いだった。



ENo.161 ミツフネ とのやりとり

ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり

ENo.415 【匿名】 とのやりとり

ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり

ENo.612 チホ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 不思議なフライ を食べました!
体調が 1 回復!(15⇒16)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









響鳴LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
呪術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議なフライ』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 4 1 3 = 8 ]成功!料理の強さが増加!
⇒ 不思議なフライ/料理:強さ58/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
ItemNo.9 美味しい草 から料理『奇妙な炒めもの』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 4 3 5 = 12 ]成功!料理の強さが増加!
⇒ 奇妙な炒めもの/料理:強さ76/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10
フェル(1247) とカードを交換しました!
破戒僧 (デストロイ)

サモン:サーヴァント を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:サーヴァント を研究しました!(深度1⇒2)
サモン:サーヴァント を研究しました!(深度2⇒3)
カース を習得!
ダークフレア を習得!
シャドウラーカー を習得!
魔力凝縮 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



七夏(12) は ネジ を入手!
放課後探検部(723) は ド根性雑草 を入手!
アイ(783) は 吸い殻 を入手!
じいや&ねえさん(814) は ド根性雑草 を入手!
放課後探検部(723) は ボロ布 を入手!
放課後探検部(723) は 不思議な石 を入手!
アイ(783) は 不思議な石 を入手!
七夏(12) は ボロ布 を入手!



放課後探検部(723) に移動を委ねました。
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 G-16(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- 放課後探検部(723) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- アイ(783) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 七夏(12) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 放課後探検部(723) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- アイ(783) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- じいや&ねえさん(814) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














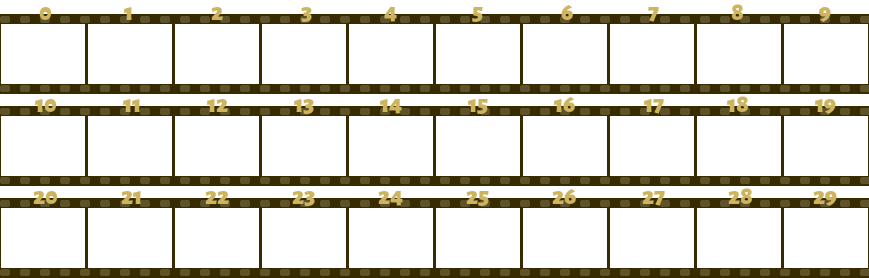





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



/04
"とじたせかい"――
双海の家系に流れる血と、血に由来する特異な力について祖父から初めて聞かされた時。
自然と頭の中に浮かんだ名前が、それだった。
代々、身の回りの物体に影響を及ぼす力を持って産まれること。
加齢に応じて力の大部分が変化しうること。
また精神面に強く影響を受けやすいこと。
言い渡された内容を掻い摘むと、その三点だった。
まだ術後間もないとはいえ電脳化したわたしには、祖父の話した内容は凡そ理解できた。
あの男
手を使わずに物を動かし、見もせずに何処に何があるか判別し。
人の持つ感情を読み取り、自分の想いまでも相手にぶつける。
その尽くを気味悪がったからこそ、"あれ"はわたしを部屋に閉じ込めた。
持たざる者なりに力の性質を知っていたが故に、広がることを恐れたのだ。
果たしてわたしの力は大きく歪んでしまった。
『お前など、生まれるべきではなかった』というただ一言が、心に深く突き刺さったからだ。
この力が精神状態によって変質しやすいのは、相手の言葉に含まれた感情を一切のフィルターを通さず直に受け取ってしまう所為だろう。
それが最大級の悪意・憎悪の塊であるなら、尚の事傷口は広くなる。
忘れようと必死になって、何重にも蓋をして、それでもある時突然思い出して消耗するくらいには。
"ミクスタ"との出会いこそあれ、念動力も千里眼も精神感応も、今では見る影もない。
一方で空間に対する認識には幾らか変化が生じた。
そこにあるもの。そこにはないもの。
そこにあるはずなのに、目には見えないもの。
目に見えているはずなのに、そこにないもの。
それらの違いを分かった上で、ありもしない虚像を作り出す。
そういった方向に進むことの良さを"ミクスタ"から学び、電脳化によって後押しを受けたのだ。
電脳技術がもたらした情報の共有化は、精神面に良い影響を与えたと言っていい。
広大なネットの海を泳ぐことで、自分に足りていなかった要素を補った。
わたしのように超常的な力を持った人間が周囲に多くないことを知り。
外部記憶と接続し、自分には許されなかったことの多くを疑似体験し続け。
さながら遅れを取り戻すかのように、膨大な情報を咀嚼する毎日を過ごした。
ネットとリアルの境が希薄になりつつある中で、わたしは"とじたせかい"の変質を目撃した。
ただ幻を作り出すだけの力が、その瞬間、不可逆的に書き換わる。
サイバーディープ・イロージョン
"侵食する電子の海"――
閉じた世界から抜け出た最初の力であった。
◆ ◆ ◆
"第一層。それは内と外とを隔てる大洋。"
◆ ◆ ◆
真っ先に気がついたのは、目の前に浮かぶ電子情報の欠片だった。
拡張現実などではない不可思議なデータ。
殊更に何の機能を実行するでもなく、ただそこに存在することを示すプロパティだけを持ち。
硝子めいた板状の破片が幾つか寄り集まって宙を漂い、きらきらと緑白色に光り輝いて。
それはわたしによって作り出されたものなのだ、と。
そう伝えんとして発光を繰り返したのち、いざ手で触れると途端に霧散する。
そこには大きな謎だけが残った。
中学入学当初は、環境の違いと電脳への注力で、交友関係を広げるのにひどく苦戦した。
ネットから流れ込む情報を処理するので手一杯であり、人付き合いに労力を割く余裕がなかったのだ。
年頃の学生が母譲りの白い髪を気にならないわけがなく、休み時間の度に代わる代わる声が掛かる日もままあった。
無愛想な返事は、彼ら彼女らにはウケが良かったらしい。
幸いにも距離を置かれることはなかったが、逆に縮められた相手が居たかと言うと些か怪しい。
春頃は、肉体の成長に対する受容と、変容した力の解明に躍起になっていた。
身体が両性の性質を併せ持つと言っても、基本となる部分は女性のものだ。
胸は徐々に膨らみ始め、皮下脂肪の増加でほんのりと肉付きがよくなり。
声や顔にも幾らか違いが表れ、とりわけ外性器には何よりも顕著で無視できない変化が訪れた。
有線通信の邪魔になるからと髪をばっさり切ったのは入学直前だったか。
お母さんの少し残念そうな顔は、今でもよく覚えている。
わたしも、お揃いでいることへの嬉しさと楽しさは確かに胸に抱いていたのだが。
すっかり髪を伸ばすという発想が頭から抜けてしまったようである。
いずれにせよ、世間一般の言う「女の子らしさ」から幾らか離れていったのは間違いない。
中学校での水泳の授業をどうするか、というのが自己の性を真剣に意識するようになったきっかけであった。
本来あるはずのない器官が備わっているだけでなく、同級生の――前の席で他の子と談笑する女生徒の肢体を目で追うことが増え。
否応なしに反応する"それ"を周りに悟らせてはいけないと、辛うじて働いた理性が危機感を抱かせもした。
余計なトラブルを招かない為に誤魔化す方法を全力で模索した結果、複数の発見を導き出した。
いつかの『電子情報の欠片』は初め宙に浮いていたが、物体や自分の体に貼り付けることも出来る。
その情報を書き換えれば、それは欠片でなく別のものとなって新たな機能を得る。
空中に映像を表示したり、スピーカーの代替としたり、凡そ電子情報としてやり取り可能なあらゆる物体を再現しうる。
それ自体に実体は無く、手で触れれば通り抜けてしまう。
風景写真を壁に貼り付けようと、それは壁以外の何物でもないし、通路上に壁の画像を投影しても前進すれば問題なく通過する。
つまり、見られると困るものに別のものを貼り付けて、視覚的に騙してしまえる力。
電脳技術を存分に活用してこそ本領を発揮する不完全な能力である。
これも『精神面に強く影響を受けた』一例かと言われると否定は難しい。
けれどそういった考えと試行錯誤が"電子の海"に関する気付きを与えたのだとすれば、この体も面倒事ばかりではないと思えた。
さしたるアクシデントにも見舞われず水泳の授業をやり過ごしたわたしは、より理解を深めるべく研究に取り掛かった。
外では必要以上に力を使わず過ごし、反面自宅に帰ってからはどこまで出来るのかを全力で検証する。
ふとした拍子に"何かの間違い"が起きてしまっては遅い。
この力が自己の手足の延長として有用であればあるほど、扱いには細心の注意を払う必要がある。
中学一年の秋。人間関係の構築に意識を向けるほどの余力が生まれ始めた頃。
クラスは元より、学校全体が"ある噂"で持ち切りになっていた。
曰く、この街のあちこちに現れる黒い靄が、人を怪物に変貌させる。
靄に触れたが最後、その者は二度と帰ってこない。
一度目を合わせれば、怪物はどこまでも追ってくる。
助かりたいなら決して一人で出歩くな、と。
ありがちな都市伝説の類いだと一蹴するのは簡単だ。
実際、生徒の殆どは怪訝な顔を浮かべていたし、わたしも半信半疑で聞いていた。
しかしここは情報の網が張り巡らされた電脳都市・海棠。
真偽を確かめる術には事欠かない街なのだ。
そうと決まれば、行動に移すのは早かった。
どこまで通用するかは定かでないものの、"電子の海"を用いた自衛手段は準備が出来ている。
最近目撃情報があった隣町、三椏の山間部を、単身噂を頼りに歩き回ることとなった。
暫くして、運良く――或いは運悪く、当たりを引いてしまった。
登山道の三叉路。行く手と帰り道、二方向を塞ぐ何かの影がある。
黒い靄。影の化け物。
わたしを待ち構えていた節すらあるそれは、一切の躊躇いもなく飛び掛かり。
影と自分とを遮るように、一本の棒が地面に突き刺さった。
棒を掴み取らんとして体の内側からすうっと現れ出たのは、緑白色の人型。
その鰐頭には覚えがある。半年前のあの夜のことは、ぼんやりとだが思い出せる。
"キベルネテス"――と、そう呼んだ記憶だけは、鮮明であるのに。
どうあれ、"鰐頭"はわたしを守ってくれた。
その点には信頼を寄せて、今度こそ逃げの姿勢に入る。
残された脇道。神社へと続く石畳の階段へ、真っ直ぐ駆け出して。
どういうわけか一瞬影の動きが鈍った様を見逃さず、ひたすらに上る。
"キベルネテス"は、贔屓目に見ても強かった。
獲物を振るえば影が削り取られ、たちまち形を保てず消えていく。
それでも数の多さを覆すには環境が適していない。
木々の合間、四方から次々と湧き出る影は限りを知らず。
また大振りの長物は木の幹や地面に触れ、乱雑に傷付けてしまう。
鳥居をくぐったところで、足がもつれ倒れ込む。
体力のない自分への恨み言ばかりが胸を満たして。
目撃者の末路、噂の顛末を想起して、いよいよ覚悟を決めたその時。
一条の光が降り注ぎ、靄もろとも、影の怪物はいなくなった。
「この山を一人で、とは関心しませんね。呑まれたらどうするつもりなのかしら」
有古山は天守神社。華やかな和装に身を包む一人の女性。
その名を雨森霖子。縦書きするな、が名乗り文句の巫女との出会いだった。



ENo.161 ミツフネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.415 【匿名】 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.612 チホ とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



| 七夏 「……わたしに出来ることはそう多くないだろうけど、 どうあれ、手を貸すよ。よろしく頼む」 |
| アイ 「……こうも続くと逆に慣れるな。 はあ、今回も面倒な相手か?」 |
| ラシェル 「私としてはあんまり慣れないで欲しいですね。 ……と言っても今更ですか。」 |
ItemNo.6 不思議なフライ を食べました!
体調が 1 回復!(15⇒16)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





TeamNo.12
|
 |
黄昏と夕闇
|



響鳴LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
呪術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議なフライ』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 4 1 3 = 8 ]成功!料理の強さが増加!
⇒ 不思議なフライ/料理:強さ58/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
ItemNo.9 美味しい草 から料理『奇妙な炒めもの』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 4 3 5 = 12 ]成功!料理の強さが増加!
⇒ 奇妙な炒めもの/料理:強さ76/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10
フェル(1247) とカードを交換しました!
破戒僧 (デストロイ)

サモン:サーヴァント を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:サーヴァント を研究しました!(深度1⇒2)
サモン:サーヴァント を研究しました!(深度2⇒3)
カース を習得!
ダークフレア を習得!
シャドウラーカー を習得!
魔力凝縮 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



七夏(12) は ネジ を入手!
放課後探検部(723) は ド根性雑草 を入手!
アイ(783) は 吸い殻 を入手!
じいや&ねえさん(814) は ド根性雑草 を入手!
放課後探検部(723) は ボロ布 を入手!
放課後探検部(723) は 不思議な石 を入手!
アイ(783) は 不思議な石 を入手!
七夏(12) は ボロ布 を入手!



放課後探検部(723) に移動を委ねました。
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 G-16(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- 放課後探検部(723) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- アイ(783) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 七夏(12) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 放課後探検部(723) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- アイ(783) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- じいや&ねえさん(814) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







TeamNo.12
|
 |
蓮華座
|




チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



TeamNo.12
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.12
双海七夏



◆キャラクター紹介◆
◆メイン・左側、白髪◆
電脳の守り人 - 相良伊橋の覗き屋
双海 七夏
http://lisge.com/ib/prof.php?id=RAkF3WGSIXxdb4d8715361031f0aad35fcfa2775632
◆サブ・右側、黒髪◆
書架の守り人 - 女学院の健啖家
黒葛 彗華
http://lisge.com/ib/prof.php?id=JBJqMoQQTNCd47ca050cf12d2a038daf4df9d4d44c3
◆ロール的連絡先◆
七夏/彗華宛IBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3165
◆メイン・左側、白髪◆
電脳の守り人 - 相良伊橋の覗き屋
双海 七夏
http://lisge.com/ib/prof.php?id=RAkF3WGSIXxdb4d8715361031f0aad35fcfa2775632
◆サブ・右側、黒髪◆
書架の守り人 - 女学院の健啖家
黒葛 彗華
http://lisge.com/ib/prof.php?id=JBJqMoQQTNCd47ca050cf12d2a038daf4df9d4d44c3
◆ロール的連絡先◆
七夏/彗華宛IBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3165
30 / 30
121 PS
チナミ区
D-2
D-2






| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 7 | 不思議なフライ | 料理 | 58 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 奇妙な炒めもの | 料理 | 88 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |
| 9 | 奇妙な炒めもの | 料理 | 76 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |
| 10 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]朦朧10(LV20)[防具]体力10(LV10)[装飾]増勢10(LV25) | |||
| 11 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 解析 | 15 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 35 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| ウィークサーチ | 6 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 魔力凝縮 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+発動する「敵貫」「敵列」「敵全」を弱化 | |
| 技巧料理 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で、作る料理の強さが増加するが、3D6が5以下なら料理の効果1~3がなくなる。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ほほえみ (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
サモン:店員A (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
|
双子の兄 黒浦鴉 召喚 (ヒートイミッター) |
0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| 練1 |
破戒僧 (デストロイ) |
0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ダークネス | [ 3 ]リフレッシュ | [ 3 ]ファーマシー |
| [ 3 ]サモン:サーヴァント |

PL / かのしき