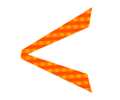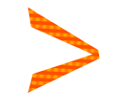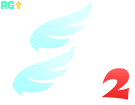<< 1:00~2:00




/03
物心ついた時から、わたしの側にはお母さんだけがいた。
お屋敷に、あの人とわたし。
二人で暮らすには大きすぎるくらいだったけれど、
フリージアの香る中庭の、芝生の上に寝転んで。
頭が痛くなるからと膝枕をしてもらった、いつかの思い出。
わたしは、そんなのんびりとした日々が好きだった。
たまに、黒い服を着た怖い人達が廊下を歩いていることがあった。
ただでさえ大きな家の中。自分以外の誰かがいたら、気になって仕方がない。
黒い人。白い人。
ふさふさの人。つるつるの人。
ヒゲの人。ツルツルの人。
何人も居るようだった。
毎日かわりばんこに廊下を歩き、いつもわたしの方を見て、
けれど声をかけようとするとどこかに行ってしまう。
わたしが大きくなっても、お屋敷にいる人は両手で数えられるほどだ。
わたし、お母さん、お父さん、お姉ちゃん、黒い服の人たち、メイドさん。
小さかった頃のわたしは、それが全てだと思っていた。
「お屋敷の外へ出てはいけない」と、お母さんは言う。
わたしはその言葉を、約束を破らずに、お屋敷の中を歩いて、走って、探検して、遊び回った。
ある時、お屋敷の地下まで迷い込んだわたしは、一際大きな扉のついた暗い部屋に入ったことがあった。
本棚と木箱が並んだ、不思議な部屋。そこはとても冷たくて、とても暗くて、とても怖かった。
ぶるぶると震えながらなんとか周りを見渡して、背の低い机の上に小さな桐の箱が置いてあることに気がついた。
その箱を持って自分の部屋に帰り、中を覗いた瞬間。
眼の前に、大きな"ワニ"が浮かんでいた。
◆ ◆ ◆
"ミクスタ"というのは、それを初めて見たその時に、ふと頭の中に浮かんだ名前だった。
ナ ナ カ マ ド
『Sorbus commixta』のもじりだと分かったのは、それからずっと先になる。
ぼんやりと薄く色付いていた頃の"ミクスタ"は、自分の部屋の中でのみ形を保つことができた。
扉や窓などのはっきりとした線を境に、室内という『海』を泳ぎ回る自由な生き物であった。
喋ったりはしない。手で触れられもしない。言っていることを理解出来ているのかも分からない。
ふよふよと浮かんだまま、こちらの呼びかけや動作に反応するように、じたばた手足を掻いて楽しませてくれた。
その一点だけで、わたしは"ミクスタ"に興味を抱いた。
一ヶ月、一年と過ぎていくにつれ、"ミクスタ"はわたしの部屋のみならず、廊下をも泳げるようになっていった。
母を始め他人に見られないよう気をつけながら、お屋敷という名の大海原に繰り出しては不思議な生き物について理解を深める。
まんまるで愛嬌のあるワニが新たに広がった世界を前に燥ぎ回る。
そんな姿を眺めるうち、わたしはこの奇妙な生き物と不可解な空間に、どうしようもなく惹かれていた。
◆ ◆ ◆
"人々から見た大海原は、それにとって川にも満たない。"
◆ ◆ ◆
その端末は、古くから双海の家で保管されていたものだ。
叔父の話によると、少なくとも二百年以上前には既に当家の所有物であったとの記録が残っている。
ただ、時期によって端末の形状が異なっているとの記載があり、その真偽には謎が多いとも。
七夏が所有者となった時、それは折りたたみ式携帯電話の形を模していた。
タッチ操作式の携帯端末が主流である現在からすれば些か古く見えるものだったが、屋敷の地下室に置いてあったことを考えれば不自然さは少ない。
しかし十数年前、叔父が初めて端末の存在を確認した際には、より前時代的な――両手でなお大きすぎるほどの黎明期の携帯電話だと言うから、それが本当に同一の端末なのか検証にひどく時間を要したらしい。
『中身を解析できない』のは共通点として充分だが、端末を起動できる者が現れるまでそれの持つ本質、役割が頭から抜け落ちていたことが、検証が遅れた何よりの要因であろう。
異質な品を代々受け継いできた意味を理解するまでに費やした時間は、不思議と長くなかった。
端末から現れ出たもの"ミクスタ"と触れ合い育つ中で、多くを知った。"それ"が明確な意思を持ち、こちらへは欠片ほどの敵意も抱かず、そして所有者の身に危険が及べば速やかに排除する。そういった機能を備えた陰の"番人"なのだと。
実際、海棠の街に居た頃は端末にこれまで多くの危機を救われ、また同じだけ救ってもきたし、他の端末と接触することで様々な現象を引き起こし、新たな発見を齎してもきた。
それらの経験を通じて所有者に成長を促している、とするのが七夏と叔父、両名の解釈である。
デバイスキーパー
端末の所有者を指した"端末の守り人"なる呼称はあの街でごく最近になって発生したものだが、七夏にしてみれば自分たち人間こそが守られるべき端末なのではないか、と信じて疑わない。
イバラシティへ場所を移してなお、"守り人"が"守り人"で居られるかは、まだわからない。
けれども、必要に迫られればこの力を躊躇いなく行使する。身を守る、その一点に於いては海棠もイバラシティも変わりはしない。
果たして己の立場を逸脱することになるとしても、自分の決断を信じ、また自分を信じてくれる誰かを信じるためになら――
わたしは、電子の海で世界を満たそう。



ENo.195 天使様 とのやりとり

ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり

ENo.513 十神 とのやりとり

ENo.654 夏鈴 とのやりとり

以下の相手に送信しました













解析LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
魔術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.8 美味しい草 から料理『奇妙な炒めもの』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 6 5 6 = 17 ]成功!料理の強さが増加!
⇒ 奇妙な炒めもの/料理:強さ88/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10
放課後探検部(723) の持つ ItemNo.8 美味しい草 から料理『奇妙な炒めもの』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 3 3 6 = 12 ]成功!料理の強さが増加!
アイ(783) の持つ ItemNo.8 美味しい草 から料理『奇妙な炒めもの』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 2 1 5 = 8 ]成功!料理の強さが増加!
クロウ(631) とカードを交換しました!
黒浦鴉 召喚 (ヒートイミッター)

ダークネス を研究しました!(深度0⇒1)
ダークネス を研究しました!(深度1⇒2)
ダークネス を研究しました!(深度2⇒3)
エチュード を習得!
ファイアダンス を習得!
精神変調耐性 を習得!
ファイアボルト を習得!
コンセントレイト を習得!
火の祝福 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



七夏(12) は 韮 を入手!
放課後探検部(723) は 白石 を入手!
アイ(783) は 白石 を入手!
じいや(814) は 韮 を入手!
放課後探検部(723) は 不思議な雫 を入手!
七夏(12) は 不思議な雫 を入手!
じいや(814) は 不思議な雫 を入手!
アイ(783) は 毛 を入手!



放課後探検部(723) に移動を委ねました。
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



/03
物心ついた時から、わたしの側にはお母さんだけがいた。
お屋敷に、あの人とわたし。
二人で暮らすには大きすぎるくらいだったけれど、
フリージアの香る中庭の、芝生の上に寝転んで。
頭が痛くなるからと膝枕をしてもらった、いつかの思い出。
わたしは、そんなのんびりとした日々が好きだった。
たまに、黒い服を着た怖い人達が廊下を歩いていることがあった。
ただでさえ大きな家の中。自分以外の誰かがいたら、気になって仕方がない。
黒い人。白い人。
ふさふさの人。つるつるの人。
ヒゲの人。ツルツルの人。
何人も居るようだった。
毎日かわりばんこに廊下を歩き、いつもわたしの方を見て、
けれど声をかけようとするとどこかに行ってしまう。
わたしが大きくなっても、お屋敷にいる人は両手で数えられるほどだ。
わたし、お母さん、
小さかった頃のわたしは、それが全てだと思っていた。
「お屋敷の外へ出てはいけない」と、お母さんは言う。
わたしはその言葉を、約束を破らずに、お屋敷の中を歩いて、走って、探検して、遊び回った。
ある時、お屋敷の地下まで迷い込んだわたしは、一際大きな扉のついた暗い部屋に入ったことがあった。
本棚と木箱が並んだ、不思議な部屋。そこはとても冷たくて、とても暗くて、とても怖かった。
ぶるぶると震えながらなんとか周りを見渡して、背の低い机の上に小さな桐の箱が置いてあることに気がついた。
その箱を持って自分の部屋に帰り、中を覗いた瞬間。
眼の前に、大きな"ワニ"が浮かんでいた。
◆ ◆ ◆
"ミクスタ"というのは、それを初めて見たその時に、ふと頭の中に浮かんだ名前だった。
ナ ナ カ マ ド
『Sorbus commixta』のもじりだと分かったのは、それからずっと先になる。
ぼんやりと薄く色付いていた頃の"ミクスタ"は、自分の部屋の中でのみ形を保つことができた。
扉や窓などのはっきりとした線を境に、室内という『海』を泳ぎ回る自由な生き物であった。
喋ったりはしない。手で触れられもしない。言っていることを理解出来ているのかも分からない。
ふよふよと浮かんだまま、こちらの呼びかけや動作に反応するように、じたばた手足を掻いて楽しませてくれた。
その一点だけで、わたしは"ミクスタ"に興味を抱いた。
一ヶ月、一年と過ぎていくにつれ、"ミクスタ"はわたしの部屋のみならず、廊下をも泳げるようになっていった。
母を始め他人に見られないよう気をつけながら、お屋敷という名の大海原に繰り出しては不思議な生き物について理解を深める。
まんまるで愛嬌のあるワニが新たに広がった世界を前に燥ぎ回る。
そんな姿を眺めるうち、わたしはこの奇妙な生き物と不可解な空間に、どうしようもなく惹かれていた。
◆ ◆ ◆
"人々から見た大海原は、それにとって川にも満たない。"
◆ ◆ ◆
その端末は、古くから双海の家で保管されていたものだ。
叔父の話によると、少なくとも二百年以上前には既に当家の所有物であったとの記録が残っている。
ただ、時期によって端末の形状が異なっているとの記載があり、その真偽には謎が多いとも。
七夏が所有者となった時、それは折りたたみ式携帯電話の形を模していた。
タッチ操作式の携帯端末が主流である現在からすれば些か古く見えるものだったが、屋敷の地下室に置いてあったことを考えれば不自然さは少ない。
しかし十数年前、叔父が初めて端末の存在を確認した際には、より前時代的な――両手でなお大きすぎるほどの黎明期の携帯電話だと言うから、それが本当に同一の端末なのか検証にひどく時間を要したらしい。
『中身を解析できない』のは共通点として充分だが、端末を起動できる者が現れるまでそれの持つ本質、役割が頭から抜け落ちていたことが、検証が遅れた何よりの要因であろう。
異質な品を代々受け継いできた意味を理解するまでに費やした時間は、不思議と長くなかった。
端末から現れ出たもの"ミクスタ"と触れ合い育つ中で、多くを知った。"それ"が明確な意思を持ち、こちらへは欠片ほどの敵意も抱かず、そして所有者の身に危険が及べば速やかに排除する。そういった機能を備えた陰の"番人"なのだと。
実際、海棠の街に居た頃は端末にこれまで多くの危機を救われ、また同じだけ救ってもきたし、他の端末と接触することで様々な現象を引き起こし、新たな発見を齎してもきた。
それらの経験を通じて所有者に成長を促している、とするのが七夏と叔父、両名の解釈である。
デバイスキーパー
端末の所有者を指した"端末の守り人"なる呼称はあの街でごく最近になって発生したものだが、七夏にしてみれば自分たち人間こそが守られるべき端末なのではないか、と信じて疑わない。
イバラシティへ場所を移してなお、"守り人"が"守り人"で居られるかは、まだわからない。
けれども、必要に迫られればこの力を躊躇いなく行使する。身を守る、その一点に於いては海棠もイバラシティも変わりはしない。
果たして己の立場を逸脱することになるとしても、自分の決断を信じ、また自分を信じてくれる誰かを信じるためになら――
わたしは、電子の海で世界を満たそう。



ENo.195 天使様 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.513 十神 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.654 夏鈴 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



| 七夏 「ああもう、巫弥子。泣くんじゃない。 わたしが傍についてるから、元気だしなさいな」 |
| 七夏 「(……とは言ったものの、先生はいないのか。 もしもの時は腹を括らないといけないな、これは)」 |
 |
ロゼッタ 「いや『己の世界のために、争え』って。 明らかに、その前までと雰囲気急に変わりすぎだろ」 |
| アイ 「――何でも良いが。 居ない人間のことで何時までも喚くなよ。 戦いは目の前に転がってるんだからな。」 |
| ラシェル 「それにしても、なんで室生さんは女装してたんでしょうね……。 覚えてたら後で問いただしておきましょうか。」 |
| アイ 「お前さっきも聞いてたじゃん…… まあ、都合一時間後だな。」 |
| ねえさん 「はいは~い。よろしくー。」 |
| ねえさん 「キミたちがマナちゃんが言ってた少年少女ってワケだ」 |
| ねえさん 「こう見えて、子供の世話は慣れてるからネ!この『ねえさん』に、ドンと任せなさい!」 |
| じいや 「それと、アイとラシェル、じゃな」 |
| じいや 「『じいや』じゃ。よろしくの。といっても、こちらも迷惑をかけるかもしれん。 持ちつ持たれつ、上手くやっていけると良いの」 |
| じいや 「さて、そちらの三人はエヴァンジェリーナ、巫弥子、朔太郎……おや? 少年が一人おったはずじゃが……少女しかおらんではないか……」 |





TeamNo.12
|
 |
スイーツ★インベーダー
|



解析LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
魔術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.8 美味しい草 から料理『奇妙な炒めもの』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 6 5 6 = 17 ]成功!料理の強さが増加!
⇒ 奇妙な炒めもの/料理:強さ88/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10
| 七夏 「腹に入れば一緒だろう、うん」 |
放課後探検部(723) の持つ ItemNo.8 美味しい草 から料理『奇妙な炒めもの』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 3 3 6 = 12 ]成功!料理の強さが増加!
アイ(783) の持つ ItemNo.8 美味しい草 から料理『奇妙な炒めもの』をつくりました!
⇒ 技巧料理![ 2 1 5 = 8 ]成功!料理の強さが増加!
クロウ(631) とカードを交換しました!
黒浦鴉 召喚 (ヒートイミッター)

ダークネス を研究しました!(深度0⇒1)
ダークネス を研究しました!(深度1⇒2)
ダークネス を研究しました!(深度2⇒3)
エチュード を習得!
ファイアダンス を習得!
精神変調耐性 を習得!
ファイアボルト を習得!
コンセントレイト を習得!
火の祝福 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



七夏(12) は 韮 を入手!
放課後探検部(723) は 白石 を入手!
アイ(783) は 白石 を入手!
じいや(814) は 韮 を入手!
放課後探検部(723) は 不思議な雫 を入手!
七夏(12) は 不思議な雫 を入手!
じいや(814) は 不思議な雫 を入手!
アイ(783) は 毛 を入手!



放課後探検部(723) に移動を委ねました。
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







TeamNo.12
|
 |
ゴリラギャング団
|


ENo.12
双海七夏



◆キャラクター紹介◆
◆メイン・左側、白髪◆
電脳の守り人 - 相良伊橋の覗き屋
双海 七夏
http://lisge.com/ib/prof.php?id=RAkF3WGSIXxdb4d8715361031f0aad35fcfa2775632
◆サブ・右側、黒髪◆
書架の守り人 - 女学院の健啖家
黒葛 彗華
http://lisge.com/ib/prof.php?id=JBJqMoQQTNCd47ca050cf12d2a038daf4df9d4d44c3
◆ロール的連絡先◆
七夏/彗華宛IBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3165
◆メイン・左側、白髪◆
電脳の守り人 - 相良伊橋の覗き屋
双海 七夏
http://lisge.com/ib/prof.php?id=RAkF3WGSIXxdb4d8715361031f0aad35fcfa2775632
◆サブ・右側、黒髪◆
書架の守り人 - 女学院の健啖家
黒葛 彗華
http://lisge.com/ib/prof.php?id=JBJqMoQQTNCd47ca050cf12d2a038daf4df9d4d44c3
◆ロール的連絡先◆
七夏/彗華宛IBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3165
15 / 30
80 PS
チナミ区
I-14
I-14






| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議なフライ | 料理 | 49 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 奇妙な炒めもの | 料理 | 88 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |
| 9 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV10)[効果2]充填10(LV20)[効果3]増幅10(LV30) | |||
| 10 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]朦朧10(LV20)[防具]体力10(LV10)[装飾]増勢10(LV25) | |||
| 11 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 30 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| 決3 | ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 技巧料理 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で、作る料理の強さが増加するが、3D6が5以下なら料理の効果1~3がなくなる。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ほほえみ (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
サモン:店員A (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
|
黒浦鴉 召喚 (ヒートイミッター) |
0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]リフレッシュ | [ 3 ]ダークネス | [ 3 ]ファーマシー |

PL / かのしき