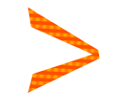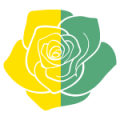<< 1:00~2:00




──曖昧な記憶だ。
とても曖昧で、そんな事が本当にあったかさえ不明瞭だ。
世界すら、信じて良いのか分からないくらい曖昧だ。
なにもかもが夢みたいに朧気で、謎だらけで。
そもそも本当の事など在りはしないかのようで。
もし。
もし、そうじゃないと言うならば。
私の夢に訴えかけてくるあの人達は、誰だろう。
私の事を繰り返し罵倒する、"私"は一体何なのだろう。
私は、私の世界は、それらは、……それらは
おいで おいで 迷路に おいで。
彼方も 此方も 解らぬ 場所へ。
たった ひとりで 右往左往。
遠くに 見えるは 魑魅魍魎。
ほんとの わたしは 何処なのか。
それすら よやみに 吸い込まれ
もう何処にも 在りはしないのか。

知世子には沢山の"わからないこと"がある。
到底解けない難問、凝っていて難しいお菓子作り、自分の見ている星空のその先の世界、自分の未来。
知世子には沢山の"わからないこと"が増える。
幼馴染みの秘密、大人の苦悩、不穏な影、そして自分自身。
最近、その"わからないこと"は妙に増加する傾向にあった。
積み重なり、降り積もり、知世子を惑わすように。
塵芥のようにつまらないものだったらまだしも、見逃せないような鋭利な破片すら見つかる。
それは触れると確実に牙を剥いて、癒えぬ傷を作っていく。
"わからないこと"は"わからない"から、徐々に"こわい"に変わっていく。
手当てもされぬままの傷はじくじくと膿み、悪い方向へと転がり落ちていく。
しかし麻痺していく神経の中では、自分の傷の痛みもまともに気付けない。
知世子はじわじわと、ゆっくりと、しかし確実に傷を育てていく。
"平和に生きられないかもしれない。"
"この幸せは張り裂けて、無くなってしまうかもしれない。"
"大事な人達が、いなくなってしまうかもしれない。"
そんな予兆は、不穏に伸びていく黒い影は、普通の中学生には重かった。
知世子の世界はとても広くて、それでいて狭い。
もっと世界の外へと手を伸ばそうとしていても、幼い知世子の世界はまだ"友達や家族、恋人と幸せに過ごせる範囲"程しかない。
世界が変わらず回り続けようとも、他の皆が幸せになろうとも。
知世子のその範囲に、世界にいる人達が、幸せではなくなったら。
最悪消えてしまったりでもしたら。
知世子にとって、それは世界の滅亡に等しいのだ。
そんな滅亡の予感に知世子は怯えながら、また夢を見る。
──それが"知世子"だけの話であったならば、どうせただの捏造だ。
そうであったならどれだけ良かったか。
"知世子"の悪夢に出てくる誰かは、チヨ子がアンジニティに来る前に出会った人々だ。
イバラシティでは夢に出るのは不思議だが、分からないのは仕方ない。
だけどどうして、名前が思い出せない?
チヨ子の姿の時でさえ、その記憶は穴が空いたように戻ってこない。
それどころかその人達がどんな顔をしていたかすら、徐々に思い出せなくなっている。
大事なものを貰った、忘れちゃいけない大切な人達がいっぱいいた筈なのに。
私は皆から愛を貰って、それで生きているのに。
それを忘れてしまっては、いけないのに。
感情とは裏腹に、笑顔も暖かさも何もかもが手から滑り落ちて、穴がどんどんぽっかりと広がって。
チヨ子はそれに対して、どうして、なんで、と繰り返すしかなかった。
チヨ子は無力だった。
今まで自分が救われたことはあるし、救った事もある。
そう思っているし、そう言われたから。
だけどチヨ子は分からなかった。
自分の救い方は、分からなかった。
この消失を、広がる空虚を、誰に言う訳にもいかなくて。
ただ呆然と空いた穴を見つめては、立ち尽くすしかなくて。
チヨ子が出来るのは、もう"大切だった"という事しか分からなくなりつつある記憶に対して、さようならと別れの挨拶をする事だけだった。
失いたくない。
けど、もう大事な物の意味すら分からなくなりつつあるから。
だから、覚悟を決めねばならない。
何度でも。
自分を殺す程の覚悟を、何度でも。
忘れたとしても、何度でも、何度でも。
星は未だ明滅し続ける。
弱いながらも、その存在を主張し続ける。
生き続けようとする。
時間は進む。残酷に。
空虚は蝕む。凄惨に。
【堂々廻りの邪竜と贄】
大人になりたかった、というのはきっとあっただろう。
大人の姿になれたのは、あくまで【オレ様】の意図の可能性もあるが。
それでもやはり、昔は大人に憧れてはいたから。
大きくなった昔の同級生に会って一緒に食事をしたり、夜に酒を飲んでゲームしてはしゃいだり。
そういうのがずっと羨ましかったのだ。
やっぱり大人になりたかったなと、今でも思える。
父親の店だって、継ぎたかった。
もう少し頑張れば、自分だって父親に匹敵する物が作れた筈だ。
言ってしまえば、そんな未来は訪れなかった。
誰も彼もに平等にやって来ると思っていた未来は、当たり前に手に入るものじゃなかった。
オレに与えられたのは、冷たくて誰の手も届かない場所だった。
"此処"は冷たい。何の温もりもない。
誰もいないし、きっと誰も知らない場所だ。
そしてオレの事も、きっと誰も知らないのだ。
それでいいと思っている。それがいいと思っている。
オレが海底から抜け出す時、【オレ様】もまた陸に這い上がる。
災厄を呼び起こす邪神を、その邪神の子を生み出す存在を、誰が望んで引き上げる?
オレは"望まれない"し"臨まない"。
悪辣なる神々をこの身体の中に廻らせたまま、ずっとずっと此処に居る。
"望まれる"ものは海底から押し上げて、"臨むべき"ものへ導いていく。
【オレ様】を"臨ませない"し"望まない"。
例え自分を否定した世界だとて、オレは決して嫌いじゃなかったから。
オレは喜んで人柱になろう。
誰も彼もから忘れ去られ、孤独な深海に身を沈めよう。
それでいい。本来オレは此処で終わるべきだったのだから。
死ねない代わりに、堂々巡りの生の中に、【オレ様】も一緒に閉じ込めてやる。
──引き裂けるような痛みが走る。
意識はある。なくなる筈がない。生かされる。
肉が空気に触れて、何かが溢れ落ちて、冷えていく。
それでも生ぬるさは消えない。命の灯火は絶やされない。
邪神は、【オレ様】は、
ハザマを彷徨う。



ENo.119 ***** とのやりとり

ENo.249 『小鷹裕吉』 とのやりとり

ENo.581 ツクシ とのやりとり

ENo.1185 夜町 とのやりとり

以下の相手に送信しました














具現LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
百薬LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.4 不思議な牙 を合成し、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
⇒ 駄物発生!駄物 を入手!
ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.8 ネジ を合成実験し、駄物 に変化することが判明しました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
『小鷹裕吉』(249) により ItemNo.6 白樺 から法衣『つばめの羽飾り』を作製してもらいました!
⇒ つばめの羽飾り/法衣:強さ26/[効果1]活力15 [効果2]- [効果3]幸運5
*****(119) により ItemNo.10 美味しい草 から料理『草餅』をつくってもらいました!
⇒ 草餅/料理:強さ40/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10
チヒロ(568) とカードを交換しました!
つよい風 (ウィンドカッター)

ブルーム を研究しました!(深度0⇒1)
ウィンドカッター を研究しました!(深度0⇒1)
ウィンドカッター を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を習得!
クリエイト:ホーネット を習得!
ヒールハーブ を習得!
ブルーム を習得!
クリエイト:マナクリスタル を習得!
レジスト を習得!
サモン:スライム を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



*****(119) は 白石 を入手!
理外のチヨ子(121) は 花びら を入手!
独りぼっちの神父(199) は 韮 を入手!
『小鷹裕吉』(249) は 花びら を入手!
理外のチヨ子(121) は 美味しい果実 を入手!
『小鷹裕吉』(249) は ネジ を入手!
理外のチヨ子(121) は 不思議な雫 を入手!
独りぼっちの神父(199) は ネジ を入手!
独りぼっちの神父(199) は 鉄板 を入手!



*****(119) に移動を委ねました。
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

Cross+Roseの音量を調整する。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







チャットが閉じられる――




























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



──曖昧な記憶だ。
とても曖昧で、そんな事が本当にあったかさえ不明瞭だ。
世界すら、信じて良いのか分からないくらい曖昧だ。
なにもかもが夢みたいに朧気で、謎だらけで。
そもそも本当の事など在りはしないかのようで。
もし。
もし、そうじゃないと言うならば。
私の夢に訴えかけてくるあの人達は、誰だろう。
私の事を繰り返し罵倒する、"私"は一体何なのだろう。
私は、私の世界は、それらは、……それらは
 |
「本当に存在しているの?」 |
おいで おいで 迷路に おいで。
彼方も 此方も 解らぬ 場所へ。
たった ひとりで 右往左往。
遠くに 見えるは 魑魅魍魎。
ほんとの わたしは 何処なのか。
それすら よやみに 吸い込まれ
もう何処にも 在りはしないのか。

知世子には沢山の"わからないこと"がある。
到底解けない難問、凝っていて難しいお菓子作り、自分の見ている星空のその先の世界、自分の未来。
知世子には沢山の"わからないこと"が増える。
幼馴染みの秘密、大人の苦悩、不穏な影、そして自分自身。
最近、その"わからないこと"は妙に増加する傾向にあった。
積み重なり、降り積もり、知世子を惑わすように。
塵芥のようにつまらないものだったらまだしも、見逃せないような鋭利な破片すら見つかる。
それは触れると確実に牙を剥いて、癒えぬ傷を作っていく。
"わからないこと"は"わからない"から、徐々に"こわい"に変わっていく。
手当てもされぬままの傷はじくじくと膿み、悪い方向へと転がり落ちていく。
しかし麻痺していく神経の中では、自分の傷の痛みもまともに気付けない。
知世子はじわじわと、ゆっくりと、しかし確実に傷を育てていく。
"平和に生きられないかもしれない。"
"この幸せは張り裂けて、無くなってしまうかもしれない。"
"大事な人達が、いなくなってしまうかもしれない。"
そんな予兆は、不穏に伸びていく黒い影は、普通の中学生には重かった。
知世子の世界はとても広くて、それでいて狭い。
もっと世界の外へと手を伸ばそうとしていても、幼い知世子の世界はまだ"友達や家族、恋人と幸せに過ごせる範囲"程しかない。
世界が変わらず回り続けようとも、他の皆が幸せになろうとも。
知世子のその範囲に、世界にいる人達が、幸せではなくなったら。
最悪消えてしまったりでもしたら。
知世子にとって、それは世界の滅亡に等しいのだ。
そんな滅亡の予感に知世子は怯えながら、また夢を見る。
──それが"知世子"だけの話であったならば、どうせただの捏造だ。
そうであったならどれだけ良かったか。
"知世子"の悪夢に出てくる誰かは、チヨ子がアンジニティに来る前に出会った人々だ。
イバラシティでは夢に出るのは不思議だが、分からないのは仕方ない。
だけどどうして、名前が思い出せない?
チヨ子の姿の時でさえ、その記憶は穴が空いたように戻ってこない。
それどころかその人達がどんな顔をしていたかすら、徐々に思い出せなくなっている。
大事なものを貰った、忘れちゃいけない大切な人達がいっぱいいた筈なのに。
私は皆から愛を貰って、それで生きているのに。
それを忘れてしまっては、いけないのに。
感情とは裏腹に、笑顔も暖かさも何もかもが手から滑り落ちて、穴がどんどんぽっかりと広がって。
チヨ子はそれに対して、どうして、なんで、と繰り返すしかなかった。
チヨ子は無力だった。
今まで自分が救われたことはあるし、救った事もある。
そう思っているし、そう言われたから。
だけどチヨ子は分からなかった。
自分の救い方は、分からなかった。
この消失を、広がる空虚を、誰に言う訳にもいかなくて。
ただ呆然と空いた穴を見つめては、立ち尽くすしかなくて。
チヨ子が出来るのは、もう"大切だった"という事しか分からなくなりつつある記憶に対して、さようならと別れの挨拶をする事だけだった。
失いたくない。
けど、もう大事な物の意味すら分からなくなりつつあるから。
だから、覚悟を決めねばならない。
何度でも。
自分を殺す程の覚悟を、何度でも。
忘れたとしても、何度でも、何度でも。
 |
星は未だ明滅し続ける。
弱いながらも、その存在を主張し続ける。
生き続けようとする。
時間は進む。残酷に。
空虚は蝕む。凄惨に。
【堂々廻りの邪竜と贄】
大人になりたかった、というのはきっとあっただろう。
大人の姿になれたのは、あくまで【オレ様】の意図の可能性もあるが。
それでもやはり、昔は大人に憧れてはいたから。
大きくなった昔の同級生に会って一緒に食事をしたり、夜に酒を飲んでゲームしてはしゃいだり。
そういうのがずっと羨ましかったのだ。
やっぱり大人になりたかったなと、今でも思える。
父親の店だって、継ぎたかった。
もう少し頑張れば、自分だって父親に匹敵する物が作れた筈だ。
言ってしまえば、そんな未来は訪れなかった。
誰も彼もに平等にやって来ると思っていた未来は、当たり前に手に入るものじゃなかった。
オレに与えられたのは、冷たくて誰の手も届かない場所だった。
"此処"は冷たい。何の温もりもない。
誰もいないし、きっと誰も知らない場所だ。
そしてオレの事も、きっと誰も知らないのだ。
それでいいと思っている。それがいいと思っている。
オレが海底から抜け出す時、【オレ様】もまた陸に這い上がる。
災厄を呼び起こす邪神を、その邪神の子を生み出す存在を、誰が望んで引き上げる?
オレは"望まれない"し"臨まない"。
悪辣なる神々をこの身体の中に廻らせたまま、ずっとずっと此処に居る。
"望まれる"ものは海底から押し上げて、"臨むべき"ものへ導いていく。
【オレ様】を"臨ませない"し"望まない"。
例え自分を否定した世界だとて、オレは決して嫌いじゃなかったから。
オレは喜んで人柱になろう。
誰も彼もから忘れ去られ、孤独な深海に身を沈めよう。
それでいい。本来オレは此処で終わるべきだったのだから。
死ねない代わりに、堂々巡りの生の中に、【オレ様】も一緒に閉じ込めてやる。
──引き裂けるような痛みが走る。
意識はある。なくなる筈がない。生かされる。
肉が空気に触れて、何かが溢れ落ちて、冷えていく。
それでも生ぬるさは消えない。命の灯火は絶やされない。
邪神は、【オレ様】は、
ハザマを彷徨う。



ENo.119 ***** とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.249 『小鷹裕吉』 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.581 ツクシ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1185 夜町 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
チヨ子 「またいっぱい物拾いしたいな~」 |
 |
チヨ子 「今回もふわちゃんに手伝ってもらお!」 |
 |
ふわちゃん 「?」 よく分かってなさそうだ。 |



スイーツ★インベーダー
|
 |
ハザマに生きるもの
|



TeamNo.12
|
 |
スイーツ★インベーダー
|



具現LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
百薬LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.4 不思議な牙 を合成し、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
 |
モチャ……っとくっ付けた。雑! |
ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.8 ネジ を合成実験し、駄物 に変化することが判明しました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
 |
モチャ……っとくっ付け…… |
 |
たと見せかけて完全にはくっ付けていない!合成実験だ!! |
『小鷹裕吉』(249) により ItemNo.6 白樺 から法衣『つばめの羽飾り』を作製してもらいました!
⇒ つばめの羽飾り/法衣:強さ26/[効果1]活力15 [効果2]- [効果3]幸運5
*****(119) により ItemNo.10 美味しい草 から料理『草餅』をつくってもらいました!
⇒ 草餅/料理:強さ40/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10
チヒロ(568) とカードを交換しました!
つよい風 (ウィンドカッター)

ブルーム を研究しました!(深度0⇒1)
ウィンドカッター を研究しました!(深度0⇒1)
ウィンドカッター を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を習得!
クリエイト:ホーネット を習得!
ヒールハーブ を習得!
ブルーム を習得!
クリエイト:マナクリスタル を習得!
レジスト を習得!
サモン:スライム を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



*****(119) は 白石 を入手!
理外のチヨ子(121) は 花びら を入手!
独りぼっちの神父(199) は 韮 を入手!
『小鷹裕吉』(249) は 花びら を入手!
理外のチヨ子(121) は 美味しい果実 を入手!
『小鷹裕吉』(249) は ネジ を入手!
理外のチヨ子(121) は 不思議な雫 を入手!
独りぼっちの神父(199) は ネジ を入手!
独りぼっちの神父(199) は 鉄板 を入手!



*****(119) に移動を委ねました。
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
エディアン 「わぁこんにちはノウレットさーん! えーと音量音量・・・コンフィグかな?」 |
Cross+Roseの音量を調整する。
 |
エディアン 「よし。・・・・・さて、どうしました?ノウレットちゃん。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたッ!」 |
 |
エディアン 「おや、てっきりあのざっくりした説明だけなのかと。」 |
 |
ノウレット 「お役に立てそうで嬉しいです!!」 |
 |
エディアン 「よろしくお願いしまーす。」 |
 |
ノウレット 「ではでは・・・・・ジャーンッ!こちらがロスト情報ですよー!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
エディアン 「なるほど、いろんなかたがいますねぇ。 彼らの願望を叶えることで影響力を得て、ハザマで強くもなれるんですか。」 |
 |
エディアン 「どこにいるかとか、願望の内容とか、そういうのは分かります?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「むむむ・・・・・頑張って見つけないといけませんねぇ。 こう、ロストには頭にマークが付いてるとか・・・そういうのは?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・システムメッセージなのかなこれ。 ・・・ノウレットちゃんの好きなものは?」 |
 |
ノウレット 「肉ですッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・嫌いなものは?」 |
 |
ノウレット 「白南海さん、です・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・さては何かしましたね、彼。」 |
 |
エディアン 「では、ロスト情報もそこそこ気にしながら進めていきましょう!」 |
 |
ノウレット 「ファイトでーすッ!!」 |
チャットが閉じられる――







いちご肉まん
|
 |
スイーツ★インベーダー
|


ENo.121
脈打つチョコレート



どんな形になろうとも、生まれた心は有るが儘。
愛の記憶を抱く限り、齧られたって失せはしない。
空虚に放逐されようと、星空色を身に宿す。
そのチョコレートは確かに、脈打っている。
「有心 知世子から愛を込めて。そして願いと祈りを込めて。
――――流星を、あなたに!」
【名前】有心 知世子(うこころ ちよこ)/理外のチヨ子
【性別】女
【年齢】15歳
【体型】152cm/43kg
【陣営】アンジ/アンジ
【好きなもの】
お菓子、花、星、恋バナ、とある小説家の本、いつメン、彼氏
【嫌いなもの】
暴力、退屈、無価値、■■■
【住所】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1219
【詳細】
爆波津中学校の3年生。
チョコレート色の髪と、ハート模様のピンクの瞳が特徴。
夜空を閉じ込めたようなペンデュラムと、緑と橙の花のピンをいつも着けている。
表情豊かで行動力に溢れる。天体観測、読書、恋バナには特に熱心。
幼馴染み二人と仲良しの小説家さんの三人を『いつメン』と呼称して仲良くしている。
7歳年上の同居人がいる。
所謂恋仲というやつで、誰よりも何よりも愛している。
二人で一つの星空であり、永遠を誓い合った王子と姫。
何処でも何時でも、ずっと一緒。
【正体】
大切な人と手を繋いで新しい世界に向かう筈だったチョコレートの少女。
否定された魂は肉体から弾き飛ばされ、アンジニティに堕ちた。
今は形のない虚の化物になりつつあるが、内に秘めた希望がその魂を繋ぎ止めている。
彼女の願いは『否定された存在を幸せにすること』だ。
恋人を、家族を、幼馴染みを、友人を、アンジニティを。
幸せにする為に、侵略を行う。
【異能】
『甘美な流星』─éclat・chocolat─
星の力を使い、治癒効果のあるチョコレートを生み出す。
生み出されるチョコは様々で、チョコを使った他のお菓子も出せる。
(チョコが苦手でも、何故かすんなり食べられるかも)
軽傷から重傷、ストレス解消まで幅広く癒せるが、重い怪我や苦悩であるほど星の力が必要。
星の力の吸収・使用中は、毛先が夜空色に光り瞳の色が変化する。
ハザマでは効果が強化される他、チヨ子が許可した者以外には毒物となる。
空虚、虚無に縁のあるものに対しては、より効果的な治療薬となる。
『永久のワルツ』─valse pour ma sucrette─
自分の肉体を結晶体、流動体、霧状体の三種類に変容させる。
【結晶】結晶に包まれる。破片は光になって消える為、無害。
【流動】液状になる。スライムに近く、絡み付いたり伸び縮み出来る。
【霧状】霧状になる。物体をすり抜ける事が可能だが、自分からも干渉は不可能。
変容する際に、たまに10cm程度の使役生物を二匹生み出す。
使役生物は頭が悪く、使い物にならない。飽きたら勝手に消える。
ハザマでは常時変容状態になり、本質の“命を生み出す”事に特化する。
使役生物は自分の意志関係なく生み出され、時間が経過すると周りの者を見境なく襲い始める。
最終的にチヨ子の手によって殺される事で、役目を終える。
――――――――――――――
健気に主の帰りを待つ、籠がひとつと鳥が一羽。
鳥籠の鍵が開いたとて、鳥はひたすら主を待つ。
時計の針がチクタクと、脳裏で響いて責め立てる。
どうかこのまま永遠に、貴方の事を想わせて。
「──ワタシの事が必要ですか?」
【名前】籠草 飛鳥(かごくさ あすか)
【性別】女
【年齢】25歳
【体型】151cm/45kg
【陣営】イバラ/???
【好きなもの】
歌唱、鳥類、コーヒー、■■
【嫌いなもの】
蔑視、ピーマン、■■
【住所】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2999
【詳細】
黒髪で黄色の目、白衣が特徴的な医学・薬学系の研究員。
二つのネックレスと左手薬指の指輪を、常時身に着けている。
口を開くとよく囀ずる。
感情の起伏が激しく落ち込みやすい部分も。
籠草という苗字は偽りであり、本来の苗字は黒歌(くろうた)。
他人には籠草と名乗り、バレるまでは隠し通す。
【異能】
『黒歌鳥のからくり時計』─tick tock twirl─
固定し、持続させる異能。
とある歌を歌う事をトリガーに発動し、飛鳥の後ろから現れるからくり時計から機械の黒歌鳥が舞う。
飛んでいるものは飛んだまま、浮いているものは浮いたまま。
そんな風に、ただの物体から周囲の人間、他人の異能によって起きた事象や近辺の天候等も固定できる。
ただ物体に対しては一日につき12回まで、それ以外に使用した場合は1回で物体5回分計算。
12回を超過すると、気絶して大きな代償を払う事になる。
ハザマでは計24回までは可能。
――――――――――――――
その身を持って、償わねばならぬものがある。
その身を持って、果たさねばならぬことがある。
助からなくても。報われなくとも。
深海に、救いの手など存在せずとも。
「オレはいつでも、此処から見てますよ」
【名前】神々廻 のぞみ(ししば ―)
【性別】男
【年齢】24歳
【体型】188cm/71kg
【陣営】アンジ/イバラ
【好きなもの】
空、海、工作、甘味、接触
【嫌いなもの】
自分、孤独、軽薄な言葉
【住所】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=4114
【詳細】
長い青髪に赤い瞳を持つ男。人前ではマスクを外さない。
マシカ区の海辺にある雑貨店『Monologia』の店主。
知世子の従兄弟でもある。
無表情に等しいが友好的。自由に生きる事を重視している。
他人との距離感を測るのが下手。
物理的に距離感を計るのも苦手。よく低い天井に頭をぶつける。
【異能】
『甘美な流水』─làpiz de labios─
自分の声を聞いた相手に好意を抱かせる異能。
口が隠れていたり相手の視界に入らなければ、無効化可能。
独り言や相手に対する言葉ではなくとも条件を満たす限り有効で、発した声や言葉が対象を特定したものである程に強力になる。
名前を呼ぶだけで、偽りの好意と同時に発情を促してしまう程に。
意識すれば相手に指定した感情を抱かせることも可能だが、精神と肉体に負担がかかる為あまり使用しない。
『水泡に帰す』─fruta prohibida─
彼はこの異能について普段口にしない。
【正体】
"死"を否定された事により堕ちてしまったイバラシティの住民。
アンジニティでとある邪神の血肉を口にしてしまい、その身体を復活の為に扱われている。
しかし神の血肉を喰らい半分程その力を奪ってしまった故にのぞみは意識と肉体の主導権を完全には失っておらず、邪神をイバラシティに行かせない為にも侵略には手を貸さない。
【全員の連絡先】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2638
【PL情報】
何でもフリーなイバラ初心者です。
手探りですが、よろしくお願いします。
既知設定はお気軽にどうぞ。
多分置きレス多めになります。
Twitter
@SeventhSora
サブの飛鳥のプロフ絵はNo.119様から!
ありがとうございます!
愛の記憶を抱く限り、齧られたって失せはしない。
空虚に放逐されようと、星空色を身に宿す。
そのチョコレートは確かに、脈打っている。
「有心 知世子から愛を込めて。そして願いと祈りを込めて。
――――流星を、あなたに!」
【名前】有心 知世子(うこころ ちよこ)/理外のチヨ子
【性別】女
【年齢】15歳
【体型】152cm/43kg
【陣営】アンジ/アンジ
【好きなもの】
お菓子、花、星、恋バナ、とある小説家の本、いつメン、彼氏
【嫌いなもの】
暴力、退屈、無価値、■■■
【住所】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1219
【詳細】
爆波津中学校の3年生。
チョコレート色の髪と、ハート模様のピンクの瞳が特徴。
夜空を閉じ込めたようなペンデュラムと、緑と橙の花のピンをいつも着けている。
表情豊かで行動力に溢れる。天体観測、読書、恋バナには特に熱心。
幼馴染み二人と仲良しの小説家さんの三人を『いつメン』と呼称して仲良くしている。
7歳年上の同居人がいる。
所謂恋仲というやつで、誰よりも何よりも愛している。
二人で一つの星空であり、永遠を誓い合った王子と姫。
何処でも何時でも、ずっと一緒。
【正体】
大切な人と手を繋いで新しい世界に向かう筈だったチョコレートの少女。
否定された魂は肉体から弾き飛ばされ、アンジニティに堕ちた。
今は形のない虚の化物になりつつあるが、内に秘めた希望がその魂を繋ぎ止めている。
彼女の願いは『否定された存在を幸せにすること』だ。
恋人を、家族を、幼馴染みを、友人を、アンジニティを。
幸せにする為に、侵略を行う。
【異能】
『甘美な流星』─éclat・chocolat─
星の力を使い、治癒効果のあるチョコレートを生み出す。
生み出されるチョコは様々で、チョコを使った他のお菓子も出せる。
(チョコが苦手でも、何故かすんなり食べられるかも)
軽傷から重傷、ストレス解消まで幅広く癒せるが、重い怪我や苦悩であるほど星の力が必要。
星の力の吸収・使用中は、毛先が夜空色に光り瞳の色が変化する。
ハザマでは効果が強化される他、チヨ子が許可した者以外には毒物となる。
空虚、虚無に縁のあるものに対しては、より効果的な治療薬となる。
『永久のワルツ』─valse pour ma sucrette─
自分の肉体を結晶体、流動体、霧状体の三種類に変容させる。
【結晶】結晶に包まれる。破片は光になって消える為、無害。
【流動】液状になる。スライムに近く、絡み付いたり伸び縮み出来る。
【霧状】霧状になる。物体をすり抜ける事が可能だが、自分からも干渉は不可能。
変容する際に、たまに10cm程度の使役生物を二匹生み出す。
使役生物は頭が悪く、使い物にならない。飽きたら勝手に消える。
ハザマでは常時変容状態になり、本質の“命を生み出す”事に特化する。
使役生物は自分の意志関係なく生み出され、時間が経過すると周りの者を見境なく襲い始める。
最終的にチヨ子の手によって殺される事で、役目を終える。
――――――――――――――
健気に主の帰りを待つ、籠がひとつと鳥が一羽。
鳥籠の鍵が開いたとて、鳥はひたすら主を待つ。
時計の針がチクタクと、脳裏で響いて責め立てる。
どうかこのまま永遠に、貴方の事を想わせて。
「──ワタシの事が必要ですか?」
【名前】籠草 飛鳥(かごくさ あすか)
【性別】女
【年齢】25歳
【体型】151cm/45kg
【陣営】イバラ/???
【好きなもの】
歌唱、鳥類、コーヒー、■■
【嫌いなもの】
蔑視、ピーマン、■■
【住所】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2999
【詳細】
黒髪で黄色の目、白衣が特徴的な医学・薬学系の研究員。
二つのネックレスと左手薬指の指輪を、常時身に着けている。
口を開くとよく囀ずる。
感情の起伏が激しく落ち込みやすい部分も。
籠草という苗字は偽りであり、本来の苗字は黒歌(くろうた)。
他人には籠草と名乗り、バレるまでは隠し通す。
【異能】
『黒歌鳥のからくり時計』─tick tock twirl─
固定し、持続させる異能。
とある歌を歌う事をトリガーに発動し、飛鳥の後ろから現れるからくり時計から機械の黒歌鳥が舞う。
飛んでいるものは飛んだまま、浮いているものは浮いたまま。
そんな風に、ただの物体から周囲の人間、他人の異能によって起きた事象や近辺の天候等も固定できる。
ただ物体に対しては一日につき12回まで、それ以外に使用した場合は1回で物体5回分計算。
12回を超過すると、気絶して大きな代償を払う事になる。
ハザマでは計24回までは可能。
――――――――――――――
その身を持って、償わねばならぬものがある。
その身を持って、果たさねばならぬことがある。
助からなくても。報われなくとも。
深海に、救いの手など存在せずとも。
「オレはいつでも、此処から見てますよ」
【名前】神々廻 のぞみ(ししば ―)
【性別】男
【年齢】24歳
【体型】188cm/71kg
【陣営】アンジ/イバラ
【好きなもの】
空、海、工作、甘味、接触
【嫌いなもの】
自分、孤独、軽薄な言葉
【住所】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=4114
【詳細】
長い青髪に赤い瞳を持つ男。人前ではマスクを外さない。
マシカ区の海辺にある雑貨店『Monologia』の店主。
知世子の従兄弟でもある。
無表情に等しいが友好的。自由に生きる事を重視している。
他人との距離感を測るのが下手。
物理的に距離感を計るのも苦手。よく低い天井に頭をぶつける。
【異能】
『甘美な流水』─làpiz de labios─
自分の声を聞いた相手に好意を抱かせる異能。
口が隠れていたり相手の視界に入らなければ、無効化可能。
独り言や相手に対する言葉ではなくとも条件を満たす限り有効で、発した声や言葉が対象を特定したものである程に強力になる。
名前を呼ぶだけで、偽りの好意と同時に発情を促してしまう程に。
意識すれば相手に指定した感情を抱かせることも可能だが、精神と肉体に負担がかかる為あまり使用しない。
『水泡に帰す』─fruta prohibida─
彼はこの異能について普段口にしない。
【正体】
"死"を否定された事により堕ちてしまったイバラシティの住民。
アンジニティでとある邪神の血肉を口にしてしまい、その身体を復活の為に扱われている。
しかし神の血肉を喰らい半分程その力を奪ってしまった故にのぞみは意識と肉体の主導権を完全には失っておらず、邪神をイバラシティに行かせない為にも侵略には手を貸さない。
【全員の連絡先】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2638
【PL情報】
何でもフリーなイバラ初心者です。
手探りですが、よろしくお願いします。
既知設定はお気軽にどうぞ。
多分置きレス多めになります。
@SeventhSora
サブの飛鳥のプロフ絵はNo.119様から!
ありがとうございます!
16 / 30
133 PS
チナミ区
I-14
I-14





































#交流歓迎
9
#片道切符チャット
5
初心者マークついてます
2
【うちの子】貸し借りOKコミュ
5
ログまとめられフリーの会
公立爆波津中学校
7
両陣営の和平を真面目に考える会
31
召喚士の館(具現コミュ)
8
チキンレース
36



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 5 | 黒いリボン | 武器 | 35 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | つばめの羽飾り | 法衣 | 26 | 活力15 | - | 幸運5 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 9 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV10)[効果2]充填10(LV20)[効果3]増幅10(LV30) | |||
| 10 | 草餅 | 料理 | 40 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |
| 11 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 12 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
| 13 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 合成 | 30 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 射手座の弓矢 (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 水瓶座の荒波 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 乙女座の口付け (ヒール) | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 捕食欲求の特異点 (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| いたずら隕石 (クリエイト:タライ) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| 決3 | 甘美な流星 (ヒールポーション) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| 希望の息吹 (プリディクション) | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |
| ヒールハーブ | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| 身を食む空虚 (クリエイト:ヴェノム) | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| 大好きな物 (クリエイト:メガネ) | 5 | 0 | 100 | 味:DX・AG増(5T) | |
| 満ちる星影 (マナポーション) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 決3 | 星雲ベッド (ファーマシー) | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| クリエイト:マナクリスタル | 5 | 0 | 110 | 味:充填LV増 | |
| レジスト | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+肉体精神変調防御 | |
| サモン:スライム | 5 | 2 | 300 | 自:スライム召喚 | |
| お手伝いふわちゃん (サモン:サーヴァント) | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 落とし子のささやき (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 揺らめく星あかり (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| ゆかりのリボン (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 夜空のペンデュラム (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 駄物発生 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『合成』で、合成成功時に自分にアイテム「駄物」が手に入る。(実験除く、1更新1つまで) |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 2 ]ウィンドカッター | [ 3 ]ヒールポーション |
| [ 1 ]ブルーム | [ 1 ]ファーマシー | [ 1 ]ハードブレイク |

PL / 七日空