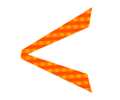<< 1:00~2:00




─────────────────────────────────
【2】
むかしむかし、あるところに。
娘が一人、住んでおりました。
青と鼠色の間、薄寒い色の肌。
海草のような深く濁った緑色の髪。
およそ人とは思えない色をした娘が、一体どんな親から生まれたのか、
それは娘自身にも分かりません。
娘はひとりぼっちでした。
娘の暮らしていた村では、迷信深い村長が娘の面倒を見ていました。
情け心によるものではありません。
村長はただただ、怖かったのです。娘が『祟り』を振り撒くことが。
娘は寂しいと思いました。
ですが、座敷から出られないこと以外はそれなりに丁重に扱われていたので、
娘は我慢していました。
本だけは与えられたので、それで字を覚え、たくさんの本を読み、
外の世界のことを、たくさんたくさん、夢に見ました。
それだけで幸せだと、思うことにしました。
ある日、村長が亡くなりました。
その日の夜、娘は捨てられました。
村から遠い遠い山の中。
外に出たこともない娘がひとり。
覚えているのは、村の若い衆に腕を掴まれた時の痛みと、罵声。
そして、目。
自分を見る、村人たちの、目。
「ああ」
「わたくしは」
「ばけもの、だったのね」
娘にはひとつ、不思議な力がありました。
触れるだけで、ひとのからだの悪いところをたちどころに言い当てる。
村長の病も、村人の病も、望まれ、触れて、教えました。
けれど幼い娘には、治し方までは分かりません。
村長は最期まで娘にすがろうとしましたが、娘は困った顔をするばかり。
それがいけなかったのでしょう。
村長の息子は、怒り狂いながら娘を殴りました。
娘が村長を呪い殺したのだと、そう叫びながら。
娘には生きるすべがありません。
食べられるものも分かりません。雨をしのぐ場所も分かりません。
どうすれば村に戻れるのかも分かりませんし、
戻ったところで彼らが受け入れてくれるとは思えません。
だけど、目の前の泉に身を投げるのは怖いし、
山の斜面を転げ落ちるのも痛そうです。
獣の声が聞こえて、ぶるぶると娘は震えました。
どうして自分は、ずっとひとりぼっちなのだろう。
こんな目に遭うなら、せめて最期くらい、誰かの傍にいたかった。
誰かに看取ってほしかった。なのに、こんなの、あんまりだ。
涙があとからあとから、青灰色の肌を濡らします。
けれど、ここは山の奥。
泣いても泣いても、助けなど来る筈が──
「やあ、これはどうしたことだ。
べっぴんさんが泣いている」
不意に聞こえた、男の声。
娘はびくりと顔を上げ、声の主から逃げようと、
その体を泉へと向けました。
天の助けだと、そう思いたかった。
でも自分の記憶にある男は、殴るし、怒鳴る。
縄で自分を縛り、こんなところに連れてきた。
それに、村で自分を掴んだ村長の息子。
彼に触れたときに“見えた”流れは、乱れ、脈打ち……
まるで物語で読んだ、人を丸のみにする大蛇のようで。
それは娘にとって、とてもとても怖いものだったのです。
もっと酷いことをされるくらいなら、いっそ身を投げてしまおうか。
そう考えた娘の手を、けれど、男の手が掴んで止めてしまいます。
「そちらは危ないぞ、娘よ。
泉は深くて、私でも足がつかないほどだ」
優しい声。
優しい波。
何が自分に触れているのか、分からなくて。
娘は思わず、男を見ようと振り返りました。
「あなた、さまは、目が」
分かるのです。娘には。
普通の体とくらべて、おかしくなっているところが。
彼の体の中、流れが正しく巡っていないところが。
けれど。
そんなことよりも、酷く驚いたのは。
「なに、盲でも、この山のことなら何でも分かる。
それよりも、寒かろう。
ついておいで。何もない小屋だが、茶くらいは出そう」
そう言って笑う、男の“流れ”が。
驚くほどに静かで、澄んでいて、心地よくて。
ほんの少しも不安も、そこには無くて。
泣きたくなるほど──綺麗で。
「わ、わたくしは、およそ常人とは思えぬ見目をしております」
「私は色は判らぬが、“かたち”は分かる。お主は器量良しだ」
「村を追い出され、山に捨てられました。行く宛もありません」
「ならばうちに居れば良い。不便な暮らしだが、生きるに困ることはない」
「よ、よそのかたに、あらぬ噂を……」
「かっかっか。うちに最後に人が来たのは、さて何日前だったかなあ」
娘と手を繋いだまま、男は語ります。
その“流れ”は何を尋ねても、ほんの少しも揺れることがありません。
嘘も、悪意も、何もない。
このひとは、何一つ隠していない。
捨てる神あれば拾う神あり、とはこのことでしょうか。
また、ほろほろと涙を流しながらも。
娘は男に手を引かれ、一歩一歩、坂を降りていきます。
「わたくしは、揺律音(ゆりね)と申します」
「荊尾 瀬渡(かたらお せと)。宜しく、揺律音」
「こちらこそ……宜しく、お願い致します」
山の麓に小屋がひとつ。
盲の男と、青灰肌の娘。
これは二人が出会い、共に暮らし始めた、
最初の日のおはなし。
─────────────────────────────────



ENo.12 七夏 とのやりとり

ENo.72 ウィル とのやりとり

ENo.95 暁人 とのやりとり

ENo.150 泥蘇光悪渡 とのやりとり

ENo.191 詩穂乃 とのやりとり

ENo.219 ステバ とのやりとり

ENo.298 避役 とのやりとり

ENo.352 根岸 とのやりとり

ENo.377 火花 とのやりとり

ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり

ENo.414 レスター とのやりとり

ENo.501 カナリア とのやりとり

ENo.512 《冒涜する天秤》 とのやりとり

ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり

ENo.587 いちま とのやりとり

ENo.656 シエル とのやりとり

ENo.897 _____ とのやりとり

以下の相手に送信しました












領域LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
命術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.6 ボロ布 から射程2の武器『右天黒月』を作製しました!
⇒ 右天黒月/武器:強さ40/[効果1]闇纏10 [効果2]- [効果3]-【射程2】
詩穂乃(191) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程2の武器『ナイフ』を作製しました!
詩穂乃(191) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『野菜(?)炒め詩穂乃風』をつくってもらいました!
⇒ 野菜(?)炒め詩穂乃風/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
ロッテ(948) とカードを交換しました!
もっと身体に良い薬草料理 (ファーマシー)

イグニス を研究しました!(深度0⇒1)
アイシクルランス を研究しました!(深度0⇒1)
グランドクラッシャー を研究しました!(深度0⇒1)
ウォーターフォール を習得!
フロウライフ を習得!
アクアヒール を習得!
アクアブランド を習得!
水の祝福 を習得!
☆チャクラグラント を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





闇(273) に移動を委ねました。
チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調17⇒16)
採集はできませんでした。
- 闇(273) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――



























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



─────────────────────────────────
【2】
むかしむかし、あるところに。
娘が一人、住んでおりました。
青と鼠色の間、薄寒い色の肌。
海草のような深く濁った緑色の髪。
およそ人とは思えない色をした娘が、一体どんな親から生まれたのか、
それは娘自身にも分かりません。
娘はひとりぼっちでした。
娘の暮らしていた村では、迷信深い村長が娘の面倒を見ていました。
情け心によるものではありません。
村長はただただ、怖かったのです。娘が『祟り』を振り撒くことが。
娘は寂しいと思いました。
ですが、座敷から出られないこと以外はそれなりに丁重に扱われていたので、
娘は我慢していました。
本だけは与えられたので、それで字を覚え、たくさんの本を読み、
外の世界のことを、たくさんたくさん、夢に見ました。
それだけで幸せだと、思うことにしました。
ある日、村長が亡くなりました。
その日の夜、娘は捨てられました。
村から遠い遠い山の中。
外に出たこともない娘がひとり。
覚えているのは、村の若い衆に腕を掴まれた時の痛みと、罵声。
そして、目。
自分を見る、村人たちの、目。
「ああ」
「わたくしは」
「ばけもの、だったのね」
娘にはひとつ、不思議な力がありました。
触れるだけで、ひとのからだの悪いところをたちどころに言い当てる。
村長の病も、村人の病も、望まれ、触れて、教えました。
けれど幼い娘には、治し方までは分かりません。
村長は最期まで娘にすがろうとしましたが、娘は困った顔をするばかり。
それがいけなかったのでしょう。
村長の息子は、怒り狂いながら娘を殴りました。
娘が村長を呪い殺したのだと、そう叫びながら。
娘には生きるすべがありません。
食べられるものも分かりません。雨をしのぐ場所も分かりません。
どうすれば村に戻れるのかも分かりませんし、
戻ったところで彼らが受け入れてくれるとは思えません。
だけど、目の前の泉に身を投げるのは怖いし、
山の斜面を転げ落ちるのも痛そうです。
獣の声が聞こえて、ぶるぶると娘は震えました。
どうして自分は、ずっとひとりぼっちなのだろう。
こんな目に遭うなら、せめて最期くらい、誰かの傍にいたかった。
誰かに看取ってほしかった。なのに、こんなの、あんまりだ。
涙があとからあとから、青灰色の肌を濡らします。
けれど、ここは山の奥。
泣いても泣いても、助けなど来る筈が──
「やあ、これはどうしたことだ。
べっぴんさんが泣いている」
不意に聞こえた、男の声。
娘はびくりと顔を上げ、声の主から逃げようと、
その体を泉へと向けました。
天の助けだと、そう思いたかった。
でも自分の記憶にある男は、殴るし、怒鳴る。
縄で自分を縛り、こんなところに連れてきた。
それに、村で自分を掴んだ村長の息子。
彼に触れたときに“見えた”流れは、乱れ、脈打ち……
まるで物語で読んだ、人を丸のみにする大蛇のようで。
それは娘にとって、とてもとても怖いものだったのです。
もっと酷いことをされるくらいなら、いっそ身を投げてしまおうか。
そう考えた娘の手を、けれど、男の手が掴んで止めてしまいます。
「そちらは危ないぞ、娘よ。
泉は深くて、私でも足がつかないほどだ」
優しい声。
優しい波。
何が自分に触れているのか、分からなくて。
娘は思わず、男を見ようと振り返りました。
「あなた、さまは、目が」
分かるのです。娘には。
普通の体とくらべて、おかしくなっているところが。
彼の体の中、流れが正しく巡っていないところが。
けれど。
そんなことよりも、酷く驚いたのは。
「なに、盲でも、この山のことなら何でも分かる。
それよりも、寒かろう。
ついておいで。何もない小屋だが、茶くらいは出そう」
そう言って笑う、男の“流れ”が。
驚くほどに静かで、澄んでいて、心地よくて。
ほんの少しも不安も、そこには無くて。
泣きたくなるほど──綺麗で。
「わ、わたくしは、およそ常人とは思えぬ見目をしております」
「私は色は判らぬが、“かたち”は分かる。お主は器量良しだ」
「村を追い出され、山に捨てられました。行く宛もありません」
「ならばうちに居れば良い。不便な暮らしだが、生きるに困ることはない」
「よ、よそのかたに、あらぬ噂を……」
「かっかっか。うちに最後に人が来たのは、さて何日前だったかなあ」
娘と手を繋いだまま、男は語ります。
その“流れ”は何を尋ねても、ほんの少しも揺れることがありません。
嘘も、悪意も、何もない。
このひとは、何一つ隠していない。
捨てる神あれば拾う神あり、とはこのことでしょうか。
また、ほろほろと涙を流しながらも。
娘は男に手を引かれ、一歩一歩、坂を降りていきます。
「わたくしは、揺律音(ゆりね)と申します」
「荊尾 瀬渡(かたらお せと)。宜しく、揺律音」
「こちらこそ……宜しく、お願い致します」
山の麓に小屋がひとつ。
盲の男と、青灰肌の娘。
これは二人が出会い、共に暮らし始めた、
最初の日のおはなし。
─────────────────────────────────



ENo.12 七夏 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.72 ウィル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.95 暁人 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.150 泥蘇光悪渡 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.191 詩穂乃 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.219 ステバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.298 避役 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.352 根岸 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.377 火花 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.414 レスター とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.501 カナリア とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.512 《冒涜する天秤》 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.587 いちま とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||
ENo.656 シエル とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.897 _____ とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
ミツフネ 「勝てない戦いはするつもりはねえけど、 そんなこと言ってられる状況でもねえわな……」 |
「……斯様に一時間が長く感じるのは、いつ以来やら」 |







領域LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
命術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.6 ボロ布 から射程2の武器『右天黒月』を作製しました!
⇒ 右天黒月/武器:強さ40/[効果1]闇纏10 [効果2]- [効果3]-【射程2】
 |
ミツフネ 「上手く使っていかなきゃな」 |
詩穂乃(191) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程2の武器『ナイフ』を作製しました!
詩穂乃(191) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『野菜(?)炒め詩穂乃風』をつくってもらいました!
⇒ 野菜(?)炒め詩穂乃風/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
 |
詩穂乃 「えーっと、えーっと…多分これで美味しいと思うんだけど…。変な味したら、ぺ、してね!」 |
ロッテ(948) とカードを交換しました!
もっと身体に良い薬草料理 (ファーマシー)

イグニス を研究しました!(深度0⇒1)
アイシクルランス を研究しました!(深度0⇒1)
グランドクラッシャー を研究しました!(深度0⇒1)
ウォーターフォール を習得!
フロウライフ を習得!
アクアヒール を習得!
アクアブランド を習得!
水の祝福 を習得!
☆チャクラグラント を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





闇(273) に移動を委ねました。
チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調17⇒16)
採集はできませんでした。
- 闇(273) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。





ENo.161
小佐間 御津舟



─────────────────────
** 注意:彼らの異能は複写できない。 **
─────────────────────
■小佐間 御津舟(おさま みつふね)
身長170cm、体重そこそこ。
相良伊橋高校二年二組に通う生徒。
バイト先が潰れてしまったので、
新たなバイト先を探している。
住居はエクレールツクナミ305号室。
安里 杏莉(ENo.102)と付き合っている。
【異能】
『???』
彼の持つ唯一の異能。
以下の異能を正しい形で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
展開空間内の全ての形を認識する能力。
五感を封じられていても認識可能。
空間内にこちらから干渉することはできない。
『整流命繋(ミツナギ)』
命の持つ“流れ”を認識、把握する能力。
流れが歪んだり欠損したりしている場合、
これを正しい流れに寄せることができる。
『巫の誓約』
大切な人を喪ってはならない。
その手に戦うための力が無くとも。
────────────────────
■小佐間 美鳥夜(おさま みとりや)
身長150cm程度。胸はぜんぜんない。
チナミ区の実家に住む中学三年生。
なのにツクナミの兄の家によくいる。
考えるより先に行動するタイプ。
【異能】
『???』
彼女の持つ唯一の異能。
以下の異能を“本来と逆の形”で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
兄の異能と同じ。
『整流命繋(ミツナギ)』
兄の異能と同じ。
『茨の誓約』
その力で他者を殺めてはならない。
誰かが危険に晒されていたとしても。
────────────────────
■昏田 三(くらだ みすじ)
身長2m弱。体重すごくおもい。
屈強な身体、血の気の無い肌をした
明らかにその筋の人間にしか見えない男。
本職は綜合警備保障。副業は家庭教師。
通信教育も承ります。
【異能:流体加速】
液体を加速させる空間を作る。
加算ではなく乗算でかかるため、
元の勢いが強いほど威力も大きくなる。
【その他技能】
射撃術、近接戦闘術、符術、
特殊装甲型宅配車両からの制圧砲撃
────────────────────
■山本(やまもと)/
亜倉 右賢(あくら うげん)
身長180cmちょい。ひょろ長いおっさん。
常に白衣を着ている。うさんくさい。
阿久津機術研究所勤務。
【異能:流浪者】
自分の意思に関係なく世界を渡ってしまう。
きっかけや転移先など一切が制御できない。
【その他技能】
魔術、魔機混合具製作、話術
────────────────────
■繋譜音(ツフネ)
譜と音を繋ぐ者。亡霊。
────────────────────
■水渡里(ミトリ)
水と里を渡す者。アンジニティ。
────────────────────
** 注意:彼らの異能は複写できない。 **
─────────────────────
■小佐間 御津舟(おさま みつふね)
身長170cm、体重そこそこ。
相良伊橋高校二年二組に通う生徒。
バイト先が潰れてしまったので、
新たなバイト先を探している。
住居はエクレールツクナミ305号室。
安里 杏莉(ENo.102)と付き合っている。
【異能】
『???』
彼の持つ唯一の異能。
以下の異能を正しい形で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
展開空間内の全ての形を認識する能力。
五感を封じられていても認識可能。
空間内にこちらから干渉することはできない。
『整流命繋(ミツナギ)』
命の持つ“流れ”を認識、把握する能力。
流れが歪んだり欠損したりしている場合、
これを正しい流れに寄せることができる。
『巫の誓約』
大切な人を喪ってはならない。
その手に戦うための力が無くとも。
────────────────────
■小佐間 美鳥夜(おさま みとりや)
身長150cm程度。胸はぜんぜんない。
チナミ区の実家に住む中学三年生。
なのにツクナミの兄の家によくいる。
考えるより先に行動するタイプ。
【異能】
『???』
彼女の持つ唯一の異能。
以下の異能を“本来と逆の形”で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
兄の異能と同じ。
『整流命繋(ミツナギ)』
兄の異能と同じ。
『茨の誓約』
その力で他者を殺めてはならない。
誰かが危険に晒されていたとしても。
────────────────────
■昏田 三(くらだ みすじ)
身長2m弱。体重すごくおもい。
屈強な身体、血の気の無い肌をした
明らかにその筋の人間にしか見えない男。
本職は綜合警備保障。副業は家庭教師。
通信教育も承ります。
【異能:流体加速】
液体を加速させる空間を作る。
加算ではなく乗算でかかるため、
元の勢いが強いほど威力も大きくなる。
【その他技能】
射撃術、近接戦闘術、符術、
特殊装甲型宅配車両からの制圧砲撃
────────────────────
■山本(やまもと)/
亜倉 右賢(あくら うげん)
身長180cmちょい。ひょろ長いおっさん。
常に白衣を着ている。うさんくさい。
阿久津機術研究所勤務。
【異能:流浪者】
自分の意思に関係なく世界を渡ってしまう。
きっかけや転移先など一切が制御できない。
【その他技能】
魔術、魔機混合具製作、話術
────────────────────
■繋譜音(ツフネ)
譜と音を繋ぐ者。亡霊。
────────────────────
■水渡里(ミトリ)
水と里を渡す者。アンジニティ。
────────────────────
16 / 30
142 PS
チナミ区
I-16
I-16




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 左天白陽 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 錆符 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 右天黒月 | 武器 | 40 | 闇纏10 | - | - | 【射程2】 |
| 7 | 野菜(?)炒め詩穂乃風 | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV25)[防具]強靭10(LV20)[装飾]耐狂10(LV20) | |||
| 9 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 10 | 爪 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]反撃10(LV30)[装飾]器用10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 武器 | 30 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 火行式改・甲 (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 火行式改・点 (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 水行式改・連 (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 水行式改・乱 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 御繋・常 (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 火行御繋・転 (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 火行式改・貫 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 水行式改・制 (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 火行式改・一矢 (ストライク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 水行式改・水鏡 (リフレクション) | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| 水行式改・刃砕 (コンテイン) | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| 水行式改・清流 (チャージ) | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| 土行式改・吼虎 (ガーディアン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| 土行式改・破軍 (カウンター) | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
| 火行式改・衝破 (イレイザー) | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| チャクラグラント | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 | |
| 火行式改・裂閃槍 (ハードブレイク) | 6 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 調息 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 調息 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 流転 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 流転 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 流転 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 構え (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 構え (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
クリスマス (ペネトレイト) |
0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
|
『メリーさんの怪』 (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
もっと身体に良い薬草料理 (ファーマシー) |
0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]レッドショック |
| [ 1 ]チャージ | [ 1 ]ファイアボルト | [ 1 ]イレイザー |
| [ 1 ]イグニス | [ 1 ]アイシクルランス | [ 1 ]グランドクラッシャー |

PL / きぬくろ