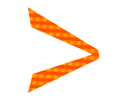<< 0:00~1:00




─────────────────────────────────
【1】
むかしむかし、あるところに。
盲(めしい)の男がひとり、住んでおりました。
盲の男は、目が見えないので、
苦労の絶えぬ暮らしをしておりました。
けれど不思議なことに、男はいつもニコニコしていて、
苦労など欠片もない、などと言うのです。
両親も傍におらず、山のふもとで一人きり。
時折行き過ぎる行商人と、物々交換で物を得て、
後は全て自給自足と言う生活。
常人でさえ音を上げる厳しい毎日ですが、
なぜだか男が倒れることはありません。
ある時、不思議に思ったひとりの行商人が
男の後を尾けてみようと考えます。
男の足は速くなく、杖を突き突き山を登るものですから
後を追うのも容易かろうと、こう考えたのです。
目が見えなければ狩りもできない、山菜もとれない。
それなのにあの男は飢える素振りもないどころか、病ひとつかからない。
ならばきっとあの男は、山の中にある恵みの園、
その場所を知っているに違いない。
ところが行商人、山に分け入って少しの後、
とんでもない考え違いに気付きました。
後を追うのが容易いなど、とんでもない。
道はなく、木々が茂って足元は常に暗く、坂は急。
獣の気配はそこかしこにあり、おちおち休みもとれません。
恵みの園などどこにもないじゃないか、と文句を吐いた行商人。
山の神のバチでも当たったのでしょうか。
浮石を踏み抜き、体勢を崩し、そのまま崖へと真っ逆さま。
谷底でくしゃりと潰れ、哀れ一巻の終わり。
── と、なっても、おかしくなかったのですが。
谷底に落ちかけた行商人の手を、盲の男が掴んだので、
行商人は九死に一生を得ることができました。
真っ青な顔で行商人は言います。
儂が悪かった。此処にゃ二度と入らねえ。二度と近寄らねえ。
だからひとつだけ教えてくれ。あんたは盲じゃあないのかい。
なんでこの山を、何の苦労もなく歩けるンだい。
盲の男は、やっぱり笑って答えました。
確かに私は盲だが、この山のことなら何でも分かる。
山が私を助けてくれる。
だから山のふもとで暮らしているのだと。
その言葉が本当かどうか、行商人には解りませんでしたが、
約束もあるし、気味も悪かったので、素直に山を下りて
それきり二度と近づきませんでした。
小屋を訪れる人間はこうして少しずつ減り、男はますます
ひとりぼっちになって行きます。
盲の男は、それでもニコニコと。
たったひとり、みすぼらしい小屋で暮らしました。
来る日も、来る日も、一人きり。
それでも彼は、ちっとも寂しくありませんでした。
何故なら彼は、山の全てを“識”っていたから。
木々の形、動物の住処、泉や川の場所。洞穴の深さ。
この山の中にあるものならば、どれだけ遠くにあったとしても、
意識を向けるだけでありとあらゆるものの形が分かります。
色や匂い、温度、味に音。そういうものは一切分かりませんが、
形だけならば目で見るよりも繊細に、はっきりと把握できるのです。
何処にうさぎの親子がいるのか。
何処に鹿が暮らしているのか。
何処にヒヨドリが巣を作っているのか。
何処に行けば水が汲めて、何処に行けば山菜が取れて、
何処に行けばキノコが生えているか……
ヒマさえあれば山に意識を向けている男は、
何でも知っていたし、だからこそこうして一人でも何とか
生きていくことができました。
男は考えます。
きっと自分はこうして、ここで一人で暮らし、老い、
やがては死ぬのだろう。
だがこの毎日は、少なくとも自分にとっては充分楽しい。
誰にも理解されないが、暮らしに不満など一切ないのだ。
こんなに贅沢な一生があるだろうか。
こうして、盲の男はいつまでも、いつまでも……
山のふもとの小さな小屋で、毎日毎日ニコニコしながら過ごすのです。
今日も。明日も。明後日も。
ある日。
山の奥にある泉の傍に、それまで『識った』ことの無い
カタチを見つけるまでは。
─────────────────────────────────



ENo.101 イクコ とのやりとり

ENo.102 安里杏莉? とのやりとり

ENo.122 よつね とのやりとり

ENo.189 水野 杏梨 とのやりとり

ENo.216 ヒビキ とのやりとり

ENo.224 鳴 とのやりとり

ENo.260 貴登子 とのやりとり

ENo.273 闇 とのやりとり

ENo.377 火花 とのやりとり

ENo.382 イオリ とのやりとり

ENo.383 レオン とのやりとり

ENo.432 カンナ とのやりとり

ENo.513 十神 とのやりとり

ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり

ENo.582 リョウ とのやりとり

ENo.612 チホ とのやりとり

ENo.723 放課後探検部 とのやりとり

ENo.1072 フーコ とのやりとり

ENo.1104 刀崎 依良 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 謎焼き を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!








武術LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
シェンラン(163) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程2の武器『魔導鋼糸』を作製しました!
めいか(1312) とカードを交換しました!
がーでぃあん (ガーディアン)

ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
レッドショック を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアボルト を研究しました!(深度0⇒1)
リフレクション を習得!
コンテイン を習得!
ガーディアン を習得!
カウンター を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





闇(273) に移動を委ねました。
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 闇(273) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――

























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



─────────────────────────────────
【1】
むかしむかし、あるところに。
盲(めしい)の男がひとり、住んでおりました。
盲の男は、目が見えないので、
苦労の絶えぬ暮らしをしておりました。
けれど不思議なことに、男はいつもニコニコしていて、
苦労など欠片もない、などと言うのです。
両親も傍におらず、山のふもとで一人きり。
時折行き過ぎる行商人と、物々交換で物を得て、
後は全て自給自足と言う生活。
常人でさえ音を上げる厳しい毎日ですが、
なぜだか男が倒れることはありません。
ある時、不思議に思ったひとりの行商人が
男の後を尾けてみようと考えます。
男の足は速くなく、杖を突き突き山を登るものですから
後を追うのも容易かろうと、こう考えたのです。
目が見えなければ狩りもできない、山菜もとれない。
それなのにあの男は飢える素振りもないどころか、病ひとつかからない。
ならばきっとあの男は、山の中にある恵みの園、
その場所を知っているに違いない。
ところが行商人、山に分け入って少しの後、
とんでもない考え違いに気付きました。
後を追うのが容易いなど、とんでもない。
道はなく、木々が茂って足元は常に暗く、坂は急。
獣の気配はそこかしこにあり、おちおち休みもとれません。
恵みの園などどこにもないじゃないか、と文句を吐いた行商人。
山の神のバチでも当たったのでしょうか。
浮石を踏み抜き、体勢を崩し、そのまま崖へと真っ逆さま。
谷底でくしゃりと潰れ、哀れ一巻の終わり。
── と、なっても、おかしくなかったのですが。
谷底に落ちかけた行商人の手を、盲の男が掴んだので、
行商人は九死に一生を得ることができました。
真っ青な顔で行商人は言います。
儂が悪かった。此処にゃ二度と入らねえ。二度と近寄らねえ。
だからひとつだけ教えてくれ。あんたは盲じゃあないのかい。
なんでこの山を、何の苦労もなく歩けるンだい。
盲の男は、やっぱり笑って答えました。
確かに私は盲だが、この山のことなら何でも分かる。
山が私を助けてくれる。
だから山のふもとで暮らしているのだと。
その言葉が本当かどうか、行商人には解りませんでしたが、
約束もあるし、気味も悪かったので、素直に山を下りて
それきり二度と近づきませんでした。
小屋を訪れる人間はこうして少しずつ減り、男はますます
ひとりぼっちになって行きます。
盲の男は、それでもニコニコと。
たったひとり、みすぼらしい小屋で暮らしました。
来る日も、来る日も、一人きり。
それでも彼は、ちっとも寂しくありませんでした。
何故なら彼は、山の全てを“識”っていたから。
木々の形、動物の住処、泉や川の場所。洞穴の深さ。
この山の中にあるものならば、どれだけ遠くにあったとしても、
意識を向けるだけでありとあらゆるものの形が分かります。
色や匂い、温度、味に音。そういうものは一切分かりませんが、
形だけならば目で見るよりも繊細に、はっきりと把握できるのです。
何処にうさぎの親子がいるのか。
何処に鹿が暮らしているのか。
何処にヒヨドリが巣を作っているのか。
何処に行けば水が汲めて、何処に行けば山菜が取れて、
何処に行けばキノコが生えているか……
ヒマさえあれば山に意識を向けている男は、
何でも知っていたし、だからこそこうして一人でも何とか
生きていくことができました。
男は考えます。
きっと自分はこうして、ここで一人で暮らし、老い、
やがては死ぬのだろう。
だがこの毎日は、少なくとも自分にとっては充分楽しい。
誰にも理解されないが、暮らしに不満など一切ないのだ。
こんなに贅沢な一生があるだろうか。
こうして、盲の男はいつまでも、いつまでも……
山のふもとの小さな小屋で、毎日毎日ニコニコしながら過ごすのです。
今日も。明日も。明後日も。
ある日。
山の奥にある泉の傍に、それまで『識った』ことの無い
カタチを見つけるまでは。
─────────────────────────────────



ENo.101 イクコ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.102 安里杏莉? とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.122 よつね とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.189 水野 杏梨 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.216 ヒビキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.224 鳴 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.260 貴登子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.273 闇 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.377 火花 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.382 イオリ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.383 レオン とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.432 カンナ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.513 十神 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.582 リョウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.612 チホ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.723 放課後探検部 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.1072 フーコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1104 刀崎 依良 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
ミツフネ 「……まあ、まだまだ小手調べ、だよな」 |
「……36時間、か……」 |
ItemNo.6 謎焼き を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







武術LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
シェンラン(163) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程2の武器『魔導鋼糸』を作製しました!
めいか(1312) とカードを交換しました!
がーでぃあん (ガーディアン)

ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
レッドショック を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアボルト を研究しました!(深度0⇒1)
リフレクション を習得!
コンテイン を習得!
ガーディアン を習得!
カウンター を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





闇(273) に移動を委ねました。
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 闇(273) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――





決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。





ENo.161
小佐間 御津舟



─────────────────────
** 注意:彼らの異能は複写できない。 **
─────────────────────
■小佐間 御津舟(おさま みつふね)
身長170cm、体重そこそこ。
相良伊橋高校二年二組に通う生徒。
バイト先が潰れてしまったので、
新たなバイト先を探している。
住居はエクレールツクナミ305号室。
安里 杏莉(ENo.102)と付き合っている。
【異能】
『???』
彼の持つ唯一の異能。
以下の異能を正しい形で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
展開空間内の全ての形を認識する能力。
五感を封じられていても認識可能。
空間内にこちらから干渉することはできない。
『整流命繋(ミツナギ)』
命の持つ“流れ”を認識、把握する能力。
流れが歪んだり欠損したりしている場合、
これを正しい流れに寄せることができる。
『巫の誓約』
大切な人を喪ってはならない。
その手に戦うための力が無くとも。
────────────────────
■小佐間 美鳥夜(おさま みとりや)
身長150cm程度。胸はぜんぜんない。
チナミ区の実家に住む中学三年生。
なのにツクナミの兄の家によくいる。
考えるより先に行動するタイプ。
【異能】
『???』
彼女の持つ唯一の異能。
以下の異能を“本来と逆の形”で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
兄の異能と同じ。
『整流命繋(ミツナギ)』
兄の異能と同じ。
『茨の誓約』
その力で他者を殺めてはならない。
誰かが危険に晒されていたとしても。
────────────────────
■昏田 三(くらだ みすじ)
身長2m弱。体重すごくおもい。
屈強な身体、血の気の無い肌をした
明らかにその筋の人間にしか見えない男。
本職は綜合警備保障。副業は家庭教師。
通信教育も承ります。
【異能:流体加速】
液体を加速させる空間を作る。
加算ではなく乗算でかかるため、
元の勢いが強いほど威力も大きくなる。
【その他技能】
射撃術、近接戦闘術、符術、
特殊装甲型宅配車両からの制圧砲撃
────────────────────
■山本(やまもと)/
亜倉 右賢(あくら うげん)
身長180cmちょい。ひょろ長いおっさん。
常に白衣を着ている。うさんくさい。
阿久津機術研究所勤務。
【異能:流浪者】
自分の意思に関係なく世界を渡ってしまう。
きっかけや転移先など一切が制御できない。
【その他技能】
魔術、魔機混合具製作、話術
────────────────────
■繋譜音(ツフネ)
譜と音を繋ぐ者。亡霊。
────────────────────
■水渡里(ミトリ)
水と里を渡す者。アンジニティ。
────────────────────
** 注意:彼らの異能は複写できない。 **
─────────────────────
■小佐間 御津舟(おさま みつふね)
身長170cm、体重そこそこ。
相良伊橋高校二年二組に通う生徒。
バイト先が潰れてしまったので、
新たなバイト先を探している。
住居はエクレールツクナミ305号室。
安里 杏莉(ENo.102)と付き合っている。
【異能】
『???』
彼の持つ唯一の異能。
以下の異能を正しい形で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
展開空間内の全ての形を認識する能力。
五感を封じられていても認識可能。
空間内にこちらから干渉することはできない。
『整流命繋(ミツナギ)』
命の持つ“流れ”を認識、把握する能力。
流れが歪んだり欠損したりしている場合、
これを正しい流れに寄せることができる。
『巫の誓約』
大切な人を喪ってはならない。
その手に戦うための力が無くとも。
────────────────────
■小佐間 美鳥夜(おさま みとりや)
身長150cm程度。胸はぜんぜんない。
チナミ区の実家に住む中学三年生。
なのにツクナミの兄の家によくいる。
考えるより先に行動するタイプ。
【異能】
『???』
彼女の持つ唯一の異能。
以下の異能を“本来と逆の形”で行使する限り、
組み合わせて使用することができる。
『空間掌握(ハコニワ)』
兄の異能と同じ。
『整流命繋(ミツナギ)』
兄の異能と同じ。
『茨の誓約』
その力で他者を殺めてはならない。
誰かが危険に晒されていたとしても。
────────────────────
■昏田 三(くらだ みすじ)
身長2m弱。体重すごくおもい。
屈強な身体、血の気の無い肌をした
明らかにその筋の人間にしか見えない男。
本職は綜合警備保障。副業は家庭教師。
通信教育も承ります。
【異能:流体加速】
液体を加速させる空間を作る。
加算ではなく乗算でかかるため、
元の勢いが強いほど威力も大きくなる。
【その他技能】
射撃術、近接戦闘術、符術、
特殊装甲型宅配車両からの制圧砲撃
────────────────────
■山本(やまもと)/
亜倉 右賢(あくら うげん)
身長180cmちょい。ひょろ長いおっさん。
常に白衣を着ている。うさんくさい。
阿久津機術研究所勤務。
【異能:流浪者】
自分の意思に関係なく世界を渡ってしまう。
きっかけや転移先など一切が制御できない。
【その他技能】
魔術、魔機混合具製作、話術
────────────────────
■繋譜音(ツフネ)
譜と音を繋ぐ者。亡霊。
────────────────────
■水渡里(ミトリ)
水と里を渡す者。アンジニティ。
────────────────────
21 / 30
51 PS
チナミ区
I-11
I-11
































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 左天白陽 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 錆符 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 25 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| 練1 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| 練1 | ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 |
| カウンター | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
| 練2 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]レッドショック |
| [ 1 ]チャージ | [ 1 ]ファイアボルト | [ 1 ]イレイザー |

PL / きぬくろ