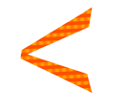<< 2:00~3:00





ざあざあと降り注ぐ大粒の涙の下。光一つ届かぬ漆黒の空の元。そこに一つ、今にも消えそうな存在がいた。
それは文字通り──誰の視界にも入らない、誰の気にも止まらない……いなくても変わらない存在だった。
人間としてみれば、齢十桁にも満たぬほどの存在。その身体とボロ着はまるで、ドブ水で洗濯したかのよう。
もとは明るかったであろうその白群は、泥と砂で濁り……光の灯らぬ深緋は、ぼうっと地面を眺めていた。
「自分という存在は、近い未来直ぐに死ぬ」──それをこれは十分以上に、悟ったかのように理解していた。
その終焉は、自分の身体が限界を迎えることにより訪れるのかもしれない。
もしかしたらそうではなく、自身の姿に気づかない存在に踏み潰されることにより迎えるものなのかもしれない。
しかし、それがどちらであったにせよ──
──死という近い結末をとうに覚悟していたがゆえに、その過程などどうでも良かった。
ただ、出来ることならば「さっさと」死にたい。これに残っていたのは、その程度の願望であった。
────声が、聞こえた。『お前はどうしたいのか』、と。
頭の中から聞こえたその声自体に疑問を抱くよりも先に、別の疑問をこれは抱いた。
……どうしたいかだなんて、考えたこともなかった。
死ぬことが決まっていて、それの備えも覚悟も終えたこれにとって──
──『どうしたいのか』などという願望は、そもそもとしてなかったのだから。
──ああいや、やっぱりあった。"私"は『さっさと』死にたいのだった。
『可及的速やかに』『早く』『疾く』死にたかった。
"何も考えずに済む"未来。そういうものを早く迎えたかった。
『さっさと死にたいのならば、いい場所がある』──続けて声が聞こえた。
流石にこれもこの時に至って、なぜその声が聞こえたのかが気になった。
しかし"私"の願い通りにさっさと死ねるのであれば、その理由などどうでもよい。──そう、思った。
──これは残された僅かな体力を使い、声の示す場所へと向かった。

──途中、死ぬことが出来る機会はたくさんあった。
煙を撒き散らし、私に泥水を浴びせ走る鉄の塊の前に、飛び出すことも出来た。
それを避けるために通った、陸と陸とを空中で繋ぐ両手から、飛び降りることも出来た。
──しかしそれらをしなかったのは、『だめだ、それではさっさと死ねない』という声が聞こえていたからだ。
たどり着いた場所は、路地裏の行き止まりだった。そこには、先客が居た。
ひとりは私などの存在よりも、遥かにはっきりとした存在の人間。
その手には、光を反射する銀色のものを持っていた。
──そして、もうひとり。それは地面に転がっていた。
何かをみて絶望しきったような人間の表情を張り付けた顔と、それがついた身体。
地面に転がっていても、なおはっきりと感じられるほどの存在であった。
これが二本の足で立っていた時はきっと、今以上にはっきりとした存在であったのだろう。
先の人間のそばに転がるこれの首元からは、自身の瞳と同じ色の水が流れていた。
ここではじめて──ああ、この存在は死んでいるのだな。と、私は思った。
私という小さな存在の比にはならないほど大きな存在が、私などよりも先に、簡単に死んだのだな、と。
同時に、理解した。
目の前に立つ彼が、その手にした銀色のもので、この存在をこの状態にしたのだということを。
その人間が私の方に振り返ったとき、私は、ひどく安心していた。
これほどまでに大きな存在に死を贈った"彼"ならば、自身のような矮小な存在など、
それこそひと思いで潰してくれるだろう、と。そう思ったからだ。
「さっさと死ねる」とは、そういうことだったのか。
頭の中に聞こえた言葉とそれを発した見知らぬ主に、私は感謝をしていた──
──それなのに、だ。
あろうことかその"彼"は、私をじっと観察し終えたと思ったら、この軽すぎる存在を拾い上げたのだ。
『──とても、小さな存在だ。危うく、踏み潰してしまうところだった』
『気づけてよかった。私はこの存在を、見落とすわけにはいかない』
──私には、その言葉が"彼"の独り言のように聞こえた。
自身に向けて掛けられた言葉であるなんて、理解が出来なかったからだ。
自身が声をかけられるほどの大きな存在であるなど、微塵も思っていなかったからだ。
"彼"はその言葉の後、少しの間を置いた。おそらくはその言葉通り、抵抗する時間をくれたのだと思う。
しかしその余力なんて、この場所に来るまでにその全てを失ってしまっていた。
きっと"彼"は私が抵抗できる体力を残していないことを承知の上で、私をすくい上げたのだろう。
そんなずるい"彼"は、間が終わればその言葉通り、私を抱えて歩き出した。
──これが、私と"師"の出会いであった。



ENo.2 狂月の瑠奈 とのやりとり

ENo.97 百合奈 とのやりとり

ENo.106 ツクモ とのやりとり

ENo.342 色蝕の塊 とのやりとり

ENo.361 シアン とのやりとり

ENo.394 飢餓の魔女 とのやりとり

ENo.514 カルセドニア とのやりとり

ENo.529 運命の輪の子供 とのやりとり

ENo.671 海の魔物 とのやりとり

ENo.692 こはり とのやりとり

ENo.779 ハルト とのやりとり

ENo.864 あやめ とのやりとり

ENo.1012 桔梗 とのやりとり

ENo.1041 サニー とのやりとり

ENo.1055 ミロスラヴァ とのやりとり

ENo.1214 照龍 とのやりとり

ENo.1324 ノブナガ とのやりとり

ENo.1329 ミフ=ニグレア とのやりとり

ENo.1491 透 とのやりとり

以下の相手に送信しました














響鳴LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
筒井 粋(288) とカードを交換しました!
スウィート・スウィッチ (ディム)


バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
バーニングチューン を研究しました!(深度1⇒2)
バーニングチューン を研究しました!(深度2⇒3)
ヒールポーション を習得!
トランス を習得!
マナポーション を習得!
ファーマシー を習得!
エネルジコ を習得!
対症下薬 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



シェリル(73) は 孔雀石 を入手!
百合奈(97) は 藍鉄鉱 を入手!
環(463) は 平石 を入手!
ふゆげ(1019) は 孔雀石 を入手!
シェリル(73) は 羽 を入手!
百合奈(97) は 針 を入手!
ふゆげ(1019) は 針 を入手!
環(463) は 針 を入手!



チナミ区 Q-9(森林)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 R-9(森林)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 R-7(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- シェリル(73) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 百合奈(97) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 環(463) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- ふゆげ(1019) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 が発生!
- シェリル(73) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- 百合奈(97) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- 環(463) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- ふゆげ(1019) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














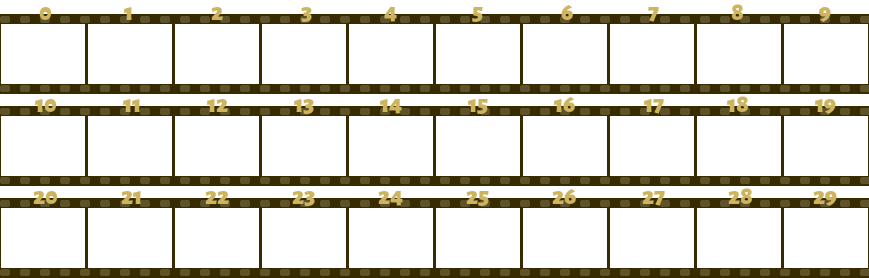







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



 |
人間が何か行動をおこす。──そこには殆どの場合、何か理由が存在する。 「理由など存在しない」と、もしその人間が言ったとしたら── ──その人間は欲がないか、そもそも人間ではないかのいずれかである。 |

ざあざあと降り注ぐ大粒の涙の下。光一つ届かぬ漆黒の空の元。そこに一つ、今にも消えそうな存在がいた。
それは文字通り──誰の視界にも入らない、誰の気にも止まらない……いなくても変わらない存在だった。
人間としてみれば、齢十桁にも満たぬほどの存在。その身体とボロ着はまるで、ドブ水で洗濯したかのよう。
もとは明るかったであろうその白群は、泥と砂で濁り……光の灯らぬ深緋は、ぼうっと地面を眺めていた。
「自分という存在は、近い未来直ぐに死ぬ」──それをこれは十分以上に、悟ったかのように理解していた。
その終焉は、自分の身体が限界を迎えることにより訪れるのかもしれない。
もしかしたらそうではなく、自身の姿に気づかない存在に踏み潰されることにより迎えるものなのかもしれない。
しかし、それがどちらであったにせよ──
──死という近い結末をとうに覚悟していたがゆえに、その過程などどうでも良かった。
ただ、出来ることならば「さっさと」死にたい。これに残っていたのは、その程度の願望であった。
────声が、聞こえた。『お前はどうしたいのか』、と。
頭の中から聞こえたその声自体に疑問を抱くよりも先に、別の疑問をこれは抱いた。
「──自分は、どうしたいのだろう?」
……どうしたいかだなんて、考えたこともなかった。
死ぬことが決まっていて、それの備えも覚悟も終えたこれにとって──
──『どうしたいのか』などという願望は、そもそもとしてなかったのだから。
──ああいや、やっぱりあった。"私"は『さっさと』死にたいのだった。
『可及的速やかに』『早く』『疾く』死にたかった。
"何も考えずに済む"未来。そういうものを早く迎えたかった。
『さっさと死にたいのならば、いい場所がある』──続けて声が聞こえた。
流石にこれもこの時に至って、なぜその声が聞こえたのかが気になった。
しかし"私"の願い通りにさっさと死ねるのであれば、その理由などどうでもよい。──そう、思った。
──これは残された僅かな体力を使い、声の示す場所へと向かった。

名もなき少女
己の出自を知らぬ、齢十にも届かぬ存在。
耐え抜くこと以外に、秀でることなどなにもない。
早く死ぬことが、彼女の望みであり願い。
耐え抜くこと以外に、秀でることなどなにもない。
早く死ぬことが、彼女の望みであり願い。
──途中、死ぬことが出来る機会はたくさんあった。
煙を撒き散らし、私に泥水を浴びせ走る鉄の塊の前に、飛び出すことも出来た。
それを避けるために通った、陸と陸とを空中で繋ぐ両手から、飛び降りることも出来た。
──しかしそれらをしなかったのは、『だめだ、それではさっさと死ねない』という声が聞こえていたからだ。
たどり着いた場所は、路地裏の行き止まりだった。そこには、先客が居た。
ひとりは私などの存在よりも、遥かにはっきりとした存在の人間。
その手には、光を反射する銀色のものを持っていた。
──そして、もうひとり。それは地面に転がっていた。
何かをみて絶望しきったような人間の表情を張り付けた顔と、それがついた身体。
地面に転がっていても、なおはっきりと感じられるほどの存在であった。
これが二本の足で立っていた時はきっと、今以上にはっきりとした存在であったのだろう。
先の人間のそばに転がるこれの首元からは、自身の瞳と同じ色の水が流れていた。
ここではじめて──ああ、この存在は死んでいるのだな。と、私は思った。
私という小さな存在の比にはならないほど大きな存在が、私などよりも先に、簡単に死んだのだな、と。
同時に、理解した。
目の前に立つ彼が、その手にした銀色のもので、この存在をこの状態にしたのだということを。
その人間が私の方に振り返ったとき、私は、ひどく安心していた。
これほどまでに大きな存在に死を贈った"彼"ならば、自身のような矮小な存在など、
それこそひと思いで潰してくれるだろう、と。そう思ったからだ。
「さっさと死ねる」とは、そういうことだったのか。
頭の中に聞こえた言葉とそれを発した見知らぬ主に、私は感謝をしていた──
──それなのに、だ。
あろうことかその"彼"は、私をじっと観察し終えたと思ったら、この軽すぎる存在を拾い上げたのだ。
『──とても、小さな存在だ。危うく、踏み潰してしまうところだった』
『気づけてよかった。私はこの存在を、見落とすわけにはいかない』
──私には、その言葉が"彼"の独り言のように聞こえた。
自身に向けて掛けられた言葉であるなんて、理解が出来なかったからだ。
自身が声をかけられるほどの大きな存在であるなど、微塵も思っていなかったからだ。
『──反応も出来ないほど衰弱しているのか。なら仕方がない』
『私は君を連れ帰る。嫌なら──抵抗するといい』
『しないのならば──それは申し訳ないが、連れ帰ることに対しての"肯定"と受け取らせてもらうよ』
『私は君を連れ帰る。嫌なら──抵抗するといい』
『しないのならば──それは申し訳ないが、連れ帰ることに対しての"肯定"と受け取らせてもらうよ』
"彼"はその言葉の後、少しの間を置いた。おそらくはその言葉通り、抵抗する時間をくれたのだと思う。
しかしその余力なんて、この場所に来るまでにその全てを失ってしまっていた。
きっと"彼"は私が抵抗できる体力を残していないことを承知の上で、私をすくい上げたのだろう。
そんなずるい"彼"は、間が終わればその言葉通り、私を抱えて歩き出した。
──これが、私と"師"の出会いであった。



 |
今の所は──恵まれている方だと思う。 なにせ、関わりの特に深いものと相見えることをしていない。 ──自身の生した選択に疑問を抱くことなく、ただ粛々と対応ができる。 |
 |
しかしこの時にもいつか、終わりがくるのであろう。 自身が話した……、信じた……、許した。そんな相手が、自身の前に立ち塞がる── ──その可能性が、連絡を取れば取るほど高まっていくことを、これは実感していた。 |
 |
いざその時が訪れたら、私はどう判断するべきであろうか? 最初に為した選択を、切り替えるべきか?それとも、貫くべきか? 少なくとも、その時の状況や感情に左右されるとは思うが── |
 |
──まあ、それはその時になったら考えればよいか。 |
ENo.2 狂月の瑠奈 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.97 百合奈 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.106 ツクモ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.342 色蝕の塊 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.361 シアン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.394 飢餓の魔女 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.514 カルセドニア とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.529 運命の輪の子供 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||||
ENo.671 海の魔物 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.692 こはり とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.779 ハルト とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.864 あやめ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1012 桔梗 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.1041 サニー とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1055 ミロスラヴァ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1214 照龍 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1324 ノブナガ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1329 ミフ=ニグレア とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1491 透 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
シェリル 「──うぅん、食材が中々見つかりませんねぇ。」 |
 |
環 「そういえば表ではバレンタインが過ぎた頃か……どれ、こっちでもチョコレートを用意できりゃよかったんだけどねー……決闘相手が落としたりしねーかな?」 |
 |
環 「そういやふゆげちゃんってチョコいいの?アウトなの?」 |
 |
物欲しそうな顔で後ろをついてきている。 |



メイドアンサンブル WITH ふゆげ
|
 |
ハザマに生きるもの
|



メイドアンサンブル WITH ふゆげ
|
 |
チェストイバラシティ
|



響鳴LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
筒井 粋(288) とカードを交換しました!
スウィート・スウィッチ (ディム)


バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
バーニングチューン を研究しました!(深度1⇒2)
バーニングチューン を研究しました!(深度2⇒3)
ヒールポーション を習得!
トランス を習得!
マナポーション を習得!
ファーマシー を習得!
エネルジコ を習得!
対症下薬 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



シェリル(73) は 孔雀石 を入手!
百合奈(97) は 藍鉄鉱 を入手!
環(463) は 平石 を入手!
ふゆげ(1019) は 孔雀石 を入手!
シェリル(73) は 羽 を入手!
百合奈(97) は 針 を入手!
ふゆげ(1019) は 針 を入手!
環(463) は 針 を入手!



チナミ区 Q-9(森林)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 R-9(森林)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 R-8(森林)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 R-7(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- シェリル(73) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 百合奈(97) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- 環(463) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- ふゆげ(1019) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》 が発生!
- シェリル(73) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- 百合奈(97) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- 環(463) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
- ふゆげ(1019) が経由した チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







メイドアンサンブル WITH ふゆげ
|
 |
operation HAZAMA
|




チナミ区 R-7
チェックポイント《廃ビル》
チェックポイント。チェックポイント《廃ビル》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《OWL》
黒闇に包まれた巨大なフクロウのようなもの。
 |
守護者《OWL》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



メイドアンサンブル WITH ふゆげ
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.73
シェリル・ウィステリア



――各種ロールは置きレス多目で進行してまいります――
――何かございましたら『連絡』機能よりご連絡ください――
【概要】
女性。身長164cm。左利き。年齢不詳。誕生日は6/23。
メイド 兼 シェアハウス「めいど亭」管理人 兼
相良伊橋高校 家庭科常勤講師 1-5担任。
【詳細】
あらゆることを卒なくこなすスーパーメイド。
特に料理と掃除の才に秀でている。
イバラシティに住むあらゆる人々にメイドとして尽くすことが、彼女の望みであり願い。
それを体現しているのか、自身の亭の管理に加え、講師をも兼任しているハードワーカーっぷり。確実に毎日が忙しいはずであるが、彼女にそのような様子は一切見られない。それどころかむしろ、その日常を楽しんでいるようである。
【異能】『オプ・ティ・マム』(RPでの情報共有可)
(情報を聞いた方 or イノカク関係者のみ公開情報)
あらゆる状況・条件下における諸問題に対する『最適解』を知ることができる能力。任意発動。
ガンコな汚れの落とし方の『最適解』。料理に加える調味料の『最適解』。戦闘で致死ダメージを避ける『最適解』…など、あらゆる『最適解』が分かる。
戦国時代であれば名軍師になったであろう、そんな能力。
ただし、その『最適解』が実行可能かどうかは分からず、また諸問題をどう認識しているかやその過程によって『最適解』は刻々と変化する。
【ハザマ下での異能】『???』(非公開情報)
少なくとも、イバラシティでの異能『オプ・ティ・マム』と全く同一ではないように思える……。
【テストプレイ時の記憶について】
テストプレイ時のシェリルと本番時(今回)のシェリルは全くの別存在です。
ゆえにテストプレイで交流のあった方々との記憶は、基本的には保持しておりません。
ただし、テストプレイにおける既知関係の継続を希望なさる方に対しては、『テストプレイ時のシェリルと築いた関係を、本番時のシェリルとの間にも同様に築いていた』という体での記憶引き継ぎを行わせていただきます(相談なしで既知RPをしていただいても構いません。その場合は上述の通りに対応させていただきます)。
【既知関係について】
本プレイで参加します高校の関係者の方々をはじめ、職業や行動範囲的に何かしらの接点があると考えられる方々による相談無しでの既知RPは大歓迎です。その際はこちらも既知RPでお返事しますことをご承知おきください。
――何かございましたら『連絡』機能よりご連絡ください――
【概要】
女性。身長164cm。左利き。年齢不詳。誕生日は6/23。
メイド 兼 シェアハウス「めいど亭」管理人 兼
相良伊橋高校 家庭科常勤講師 1-5担任。
【詳細】
あらゆることを卒なくこなすスーパーメイド。
特に料理と掃除の才に秀でている。
イバラシティに住むあらゆる人々にメイドとして尽くすことが、彼女の望みであり願い。
それを体現しているのか、自身の亭の管理に加え、講師をも兼任しているハードワーカーっぷり。確実に毎日が忙しいはずであるが、彼女にそのような様子は一切見られない。それどころかむしろ、その日常を楽しんでいるようである。
【異能】『オプ・ティ・マム』(RPでの情報共有可)
(情報を聞いた方 or イノカク関係者のみ公開情報)
あらゆる状況・条件下における諸問題に対する『最適解』を知ることができる能力。任意発動。
ガンコな汚れの落とし方の『最適解』。料理に加える調味料の『最適解』。戦闘で致死ダメージを避ける『最適解』…など、あらゆる『最適解』が分かる。
戦国時代であれば名軍師になったであろう、そんな能力。
ただし、その『最適解』が実行可能かどうかは分からず、また諸問題をどう認識しているかやその過程によって『最適解』は刻々と変化する。
【ハザマ下での異能】『???』(非公開情報)
少なくとも、イバラシティでの異能『オプ・ティ・マム』と全く同一ではないように思える……。
【テストプレイ時の記憶について】
テストプレイ時のシェリルと本番時(今回)のシェリルは全くの別存在です。
ゆえにテストプレイで交流のあった方々との記憶は、基本的には保持しておりません。
ただし、テストプレイにおける既知関係の継続を希望なさる方に対しては、『テストプレイ時のシェリルと築いた関係を、本番時のシェリルとの間にも同様に築いていた』という体での記憶引き継ぎを行わせていただきます(相談なしで既知RPをしていただいても構いません。その場合は上述の通りに対応させていただきます)。
【既知関係について】
本プレイで参加します高校の関係者の方々をはじめ、職業や行動範囲的に何かしらの接点があると考えられる方々による相談無しでの既知RPは大歓迎です。その際はこちらも既知RPでお返事しますことをご承知おきください。
30 / 30
254 PS
チナミ区
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 薙刀 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 大切なキーホルダー | 魔晶 | 17 | 幸運10 | - | 充填5 | |
| 6 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 7 | 藍鉄鉱 | 素材 | 20 | [武器]放凍15(LV25)[防具]反凍10(LV20)[装飾]舞凍15(LV25) | |||
| 8 | メイド服 | 法衣 | 20 | 命脈10 | - | 幸運6 | |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 11 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
| 12 | 孔雀石 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV25)[防具]耐狂15(LV25)[装飾]放毒10(LV20) | |||
| 13 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 解析 | 15 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 35 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| 練1 | リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| フィジカルブースター | 6 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
| カプリシャスナイト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&護衛 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| トランス | 5 | 0 | 100 | 自:混乱+自:AT・HL増+魅了を祝福化 | |
| マナポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| 練1 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| エネルジコ | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・MSP増 | |
| アウェイクニング | 5 | 0 | 80 | 味精:HP増+精神変調を守護化 | |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| ケイオティックチェイス | 5 | 2 | 110 | 自:混乱・魅了+敵全:精確攻撃+敵傷:攻撃 | |
| ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 対症下薬 | 5 | 3 | 0 | 【HP回復後】対:変調軽減+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| 技巧料理 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で、作る料理の強さが増加するが、3D6が5以下なら料理の効果1~3がなくなる。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ちくちくする (スイープ) |
0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
|
**** (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練1 |
card_ignis (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
|
スウィート・スウィッチ (ディム) |
0 | 50 | 敵:SP光撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒールポーション | [ 3 ]パワフルヒール | [ 3 ]ストライク |
| [ 3 ]バーニングチューン | [ 2 ]オートヒール |

PL / ちるきゅー







































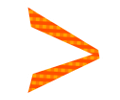

.png)