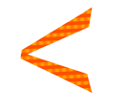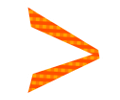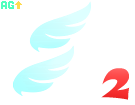<< 2:00~3:00




…笑顔のはなし
笑顔が嫌いだ。
でも誤解しないで欲しい、決して笑顔が悪いものだと言っているわけではない。
笑顔に隠されていることが嫌いだ。
相手によく思われるための上面が嫌いだ。
僕の遠い昔にいるあれらも、そういうものばかりだった。
僕に一番、それを向けていた人物は
僕に価値がないと知ると、途端にそれは剥がれ落ちて。
目的が果たせないと理解したのに、捨てきれないのかしがみついて
どうにもならないと知りながら、僕の前を去ることはなかった。
家のものの前ではまだ冷静であると振る舞っていたようだけれど
周囲の目がなくなるとヒステリーを起こすので、僕は機嫌を損ねないように息をひそめた。
おとなしくしていれば、言うことを聞いていれば。
罵られるか、嬲られる程度で済むのだが、僕が楽しんだり笑ったりしているのを見ると
それはもうひどく痛めつけてくるので、僕は笑わないように気持ちを抑えることを覚えた。
僕は。
あの日、失敗したのだ。
あの生活の中で、好きな生き物がひとつあった。
(正確には一つじゃあない、蔵には色々な虫がいたし、鼠も出たことがあったけれど)
蔵のたかいたかい、位置の窓。
景色を見ることも叶わない、ただ空気が通るだけの窓からやってきた、小さな来訪者。
初めて見るものに驚いたけれど、調べてみたらそれが鳥だと知った。
綺麗な羽、小首をかしげる様が可愛らしく、とても良い声で鳴く。
しばらくはその小さな来客と秘密の会談を楽しんでいた。
それを見つかってしまった。
殴られるかと思った、でもあれの矛先は僕ではなく、鳥の命を摘み取ることに向いたのだ。
その方が僕を痛めつけられると思ったのかもしれない。
泣かなかった。
泣けなかった、まったく、悲しくなんてなかったので。
あんなに好きだったのに、こんなに好きなのに、涙はおろか声を一つあげることはなくて。
結局その後、散々痛めつけられたけれど、それもどうでもよいことだった。
あれが居なくなった後に、打ち捨てられた鳥だったものを拾い上げる。
こんなに綺麗なのだ。もう動かなくなってしまったのに、もう鳴かないのに。
こんなにもきれいなのだ。
少し、ひしゃげてしまっていたが、その綺麗な鳥の羽を一つ一つ引き抜いて
すっかり丸裸にしてしまう。
お気に入りの棚の上に白布を敷いて、その上にそっと置いた。
羽も丁寧に並べて、とても綺麗だった。
隠すための蓋をして、それから毎日眺めていた。
…けれどそれも長くは続かない。
異臭がすると、あれは言った。
腐敗した鳥から漂う匂いだ。
原因はすぐに突き止められる、騒ぎ立てるあれの声は、耳障りだった。
そして。
あれが、鳥を捨てようとした。汚いと、そう言って。
とても嫌な気分で、考えるより先に手を伸ばしていた。
あれの目に僕がどう見えていたのかはわからない。けどおそらく…失敗したのだろう。
あの家庭教師は、とても楽しそうに笑った。
もっと上手く隠せていれば。
もっと大事にできていれば。
この日、蔵を出て、世界を知ることもなかったのかもしれない。
:
:
蔵での生活は、自由とは言えなかったけれど
それでもあの蔵の中で言えば自由であったし、好きなものも沢山あって
それなりに気に入っていたので。
例えこの話を誰かにしたとして、そのものが思うほど辛いものではなかったと
今でも思うことがある。
僕があの日に学んだことは、
大事なものは、誰にも取られないところに、しまっておくということ。
そしてそれを成すための異能の発現だった。
笑顔は悪いものではない。
それが見えている間は害されることはない"はず"の、"安心"を図れるものだから。
けれど笑顔は信用できない。その裏に何かがあると思ってしまうからだ。
なにごとにも例外はある。
廿里 崇司の経験の中でも、その家庭教師の笑顔が最たるものだ。
結局のところ、笑顔は判断材料に過ぎないということで
安心や信頼、庇護などを向けられ育つことがなかった彼にとって
安心の材料になり得るものでは無い。と、いうだけの話である。
───そして現在。
イバラシティに居る廿里 崇司という人間は、他者と接する時に笑顔を作る。
意図的な笑顔は、"無害である"と示すため。
嫌いだと自覚しながらも、己もまたその手段を使う。
結局のところ。己もあの家の人間と同じ、何一つ変わることはない。
…それだけのこと
…それは緩やかな"変化"。
廿里崇司を脅かし、恐怖させるもの



ENo.73 シェリル とのやりとり

ENo.263 狐疑 とのやりとり

ENo.418 ルリオ とのやりとり

ENo.747 布施 とのやりとり

ENo.758 虫喰い山羊 とのやりとり

ENo.1223 アンジー とのやりとり

以下の相手に送信しました













領域LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
布施(747) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『腐れた輪光』を作製しました!
虫喰い山羊(758) により ItemNo.7 赤糸のマフラー に ItemNo.8 杉 を付加してもらいました!
⇒ 赤糸のマフラー/装飾:強さ40/[効果1]耐闇10 [効果2]舞盲10 [効果3]-
『高国藤久』(58) とカードを交換しました!
死の三連星 (マーチ)


アリア を研究しました!(深度1⇒2)
ウィンドカッター を研究しました!(深度1⇒2)
コンセントレイト を研究しました!(深度1⇒2)
ガーディアン を習得!
タクシックゾーン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ルリオ(418) は 吸い殻 を入手!
つづり(492) は ド根性雑草 を入手!
布施(747) は 吸い殻 を入手!
虫喰い山羊(758) は ド根性雑草 を入手!
つづり(492) は 不思議な石 を入手!
つづり(492) は ボロ布 を入手!
つづり(492) は 不思議な石 を入手!
つづり(492) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
虫喰い山羊(758) のもとに 歩行石壁 が興味津々な様子で近づいてきます。
虫喰い山羊(758) のもとに 歩行軍手 が興味津々な様子で近づいてきます。
虫喰い山羊(758) のもとに 大黒猫 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



ルリオ(418) に移動を委ねました。
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 K-16(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 B-4(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- ルリオ(418) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- つづり(492) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- ルリオ(418) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- つづり(492) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 布施(747) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 虫喰い山羊(758) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














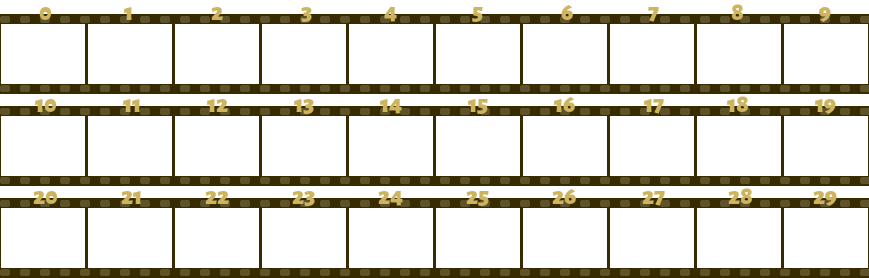





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



…笑顔のはなし
笑顔が嫌いだ。
でも誤解しないで欲しい、決して笑顔が悪いものだと言っているわけではない。
笑顔に隠されていることが嫌いだ。
相手によく思われるための上面が嫌いだ。
僕の遠い昔にいるあれらも、そういうものばかりだった。
僕に一番、それを向けていた人物は
僕に価値がないと知ると、途端にそれは剥がれ落ちて。
目的が果たせないと理解したのに、捨てきれないのかしがみついて
どうにもならないと知りながら、僕の前を去ることはなかった。
家のものの前ではまだ冷静であると振る舞っていたようだけれど
周囲の目がなくなるとヒステリーを起こすので、僕は機嫌を損ねないように息をひそめた。
おとなしくしていれば、言うことを聞いていれば。
罵られるか、嬲られる程度で済むのだが、僕が楽しんだり笑ったりしているのを見ると
それはもうひどく痛めつけてくるので、僕は笑わないように気持ちを抑えることを覚えた。
僕は。
あの日、失敗したのだ。
あの生活の中で、好きな生き物がひとつあった。
(正確には一つじゃあない、蔵には色々な虫がいたし、鼠も出たことがあったけれど)
蔵のたかいたかい、位置の窓。
景色を見ることも叶わない、ただ空気が通るだけの窓からやってきた、小さな来訪者。
初めて見るものに驚いたけれど、調べてみたらそれが鳥だと知った。
綺麗な羽、小首をかしげる様が可愛らしく、とても良い声で鳴く。
しばらくはその小さな来客と秘密の会談を楽しんでいた。
それを見つかってしまった。
殴られるかと思った、でもあれの矛先は僕ではなく、鳥の命を摘み取ることに向いたのだ。
その方が僕を痛めつけられると思ったのかもしれない。
泣かなかった。
泣けなかった、まったく、悲しくなんてなかったので。
あんなに好きだったのに、こんなに好きなのに、涙はおろか声を一つあげることはなくて。
結局その後、散々痛めつけられたけれど、それもどうでもよいことだった。
あれが居なくなった後に、打ち捨てられた鳥だったものを拾い上げる。
こんなに綺麗なのだ。もう動かなくなってしまったのに、もう鳴かないのに。
こんなにもきれいなのだ。
少し、ひしゃげてしまっていたが、その綺麗な鳥の羽を一つ一つ引き抜いて
すっかり丸裸にしてしまう。
お気に入りの棚の上に白布を敷いて、その上にそっと置いた。
羽も丁寧に並べて、とても綺麗だった。
隠すための蓋をして、それから毎日眺めていた。
…けれどそれも長くは続かない。
異臭がすると、あれは言った。
腐敗した鳥から漂う匂いだ。
原因はすぐに突き止められる、騒ぎ立てるあれの声は、耳障りだった。
そして。
あれが、鳥を捨てようとした。汚いと、そう言って。
とても嫌な気分で、考えるより先に手を伸ばしていた。
あれの目に僕がどう見えていたのかはわからない。けどおそらく…失敗したのだろう。
あの家庭教師は、とても楽しそうに笑った。
もっと上手く隠せていれば。
もっと大事にできていれば。
この日、蔵を出て、世界を知ることもなかったのかもしれない。
:
:
蔵での生活は、自由とは言えなかったけれど
それでもあの蔵の中で言えば自由であったし、好きなものも沢山あって
それなりに気に入っていたので。
例えこの話を誰かにしたとして、そのものが思うほど辛いものではなかったと
今でも思うことがある。
僕があの日に学んだことは、
大事なものは、誰にも取られないところに、しまっておくということ。
そしてそれを成すための異能の発現だった。
笑顔は悪いものではない。
それが見えている間は害されることはない"はず"の、"安心"を図れるものだから。
けれど笑顔は信用できない。その裏に何かがあると思ってしまうからだ。
なにごとにも例外はある。
廿里 崇司の経験の中でも、その家庭教師の笑顔が最たるものだ。
結局のところ、笑顔は判断材料に過ぎないということで
安心や信頼、庇護などを向けられ育つことがなかった彼にとって
安心の材料になり得るものでは無い。と、いうだけの話である。
───そして現在。
イバラシティに居る廿里 崇司という人間は、他者と接する時に笑顔を作る。
意図的な笑顔は、"無害である"と示すため。
嫌いだと自覚しながらも、己もまたその手段を使う。
結局のところ。己もあの家の人間と同じ、何一つ変わることはない。
…それだけのこと
 |
つづり 「そのはずだった…」 |
…それは緩やかな"変化"。
廿里崇司を脅かし、恐怖させるもの



 |
「…………………」 |
 |
つづり 「何をやってるんだろう…僕は……。」 |
ENo.73 シェリル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.263 狐疑 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.418 ルリオ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.747 布施 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.758 虫喰い山羊 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1223 アンジー とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
ぴゅお~ん |
 |
つづり 「美味しそうな果実拾いましたよ、皆さんの分もあればわけれるんですけど…。 布施さんが成長させたらたくさん実がなりますかね?」 |
 |
布施 「ふっ、はははっ!(言葉を発さない異形と気まずそうな青年の様子にたまらず吹き出している)」 |





正運極心
|
 |
運動不足
|



領域LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
布施(747) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『腐れた輪光』を作製しました!
虫喰い山羊(758) により ItemNo.7 赤糸のマフラー に ItemNo.8 杉 を付加してもらいました!
⇒ 赤糸のマフラー/装飾:強さ40/[効果1]耐闇10 [効果2]舞盲10 [効果3]-
 |
フェアおじ 「憤怒…ッ!(おじさん、魂の付加作業…!)」 |
『高国藤久』(58) とカードを交換しました!
死の三連星 (マーチ)


アリア を研究しました!(深度1⇒2)
ウィンドカッター を研究しました!(深度1⇒2)
コンセントレイト を研究しました!(深度1⇒2)
ガーディアン を習得!
タクシックゾーン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ルリオ(418) は 吸い殻 を入手!
つづり(492) は ド根性雑草 を入手!
布施(747) は 吸い殻 を入手!
虫喰い山羊(758) は ド根性雑草 を入手!
つづり(492) は 不思議な石 を入手!
つづり(492) は ボロ布 を入手!
つづり(492) は 不思議な石 を入手!
つづり(492) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
虫喰い山羊(758) のもとに 歩行石壁 が興味津々な様子で近づいてきます。
虫喰い山羊(758) のもとに 歩行軍手 が興味津々な様子で近づいてきます。
虫喰い山羊(758) のもとに 大黒猫 が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



ルリオ(418) に移動を委ねました。
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 K-16(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 B-4(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- ルリオ(418) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- つづり(492) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- ルリオ(418) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- つづり(492) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 布施(747) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 虫喰い山羊(758) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







焼け野の鴉
|
 |
運動不足ニティ
|




チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



運動不足ニティ
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.492
廿里 崇司



テストより継続キャラです。
前回の記憶を引き継いでいます。
ハザマでの記憶はイバラシティで反映はされていません
(ハザマでは思い出せます)
----------------☆------------------
名前:廿里 崇司(つづり そうし)
年齢:21 性別:男性
身長:168cm 体重:55kg(細身)
一人称:僕 二人称:キミ、あなた、貴方
物静かで読書が趣味な何処にでもいる青年。
ツクナミ区にてシジマ書店を営んでいる、コーヒーが好物。
アンジニティ住民だが、ごくごく平凡な人間である。
特殊な蒐集癖を持ち、とある罪でアンジニティに堕とされた。
彼はイバラ/アンジ両側で外見、性格ともに変化は無く、
その生い立ちすら差異はない。
★異能は『蒐集装幀ビブリオ』
欲しいと思った物を異能書物へ吸収し保管することが出来る。
物理的な物に限らずエネルギー物質ですら収集可能で
奪ったものを使い攻撃を仕掛けるなどの使用もできる。
収めた物を複製する事もできるらしい。
制約として、ビブリオには生きているものは収集できない。
が、何を生きているとするのかは線引きがはっきりしておらず、本人の認識によるところが大きい。
☆ただ欲しいと思うだけで基本的に悪意はない。
【魔術】
異能とは別に、つづりが行使するもの。
蒐集物の中にある魔導書より習得した
これによりつづりは実質、魔術師としての活動が可能だが
普段の生活で使ってはいないようだ。
使える魔術の幅は広いが、使用頻度の高いものは
ゼブルの瞳という魔導の瞳での看破、鑑定、暴露である。
【シジマ書店】
店内には認識錯誤の魔術が施されており
求める本が目に付きやすく、それ以外のものは意識より逸れる効果がある。
また、必要としないものには絶対に見つけられない。という効果も付与される。
また、防護の術も同時展開されているので並の方法では
本が傷つけられるという事はない。
魔術に関する本なども置いてあり、それら全ては複製品。
原本はつづりが異能"ビブリオ"の内部に保管している。
一般書籍は業者を介しての取り寄せである。
(業者は特殊なものであるがその正体はつづり本人は知らない)
店自体が異能に近い何かであるかもしれないがつづりのものではない。
しかし、つづりに縁が紐付けられているものである。
☆------------------------------☆
<Special Thanks>
宮沢さん、鴉瓜さん
※一部イラストはご依頼して作成いただいたものです
素敵なイラストをありがとうございます!
☆------------------------------☆
エンジョイしたい、交流メインプレイです
動ける時間帯は夜が多め、ロールお返事などゆっくりです。
必ずしも友好的なキャラというわけではありません。
☆PL向け情報
[友好/不穏/大人向け etc]
・ロールは基本的に何でもOKです。
此方でキャラに合わせたお返事を返します。
ただ、ロールが得意とは言い切れません!
温かく見守って下さい
・出来るだけ流れは追いたいですがゲーム仕様上難しいです
頑張りますがわからない時は聞きます、よしなに!
それか適当に話を合わせます、此方、ぶっつけ本番ばかり
ですのでなんとでもなりましょう[楽観視]
・所謂、NL(HL),GL,BL等も全く問題ないです。
前回の記憶を引き継いでいます。
ハザマでの記憶はイバラシティで反映はされていません
(ハザマでは思い出せます)
----------------☆------------------
名前:廿里 崇司(つづり そうし)
年齢:21 性別:男性
身長:168cm 体重:55kg(細身)
一人称:僕 二人称:キミ、あなた、貴方
物静かで読書が趣味な何処にでもいる青年。
ツクナミ区にてシジマ書店を営んでいる、コーヒーが好物。
アンジニティ住民だが、ごくごく平凡な人間である。
特殊な蒐集癖を持ち、とある罪でアンジニティに堕とされた。
彼はイバラ/アンジ両側で外見、性格ともに変化は無く、
その生い立ちすら差異はない。
★異能は『蒐集装幀ビブリオ』
欲しいと思った物を異能書物へ吸収し保管することが出来る。
物理的な物に限らずエネルギー物質ですら収集可能で
奪ったものを使い攻撃を仕掛けるなどの使用もできる。
収めた物を複製する事もできるらしい。
制約として、ビブリオには生きているものは収集できない。
が、何を生きているとするのかは線引きがはっきりしておらず、本人の認識によるところが大きい。
☆ただ欲しいと思うだけで基本的に悪意はない。
【魔術】
異能とは別に、つづりが行使するもの。
蒐集物の中にある魔導書より習得した
これによりつづりは実質、魔術師としての活動が可能だが
普段の生活で使ってはいないようだ。
使える魔術の幅は広いが、使用頻度の高いものは
ゼブルの瞳という魔導の瞳での看破、鑑定、暴露である。
【シジマ書店】
店内には認識錯誤の魔術が施されており
求める本が目に付きやすく、それ以外のものは意識より逸れる効果がある。
また、必要としないものには絶対に見つけられない。という効果も付与される。
また、防護の術も同時展開されているので並の方法では
本が傷つけられるという事はない。
魔術に関する本なども置いてあり、それら全ては複製品。
原本はつづりが異能"ビブリオ"の内部に保管している。
一般書籍は業者を介しての取り寄せである。
(業者は特殊なものであるがその正体はつづり本人は知らない)
店自体が異能に近い何かであるかもしれないがつづりのものではない。
しかし、つづりに縁が紐付けられているものである。
☆------------------------------☆
<Special Thanks>
宮沢さん、鴉瓜さん
※一部イラストはご依頼して作成いただいたものです
素敵なイラストをありがとうございます!
☆------------------------------☆
エンジョイしたい、交流メインプレイです
動ける時間帯は夜が多め、ロールお返事などゆっくりです。
必ずしも友好的なキャラというわけではありません。
☆PL向け情報
[友好/不穏/大人向け etc]
・ロールは基本的に何でもOKです。
此方でキャラに合わせたお返事を返します。
ただ、ロールが得意とは言い切れません!
温かく見守って下さい
・出来るだけ流れは追いたいですがゲーム仕様上難しいです
頑張りますがわからない時は聞きます、よしなに!
それか適当に話を合わせます、此方、ぶっつけ本番ばかり
ですのでなんとでもなりましょう[楽観視]
・所謂、NL(HL),GL,BL等も全く問題ないです。
30 / 30
109 PS
チナミ区
B-4
B-4





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 蒐集装幀ビブリオ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 黒いカーディガン | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 赤糸のマフラー | 装飾 | 40 | 耐闇10 | 舞盲10 | - | |
| 8 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 9 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
| 10 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 13 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 20 | 呪詛/邪気/闇 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 装飾 | 35 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 練1 | プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| 練1 | シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |
| ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
【桃太郎戦闘術・猿 鞭弾】カナ (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
幼少からの悪童 (ブレイドフォーム) |
0 | 160 | 自:AT増 | |
|
ノースウィンド (ガーディアン) |
0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
|
死の三連星 (マーチ) |
0 | 100 | 味全:AT増(4T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]ウィンドカッター | [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]デアデビル |
| [ 1 ]ファイアダンス | [ 1 ]パリィ | [ 1 ]アラベスク |
| [ 2 ]アリア | [ 1 ]レッドショック | [ 2 ]コンセントレイト |

PL / iti