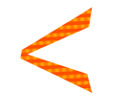<< 1:00>> 3:00




父と母はいつも多忙だ。
家に三人が揃う日は、僕がひとりで残される日よりもずっと少なかった。僕が生まれたその日のうちから母はベッドの上で仕事をしていたらしいし、断片的に残っている幼い頃の記憶は、母のものよりもベビーシッターの人とのものがずっと多い。
この国でそうした保育の委託をするような家庭が限られることだとか、親からの子供に対する愛情が不足していると指摘され得る――それが正しい指摘かどうかはともかくとして――状態であることだとかを知ったのは、小学生に上がってほかの子供と接するようになった後のことだ。
そういう考え方に接した時、学校や友達を通じてかかわったひとに何かしら、寂しくないのかとか、ご両親ももっとあなたと一緒にいてあげればいいのにねとか言われるたびに、もやっとした反発を抱いていた。
それは、かれらの言葉がまるきり見当はずれの間違いだから怒りを覚えたというのとは違う。
両親は常にだれかしら大人を家に置いていて、かれらが僕の面倒を見てくれたので、不満や不自由を感じる隙間はなかった。だから、つまり、自分が思いもつかなかった新しい考えを提示されたことに対して、妥当かどうかを考える前にとっさに嫌だなと感じたのだ。
自分の置かれている状態について不満を抱くのだったら、自分から思いつきたかった。そういうことだ。取り組んでいるパズルの答えを横から教えられると、二度とそのパズルに取り組む気分ではなくなってしまう。それは、僕が愛されているかどうかということよりもずっとずっと僕にとっての重大事で、重大事ではあるのだけれど、それを口に出すのは前者の問題について怒るよりもずっと子供っぽく理不尽なものであるように感じたので、だれにも言わないようにしていた。
ただ、もちろん、考えたことはある。僕が今この生活をどう考えているのか。それか、どう思うべきなのかということについて。
読書感想文は昔からすごく苦手だった。もちろん、感情がないとか、感じることが何もないとか、そんなわけはないんだけれど、それを言葉にすることはひどく難しい。
確かに言えることは、二人が家を空けがちだということより、読書感想文を書かされる方がずっと大変で苦痛だということだ。だから、いつもは考えない。
なのに今こうして考えを巡らせているのは、あの榊というひとの話を聞いたからだ。
父も母も、仕事でいつも通りに家にはいなかった。ふたりとも別々に島外へ出張に行っていて、帰ってくる目処も立っていなかったので、榊さんの言葉が届いてもいないだろう。
だからもし、ふたりが仕事から帰ってくる前にアンジニティに敗北してしまったら、帰ってきた時に僕はいないということになる。
ひょっとしたら、僕に成り代わっただれかがいるのかも知れない。そう思った時に、どうしてか、いつも通りスマートフォンでメッセージを送ることさえできなくなってしまった。
もしふたりがほかの家の親のように、少なくともこの島にいつもいてくれて、僕と同じ言葉を聞いてくれていたら?
でも、それは言ったって仕方がないことだ。
僕は結局二人に榊さんのことを連絡せずじまい。
さすがにだれかとこの話がしたいけれど、学校の友達に親の話をするのはやっぱりちょっと気が引ける。
明日来てもらった時に、ルネさんに言ってみようかな。
◆ ◆ ◆
生々しい十日分の記憶は、確かに自分のものであり、確かに自分のものではない。
ひとつひとつ注意深く精査すれば、その時に抱いた感情や五感までもが自分のもののように蘇る。いや、まぎれもなくみずからが感じたことではあるのだけれど、その感覚の下にある土台はおのれではない。だから、どうしても違和感が出る。
ワールドスワップとは、異世界に侵攻し、侵略し、侵食するための術式であるらしい。
その効果によって、アンジニティの囚人は対象の世界にかりそめの姿かたち・記憶・人格・身分が用意され、本来の記憶を失った状態で配置される。
ニアクに与えられたのは、少年だった。【古月さだめ】という名の、まったくの異世界で十四年間の人生を送った少年。ワールドスワップによって用意された、いつわりの設定だ。
自分が生まれたころからその世界の住民であると信じて疑わず、日常を謳歌している。
その暮らしぶりは、なるほど流刑地たる不毛の地とは、天と地ほどの差があった。
流通・農耕・技術が発達しており、土地もアンジニティとは比べ物にならないほど肥沃なのだろう。住む家や、身に着けるもの、口にするもの、すべてが恵まれていると感じる。【古月さだめ】が持つ自分と両親の関係性に関する悩みとて、ほかに憂いがなく平和であるからこそ生まれてくるものだ。
もしかすると、それは餌であるのかも知れない。侵攻を成功させさえすれば、この豊かさが当然のように手に入るのだと。
それは、間違いない事実なのだけれど。それを先んじて味わわされることが、だ。
豊かであり、自由である。
それを、だれを犠牲にしてでも手に入れたいものはいるだろう。
アンジニティは世界から否定され、放逐されたものが落とされる流刑地である。世界へ通じる道は開かれ、外への道は断絶している。
【否定】された経緯は囚人によってさまざまだ。あるいは不当な仕打ちで、あるいは当然の報いで、不毛の地へと送られてきた。
救いようのないものもいるけれど、救いようがあったろうに、その道を断たれてしまったものもいる。
獄に繋がれるべきではないものも、中にはいる。それはニアクも認識している。
かれらにひと時の夢を見せ、多くの人間を犠牲にする行為を強いる。
もしくは、その夢をみずからの意志でもって諦めさせる。
それがワールドスワップのもたらすものだとするなら、むごいと言うほかない。
ニアクがまるで自分にかかわりがない話として考えられるのも、記憶がないからに過ぎないだろう。
記憶があったところで――なにも覚えていない自分にさえ、こんなにも悔悟の念があるのだから――外に出たいなどという望みを持つことはなかったかも知れない。
何にせよ、ワールドスワップによってアンジニティの囚人がすべて解き放たれるようなことは、あってはならないことだ。
なら、囚人として、自分はこの企みを阻止しよう。
◆ ◆ ◆
モドラに案内されたのは、なるほどあばら家だった。雨風をしのげるかも怪しい。
ただ、その見てくれのわりに、家の中は――仕事に使うのであろうさまざまの工具がひしめき合っているけれど――きれいに片づけられている。
「さて、どこから話したもんかね。俺は、身の上話でも、食料の相談でも、修繕の相談でもいいんだけど」
テーブルに着くように促されてから程なくして、湯を沸かす音と茶のいい香りが鼻をくすぐった。
アンジニティという土地は、とかく不毛の地であって、ろくに物資が手に入らない。茶を振る舞われるのは、ここでは初めての経験だ。
「食糧、は私には必要はない。身の上――も、私の方は今話したっきりだ。
修繕も、こっちには出せる対価がない。そっちの話を聞かせてもらえるか。こちらが出せるものが、何かあるかも知れない。
とは言え、私に手伝えることがあるかは怪しそうだなぁ……」
片づけられてはいるものの狭い部屋だ。仕事道具が置かれているのもあって、なお窮屈に見える。
モドラの仕事を直接なにか手伝えるべくもないから、できるとすれば、例えば運搬などの力仕事か。
しかし、かれはわざわざニアクに何かを依頼するほど困っている様子は見られなかったし、あえてで手伝いを頼んでもらうというのも少し気が引けた。
「飲み食いに余裕があるってんなら、それを分け前にもらいたいくらいだけど…。
俺の話、ねえ… ここから出られないこと以外は、そんなに困ってないよ」
確かに、それはアンジニティの囚人たちに共通する『困りごと』ではあるだろう。
テーブルの上に、茶の入ったマグと小さな籠が置かれる。籠の中には、数枚のクッキーが収められていた。ニアクは少し驚いて、目を瞬かせる。見上げたモドラの顔は、こちらの表情に気が付いてか、どこか得意げだ。
「……菓子まであるのか。ますます、困っているようには見えないな」
「生活の彩りが最優先なんだ。気分が楽しくないと、健康に差し障るかもしれないと思ってさ。恋人でもいたらいいとは思ってるけど」
モドラの言葉を聞きながら、マグを持ち上げて、ニアクは茶に口をつける。
茶の味は、悪くはない。こうしたしっかりした飲料を口にするのは、久方ぶりの気がした。
「恋人? アンジニティで?」
「恋人。ここで。おかしい?
ここの生活は何十年だって続くかもしれないし、そういうことだってあるでしょう」
「……そう言われてみたら、そういう囚人がいてもおかしくはないか」
墜とされたが最後、どこにも繋がることのない閉じられた世界。伴侶を求める囚人もいるだろう。
ニアクはマグを置いて、枷に繋がった千切れた鎖を撫でた。狭い部屋の中にいるとひとつひとつの音が大きく聞こえて、先程から鎖のじゃらじゃらと鳴る音が少し気になっている。ずっと鎖を付けたままの自分でさえ気にかかるから、モドラはもっと気になるかも知れない。対面に座る男は、相変わらず笑みを浮かべていたが。
「ここでどう囚人が過ごすかまでは制限されていない。それは分かる。
私への罰としては、それは不十分に感じる……」
呟いて、目を伏せる。こうして腰かけて、茶と菓子を振る舞われることも、自分が受けてはならないもてなしのような気が改めてしてくる。
とは言え、かれの誘いに応えてここまで来たのは自分なのだから、そこで出されたものに手をつけないというのも、問題だろう。悩んだ後で、ニアクは菓子へ手を伸ばす。
「自罰的っつーか、責任感が強いっつーか…。
ニアクのそれって、性格なのか、今までの経験のせいなのか、なんなんだろね。
まあ、規範的な人って、俺は好きだよ」
組んだ両腕をテーブルに載せたまま、モドラはテーブルの上にべたりと伏せた。視線は、ニアクの鎖に注がれている。
「規範的? 馬鹿な……」
否定しかけた後で、ニアクは小さくかぶりを振った。見上げてくるモドラの視線を、眉根を寄せて見下ろす。
「――いや、それが行儀が悪いって注意する程度にはな。
自罰的になるのは罪悪感があるからだ。罪を犯した。罪の中身さえ覚えていない。
それが気持ち悪い……」
クッキーを口に放り込み、ニアクは嘆息した。
「結局、お前に対価は出せなさそうだ」
「後払いでもいいよォ。一番の要件をまだ聞いてないよね。
どれをどういう風に直してほしい?」
言われて、手首を上げる。再び鎖が揺れる音がした。
「この千切れた鎖を繋ぎ直して欲しい。
その後は元収められてた場所に戻るから、後払いはできないんだよな。何が欲しい。どれぐらいかかる?」
「こっちからも、質問が増えちまうな」
背筋を伸ばしたモドラは、自分の膝の上に両手を下ろし、
「対価と時間は、鎖の作り次第だね。
よくある素材なら、材料集めを手伝ってくれればいい。多めに集めて、俺の取り分にする。作業込みでも数日で済む。
鎖自体が難しい代物なら、調べてみないと見積もりは立てられないね……ここまではいい?」
「ああ」
ニアクが頷くのに、モドラは膝の上に置いていた手をテーブルの上に移した。わずか、こちらに身を乗り出して、
「収められてた場所、って、ニアクの今の記憶が始まった場所?
そこに戻るのがニアクのためになるってこと?」
問いに、ニアクは目を瞠った。



ENo.116 雲谷 煙次/ケムルス とのやりとり

ENo.132 西丘ラフィエル とのやりとり

ENo.1355 ヘイゼル・ブラックカラント とのやりとり

ENo.1418 啼鳥 小夜 とのやりとり

ENo.1457 モドラヘレク・ダンヘンリー とのやりとり

ENo.1495 鹿瀬 満月 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 謎の果実が入ったスコーン を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










ニアク(79) は 何かの殻 を入手!
ヘイゼル(1355) は ぬめぬめ を入手!
モドラ(1457) は ボロ布 を入手!
みつき(1495) は 何かの殻 を入手!
モドラ(1457) は 甲殻 を入手!
モドラ(1457) は 何か柔らかい物体 を入手!
ヘイゼル(1355) は 何か柔らかい物体 を入手!
モドラ(1457) は ねばねば を入手!



時空LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
TBD(1501) により ItemNo.8 駄木 から射程1の武器『筋肉質な腕』を作製してもらいました!
⇒ 筋肉質な腕/武器:強さ33/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ポテトガレット』をつくりました!
⇒ ポテトガレット/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
ことりん(37) とカードを交換しました!
斥力陽砲 (イレイザー)


アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ビブラート を研究しました!(深度1⇒2)
アリア を研究しました!(深度1⇒2)
ヘイスト を習得!
ヴァニッシュ を習得!
スナイプ を習得!



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 G-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















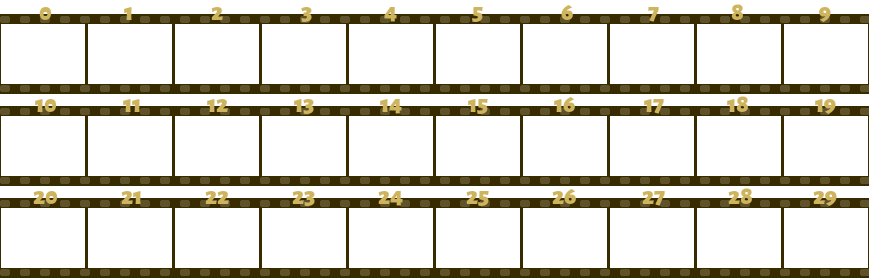





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



父と母はいつも多忙だ。
家に三人が揃う日は、僕がひとりで残される日よりもずっと少なかった。僕が生まれたその日のうちから母はベッドの上で仕事をしていたらしいし、断片的に残っている幼い頃の記憶は、母のものよりもベビーシッターの人とのものがずっと多い。
この国でそうした保育の委託をするような家庭が限られることだとか、親からの子供に対する愛情が不足していると指摘され得る――それが正しい指摘かどうかはともかくとして――状態であることだとかを知ったのは、小学生に上がってほかの子供と接するようになった後のことだ。
そういう考え方に接した時、学校や友達を通じてかかわったひとに何かしら、寂しくないのかとか、ご両親ももっとあなたと一緒にいてあげればいいのにねとか言われるたびに、もやっとした反発を抱いていた。
それは、かれらの言葉がまるきり見当はずれの間違いだから怒りを覚えたというのとは違う。
両親は常にだれかしら大人を家に置いていて、かれらが僕の面倒を見てくれたので、不満や不自由を感じる隙間はなかった。だから、つまり、自分が思いもつかなかった新しい考えを提示されたことに対して、妥当かどうかを考える前にとっさに嫌だなと感じたのだ。
自分の置かれている状態について不満を抱くのだったら、自分から思いつきたかった。そういうことだ。取り組んでいるパズルの答えを横から教えられると、二度とそのパズルに取り組む気分ではなくなってしまう。それは、僕が愛されているかどうかということよりもずっとずっと僕にとっての重大事で、重大事ではあるのだけれど、それを口に出すのは前者の問題について怒るよりもずっと子供っぽく理不尽なものであるように感じたので、だれにも言わないようにしていた。
ただ、もちろん、考えたことはある。僕が今この生活をどう考えているのか。それか、どう思うべきなのかということについて。
読書感想文は昔からすごく苦手だった。もちろん、感情がないとか、感じることが何もないとか、そんなわけはないんだけれど、それを言葉にすることはひどく難しい。
確かに言えることは、二人が家を空けがちだということより、読書感想文を書かされる方がずっと大変で苦痛だということだ。だから、いつもは考えない。
なのに今こうして考えを巡らせているのは、あの榊というひとの話を聞いたからだ。
父も母も、仕事でいつも通りに家にはいなかった。ふたりとも別々に島外へ出張に行っていて、帰ってくる目処も立っていなかったので、榊さんの言葉が届いてもいないだろう。
だからもし、ふたりが仕事から帰ってくる前にアンジニティに敗北してしまったら、帰ってきた時に僕はいないということになる。
ひょっとしたら、僕に成り代わっただれかがいるのかも知れない。そう思った時に、どうしてか、いつも通りスマートフォンでメッセージを送ることさえできなくなってしまった。
もしふたりがほかの家の親のように、少なくともこの島にいつもいてくれて、僕と同じ言葉を聞いてくれていたら?
でも、それは言ったって仕方がないことだ。
僕は結局二人に榊さんのことを連絡せずじまい。
さすがにだれかとこの話がしたいけれど、学校の友達に親の話をするのはやっぱりちょっと気が引ける。
明日来てもらった時に、ルネさんに言ってみようかな。
◆ ◆ ◆
生々しい十日分の記憶は、確かに自分のものであり、確かに自分のものではない。
ひとつひとつ注意深く精査すれば、その時に抱いた感情や五感までもが自分のもののように蘇る。いや、まぎれもなくみずからが感じたことではあるのだけれど、その感覚の下にある土台はおのれではない。だから、どうしても違和感が出る。
ワールドスワップとは、異世界に侵攻し、侵略し、侵食するための術式であるらしい。
その効果によって、アンジニティの囚人は対象の世界にかりそめの姿かたち・記憶・人格・身分が用意され、本来の記憶を失った状態で配置される。
ニアクに与えられたのは、少年だった。【古月さだめ】という名の、まったくの異世界で十四年間の人生を送った少年。ワールドスワップによって用意された、いつわりの設定だ。
自分が生まれたころからその世界の住民であると信じて疑わず、日常を謳歌している。
その暮らしぶりは、なるほど流刑地たる不毛の地とは、天と地ほどの差があった。
流通・農耕・技術が発達しており、土地もアンジニティとは比べ物にならないほど肥沃なのだろう。住む家や、身に着けるもの、口にするもの、すべてが恵まれていると感じる。【古月さだめ】が持つ自分と両親の関係性に関する悩みとて、ほかに憂いがなく平和であるからこそ生まれてくるものだ。
もしかすると、それは餌であるのかも知れない。侵攻を成功させさえすれば、この豊かさが当然のように手に入るのだと。
それは、間違いない事実なのだけれど。それを先んじて味わわされることが、だ。
豊かであり、自由である。
それを、だれを犠牲にしてでも手に入れたいものはいるだろう。
アンジニティは世界から否定され、放逐されたものが落とされる流刑地である。世界へ通じる道は開かれ、外への道は断絶している。
【否定】された経緯は囚人によってさまざまだ。あるいは不当な仕打ちで、あるいは当然の報いで、不毛の地へと送られてきた。
救いようのないものもいるけれど、救いようがあったろうに、その道を断たれてしまったものもいる。
獄に繋がれるべきではないものも、中にはいる。それはニアクも認識している。
かれらにひと時の夢を見せ、多くの人間を犠牲にする行為を強いる。
もしくは、その夢をみずからの意志でもって諦めさせる。
それがワールドスワップのもたらすものだとするなら、むごいと言うほかない。
ニアクがまるで自分にかかわりがない話として考えられるのも、記憶がないからに過ぎないだろう。
記憶があったところで――なにも覚えていない自分にさえ、こんなにも悔悟の念があるのだから――外に出たいなどという望みを持つことはなかったかも知れない。
何にせよ、ワールドスワップによってアンジニティの囚人がすべて解き放たれるようなことは、あってはならないことだ。
なら、囚人として、自分はこの企みを阻止しよう。
◆ ◆ ◆
モドラに案内されたのは、なるほどあばら家だった。雨風をしのげるかも怪しい。
ただ、その見てくれのわりに、家の中は――仕事に使うのであろうさまざまの工具がひしめき合っているけれど――きれいに片づけられている。
「さて、どこから話したもんかね。俺は、身の上話でも、食料の相談でも、修繕の相談でもいいんだけど」
テーブルに着くように促されてから程なくして、湯を沸かす音と茶のいい香りが鼻をくすぐった。
アンジニティという土地は、とかく不毛の地であって、ろくに物資が手に入らない。茶を振る舞われるのは、ここでは初めての経験だ。
「食糧、は私には必要はない。身の上――も、私の方は今話したっきりだ。
修繕も、こっちには出せる対価がない。そっちの話を聞かせてもらえるか。こちらが出せるものが、何かあるかも知れない。
とは言え、私に手伝えることがあるかは怪しそうだなぁ……」
片づけられてはいるものの狭い部屋だ。仕事道具が置かれているのもあって、なお窮屈に見える。
モドラの仕事を直接なにか手伝えるべくもないから、できるとすれば、例えば運搬などの力仕事か。
しかし、かれはわざわざニアクに何かを依頼するほど困っている様子は見られなかったし、あえてで手伝いを頼んでもらうというのも少し気が引けた。
「飲み食いに余裕があるってんなら、それを分け前にもらいたいくらいだけど…。
俺の話、ねえ… ここから出られないこと以外は、そんなに困ってないよ」
確かに、それはアンジニティの囚人たちに共通する『困りごと』ではあるだろう。
テーブルの上に、茶の入ったマグと小さな籠が置かれる。籠の中には、数枚のクッキーが収められていた。ニアクは少し驚いて、目を瞬かせる。見上げたモドラの顔は、こちらの表情に気が付いてか、どこか得意げだ。
「……菓子まであるのか。ますます、困っているようには見えないな」
「生活の彩りが最優先なんだ。気分が楽しくないと、健康に差し障るかもしれないと思ってさ。恋人でもいたらいいとは思ってるけど」
モドラの言葉を聞きながら、マグを持ち上げて、ニアクは茶に口をつける。
茶の味は、悪くはない。こうしたしっかりした飲料を口にするのは、久方ぶりの気がした。
「恋人? アンジニティで?」
「恋人。ここで。おかしい?
ここの生活は何十年だって続くかもしれないし、そういうことだってあるでしょう」
「……そう言われてみたら、そういう囚人がいてもおかしくはないか」
墜とされたが最後、どこにも繋がることのない閉じられた世界。伴侶を求める囚人もいるだろう。
ニアクはマグを置いて、枷に繋がった千切れた鎖を撫でた。狭い部屋の中にいるとひとつひとつの音が大きく聞こえて、先程から鎖のじゃらじゃらと鳴る音が少し気になっている。ずっと鎖を付けたままの自分でさえ気にかかるから、モドラはもっと気になるかも知れない。対面に座る男は、相変わらず笑みを浮かべていたが。
「ここでどう囚人が過ごすかまでは制限されていない。それは分かる。
私への罰としては、それは不十分に感じる……」
呟いて、目を伏せる。こうして腰かけて、茶と菓子を振る舞われることも、自分が受けてはならないもてなしのような気が改めてしてくる。
とは言え、かれの誘いに応えてここまで来たのは自分なのだから、そこで出されたものに手をつけないというのも、問題だろう。悩んだ後で、ニアクは菓子へ手を伸ばす。
「自罰的っつーか、責任感が強いっつーか…。
ニアクのそれって、性格なのか、今までの経験のせいなのか、なんなんだろね。
まあ、規範的な人って、俺は好きだよ」
組んだ両腕をテーブルに載せたまま、モドラはテーブルの上にべたりと伏せた。視線は、ニアクの鎖に注がれている。
「規範的? 馬鹿な……」
否定しかけた後で、ニアクは小さくかぶりを振った。見上げてくるモドラの視線を、眉根を寄せて見下ろす。
「――いや、それが行儀が悪いって注意する程度にはな。
自罰的になるのは罪悪感があるからだ。罪を犯した。罪の中身さえ覚えていない。
それが気持ち悪い……」
クッキーを口に放り込み、ニアクは嘆息した。
「結局、お前に対価は出せなさそうだ」
「後払いでもいいよォ。一番の要件をまだ聞いてないよね。
どれをどういう風に直してほしい?」
言われて、手首を上げる。再び鎖が揺れる音がした。
「この千切れた鎖を繋ぎ直して欲しい。
その後は元収められてた場所に戻るから、後払いはできないんだよな。何が欲しい。どれぐらいかかる?」
「こっちからも、質問が増えちまうな」
背筋を伸ばしたモドラは、自分の膝の上に両手を下ろし、
「対価と時間は、鎖の作り次第だね。
よくある素材なら、材料集めを手伝ってくれればいい。多めに集めて、俺の取り分にする。作業込みでも数日で済む。
鎖自体が難しい代物なら、調べてみないと見積もりは立てられないね……ここまではいい?」
「ああ」
ニアクが頷くのに、モドラは膝の上に置いていた手をテーブルの上に移した。わずか、こちらに身を乗り出して、
「収められてた場所、って、ニアクの今の記憶が始まった場所?
そこに戻るのがニアクのためになるってこと?」
問いに、ニアクは目を瞠った。



ENo.116 雲谷 煙次/ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.132 西丘ラフィエル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1355 ヘイゼル・ブラックカラント とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1418 啼鳥 小夜 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1457 モドラヘレク・ダンヘンリー とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
| |||||
ENo.1495 鹿瀬 満月 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
ニアク 「ハザマにうろつく得体の知れない連中はいいとして……あれは敵か?」 |
 |
ヘイゼル 「お前たちはいいとして……」 |
 |
ヘイゼル 「そこの子供も罪人なのか?」 |
 |
モドラ 「他人の記憶が流れてくんの、気が散るんだよな…」 |
 |
モドラ 「まあまあまあそれはそれとして 無事合流できてよかったよかった。 短期決戦、ぼちぼち頑張りましょうねえ。」 |
 |
みつき 「とりあえずチェックポイント目指してすすめー! ってかんじかな?」 |
ItemNo.6 謎の果実が入ったスコーン を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!



べとれいやー
|
 |
ハザマに生きるもの
|



べとれいやー
|
 |
PhantomGazer
|



ニアク(79) は 何かの殻 を入手!
ヘイゼル(1355) は ぬめぬめ を入手!
モドラ(1457) は ボロ布 を入手!
みつき(1495) は 何かの殻 を入手!
モドラ(1457) は 甲殻 を入手!
モドラ(1457) は 何か柔らかい物体 を入手!
ヘイゼル(1355) は 何か柔らかい物体 を入手!
モドラ(1457) は ねばねば を入手!



時空LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
TBD(1501) により ItemNo.8 駄木 から射程1の武器『筋肉質な腕』を作製してもらいました!
⇒ 筋肉質な腕/武器:強さ33/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ポテトガレット』をつくりました!
⇒ ポテトガレット/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
 |
ニアク 「……うん、味はある」 |
ことりん(37) とカードを交換しました!
斥力陽砲 (イレイザー)


アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ビブラート を研究しました!(深度1⇒2)
アリア を研究しました!(深度1⇒2)
ヘイスト を習得!
ヴァニッシュ を習得!
スナイプ を習得!



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 G-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――



べとれいやー
|
 |
ハザマに生きるもの
|




(仮PT名)
|
 |
べとれいやー
|


ENo.79
ニアク・セイン=アーデ



古月さだめ(ふるづき・さだめ)
中学二年生。得意科目は特になし。
ある金持ちの一人息子だが、両親は長期の海外出張で長く不在にしている……という『設定』を、本人も周囲も信じている(両親にメッセージを送ると、ちゃんと返ってくる)
両親から生活のために渡されている『お小遣い』を、街で知り合った青年に渡して、料理などを作ってもらっている。
自分の異能のことはまだよく分かっていない。すぐに分かる、とは言われるものの、ちょっと気にしている。
◇ ◆ ◇
ニアク・セイン=アーデ
ハザマでの姿。
記憶がない女。砕けた手枷だけが罪を犯したという事実だけを突きつけてくる。
深い懺悔の念があり、『記憶はないが罪人は獄に繋がれるもの』という感情から、ワールドスワップを阻止しようとしている。
自称画家だが、およそ絵を描くのに向いている服装ではない。
中学二年生。得意科目は特になし。
ある金持ちの一人息子だが、両親は長期の海外出張で長く不在にしている……という『設定』を、本人も周囲も信じている(両親にメッセージを送ると、ちゃんと返ってくる)
両親から生活のために渡されている『お小遣い』を、街で知り合った青年に渡して、料理などを作ってもらっている。
自分の異能のことはまだよく分かっていない。すぐに分かる、とは言われるものの、ちょっと気にしている。
◇ ◆ ◇
ニアク・セイン=アーデ
ハザマでの姿。
記憶がない女。砕けた手枷だけが罪を犯したという事実だけを突きつけてくる。
深い懺悔の念があり、『記憶はないが罪人は獄に繋がれるもの』という感情から、ワールドスワップを阻止しようとしている。
自称画家だが、およそ絵を描くのに向いている服装ではない。
21 / 30
43 PS
チナミ区
I-11
I-11




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 手錠の尖ったところ | 装飾 | 30 | [効果1]器用10 [効果2]- [効果3]- |
| 5 | 黒いスーツ | 防具 | 30 | [効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 何かの殻 | 素材 | 15 | [武器]加速10(LV15)[防具]幸運10(LV5)[装飾]水纏15(LV25) |
| 7 | ポテトガレット | 料理 | 33 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 8 | 筋肉質な腕 | 武器 | 33 | [効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 23 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&盲目 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| ヴァニッシュ | 5 | 0 | 80 | 敵:闇撃&治癒LV減+風撃&復活LV減 | |
| スナイプ | 5 | 0 | 60 | 自:DX増(3T) | |
| ブラックアサルト | 5 | 0 | 90 | 敵:3連鎖闇撃&闇痛撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]アクアヒール | [ 2 ]ビブラート | [ 2 ]アリア |

PL / ω