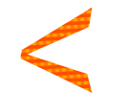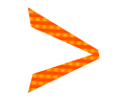<< 0:00>> 2:00




覚えていない。
覚えていない。
記憶を掘り返そうとしても、はっきりとした手応えが返ってくることはない。
生温い、あたたかい海の中に浸されているような穏やかな感覚だけがある。
何もかも忘れて眠りにつくのが倖せなのだと、身勝手な思いが胸を占めている。
けれども恐らくその泥の中の安寧こそ、私自身の罪科なのだ。
拭い去ることのできない、途方もない過ちなのだ。
決して外される時の来らぬ、永遠の軛なのだ。
だというのに、罪業の有様が、その姿かたちばかりは明瞭に分かるにもかかわらず、その中身を覗き見ることができないでいる。
私が一体何を仕出かしてしまったのかが分からない。
取り返しのつかない痛苦と罪が厳然とそこにあるにもかかわらず、どうしても手が届かない。
何も、思い出せない。
思い出せないことが罰であると、厚顔に己を偽ることなどできはしない。
必ず、必ず思い出して、罰を受けなければ、報いを与えられなければ、どうしてまともに立っていられよう!
◇ ◆ ◇
手首に嵌められた枷には、鍵穴がなかった。
着けた後に鋳つぶしたのか、そもそも鍵穴などなく、溶かして継いだものなのかさえ分からない。表面はつるりとしており、継ぎ目さえ見当たらない。
それほど丹念な枷であるにもかかわらず、それを繋ぐ鎖が半ばであっさりと千切れているのもまた、いかにも奇妙だった。奇妙だし、この状態は恐らく、この戒めを施した誰かにとっては、好ましくないことであろう。
――などと、推定でしかものを語れないのは、自分が何故ここにいるかも分からないどころか、何者かさえ覚えていないからだ。
荒れた大地にできた水たまりに自分の顔をうつした時、はて果たして自分はこんな顔をしていたのだったか――と、疑問に思ったほどだった。
名前は憶えている。ニアク=セイン・アーデ。
これは間違いなく、自分の名前だという確信があった。どこかに刻まれていたわけではない、記憶の中にある名前だ。
逆に言えば、はっきりと言えることはこれぐらいで、自分の容姿にしろ、服装にしろ、枷にしろ、体調にしろ、ひとつひとつ確認しなければ分からないありさまだった。
そして、分かることは少ない。名前にしても、確信があるとは言ったものの、証拠が出てきたわけでもなく、あくまでそんな気がする――というだけだ。
記憶の中に残っていたその名が、確かに自分の名前であるという実感がある。
だから、事実と思う。
覚束ない。
万事が万事その調子で、何とも寄る辺がなかった。
とは言え――そうした不安に身を浸し続けているには、自分の図体はずいぶんと大きく、また頑強だ。
記憶がないと言っても、そうしたことは理解している。
枷は枷だし、水面には顔が映るし、罪人は獄に繋がれているのが正しい姿である。
そして、自分は人間にしてはずいぶん作りが頑丈にできている。
鉄の枷をぶん回しても肩や腕が痛んだり疲労を感じたりすることはなく、一昼夜歩き通して足腰がへばることもない。
腹は減るので、何かしら食べる必要はあって、水ぐらいは摂っておいた方がいいとは思われるが、それに伴うはずの切迫感がない。
水面に映した姿は人間の女に見えたが、そうした自分は知識の中にあるそれとは乖離しているように思える。
人間かどうかさえ、怪しいのかも知れなかった。
そんなことさえ分からない。
分からないが、分からないと思っているばかりは性に合わないのもまた事実だった。
思い出せないのであれば、思い出せないなりに。
まずは、行動をすべきだろう。
◇ ◆ ◇
「――モドラへレク=ダンヘンリーか?」
こちらに目を向けた男は、一瞬だけ胡乱な顔になったが、すぐにそれを覆い隠すように相好を崩してみせた。
癖のついた金髪に赤い目をした、褐色の肌の男である。
羽織った安いつくりの上着は、この不毛の土地で過ごすにはいささかくたびれすぎているように見えるけれども、碌な資源も物資もないこの場所らしい服装ではあった。
「そうですよ。あなたは?」
「ニアク・セイン=アーデ」
努めて――というような様子で穏やかに問い返してくる男に、ニアクもまた抑えた調子で名乗りを上げた。
肘を畳み、両の手首を自分の顔の横辺りまで持ち上げる。枷に繋がれた鎖がじゃらりと音を慣らすのが、耳元でひどく大きく聞こえた。
「腕のいい職人だという評判を聞いたんだ。修繕を頼みたい。金はないんだが……」
「ニアクと呼べばいいかい」
腕を組んで、目を細めてかれは鎖を見つめる。
「俺にできることなら、やりますよ。
………あと、タダ働きはしたくないな。せめて何か余らせてない? ガラクタでもいいから」
「それでいい。モドラへレク」
腕をだらりと下げて、ニアクは首を傾げた。
「……そうだな。そりゃそうだ。分かってた。
なのに、何でかそう言われた時のための備えを何にもしてなかったんだよな……」
「モドラで頼むよ――何にも?」
同じように首を傾げて、モドラへレク――モドラ――は苦笑する。
困惑されるのも無理はないことだった。記憶を失っているとは言え、先述の通り、ニアクも道理を喪っているわけではない。
他人に何かを頼むには、何かしらの対価が必要だ。そうでない場合もあるけれども、それは善意や好意に基づくものがほとんどであり、そのようなものは自分たちの間には望むべくもないだろう。
そうでなくては恐らく互いに、このような場所へは放逐されない。
――いや、自分はまったく、どのような罪で自分がここに置かれているのか覚えてはいないのだが。
「手伝わせる仕事でもありゃいいんだろうけど、あいにく俺も暇でさ。
………なんならうちで水でも飲んでいくかい? 長話になりそうだし」
ぶらりと手を挙げて、かれは指先を巡らせる。
ニアクはつられて、そちらへ何となく顔を向けた。恐らくモドラの言う『うち』がある方角だろう。
逡巡する。
千切れた鎖を職人に修理してもらい、とりあえずは再び獄に繋がれる。
それで罪人としての務めは果たされる。そう思っていた。
このモドラという男は、腕利きなのだと聞いている。恐らく、枷を直すということだけ考えれば、この男に任せれば問題はないだろう。
だが、この男に支払うための対価を用意することを、まったく考えていなかったとは。
話をしたところで、こちらに支払える対価がなければ鎖の修理に取り掛かってはもらえないはずだ。
けれど、この男がこう問いかけてきた以上は、取引の余地はあると考えられる。
なら、男が求めているものがなにかあれば、それを聞き出すことはできるかも知れない。
「どんな水だ? 泥が混ざってたり、鉄錆なんかの臭いがしなきゃ歓迎なんだけど……」
ニアクの問いに頷きながら、男は踵を返す。
その後ろに続きながら、ニアクはふと天を仰いだ。



ENo.1457 モドラヘレク・ダンヘンリー とのやりとり

以下の相手に送信しました












駄木(50 PS)を購入しました。
呪術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
とす(1090) により ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『手錠の尖ったところ』を作製してもらいました!
⇒ 手錠の尖ったところ/装飾:強さ30/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
モドラ(1457) により ItemNo.5 不思議な石 から防具『黒いスーツ』を作製してもらいました!
⇒ 黒いスーツ/防具:強さ30/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
モドラ(1457) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『謎の果実が入ったスコーン』をつくりました!
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『謎の果実が入ったスコーン』をつくりました!
⇒ 謎の果実が入ったスコーン/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
TBD(1501) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『謎の果実が入ったスコーン』をつくりました!
劉(390) とカードを交換しました!
闇に潜むもの (ブレイク)


アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ビブラート を研究しました!(深度0⇒1)
アリア を研究しました!(深度0⇒1)
ダークネス を習得!
プリディクション を習得!
ブラックアサルト を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 G-8(沼地)に移動!(体調26⇒25)
みつき(1495) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



覚えていない。
覚えていない。
記憶を掘り返そうとしても、はっきりとした手応えが返ってくることはない。
生温い、あたたかい海の中に浸されているような穏やかな感覚だけがある。
何もかも忘れて眠りにつくのが倖せなのだと、身勝手な思いが胸を占めている。
けれども恐らくその泥の中の安寧こそ、私自身の罪科なのだ。
拭い去ることのできない、途方もない過ちなのだ。
決して外される時の来らぬ、永遠の軛なのだ。
だというのに、罪業の有様が、その姿かたちばかりは明瞭に分かるにもかかわらず、その中身を覗き見ることができないでいる。
私が一体何を仕出かしてしまったのかが分からない。
取り返しのつかない痛苦と罪が厳然とそこにあるにもかかわらず、どうしても手が届かない。
何も、思い出せない。
思い出せないことが罰であると、厚顔に己を偽ることなどできはしない。
必ず、必ず思い出して、罰を受けなければ、報いを与えられなければ、どうしてまともに立っていられよう!
◇ ◆ ◇
手首に嵌められた枷には、鍵穴がなかった。
着けた後に鋳つぶしたのか、そもそも鍵穴などなく、溶かして継いだものなのかさえ分からない。表面はつるりとしており、継ぎ目さえ見当たらない。
それほど丹念な枷であるにもかかわらず、それを繋ぐ鎖が半ばであっさりと千切れているのもまた、いかにも奇妙だった。奇妙だし、この状態は恐らく、この戒めを施した誰かにとっては、好ましくないことであろう。
――などと、推定でしかものを語れないのは、自分が何故ここにいるかも分からないどころか、何者かさえ覚えていないからだ。
荒れた大地にできた水たまりに自分の顔をうつした時、はて果たして自分はこんな顔をしていたのだったか――と、疑問に思ったほどだった。
名前は憶えている。ニアク=セイン・アーデ。
これは間違いなく、自分の名前だという確信があった。どこかに刻まれていたわけではない、記憶の中にある名前だ。
逆に言えば、はっきりと言えることはこれぐらいで、自分の容姿にしろ、服装にしろ、枷にしろ、体調にしろ、ひとつひとつ確認しなければ分からないありさまだった。
そして、分かることは少ない。名前にしても、確信があるとは言ったものの、証拠が出てきたわけでもなく、あくまでそんな気がする――というだけだ。
記憶の中に残っていたその名が、確かに自分の名前であるという実感がある。
だから、事実と思う。
覚束ない。
万事が万事その調子で、何とも寄る辺がなかった。
とは言え――そうした不安に身を浸し続けているには、自分の図体はずいぶんと大きく、また頑強だ。
記憶がないと言っても、そうしたことは理解している。
枷は枷だし、水面には顔が映るし、罪人は獄に繋がれているのが正しい姿である。
そして、自分は人間にしてはずいぶん作りが頑丈にできている。
鉄の枷をぶん回しても肩や腕が痛んだり疲労を感じたりすることはなく、一昼夜歩き通して足腰がへばることもない。
腹は減るので、何かしら食べる必要はあって、水ぐらいは摂っておいた方がいいとは思われるが、それに伴うはずの切迫感がない。
水面に映した姿は人間の女に見えたが、そうした自分は知識の中にあるそれとは乖離しているように思える。
人間かどうかさえ、怪しいのかも知れなかった。
そんなことさえ分からない。
分からないが、分からないと思っているばかりは性に合わないのもまた事実だった。
思い出せないのであれば、思い出せないなりに。
まずは、行動をすべきだろう。
◇ ◆ ◇
「――モドラへレク=ダンヘンリーか?」
こちらに目を向けた男は、一瞬だけ胡乱な顔になったが、すぐにそれを覆い隠すように相好を崩してみせた。
癖のついた金髪に赤い目をした、褐色の肌の男である。
羽織った安いつくりの上着は、この不毛の土地で過ごすにはいささかくたびれすぎているように見えるけれども、碌な資源も物資もないこの場所らしい服装ではあった。
「そうですよ。あなたは?」
「ニアク・セイン=アーデ」
努めて――というような様子で穏やかに問い返してくる男に、ニアクもまた抑えた調子で名乗りを上げた。
肘を畳み、両の手首を自分の顔の横辺りまで持ち上げる。枷に繋がれた鎖がじゃらりと音を慣らすのが、耳元でひどく大きく聞こえた。
「腕のいい職人だという評判を聞いたんだ。修繕を頼みたい。金はないんだが……」
「ニアクと呼べばいいかい」
腕を組んで、目を細めてかれは鎖を見つめる。
「俺にできることなら、やりますよ。
………あと、タダ働きはしたくないな。せめて何か余らせてない? ガラクタでもいいから」
「それでいい。モドラへレク」
腕をだらりと下げて、ニアクは首を傾げた。
「……そうだな。そりゃそうだ。分かってた。
なのに、何でかそう言われた時のための備えを何にもしてなかったんだよな……」
「モドラで頼むよ――何にも?」
同じように首を傾げて、モドラへレク――モドラ――は苦笑する。
困惑されるのも無理はないことだった。記憶を失っているとは言え、先述の通り、ニアクも道理を喪っているわけではない。
他人に何かを頼むには、何かしらの対価が必要だ。そうでない場合もあるけれども、それは善意や好意に基づくものがほとんどであり、そのようなものは自分たちの間には望むべくもないだろう。
そうでなくては恐らく互いに、このような場所へは放逐されない。
――いや、自分はまったく、どのような罪で自分がここに置かれているのか覚えてはいないのだが。
「手伝わせる仕事でもありゃいいんだろうけど、あいにく俺も暇でさ。
………なんならうちで水でも飲んでいくかい? 長話になりそうだし」
ぶらりと手を挙げて、かれは指先を巡らせる。
ニアクはつられて、そちらへ何となく顔を向けた。恐らくモドラの言う『うち』がある方角だろう。
逡巡する。
千切れた鎖を職人に修理してもらい、とりあえずは再び獄に繋がれる。
それで罪人としての務めは果たされる。そう思っていた。
このモドラという男は、腕利きなのだと聞いている。恐らく、枷を直すということだけ考えれば、この男に任せれば問題はないだろう。
だが、この男に支払うための対価を用意することを、まったく考えていなかったとは。
話をしたところで、こちらに支払える対価がなければ鎖の修理に取り掛かってはもらえないはずだ。
けれど、この男がこう問いかけてきた以上は、取引の余地はあると考えられる。
なら、男が求めているものがなにかあれば、それを聞き出すことはできるかも知れない。
「どんな水だ? 泥が混ざってたり、鉄錆なんかの臭いがしなきゃ歓迎なんだけど……」
ニアクの問いに頷きながら、男は踵を返す。
その後ろに続きながら、ニアクはふと天を仰いだ。



ENo.1457 モドラヘレク・ダンヘンリー とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||
以下の相手に送信しました



 |
ニアク 「……いや、やっぱり、まずいと思うね、私は……」 |







駄木(50 PS)を購入しました。
呪術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
とす(1090) により ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『手錠の尖ったところ』を作製してもらいました!
⇒ 手錠の尖ったところ/装飾:強さ30/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
モドラ(1457) により ItemNo.5 不思議な石 から防具『黒いスーツ』を作製してもらいました!
⇒ 黒いスーツ/防具:強さ30/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
モドラ(1457) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『謎の果実が入ったスコーン』をつくりました!
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『謎の果実が入ったスコーン』をつくりました!
⇒ 謎の果実が入ったスコーン/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
 |
ニアク 「えーと……こんなもんか」 |
TBD(1501) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『謎の果実が入ったスコーン』をつくりました!
劉(390) とカードを交換しました!
闇に潜むもの (ブレイク)


アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ビブラート を研究しました!(深度0⇒1)
アリア を研究しました!(深度0⇒1)
ダークネス を習得!
プリディクション を習得!
ブラックアサルト を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 G-8(沼地)に移動!(体調26⇒25)
みつき(1495) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――



うさぎの道はじごくみち
|
 |
ハザマに生きるもの
|




秘密結社『欠けた蜜蝋』
|
 |
うさぎの道はじごくみち
|


ENo.79
ニアク・セイン=アーデ



古月さだめ(ふるづき・さだめ)
中学二年生。得意科目は特になし。
ある金持ちの一人息子だが、両親は長期の海外出張で長く不在にしている……という『設定』を、本人も周囲も信じている(両親にメッセージを送ると、ちゃんと返ってくる)
両親から生活のために渡されている『お小遣い』を、街で知り合った青年に渡して、料理などを作ってもらっている。
自分の異能のことはまだよく分かっていない。すぐに分かる、とは言われるものの、ちょっと気にしている。
◇ ◆ ◇
ニアク・セイン=アーデ
ハザマでの姿。
記憶がない女。砕けた手枷だけが罪を犯したという事実だけを突きつけてくる。
深い懺悔の念があり、『記憶はないが罪人は獄に繋がれるもの』という感情から、ワールドスワップを阻止しようとしている。
自称画家だが、およそ絵を描くのに向いている服装ではない。
中学二年生。得意科目は特になし。
ある金持ちの一人息子だが、両親は長期の海外出張で長く不在にしている……という『設定』を、本人も周囲も信じている(両親にメッセージを送ると、ちゃんと返ってくる)
両親から生活のために渡されている『お小遣い』を、街で知り合った青年に渡して、料理などを作ってもらっている。
自分の異能のことはまだよく分かっていない。すぐに分かる、とは言われるものの、ちょっと気にしている。
◇ ◆ ◇
ニアク・セイン=アーデ
ハザマでの姿。
記憶がない女。砕けた手枷だけが罪を犯したという事実だけを突きつけてくる。
深い懺悔の念があり、『記憶はないが罪人は獄に繋がれるもの』という感情から、ワールドスワップを阻止しようとしている。
自称画家だが、およそ絵を描くのに向いている服装ではない。
25 / 30
0 PS
チナミ区
G-8
G-8




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 手錠の尖ったところ | 装飾 | 30 | [効果1]器用10 [効果2]- [効果3]- |
| 5 | 黒いスーツ | 防具 | 30 | [効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 謎の果実が入ったスコーン | 料理 | 30 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]攻撃10(LV20) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 20 | 料理に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| ダークネス | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&盲目 |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) |
| ブラックアサルト | 5 | 0 | 90 | 敵:3連鎖闇撃&闇痛撃 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]ビブラート | [ 1 ]アリア |

PL / ω