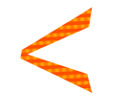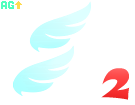<< 1:00>> 3:00




薄明かり。朝を知らせる小鳥の声。朝のニュースの音声に、ぼんやりと見上げる天井。
いつも通りの朝の光景。いつも通りじゃないのは、しんと静まった目覚まし時計。
「なつ、八時半過ぎてるけど、起きなくていいのか?」
「ぅえ……? あっ、ヤバ。かけ忘れた!」
ばさりと両足で布団をはねのけて、なつ子は目を覚ます。
その音があちらまで響いたか、台所から声をかけた男がくつくつと笑う声が聞こえた。
「いいよ。メシはすぐ出来るからさ、もう少し寝てなって」
「ごめん……。ありがと、英司」
「俺先に会社行くから、鍵はよろしくな」
そう返されると、すぐに食欲をそそる香りが漂い始める。
香ばしいトーストに、よく煮込まれたトマトスープ。時短料理なんて、可愛らしいものではない。一瞬の出来事だ。
――この男の異能は本当に便利なものだなと、毛布にくるまりながら、なつ子は考える。
革靴、蝶番、鍵が回る音。彼の出かけていく気配を確認して、なつ子は今度こそ布団を這い出た。
向かうテーブルに並べられた朝餉は、どう見ても、朝支度の合間にこしらえたものとは思えないほどに豪勢なものだった。
手を合わせ、寝ぼけた口にトマトスープを運ぶ。
――あたたかい。
(こういう異能に、生まれてきたかったなあ……)
テレビの右端に浮かぶ時刻を注視しながら、なつ子はしみじみとその思いを反芻した。
前田英司。なつ子よりは一回りにならない程度に年上の男で、数ヶ月前から「そういう関係」だ。評価をするなら、素直に良物件だろう。
勤め先ではそこそこのポストを担当しているらしく、金銭的な世話も惜しみなく行ってくれるし、そして何より料理がうまい。
彼が持って生まれた異能は、「近くにある材料を瞬時に成果物に変える」というもの。
彼はその異能を活用して、なつ子も名前を知っていた有名レストランに勤務している。日常生活から有事の際まで活用幅の広い、”アタリ”技能だ。
英司以外にも、異能を活用して生計を立てている者は多い。
対するなつ子の異能、「聴跳強化」は正直”ハズレ”そのものだった。
聴力と跳躍力を強化する異能。しかし、強化幅としても半端すぎる。
聴力を上げたところで、数キロ先の出来事まで把握できるわけでもなければ、跳躍したってせいぜいマンションの二階が限度だ。空が飛べるわけではない。
おかげさまで足腰はしっかりしているから、山坂や階段が苦にならない利点こそあるが、異能が生活を豊かにしてくれるのは、精々そのあたりまでだろう。
異能で得をする者がいれば、それに押しのけられる者もいる。
力仕事であっても、筋力強化や重力無視、巨大化の異能さえあれば女性の方がずっと役立つし、相手のニーズに合わせて変身できる異能さえあれば、性別や年齢を無視したアクターになることだってできるかもしれない。
だが、ぴょんぴょん跳ね回るうさぎのようなこの異能に、そんな力はない。
いや、ごく希にならあるかもしれない。ただ、この異能が役立つ状況というのは、大抵あまり良い状況ではなかった。
マンションの二階ほど下、いや、エントランスか。誰かの話し声がなつ子の耳に飛び込んでくる。
「そういえば、上の前田さんって、ご結婚されたのかしら。奥さん、ずいぶんお若いのねぇ」
「やあね、アンタ知らなかったの? みんな大きい声じゃ言ってないけど、フリンよ、フリン。前田さん、単身赴任なのよぉ。前に奥さんとお子さんが遊びに来てるの、何度か見たもの」
「んまっ。……あらあ~」
その後は聞かないことにした。おそらく今頃彼女たちは、自分たちがどんな生活を送っているのかという妄想話で盛り上がっているのだろう。
あまり否定できそうにないのが、悲しいところだが。
さしてショックはない。そういう話はちらほら飛び込んできていたし、彼に限らず、今までだって何度も起きたことだ。
ハンサムで優しく収入もよく、男なのに料理だってうまい。そんな男性が単に縁に恵まれずフリー。
基本的にはあり得ない。
ウラがあるのが世の常だ。彼もただ、その一人だっただけ。
(……できたらもう少し続けたかったけど、潮時だなー……)
食器を片付けて、仕事道具の放り込まれた鞄に、寝泊まりグッズを追加した。もう二度と、この家には帰らない。
英司から、彼に妻子がいる情報はまだ一言も聞いていなかった。
今のうちに逃げ出せば、大人の男に騙された、哀れな娘の立場で終わる。
聴力強化が今の暮らしで唯一、そして最も役立つ用途はおそらく、他人の情報の傍受。
これに何度も助けられ、そして何度も彷徨わされている。
この役立たずの耳は、破れかぶれな暮らしをする上での、最後の切り札だ。
だからこそ、なつ子は基本的に、他人に聴力のことを話したりなんてしない。
話すことは、お前を補足できると言っていることと同じ。
そうすれば、人は身構えるし、口は堅くなり、得られるカードも得られなくなる。
ドアを開けると、いつも通りの朝日がまぶしくて、暖かだ。
何度も訪れたドアの鍵穴に合鍵を突っ込み、最後の施錠をして、なつ子は薄く笑った。
「ありがと、でもごめんね。ご飯おいしかったよ。バイバイ」
それだけ言って、なつ子は手のひらの合鍵を玄関ポストに突っ込んだ。



ENo.1495 鹿瀬 満月 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 紫色のグミ を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










ニアク(79) は 何かの殻 を入手!
ヘイゼル(1355) は ぬめぬめ を入手!
モドラ(1457) は ボロ布 を入手!
みつき(1495) は 何かの殻 を入手!
モドラ(1457) は 甲殻 を入手!
モドラ(1457) は 何か柔らかい物体 を入手!
ヘイゼル(1355) は 何か柔らかい物体 を入手!
モドラ(1457) は ねばねば を入手!



具現LV を 3 UP!(LV0⇒3、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
佐藤(179) により ItemNo.4 牙縫い に ItemNo.5 不思議な石 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
とす(1090) により ItemNo.7 どうでもよさげな物体 から装飾『サバイバルトラップ』を作製してもらいました!
⇒ サバイバルトラップ/装飾:強さ33/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-
叶原(738) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から防具『牙のお守り』を作製しました!
ItemNo.4 何か柔らかい物体 から防具『なれはての毛皮』を作製しました!
⇒ なれはての毛皮/防具:強さ33/[効果1]鎮痛10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
フレッド(1453) の持つ ItemNo.8 駄木 から防具『かたいマント』を作製しました!
色欲(228) とカードを交換しました!
Luxria_Lv2 (イレイザー)


スタードリーム を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 G-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















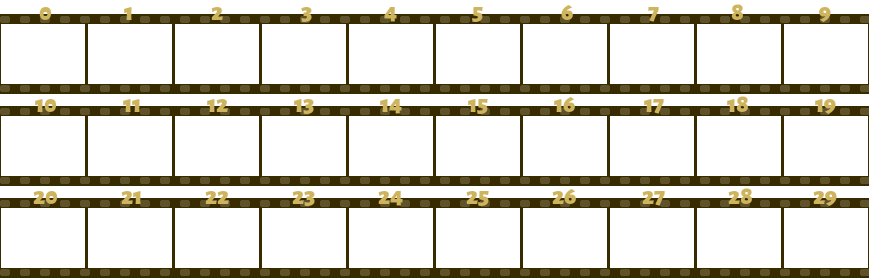





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



薄明かり。朝を知らせる小鳥の声。朝のニュースの音声に、ぼんやりと見上げる天井。
いつも通りの朝の光景。いつも通りじゃないのは、しんと静まった目覚まし時計。
「なつ、八時半過ぎてるけど、起きなくていいのか?」
「ぅえ……? あっ、ヤバ。かけ忘れた!」
ばさりと両足で布団をはねのけて、なつ子は目を覚ます。
その音があちらまで響いたか、台所から声をかけた男がくつくつと笑う声が聞こえた。
「いいよ。メシはすぐ出来るからさ、もう少し寝てなって」
「ごめん……。ありがと、英司」
「俺先に会社行くから、鍵はよろしくな」
そう返されると、すぐに食欲をそそる香りが漂い始める。
香ばしいトーストに、よく煮込まれたトマトスープ。時短料理なんて、可愛らしいものではない。一瞬の出来事だ。
――この男の異能は本当に便利なものだなと、毛布にくるまりながら、なつ子は考える。
革靴、蝶番、鍵が回る音。彼の出かけていく気配を確認して、なつ子は今度こそ布団を這い出た。
向かうテーブルに並べられた朝餉は、どう見ても、朝支度の合間にこしらえたものとは思えないほどに豪勢なものだった。
手を合わせ、寝ぼけた口にトマトスープを運ぶ。
――あたたかい。
(こういう異能に、生まれてきたかったなあ……)
テレビの右端に浮かぶ時刻を注視しながら、なつ子はしみじみとその思いを反芻した。
前田英司。なつ子よりは一回りにならない程度に年上の男で、数ヶ月前から「そういう関係」だ。評価をするなら、素直に良物件だろう。
勤め先ではそこそこのポストを担当しているらしく、金銭的な世話も惜しみなく行ってくれるし、そして何より料理がうまい。
彼が持って生まれた異能は、「近くにある材料を瞬時に成果物に変える」というもの。
彼はその異能を活用して、なつ子も名前を知っていた有名レストランに勤務している。日常生活から有事の際まで活用幅の広い、”アタリ”技能だ。
英司以外にも、異能を活用して生計を立てている者は多い。
対するなつ子の異能、「聴跳強化」は正直”ハズレ”そのものだった。
聴力と跳躍力を強化する異能。しかし、強化幅としても半端すぎる。
聴力を上げたところで、数キロ先の出来事まで把握できるわけでもなければ、跳躍したってせいぜいマンションの二階が限度だ。空が飛べるわけではない。
おかげさまで足腰はしっかりしているから、山坂や階段が苦にならない利点こそあるが、異能が生活を豊かにしてくれるのは、精々そのあたりまでだろう。
異能で得をする者がいれば、それに押しのけられる者もいる。
力仕事であっても、筋力強化や重力無視、巨大化の異能さえあれば女性の方がずっと役立つし、相手のニーズに合わせて変身できる異能さえあれば、性別や年齢を無視したアクターになることだってできるかもしれない。
だが、ぴょんぴょん跳ね回るうさぎのようなこの異能に、そんな力はない。
いや、ごく希にならあるかもしれない。ただ、この異能が役立つ状況というのは、大抵あまり良い状況ではなかった。
マンションの二階ほど下、いや、エントランスか。誰かの話し声がなつ子の耳に飛び込んでくる。
「そういえば、上の前田さんって、ご結婚されたのかしら。奥さん、ずいぶんお若いのねぇ」
「やあね、アンタ知らなかったの? みんな大きい声じゃ言ってないけど、フリンよ、フリン。前田さん、単身赴任なのよぉ。前に奥さんとお子さんが遊びに来てるの、何度か見たもの」
「んまっ。……あらあ~」
その後は聞かないことにした。おそらく今頃彼女たちは、自分たちがどんな生活を送っているのかという妄想話で盛り上がっているのだろう。
あまり否定できそうにないのが、悲しいところだが。
さしてショックはない。そういう話はちらほら飛び込んできていたし、彼に限らず、今までだって何度も起きたことだ。
ハンサムで優しく収入もよく、男なのに料理だってうまい。そんな男性が単に縁に恵まれずフリー。
基本的にはあり得ない。
ウラがあるのが世の常だ。彼もただ、その一人だっただけ。
(……できたらもう少し続けたかったけど、潮時だなー……)
食器を片付けて、仕事道具の放り込まれた鞄に、寝泊まりグッズを追加した。もう二度と、この家には帰らない。
英司から、彼に妻子がいる情報はまだ一言も聞いていなかった。
今のうちに逃げ出せば、大人の男に騙された、哀れな娘の立場で終わる。
聴力強化が今の暮らしで唯一、そして最も役立つ用途はおそらく、他人の情報の傍受。
これに何度も助けられ、そして何度も彷徨わされている。
この役立たずの耳は、破れかぶれな暮らしをする上での、最後の切り札だ。
だからこそ、なつ子は基本的に、他人に聴力のことを話したりなんてしない。
話すことは、お前を補足できると言っていることと同じ。
そうすれば、人は身構えるし、口は堅くなり、得られるカードも得られなくなる。
ドアを開けると、いつも通りの朝日がまぶしくて、暖かだ。
何度も訪れたドアの鍵穴に合鍵を突っ込み、最後の施錠をして、なつ子は薄く笑った。
「ありがと、でもごめんね。ご飯おいしかったよ。バイバイ」
それだけ言って、なつ子は手のひらの合鍵を玄関ポストに突っ込んだ。



ENo.1495 鹿瀬 満月 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
ニアク 「ハザマにうろつく得体の知れない連中はいいとして……あれは敵か?」 |
 |
ヘイゼル 「お前たちはいいとして……」 |
 |
ヘイゼル 「そこの子供も罪人なのか?」 |
 |
モドラ 「他人の記憶が流れてくんの、気が散るんだよな…」 |
 |
モドラ 「まあまあまあそれはそれとして 無事合流できてよかったよかった。 短期決戦、ぼちぼち頑張りましょうねえ。」 |
 |
みつき 「とりあえずチェックポイント目指してすすめー! ってかんじかな?」 |
ItemNo.6 紫色のグミ を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 治癒10活力10鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!



べとれいやー
|
 |
ハザマに生きるもの
|



べとれいやー
|
 |
PhantomGazer
|



ニアク(79) は 何かの殻 を入手!
ヘイゼル(1355) は ぬめぬめ を入手!
モドラ(1457) は ボロ布 を入手!
みつき(1495) は 何かの殻 を入手!
モドラ(1457) は 甲殻 を入手!
モドラ(1457) は 何か柔らかい物体 を入手!
ヘイゼル(1355) は 何か柔らかい物体 を入手!
モドラ(1457) は ねばねば を入手!



具現LV を 3 UP!(LV0⇒3、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
佐藤(179) により ItemNo.4 牙縫い に ItemNo.5 不思議な石 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
 |
佐藤 「どうも。こんな感じで大丈夫っすかね?」 |
とす(1090) により ItemNo.7 どうでもよさげな物体 から装飾『サバイバルトラップ』を作製してもらいました!
⇒ サバイバルトラップ/装飾:強さ33/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-
| エインモーネ 「………物騒だな」 |
叶原(738) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から防具『牙のお守り』を作製しました!
ItemNo.4 何か柔らかい物体 から防具『なれはての毛皮』を作製しました!
⇒ なれはての毛皮/防具:強さ33/[効果1]鎮痛10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
ヘイゼル 「多少はまともな装備になったか」 |
フレッド(1453) の持つ ItemNo.8 駄木 から防具『かたいマント』を作製しました!
色欲(228) とカードを交換しました!
Luxria_Lv2 (イレイザー)


スタードリーム を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 G-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――



べとれいやー
|
 |
ハザマに生きるもの
|




(仮PT名)
|
 |
べとれいやー
|


ENo.1355
ヘイゼル・ブラックカラント



出身:アンジニティ
所属:イバラシティ
◆須栗なつ子(すぐり・なつこ)
19歳女性。無職。しいて言えば安定しないフリーター。
機能不全家庭で育ち、高校を卒業すると共に実家を飛び出した。以降、アルバイトを転々としたり、適当な男と寝たりしつつ食いつないでいる。一応一人暮らし。
家族にいい思い出がないのか、実家で暮らしていた頃の記憶があまりない。
一人っ子のはず。両足がある。顔はわりといい。
異能は「聴跳強化」。聴力・跳躍力を状況に応じて大幅に上げることができる、肉体強化系の異能。ただし聴力の強化については、他人にあまり話したがらない。
――という、イバラシティでの姿と記憶を付与された、アンジニティの女性。
◆ヘイゼル・ブラックカラント
なつ子の本来の姿および本名。右足がない。四人兄妹の上から三番目。
流れの民と呼ばれる獣人族のレプレス(兎)。元は天界で罪を犯した天使を堕天させたものと、その子孫から成る種族で、ヘイゼル自身は罪人ではなかった。しかし、他世界の天使に害をなす可能性がある行動を取ったことで、天界への復讐の可能性があると天界側に認識され、めでたくアンジニティ送りとなった。本人はわりとせいせいしていた。
イバラシティ側に加勢しているが、特に正義の心や味方意識のようなものはなく、仮初の平和な暮らしへの嫌悪感や、在るべきものは在るべき場所にあればそれでいいという考え方から。
もともと勢力争い等にも興味はないし、静かに暮らせたらそれでいい。巻き込まれて迷惑している。
右足は理不尽に奪われて失った。数人の親族の命や、妹の両足も。
正義だなんだに興味はないが、自分自身が理不尽に奪う側になるのはあまり趣味じゃない。……程度の美意識感覚は有している模様。
◇イバラシティでの異能について
なつ子の異能「聴跳強化」は、イバラシティに溶け込む為のダミー異能です。
身体能力はヘイゼル自身が本来持っているものであり、それを逆に、イバラシティの住人を模している間は人間並みのものに押さえ込んでいるイメージです。
ただし跳躍力については、本来のヘイゼルの姿では片足がない為、能力発動をしている状態のなつ子の方が優れているようです。
◇生産や交流について
チェック率が低いので、なつ子宛てメッセは頂いても置きレス状態になると思います。
なおPLは途中で力尽きる常習犯です。それもあって控えめに遊ぶ予定ですが、生産枠が余ってももったいないので、枠交換や取引等のご相談はお気軽にどうぞ。
所属:イバラシティ
◆須栗なつ子(すぐり・なつこ)
19歳女性。無職。しいて言えば安定しないフリーター。
機能不全家庭で育ち、高校を卒業すると共に実家を飛び出した。以降、アルバイトを転々としたり、適当な男と寝たりしつつ食いつないでいる。一応一人暮らし。
家族にいい思い出がないのか、実家で暮らしていた頃の記憶があまりない。
一人っ子のはず。両足がある。顔はわりといい。
異能は「聴跳強化」。聴力・跳躍力を状況に応じて大幅に上げることができる、肉体強化系の異能。ただし聴力の強化については、他人にあまり話したがらない。
――という、イバラシティでの姿と記憶を付与された、アンジニティの女性。
◆ヘイゼル・ブラックカラント
なつ子の本来の姿および本名。右足がない。四人兄妹の上から三番目。
流れの民と呼ばれる獣人族のレプレス(兎)。元は天界で罪を犯した天使を堕天させたものと、その子孫から成る種族で、ヘイゼル自身は罪人ではなかった。しかし、他世界の天使に害をなす可能性がある行動を取ったことで、天界への復讐の可能性があると天界側に認識され、めでたくアンジニティ送りとなった。本人はわりとせいせいしていた。
イバラシティ側に加勢しているが、特に正義の心や味方意識のようなものはなく、仮初の平和な暮らしへの嫌悪感や、在るべきものは在るべき場所にあればそれでいいという考え方から。
もともと勢力争い等にも興味はないし、静かに暮らせたらそれでいい。巻き込まれて迷惑している。
右足は理不尽に奪われて失った。数人の親族の命や、妹の両足も。
正義だなんだに興味はないが、自分自身が理不尽に奪う側になるのはあまり趣味じゃない。……程度の美意識感覚は有している模様。
◇イバラシティでの異能について
なつ子の異能「聴跳強化」は、イバラシティに溶け込む為のダミー異能です。
身体能力はヘイゼル自身が本来持っているものであり、それを逆に、イバラシティの住人を模している間は人間並みのものに押さえ込んでいるイメージです。
ただし跳躍力については、本来のヘイゼルの姿では片足がない為、能力発動をしている状態のなつ子の方が優れているようです。
◇生産や交流について
チェック率が低いので、なつ子宛てメッセは頂いても置きレス状態になると思います。
なおPLは途中で力尽きる常習犯です。それもあって控えめに遊ぶ予定ですが、生産枠が余ってももったいないので、枠交換や取引等のご相談はお気軽にどうぞ。
21 / 30
43 PS
チナミ区
I-11
I-11




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | なれはての毛皮 | 防具 | 33 | [効果1]鎮痛10 [効果2]- [効果3]- |
| 5 | ||||
| 6 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV25)[装飾]加速10(LV25) |
| 7 | サバイバルトラップ | 装飾 | 33 | [効果1]回復10 [効果2]- [効果3]- |
| 8 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 制約 | 20 | 拘束/罠/リスク |
| 具現 | 3 | 創造/召喚 |
| 防具 | 23 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| キャプチャー | 5 | 0 | 70 | 自:束縛LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]キャプチャー |
| [ 1 ]コロージョン | [ 1 ]クイックアナライズ | [ 1 ]スタードリーム |

PL / メシエナンバー