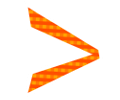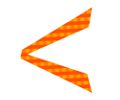<< 4:00~5:00





セリカ・オラシオンという少年がいた。

14歳の少年。年相応に格好いいものが好きで、年齢より幾ばくか幼い印象を与えていた。
自分より一つ年下……今になれば、同い年だったのかもしれない。
彼はよく店に来て飴玉を買っていた。接点と言えばそれくらいで。
何回か一緒に何かと戦っていたような記憶もある。今となってはあまり思い出せないが。
だから、特別仲がいいわけではなかった。
少なくとも自分は本当の意味で彼に心を開いていたわけではなかった。何故なら彼を最後に見たのは10月の頭くらいだったから。
その頃の自分は自我を確立できていないただの演者だった。
「正直なところ、自分が元々誰だったのかすらも知らない。」
いつしか、彼がそう零していた。
深入りはしなかった。しようとも思わなかった。
けれど
多分、自分と彼はとてもよく似ていたんだろう。
彼もきっと、「自分とは誰か」を探し求めていた。
11月に入ってから、彼の姿を見なくなった。
彼も店を持っていたし、別段気にすることはなかった。
彼と再会したのは、学校の教室だった。
自分より一つ下だったはずの年齢は、一つ上になっていて。

「やあ、"セリカ"の記憶が君に会いたがってたから、こうやって連絡しちゃった。
……わかる?俺があいつの皮を被って行動してること。そして、彼はもういないこと。」
「──ごめんよ、俺は。"セリカ"を殺した犯人。
こちら側で、君達の敵にならなきゃいけない存在なんだ。どうか許してほしい。」
セリカ・オラシオンという少年がいた。
いた、のだ。しかし。

その少年はもう、この世のどこにもいない。
悲しい、という感情が薄い。
虚しい、とか。やるせない、とか。そういうことはわかる。悲しいと感じることもあるけれど。
自分は、涙を流せないのだ。たとえ大事な人が飴玉になっても、友人が死んでも、両親が自分を通して別の人を見ていたとしても、自分が捨て子とわかっても、隣人がアンジニティになったとしても。
「ああ、そうか」って。
そんな気持ちがあるだけで。
悲しむべきなのだろう。苦しむべきなのだろう。涙を流して、慟哭するべきなのだろう。
だけど、それができない。
涙を流して感情を吐き出せたのならどれほど楽なのだろう。
だから自分は、その言葉に対して、その状況に対して、『怒る』ことしかできなかった。
正しくない。適切ではないとわかっていたけれど、それでも感情をぶつけずにはいられなかった。
自分は彼に何ができるだろうか。何をすれば彼への弔いになるだろうか。
何をすれば────


──殺す?
そうだ。セリカ君は殺されたんだ。
悲鳴を上げても、助けを乞うても、救われることはなく。
何を思ったのだろう。誰に助けを求めたのだろう。
『自分は一体何なのか』
『誰かの代わりを続けている自分は一体誰なのか』
君はそれを苦痛だと言ったね。
結局君はないものを演じるしかなくて、二度と帰ってこない『セリカ』へ負い目を感じながら、『セリカ』ではない自分になりたかった。
あたしはね、セリカ君。
それに対する一つの答えを見つけたんだ。
誰かに教えてもらわなかったら気付けないそれを、手に入れることができたんだ。
だから
今度はあたしが君に、それを教えてあげたかったな。
ああ、本当に──
──その行動は命令違反にあたります──
自分が被り続けた殻も、演じている『誰か』も、負い目や苦しみだってそれは紛れもなく『自分自身』のもので。
価値がない、なんてことにはならないんだと。
教えてあげなければいけなかった。
他でもない、同じ悩みを持っていただろうあたしが。
この戦争が終わってイバラシティが勝ったのなら、彼は帰ってくるのだろうか。
それとも、殺されてしまったものは生き返らないのだろうか。
わからない。わからないけど。
『彼』を尊重するのなら、殺さなければならない。
あれは人を殺して、侵略活動を続けている。
交戦の意志があって、邪悪な笑い声を響かせている。
逃げてはいけない。それは相手に対する侮辱だ。
自らの手に握られている武器を見る。
使い方次第で人を傷つけも癒せもする異能、咲魔式。
──殺すことだって、できる。
……でも、あの獣を悪だと言うのなら。
自分は、どうなのだろうか。
自分は6歳だった頃、『御堂翠華』だった自分によって作り上げられた人格だ。
両親を飴玉に変えた状態で生き続ける負い目に耐えられなかった自分が、外で活動するために作り上げた『偽物』。
いつかは消えるはずだった自分は、あの言葉に引き上げられて自我を持った。
コメット・エーデルシュタインとして生きることを選んだ。
なら、望まれていた『御堂翠華』はどうなるんだ。
自分は、それを殺したことになるのだろうか。
空に浮く黒い着物の少女を意識する。
仮の存在といえど、『御堂翠華』は確かに自分に言ったのだ。
──恩知らず。よくも私を捨てたな、と。
あの時はその理由がよくわからなかったけれど。
自分が選び取ったものを譲り渡す気なんてないけれど。
両親が元に戻った時、彼らは誰を愛せばいい?
愛娘を失って、その代わりとして引き取った子供さえ別人になっていく。
『御堂翠華』は、死んでしまったのか?
もう戻るつもりのない子どもの自分の手をどうやって引けばいい?
確かにあの自分を愛していた人はいたのだ。たとえ自分を通して別の誰かを見ていたとしても。
──ああ、悲しい苦しい。
ぽとりと、飴玉が落ちた。
雫のように小さい飴玉が、ぽろぽろと掌に落ちていく。
それはまるで涙のようで、零れるたびに心臓に刺さって棘のような痛みが抜けていった。
『私の場合は、たぶん、異能の使い過ぎの反動でこうなった、と思う。』
ふと、通信で聞いた声が頭をよぎった。
──もう、さっきまで処理しきれず燻ぶっていた感情はどこにもなくて。
だけどそれは、自分の掌にあることがわかって。
「──まさか」
『夢幻泡飴』──触れたものを飴玉に変える異能。
「……そう、か。」
「そう、だね。」
「こうすれば、もう、どこにもいかないからね」
零れた飴玉を大事に握って、空っぽの缶に入れる。
「……嫌になるよ。こんなことばっかり、あたしは上手になっていく。」
不必要で、でも捨てたくない感情をすべて飴玉に変えて。
泣けない代わりに飴玉にして外に出して。
いつかはもっと大事なものさえ飴玉に変えてしまうのだろうか。
この場所で進むために、恐怖や後悔を全部消していくんだろう。
これは、よくないことだ。
正しくないことだ。
だけど、進むために必要なことだ。
あと少し、答えを出せるその時間までは。
「そんなこと考えてるお姉さんでよければ、
何度でも、弱音を吐いて頂戴。
何度でも、聞いてあげるから、ね。」
………………
……………………………
→CHAT・・・To.サクマ



ENo.58 『高国藤久』 とのやりとり

ENo.161 ミツフネ とのやりとり

ENo.183 黒い兵士 とのやりとり

ENo.256 ナガレ とのやりとり

ENo.282 巽 とのやりとり

ENo.551 勇者 とのやりとり

ENo.671 海の魔物 とのやりとり

ENo.702 玖楠 とのやりとり

ENo.717 Qimranut とのやりとり

ENo.801 セオリ とのやりとり

ENo.1072 フーコ とのやりとり

ENo.1286 ネン とのやりとり

以下の相手に送信しました




ヒビキ(216) に ItemNo.7 フローラルポプリ を手渡ししました。
まさこ(281) から 雑木 を手渡しされました。










エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
命術LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
百薬LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
武術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
装飾LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ItemNo.11 ネジ から装飾『フランケンシュタインの復讐』を作製しました!
⇒ フランケンシュタインの復讐/装飾:強さ82/[効果1]舞乱10 [効果2]- [効果3]-
桔柳(1211) とカードを交換しました!
廻血 (ブレイドフォーム)

クリエイト:グレイル を研究しました!(深度0⇒1)
五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
フロウライフ を習得!
肉体変調耐性 を習得!
チャージ を習得!
アクアブランド を習得!
パワフルポーション を習得!
イレイザー を習得!
チャクラグラント を習得!
医食同源 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 に転送されました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
採集はできませんでした。
- ヒビキ(216) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- コメット(253) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- まさこ(281) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- ヒビキ(216) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園(ベースキャンプ外のため無効)
- コメット(253) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園(ベースキャンプ外のため無効)
- まさこ(281) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園(ベースキャンプ外のため無効)






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――


















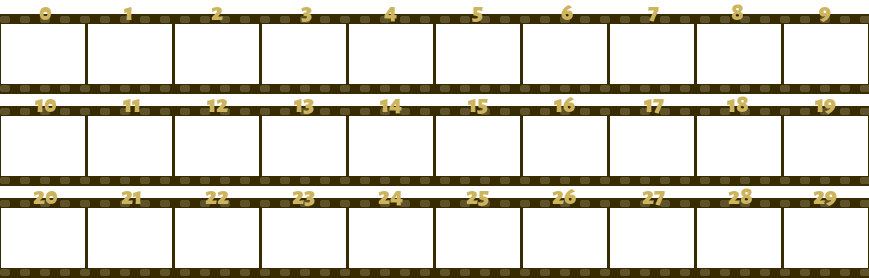







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




セリカ・オラシオンという少年がいた。

セリカ・オラシオン
祈 蒼空と書く。
普段から中々にファンタジーな格好をして出歩く、やたら目立つ少年。青と赤のオッドアイと傷跡が特徴的である。
普段から中々にファンタジーな格好をして出歩く、やたら目立つ少年。青と赤のオッドアイと傷跡が特徴的である。
14歳の少年。年相応に格好いいものが好きで、年齢より幾ばくか幼い印象を与えていた。
自分より一つ年下……今になれば、同い年だったのかもしれない。
彼はよく店に来て飴玉を買っていた。接点と言えばそれくらいで。
何回か一緒に何かと戦っていたような記憶もある。今となってはあまり思い出せないが。
だから、特別仲がいいわけではなかった。
少なくとも自分は本当の意味で彼に心を開いていたわけではなかった。何故なら彼を最後に見たのは10月の頭くらいだったから。
その頃の自分は自我を確立できていないただの演者だった。
「正直なところ、自分が元々誰だったのかすらも知らない。」
いつしか、彼がそう零していた。
深入りはしなかった。しようとも思わなかった。
けれど
多分、自分と彼はとてもよく似ていたんだろう。
彼もきっと、「自分とは誰か」を探し求めていた。
11月に入ってから、彼の姿を見なくなった。
彼も店を持っていたし、別段気にすることはなかった。
彼と再会したのは、学校の教室だった。
自分より一つ下だったはずの年齢は、一つ上になっていて。

「やあ、"セリカ"の記憶が君に会いたがってたから、こうやって連絡しちゃった。
……わかる?俺があいつの皮を被って行動してること。そして、彼はもういないこと。」
「──ごめんよ、俺は。"セリカ"を殺した犯人。
こちら側で、君達の敵にならなきゃいけない存在なんだ。どうか許してほしい。」
セリカ・オラシオンという少年がいた。
いた、のだ。しかし。

セリカ・オラシオン
交通事故、及びQimranutの干渉により死亡した。
その少年はもう、この世のどこにもいない。
悲しい、という感情が薄い。
虚しい、とか。やるせない、とか。そういうことはわかる。悲しいと感じることもあるけれど。
自分は、涙を流せないのだ。たとえ大事な人が飴玉になっても、友人が死んでも、両親が自分を通して別の人を見ていたとしても、自分が捨て子とわかっても、隣人がアンジニティになったとしても。
「ああ、そうか」って。
そんな気持ちがあるだけで。
悲しむべきなのだろう。苦しむべきなのだろう。涙を流して、慟哭するべきなのだろう。
だけど、それができない。
涙を流して感情を吐き出せたのならどれほど楽なのだろう。
だから自分は、その言葉に対して、その状況に対して、『怒る』ことしかできなかった。
正しくない。適切ではないとわかっていたけれど、それでも感情をぶつけずにはいられなかった。
自分は彼に何ができるだろうか。何をすれば彼への弔いになるだろうか。
何をすれば────


──殺す?
そうだ。セリカ君は殺されたんだ。
悲鳴を上げても、助けを乞うても、救われることはなく。
何を思ったのだろう。誰に助けを求めたのだろう。
『自分は一体何なのか』
『誰かの代わりを続けている自分は一体誰なのか』
君はそれを苦痛だと言ったね。
結局君はないものを演じるしかなくて、二度と帰ってこない『セリカ』へ負い目を感じながら、『セリカ』ではない自分になりたかった。
あたしはね、セリカ君。
それに対する一つの答えを見つけたんだ。
誰かに教えてもらわなかったら気付けないそれを、手に入れることができたんだ。
だから
今度はあたしが君に、それを教えてあげたかったな。
ああ、本当に──
──その行動は命令違反にあたります──
自分が被り続けた殻も、演じている『誰か』も、負い目や苦しみだってそれは紛れもなく『自分自身』のもので。
価値がない、なんてことにはならないんだと。
教えてあげなければいけなかった。
他でもない、同じ悩みを持っていただろうあたしが。
この戦争が終わってイバラシティが勝ったのなら、彼は帰ってくるのだろうか。
それとも、殺されてしまったものは生き返らないのだろうか。
わからない。わからないけど。
『彼』を尊重するのなら、殺さなければならない。
あれは人を殺して、侵略活動を続けている。
交戦の意志があって、邪悪な笑い声を響かせている。
逃げてはいけない。それは相手に対する侮辱だ。
自らの手に握られている武器を見る。
使い方次第で人を傷つけも癒せもする異能、咲魔式。
──殺すことだって、できる。
……でも、あの獣を悪だと言うのなら。
自分は、どうなのだろうか。
自分は6歳だった頃、『御堂翠華』だった自分によって作り上げられた人格だ。
両親を飴玉に変えた状態で生き続ける負い目に耐えられなかった自分が、外で活動するために作り上げた『偽物』。
いつかは消えるはずだった自分は、あの言葉に引き上げられて自我を持った。
コメット・エーデルシュタインとして生きることを選んだ。
なら、望まれていた『御堂翠華』はどうなるんだ。
自分は、それを殺したことになるのだろうか。
空に浮く黒い着物の少女を意識する。
仮の存在といえど、『御堂翠華』は確かに自分に言ったのだ。
──恩知らず。よくも私を捨てたな、と。
あの時はその理由がよくわからなかったけれど。
自分が選び取ったものを譲り渡す気なんてないけれど。
両親が元に戻った時、彼らは誰を愛せばいい?
愛娘を失って、その代わりとして引き取った子供さえ別人になっていく。
『御堂翠華』は、死んでしまったのか?
もう戻るつもりのない子どもの自分の手をどうやって引けばいい?
確かにあの自分を愛していた人はいたのだ。たとえ自分を通して別の誰かを見ていたとしても。
──ああ、
ぽとりと、飴玉が落ちた。
雫のように小さい飴玉が、ぽろぽろと掌に落ちていく。
それはまるで涙のようで、零れるたびに心臓に刺さって棘のような痛みが抜けていった。
『私の場合は、たぶん、異能の使い過ぎの反動でこうなった、と思う。』
ふと、通信で聞いた声が頭をよぎった。
──もう、さっきまで処理しきれず燻ぶっていた感情はどこにもなくて。
だけどそれは、自分の掌にあることがわかって。
「──まさか」
『夢幻泡飴』──触れたものを飴玉に変える異能。
「……そう、か。」
「そう、だね。」
「こうすれば、もう、どこにもいかないからね」
零れた飴玉を大事に握って、空っぽの缶に入れる。
「……嫌になるよ。こんなことばっかり、あたしは上手になっていく。」
不必要で、でも捨てたくない感情をすべて飴玉に変えて。
泣けない代わりに飴玉にして外に出して。
いつかはもっと大事なものさえ飴玉に変えてしまうのだろうか。
この場所で進むために、恐怖や後悔を全部消していくんだろう。
これは、よくないことだ。
正しくないことだ。
だけど、進むために必要なことだ。
あと少し、答えを出せるその時間までは。
「そんなこと考えてるお姉さんでよければ、
何度でも、弱音を吐いて頂戴。
何度でも、聞いてあげるから、ね。」
………………
……………………………
→CHAT・・・To.サクマ



ENo.58 『高国藤久』 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.161 ミツフネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.183 黒い兵士 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.256 ナガレ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.282 巽 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.551 勇者 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.671 海の魔物 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.702 玖楠 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.717 Qimranut とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.801 セオリ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1072 フーコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1286 ネン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
ヒビキ 「(おなかすいたな……)」 |
 |
コメット 「どうして案内役の2人は春みたいな空気出してるんですかね?」 |
 |
ニフリート 「俺達が倒すべき相手、間違ってるんじゃね?処す?処す?」 |
 |
まさこ 「格上相手とマッチングさせんじゃねぇよ! 早くメンテしてマッチングシステム直せや!」 |
 |
まさこ 「人類皆平等なはずだろ! アンジニティだけ贔屓してんじゃねぇ!!」 |
 |
ガチョウ 「...Foolish girl.」 |
 |
まさこ 「戦って勝ちてぇ」 |
| シュナイダー 「ぬ、ゥ――!? 」 |
| シュナイダー 「ふ、む……。なるほど、侵略。 ……伊達に、大袈裟ではない様ですね。」 |
| シュナイダー 凄まじい練度。 躊躇いの無さ。 ――痛感する。 彼らの"本気"を。 |
| シュナイダー ――しかして、それは。 屈する理由には在らず。 |
| シュナイダー 「――成果は出ています。少なからず。 行きましょう、生かしましょう。 立ち上がれるのであれば。 立ち向かえるのなら。 全ては糧となるだけです。 ――次の機会のね。」 |
ヒビキ(216) に ItemNo.7 フローラルポプリ を手渡ししました。
まさこ(281) から 雑木 を手渡しされました。
 |
まさこ 「とっておきだ……上手く使えよ?」 |



Two sides of the same Coin
|
 |
ハザマに生きるもの
|



星の十字教団
|
 |
Two sides of the same Coin
|



エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
命術LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
百薬LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
武術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
装飾LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
ItemNo.11 ネジ から装飾『フランケンシュタインの復讐』を作製しました!
⇒ フランケンシュタインの復讐/装飾:強さ82/[効果1]舞乱10 [効果2]- [効果3]-
 |
コメット 「調節と制御……気休めにはなるか。」 |
桔柳(1211) とカードを交換しました!
廻血 (ブレイドフォーム)

クリエイト:グレイル を研究しました!(深度0⇒1)
五月雨 を研究しました!(深度0⇒1)
ハードブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
フロウライフ を習得!
肉体変調耐性 を習得!
チャージ を習得!
アクアブランド を習得!
パワフルポーション を習得!
イレイザー を習得!
チャクラグラント を習得!
医食同源 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「はいお疲れさん。サービスの飴ちゃん持ってきな。」 |
特に移動せずその場に留まることにしました。
採集はできませんでした。
- ヒビキ(216) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- コメット(253) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- まさこ(281) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- ヒビキ(216) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園(ベースキャンプ外のため無効)
- コメット(253) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園(ベースキャンプ外のため無効)
- まさこ(281) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園(ベースキャンプ外のため無効)






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――



Two sides of the same Coin
|
 |
ハザマに生きるもの
|




TeamNo.429
|
 |
Two sides of the same Coin
|


ENo.253
彗星・コメット



「あたしはコメット。咲魔式の後継者でトレジャーハンターさ。」
────彼女のプロフィールは、大部分が嘘でできている。
名前:コメット・エーデルシュタイン
年齢:16歳
身長:155cm
体重:49kg
誕生日:3月9日
性別:女性
武器:銃
学ランに着物にスチームパンクという異な出で立ちの少女。飄々とした性格、まるで舞台の上に立っているかのような身振りをする。いつも近くにいる黒猫を「お義父様」「先代」と呼んでいる。
家では飴屋『ほうきぼし』を営んでおり、外にいる時も飴玉を缶に入れて持ち歩いている。店員としての性格は明るく大和撫子。
学校では優等生のような振る舞いをしている。事実頭はいい。
両親はどちらも生みの親ではないらしく、説明する時は「スラム街で捨てられたところを魔女に気まぐれ拾われた」と言っている。その気まぐれがいつ消えてもいいように、身の回りの事は全て自分で出来るようにしている。
異能:『咲魔式』飴玉を用いた魔法
咲魔式の戦闘方式として飴玉を弾丸として用いる。飴玉の味、素材によって様々な効果をもたらす。現在投薬による異能改造が途切れているため、不完全な状態で発動している。専用の銃を用いなければ発動できない。
咲魔式:特殊な戦闘流派。先代はニフリート。飴玉を弾丸として用いる戦闘方法が特徴。通常の弾丸では不可能なトリッキーな戦い方ができる。コメットは咲魔式を扱える素養が異能として備わっていたらしい。
巽燈史郎(ENo.282)とは恋人関係(一応)
お店→http://lisge.com/ib/talk.php?p=386
全身図→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=comet.png
店員→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=coshop.png
「俺の娘だ。すごくねえわけねぇだろが。」
名前:ニフリート
性別:オス
コメットのそばにいつもいる黒猫。コメットには「お義父様」と呼ばれている。咲魔式の先代当主だったが、跡継ぎを残せぬまま老衰。死ぬ寸前に魔女と契約し、跡継ぎを探す旅を続けていた。姿を猫に変えられてしまっているためか言動もかなり猫。声が渋い。
サブ
魔女
大きな帽子をかぶった女性。コメットの義母という立ち位置だが、感情が薄く母親らしいことは何もしていない。花と宝石にまつわる魔女であり、歩いた後に宝石でできた花を咲かせたり、花を使って不思議な魔法を扱う。
ただし、本物の花は咲かせることができない。
御堂すいか(仮)
性別:女性
享年:3歳
御堂呉服店に住み着いている地縛霊。コメットと姿がよく似ているが、瞳の色は茶色。異能の暴発により死亡している。ものぐさ。
異能:テレキネシス
対象を好きな場所へ移動させたり曲げたりできる異能。脳への負担が大きいため、対象にXYZ軸を指定して、決めた方向へ動かすことができるように設定している。
「あたしは、コメット・エーデルシュタインだ。それがいい。」
偽名:コメット・エーデルシュタイン
本名:????
年齢:15歳(戸籍より一つ下。)
誕生日:5月22日(保護日)、11月28日(コメットとしての自我形成日)
捨て子。施設で2歳まで育てられ、御堂家の両親に亡くなった娘の代わりにと引き取られる。名前は無くなった娘と同じ『御堂翠華』である。
御堂家とはイバラシティに存在した名家である。
古くから呉服屋を営むその家で翠華は一人娘として育てられた。
礼儀作法を教えこまえ、両親に蝶よ花よと育てられた彼女は自らの異能も知らないまま無垢で純粋に育つ。
誰かの役に立ちたい、いつか家を継ぐものとして恥ずかしくない者でありたいと思っていたところに魔女と黒猫から咲魔式を継いで欲しいと持ちかけられる。
自らの異能が誰かの役に立つならば、と彼女はその願いを了承し、その旨を親に話しに行った。
かつての異能:『夢幻泡飴』
御堂翠華は飴が好きだったという事実と、本人の持つ『瞳への執着』が混ぜ合わさって生まれた異能。触れたものを時間ごと止めて飴玉に変えてしまう。美しいものは美しいままに。ずっと手の届く場所へ。発動した当時から今まで常に暴走状態である。
正しい異能:『白紙の役者』(タイトル・ロール・エトワール)
台本通りに演じ切る役者。何度でも書き換え可能の台本。端的に言って超強力な自己暗示。
『主』を設定し、その主が望んだように自身の思考、行動、異能さえ変革する異能。本人の羞恥や違和感も消し飛ばし、演じることができる。外見も時間はかかるが変更することができる。(髪の色、目の形など)
母親に「泣かず暴れない赤ん坊であれ」と願われればその通りに。御堂呉服店の夫婦に「御堂翠華であれ」と願われればその通りに演じ切った。『主』の対象は自分であっても構わない。
この異能には『観察』と『情報』が大きく作用する。「御堂翠華であれ」と願われた際に異能の情報を知らなかったため、御堂翠華本来の異能とは別の異能が備わった。同様に、他者を模倣した際に異能の効果を正確に把握していない場合は異能の模倣はできない。つまり基本的に知らないものを模倣することはできない。近づけたとしても『その異能を真似た別のもの』でしかない。
デメリット
・『主』を設定しないことはできない。もし設定しない場合生命活動のみを続ける抜け殻になってしまう。
・リソースは限られているためあまり過度な役を充てられると他の能力が大幅に落ちる。
・『主』を変える意志を奪われた場合自分では主を変えられない。
異能の使用例:めちゃくちゃ辛いものを食べる時に『主』を自分に設定。内容を『平然と食べる人』に設定。するとポーカーフェイスで辛いものを食べられるが、辛いものが嫌い過ぎた場合喋る能力が失われる。
SIDE:ANSINITY
名前:御堂翠華
年齢:6歳
魔女と黒猫に出会うことが無かったコメットのIF。世界の半分を飴玉に変えてしまい、否定の世界へ追放された。
この世界に来るにあたり、『コメットの過去の亡霊』として呉服店に固定されてしまった。元からそこに住む地縛霊『御堂すいか』の体を借りている。
ハザマでは両親を元に戻すことを条件に渋々ながらコメットに協力している。
異能:『夢幻泡飴』触れたものを飴玉に変える異能
彼女は両親の手を握った。自分をまっすぐに見つめる瞳が美しいと思った。
いつまでも、近くで眺めていたかった。
気づいたら、両親の姿はなかった。両親は娘の異能によって飴玉に変えられてしまったのだ。
アンジニティに落ちた時点で、彼女の異能は夢幻泡飴に固定されている。
ハザマにおいて、コメットの体は少しずつ飴に置換されていく。
────彼女のプロフィールは、大部分が嘘でできている。
名前:コメット・エーデルシュタイン
年齢:16歳
身長:155cm
体重:49kg
誕生日:3月9日
性別:女性
武器:銃
学ランに着物にスチームパンクという異な出で立ちの少女。飄々とした性格、まるで舞台の上に立っているかのような身振りをする。いつも近くにいる黒猫を「お義父様」「先代」と呼んでいる。
家では飴屋『ほうきぼし』を営んでおり、外にいる時も飴玉を缶に入れて持ち歩いている。店員としての性格は明るく大和撫子。
学校では優等生のような振る舞いをしている。事実頭はいい。
両親はどちらも生みの親ではないらしく、説明する時は「スラム街で捨てられたところを魔女に気まぐれ拾われた」と言っている。その気まぐれがいつ消えてもいいように、身の回りの事は全て自分で出来るようにしている。
異能:『咲魔式』飴玉を用いた魔法
咲魔式の戦闘方式として飴玉を弾丸として用いる。飴玉の味、素材によって様々な効果をもたらす。現在投薬による異能改造が途切れているため、不完全な状態で発動している。専用の銃を用いなければ発動できない。
咲魔式:特殊な戦闘流派。先代はニフリート。飴玉を弾丸として用いる戦闘方法が特徴。通常の弾丸では不可能なトリッキーな戦い方ができる。コメットは咲魔式を扱える素養が異能として備わっていたらしい。
巽燈史郎(ENo.282)とは恋人関係(一応)
お店→http://lisge.com/ib/talk.php?p=386
全身図→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=comet.png
店員→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=coshop.png
「俺の娘だ。すごくねえわけねぇだろが。」
名前:ニフリート
性別:オス
コメットのそばにいつもいる黒猫。コメットには「お義父様」と呼ばれている。咲魔式の先代当主だったが、跡継ぎを残せぬまま老衰。死ぬ寸前に魔女と契約し、跡継ぎを探す旅を続けていた。姿を猫に変えられてしまっているためか言動もかなり猫。声が渋い。
サブ
魔女
大きな帽子をかぶった女性。コメットの義母という立ち位置だが、感情が薄く母親らしいことは何もしていない。花と宝石にまつわる魔女であり、歩いた後に宝石でできた花を咲かせたり、花を使って不思議な魔法を扱う。
ただし、本物の花は咲かせることができない。
御堂すいか(仮)
性別:女性
享年:3歳
御堂呉服店に住み着いている地縛霊。コメットと姿がよく似ているが、瞳の色は茶色。異能の暴発により死亡している。ものぐさ。
異能:テレキネシス
対象を好きな場所へ移動させたり曲げたりできる異能。脳への負担が大きいため、対象にXYZ軸を指定して、決めた方向へ動かすことができるように設定している。
「あたしは、コメット・エーデルシュタインだ。それがいい。」
偽名:コメット・エーデルシュタイン
本名:????
年齢:15歳(戸籍より一つ下。)
誕生日:5月22日(保護日)、11月28日(コメットとしての自我形成日)
捨て子。施設で2歳まで育てられ、御堂家の両親に亡くなった娘の代わりにと引き取られる。名前は無くなった娘と同じ『御堂翠華』である。
御堂家とはイバラシティに存在した名家である。
古くから呉服屋を営むその家で翠華は一人娘として育てられた。
礼儀作法を教えこまえ、両親に蝶よ花よと育てられた彼女は自らの異能も知らないまま無垢で純粋に育つ。
誰かの役に立ちたい、いつか家を継ぐものとして恥ずかしくない者でありたいと思っていたところに魔女と黒猫から咲魔式を継いで欲しいと持ちかけられる。
自らの異能が誰かの役に立つならば、と彼女はその願いを了承し、その旨を親に話しに行った。
かつての異能:『夢幻泡飴』
御堂翠華は飴が好きだったという事実と、本人の持つ『瞳への執着』が混ぜ合わさって生まれた異能。触れたものを時間ごと止めて飴玉に変えてしまう。美しいものは美しいままに。ずっと手の届く場所へ。発動した当時から今まで常に暴走状態である。
正しい異能:『白紙の役者』(タイトル・ロール・エトワール)
台本通りに演じ切る役者。何度でも書き換え可能の台本。端的に言って超強力な自己暗示。
『主』を設定し、その主が望んだように自身の思考、行動、異能さえ変革する異能。本人の羞恥や違和感も消し飛ばし、演じることができる。外見も時間はかかるが変更することができる。(髪の色、目の形など)
母親に「泣かず暴れない赤ん坊であれ」と願われればその通りに。御堂呉服店の夫婦に「御堂翠華であれ」と願われればその通りに演じ切った。『主』の対象は自分であっても構わない。
この異能には『観察』と『情報』が大きく作用する。「御堂翠華であれ」と願われた際に異能の情報を知らなかったため、御堂翠華本来の異能とは別の異能が備わった。同様に、他者を模倣した際に異能の効果を正確に把握していない場合は異能の模倣はできない。つまり基本的に知らないものを模倣することはできない。近づけたとしても『その異能を真似た別のもの』でしかない。
デメリット
・『主』を設定しないことはできない。もし設定しない場合生命活動のみを続ける抜け殻になってしまう。
・リソースは限られているためあまり過度な役を充てられると他の能力が大幅に落ちる。
・『主』を変える意志を奪われた場合自分では主を変えられない。
異能の使用例:めちゃくちゃ辛いものを食べる時に『主』を自分に設定。内容を『平然と食べる人』に設定。するとポーカーフェイスで辛いものを食べられるが、辛いものが嫌い過ぎた場合喋る能力が失われる。
SIDE:ANSINITY
名前:御堂翠華
年齢:6歳
魔女と黒猫に出会うことが無かったコメットのIF。世界の半分を飴玉に変えてしまい、否定の世界へ追放された。
この世界に来るにあたり、『コメットの過去の亡霊』として呉服店に固定されてしまった。元からそこに住む地縛霊『御堂すいか』の体を借りている。
ハザマでは両親を元に戻すことを条件に渋々ながらコメットに協力している。
異能:『夢幻泡飴』触れたものを飴玉に変える異能
彼女は両親の手を握った。自分をまっすぐに見つめる瞳が美しいと思った。
いつまでも、近くで眺めていたかった。
気づいたら、両親の姿はなかった。両親は娘の異能によって飴玉に変えられてしまったのだ。
アンジニティに落ちた時点で、彼女の異能は夢幻泡飴に固定されている。
ハザマにおいて、コメットの体は少しずつ飴に置換されていく。
30 / 30
216 PS
チナミ区
H-16
H-16






































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | タッセルイヤリング | 装飾 | 20 | 体力10 | - | - | |
| 5 | キャノンドロップス | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 7 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]回復10(LV15)[防具]活力10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 8 | ゴリー・スーツ | 防具 | 40 | 体力10 | - | - | |
| 9 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 10 | 狐のキーホルダー | 装飾 | 45 | 回復10 | - | - | |
| 11 | フランケンシュタインの復讐 | 装飾 | 82 | 舞乱10 | - | - | |
| 12 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 13 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |
| 装飾 | 45 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| 決3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| 決1 | ヒールポーション | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| カームフレア | 6 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| フィーバー | 6 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |
| リフレッシュ | 6 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アクアリカバー | 6 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヒールハーブ | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 決2 | アクアヒール | 6 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| パワフルポーション | 5 | 0 | 120 | 自:AT・DF増+猛毒・麻痺・衰弱 | |
| オートヒール | 6 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| チャクラグラント | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 | |
| パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| ヒールミスト | 5 | 0 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程3以上ならDX減(2T) | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 | |
| クライオセラピー | 5 | 0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 医食同源 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:食事による付加効果のLV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
守護天使 (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
ヘイルカードかーど (ヘイルカード) |
0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| 決2 |
オゾン水 (アクアヒール) |
0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
|
芽吹き (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 | |
|
ミーシャ・ハードブレイク (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| 決1 |
廻血 (ブレイドフォーム) |
0 | 160 | 自:AT増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]ダークネス | [ 1 ]ビブラート |
| [ 2 ]カームフレア | [ 1 ]ウォーターフォール | [ 1 ]ファイアボルト |
| [ 1 ]クリエイト:グレイル | [ 1 ]五月雨 | [ 1 ]ヘイルカード |
| [ 1 ]ハードブレイク | [ 1 ]リンクブレイク | [ 1 ]フェイタルポイント |
| [ 1 ]デアデビル | [ 2 ]チェインリアクト | [ 1 ]コールドウェイブ |
| [ 1 ]パワフルヒール |

PL / アルス