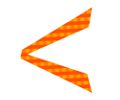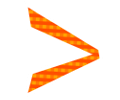<< 4:00~5:00




全員殺してやろうか、と。何度思っただろう。
「■■■■、■■■■■。■■、■■■」
「■■。■■■」
「■■■■。……巽くん、次は―――」
「(何が“巽くん”だ)」
温度のない漢字10文字。覚える気にもならない“能力”の出力装置としか自分を見ていない連中。
知らないのだろう。
この邪魔くさい機械も、首輪や枷には足りないというのに。
彼らの顔には、危機感が足りない。
気遣いも、施しも、余裕という土壌にようやく芽生えるものだということを、奴らは教えてくれた。
これがある以前と以後で、俺への接し方が笑えるほどに変わったものだから。
――――
……もう何度目にもなる、下らない“手遊び”を、馬鹿みたいに繰り返す。
高エネルギー物理学。この世界を構成する最小単位、素粒子の探求。
例えば、ソラから落ちてくるそれを捕まえたり。
例えば、手元で条件を作り、発生したそれを取り出したり。
「君の力は、人間社会に多大に貢献し得るものなんだよ」
……本気で言っていたなら救えない。
子供相手に“その気にさせる”文句としてそれなら下手くそにすぎるから、多分本気だったのだろう。
失笑ものだ。今はもう顔を見ないいつかの誰かも。
その気になった、自分も。
未知の素粒子がどうのとデータを見て舞い上がる連中の、気分高揚に貢献はしても。
“人間社会”とやらが、何か良くなっている気は微塵もしない。
……少なくとも。
俺の家から、笑顔が、減った。
「(全員殺してやろうか)」
ぐるぐる、ぐるぐる。
定められた範囲を加速し、時に衝突させられる陽子の群れが。
気まぐれ一つでそちらに向くのだということを、理解している者はどれ程居るのだろう。
まともに考えてそうであるように、自分の体を透過してくれると高をくくっているのだろうか。
今まさにそれを、自分達の指揮下、“異能”で以て捻じ曲げながら。
「(……あぁ、でも)」
その後どうするか、というところで些細な稚気は萎んでしまう。
歳不相応に聡明にすぎる子供。
常ならざる能力を生まれ持った長子に対し。愛すべき両親の対応は、むしろ出来た人のそれだろう。
“せめて”と役立とうとした息子に、子供で在れと説いた。
気味の悪い子供であることへの負い目に苦しむ息子に、“一緒に頑張ろう”と。
自分達なりに、家族であろう、と。
それが出来なかったからここにいる。逃げてきた、どん詰まり。
わかっていた。この“貢献”は、決して巽家を幸福にはしない。
わかってはいた、のだけれど。
「巽くん、次は―――」
「……」
黙って、従う。
こんな奴らはどうでもいい。人間社会とやらも、どうでもいい。
ただ。
あの優しい人達が、互いへの愛と敬意の後、少なからず心身にも、経済的にも負担を負って。
産み落とされたモノが。ただ気持ちの悪い何かであってはならないのだ。
せめて負担を埋め合わせ、投資に余りあるものでなければならない。
「(弟でも、妹でもいいな)」
「(あぁ、でも、弟の次に妹がいい。頑張れ、お兄ちゃん)」
実験の中、未来の夢想が楽しみだった。
「(そしたら、ここの誰か一人、最初に目に付いた奴をひっぱたいて、辞めよう)」
「(母さんの代わりに家事をして、父さんが居ない時は話し相手になろう)」
「(……落ち着いたら。ここで稼いだ分で、一人暮らしをしよう)」
どうか、やり直して欲しい。
優しい人達だった。心から尊敬できる人達だった。
だから、きっと。
こんな間違いがなければ、世界で一番幸せな家庭を作れるはずだった。
「巽くん、次は」
「わかってる、次は―――」
―――世界が、真っ暗になった。
パニックになった頭が状況を理解するのに、数秒を要した。
「(なにも、みえない?)」
視覚は問題なく働いている。部屋も、自分の体も見える。
止まったのは、自分の“観測”。己の意思に関係なく、能力が止まっている。
実験室にただ一つのドアが開く。スピーカーは沈黙したまま。
……気だるげに部屋を見渡し、後こちらに目を遣ったそいつは。
頭の天辺からつま先まで、“黒”い男だった。
「―――……概ね予想通りではあるけれど」
「……誰?」
睨む視線も意に介さず、溜め息をついて。
「胸糞悪いな」
それが、1つ目。
自分の人生を変えた、出会いだった。
――――
「―――、……」
頭を振る。
意識が朦朧としていた。自覚できている内は深刻な問題にはならないだろうが。
休んでいる暇はない。時間がないのだ。
道行けば襲いかかってくるハザマの住人。
アンジニティの侵略者の手がこちらに及ばないのはどういう考えがあってのことか。
わからないが、今は僥倖だった。それらへの対処だけでも中々に体力を使うものだから。
「(侵略、戦争……)」
“どうにか”できるものであるのか。考えることに意味はない。出来るものとして動く他ないのだから。
……両陣営の案内人らしい連中のやり取りが、Cross+Roseの機能で確認できる。
どうやら連中も、全ては知らないらしい。不測の事態、期待をかけるならその辺りだろうか。
「(奴らの思うままに自体を進めれば、“本来”の結末に至るだけだろう)」
ロストがどうの、そういった“余分”に取り組む意義は十分に感じられる。
「(コメットの問題は……)」
……分からない。結局、“あちら”の自分も、それについて何も貢献していない。
「(ハザマの家に、何か、残っていれば……或いは)」
いびつな形ではあるが、この世界にはあちら側の名残が感じられる。
では、チナミ区のあの座標には、コメットの家の名残とでも言えるものがあるはずだった。
「(少なくとも、魔女殿はこの事態に“巻き込まれて”はいない)」
であるならば―――
「…………あぁ、全く」
展開した防御式の外縁に、何かが触れる。形状は四足獣、恐らくはこの世界の住民。
あちらからすれば、侵略がどうのとそれこそ“知ったことではない”のだろう。
理不尽だ。わかっている。わかっては、いるのだけれど。
「邪魔、を、するな」
寛容は余裕から生じる。
今、自分には、余裕がなかった。



ENo.17 サクマ とのやりとり

ENo.102 安里杏莉? とのやりとり

ENo.136 ティトリ とのやりとり

ENo.161 ミツフネ とのやりとり

ENo.229 神の力 とのやりとり

ENo.256 ナガレ とのやりとり

ENo.298 避役 とのやりとり

ENo.342 色蝕の塊 とのやりとり

ENo.658 天弖 とのやりとり

ENo.671 海の魔物 とのやりとり

ENo.801 セオリ とのやりとり

ENo.854 ルーシー とのやりとり

ENo.964 姿無きエリスロス とのやりとり

ENo.1072 フーコ とのやりとり

ENo.1104 刀崎 依良 とのやりとり

ENo.1286 ネン とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。












コウキ(1026) から 60 PS 受け取りました。
アリヒト(18) から 爪 を受け取りました。
スペイド(799) に ItemNo.7 柳 を送付しました。
アリヒト(18) に ItemNo.12 牙 を送付しました。
ミツフネ(161) に ItemNo.14 左天白陽・改 を送付しました。
コウキ(1026) に ItemNo.10 美味しい果実 を送付しました。
スペイド(799) から 不思議な雫 を受け取りました。
具現LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
コウキ(1026) の持つ ItemNo.3 千子村正 に ItemNo.4 何か柔らかい物体 を付加しました!
コウキ(1026) の持つ ItemNo.14 緋緋色金二枚胴具足 に ItemNo.6 ボロ布 を付加しました!
コウキ(1026) の持つ ItemNo.10 死返玉 に ItemNo.5 羽 を付加しました!
ノブナガ(1324) とカードを交換しました!
ぷよぷよした何か (サモン:スライム)

チェインリアクト を研究しました!(深度0⇒1)
チェインリアクト を研究しました!(深度1⇒2)
バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
マーチ を習得!
アースタンブア を習得!
クリエイト:パワードスピーカー を習得!
ビブラート を習得!
フリーズノート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





カミセイ区 J-2(道路)に移動!(体調6⇒5)
カミセイ区 J-3(道路)に移動!(体調5⇒4)
カミセイ区 I-3(沼地)に移動!(体調4⇒3)
カミセイ区 H-3(沼地)に移動!(体調3⇒2)
カミセイ区 H-4(チェックポイント)に移動!(体調2⇒1)
MISSION!!
カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》 が発生!
- 巽(282) が経由した カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――








仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)












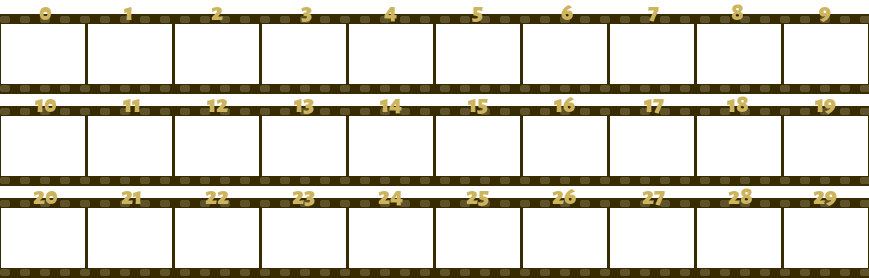







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



全員殺してやろうか、と。何度思っただろう。
「■■■■、■■■■■。■■、■■■」
「■■。■■■」
「■■■■。……巽くん、次は―――」
「(何が“巽くん”だ)」
温度のない漢字10文字。覚える気にもならない“能力”の出力装置としか自分を見ていない連中。
知らないのだろう。
この邪魔くさい機械も、首輪や枷には足りないというのに。
彼らの顔には、危機感が足りない。
気遣いも、施しも、余裕という土壌にようやく芽生えるものだということを、奴らは教えてくれた。
これがある以前と以後で、俺への接し方が笑えるほどに変わったものだから。
――――
……もう何度目にもなる、下らない“手遊び”を、馬鹿みたいに繰り返す。
高エネルギー物理学。この世界を構成する最小単位、素粒子の探求。
例えば、ソラから落ちてくるそれを捕まえたり。
例えば、手元で条件を作り、発生したそれを取り出したり。
「君の力は、人間社会に多大に貢献し得るものなんだよ」
……本気で言っていたなら救えない。
子供相手に“その気にさせる”文句としてそれなら下手くそにすぎるから、多分本気だったのだろう。
失笑ものだ。今はもう顔を見ないいつかの誰かも。
その気になった、自分も。
未知の素粒子がどうのとデータを見て舞い上がる連中の、気分高揚に貢献はしても。
“人間社会”とやらが、何か良くなっている気は微塵もしない。
……少なくとも。
俺の家から、笑顔が、減った。
「(全員殺してやろうか)」
ぐるぐる、ぐるぐる。
定められた範囲を加速し、時に衝突させられる陽子の群れが。
気まぐれ一つでそちらに向くのだということを、理解している者はどれ程居るのだろう。
まともに考えてそうであるように、自分の体を透過してくれると高をくくっているのだろうか。
今まさにそれを、自分達の指揮下、“異能”で以て捻じ曲げながら。
「(……あぁ、でも)」
その後どうするか、というところで些細な稚気は萎んでしまう。
歳不相応に聡明にすぎる子供。
常ならざる能力を生まれ持った長子に対し。愛すべき両親の対応は、むしろ出来た人のそれだろう。
“せめて”と役立とうとした息子に、子供で在れと説いた。
気味の悪い子供であることへの負い目に苦しむ息子に、“一緒に頑張ろう”と。
自分達なりに、家族であろう、と。
それが出来なかったからここにいる。逃げてきた、どん詰まり。
わかっていた。この“貢献”は、決して巽家を幸福にはしない。
わかってはいた、のだけれど。
「巽くん、次は―――」
「……」
黙って、従う。
こんな奴らはどうでもいい。人間社会とやらも、どうでもいい。
ただ。
あの優しい人達が、互いへの愛と敬意の後、少なからず心身にも、経済的にも負担を負って。
産み落とされたモノが。ただ気持ちの悪い何かであってはならないのだ。
せめて負担を埋め合わせ、投資に余りあるものでなければならない。
「(弟でも、妹でもいいな)」
「(あぁ、でも、弟の次に妹がいい。頑張れ、お兄ちゃん)」
実験の中、未来の夢想が楽しみだった。
「(そしたら、ここの誰か一人、最初に目に付いた奴をひっぱたいて、辞めよう)」
「(母さんの代わりに家事をして、父さんが居ない時は話し相手になろう)」
「(……落ち着いたら。ここで稼いだ分で、一人暮らしをしよう)」
どうか、やり直して欲しい。
優しい人達だった。心から尊敬できる人達だった。
だから、きっと。
こんな間違いがなければ、世界で一番幸せな家庭を作れるはずだった。
「巽くん、次は」
「わかってる、次は―――」
―――世界が、真っ暗になった。
パニックになった頭が状況を理解するのに、数秒を要した。
「(なにも、みえない?)」
視覚は問題なく働いている。部屋も、自分の体も見える。
止まったのは、自分の“観測”。己の意思に関係なく、能力が止まっている。
実験室にただ一つのドアが開く。スピーカーは沈黙したまま。
……気だるげに部屋を見渡し、後こちらに目を遣ったそいつは。
頭の天辺からつま先まで、“黒”い男だった。
「―――……概ね予想通りではあるけれど」
「……誰?」
睨む視線も意に介さず、溜め息をついて。
「胸糞悪いな」
それが、1つ目。
自分の人生を変えた、出会いだった。
――――
「―――、……」
頭を振る。
意識が朦朧としていた。自覚できている内は深刻な問題にはならないだろうが。
休んでいる暇はない。時間がないのだ。
道行けば襲いかかってくるハザマの住人。
アンジニティの侵略者の手がこちらに及ばないのはどういう考えがあってのことか。
わからないが、今は僥倖だった。それらへの対処だけでも中々に体力を使うものだから。
「(侵略、戦争……)」
“どうにか”できるものであるのか。考えることに意味はない。出来るものとして動く他ないのだから。
……両陣営の案内人らしい連中のやり取りが、Cross+Roseの機能で確認できる。
どうやら連中も、全ては知らないらしい。不測の事態、期待をかけるならその辺りだろうか。
「(奴らの思うままに自体を進めれば、“本来”の結末に至るだけだろう)」
ロストがどうの、そういった“余分”に取り組む意義は十分に感じられる。
「(コメットの問題は……)」
……分からない。結局、“あちら”の自分も、それについて何も貢献していない。
「(ハザマの家に、何か、残っていれば……或いは)」
いびつな形ではあるが、この世界にはあちら側の名残が感じられる。
では、チナミ区のあの座標には、コメットの家の名残とでも言えるものがあるはずだった。
「(少なくとも、魔女殿はこの事態に“巻き込まれて”はいない)」
であるならば―――
「…………あぁ、全く」
展開した防御式の外縁に、何かが触れる。形状は四足獣、恐らくはこの世界の住民。
あちらからすれば、侵略がどうのとそれこそ“知ったことではない”のだろう。
理不尽だ。わかっている。わかっては、いるのだけれど。
「邪魔、を、するな」
寛容は余裕から生じる。
今、自分には、余裕がなかった。



ENo.17 サクマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.102 安里杏莉? とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.136 ティトリ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.161 ミツフネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.229 神の力 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.256 ナガレ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.298 避役 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.342 色蝕の塊 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.658 天弖 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.671 海の魔物 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.801 セオリ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.854 ルーシー とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.964 姿無きエリスロス とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1072 フーコ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1104 刀崎 依良 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1286 ネン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。





対戦相手消失のため不戦勝!



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 6 増加!
影響力が 6 増加!



コウキ(1026) から 60 PS 受け取りました。
| コウキ 「不思議な力を秘めたパワーストーンという触れ込みですが、このままでは使えないようですね。精錬の様な加工が必要かも知れません。」 |
アリヒト(18) から 爪 を受け取りました。
スペイド(799) に ItemNo.7 柳 を送付しました。
アリヒト(18) に ItemNo.12 牙 を送付しました。
ミツフネ(161) に ItemNo.14 左天白陽・改 を送付しました。
コウキ(1026) に ItemNo.10 美味しい果実 を送付しました。
スペイド(799) から 不思議な雫 を受け取りました。
具現LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
コウキ(1026) の持つ ItemNo.3 千子村正 に ItemNo.4 何か柔らかい物体 を付加しました!
コウキ(1026) の持つ ItemNo.14 緋緋色金二枚胴具足 に ItemNo.6 ボロ布 を付加しました!
コウキ(1026) の持つ ItemNo.10 死返玉 に ItemNo.5 羽 を付加しました!
ノブナガ(1324) とカードを交換しました!
ぷよぷよした何か (サモン:スライム)

チェインリアクト を研究しました!(深度0⇒1)
チェインリアクト を研究しました!(深度1⇒2)
バーニングチューン を研究しました!(深度0⇒1)
マーチ を習得!
アースタンブア を習得!
クリエイト:パワードスピーカー を習得!
ビブラート を習得!
フリーズノート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





カミセイ区 J-2(道路)に移動!(体調6⇒5)
カミセイ区 J-3(道路)に移動!(体調5⇒4)
カミセイ区 I-3(沼地)に移動!(体調4⇒3)
カミセイ区 H-3(沼地)に移動!(体調3⇒2)
カミセイ区 H-4(チェックポイント)に移動!(体調2⇒1)
MISSION!!
カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》 が発生!
- 巽(282) が経由した カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――







カミセイ区 H-4
チェックポイント《森の学舎》
チェックポイント。チェックポイント《森の学舎》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《SNAKE》
黒闇に包まれた巨大なヘビのようなもの。
 |
守護者《SNAKE》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



ENo.282
巽燈史郎



●巽 燈史郎(タツミ トウシロウ)
相良伊橋高校に通う2年生。
身長179cm、体重66kg。座右の銘は『即断即決』。
着崩さない制服、キビキビした挙動、生徒会にも書紀として所属し、正に絵に書いたような優等生。……であることに間違いはないのだが、時にその行動力は、自身の良心に沿って妙な方向に突き抜けることもある。
後述する異能の関係もあり、成績は良好。特に数学、物理学に強い。
趣味は天体観測である。
◆RPにより開示(ENo.58「高国藤久」を除き既知設定任意)
前科一犯。6人の少年に暴行した事件で傷害罪、家庭裁判所で有罪判決を受ける。
事件の状況から検察の求刑よりいくらか減刑され、家庭裁判所から保護観察処分を言い渡される。20歳までの期間であるため、現在も保護観察官と生活を送っている。
・異能:『地心天動』
一言で言えば“天動説”。
地球を中心に、あらゆる“衛星”が公転しているという仮想を現実に投影するもの。
「対象を観測・指定」「自分を中心に軌道を設定」「公転の方向・速度を決定」「発動」というプロセスを踏む。最も難解な二番目を「(その距離を半径とした)円状」とすることで大きく手順を短縮できるが、例えば自身に近づく、遠のくといった軌道は、公転の円を脳内で結ぶまでのタイムラグを要する。
巽燈史郎はこの異能を利用し、事故、不意打ちへの対策として、『半径1m以内』『時速20km以上で進行する無機物』を対象として、『等速・円状の軌道での公転』を設定している。
交通量が多い、人混み、会話の流れでそういった状態が発生しうる等、状況に応じての解除。或いは危険な場所での条件変更等例外はあるが、基本的には常時発動である。
(PCの知覚任意)
『観測』が全ての前提であるために、何らかの認識阻害が発生している場合、巽の観測下には『観測不可の領域』が発生する。その先に異能による干渉はできない。
――――――――――◆―――――――――――
●フェイ
女性。年齢不詳。恐らく10代後半~20代前半、中国人。
身長170cm、体重70kg。
主に香港を活動範囲としていた“ボディーガード”。
……と言えば聞こえはいいが、実態は金で雇われ、必要に応じて行使される暴力装置である。
元は護身のために、少ない糧の更に一部を対価に、同じ立場に身をやつしていた名も知らぬ男に武術を習ったのが始まり。
多くの師の元で多くの武術を習い、またその尽くから破門を受けている。
現在の師は剋天流を修めており、木行式の達人。
その命令によってこの島にやって来た。その理由を理解することもまた、修行の一環であるようだ。
中国暗黒街において『剑齿虎』としてそれなりに名が通っている。佩(フェイ)とは“武器を佩いている”という、後述の異能と卓越した武術から来る仇名の一つ。
・異能:『地煞七十二変化』
自身の体を違うものに変化させる。
幼く、未だ武術も修めていなかった頃。身を守るため『虎』に变化し、その尽くを撃退する。
しかし『虎』も『人体』も深くは知らず行った為に、元に戻りきれなかった部分が幾らか存在し、それ以来自分の肉体そのものを変化させることは辞めている。
主に千切った髪を武器や分身に变化させて扱う。
複雑なものほど持続時間・耐久性は下がる。
――――――――――◆―――――――――――
――――――――――◆―――――――――――
●間明 蓮(マギラ レン)
21歳。剣道道場『錬心舘』経営。身長176cm。体重97㎏。
両親は逝去しており、一人で住むには広い武家屋敷と、質素に生きるなら十分な不労所得を有している。趣味は散歩、そして剣道。
大会の類に出たことはなく、部内でもあまり試合をすることはなかった。出たいと思ったことも、試合を組むことを避ける節があった顧問への不満も無く、当時も今も、ただ『趣味』として稽古を続けている。
……しかし、ここ最近はその向き合い方にも変化があり。
・異能:――
静止視力・動体視力・深視力から成る空間認識能力。
筋力・平衡感覚から成る継続的・瞬発的な身体操作。
それらを限りなく認識通り運用するための、神経伝達速度と心肺能力。
彼に異能はなく、それら全て、人間が例外なく生まれ持つ、身体能力である。
――――――――――◆―――――――――――
相良伊橋高校に通う2年生。
身長179cm、体重66kg。座右の銘は『即断即決』。
着崩さない制服、キビキビした挙動、生徒会にも書紀として所属し、正に絵に書いたような優等生。……であることに間違いはないのだが、時にその行動力は、自身の良心に沿って妙な方向に突き抜けることもある。
後述する異能の関係もあり、成績は良好。特に数学、物理学に強い。
趣味は天体観測である。
◆RPにより開示(ENo.58「高国藤久」を除き既知設定任意)
前科一犯。6人の少年に暴行した事件で傷害罪、家庭裁判所で有罪判決を受ける。
事件の状況から検察の求刑よりいくらか減刑され、家庭裁判所から保護観察処分を言い渡される。20歳までの期間であるため、現在も保護観察官と生活を送っている。
・異能:『地心天動』
一言で言えば“天動説”。
地球を中心に、あらゆる“衛星”が公転しているという仮想を現実に投影するもの。
「対象を観測・指定」「自分を中心に軌道を設定」「公転の方向・速度を決定」「発動」というプロセスを踏む。最も難解な二番目を「(その距離を半径とした)円状」とすることで大きく手順を短縮できるが、例えば自身に近づく、遠のくといった軌道は、公転の円を脳内で結ぶまでのタイムラグを要する。
巽燈史郎はこの異能を利用し、事故、不意打ちへの対策として、『半径1m以内』『時速20km以上で進行する無機物』を対象として、『等速・円状の軌道での公転』を設定している。
交通量が多い、人混み、会話の流れでそういった状態が発生しうる等、状況に応じての解除。或いは危険な場所での条件変更等例外はあるが、基本的には常時発動である。
(PCの知覚任意)
『観測』が全ての前提であるために、何らかの認識阻害が発生している場合、巽の観測下には『観測不可の領域』が発生する。その先に異能による干渉はできない。
――――――――――◆―――――――――――
●フェイ
女性。年齢不詳。恐らく10代後半~20代前半、中国人。
身長170cm、体重70kg。
主に香港を活動範囲としていた“ボディーガード”。
……と言えば聞こえはいいが、実態は金で雇われ、必要に応じて行使される暴力装置である。
元は護身のために、少ない糧の更に一部を対価に、同じ立場に身をやつしていた名も知らぬ男に武術を習ったのが始まり。
多くの師の元で多くの武術を習い、またその尽くから破門を受けている。
現在の師は剋天流を修めており、木行式の達人。
その命令によってこの島にやって来た。その理由を理解することもまた、修行の一環であるようだ。
中国暗黒街において『剑齿虎』としてそれなりに名が通っている。佩(フェイ)とは“武器を佩いている”という、後述の異能と卓越した武術から来る仇名の一つ。
・異能:『地煞七十二変化』
自身の体を違うものに変化させる。
幼く、未だ武術も修めていなかった頃。身を守るため『虎』に变化し、その尽くを撃退する。
しかし『虎』も『人体』も深くは知らず行った為に、元に戻りきれなかった部分が幾らか存在し、それ以来自分の肉体そのものを変化させることは辞めている。
主に千切った髪を武器や分身に变化させて扱う。
複雑なものほど持続時間・耐久性は下がる。
――――――――――◆―――――――――――
――――――――――◆―――――――――――
●間明 蓮(マギラ レン)
21歳。剣道道場『錬心舘』経営。身長176cm。体重97㎏。
両親は逝去しており、一人で住むには広い武家屋敷と、質素に生きるなら十分な不労所得を有している。趣味は散歩、そして剣道。
大会の類に出たことはなく、部内でもあまり試合をすることはなかった。出たいと思ったことも、試合を組むことを避ける節があった顧問への不満も無く、当時も今も、ただ『趣味』として稽古を続けている。
……しかし、ここ最近はその向き合い方にも変化があり。
・異能:――
静止視力・動体視力・深視力から成る空間認識能力。
筋力・平衡感覚から成る継続的・瞬発的な身体操作。
それらを限りなく認識通り運用するための、神経伝達速度と心肺能力。
彼に異能はなく、それら全て、人間が例外なく生まれ持つ、身体能力である。
――――――――――◆―――――――――――
1 / 30
441 PS
カミセイ区
H-4
H-4



































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | ジャケット | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 頭痛薬 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | 携行食(耐疫10) | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 8 | 違法改造EaCM | 防具 | 60 | 活力15 | - | - | |
| 9 | レジンフラワーペンダント | 装飾 | 40 | 祝福10 | 回復10 | - | |
| 10 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||
| 11 | HFC-282t | 装飾 | 50 | 耐火10 | - | - | |
| 12 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
| 13 | 小惑星の力学 | 装飾 | 50 | 回復10 | - | - | |
| 14 | |||||||
| 15 | カーディガン | 防具 | 75 | 活力15 | - | - | |
| 16 | 爪 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]反撃10(LV30)[装飾]器用10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 付加 | 25 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 20 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決1 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| 決1 | ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| 決1 | ボロウライフ | 6 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| コールドウェイブ | 6 | 0 | 80 | 敵4:水撃&凍結+自:炎上 | |
| 決1 | ヘイルカード | 7 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| 決1 | アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |
| アースタンブア | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&自:3D6が15以上ならMHP・MSP増 | |
| クリエイト:パワードスピーカー | 5 | 0 | 130 | 自:魅了LV増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| 決2 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| フリーズノート | 5 | 0 | 110 | 敵従全:水領痛撃 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| サモン:ハンター | 5 | 4 | 300 | 自:ハンター召喚 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
おひるねのうた (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
鰐淵さん誘拐事件~洗濯編~ (アクアヒール) |
0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
|
いのち (ライフリンク) |
0 | 50 | 自従傷:HP増+HP譲渡 | |
|
守ってやるよ (リストア) |
0 | 120 | 味全:HP増+環境変調を守護化 | |
|
ぷよぷよした何か (サモン:スライム) |
2 | 300 | 自:スライム召喚 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]イレイザー | [ 3 ]オートヒール | [ 2 ]チェインリアクト |
| [ 3 ]ストライク | [ 3 ]ハードブレイク | [ 1 ]バーニングチューン |
| [ 3 ]五月雨 |

PL / Lamb