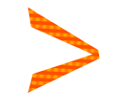<< 1:00~2:00




──赤黒い世界。血に塗れた汚い世界で、私はずっと蹲っていた。
襲い掛かってくるのならば、それに触れた。触れれば全て飴玉に変わった。
それを口に入れる気力すらなくて、私の周りには飴玉がたくさん転がっていた。

私は、どうしてこんなところで蹲っているんだっけ。
光の差さない、何も動かない。時計の針も進まない。そんな場所でこうして一人で蹲って、随分時間が経った気がする。
動くものに寄り添って、呼ばれる声に振り向いたことだってあったはずなのに。
名前すら思い出せないけれど、大事な、かけがえのないものがあったはずなのに。
どうして私の手元にはそれがないんだろう。どうして私の手を誰も握ってはくれないのだろう。どうしてみんないなくなってしまうのだろう。
誰かが、手を差し伸べてくれたこともあった気がする。
この暗くて汚い世界で、自分なら大丈夫だと、手を取ろうとしてくれた人もいた気がする。
でも、その人はここにはいない。いないということは、床に散らばる飴玉の内のひとつになってしまったのだろう。
どうして、私は誰かの手を握れないのだろう。どうして、私は誰かと共に歩むことができないんだろう。
──罪は、消えない。忘れたって過去はなかったことになんてなってくれないし、時間は巻き戻ってくれない。

──なら、泥臭くて最悪な手でも、自分にできることをするしかないと思ったから。
『ねえ、いらないなら、ちょうだいよ。』
じゃり、と砂を手で掴む。地面に倒れ伏してからしばらく意識が無かったが、どうやら命は助かったらしい。
右手の指の飴化はだいぶ進行してしまっている。……そこだけは痛みも感じなかった。
口から血の塊を吐き出す。……命は助かったとはいえ、受けた傷は浅くない。
顔、腕、脚には無数の切り傷や噛み痕が刻まれ、体の中には病魔が巣食っている。
抉れた脇腹から血が零れ落ち、立ち上がろうとした足が崩れ落ちそうになる。
倒れかけた体を大きな体が支えた。
周囲に大量の飴玉を浮かべて、術式を展開してくれたらしい。
咲魔式先代当主──ニフリートによる治癒はみるみるうちに体を楽にしてくれた。
普段が真面目ではないだけで、やはり彼は正当な咲魔式の継承者であるということがわかる。
質も威力も自分とは桁違いだ。自分は中途半端に異能改変を施しているから当然ではあるのだが。
端末を取り出して、傍らの義父に振って見せる。
もう一度力を込め、地面を踏みしめて立つ。
大丈夫、もう歩ける。
過去の自分──正しくは、魔女に拾われることなく全てを飴玉に変えて否定の世界へ落ちた自分の姿に苦笑して歩き出す。
いったいどうしたらこうなってしまうのやら、と思いつつ、気持ちがわかる部分もある。
怒りにせよ憎しみにせよ、彼女もまた自分だけの感情を手に入れることができた。
道は違えた。自分たちの目指すところは同じでも、手段が全く違う方向へ向かってしまった。
自分と彼女は、もうきっと同じ存在ではないのだから。
──彗星は、『よごれた雪だるま』に例えられる。
別に、それが名前の由来じゃない。自虐的な要素はあれど、自分の名前を考えたのはおおよそ希望的な理由と意味だ。
『輝く塵』。冷たい氷が集まり、輝き、やがて燃え尽きる。
殻を作り上げて目的を果たし、いつか消える。そう望まれて『御堂翠華』から『コメット・エーデルシュタイン』は生まれた。
冷たい場所で生まれた。あたしは、それだけはよく覚えている。
温かい場所から遠くて、でもそもそも温かい場所なんて知らなかったから「冷たい」なんて感想を抱くこともなくて。
きっと自分は、望まれないで生まれた。
だから、「望まれること」を求め続けたのだろう。
『コメット・エーデルシュタイン』を作った『御堂翠華』の問題をひとつひとつ片付けて、消えるだけ。
だけどあたしは、命が惜しくなってしまって。
──彗星は、氷微惑星が惑星の引力に引かれて軌道を変えるらしい。
太陽系の内側へと向かい、やがて尾をひいて彗星へと変わる。
太陽へと進んで、一番近くにふれて、……燃え尽きて、二度と帰ってこない。
だけどあたしは──

「お前を攫う、コメット・エーデルシュタイン。着地点は、これから見つける」
「信じろ」
「娘さんを俺にください」
「俺は、俺の全力を以て、コメット・エーデルシュタインを“手に入れる”」
「いずれ胸を張ってこれは“愛”だと言える日まで。俺は彼女を手放さない」

「約束する。幸せにする」
「お前に“生きたい”と思わせた責任を取ると、誓う」
「大好きだ、コメット。……俺の、唯一」
あたしは、捕まってしまった。
燃え尽きる前に。通り過ぎる前に。
──捕まってしまった。
あの声で、名前を呼ばれて。
あの目で、見つめられて。
あの手で、握られて。
捕まってしまったら、もうただの殻には戻れないと知っていたのに。
寂しくなって、切なくなって、苦しむことなんてわかっていたのに。
その手を、取ってしまった。
未来を生きる道を選んでしまった。
御堂翠華への、義両親への裏切りに等しい。
だけど、心はもう止まらなかった。
だって、一緒に考えようと言われてしまったから。
弱音を聞いてくれと言われてしまったから。
何一つ取りこぼさずに、幸せな未来を一緒に見つけようと提示されて。
頷かないわけがなかった。
「……いつか、本土の海も見に行きたいな。浄土ヶ浜なんて、絶景で有名だし」

「……君の思い描く"いつか"を、きっと未来で観に行こう。」
"いつか"は、叶わない?
"みんなで卒業"は、できない?
どちらかしか選べない。あの場所の日常は、どの道崩れ去ってしまうだろう。
それに対して、きっと君は悩んでしまうだろうけど。
「──さあ、立って。」
「あたしは、大丈夫。」
「だから、君も大丈夫だ。」
嘘ばかりだけど、強がりばかりで、つぎはぎだらけだけど。
その『嘘』も、『強がり』だって、本物にしていこうと思ったから。
泣きそうなほど重厚な弱虫を、きっと君は笑わないだろう。
『コメット・エーデルシュタイン』とういう役を充てられて、舞台に立った。
「俺が一緒に今まで過ごしてきたのはコメット・エーデルシュタインだ」と言われて、役を張り付けられたまま舞台から下ろされた。いや、『役』だけが、舞台から引き下ろされてしまった。
それでも、舞台の上に憧れて。自分を引き下ろした彼を見上げることしかできなくて。
だから、今度は自分の意志で舞台に上がった。
手を取って、確かに握って、今度はしっかり目を合わせて。
舞台の上において客席以外を見るのはご法度だ。だけど、そんなこと今は関係ない。
幕は下りている。これから上がっていく。カーテンコールを前にして、あたしは不敵に笑うのだ。

──あたしは、大丈夫だと。



ENo.17 サクマ とのやりとり

ENo.55 ゆい とのやりとり

ENo.281 まさこ とのやりとり

ENo.403 アミナ とのやりとり

ENo.437 晴太 とのやりとり

ENo.632 サフィア とのやりとり

ENo.671 海の魔物 とのやりとり

ENo.824 オルトロス とのやりとり

ENo.1520 "大地の不純物" とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 飴細工 を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












魔術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
料理LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
命術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
自然LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 15 UP!(LV15⇒30、-15CP)
巽(282) の持つ ItemNo.9 花びら から装飾『レジンフラワーペンダント』を作製しました!
まさこ(281) の持つ ItemNo.8 花びら から装飾『花びらのコサージュ』を作製しました!
勇者(551) により ItemNo.8 韮 から防具『ゴリー・スーツ』を作製してもらいました!
⇒ ゴリー・スーツ/防具:強さ40/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-
リーナ(1254) とカードを交換しました!
オゾン水 (アクアヒール)

フェイタルポイント を研究しました!(深度0⇒1)
リンクブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
デアデビル を研究しました!(深度0⇒1)
ブルーム を習得!
オートヒール を習得!
水の祝福 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ヒビキ(216) は 韮 を入手!
コメット(253) は 白石 を入手!
まさこ(281) は 韮 を入手!
勇者(551) は 韮 を入手!
コメット(253) は ネジ を入手!
ヒビキ(216) は 毛 を入手!
まさこ(281) は 不思議な雫 を入手!
勇者(551) は 不思議な雫 を入手!



チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調19⇒18)
採集はできませんでした。
- ヒビキ(216) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- コメット(253) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- まさこ(281) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――



























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



──赤黒い世界。血に塗れた汚い世界で、私はずっと蹲っていた。
襲い掛かってくるのならば、それに触れた。触れれば全て飴玉に変わった。
それを口に入れる気力すらなくて、私の周りには飴玉がたくさん転がっていた。

私は、どうしてこんなところで蹲っているんだっけ。
光の差さない、何も動かない。時計の針も進まない。そんな場所でこうして一人で蹲って、随分時間が経った気がする。
動くものに寄り添って、呼ばれる声に振り向いたことだってあったはずなのに。
名前すら思い出せないけれど、大事な、かけがえのないものがあったはずなのに。
どうして私の手元にはそれがないんだろう。どうして私の手を誰も握ってはくれないのだろう。どうしてみんないなくなってしまうのだろう。
誰かが、手を差し伸べてくれたこともあった気がする。
この暗くて汚い世界で、自分なら大丈夫だと、手を取ろうとしてくれた人もいた気がする。
でも、その人はここにはいない。いないということは、床に散らばる飴玉の内のひとつになってしまったのだろう。
どうして、私は誰かの手を握れないのだろう。どうして、私は誰かと共に歩むことができないんだろう。
──罪は、消えない。忘れたって過去はなかったことになんてなってくれないし、時間は巻き戻ってくれない。

──なら、泥臭くて最悪な手でも、自分にできることをするしかないと思ったから。
『ねえ、いらないなら、ちょうだいよ。』
 |
???? 「ふふふ、ふふ。やーい、負けてやんの。」 |
 |
コメット 「……楽しそうだなぁ、まったく。」 |
じゃり、と砂を手で掴む。地面に倒れ伏してからしばらく意識が無かったが、どうやら命は助かったらしい。
右手の指の飴化はだいぶ進行してしまっている。……そこだけは痛みも感じなかった。
 |
コメット 「ッ、………っげほ……」 |
口から血の塊を吐き出す。……命は助かったとはいえ、受けた傷は浅くない。
顔、腕、脚には無数の切り傷や噛み痕が刻まれ、体の中には病魔が巣食っている。
抉れた脇腹から血が零れ落ち、立ち上がろうとした足が崩れ落ちそうになる。
 |
ニフリート 「おい、じっとしてろ。動くと傷が塞がらねぇ。」 |
倒れかけた体を大きな体が支えた。
周囲に大量の飴玉を浮かべて、術式を展開してくれたらしい。
 |
コメット 「あり、がとう……先代。」 |
 |
ニフリート 「こういう時に限ってそう呼ぶんじゃねぇ。お義父様でいいんだよ。」 |
咲魔式先代当主──ニフリートによる治癒はみるみるうちに体を楽にしてくれた。
普段が真面目ではないだけで、やはり彼は正当な咲魔式の継承者であるということがわかる。
質も威力も自分とは桁違いだ。自分は中途半端に異能改変を施しているから当然ではあるのだが。
 |
コメット 「……うん。ありがとう。もう立てるよ。」 |
 |
ニフリート 「ホントかよ。まだ完治しちゃいねぇぞ。」 |
 |
コメット 「知ってる。でも、いい。あまりのんびりはしていられないし。」 |
端末を取り出して、傍らの義父に振って見せる。
 |
コメット 「……言わなきゃいけないことがあるんだ。いろんな人にね。」 |
もう一度力を込め、地面を踏みしめて立つ。
大丈夫、もう歩ける。
 |
???? 「タフだなあ。」 |
 |
コメット 「どうも。」 |
 |
???? 「……全然褒めてないんだけど?はあ、呆れちゃう。」 |
 |
コメット 「そうは言いつつ、あたしの戦いに協力してくれているじゃないか。」 |
 |
???? 「勘違いしないで。お父様とお母様のためなんだから。」 |
過去の自分──正しくは、魔女に拾われることなく全てを飴玉に変えて否定の世界へ落ちた自分の姿に苦笑して歩き出す。
いったいどうしたらこうなってしまうのやら、と思いつつ、気持ちがわかる部分もある。
怒りにせよ憎しみにせよ、彼女もまた自分だけの感情を手に入れることができた。
道は違えた。自分たちの目指すところは同じでも、手段が全く違う方向へ向かってしまった。
 |
コメット 「似てないね、あたし達。」 |
 |
???? 「……そうだね。」 |
自分と彼女は、もうきっと同じ存在ではないのだから。
 |
???? 「……あのさあ、なんか負けたくせに浮かれてない? 表情が気持ち悪いんだけど。」 |
 |
コメット 「ふふふ。そうだろう。あたしは浮かれているのさ。」 |
──彗星は、『よごれた雪だるま』に例えられる。
別に、それが名前の由来じゃない。自虐的な要素はあれど、自分の名前を考えたのはおおよそ希望的な理由と意味だ。
『輝く塵』。冷たい氷が集まり、輝き、やがて燃え尽きる。
殻を作り上げて目的を果たし、いつか消える。そう望まれて『御堂翠華』から『コメット・エーデルシュタイン』は生まれた。
冷たい場所で生まれた。あたしは、それだけはよく覚えている。
温かい場所から遠くて、でもそもそも温かい場所なんて知らなかったから「冷たい」なんて感想を抱くこともなくて。
きっと自分は、望まれないで生まれた。
だから、「望まれること」を求め続けたのだろう。
『コメット・エーデルシュタイン』を作った『御堂翠華』の問題をひとつひとつ片付けて、消えるだけ。
だけどあたしは、命が惜しくなってしまって。
──彗星は、氷微惑星が惑星の引力に引かれて軌道を変えるらしい。
太陽系の内側へと向かい、やがて尾をひいて彗星へと変わる。
太陽へと進んで、一番近くにふれて、……燃え尽きて、二度と帰ってこない。
だけどあたしは──

「お前を攫う、コメット・エーデルシュタイン。着地点は、これから見つける」
「信じろ」
「娘さんを俺にください」
「俺は、俺の全力を以て、コメット・エーデルシュタインを“手に入れる”」
「いずれ胸を張ってこれは“愛”だと言える日まで。俺は彼女を手放さない」

「約束する。幸せにする」
「お前に“生きたい”と思わせた責任を取ると、誓う」
「大好きだ、コメット。……俺の、唯一」
あたしは、捕まってしまった。
燃え尽きる前に。通り過ぎる前に。
──捕まってしまった。
あの声で、名前を呼ばれて。
あの目で、見つめられて。
あの手で、握られて。
捕まってしまったら、もうただの殻には戻れないと知っていたのに。
寂しくなって、切なくなって、苦しむことなんてわかっていたのに。
その手を、取ってしまった。
未来を生きる道を選んでしまった。
御堂翠華への、義両親への裏切りに等しい。
だけど、心はもう止まらなかった。
だって、一緒に考えようと言われてしまったから。
弱音を聞いてくれと言われてしまったから。
何一つ取りこぼさずに、幸せな未来を一緒に見つけようと提示されて。
頷かないわけがなかった。
「……いつか、本土の海も見に行きたいな。浄土ヶ浜なんて、絶景で有名だし」

「……君の思い描く"いつか"を、きっと未来で観に行こう。」
"いつか"は、叶わない?
"みんなで卒業"は、できない?
どちらかしか選べない。あの場所の日常は、どの道崩れ去ってしまうだろう。
それに対して、きっと君は悩んでしまうだろうけど。
「──さあ、立って。」
「あたしは、大丈夫。」
「だから、君も大丈夫だ。」
嘘ばかりだけど、強がりばかりで、つぎはぎだらけだけど。
その『嘘』も、『強がり』だって、本物にしていこうと思ったから。
泣きそうなほど重厚な弱虫を、きっと君は笑わないだろう。
『コメット・エーデルシュタイン』とういう役を充てられて、舞台に立った。
「俺が一緒に今まで過ごしてきたのはコメット・エーデルシュタインだ」と言われて、役を張り付けられたまま舞台から下ろされた。いや、『役』だけが、舞台から引き下ろされてしまった。
それでも、舞台の上に憧れて。自分を引き下ろした彼を見上げることしかできなくて。
だから、今度は自分の意志で舞台に上がった。
手を取って、確かに握って、今度はしっかり目を合わせて。
舞台の上において客席以外を見るのはご法度だ。だけど、そんなこと今は関係ない。
幕は下りている。これから上がっていく。カーテンコールを前にして、あたしは不敵に笑うのだ。

──あたしは、大丈夫だと。



ENo.17 サクマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.55 ゆい とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.281 まさこ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.403 アミナ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.437 晴太 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.632 サフィア とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.671 海の魔物 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.824 オルトロス とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1520 "大地の不純物" とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
ヒビキ 「あれっ今回決闘なし!?」「ま、そう言う事もあるさ」 |
 |
???? 「くすくす。やーい、まけてやんの!」 |
 |
コメット 「いつつ……手ひどくやられたね。みなさん、生きてますか?」 |
 |
コメット 「死んでないだけ儲けものだけど、これがずっと続くとなると肝が冷えますね。」 |
 |
ニフリート 「凹んでる暇はねぇぞ。休んだら立て直して出発する。」 |
 |
コメット 「……あ、シュナウダーさん防具ありがとうございます。助かりま……」 |
 |
コメット 「」 |
 |
"ゴリースーツ" |
 |
まさこ 「このままゴミ掃除を続けていけば、 いつかは魔界大帝アンジニティにぶち当たるか……」 |
 |
まさこ 「まだまだ長い旅になりそうだ。 オーブとか稼ぎながら進んでいこうぜ。」 |
| シュナイダー 「良い様にやられてしまうとは……。 しかし、アンジニティ――確かに生きている。」 |
| シュナイダー 「――、――。」 |
| シュナイダー 「考えすぎてしまうのは良くありませんね。 行きましょう、皆さん。 負けはしましたが、まだ動けます。」 |
| シュナイダー 「まだ終わっていません。」 |
ItemNo.6 飴細工 を食べました!
 |
こめっと 「あーん、もったいない!食べるけど!」 |
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





ホットペッパー団
|
 |
ワクワク動物探検隊
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 2 増加!
影響力が 2 増加!



魔術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
料理LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
命術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
自然LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
装飾LV を 15 UP!(LV15⇒30、-15CP)
巽(282) の持つ ItemNo.9 花びら から装飾『レジンフラワーペンダント』を作製しました!
まさこ(281) の持つ ItemNo.8 花びら から装飾『花びらのコサージュ』を作製しました!
勇者(551) により ItemNo.8 韮 から防具『ゴリー・スーツ』を作製してもらいました!
⇒ ゴリー・スーツ/防具:強さ40/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-
| シュナイダー 「ギリースーツと呼ぶらしいですね?」 |
リーナ(1254) とカードを交換しました!
オゾン水 (アクアヒール)

フェイタルポイント を研究しました!(深度0⇒1)
リンクブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
デアデビル を研究しました!(深度0⇒1)
ブルーム を習得!
オートヒール を習得!
水の祝福 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ヒビキ(216) は 韮 を入手!
コメット(253) は 白石 を入手!
まさこ(281) は 韮 を入手!
勇者(551) は 韮 を入手!
コメット(253) は ネジ を入手!
ヒビキ(216) は 毛 を入手!
まさこ(281) は 不思議な雫 を入手!
勇者(551) は 不思議な雫 を入手!



チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調19⇒18)
採集はできませんでした。
- ヒビキ(216) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- コメット(253) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- まさこ(281) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



ワクワク動物探検隊
|
 |
卓城衛勇隊
|


ENo.253
彗星・コメット



「あたしはコメット。咲魔式の後継者でトレジャーハンターさ。」
名前:コメット・エーデルシュタイン
年齢:15歳
身長:154cm
体重:47kg
誕生日:3月9日
性別:女性
武器:銃
学ランに着物にスチームパンクという異な出で立ちの少女。飄々とした性格、まるで舞台の上に立っているかのような身振りをする。いつも近くにいる黒猫を「お義父様」「先代」と呼んでいる。
家では飴屋『ほうきぼし』を営んでおり、外にいる時も飴玉を缶に入れて持ち歩いている。店員としての性格は明るく大和撫子。
学校では優等生のような振る舞いをしている。事実頭はいい。
両親はどちらも生みの親ではないらしく、説明する時は「スラム街で捨てられたところを魔女に気まぐれ拾われた」と言っている。その気まぐれがいつ消えてもいいように、身の回りの事は全て自分で出来るようにしている。
異能:『咲魔式』飴玉↔弾丸への置換
咲魔式の戦闘方式として飴玉を弾丸として用いる。飴玉の味、素材によって様々な効果をもたらす弾丸を生成することが出来る。逆に弾丸を飴玉に変えることも出来る。
咲魔式:特殊な戦闘流派。先代はニフリート。飴玉を弾丸として用いる戦闘方法が特徴。通常の弾丸では不可能なトリッキーな戦い方ができる。コメットは咲魔式を扱える素養が異能として備わっていたらしい。
お店→http://lisge.com/ib/talk.php?p=386
全身図→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=comet.png
店員→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=coshop.png
「俺の娘だ。すごくねえわけねぇだろが。」
名前:ニフリート
性別:オス
コメットのそばにいつもいる黒猫。コメットには「お義父様」と呼ばれている。咲魔式の先代当主だったが、跡継ぎを残せぬまま老衰。死ぬ寸前に魔女と契約し、跡継ぎを探す旅を続けていた。姿を猫に変えられてしまっているためか言動もかなり猫。声が渋い。
「お母様、お父様……必ず元に戻します」
偽名:コメット・エーデルシュタイン
本名:御堂翠華(みどう すいか)
御堂家とはイバラシティに存在した名家である。
古くから呉服屋を営むその家に翠華は一人娘として生まれた。
礼儀作法を教えこまえ、両親に蝶よ花よと育てられた彼女は自らの異能も知らないまま無垢で純粋に育つ。
誰かの役に立ちたい、いつか家をつぐものとして恥ずかしくない者でありたいと思っていたところに魔女と黒猫から咲魔式を継いで欲しいと持ちかけられる。
自らの異能が誰かの役に立つならば、と彼女はその願いを了承し、その旨を親に話しに行った。
正しい異能:『夢幻泡飴』触れたものを飴玉に変える異能
彼女は両親の手を握った。自分をまっすぐに見つめる瞳が美しいと思った。
いつまでも、近くで眺めていたかった。
気づいたら、両親の姿はなかった。両親は娘の異能によって飴玉に変えられてしまったのだ。
未だにコメットの異能は制御できておらず、魔女と黒猫によっていくつものロックがかけられている。
コメットは両親を元に戻すため、翠華としての自分を閉じ込めて黒猫ニフリートに異能の制御を教わっている。
ハザマにおいて、コメットの体は少しずつ飴に置換されていく。
名前:コメット・エーデルシュタイン
年齢:15歳
身長:154cm
体重:47kg
誕生日:3月9日
性別:女性
武器:銃
学ランに着物にスチームパンクという異な出で立ちの少女。飄々とした性格、まるで舞台の上に立っているかのような身振りをする。いつも近くにいる黒猫を「お義父様」「先代」と呼んでいる。
家では飴屋『ほうきぼし』を営んでおり、外にいる時も飴玉を缶に入れて持ち歩いている。店員としての性格は明るく大和撫子。
学校では優等生のような振る舞いをしている。事実頭はいい。
両親はどちらも生みの親ではないらしく、説明する時は「スラム街で捨てられたところを魔女に気まぐれ拾われた」と言っている。その気まぐれがいつ消えてもいいように、身の回りの事は全て自分で出来るようにしている。
異能:『咲魔式』飴玉↔弾丸への置換
咲魔式の戦闘方式として飴玉を弾丸として用いる。飴玉の味、素材によって様々な効果をもたらす弾丸を生成することが出来る。逆に弾丸を飴玉に変えることも出来る。
咲魔式:特殊な戦闘流派。先代はニフリート。飴玉を弾丸として用いる戦闘方法が特徴。通常の弾丸では不可能なトリッキーな戦い方ができる。コメットは咲魔式を扱える素養が異能として備わっていたらしい。
お店→http://lisge.com/ib/talk.php?p=386
全身図→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=comet.png
店員→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=coshop.png
「俺の娘だ。すごくねえわけねぇだろが。」
名前:ニフリート
性別:オス
コメットのそばにいつもいる黒猫。コメットには「お義父様」と呼ばれている。咲魔式の先代当主だったが、跡継ぎを残せぬまま老衰。死ぬ寸前に魔女と契約し、跡継ぎを探す旅を続けていた。姿を猫に変えられてしまっているためか言動もかなり猫。声が渋い。
「お母様、お父様……必ず元に戻します」
偽名:コメット・エーデルシュタイン
本名:御堂翠華(みどう すいか)
御堂家とはイバラシティに存在した名家である。
古くから呉服屋を営むその家に翠華は一人娘として生まれた。
礼儀作法を教えこまえ、両親に蝶よ花よと育てられた彼女は自らの異能も知らないまま無垢で純粋に育つ。
誰かの役に立ちたい、いつか家をつぐものとして恥ずかしくない者でありたいと思っていたところに魔女と黒猫から咲魔式を継いで欲しいと持ちかけられる。
自らの異能が誰かの役に立つならば、と彼女はその願いを了承し、その旨を親に話しに行った。
正しい異能:『夢幻泡飴』触れたものを飴玉に変える異能
彼女は両親の手を握った。自分をまっすぐに見つめる瞳が美しいと思った。
いつまでも、近くで眺めていたかった。
気づいたら、両親の姿はなかった。両親は娘の異能によって飴玉に変えられてしまったのだ。
未だにコメットの異能は制御できておらず、魔女と黒猫によっていくつものロックがかけられている。
コメットは両親を元に戻すため、翠華としての自分を閉じ込めて黒猫ニフリートに異能の制御を教わっている。
ハザマにおいて、コメットの体は少しずつ飴に置換されていく。
18 / 30
70 PS
チナミ区
H-13
H-13




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | タッセルイヤリング | 装飾 | 20 | 体力10 | - | - | |
| 5 | キャノンドロップス | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 7 | 携行食 | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | ゴリー・スーツ | 防具 | 40 | 体力10 | - | - | |
| 9 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV25)[防具]強靭10(LV20)[装飾]耐狂10(LV20) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 11 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 装飾 | 30 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 咲魔式:林檎 (ティンダー) | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| 咲魔式:蜜柑 (ウォーターフォール) | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 咲魔式:小豆 (ストーンブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| 咲魔式:サイダー (ヒールポーション) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| 咲魔式:苺 (カームフレア) | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| 咲魔式:檸檬 (レッドアゲート) | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| 夢幻泡飴 (フィーバー) | 6 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |
| 咲魔式:ハッカ (リフレッシュ) | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| 咲魔式:パイン (アクアリカバー) | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| 咲魔式:ココア (ヒールハーブ) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| 咲魔式:葡萄 (アクアヒール) | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 魔女の祝福 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 咲魔式:ガナッシュ (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 咲魔式:装填 (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]デアデビル | [ 2 ]カームフレア | [ 1 ]ファイアボルト |
| [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]ダークネス | [ 1 ]ビブラート |
| [ 1 ]フェイタルポイント | [ 1 ]リンクブレイク |

PL / アルス