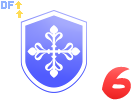<< 2:00>> 4:00




しばらくの間、リオネル・サンドリヨンは自宅で無意味に怒られる日々が続く。それは父が次の仕事を見つけた後、両親が喧嘩をする理由が無くなった後も変わらなかった。リオネル・サンドリヨンもそのころには『不幸』を『喰らう』ようなことはやめていたが、それでも理不尽に怒られ続けた。リオネル・サンドリヨンが力を使い続けた結果、何もしていなくとも「リオネルを見ていると反射的に怒りが沸き起こる」ようになってしまった。
そんなリオネル・サンドリヨンにとっての心の支えは友人であった。当時、リオネル・サンドリヨンの友人といえばたったひとりしかいなかった。
その友人はいつも人に囲まれているように見えた。
その友人は勉強も運動もクラスで一番得意だった。
その友人はいつも自信満々な立ち振る舞いをしていた。
その友人はリオネル・サンドリヨンにとって憧れでもあった。彼は自分が持っていないものを持っているように見えていたのだ。
リオネル・サンドリヨンは学校に行く時と学校から帰る時、必ずと言っていいほど その友人と一緒に帰った。概ね友人が喋り、リオネル・サンドリヨンは話を聞くだけだった。
「学校の勉強は簡単すぎてつまらない」
「クラスの皆と話していてもつまらない」
「楽しいのはリオと話してる時だけ」
そういった話が殆どだった。当時のリオネル・サンドリヨンは、憧れの友人に認められたような気がして誇らしく思っていた。当時は唯一の救いであったと表現しても過言ではない。
その出来事が起きたのは、小学校4年生になったばかりの頃。クラス替えが行われたが、リオネル・サンドリヨンは友人と同じクラスになった。
友人は誰にも話しかけられなくなり。
友人よりも勉強 あるいは運動が出来る者も現れ。
友人は俯いて過ごすようになった。
それでもリオネル・サンドリヨンは相変わらず、友人と一緒に過ごした。学校に行くときも、学校から帰る時も。状況が変わってもリオネル・サンドリヨンにとって憧れの友人であることに変わりはなく、友人から離れる理由は何一つなかった。
その友人が人に囲まれていたのは、幼稚園の頃からの知り合いがたまたまクラスに多かったから。
その友人は確かに勉強も運動も得意であったが、だからこそ努力をせずに少しずつ追い抜かれた。
そんな事情もつゆ知らず、リオネル・サンドリヨンは友人が孤独を覚えているのではないかと『認識』して、それ自体は間違いでなかった。
友人にとっては耐えがたいことだろうと考えた。自分が同じ立場だったとしても、あまり良い気はしない。良い気はしないが、自分ならば耐えられる。リオネル・サンドリヨンはそう感じた。
リオネル・サンドリヨンはどうやら他の誰かに使えない力があるらしいと既に自覚していた。だから、自分が代わりに引き受けよう、と。リオネル・サンドリヨンは考えたのだ。以前と違う使い方だった。発動する補償はなかったが、しかしリオネル・サンドリヨンが『孤独を喰らう』と願えば、あの時と同じ蜂蜜に似た甘い味がした。
次の日から、リオネル・サンドリヨンがクラスメイトから話しかけられなくなった。リオネル・サンドリヨンは、普段と殆ど変わらない日々を過ごすことになる。
殆ど、というのは。
その元友人からも、無視されるようになったから。
リオネル・サンドリヨンの力が意図せぬ形で発動したのか、或いは単に友好感情が実は一方的であったのか、当時は区別がついていなかった。実際のところ、リオネル・サンドリヨンに『運が無くて』唯一の友人の本質に気づくことが出来なかったという、それだけの話である。かつての友人は、ただ自分の話を黙って聞いてくれる都合のいい存在しか必要としていなかった。リオネル・サンドリヨンは間違いなくそれに当てはまる存在であったが、独りであったときに話しかけられることで、酷く惨めな思いをした。そしてリオネル・サンドリヨンによる『孤独喰らい』履行後、リオネル・サンドリヨン以外に都合のいい存在が見つかった。だからリオネル・サンドリヨンとの交友関係が捨てられた。
そんな事情は現在のリオネル・サンドリヨンにすら把握できていない。
それでも、それでよかったのだと、リオネル・サンドリヨンは自らに言い聞かせた。
理由は分からないが自分はかつての友人にとって気に食わない存在になったのだろうと。
それが彼の願いであれば、それは尊ぶべきだろうと。
本当は誰かと共に在りたかったのに。本当は、独りになりたくないのに。
独りは、苦しくて、寒くて、苦手だ。



ENo.300 禍根 とのやりとり

ENo.410 都月桐胡 とのやりとり

ENo.505 《夜明け》と《黄昏》 とのやりとり

ENo.524 赤錆 鉄郎 とのやりとり

ENo.558 白大甕 環 とのやりとり

ENo.683 東堂玄樹 とのやりとり

ENo.687 加唐揚羽/肉盛薔薇/気津根仕郎 とのやりとり

ENo.1346 チサキ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 アーティチョークのアジフライ定食 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









禍根(300) は 吸い殻 を入手!
四ツ谷幽綺(448) は パンの耳 を入手!
とぐる(567) は パンの耳 を入手!
不幸喰らい(569) は 吸い殻 を入手!
四ツ谷幽綺(448) は 毛 を入手!
とぐる(567) は 不思議な雫 を入手!
不幸喰らい(569) は 毛 を入手!
四ツ谷幽綺(448) は 毛 を入手!



道端ガムマン をエイドとして招き入れました!
制約LV を 3 UP!(LV3⇒6、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
ミツフネ(940) の持つ ItemNo.8 吸い殻 から防具『透明な篭手』を作製しました!
みぅ(696) とカードを交換しました!
荊街八景 (イレイザー)


エスコート を研究しました!(深度1⇒2)
テリトリー を研究しました!(深度1⇒2)
オフェンシブ を研究しました!(深度1⇒2)
リストリクト を習得!
オフェンシブ を習得!
サンクタム を習得!



チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――














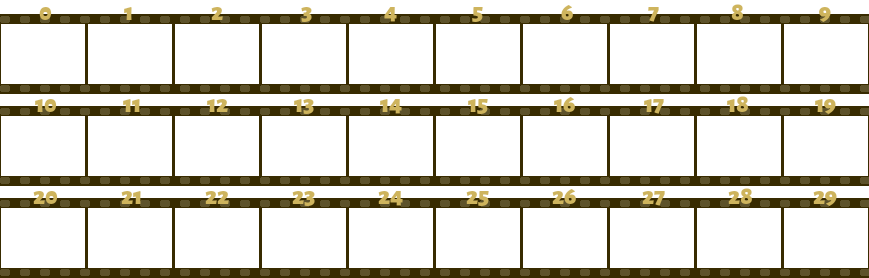


































No.1 道端ガムマン (種族:道端ガムマン)






異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



しばらくの間、リオネル・サンドリヨンは自宅で無意味に怒られる日々が続く。それは父が次の仕事を見つけた後、両親が喧嘩をする理由が無くなった後も変わらなかった。リオネル・サンドリヨンもそのころには『不幸』を『喰らう』ようなことはやめていたが、それでも理不尽に怒られ続けた。リオネル・サンドリヨンが力を使い続けた結果、何もしていなくとも「リオネルを見ていると反射的に怒りが沸き起こる」ようになってしまった。
そんなリオネル・サンドリヨンにとっての心の支えは友人であった。当時、リオネル・サンドリヨンの友人といえばたったひとりしかいなかった。
その友人はいつも人に囲まれているように見えた。
その友人は勉強も運動もクラスで一番得意だった。
その友人はいつも自信満々な立ち振る舞いをしていた。
その友人はリオネル・サンドリヨンにとって憧れでもあった。彼は自分が持っていないものを持っているように見えていたのだ。
リオネル・サンドリヨンは学校に行く時と学校から帰る時、必ずと言っていいほど その友人と一緒に帰った。概ね友人が喋り、リオネル・サンドリヨンは話を聞くだけだった。
「学校の勉強は簡単すぎてつまらない」
「クラスの皆と話していてもつまらない」
「楽しいのはリオと話してる時だけ」
そういった話が殆どだった。当時のリオネル・サンドリヨンは、憧れの友人に認められたような気がして誇らしく思っていた。当時は唯一の救いであったと表現しても過言ではない。
その出来事が起きたのは、小学校4年生になったばかりの頃。クラス替えが行われたが、リオネル・サンドリヨンは友人と同じクラスになった。
友人は誰にも話しかけられなくなり。
友人よりも勉強 あるいは運動が出来る者も現れ。
友人は俯いて過ごすようになった。
それでもリオネル・サンドリヨンは相変わらず、友人と一緒に過ごした。学校に行くときも、学校から帰る時も。状況が変わってもリオネル・サンドリヨンにとって憧れの友人であることに変わりはなく、友人から離れる理由は何一つなかった。
その友人が人に囲まれていたのは、幼稚園の頃からの知り合いがたまたまクラスに多かったから。
その友人は確かに勉強も運動も得意であったが、だからこそ努力をせずに少しずつ追い抜かれた。
そんな事情もつゆ知らず、リオネル・サンドリヨンは友人が孤独を覚えているのではないかと『認識』して、それ自体は間違いでなかった。
友人にとっては耐えがたいことだろうと考えた。自分が同じ立場だったとしても、あまり良い気はしない。良い気はしないが、自分ならば耐えられる。リオネル・サンドリヨンはそう感じた。
リオネル・サンドリヨンはどうやら他の誰かに使えない力があるらしいと既に自覚していた。だから、自分が代わりに引き受けよう、と。リオネル・サンドリヨンは考えたのだ。以前と違う使い方だった。発動する補償はなかったが、しかしリオネル・サンドリヨンが『孤独を喰らう』と願えば、あの時と同じ蜂蜜に似た甘い味がした。
次の日から、リオネル・サンドリヨンがクラスメイトから話しかけられなくなった。リオネル・サンドリヨンは、普段と殆ど変わらない日々を過ごすことになる。
殆ど、というのは。
その元友人からも、無視されるようになったから。
リオネル・サンドリヨンの力が意図せぬ形で発動したのか、或いは単に友好感情が実は一方的であったのか、当時は区別がついていなかった。実際のところ、リオネル・サンドリヨンに『運が無くて』唯一の友人の本質に気づくことが出来なかったという、それだけの話である。かつての友人は、ただ自分の話を黙って聞いてくれる都合のいい存在しか必要としていなかった。リオネル・サンドリヨンは間違いなくそれに当てはまる存在であったが、独りであったときに話しかけられることで、酷く惨めな思いをした。そしてリオネル・サンドリヨンによる『孤独喰らい』履行後、リオネル・サンドリヨン以外に都合のいい存在が見つかった。だからリオネル・サンドリヨンとの交友関係が捨てられた。
そんな事情は現在のリオネル・サンドリヨンにすら把握できていない。
それでも、それでよかったのだと、リオネル・サンドリヨンは自らに言い聞かせた。
理由は分からないが自分はかつての友人にとって気に食わない存在になったのだろうと。
それが彼の願いであれば、それは尊ぶべきだろうと。



ENo.300 禍根 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.410 都月桐胡 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.505 《夜明け》と《黄昏》 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.524 赤錆 鉄郎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.558 白大甕 環 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.683 東堂玄樹 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.687 加唐揚羽/肉盛薔薇/気津根仕郎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1346 チサキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
竜が見つめるのは、もうひとりの自分が働く場所で出している料理。 なぜ禍根がこれを。そんな疑問もあったが、それよりも。 「禍根、前もって伝えていなくてすまない。 オレは件の力で他者の不幸を喰らう。力の発動が食事を兼ねる。 つまりは人間と同じものを食すことが出来ない」 この少々特殊な食性で困ることがあるとは思わなかった。 「……定期的に負傷の度合を申告してほしい。 それをオレが引き受ければ、それがオレにとっての食事になる」 だそうだ。 それはそれとして今回は普通に食事を使用する。深く考えてはいけない。 |
ItemNo.7 アーティチョークのアジフライ定食 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





はぐれものの狼煙
|
 |
創藍オカルト研究部
|



禍根(300) は 吸い殻 を入手!
四ツ谷幽綺(448) は パンの耳 を入手!
とぐる(567) は パンの耳 を入手!
不幸喰らい(569) は 吸い殻 を入手!
四ツ谷幽綺(448) は 毛 を入手!
とぐる(567) は 不思議な雫 を入手!
不幸喰らい(569) は 毛 を入手!
四ツ谷幽綺(448) は 毛 を入手!



道端ガムマン をエイドとして招き入れました!
制約LV を 3 UP!(LV3⇒6、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
ミツフネ(940) の持つ ItemNo.8 吸い殻 から防具『透明な篭手』を作製しました!
みぅ(696) とカードを交換しました!
荊街八景 (イレイザー)


エスコート を研究しました!(深度1⇒2)
テリトリー を研究しました!(深度1⇒2)
オフェンシブ を研究しました!(深度1⇒2)
リストリクト を習得!
オフェンシブ を習得!
サンクタム を習得!



チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――





ENo.569
リオネル・サンドリヨン



虚無アイコン(Eno.38)とデフォルメアイコン(Eno.158)は頂き物です。感謝!
リオネル・サンドリヨン(Lionel・Cendrillon)
相良伊橋高校2年4組
195cm 91Kg 11月6日生まれ
性別:男
髪:夕焼け色、ハーフアップ
目:銀色
他の特徴:そばかす
こんな見た目だが母国語は日本語である。得意科目も現代文である。英語とフランス語の日常会話が可能。
好きな科目は世界史と体育。苦手な科目は数学。嫌いな科目は英語(成績はなかなか)。ド文系。
将来の夢とか進路とかは未定。焦る。とりあえず進学してそこから先は後で考えることにしている。
性格はだいぶ真面目な方。気性穏やかで、臆病な本質ゆえに争いごとは得意ではない。それでも、仲間が傍にいるのであればいかなる窮地でも共に在ろうとし、仲間が貶められることがあれば相応に激昂し、仲間に危機が迫れば周りを驚かせるような行動に出ることもある。
過去に色々あったようで、どちらかというと抱え込みやすい気質。しかし、色々な人との出会いを経て、少しずつ改めようとしている。
コーポロザ301号室で暮らしている。
【http://lisge.com/ib/talk.php?p=226】
ソロール(場所設定はまちまち)
【http://lisge.com/ib/talk.php?p=734】
どうやらバイトをしているらしい。【http://lisge.com/ib/talk.php?s=140】
カラミティ イーター
異能≪不幸喰らい≫
・誰かの代わりに『不幸』を引き受けることができる。
・発動のためには、その『不幸』を何らかの形で認識する必要があり、彼の認識と実情に齟齬があると発動が不完全になる。
・異能が発動した際『蜜のような味』がする。異能の使用後、食欲が失せることもある。
・異能『所持』の代償で不幸体質になっている。異能『使用』の代償で、不幸が悪化する。それは誰かの代わりに受けた『不幸』とまた別である。
彼の正体はアンジニティの咎人である。アンジニティとしての姿は人にあらず、『四肢に鎖をつけ、体内に瘴気を宿した硝子の竜』のような出で立ちをしている。
その力を使うことで、病を、傷を、痛みを、怒りを、悲しみを、時には争いそのものを『喰らい』腹を満たす化け物。
争いごとがあるたびに近寄ってくることから、災厄の象徴のような扱いを受けているかもしれない。
『不幸を喰らう』際には腹を満たすだけでなく、その不幸を硝子の竜が引き受けているというのに。
嘗て何らかの『シメイ』を賜り、侵略を阻止することもまたその延長線上にあると考えた硝子の竜。同時にそれがエゴであるということも認識している。
時折、傷を『喰らう』という形でイバラシティに与する者の治療を行う姿が見られるかもしれない。自らの姿が人間から見て異質であると自覚し、守ると決めた者たちから敵対されることを覚悟を決めて。
【アンジ体イラストはEno.152PL様より有償にて依頼しました!ありがとうございます!】
リオネル・サンドリヨン(Lionel・Cendrillon)
相良伊橋高校2年4組
195cm 91Kg 11月6日生まれ
性別:男
髪:夕焼け色、ハーフアップ
目:銀色
他の特徴:そばかす
こんな見た目だが母国語は日本語である。得意科目も現代文である。英語とフランス語の日常会話が可能。
好きな科目は世界史と体育。苦手な科目は数学。嫌いな科目は英語(成績はなかなか)。ド文系。
将来の夢とか進路とかは未定。焦る。とりあえず進学してそこから先は後で考えることにしている。
性格はだいぶ真面目な方。気性穏やかで、臆病な本質ゆえに争いごとは得意ではない。それでも、仲間が傍にいるのであればいかなる窮地でも共に在ろうとし、仲間が貶められることがあれば相応に激昂し、仲間に危機が迫れば周りを驚かせるような行動に出ることもある。
過去に色々あったようで、どちらかというと抱え込みやすい気質。しかし、色々な人との出会いを経て、少しずつ改めようとしている。
コーポロザ301号室で暮らしている。
【http://lisge.com/ib/talk.php?p=226】
ソロール(場所設定はまちまち)
【http://lisge.com/ib/talk.php?p=734】
どうやらバイトをしているらしい。【http://lisge.com/ib/talk.php?s=140】
カラミティ イーター
異能≪不幸喰らい≫
・誰かの代わりに『不幸』を引き受けることができる。
・発動のためには、その『不幸』を何らかの形で認識する必要があり、彼の認識と実情に齟齬があると発動が不完全になる。
・異能が発動した際『蜜のような味』がする。異能の使用後、食欲が失せることもある。
・異能『所持』の代償で不幸体質になっている。異能『使用』の代償で、不幸が悪化する。それは誰かの代わりに受けた『不幸』とまた別である。
彼の正体はアンジニティの咎人である。アンジニティとしての姿は人にあらず、『四肢に鎖をつけ、体内に瘴気を宿した硝子の竜』のような出で立ちをしている。
その力を使うことで、病を、傷を、痛みを、怒りを、悲しみを、時には争いそのものを『喰らい』腹を満たす化け物。
争いごとがあるたびに近寄ってくることから、災厄の象徴のような扱いを受けているかもしれない。
『不幸を喰らう』際には腹を満たすだけでなく、その不幸を硝子の竜が引き受けているというのに。
嘗て何らかの『シメイ』を賜り、侵略を阻止することもまたその延長線上にあると考えた硝子の竜。同時にそれがエゴであるということも認識している。
時折、傷を『喰らう』という形でイバラシティに与する者の治療を行う姿が見られるかもしれない。自らの姿が人間から見て異質であると自覚し、守ると決めた者たちから敵対されることを覚悟を決めて。
【アンジ体イラストはEno.152PL様より有償にて依頼しました!ありがとうございます!】
16 / 30
102 PS
チナミ区
K-14
K-14



































No.1 道端ガムマン (種族:道端ガムマン)
 |
|
|
||||||||||||



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 頑強の枷 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 5 | Calamity | 武器 | 20 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) | |||
| 9 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 6 | 拘束/罠/リスク |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 防具 | 26 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 色無き爪 (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 色無き牙 (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 色無き角 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 色無き尾 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| 苦痛喰らい (ヒール) | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 遠い記憶、嘗ての役目 (エキサイト) | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| 竜の翼、硝子の盾 (プロテクション) | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| オフェンシブ | 5 | 0 | 80 | 自:AT増+AG減 | |
| 硝子の竜の逆鱗は如何に (スパイン) | 5 | 0 | 110 | 自:反撃LV増 | |
| サンクタム | 5 | 0 | 60 | 味全:守護+祝福状態なら更に守護 | |
| 『守護者』は刃を降ろす (イレイザー) | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 | |
| 畏怖喰らい (テリトリー) | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |
| 矛先喰らい (エスコート) | 6 | 0 | 80 | 自:次受ダメ減+味列:護衛 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 其は堕した■■ (攻撃) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 其は嘗てのシメイ (防御) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 其は灰被る国に非ざる物 (器用) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 其は臆病者の勇気 (敏捷) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 其は嘗ての存在意義 (回復) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 其は調和竜の呪縛 (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 其は嘗ての願い (体力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 其は調和竜の詛呪 (治癒) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 其は調和竜の呪詛 (鎮痛) | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 其は力の対価 (幸運) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]プロテクション | [ 2 ]オフェンシブ |
| [ 1 ]スパイン | [ 2 ]テリトリー | [ 2 ]エスコート |

PL / logi_minamo