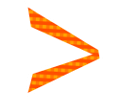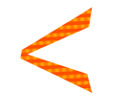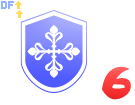<< 1:00>> 3:00




それは遠い過去の話。
リオネル・サンドリヨンが記憶している限り、異能を使えるようになったのは小学2年生の頃であった。
それまでは自身が異能を持っていることなど気づきもせず、家族のどちらも異能と呼ばれるものが実在しているなどとは思いもせず。異国由来の血筋ゆえに少々目立ちやすい以外は、ごく普通の暮らしをしていた。
テストで100点を取れば、母に沢山褒められた。
分からない問題があれば、父に何度も教えてもらった。
出来ないことが新たに出来るようになるたびに、自分のことのように喜んでもらった。
まだ子供だったリオネル・サンドリヨンは、根拠もなく、そんな暖かい日々が続くと思っていた。きっとリオネル・サンドリヨンの両親もまた同じだったのだろう。
その年の冬が訪れるまでは。
それはある日の夜半。リオネル・サンドリヨンは何かの音で目が覚めた。臆病な気質であった彼だが、それを目の当たりにする直前まで恐怖は感じていなかった。なぜなら、その物音の正体は事件性が高いものではなく。
実の両親が喧嘩する声、テーブルをたたく音であったから。
それは客観的に見れば事件でも何でもない。大人がその喧嘩の内容を聞けば、確かに真剣に話す必要のある内容であった。父の会社が倒産し、この先の行く末を決める相談であったから。熱が入ることも、頷けることである。
しかし、まだ子供といえる年齢であったリオネル・サンドリヨンにとっては恐ろしい光景に思われた。家族がこのように言い争っているところを、見たことが無かった。それがますます恐怖に拍車をかけた。
『不幸にも』リオネル・サンドリヨンは穏やかかつ臆病な気質を持っていた。だからこそ、今繰り広げられている光景が永遠に続いてしまいそうに思えた。
『不幸にも』リオネル・サンドリヨンは心の底から両親の幸せを願って、そして今の光景を『不幸』と認識した。
『不幸にも』リオネル・サンドリヨンは、自身の幸せと大事な者の幸せが直結するような考え方をしていた。そんなリオネル・サンドリヨンが咄嗟に願ったのは。
――おこるなら、オレをおこって。
願って間もなく、口内に 蜂蜜に似た甘い甘い味が広がっていった。
それとほぼ同時に両親はリオネル・サンドリヨンの存在に気づいた。詰め寄ったのは母の方だ。
明日も学校。どうしてこんな時間まで起きている。これ以上面倒ごとを増やさないで。……。
それは客観的に見て八つ当たりであった。それでも、リオネル・サンドリヨンは。父さんと母さんが喧嘩をやめた。そう認識して、満足した。以降も同じ案件での喧嘩が続き、そのたびにリオネル・サンドリヨンはその『怒りの矛先』を『喰らった』。それはリオネル・サンドリヨンが小学校3年生の夏休み手前まで続くことになる。
リオネル・サンドリヨンが止めようとしたこの『喧嘩』は、一家の行く末の相談でもあった。その相談のたびにリオネル・サンドリヨンがそれを中断させた形になった。少し成長してからそのことに気づくのだが、この時はまだ気づけない。幼いリオネル・サンドリヨンは、自分の一番の望みを投げ打って、二番目の望みを叶えたと思っていた。
家族の幸せこそが自分の幸せ。
本当は、自分も一緒に幸せになりたかった。



ENo.38 稚環 輪 とのやりとり

ENo.300 禍根 とのやりとり

ENo.413 伊上 司 とのやりとり

ENo.448 四ツ谷幽綺&折和アイネ とのやりとり

ENo.567 半転 とぐる とのやりとり

以下の相手に送信しました














禍根(300) は 吸い殻 を入手!
四ツ谷幽綺(448) は 美味しくない草 を入手!
とぐる(567) は 美味しくない草 を入手!
不幸喰らい(569) は パンの耳 を入手!
とぐる(567) は 不思議な石 を入手!
禍根(300) は ねばねば を入手!
禍根(300) は ねばねば を入手!
とぐる(567) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
禍根(300) のもとに ヤンキー が微笑を浮かべて近づいてきます。



制約LV を 3 UP!(LV0⇒3、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
禍根(300) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『アーティチョークのアジフライ定食』をつくってもらいました!
⇒ アーティチョークのアジフライ定食/料理:強さ29/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
スミレ(165) とカードを交換しました!
慈悲深き銀弾の十字架 (ワイドアナライズ)

プロテクション を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
オフェンシブ を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-8(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-10(道路)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















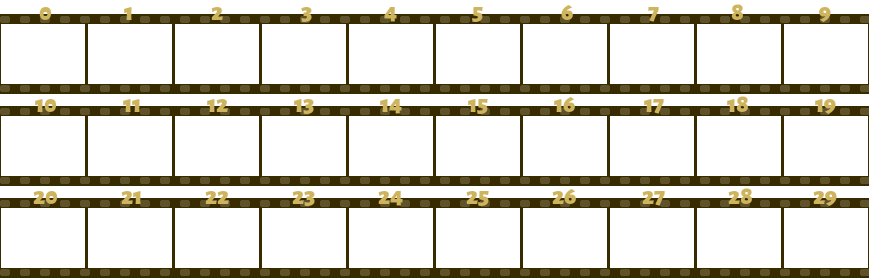





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



それは遠い過去の話。
リオネル・サンドリヨンが記憶している限り、異能を使えるようになったのは小学2年生の頃であった。
それまでは自身が異能を持っていることなど気づきもせず、家族のどちらも異能と呼ばれるものが実在しているなどとは思いもせず。異国由来の血筋ゆえに少々目立ちやすい以外は、ごく普通の暮らしをしていた。
テストで100点を取れば、母に沢山褒められた。
分からない問題があれば、父に何度も教えてもらった。
出来ないことが新たに出来るようになるたびに、自分のことのように喜んでもらった。
まだ子供だったリオネル・サンドリヨンは、根拠もなく、そんな暖かい日々が続くと思っていた。きっとリオネル・サンドリヨンの両親もまた同じだったのだろう。
その年の冬が訪れるまでは。
それはある日の夜半。リオネル・サンドリヨンは何かの音で目が覚めた。臆病な気質であった彼だが、それを目の当たりにする直前まで恐怖は感じていなかった。なぜなら、その物音の正体は事件性が高いものではなく。
実の両親が喧嘩する声、テーブルをたたく音であったから。
それは客観的に見れば事件でも何でもない。大人がその喧嘩の内容を聞けば、確かに真剣に話す必要のある内容であった。父の会社が倒産し、この先の行く末を決める相談であったから。熱が入ることも、頷けることである。
しかし、まだ子供といえる年齢であったリオネル・サンドリヨンにとっては恐ろしい光景に思われた。家族がこのように言い争っているところを、見たことが無かった。それがますます恐怖に拍車をかけた。
『不幸にも』リオネル・サンドリヨンは穏やかかつ臆病な気質を持っていた。だからこそ、今繰り広げられている光景が永遠に続いてしまいそうに思えた。
『不幸にも』リオネル・サンドリヨンは心の底から両親の幸せを願って、そして今の光景を『不幸』と認識した。
『不幸にも』リオネル・サンドリヨンは、自身の幸せと大事な者の幸せが直結するような考え方をしていた。そんなリオネル・サンドリヨンが咄嗟に願ったのは。
――おこるなら、オレをおこって。
願って間もなく、口内に 蜂蜜に似た甘い甘い味が広がっていった。
それとほぼ同時に両親はリオネル・サンドリヨンの存在に気づいた。詰め寄ったのは母の方だ。
明日も学校。どうしてこんな時間まで起きている。これ以上面倒ごとを増やさないで。……。
それは客観的に見て八つ当たりであった。それでも、リオネル・サンドリヨンは。父さんと母さんが喧嘩をやめた。そう認識して、満足した。以降も同じ案件での喧嘩が続き、そのたびにリオネル・サンドリヨンはその『怒りの矛先』を『喰らった』。それはリオネル・サンドリヨンが小学校3年生の夏休み手前まで続くことになる。
リオネル・サンドリヨンが止めようとしたこの『喧嘩』は、一家の行く末の相談でもあった。その相談のたびにリオネル・サンドリヨンがそれを中断させた形になった。少し成長してからそのことに気づくのだが、この時はまだ気づけない。幼いリオネル・サンドリヨンは、自分の一番の望みを投げ打って、二番目の望みを叶えたと思っていた。
家族の幸せこそが自分の幸せ。



ENo.38 稚環 輪 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.300 禍根 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.413 伊上 司 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.448 四ツ谷幽綺&折和アイネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.567 半転 とぐる とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
硝子の竜は、静かに面々を眺めている。胸に嵌った宝石の色が青く沈んだ。 |



はぐれものの狼煙
|
 |
ハザマに生きるもの
|



狂人共の行軍記
|
 |
はぐれものの狼煙
|



禍根(300) は 吸い殻 を入手!
四ツ谷幽綺(448) は 美味しくない草 を入手!
とぐる(567) は 美味しくない草 を入手!
不幸喰らい(569) は パンの耳 を入手!
とぐる(567) は 不思議な石 を入手!
禍根(300) は ねばねば を入手!
禍根(300) は ねばねば を入手!
とぐる(567) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
禍根(300) のもとに ヤンキー が微笑を浮かべて近づいてきます。



制約LV を 3 UP!(LV0⇒3、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
禍根(300) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『アーティチョークのアジフライ定食』をつくってもらいました!
⇒ アーティチョークのアジフライ定食/料理:強さ29/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
| 禍根 「竜種の好みは分かりませんので、まずは通常生体の好ましいものとしての料理を作製しました、マスター。忌憚なき意見を述べてくれると助かります。」 |
スミレ(165) とカードを交換しました!
慈悲深き銀弾の十字架 (ワイドアナライズ)

プロテクション を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
オフェンシブ を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 I-8(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-10(道路)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――







はぐれものの狼煙
|
 |
はいずるものたち
|


ENo.569
リオネル・サンドリヨン



虚無アイコン(Eno.38)とデフォルメアイコン(Eno.158)は頂き物です。感謝!
リオネル・サンドリヨン(Lionel・Cendrillon)
相良伊橋高校2年4組
195cm 91Kg 11月6日生まれ
性別:男
髪:夕焼け色、ハーフアップ
目:銀色
他の特徴:そばかす
こんな見た目だが母国語は日本語である。得意科目も現代文である。英語とフランス語の日常会話が可能。
好きな科目は世界史と体育。苦手な科目は数学。嫌いな科目は英語(成績はなかなか)。ド文系。
将来の夢とか進路とかは未定。焦る。とりあえず進学してそこから先は後で考えることにしている。
性格はだいぶ真面目な方だが、程々に緩くを心掛ける。気質は穏やかで争いごとは得意ではない。それでも、仲間が傍にいるのであればいかなる窮地でも共に在ろうとし、仲間に危機が迫れば周りを驚かせるような行動に出ることもある。それを一種の狂気と受け取るか勇気と受け取るかは、人によって異なるだろう。
過去に色々あったようで、どちらかというと抱え込みやすい気質。しかし、色々な人との出会いを経て、少しずつ改めようとしている。
コーポロザ301号室で暮らしている。
【http://lisge.com/ib/talk.php?p=226】
ソロール(場所設定はまちまち)
【http://lisge.com/ib/talk.php?p=734】
どうやらバイトをしているらしい。【http://lisge.com/ib/talk.php?s=140】
カラミティ イーター
異能≪不幸喰らい≫
・誰かの代わりに『不幸』を引き受けることができる。
・発動のためには、その『不幸』を何らかの形で認識する必要があり、彼の認識と実情に齟齬があると発動が不完全になる。
・異能が発動した際『蜜のような味』がする。異能の使用後、食欲が失せることもある。
・異能『所持』の代償で不幸体質になっている。異能『使用』の代償で、不幸が悪化する。それは誰かの代わりに受けた『不幸』とまた別である。
彼はイバラシティに加担するが、その正体はアンジニティの咎人である。アンジニティとしての姿は人にあらず、『四肢に鎖をつけ、体内に瘴気を宿した硝子の竜』のような出で立ちをしている。
その力を使うことで、病を、傷を、痛みを、怒りを、悲しみを、時には争いそのものを『喰らい』腹を満たす化け物。
争いごとがあるたびに近寄ってくることから、災いの象徴のような扱いを受けているかもしれない。
『不幸を喰らう』際には腹を満たすだけでなく、その不幸を硝子の竜が引き受けているというのに。
どういうわけか侵略を阻止することにした硝子の竜。
時折、傷を『喰らう』という形でイバラシティに与する者の治療を行う姿が見られるかもしれない。
【アンジ体イラストはEno.152PL様より有償にて依頼しました!ありがとうございます!】
リオネル・サンドリヨン(Lionel・Cendrillon)
相良伊橋高校2年4組
195cm 91Kg 11月6日生まれ
性別:男
髪:夕焼け色、ハーフアップ
目:銀色
他の特徴:そばかす
こんな見た目だが母国語は日本語である。得意科目も現代文である。英語とフランス語の日常会話が可能。
好きな科目は世界史と体育。苦手な科目は数学。嫌いな科目は英語(成績はなかなか)。ド文系。
将来の夢とか進路とかは未定。焦る。とりあえず進学してそこから先は後で考えることにしている。
性格はだいぶ真面目な方だが、程々に緩くを心掛ける。気質は穏やかで争いごとは得意ではない。それでも、仲間が傍にいるのであればいかなる窮地でも共に在ろうとし、仲間に危機が迫れば周りを驚かせるような行動に出ることもある。それを一種の狂気と受け取るか勇気と受け取るかは、人によって異なるだろう。
過去に色々あったようで、どちらかというと抱え込みやすい気質。しかし、色々な人との出会いを経て、少しずつ改めようとしている。
コーポロザ301号室で暮らしている。
【http://lisge.com/ib/talk.php?p=226】
ソロール(場所設定はまちまち)
【http://lisge.com/ib/talk.php?p=734】
どうやらバイトをしているらしい。【http://lisge.com/ib/talk.php?s=140】
カラミティ イーター
異能≪不幸喰らい≫
・誰かの代わりに『不幸』を引き受けることができる。
・発動のためには、その『不幸』を何らかの形で認識する必要があり、彼の認識と実情に齟齬があると発動が不完全になる。
・異能が発動した際『蜜のような味』がする。異能の使用後、食欲が失せることもある。
・異能『所持』の代償で不幸体質になっている。異能『使用』の代償で、不幸が悪化する。それは誰かの代わりに受けた『不幸』とまた別である。
彼はイバラシティに加担するが、その正体はアンジニティの咎人である。アンジニティとしての姿は人にあらず、『四肢に鎖をつけ、体内に瘴気を宿した硝子の竜』のような出で立ちをしている。
その力を使うことで、病を、傷を、痛みを、怒りを、悲しみを、時には争いそのものを『喰らい』腹を満たす化け物。
争いごとがあるたびに近寄ってくることから、災いの象徴のような扱いを受けているかもしれない。
『不幸を喰らう』際には腹を満たすだけでなく、その不幸を硝子の竜が引き受けているというのに。
どういうわけか侵略を阻止することにした硝子の竜。
時折、傷を『喰らう』という形でイバラシティに与する者の治療を行う姿が見られるかもしれない。
【アンジ体イラストはEno.152PL様より有償にて依頼しました!ありがとうございます!】
20 / 30
67 PS
チナミ区
I-11
I-11



































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 頑強の枷 | 防具 | 30 | [効果1]防御10 [効果2]- [効果3]- |
| 5 | Calamity | 武器 | 20 | [効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | アーティチョークのアジフライ定食 | 料理 | 29 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 8 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 3 | 拘束/罠/リスク |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 防具 | 23 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 色無き爪 (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 色無き牙 (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 色無き角 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 色無き尾 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| 苦痛喰らい (ヒール) | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 決3 | 遠い記憶、嘗ての役目 (エキサイト) | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| 竜の翼、硝子の盾 (プロテクション) | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| 硝子の竜の逆鱗は如何に (スパイン) | 5 | 0 | 110 | 自:反撃LV増 | |
| 決3 | 『守護者』は刃を降ろす (イレイザー) | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| 畏怖喰らい (テリトリー) | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |
| 矛先喰らい (エスコート) | 5 | 0 | 80 | 自:次受ダメ減+味列:護衛 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 其は堕した■■ (攻撃) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 其は嘗てのシメイ (防御) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 其は灰被る国に非ざる物 (器用) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 其は臆病者の勇気 (敏捷) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 其は嘗ての存在意義 (回復) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 其は調和竜の呪縛 (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 其は嘗ての願い (体力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 其は調和竜の詛呪 (治癒) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 其は調和竜の呪詛 (鎮痛) | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 其は力の対価 (幸運) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]プロテクション | [ 1 ]オフェンシブ |
| [ 1 ]スパイン | [ 1 ]テリトリー | [ 1 ]エスコート |

PL / logi_minamo