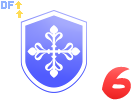<< 2:00>> 4:00




(before at 2:00)
体育の授業でも走ったことないくらい、本気で、全力で走って。転んで、歩いて躓いて、また走って。
約束していた辺りで、無事に千穂ちゃんと会えた。
千穂ちゃんはいつも通り、「にししっ」って、人の好い笑みを見せてくれて。私はほんとに……本当に、ほっとした。
おんなじソラコーの先輩だっていう慕先輩と、ちょっと寡黙そうな一穂くん。初めましての二人。
千穂ちゃんは、とっても頼りになる。だけど、千穂ちゃんにばかり頼っていられないし、二人よりも四人の方が、もっと心強いから。
私は慕先輩と一穂くんの手を、取った。
みんなと、一緒だから。だからこそ私は、怯えていられない。笑っていないといけない。そうしないと、きっとまた私は――
ざざっ、というノイズと共に、VRチャットの画面が少女の眼前に映し出される。
未だに安否が不明だった者からの連絡を受けて、少女はほっと胸を撫で下ろした。
しかし――
「…………どう、して」
触れられないの、という言葉は、声にならなかった。
車椅子の少女からのメッセージを再生すると、少女は一度、自分の目元を指で拭った。
それでも溢れた想いは一滴、また一滴と、荒廃した地に落ちていく。
通信機能が映し出す映像は、まるで対話の相手が目の前に存在しているかの如く鮮明でリアルだ。
良くも悪くも、今はその技術の優秀さに腹立たしさを覚える。
泣いている相手に手を伸ばすことができない。大丈夫だよ、心配ないよ、と抱き締めることもできない。
相手に届けられるのは、触れることのできない虚構と、言葉だけ。
気付けば、拳を硬く握りしめていた。
傍には居られないが、幸い、向こうも知り合いと会うことができたようだ。こうして通信も繋がる。
それだけで良かったと、そう、自分に言い聞かせて。
他に、まだ連絡が取れていない知り合いで特に安否を確認しておきたい人は、と思考を切り替える。
学生寮の寮母と、同じ高校の先輩――既に卒業式を終えた、園芸部の穏和で淑やかな少女の顔が浮かんだ。
彼女達にも連絡を取ろう、と思い立つ。その時、更に通信が入り――
――微笑みを浮かべたまま、少女は返信を終える。その時の少女の顔を、見る者が居たのなら。
“まるで抜け殻のようだ”と、評しただろう。
真っ白で、頭が上手く回らない。だから、彼女はいつものように。思考すること自体を、放棄した。
――時計の針は、回り続ける。
(at 2:00)
「……っ!?」
ぐわん、と脳内を揺さぶるような衝撃。次いで気分が悪くなりそうな感覚に、少女は頭を抱えて蹲った。
単なる頭痛ではない。脳内に無遠慮に直接手を入れられて、無理矢理スペースを抉じ開けられて。
記憶がぎゅうぎゅうに押し込められた段ボールを、幾つも無造作に詰め込まれるような。
「……っは、―――」
スカートの裾をぎゅっと握り、記憶の奔流と混濁に耐える。
この気分の悪さならいっそ気絶してしまった方が楽かもしれない、と少女は思う。
相良伊橋高校で卒業式が行われた記憶が流れ込んできたのは、ほんの一時間前。
なのに今では、高校はもう春休み期間に入っている――。
十日分かそれ以上の、イバラシティでの記憶。
ハザマではこうして実際に侵略が始まり、今もなお進行中だと言うのに。
慕っている先輩が、創峰大学に合格したという一足早い桜の開花報告と一緒に、ステキな贈り物を持ってきてくれた。
もしかしたら進学先はイバラシティの外で。先輩と会うのは、これっきりになってしまうんじゃないか、って思ってて。
報告を聞くまで、不安だった。
“これからもよろしくお願いします”。先輩の口からその言葉が紡がれた瞬間に、私の心にも、春の風が舞い込んだみたい――
ウシ区にある、今は営業してないゲームセンター。ひっそりとした店内の階段を登って、向かった先。
六階建ての屋上から見下ろす、夕暮れのウシ区の街は新鮮で。茜色に煌めく様が、とってもキレイだった。
途中で買ったクレープを頬張りながら。のんびり景色を眺めていたら、私以外にも、屋上に上がってきた人たちがいた。
ぶっきらぼうだけど、根は優しそうなおにーさんと。避田高校生の、元気いっぱいな女の子。
二人とお話した数時間は、濃くて。それに、ウシ区の守護像前のたこ焼き屋さんの並ぶ通りは、とっても良い匂いがしてて――
嵐が丘さんのお店にあった十字架。前はなかった気がする。
あの声の持ち主は、一体誰だったんだろう。嵐が丘さんに聞いてみれば、知ってるかな――
ホワイトデーに学校の屋上で、最近よく話すようになった気がする男の子から、バレンタインデーのお返しをもらった。
それもクッキーだけじゃなくて、小さな可愛いクマのぬいぐるみも一緒。
私がバレンタインデーに彼にあげたのは、みんなにも配っていたチョコレートブラウニーだったから。
ちょっと不釣り合いで、もらい過ぎちゃってる、そんな気もする。
贈り物のお礼の、贈り物。私はいつも、自分の好意でプレゼントをしているから、
お返しはいいよって、思ってるんだけど。それでも、やっぱりもらえると嬉しい――
二度目の感覚で、少女は確信する。“イバラシティでの自分たちは、ハザマの記憶を持たない”のだと。
1日1日の記憶が、重く――普段は何気なく過ごしている日常はただひたすらに、暖かくて。
愛おしく大切なものだと、感じさせられるようで。
――“いつもと変わらない日常”が、向こうでは続いている。



ENo.6 雪瀬 かりん とのやりとり

ENo.11 百地 初白 とのやりとり

ENo.400 恋文 慕/秘 とのやりとり

ENo.521 嵐が丘エリカ とのやりとり

ENo.638 プテラ・プテル とのやりとり

ENo.687 加唐揚羽/肉盛薔薇/気津根仕郎 とのやりとり

以下の相手に送信しました













一穂(8) は 吸い殻 を入手!
結乃(233) は パンの耳 を入手!
チホ(388) は 吸い殻 を入手!
恋文(400) は 吸い殻 を入手!
結乃(233) は ボロ布 を入手!
結乃(233) は 毛 を入手!
恋文(400) は 毛 を入手!
恋文(400) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
一穂(8) のもとに ちわわ がゆっくりと近づいてきます。



命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
チホ(388) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『すりおろし林檎入り特製カレー』をつくりました!
ルカ(1547) とカードを交換しました!
加護 (プロテクション)

アグリローズ を研究しました!(深度0⇒1)
イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
ハイポーション を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を習得!
レジスト を習得!
ヒーリングスキル を習得!



チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――


















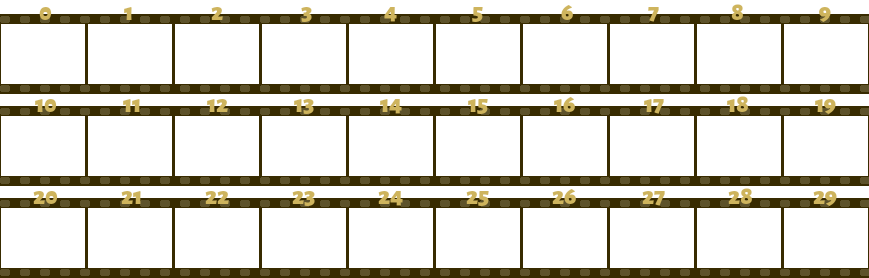





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



(before at 2:00)
体育の授業でも走ったことないくらい、本気で、全力で走って。転んで、歩いて躓いて、また走って。
約束していた辺りで、無事に千穂ちゃんと会えた。
千穂ちゃんはいつも通り、「にししっ」って、人の好い笑みを見せてくれて。私はほんとに……本当に、ほっとした。
おんなじソラコーの先輩だっていう慕先輩と、ちょっと寡黙そうな一穂くん。初めましての二人。
千穂ちゃんは、とっても頼りになる。だけど、千穂ちゃんにばかり頼っていられないし、二人よりも四人の方が、もっと心強いから。
私は慕先輩と一穂くんの手を、取った。
みんなと、一緒だから。だからこそ私は、怯えていられない。笑っていないといけない。そうしないと、きっとまた私は――
ざざっ、というノイズと共に、VRチャットの画面が少女の眼前に映し出される。
未だに安否が不明だった者からの連絡を受けて、少女はほっと胸を撫で下ろした。
しかし――
「…………どう、して」
触れられないの、という言葉は、声にならなかった。
車椅子の少女からのメッセージを再生すると、少女は一度、自分の目元を指で拭った。
それでも溢れた想いは一滴、また一滴と、荒廃した地に落ちていく。
通信機能が映し出す映像は、まるで対話の相手が目の前に存在しているかの如く鮮明でリアルだ。
良くも悪くも、今はその技術の優秀さに腹立たしさを覚える。
泣いている相手に手を伸ばすことができない。大丈夫だよ、心配ないよ、と抱き締めることもできない。
相手に届けられるのは、触れることのできない虚構と、言葉だけ。
気付けば、拳を硬く握りしめていた。
傍には居られないが、幸い、向こうも知り合いと会うことができたようだ。こうして通信も繋がる。
それだけで良かったと、そう、自分に言い聞かせて。
他に、まだ連絡が取れていない知り合いで特に安否を確認しておきたい人は、と思考を切り替える。
学生寮の寮母と、同じ高校の先輩――既に卒業式を終えた、園芸部の穏和で淑やかな少女の顔が浮かんだ。
彼女達にも連絡を取ろう、と思い立つ。その時、更に通信が入り――
――微笑みを浮かべたまま、少女は返信を終える。その時の少女の顔を、見る者が居たのなら。
“まるで抜け殻のようだ”と、評しただろう。
真っ白で、頭が上手く回らない。だから、彼女はいつものように。思考すること自体を、放棄した。
――時計の針は、回り続ける。
◇
(at 2:00)
「……っ!?」
ぐわん、と脳内を揺さぶるような衝撃。次いで気分が悪くなりそうな感覚に、少女は頭を抱えて蹲った。
単なる頭痛ではない。脳内に無遠慮に直接手を入れられて、無理矢理スペースを抉じ開けられて。
記憶がぎゅうぎゅうに押し込められた段ボールを、幾つも無造作に詰め込まれるような。
「……っは、―――」
スカートの裾をぎゅっと握り、記憶の奔流と混濁に耐える。
この気分の悪さならいっそ気絶してしまった方が楽かもしれない、と少女は思う。
相良伊橋高校で卒業式が行われた記憶が流れ込んできたのは、ほんの一時間前。
なのに今では、高校はもう春休み期間に入っている――。
十日分かそれ以上の、イバラシティでの記憶。
ハザマではこうして実際に侵略が始まり、今もなお進行中だと言うのに。
慕っている先輩が、創峰大学に合格したという一足早い桜の開花報告と一緒に、ステキな贈り物を持ってきてくれた。
もしかしたら進学先はイバラシティの外で。先輩と会うのは、これっきりになってしまうんじゃないか、って思ってて。
報告を聞くまで、不安だった。
“これからもよろしくお願いします”。先輩の口からその言葉が紡がれた瞬間に、私の心にも、春の風が舞い込んだみたい――
ウシ区にある、今は営業してないゲームセンター。ひっそりとした店内の階段を登って、向かった先。
六階建ての屋上から見下ろす、夕暮れのウシ区の街は新鮮で。茜色に煌めく様が、とってもキレイだった。
途中で買ったクレープを頬張りながら。のんびり景色を眺めていたら、私以外にも、屋上に上がってきた人たちがいた。
ぶっきらぼうだけど、根は優しそうなおにーさんと。避田高校生の、元気いっぱいな女の子。
二人とお話した数時間は、濃くて。それに、ウシ区の守護像前のたこ焼き屋さんの並ぶ通りは、とっても良い匂いがしてて――
嵐が丘さんのお店にあった十字架。前はなかった気がする。
あの声の持ち主は、一体誰だったんだろう。嵐が丘さんに聞いてみれば、知ってるかな――
ホワイトデーに学校の屋上で、最近よく話すようになった気がする男の子から、バレンタインデーのお返しをもらった。
それもクッキーだけじゃなくて、小さな可愛いクマのぬいぐるみも一緒。
私がバレンタインデーに彼にあげたのは、みんなにも配っていたチョコレートブラウニーだったから。
ちょっと不釣り合いで、もらい過ぎちゃってる、そんな気もする。
贈り物のお礼の、贈り物。私はいつも、自分の好意でプレゼントをしているから、
お返しはいいよって、思ってるんだけど。それでも、やっぱりもらえると嬉しい――
二度目の感覚で、少女は確信する。“イバラシティでの自分たちは、ハザマの記憶を持たない”のだと。
1日1日の記憶が、重く――普段は何気なく過ごしている日常はただひたすらに、暖かくて。
愛おしく大切なものだと、感じさせられるようで。
――“いつもと変わらない日常”が、向こうでは続いている。
The evening.3



ENo.6 雪瀬 かりん とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.11 百地 初白 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.400 恋文 慕/秘 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.521 嵐が丘エリカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.638 プテラ・プテル とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||||||
ENo.687 加唐揚羽/肉盛薔薇/気津根仕郎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
一穂 「皆様、戦いには慣れましたでしょうか。 僕はもう慣れておりますので、お気になさりませぬよう……」 |
 |
道端の、建造物だったと思わしき残骸に腰かけて、ぼんやりとしている。 |
 |
チホ 「(……違いますよね、先輩。先輩は…ウチは…)」 |





【問】“i”までの距離を求めよ
|
 |
TeamNo.359
|



一穂(8) は 吸い殻 を入手!
結乃(233) は パンの耳 を入手!
チホ(388) は 吸い殻 を入手!
恋文(400) は 吸い殻 を入手!
結乃(233) は ボロ布 を入手!
結乃(233) は 毛 を入手!
恋文(400) は 毛 を入手!
恋文(400) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
一穂(8) のもとに ちわわ がゆっくりと近づいてきます。



命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
チホ(388) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『すりおろし林檎入り特製カレー』をつくりました!
ルカ(1547) とカードを交換しました!
加護 (プロテクション)

アグリローズ を研究しました!(深度0⇒1)
イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
ハイポーション を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を習得!
レジスト を習得!
ヒーリングスキル を習得!



チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 J-12(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――







(仮PT名)
|
 |
千夜天水
|


ENo.233
岬 結乃



岬 結乃<Misaki Yuino>
Age:17 Sex:Female Height:162cm Weight:49kg
相良伊橋高校2年5組に在籍する女学生。附属する学生寮暮らし。
得意科目は言語系。数学と体育が苦手。成績は総合して中の上。
料理部と美術部の両方に所属しているが、どちらも顔を出す頻度は時々。美術部では絵画よりも彫刻に力を入れている。
昼休みは校舎内よりも外のベンチや花壇の傍、屋上などで過ごしていることが多い。甘いもの、特にクッキーやワッフルといった焼き菓子が好物。カバンの中には常に菓子類が入っている。散歩やショッピングも趣味で、放課後にふらふら街中を歩いている姿を見かけることがあるだろう。
“自分も、周りの人を見るのも、気恥ずかしいから”という理由で、公衆浴場や遊泳場が苦手。体育の水泳の授業も、1年の頃から一貫して見学(教室自習)組である。
性格はマイペースで、のんびり屋。沸点が高く、本気で怒ることは滅多にない。どんな相手にもふわ~っと近寄っていって手持ちの菓子を差し出す。そんな性格。
出身はイバラシティの外であり、高校進学に伴ってイバラシティに越してきた。過去に経験したある事情から、自身の異能に嫌悪感を抱いている。また、その影響で人間関係の中でも特に恋愛に対して、憧れはあるものの、深く踏み込むことのないように自身の中で一線を引いている節がある。
異能:《■■■■・■■作用/O------- of E------》
(更新毎に公開予定)
クラスメイト含め、他人には一切口外していない。はっきりと明言しないだけで、訊けば何らかの、端っこの情報くらいは言うかもしれない。
情報遮断の効果などは無い為、異能を見通す能力を持つ者なら、知ることが出来るだろう。
関係のある主なプレイス・スポット
・相良伊橋高校、及び隣接する学生寮306号室
・嵐が丘魔法洋菓子店でアルバイト中(2019.01.14~)
・IBARINEのアカウント、『色彩々のゼリー(会話ログ)』
*
・既知設定ご自由に
・プレイスでの発言は基本遅レスと置きレスになりがちです
・レンタルは栗鼠倫内において基本ご自由に
・Icon.No.10は、PicrewのGORILLA_ARTで作成したものに加筆したものです
Age:17 Sex:Female Height:162cm Weight:49kg
相良伊橋高校2年5組に在籍する女学生。附属する学生寮暮らし。
得意科目は言語系。数学と体育が苦手。成績は総合して中の上。
料理部と美術部の両方に所属しているが、どちらも顔を出す頻度は時々。美術部では絵画よりも彫刻に力を入れている。
昼休みは校舎内よりも外のベンチや花壇の傍、屋上などで過ごしていることが多い。甘いもの、特にクッキーやワッフルといった焼き菓子が好物。カバンの中には常に菓子類が入っている。散歩やショッピングも趣味で、放課後にふらふら街中を歩いている姿を見かけることがあるだろう。
“自分も、周りの人を見るのも、気恥ずかしいから”という理由で、公衆浴場や遊泳場が苦手。体育の水泳の授業も、1年の頃から一貫して見学(教室自習)組である。
性格はマイペースで、のんびり屋。沸点が高く、本気で怒ることは滅多にない。どんな相手にもふわ~っと近寄っていって手持ちの菓子を差し出す。そんな性格。
出身はイバラシティの外であり、高校進学に伴ってイバラシティに越してきた。過去に経験したある事情から、自身の異能に嫌悪感を抱いている。また、その影響で人間関係の中でも特に恋愛に対して、憧れはあるものの、深く踏み込むことのないように自身の中で一線を引いている節がある。
異能:《■■■■・■■作用/O------- of E------》
(更新毎に公開予定)
クラスメイト含め、他人には一切口外していない。はっきりと明言しないだけで、訊けば何らかの、端っこの情報くらいは言うかもしれない。
情報遮断の効果などは無い為、異能を見通す能力を持つ者なら、知ることが出来るだろう。
関係のある主なプレイス・スポット
・相良伊橋高校、及び隣接する学生寮306号室
・嵐が丘魔法洋菓子店でアルバイト中(2019.01.14~)
・IBARINEのアカウント、『色彩々のゼリー(会話ログ)』
*
・既知設定ご自由に
・プレイスでの発言は基本遅レスと置きレスになりがちです
・レンタルは栗鼠倫内において基本ご自由に
・Icon.No.10は、PicrewのGORILLA_ARTで作成したものに加筆したものです
15 / 30
122 PS
チナミ区
K-14
K-14





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 相良伊橋高校制服(ちょっと丈夫) | 防具 | 33 | 防御10 | - | - | |
| 5 | 水鉄砲(特注品) | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | ココナッツドーナツとココア | 料理 | 33 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 8 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]防御10(LV20)[効果3]治癒10(LV30) | |||
| 9 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]魅了10(LV20)[防具]幸運10(LV10)[装飾]守護10(LV20) | |||
| 10 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]防御10(LV20)[効果3]治癒10(LV30) | |||
| 11 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 12 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 13 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV20)[防具]体力10(LV5)[装飾]防御10(LV15) | |||
| 14 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 26 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練1 | アクアヒール | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| 練3 | ヒールポーション | 6 | 0 | 60 | 味傷:HP増 |
| レジスト | 5 | 0 | 80 | 自:肉体・精神変調耐性増 | |
| ヒーリングスキル | 5 | 0 | 50 | 自:HL増 | |
| パワーブースト | 5 | 0 | 40 | 自:AT増(1T)+連続増 | |
| 練3 | ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 |
| コロージョン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 | |
| デッドリィトクシン | 5 | 0 | 160 | 自:猛毒・衰弱・盲目・腐食特性増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]クリエイト:タライ | [ 1 ]アグリローズ | [ 1 ]リップル |
| [ 1 ]イバラ | [ 1 ]ペリル | [ 1 ]ハイポーション |

PL / 姫桜ゆうり