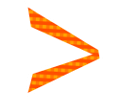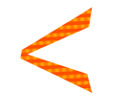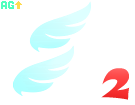<< 1:00>> 3:00




01 / 00:00
覚えのある街並みが眼前に広がる。しかしそこは荒れ果てていて、人気も無く、記憶にあるそれとは決定的に異なっていた。
例のアンジニティとやらが攻めて来たにしては、既に事が終わっているようにも見え、先程の怪物の存在意義に首を傾げる。
以前、核によって荒廃した世界を自由気ままに旅するゲームに熱中した時期があった。そのせいもあって、視界に飛び込んでくる一々に律儀に驚きはしなかったが、それと同じシチュエーションをイバラシティに当てはめてみれば、正しくこういう状況になるのだと不思議な高揚感を覚えるばかりだ。
あれにもVR版はあって、当然一頻り遊びもしたけれど、そんな発展途上の疑似体験ではありえない現象の幾つかを確認してしまった。
双海七夏はジャンルを問わずあらゆる遊戯へ興味を示してきたが、ことデジタルなゲームに関しては公正を貫いてきたつもりだ。
身に宿した人ではない力と、電脳化によって得た電子技術。その二つをゲームの世界に持ち込まない。あくまで対等の条件で勝負に臨む――というのが、彼女の心情である。
ところが赤黒い怪物と対峙して、あの黒スーツに唆されて。咄嗟に「これは危険だ」と考えを改めた。
"貴方の能力に、期待していますよ……?"
いつか聞いた男の声が頭の中で木霊する。文言から察するに、あれこそが始まりの合図だったのか。
能力、という部分が引っかかり、改めて自分の状態を確かめる。身体機能を計る各種ウィンドウを視界のあちこちに散らしながら、周囲の状況、いま身につけているもの、そして自分の持つ力が万全かどうかを、一つひとつ丁寧に調べていく。
先の戦いでの疲労が抜けていないこと以外で、肉体面の異常は検知されない。寧ろ普段よりもよく動けるような感じすらあるが、興奮していただけとすれば不自然ではない。電脳内も、電波がよろしくない点を除けば至って正常である。
衣服や装備に関しても日頃外を出歩く時と同じようで、例のボストンバッグこそ無いものの、携帯用の外部記憶装置とヘッドホンを模した有線用のチョーカーはしっかり手元にある。尤もこの環境で電子戦が求められるとも思えず、ただひたすらに邪魔になるだけであろうが――この世界での出来事のバックアップが取れるのは間違いなく大事だ。
能力については凡そ普段通り。寧ろ"ミクスタ"が同伴出来ている。守り人として過不足なく活動出来るというのは精神的に大きなプラスとなるはずだ。
それらの装備や異能が、五感で感じ取った諸々の情報が、そして何より己のゴーストが、少なくともここはゲームの中ではないとの結論を弾き出した。
別に何かが解決するわけではないと分かっていても、その場その時で自分の答えを出していく。
でなければきっと思考の海に沈んだきり、浮かび上がってこられなくなる。
ただ今後誰かと出会い、行動を共にするとして、また能力を秘匿して過ごすべきかどうかは心が揺れている。
恐らく"夢"を見るか"声"を聞くかした者は全員がこの場に集められているのだろうが、仮に何処かで見知った相手と鉢合わせて剰え敵対するようなことになったなら、一瞬決断が鈍るだけでそれは命取りになり得る。
些細な拘りのせいで大切な誰かが傷付くようなことはあってはいけない。
そんな小さな自衛なぞ捨て去って、昔のように覚悟を決める。なるべく早く。
いずれその時は来る。そんな予感が胸中で芽を出していた。
◆ ◆ ◆
ふと空を見上げると、やや古臭さを感じる『LOGIN』の文字がそこに浮かんでいた。
注視するうち、本当にログインしているかの如く文字が切り替わり、幾つかの情報が映し出されていく。この世界のこと、どこに誰が居て、何が起きたか――といった重要な事柄の数々。それに付随するチャット機能を目にして、つい声を荒げるかのように勢いでメッセージを送信すると、その前時代的なタイムラグで目が覚める。
生憎と情報の反映はリアルタイムではなかった。
どうやら視覚野の不具合でも電脳に干渉されているわけでもなく、この世界の持つシステムの一つであるらしいことは伝わってくる。
この世界はゲームの中ではない、と一度は決めつけておいて、そう間を置かぬうちに再び頭を抱えそうになった。
なまじ能力の性質上、力が使えるからといって仮想現実というものを完全に否定しきれないのが面倒なところであり。
カードは出せる。視覚的な細工も不備はなく、"電脳世界"も果たして充分に機能していた。
しかしその先はどうだ。確かめるに越したことはないが、可能なら使う機会が訪れない方がずっといい。
結局、思考の行き着く先は覚悟の話になるのか、と自分に呆れる外ない。
ともあれ、空のあれが幻覚でないのなら、送ったものに対してじき何かしらのレスポンスが返ってくる。
あんなものでも役には立つはずで、どれだけのことが出来るかくらいは知っておいても損は無かろう。
空に浮かぶ『Cross+Rose』とやらの機能の一つ、歯抜けの多い名簿に目を通していて、幾つか顔と名前の一致しない人物がいること、そしてそれらのある共通点に気が付いた。
彼ら彼女らがイバラシティに属する人間か、アンジニティとして侵略する側か、といった至極単純なものだけではない。
以前から気になっていた"夢"、内容を大きく二分出来る理由に当てはまりうるのだと。
あれだけ探していた『鍵』、パズルのピースがこうもあっさりと見つかってしまうのは、いくらなんでも。
◆ ◆ ◆
――。
――――。
――――――。
いつになく、思考が鈍い。
その原因が自分の送ったそれと入れ違いになる形で受信した件のメッセージにあることは明白だった。
"……私は……『アンジニティ』の人間だから……"
胸中に湧いて出たこの気持ちは、裏切られたとか失望したとか、そういった負の感情とは違う。
どちらかと言えば、理解や納得の方が近い。
このところ彼女に対し抱いていた些細な違和感の正体として、『アンジニティ』はおそらくこれ以上ない答えのはずだ。
それを会って直接確かめるだけの勇気が、果たしてあるのか。
"わたしにとって、かりんはかりんだよ"
屋上でのやり取りが脳裏を擦過する。
確かに、立ち塞がるのであれば腹を括るつもりでいた。
けれど、あの口振りからすると中身まで完全に別人というわけではないだろう。少なくとも、記憶は同一のものを有している。
自分の知っている"雪瀬かりん"であるのなら、口にした決意を曲げるようなことは起こり得まい。
彼女を信じている自分自身を信じられなくてどうするというのだ。
細かい部分は後回しにして一先ず合流を急ぎ、改めて状況を整理すればいい。
それからでも、遅くはない。
こんな疑念が生じるのは、いつかの再現を恐れているせいか?
/ 01:00



ENo.6 雪瀬 かりん とのやりとり

ENo.102 守屋 弓弦 とのやりとり

ENo.445 餅田 ハナ子 とのやりとり

ENo.608 露美智世 とのやりとり

ENo.709 ティーナ とのやりとり

ENo.922 黒木 蒔那 とのやりとり

以下の相手に送信しました












夏鈴(6) は パンの耳 を入手!
七夏(89) は 美味しくない草 を入手!
結唯(110) は 美味しくない草 を入手!
結唯(110) は 不思議な雫 を入手!
結唯(110) は 不思議な石 を入手!
夏鈴(6) は 毛 を入手!



夏鈴(6) により ItemNo.8 駄木 から防具『『電子海洋の衣』』を作製してもらいました!
⇒ 『電子海洋の衣』/防具:強さ33/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-
結唯(110) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ランチセット』をつくってもらいました!
⇒ ランチセット/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
結唯(110) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議なサラダ』をつくってもらいました!
⇒ 不思議なサラダ/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
玄(579) とカードを交換しました!
試薬メルクリウス (プリディクション)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)



特に何もしませんでした。






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















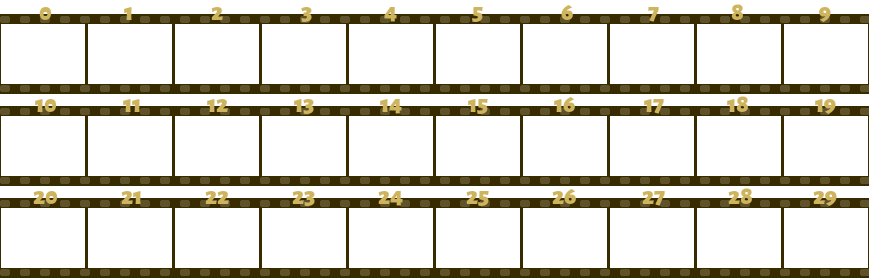





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [取引]OK.



01 / 00:00
覚えのある街並みが眼前に広がる。しかしそこは荒れ果てていて、人気も無く、記憶にあるそれとは決定的に異なっていた。
例のアンジニティとやらが攻めて来たにしては、既に事が終わっているようにも見え、先程の怪物の存在意義に首を傾げる。
以前、核によって荒廃した世界を自由気ままに旅するゲームに熱中した時期があった。そのせいもあって、視界に飛び込んでくる一々に律儀に驚きはしなかったが、それと同じシチュエーションをイバラシティに当てはめてみれば、正しくこういう状況になるのだと不思議な高揚感を覚えるばかりだ。
あれにもVR版はあって、当然一頻り遊びもしたけれど、そんな発展途上の疑似体験ではありえない現象の幾つかを確認してしまった。
双海七夏はジャンルを問わずあらゆる遊戯へ興味を示してきたが、ことデジタルなゲームに関しては公正を貫いてきたつもりだ。
身に宿した人ではない力と、電脳化によって得た電子技術。その二つをゲームの世界に持ち込まない。あくまで対等の条件で勝負に臨む――というのが、彼女の心情である。
ところが赤黒い怪物と対峙して、あの黒スーツに唆されて。咄嗟に「これは危険だ」と考えを改めた。
"貴方の能力に、期待していますよ……?"
いつか聞いた男の声が頭の中で木霊する。文言から察するに、あれこそが始まりの合図だったのか。
能力、という部分が引っかかり、改めて自分の状態を確かめる。身体機能を計る各種ウィンドウを視界のあちこちに散らしながら、周囲の状況、いま身につけているもの、そして自分の持つ力が万全かどうかを、一つひとつ丁寧に調べていく。
先の戦いでの疲労が抜けていないこと以外で、肉体面の異常は検知されない。寧ろ普段よりもよく動けるような感じすらあるが、興奮していただけとすれば不自然ではない。電脳内も、電波がよろしくない点を除けば至って正常である。
衣服や装備に関しても日頃外を出歩く時と同じようで、例のボストンバッグこそ無いものの、携帯用の外部記憶装置とヘッドホンを模した有線用のチョーカーはしっかり手元にある。尤もこの環境で電子戦が求められるとも思えず、ただひたすらに邪魔になるだけであろうが――この世界での出来事のバックアップが取れるのは間違いなく大事だ。
能力については凡そ普段通り。寧ろ"ミクスタ"が同伴出来ている。守り人として過不足なく活動出来るというのは精神的に大きなプラスとなるはずだ。
それらの装備や異能が、五感で感じ取った諸々の情報が、そして何より己のゴーストが、少なくともここはゲームの中ではないとの結論を弾き出した。
別に何かが解決するわけではないと分かっていても、その場その時で自分の答えを出していく。
でなければきっと思考の海に沈んだきり、浮かび上がってこられなくなる。
ただ今後誰かと出会い、行動を共にするとして、また能力を秘匿して過ごすべきかどうかは心が揺れている。
恐らく"夢"を見るか"声"を聞くかした者は全員がこの場に集められているのだろうが、仮に何処かで見知った相手と鉢合わせて剰え敵対するようなことになったなら、一瞬決断が鈍るだけでそれは命取りになり得る。
些細な拘りのせいで大切な誰かが傷付くようなことはあってはいけない。
そんな小さな自衛なぞ捨て去って、昔のように覚悟を決める。なるべく早く。
| 七夏 「キベルネテス "この子"を曝すことを躊躇わない、覚悟……」 |
いずれその時は来る。そんな予感が胸中で芽を出していた。
◆ ◆ ◆
ふと空を見上げると、やや古臭さを感じる『LOGIN』の文字がそこに浮かんでいた。
注視するうち、本当にログインしているかの如く文字が切り替わり、幾つかの情報が映し出されていく。この世界のこと、どこに誰が居て、何が起きたか――といった重要な事柄の数々。それに付随するチャット機能を目にして、つい声を荒げるかのように勢いでメッセージを送信すると、その前時代的なタイムラグで目が覚める。
生憎と情報の反映はリアルタイムではなかった。
どうやら視覚野の不具合でも電脳に干渉されているわけでもなく、この世界の持つシステムの一つであるらしいことは伝わってくる。
この世界はゲームの中ではない、と一度は決めつけておいて、そう間を置かぬうちに再び頭を抱えそうになった。
なまじ能力の性質上、力が使えるからといって仮想現実というものを完全に否定しきれないのが面倒なところであり。
| 七夏 「開始直後に能力の半分までは確認が取れたのは幸いだった、けれど」 |
カードは出せる。視覚的な細工も不備はなく、"電脳世界"も果たして充分に機能していた。
しかしその先はどうだ。確かめるに越したことはないが、可能なら使う機会が訪れない方がずっといい。
| 七夏 「発想がループしてやいないか……」 |
結局、思考の行き着く先は覚悟の話になるのか、と自分に呆れる外ない。
ともあれ、空のあれが幻覚でないのなら、送ったものに対してじき何かしらのレスポンスが返ってくる。
あんなものでも役には立つはずで、どれだけのことが出来るかくらいは知っておいても損は無かろう。
空に浮かぶ『Cross+Rose』とやらの機能の一つ、歯抜けの多い名簿に目を通していて、幾つか顔と名前の一致しない人物がいること、そしてそれらのある共通点に気が付いた。
彼ら彼女らがイバラシティに属する人間か、アンジニティとして侵略する側か、といった至極単純なものだけではない。
以前から気になっていた"夢"、内容を大きく二分出来る理由に当てはまりうるのだと。
あれだけ探していた『鍵』、パズルのピースがこうもあっさりと見つかってしまうのは、いくらなんでも。
◆ ◆ ◆
――。
――――。
――――――。
いつになく、思考が鈍い。
その原因が自分の送ったそれと入れ違いになる形で受信した件のメッセージにあることは明白だった。
"……私は……『アンジニティ』の人間だから……"
| 七夏 「…………」 |
胸中に湧いて出たこの気持ちは、裏切られたとか失望したとか、そういった負の感情とは違う。
どちらかと言えば、理解や納得の方が近い。
このところ彼女に対し抱いていた些細な違和感の正体として、『アンジニティ』はおそらくこれ以上ない答えのはずだ。
| 七夏 「かりん――いや、"あの時"の夏鈴は……そういうこと、だったのか?」 |
それを会って直接確かめるだけの勇気が、果たしてあるのか。
"わたしにとって、かりんはかりんだよ"
屋上でのやり取りが脳裏を擦過する。
確かに、立ち塞がるのであれば腹を括るつもりでいた。
けれど、あの口振りからすると中身まで完全に別人というわけではないだろう。少なくとも、記憶は同一のものを有している。
自分の知っている"雪瀬かりん"であるのなら、口にした決意を曲げるようなことは起こり得まい。
| 七夏 「自分で自分を疑うなんて、らしくない。 わたしだって散々隠し事をしてきただろうに――」 |
彼女を信じている自分自身を信じられなくてどうするというのだ。
細かい部分は後回しにして一先ず合流を急ぎ、改めて状況を整理すればいい。
それからでも、遅くはない。
こんな疑念が生じるのは、いつかの再現を恐れているせいか?
| 七夏 「"みーちゃん"……未来、わたしは……」 |
/ 01:00



ENo.6 雪瀬 かりん とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.102 守屋 弓弦 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.445 餅田 ハナ子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.608 露美智世 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.709 ティーナ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.922 黒木 蒔那 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



| 七夏 「大した力にはなれないけれど、手を貸すよ。 ……暫くの間、よろしく頼む」 |







夏鈴(6) は パンの耳 を入手!
七夏(89) は 美味しくない草 を入手!
結唯(110) は 美味しくない草 を入手!
結唯(110) は 不思議な雫 を入手!
結唯(110) は 不思議な石 を入手!
夏鈴(6) は 毛 を入手!



夏鈴(6) により ItemNo.8 駄木 から防具『『電子海洋の衣』』を作製してもらいました!
⇒ 『電子海洋の衣』/防具:強さ33/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-
結唯(110) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ランチセット』をつくってもらいました!
⇒ ランチセット/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
 |
結唯 「腹が減っては戦はなんとやらって」 |
結唯(110) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議なサラダ』をつくってもらいました!
⇒ 不思議なサラダ/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
 |
結唯 「食べられるものにはなってるはずだけど……」 |
玄(579) とカードを交換しました!
試薬メルクリウス (プリディクション)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)



特に何もしませんでした。






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――







Quartet
|
 |
TeamNo.45
|


ENo.89
双海七夏



名前/双海七夏 (ふたみ ななか)
性別/女
年齢/16歳→17歳
身長・体重/157cm 45kg
誕生日/1月27日
所属/相良伊橋高校二年五組、ファッションファッション部・民族文化研究部
住所/ツクナミ区 E-6 エクレールツクナミ702
( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2138 )
連絡先/個人宛IBALINE
( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2237 )
「コネクタがどれもこれも旧式じゃんか……よくこんなんで生活出来るなぁ」
「エロスこそ学業を乗り切る原動力。わざわざ登校するからには相応の対価を貰わなきゃあ」
「電子の海に溺れてみる?」
「からあげ……」
◆紹介◆
相良伊橋高二年の新学期に合わせて諸事情でイバラシティにやってきた高校生。ついてる。
電脳化しており、首の裏に接続用の端子がある。じっくり見ないと分からない感じ。通信中は何故かアホ毛がぴょこぴょこする。
制服のブレザーの内側に薄型のバッテリーや外付けのドライブを収納。見た目より重く校内ではたまに羽織る程度。
幼少期のあれやそれやでインドアが板についた。外に出たくない気持ちは強いものの、引きこもりというよりただの面倒臭がり。一度外出すれば一転して活発に歩き回る。要は電子機器に囲まれていたいだけ。
ネットサーフィンとオンラインゲーム、覗きが趣味。ハック、クラックはお手の物。
放課後や休日など時間が空いている時は街に繰り出し、食べ歩きやネットカフェ巡りに興じる。それとは別に、個人的な理由から「あるもの」を探して街を調べてもいる。
欲望に正直。女の子が好き。割と頻繁にいやらしいこと考えてる。たまに鼻血も出る。
好きな食べ物はホットドッグとフライドポテト、じゃがバター。ついで肉類、とりわけ鶏肉をよく食べる。
苦手な食べ物は辛いもの全般。イエローマスタードは平気。
一人称は「わたし」、二人称は「キミ」。他人を名前で呼ぶ時は呼び捨て。場合によってはあだ名を付ける。
◆能力◆
触れずに物を浮かせたり、自ら宙に舞ったりといった特異な力を持つ。世間一般で言うところの異能者。
後から力を加えない限りそれらはある程度の高さで浮遊した状態を維持し続ける。感覚としては無重量状態のそれだが、生物の体内で発生しうる各種変化は見られず、重力操作などとは異なる。
それとは別に、薄く色付いた透明なカードをどこからともなく取り出して、投擲したりナイフの代わりに使ったりもする。
が、これらは副次的に発生している現象であり、能力の本体・本質の部分は人前で見せようとしない。
手を抜いて楽したいとか他人を信用していないといった性質のものではなく、単純に対策が立てやすくタネが割れて周知されると困るから。
親しくなった相手には「火やら氷やら雷やら出すようなそういう派手なものでもなければ、怪力になったり傷がすぐ治ったりといったわかりやすいものでもないし、ましてや人と正面からやりあえる感じでもない」と自嘲気味に話すかもしれない。
その割には人前でふわふわ浮いたりする。
メタ的なおはなし
◆電脳について◆
Q.電脳化って何?
A.脳にマイクロマシンやナノマシンなどを注入し神経細胞とごにょごにょして脳と外部世界とを直接接続する技術。
俗に言うブレイン・マシン・インターフェース。
脳みそを取り出して機械にしました、というわけではない。
Q.電脳化すると何ができるの?
A.場所・環境を問わずネット上のあらゆる情報をリアルタイムに閲覧・検索・共有し、他者とのより正確なコミュニケーションが可能になる。
他にも手足を使わずに機械の操作ができたり、無線・有線関係なく端末を用いずに通信を行え、また電脳化している相手となら一部感覚の共有もできる。
見たものを写真・映像の両方で自由に記録する、専用の記憶装置に自分の記憶を移す、外部の必要な情報を抜き出して保管するなどして記憶力を増強したり、装置を経由して他人の記憶にアクセスし疑似体験するといったことも。
簡単に言えば、目に見えないほど小さなパソコンを自分の頭の中に作り上げる技術。
Q.割とずるくない?
A.異能だと認識されてもおかしくない。
元々外の街の最先端技術なので普通の人から見れば充分人間離れしているし、やれることの幾つかは法に触れかねない。
但しイバラシティ自体の電子化がそこまで進んでいないことと、携帯電話や無線通信に相乗りしている形になることを考慮するとスペックの半分も発揮できない。
手を使わずにやれるのは写真撮影とブラウジング、電話くらい。電子機器と直接繋がった場合はその限りでない。
Q.描写的には?
A.「こめかみを指でとんとん」「額に指をあてる」「顎に手を添える」など、七夏の癖でもあるアナクロな考える人的ポーズは大体通信中。
他にも「視界の隅に~」から始まり「ウィンドウ」や「表示」などを含む文章も同様。
Q."ミクスタ"?
A.七夏を補佐する人工知能の名前。
デフォルメされた緑色のワニのキャラクターとしての姿を取り、七夏の電脳内に常駐して彼女からの指示を実行する。
言葉を発することはない。イメージはデスクトップマスコット。もっと言えばネッ○ナビ。
性別/女
年齢/16歳→17歳
身長・体重/157cm 45kg
誕生日/1月27日
所属/相良伊橋高校二年五組、ファッションファッション部・民族文化研究部
住所/ツクナミ区 E-6 エクレールツクナミ702
( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2138 )
連絡先/個人宛IBALINE
( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2237 )
「コネクタがどれもこれも旧式じゃんか……よくこんなんで生活出来るなぁ」
「エロスこそ学業を乗り切る原動力。わざわざ登校するからには相応の対価を貰わなきゃあ」
「電子の海に溺れてみる?」
「からあげ……」
◆紹介◆
相良伊橋高二年の新学期に合わせて諸事情でイバラシティにやってきた高校生。ついてる。
電脳化しており、首の裏に接続用の端子がある。じっくり見ないと分からない感じ。通信中は何故かアホ毛がぴょこぴょこする。
制服のブレザーの内側に薄型のバッテリーや外付けのドライブを収納。見た目より重く校内ではたまに羽織る程度。
幼少期のあれやそれやでインドアが板についた。外に出たくない気持ちは強いものの、引きこもりというよりただの面倒臭がり。一度外出すれば一転して活発に歩き回る。要は電子機器に囲まれていたいだけ。
ネットサーフィンとオンラインゲーム、覗きが趣味。ハック、クラックはお手の物。
放課後や休日など時間が空いている時は街に繰り出し、食べ歩きやネットカフェ巡りに興じる。それとは別に、個人的な理由から「あるもの」を探して街を調べてもいる。
欲望に正直。女の子が好き。割と頻繁にいやらしいこと考えてる。たまに鼻血も出る。
好きな食べ物はホットドッグとフライドポテト、じゃがバター。ついで肉類、とりわけ鶏肉をよく食べる。
苦手な食べ物は辛いもの全般。イエローマスタードは平気。
一人称は「わたし」、二人称は「キミ」。他人を名前で呼ぶ時は呼び捨て。場合によってはあだ名を付ける。
◆能力◆
触れずに物を浮かせたり、自ら宙に舞ったりといった特異な力を持つ。世間一般で言うところの異能者。
後から力を加えない限りそれらはある程度の高さで浮遊した状態を維持し続ける。感覚としては無重量状態のそれだが、生物の体内で発生しうる各種変化は見られず、重力操作などとは異なる。
それとは別に、薄く色付いた透明なカードをどこからともなく取り出して、投擲したりナイフの代わりに使ったりもする。
が、これらは副次的に発生している現象であり、能力の本体・本質の部分は人前で見せようとしない。
手を抜いて楽したいとか他人を信用していないといった性質のものではなく、単純に対策が立てやすくタネが割れて周知されると困るから。
親しくなった相手には「火やら氷やら雷やら出すようなそういう派手なものでもなければ、怪力になったり傷がすぐ治ったりといったわかりやすいものでもないし、ましてや人と正面からやりあえる感じでもない」と自嘲気味に話すかもしれない。
その割には人前でふわふわ浮いたりする。
メタ的なおはなし
◆電脳について◆
Q.電脳化って何?
A.脳にマイクロマシンやナノマシンなどを注入し神経細胞とごにょごにょして脳と外部世界とを直接接続する技術。
俗に言うブレイン・マシン・インターフェース。
脳みそを取り出して機械にしました、というわけではない。
Q.電脳化すると何ができるの?
A.場所・環境を問わずネット上のあらゆる情報をリアルタイムに閲覧・検索・共有し、他者とのより正確なコミュニケーションが可能になる。
他にも手足を使わずに機械の操作ができたり、無線・有線関係なく端末を用いずに通信を行え、また電脳化している相手となら一部感覚の共有もできる。
見たものを写真・映像の両方で自由に記録する、専用の記憶装置に自分の記憶を移す、外部の必要な情報を抜き出して保管するなどして記憶力を増強したり、装置を経由して他人の記憶にアクセスし疑似体験するといったことも。
簡単に言えば、目に見えないほど小さなパソコンを自分の頭の中に作り上げる技術。
Q.割とずるくない?
A.異能だと認識されてもおかしくない。
元々外の街の最先端技術なので普通の人から見れば充分人間離れしているし、やれることの幾つかは法に触れかねない。
但しイバラシティ自体の電子化がそこまで進んでいないことと、携帯電話や無線通信に相乗りしている形になることを考慮するとスペックの半分も発揮できない。
手を使わずにやれるのは写真撮影とブラウジング、電話くらい。電子機器と直接繋がった場合はその限りでない。
Q.描写的には?
A.「こめかみを指でとんとん」「額に指をあてる」「顎に手を添える」など、七夏の癖でもあるアナクロな考える人的ポーズは大体通信中。
他にも「視界の隅に~」から始まり「ウィンドウ」や「表示」などを含む文章も同様。
Q."ミクスタ"?
A.七夏を補佐する人工知能の名前。
デフォルメされた緑色のワニのキャラクターとしての姿を取り、七夏の電脳内に常駐して彼女からの指示を実行する。
言葉を発することはない。イメージはデスクトップマスコット。もっと言えばネッ○ナビ。
25 / 30
32 PS
チナミ区
J-5
J-5











| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 『電脳回路の栞』 | 装飾 | 20 | [効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | ランチセット | 料理 | 33 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議なサラダ | 料理 | 33 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 8 | 『電子海洋の衣』 | 防具 | 33 | [効果1]防御10 [効果2]- [効果3]- |
| 9 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 装飾 | 10 | 装飾作製に影響 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ディスカード (ブレイク) | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| トリック (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| テリトリー | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]イレイザー |

PL / かのしき