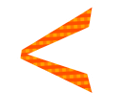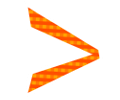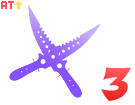<< 7:00~8:00




おれが生まれた村の風景は、ぼんやりと覚えている。
山間の小さな村で、イバラシティほど多くの人は住んでいない。土を盛った小山のような家が20軒かそれより少し多いくらいあって、その周りには青々とした田畑が広がっていた。
田畑を横切るように流れる大きな川ではよく子供が遊んでいたのを覚えている。魚取りや石投げ遊びに興じる子供達の楽しそうな様子を、おれは混ざる事もできずにただただ眺めているだけだった。
おれは生まれ故郷の土を踏み締める事もなく死んだけれど、なぜだか意識はずっと消えずに残っていた。
初めは山の中をうろついていたが、次第に村の方へ降りていって、そこからは山の方へ人が近付かない限りはずっと村の様子を見守っていた。
言葉を習わなかったおれは村のみんなが口を開けて何かを話していても、その内容を理解できなかった。だから、懸命に耳を澄ましてみんなの心に耳を傾けた。
喜び。安息。焦り。不安。恐怖。怒り。意識を研ぎ澄ませば色んな感情に触れられた。
でも、ある時期を境に村の中で感じ取れる心に偏りが見えてきた。
ある時は日照りが続き、田畑が渇いて人々が痩せ細っていった。
ある時は床に伏せる人が増え、様子がおかしくなって死んでいく者もいた。
ある時は長雨が降り続き、山が崩れたり川の水が溢れたりして土地も家も人も壊されていった。
やがて、村のみんなは山に小さな祠を作ってそこに手を合わせるようになった。
祠が立った場所は、おれが最初の頃にうろついていた山の中。おそらくはおれが埋められた位置だった。
村で人が死ぬ度、災いが起こる度、必ず村から人がやってきて祠に手を合わせた。
祠の前にわずかな作物や魚が置かれる事もあった。見知らぬ人が舞を踊ったり何かを唱えたりする事もあった。
彼らが祠の前で話す言葉はやはりおれには聞き取れなかった。けれど、心の声は痛いほどに届いていた。
村のみんなはおれのせいで村が災いに遭ったのだと考えていた。
だから祠を作って、捧げ物をして、手を合わせて、どうか怒りを鎮めてくださいとおれに頼んでいたのだろう。
おれ自身はそんな事をした覚えは全くなかった。けれど、おれが死んだ少し後から村の様子が大きく変わってしまったのは確かだった。
その後も、おれが戸惑い続けている間に村は荒れ果てていった。
流行り病で人が死んだ。長雨で作物が腐った。山から降りてきた獣が村を襲った。
おれが何もしないうちに村は荒廃し、やがて村から人が消えた。
否定の世界に堕ちるまで、おれは古ぼけた祠と共に山に留まり続けた。
自分の存在を呪いながら、生まれた罪を悔いながら、ずっと村の残骸を見下ろしていた。
何か温かいものに触れられた気がして、意識を己の内側から外に向ける。
己の外に広がる景色は記憶にある故郷のそれとはずいぶんと異なっている。空は赤く、道は舗装され、歩道と林は鉄製の柵で区切られている。
荒廃した雰囲気はあれど、自分の生まれ育った土地と比べるとかなり近代的な発展の跡が残された世界。
おれの目の前には、いつの間にかあの人がいた。
どこかいたたまれなさそうな顔をした彼の手には、小ぶりな桜の枝が握られている。
——細く骨張った指が髪を掻き分け、花飾りのように桜の枝を挿す。
ためらうように髪に触れるやさしい指。刃を握る時の荒々しさとは遠くかけ離れた穏やかな人の手。
ゆっくりと、左耳の上に挿された花に触れる。
二人分の想いが込められた花はやわらかな温度を宿して咲いている。
否定の世界に堕ちたばかりの頃は、自分はこの世にいてはいけないのだと思っていた。
自分がいるせいでみんなは不幸になった。自分はそこにいるだけで災いをもたらす呪いに似た存在だ。
けれど、忌まわしいこの身を拒まない人がいた。仲間として認めてくれた人がいた。
親しみを持って接してくれる人もいた。守りたいと言ってくれる人もいた。
高国藤久は生者を恨む怨霊だ。否定の世界で天からの声を聞いた後、おれ達を侵略に誘ったのは藤久だった。
藤久の周囲には無数の声が響いている。大勢の思念が渦巻いて、波のようにうねって鳴いている。
蒼黒の嵐の奥から微かに聞こえる「さびしい」という声は、一体誰が発したものなのだろう。
雛菊は幼くして死んだ少女だ。いつも穏やかな笑みを浮かべていて、時々おれの頭を撫でてくれる。
雛菊の心の声はいつも静かだ。最初は藤久やあの人の声に掻き消されているだけかと思っていたけれど、二人きりになった時にそもそも音がしないのだと気付いた。
雛菊の心が激しく揺れ動く音をおれはまだ聞いた事がない。雛菊の心には波もなく、流れもなく、時折小さな波紋が生まれる他に変化はない。とても不思議な雰囲気だった。
祐善ちさは悪意に満ちた死を与えられた少女だ。ちさはおれの事をよく気にかけてくれて、頭を撫でたり手を繋いだりしてくれた。
ちさはおれに自分のきょうだいを重ねているらしい。おれの姿に、触れ合う手に、いつか離れ離れになった家族のぬくもりを感じているのだろう。おれと同じだ。
ちさの隣にいると、時々心が軋む音がする。噛み殺した悲鳴にも似た音が、少しずつ内側からちさを抉っている。
杉乃遼馬の事は、おれはよく知らない。最初は少し離れた所にいておれ達の話に加わらなかったけど、最近は少し打ち解けてきたような感じがする。
遼馬と話した経験は数えるほどしかないけれど、遼馬の心からは痛いくらいにやさしい音が聞こえる。
会津仁弥とアイネはおれを知らないはずだった。でも、四ツ谷幽綺を守りたいという理由でおれ達の力になってくれた。
アイネは普段会津くんの心の奥にいるのか、ほとんど声は聞こえない。時々アイネが顔を覗かせると、吼えるような慟哭が響き渡る。
会津くんは何食わぬ顔で澄ましているけれど、心の奥からは寂しいと泣く声がする。
彼らのために何ができるだろう。
制御のできない呪いでしかない自分が、彼らの役に立つ事はできるだろうか。
強い願いを抱いて戦い続ける彼らを支えて、その願いを叶える事はできるのだろうか。
あの人の心は叫びで満ちている。怒りや憎悪や苦しみの奥で、捨てきれない想いがひとつだけか細い声で泣いている。
あの人は自分の本当の願いに気付いていない。
激情で目と耳を塞いで、向き合わないように心の底に閉じ込めている。
おれを受け入れてくれたみんなのために、その願いのために戦いたい。
けれど、イバラシティの人々を傷付けたくはない。
四ツ谷幽綺の友人に——彼が愛する人々に傷付いて欲しくはない。
イバラシティの侵略と、イバラシティの住人を守る事。両方を取るのは不可能だ。
少なくとも今のおれにはできっこない。
みんなを守れるだけの力を。
誰かを傷付けずに済む力を。
自分の願いを叶えられるだけの力を、おれにください。
祈りを捧げられる側だったおれが何かに祈る事なんて馬鹿げているだろうけど。
少しでもこの願いが叶うように、己の望む姿に近付けるように、ただただ手を合わせて祈った。



ENo.54 鋼鉄メイデンさん とのやりとり

ENo.161 ミツフネ とのやりとり

ENo.216 ヒビキ とのやりとり

ENo.224 鳴 とのやりとり

ENo.377 火花 とのやりとり

ENo.383 レオン とのやりとり

ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり

ENo.397 都月 とのやりとり

ENo.501 カナリア とのやりとり

ENo.513 十神 とのやりとり

ENo.582 リョウ とのやりとり

ENo.587 いちま とのやりとり

ENo.631 クロウ とのやりとり

ENo.656 『 』 とのやりとり

ENo.897 _____ とのやりとり

ENo.1121 祐善 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.8 梅干しおにぎり を食べました!
体調が 1 回復!(11⇒12)
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 強靭15 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










具現LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
解析LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
武術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
命術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV57⇒62、-5CP)
『高国藤久』(58) の持つ ItemNo.7 毒鉄鉱 から射程2の武器『小刀『潮盈珠』』を作製しました!
ItemNo.14 毒鉄鉱 から射程1の武器『鬼憑きの鎖』を作製しました!
⇒ 鬼憑きの鎖/武器:強さ180/[効果1]疫病15 [効果2]- [効果3]-【射程1】
祐善(1121) の持つ ItemNo.15 ド根性雑草 から射程3の武器『刻意』を作製しました!
『高国藤久』(58) により ItemNo.16 禁断じゃない果実 から料理『梅干しおにぎり』をつくってもらいました!
⇒ 技巧料理![ 2 2 2 = 6 ]成功!料理の強さが増加!
⇒ 梅干しおにぎり/料理:強さ39/[効果1]攻撃5 [効果2]防御5 [効果3]器用5
「蛇」(929) とカードを交換しました!
悪霊纏い (アウトレイジ)
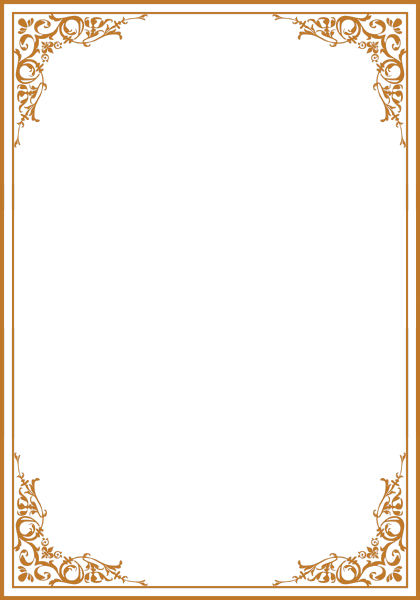
レッドショック を研究しました!(深度0⇒1)
レッドショック を研究しました!(深度1⇒2)
ワールウィンド を研究しました!(深度0⇒1)
チャージ を習得!
アクアヒール を習得!
アクアブランド を習得!
コラプション を習得!
サモン:ウォリアー を習得!
ディープフリーズ を習得!
五月雨 を習得!
イレイザー を習得!
アウトレイジ を習得!
集気 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



『高国藤久』(58) は 毒鉄鉱 を入手!
“移ろふ者共”(414) は 猫目石 を入手!
祐善(1121) は 猫目石 を入手!
杉乃(1139) は 燐灰石 を入手!
祐善(1121) は 不思議な雫 を入手!
杉乃(1139) は 針 を入手!
『高国藤久』(58) は 紅小石 を入手!
『高国藤久』(58) は 爪 を入手!



『高国藤久』(58) に移動を委ねました。
カミセイ区 R-3(山岳)に移動!(体調12⇒11)
カミセイ区 Q-3(道路)に移動!(体調11⇒10)
カミセイ区 P-3(道路)に移動!(体調10⇒9)
カミセイ区 O-3(森林)に移動!(体調9⇒8)
カミセイ区 N-3(森林)に移動!(体調8⇒7)





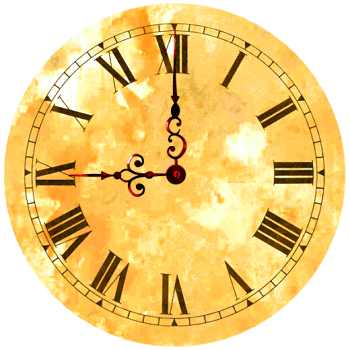
[816 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[370 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[367 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[104 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[147 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。
ドライバーさんから伝えられた内容に動揺している様子のふたり。
ザザッ――
チャットに雑音が混じる・・・
ザザッ――
ザザッ――
ザザッ――
チャットが閉じられる――










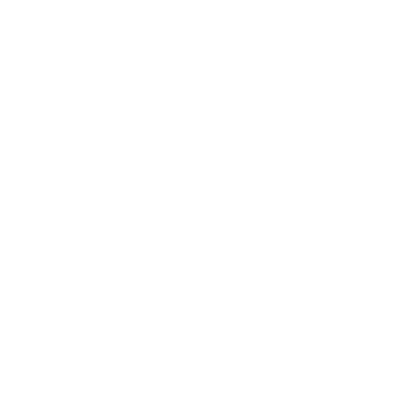
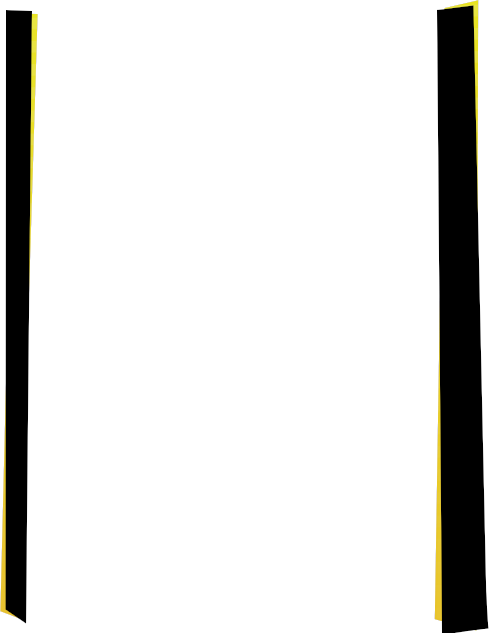
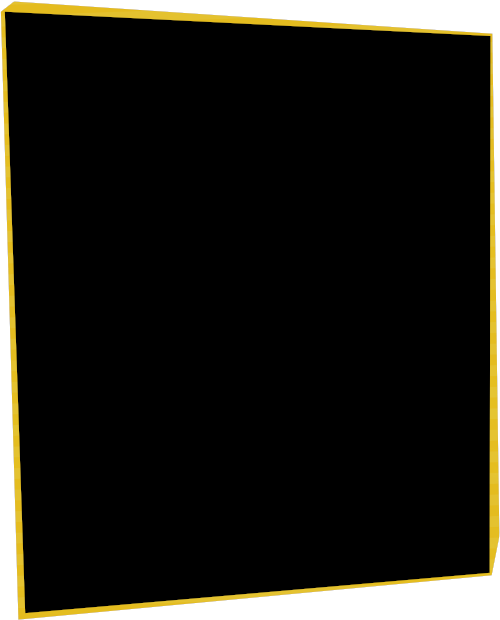





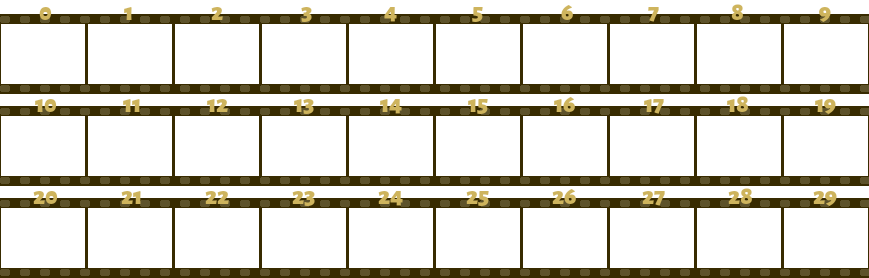







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



おれが生まれた村の風景は、ぼんやりと覚えている。
山間の小さな村で、イバラシティほど多くの人は住んでいない。土を盛った小山のような家が20軒かそれより少し多いくらいあって、その周りには青々とした田畑が広がっていた。
田畑を横切るように流れる大きな川ではよく子供が遊んでいたのを覚えている。魚取りや石投げ遊びに興じる子供達の楽しそうな様子を、おれは混ざる事もできずにただただ眺めているだけだった。
おれは生まれ故郷の土を踏み締める事もなく死んだけれど、なぜだか意識はずっと消えずに残っていた。
初めは山の中をうろついていたが、次第に村の方へ降りていって、そこからは山の方へ人が近付かない限りはずっと村の様子を見守っていた。
言葉を習わなかったおれは村のみんなが口を開けて何かを話していても、その内容を理解できなかった。だから、懸命に耳を澄ましてみんなの心に耳を傾けた。
喜び。安息。焦り。不安。恐怖。怒り。意識を研ぎ澄ませば色んな感情に触れられた。
でも、ある時期を境に村の中で感じ取れる心に偏りが見えてきた。
 |
こわい。こわい。いやだ。たすけて。 |
ある時は日照りが続き、田畑が渇いて人々が痩せ細っていった。
ある時は床に伏せる人が増え、様子がおかしくなって死んでいく者もいた。
ある時は長雨が降り続き、山が崩れたり川の水が溢れたりして土地も家も人も壊されていった。
 |
こわい。たすけて。どうして、 |
やがて、村のみんなは山に小さな祠を作ってそこに手を合わせるようになった。
祠が立った場所は、おれが最初の頃にうろついていた山の中。おそらくはおれが埋められた位置だった。
 |
おねがい |
 |
たすけて |
村で人が死ぬ度、災いが起こる度、必ず村から人がやってきて祠に手を合わせた。
祠の前にわずかな作物や魚が置かれる事もあった。見知らぬ人が舞を踊ったり何かを唱えたりする事もあった。
彼らが祠の前で話す言葉はやはりおれには聞き取れなかった。けれど、心の声は痛いほどに届いていた。
 |
もうやめて |
 |
おねがい |
 |
たすけて |
村のみんなはおれのせいで村が災いに遭ったのだと考えていた。
だから祠を作って、捧げ物をして、手を合わせて、どうか怒りを鎮めてくださいとおれに頼んでいたのだろう。
おれ自身はそんな事をした覚えは全くなかった。けれど、おれが死んだ少し後から村の様子が大きく変わってしまったのは確かだった。
その後も、おれが戸惑い続けている間に村は荒れ果てていった。
流行り病で人が死んだ。長雨で作物が腐った。山から降りてきた獣が村を襲った。
おれが何もしないうちに村は荒廃し、やがて村から人が消えた。
 |
「おれが、いけないの?」 |
 |
「おれがいたから、みんないなくなったの?」 |
 |
「おれは、ここにいちゃいけなかったの?」 |
否定の世界に堕ちるまで、おれは古ぼけた祠と共に山に留まり続けた。
自分の存在を呪いながら、生まれた罪を悔いながら、ずっと村の残骸を見下ろしていた。
 |
「 、 」 |
何か温かいものに触れられた気がして、意識を己の内側から外に向ける。
己の外に広がる景色は記憶にある故郷のそれとはずいぶんと異なっている。空は赤く、道は舗装され、歩道と林は鉄製の柵で区切られている。
荒廃した雰囲気はあれど、自分の生まれ育った土地と比べるとかなり近代的な発展の跡が残された世界。
 |
レスター 「……やる。俺が持っていても仕方ない」 |
おれの目の前には、いつの間にかあの人がいた。
どこかいたたまれなさそうな顔をした彼の手には、小ぶりな桜の枝が握られている。
 |
“ ” 「それ、この間拾った桜?」 |
 |
レスター 「ちさが長持ちするように手を加えたらしい。 お前が持っておけ」 |
——細く骨張った指が髪を掻き分け、花飾りのように桜の枝を挿す。
ためらうように髪に触れるやさしい指。刃を握る時の荒々しさとは遠くかけ離れた穏やかな人の手。
 |
“ ” 「……いいの?」 |
 |
レスター 「いい。お前の手元にあった方が長持ちするだろう」 |
 |
“ ” 「………………」 |
ゆっくりと、左耳の上に挿された花に触れる。
二人分の想いが込められた花はやわらかな温度を宿して咲いている。
否定の世界に堕ちたばかりの頃は、自分はこの世にいてはいけないのだと思っていた。
自分がいるせいでみんなは不幸になった。自分はそこにいるだけで災いをもたらす呪いに似た存在だ。
けれど、忌まわしいこの身を拒まない人がいた。仲間として認めてくれた人がいた。
親しみを持って接してくれる人もいた。守りたいと言ってくれる人もいた。
高国藤久は生者を恨む怨霊だ。否定の世界で天からの声を聞いた後、おれ達を侵略に誘ったのは藤久だった。
藤久の周囲には無数の声が響いている。大勢の思念が渦巻いて、波のようにうねって鳴いている。
蒼黒の嵐の奥から微かに聞こえる「さびしい」という声は、一体誰が発したものなのだろう。
雛菊は幼くして死んだ少女だ。いつも穏やかな笑みを浮かべていて、時々おれの頭を撫でてくれる。
雛菊の心の声はいつも静かだ。最初は藤久やあの人の声に掻き消されているだけかと思っていたけれど、二人きりになった時にそもそも音がしないのだと気付いた。
雛菊の心が激しく揺れ動く音をおれはまだ聞いた事がない。雛菊の心には波もなく、流れもなく、時折小さな波紋が生まれる他に変化はない。とても不思議な雰囲気だった。
祐善ちさは悪意に満ちた死を与えられた少女だ。ちさはおれの事をよく気にかけてくれて、頭を撫でたり手を繋いだりしてくれた。
ちさはおれに自分のきょうだいを重ねているらしい。おれの姿に、触れ合う手に、いつか離れ離れになった家族のぬくもりを感じているのだろう。おれと同じだ。
ちさの隣にいると、時々心が軋む音がする。噛み殺した悲鳴にも似た音が、少しずつ内側からちさを抉っている。
杉乃遼馬の事は、おれはよく知らない。最初は少し離れた所にいておれ達の話に加わらなかったけど、最近は少し打ち解けてきたような感じがする。
遼馬と話した経験は数えるほどしかないけれど、遼馬の心からは痛いくらいにやさしい音が聞こえる。
会津仁弥とアイネはおれを知らないはずだった。でも、四ツ谷幽綺を守りたいという理由でおれ達の力になってくれた。
アイネは普段会津くんの心の奥にいるのか、ほとんど声は聞こえない。時々アイネが顔を覗かせると、吼えるような慟哭が響き渡る。
会津くんは何食わぬ顔で澄ましているけれど、心の奥からは寂しいと泣く声がする。
 |
“ ” 「………………」 |
彼らのために何ができるだろう。
制御のできない呪いでしかない自分が、彼らの役に立つ事はできるだろうか。
強い願いを抱いて戦い続ける彼らを支えて、その願いを叶える事はできるのだろうか。
 |
“ ” 「おれは、」 |
あの人の心は叫びで満ちている。怒りや憎悪や苦しみの奥で、捨てきれない想いがひとつだけか細い声で泣いている。
あの人は自分の本当の願いに気付いていない。
激情で目と耳を塞いで、向き合わないように心の底に閉じ込めている。
 |
“ ” 「おれは、みんなの力になりたい」 |
おれを受け入れてくれたみんなのために、その願いのために戦いたい。
けれど、イバラシティの人々を傷付けたくはない。
四ツ谷幽綺の友人に——彼が愛する人々に傷付いて欲しくはない。
イバラシティの侵略と、イバラシティの住人を守る事。両方を取るのは不可能だ。
少なくとも今のおれにはできっこない。
 |
“ ” 「だから、もっと力が欲しい」 |
みんなを守れるだけの力を。
誰かを傷付けずに済む力を。
自分の願いを叶えられるだけの力を、おれにください。
 |
“ ” 「……おとうさん」 |
祈りを捧げられる側だったおれが何かに祈る事なんて馬鹿げているだろうけど。
少しでもこの願いが叶うように、己の望む姿に近付けるように、ただただ手を合わせて祈った。



ENo.54 鋼鉄メイデンさん とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.161 ミツフネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.216 ヒビキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.224 鳴 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.377 火花 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||
ENo.383 レオン とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.397 都月 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.501 カナリア とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.513 十神 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.582 リョウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.587 いちま とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||
ENo.631 クロウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.656 『 』 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.897 _____ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1121 祐善 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
怨霊 高国藤久 「欠けは、無いか。……無事に合流できたみてえだな。 演習、どうだった? あはは、楽しかったか? それとも、怖かった? それとも……」 |
 |
怨霊 高国藤久 「なあ、またやろうぜ。今度は違う組み合わせで、さ」 ちらりと遼馬に視線を向けた。 ばちばちと火花を飛ばしている──! |
 |
杉乃 遼馬 「───は、望むところだ」 |
 |
雛菊 「みんな、お疲れ様。 ちさがレスターと並んでいるの見て、すごくびっくりしちゃった」 |
 |
“ ” 「藤久達も、おつかれさま。 もっとふたりの手助けをしたかったけど、まだ力不足だったみたい。 次はちゃんと役に立てるようにしたいな」 |
 |
レスター 「次があっても俺は出る気はない。やりたければお前だけで参加しろ」 |
 |
“ ” 「うん、わかった。 その時は応援してくれる?」 |
 |
レスター 「……気が向いたらな」 |
 |
雛菊 「ふふ、お疲れ様。 その時は一緒に応援がんばろうね? レスター。 そうだ。今回、ちさがレスターと並んでいるの見て、すごくびっくりしちゃった」 |
 |
祐善 「驚いてくれた? ……その、うまく、動けなくって……負けちゃった、けど。 私こそ、驚いたよ。高国くんと、杉乃先輩」 思ったよりずっと息があってて、と揶揄いを滲ませた声色。 当のふたりを見やると、その色をもう少し濃くして。 |
 |
祐善 「いつの間に、そんなに仲良くなったの?」 |
 |
怨霊 高国藤久 「なってない」 |
 |
杉乃 遼馬 「なってない」 |
 |
祐善 「なってるね」 仲良くなってるよね、という顔をしている。 「……あの人に言ったあれ、案外間違いじゃなかったかも」 |
 |
会津 仁弥 「……なんというか、声を揃えてる時点で否定できてませんよね?」 |
 |
雛菊 「ふたりとも意地っ張りだから」 |
 |
雛菊 「ふふっ」 |
 |
雛菊 「それじゃ、行こっか」 |
ItemNo.8 梅干しおにぎり を食べました!
 |
“ ” 「会津くん、半分食べる?」 |
 |
会津仁弥 「いえ、気持ちだけで十分です。 俺はまだ大丈夫ですから」 |
 |
アイネ 『ならオレが貰うぜ。お前は泥水でもすすってろ』 |
 |
会津仁弥 「人の身体で勝手に食事を取るな。断食させるぞ」 |
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 強靭15 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!



落華残影/絡禍惨影
|
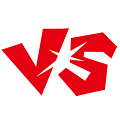 |
ハザマに生きるもの
|



落華残影/絡禍惨影
|
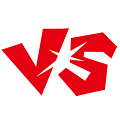 |
《地方武侠》LUCKY STAR
|



具現LV を 5 DOWN。(LV20⇒15、+5CP、-5FP)
解析LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
武術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
命術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV57⇒62、-5CP)
『高国藤久』(58) の持つ ItemNo.7 毒鉄鉱 から射程2の武器『小刀『潮盈珠』』を作製しました!
ItemNo.14 毒鉄鉱 から射程1の武器『鬼憑きの鎖』を作製しました!
⇒ 鬼憑きの鎖/武器:強さ180/[効果1]疫病15 [効果2]- [効果3]-【射程1】
祐善(1121) の持つ ItemNo.15 ド根性雑草 から射程3の武器『刻意』を作製しました!
『高国藤久』(58) により ItemNo.16 禁断じゃない果実 から料理『梅干しおにぎり』をつくってもらいました!
⇒ 技巧料理![ 2 2 2 = 6 ]成功!料理の強さが増加!
⇒ 梅干しおにぎり/料理:強さ39/[効果1]攻撃5 [効果2]防御5 [効果3]器用5
 |
怨霊 高国藤久 「あ、そうだ。神さま、これやるよ」 おにぎりと共に差し出されるのは、草で編んだ風ぐるまだ。 |
 |
怨霊 高国藤久 「もうこういうので遊ぶ歳じゃねえのかな……」 |
「蛇」(929) とカードを交換しました!
悪霊纏い (アウトレイジ)
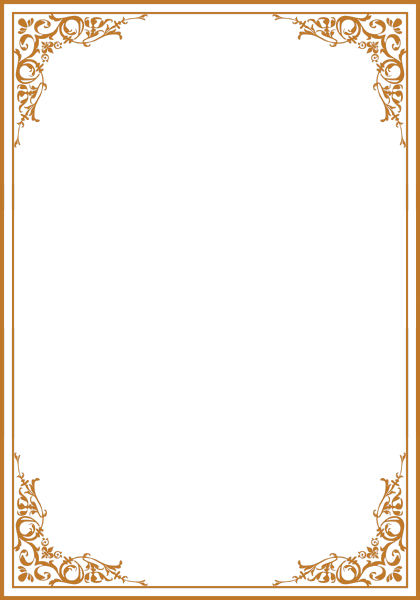
レッドショック を研究しました!(深度0⇒1)
レッドショック を研究しました!(深度1⇒2)
ワールウィンド を研究しました!(深度0⇒1)
チャージ を習得!
アクアヒール を習得!
アクアブランド を習得!
コラプション を習得!
サモン:ウォリアー を習得!
ディープフリーズ を習得!
五月雨 を習得!
イレイザー を習得!
アウトレイジ を習得!
集気 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



『高国藤久』(58) は 毒鉄鉱 を入手!
“移ろふ者共”(414) は 猫目石 を入手!
祐善(1121) は 猫目石 を入手!
杉乃(1139) は 燐灰石 を入手!
祐善(1121) は 不思議な雫 を入手!
杉乃(1139) は 針 を入手!
『高国藤久』(58) は 紅小石 を入手!
『高国藤久』(58) は 爪 を入手!



『高国藤久』(58) に移動を委ねました。
カミセイ区 R-3(山岳)に移動!(体調12⇒11)
カミセイ区 Q-3(道路)に移動!(体調11⇒10)
カミセイ区 P-3(道路)に移動!(体調10⇒9)
カミセイ区 O-3(森林)に移動!(体調9⇒8)
カミセイ区 N-3(森林)に移動!(体調8⇒7)





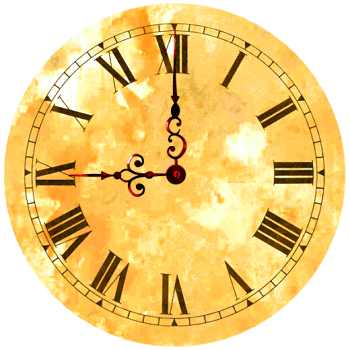
[816 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[370 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[367 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[104 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[147 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・怖いだろうがよ。」 |
 |
エディアン 「・・・勘弁してくれませんか。」 |
 |
白南海 「ナレハテってあの!アレだろォッ!!?ドッロドロしてんじゃねーっすか!! なんすかあれキッモいのッ!!うげぇぇぇぇうげえええぇぇぇ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「私だって嫌ですよあんなの・・・・・ ・・・え、案内役って影響力どういう扱いに・・・??私達は関係ないですよね・・・????」 |
 |
白南海 「あんたアンジニティならそーゆーの平気じゃねーんすか? 何かアンジニティってそういう、変な、キモいの多いんじゃ?」 |
 |
エディアン 「こんな麗しき乙女を前に、ド偏見を撒き散らさないでくれます? 貴方こそ、アレな業界の人間なら似たようなの見慣れてるでしょうに。」 |
 |
白南海 「あいにくウチはキレイなお仕事しかしてないもんで。えぇ、本当にキレイなもんで。」 |
ドライバーさんから伝えられた内容に動揺している様子のふたり。
 |
白南海 「・・・っつーか、あれ本当にドライバーのオヤジっすか?何か雰囲気違くねぇ・・・??」 |
 |
エディアン 「まぁ別の何か、でしょうね。 雰囲気も言ってることも別人みたいでしたし。普通に、スワップ発動者さん?・・・うーん。」 |
ザザッ――
チャットに雑音が混じる・・・
 |
エディアン 「・・・・・?なんでしょう、何か変な雑音が。」 |
ザザッ――
 |
白南海 「ただの故障じゃねーっすか。」 |
ザザッ――
 |
声 「――・・・レーション、ヒノデコーポレーション。 襲撃に・・・・・・・・いる・・・ 大量・・・・・こ・・・・・・死体・・・・・・ゾ・・・・・・」 |
 |
声 「・・・・・ゾンビだッ!!!!助け――」 |
ザザッ――
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「ホラーはぁぁ――ッ!!!! やぁぁめろォォ―――ッ!!!!」 |
 |
エディアン 「勘弁してください勘弁してくださいマジ勘弁してください。 ホラーはプレイしないんですコメ付き実況でしか見れないんですやめてください。」 |
チャットが閉じられる――







落華残影/絡禍惨影
|
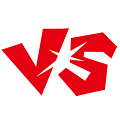 |
【Stairwell】ご飯おいしいは正義
|


ENo.414
『亡霊』と『祟り神』
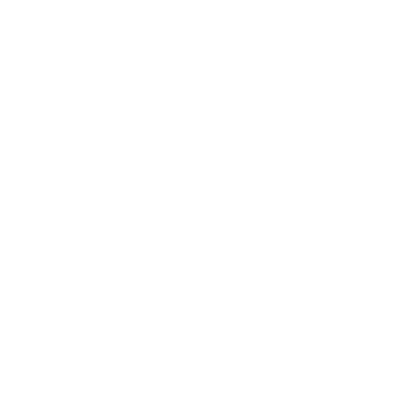
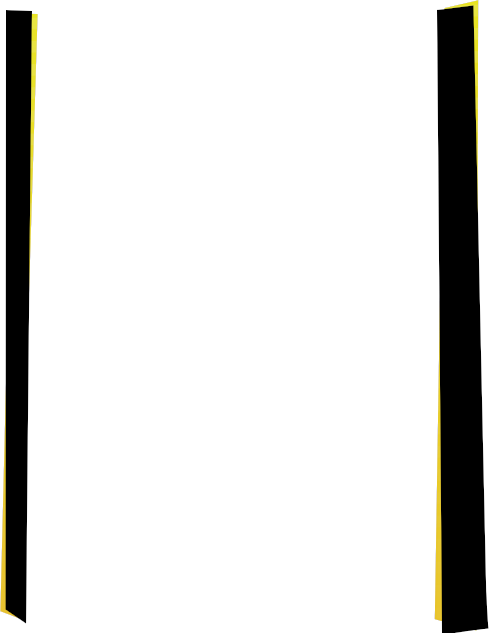
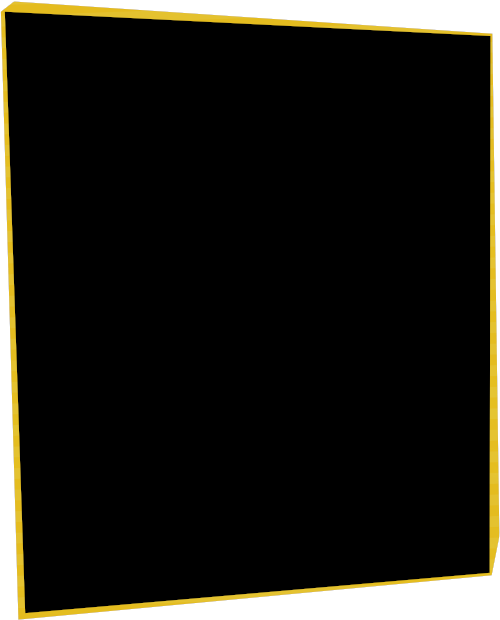
「貴方が探している人は此処にはいない」
「彼はとうに死んでしまったのだから」
《Side:ANSINITY》
◇レスター
没年:191×年
享年:26歳
かつて、どこかの世界で生きていた人間の残骸。
の最中に船舶事故で命を落とし、死際の未練から世界にしがみついた亡霊の成れの果て。
自身を 、死に追いやった人間への怒りで怨霊と化し殺人を繰り返していたが、かつて にあった から存在を否定されアンジニティに堕ちた。
幸福になる事を諦め、今はただ終焉だけを望んでいる。
◇タタリガミ
没年:平安時代中〜末期頃
享年:0歳
山間の集落で祀られていた無名の神。
『穢れ』と呼ばれる男女の双子であったために生後間も無く殺され、死後になっても災禍の源という立場を押し付けられ続けた結果、本物の祟り神と化してしまった子供の魂。
アンジニティに堕ちてからは力の大部分を失っていたが、イバラシティの記憶の影響で神格を取り戻しつつある。
◇会津仁弥/アイネ
イバラシティ陣営から離反してアンジニティ側の協力者となった裏切り者。イバラシティの住人・会津仁弥と、別世界の侵略戦争を体験したアンジニティ・アイネの二人組。
主人格は会津仁弥の方で、副人格のアイネは必要な時や気が向いた時にのみ現れる。また、会津仁弥は自分自身の異能と『折和逢音』の異能を、アイネは『折和逢音』の異能と本来の自分が持つ異能を行使する事が可能である。
副人格はアンジニティの住人だが、宿主たる主人格はイバラシティの住人であるため侵略が成った時には互いにアンジニティの世界へ堕ちるものと思われる。
《Side:IBARACITY》
◇四ツ谷幽綺(よつや ゆうき)
年齢:18歳
性別:男性
身長:約171cm
体重:痩せ気味(自己申告)
誕生日:4月9日
相良伊橋高校の3年5組に所属する少年。
異能は事象の確率操作をする力、『神の見えざる指』(ミザリー・メイカー)。自分を含めた身近な人物に不幸な出来事が起こる可能性を高める事しかできないため、普段は封印している。
元の世界では18年前の4月9日に死亡しており、『ワールドスワップ』でタタリガミの依代に設定された事で本来あり得なかったはずの人生を歩んでいる。
◇レスター・アークライト
年齢:27歳(仮定)
性別:男性
身長:185cm
体重:最近測っていない
誕生日:2月7日、5月14日、7月2日、10月31日(どれが本体かは気分で変わる)
ウラド区のレンタルCD・DVD店「IVAYA」の書籍コーナーで働く青年。
異能は思い込みによって身体能力を向上させる力『幻想転身』(メガロマニア)。
6年前に記憶を失った状態でイバラシティの海岸に流れ着き、飛鳥望というルポライターの青年に保護された。現在は飛鳥望が海外出張中のため一人暮らし。
記憶を取り戻す気はさほどなく、ほどほどに過去を調べながらイバラシティでの暮らしを満喫している。
不幸な事故により命を絶たれた青年の、あり得たかもしれない姿。
◇会津仁弥(あいづ ひとみ)
年齢:17歳
性別:男性
身長:175cm
体重:平均程度
誕生日:7月21日
相良伊橋高校の3年2組に在籍する少年。
イバラシティ外の出身であり、異能を発現させた頃から両親と不和を起こして厄介払いのような形でイバラシティに越してきた。
4年前に死亡した『折和逢音』の角膜を移植された影響で、彼の魂の残滓をその身に宿している。基本的に肉体の主導権は会津仁弥が握っているが、会津仁弥の感情が不安定になる、あるいは自ら主導権を譲る事で『折和逢音』の人格が表層化する。
異能は眼で視たものの性質を反転させる『虚は実に、愛は哀に』(アッシュ・トゥ・ブレイズ)と誰かの記憶を視る『甘美なる夢よ、我が愛よ』(クラック・アイズ)の二つ。さらに折和逢音の『連理の枝』(ステイ・ウィズ・ミー)も扱えるようだ。
◇久能詩夜(くのう しや)
年齢:22歳
身長:192cm
誕生日:3月3日
相良伊橋高校に勤める新人教師。担当教科は情報科学。
異能は影を操る力『小さな騎士の詩』(スタンド・バイ・ミー)。
穏やかで控えめな性格をしており、普段は良識的な面が目立つがロボのことになると人が変わる。
ソラコーのOBで、昔は親友共々水泳部に所属していた。
白南海から召集を受けなかったのか、ハザマに姿を現す事はない。
◇折和 逢音(おりわ あいね)
享年:18歳
身長:172cm
誕生日:7月26日
忌日:3月2日
相良伊橋高校の卒業生。
異能は強い感情を抱く相手との間に引力を発生させる力『連理の枝』(ステイ・ウィズ・ミー)。
4年前、卒業式の翌日にミナト区の海浜公園で転落死。遺骨は当人の生前の意志を汲み、鰐目蛙崖から海へ散骨された。
『こちら側』の世界の彼はワールドスワップによって創られた存在ではなく、確かにイバラシティに生きていた人間だった。
だが、故人となった彼の記憶は角膜を介して会津仁弥の中に宿り、それが並行世界のアンジニティを手繰り寄せる結果となった。
会津仁弥は本来『折和逢音』の人格を持ってはいない。会津仁弥の心の中に住まう折和逢音は『アンジニティのアイネ』がワールドスワップにより折和逢音の記憶を植え付けられた存在である。
18歳の春に死んだ折和逢音は、成り代わられた事さえ知らずに海の中で眠っている。
------------
・一部のアイコンにはフリー素材をお借りしております
背後→@3dorino_SUSK
「彼はとうに死んでしまったのだから」
《Side:ANSINITY》
◇レスター
没年:191×年
享年:26歳
かつて、どこかの世界で生きていた人間の残骸。
の最中に船舶事故で命を落とし、死際の未練から世界にしがみついた亡霊の成れの果て。
自身を 、死に追いやった人間への怒りで怨霊と化し殺人を繰り返していたが、かつて にあった から存在を否定されアンジニティに堕ちた。
幸福になる事を諦め、今はただ終焉だけを望んでいる。
◇タタリガミ
没年:平安時代中〜末期頃
享年:0歳
山間の集落で祀られていた無名の神。
『穢れ』と呼ばれる男女の双子であったために生後間も無く殺され、死後になっても災禍の源という立場を押し付けられ続けた結果、本物の祟り神と化してしまった子供の魂。
アンジニティに堕ちてからは力の大部分を失っていたが、イバラシティの記憶の影響で神格を取り戻しつつある。
◇会津仁弥/アイネ
イバラシティ陣営から離反してアンジニティ側の協力者となった裏切り者。イバラシティの住人・会津仁弥と、別世界の侵略戦争を体験したアンジニティ・アイネの二人組。
主人格は会津仁弥の方で、副人格のアイネは必要な時や気が向いた時にのみ現れる。また、会津仁弥は自分自身の異能と『折和逢音』の異能を、アイネは『折和逢音』の異能と本来の自分が持つ異能を行使する事が可能である。
副人格はアンジニティの住人だが、宿主たる主人格はイバラシティの住人であるため侵略が成った時には互いにアンジニティの世界へ堕ちるものと思われる。
《Side:IBARACITY》
◇四ツ谷幽綺(よつや ゆうき)
年齢:18歳
性別:男性
身長:約171cm
体重:痩せ気味(自己申告)
誕生日:4月9日
相良伊橋高校の3年5組に所属する少年。
異能は事象の確率操作をする力、『神の見えざる指』(ミザリー・メイカー)。自分を含めた身近な人物に不幸な出来事が起こる可能性を高める事しかできないため、普段は封印している。
元の世界では18年前の4月9日に死亡しており、『ワールドスワップ』でタタリガミの依代に設定された事で本来あり得なかったはずの人生を歩んでいる。
◇レスター・アークライト
年齢:27歳(仮定)
性別:男性
身長:185cm
体重:最近測っていない
誕生日:2月7日、5月14日、7月2日、10月31日(どれが本体かは気分で変わる)
ウラド区のレンタルCD・DVD店「IVAYA」の書籍コーナーで働く青年。
異能は思い込みによって身体能力を向上させる力『幻想転身』(メガロマニア)。
6年前に記憶を失った状態でイバラシティの海岸に流れ着き、飛鳥望というルポライターの青年に保護された。現在は飛鳥望が海外出張中のため一人暮らし。
記憶を取り戻す気はさほどなく、ほどほどに過去を調べながらイバラシティでの暮らしを満喫している。
不幸な事故により命を絶たれた青年の、あり得たかもしれない姿。
◇会津仁弥(あいづ ひとみ)
年齢:17歳
性別:男性
身長:175cm
体重:平均程度
誕生日:7月21日
相良伊橋高校の3年2組に在籍する少年。
イバラシティ外の出身であり、異能を発現させた頃から両親と不和を起こして厄介払いのような形でイバラシティに越してきた。
4年前に死亡した『折和逢音』の角膜を移植された影響で、彼の魂の残滓をその身に宿している。基本的に肉体の主導権は会津仁弥が握っているが、会津仁弥の感情が不安定になる、あるいは自ら主導権を譲る事で『折和逢音』の人格が表層化する。
異能は眼で視たものの性質を反転させる『虚は実に、愛は哀に』(アッシュ・トゥ・ブレイズ)と誰かの記憶を視る『甘美なる夢よ、我が愛よ』(クラック・アイズ)の二つ。さらに折和逢音の『連理の枝』(ステイ・ウィズ・ミー)も扱えるようだ。
◇久能詩夜(くのう しや)
年齢:22歳
身長:192cm
誕生日:3月3日
相良伊橋高校に勤める新人教師。担当教科は情報科学。
異能は影を操る力『小さな騎士の詩』(スタンド・バイ・ミー)。
穏やかで控えめな性格をしており、普段は良識的な面が目立つがロボのことになると人が変わる。
ソラコーのOBで、昔は親友共々水泳部に所属していた。
白南海から召集を受けなかったのか、ハザマに姿を現す事はない。
◇折和 逢音(おりわ あいね)
享年:18歳
身長:172cm
誕生日:7月26日
忌日:3月2日
相良伊橋高校の卒業生。
異能は強い感情を抱く相手との間に引力を発生させる力『連理の枝』(ステイ・ウィズ・ミー)。
4年前、卒業式の翌日にミナト区の海浜公園で転落死。遺骨は当人の生前の意志を汲み、鰐目蛙崖から海へ散骨された。
『こちら側』の世界の彼はワールドスワップによって創られた存在ではなく、確かにイバラシティに生きていた人間だった。
だが、故人となった彼の記憶は角膜を介して会津仁弥の中に宿り、それが並行世界のアンジニティを手繰り寄せる結果となった。
会津仁弥は本来『折和逢音』の人格を持ってはいない。会津仁弥の心の中に住まう折和逢音は『アンジニティのアイネ』がワールドスワップにより折和逢音の記憶を植え付けられた存在である。
18歳の春に死んだ折和逢音は、成り代わられた事さえ知らずに海の中で眠っている。
------------
・一部のアイコンにはフリー素材をお借りしております
背後→@3dorino_SUSK
7 / 30
888 PS
カミセイ区
N-3
N-3







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 大振りのナイフ | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 革のベルト | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 細い鎖 | 装飾 | 40 | 増勢10 | - | - | |
| 7 | 厄寄せの手綱 | 武器 | 60 | 混乱10 | - | - | 【射程1】 |
| 8 | 猫目石 | 素材 | 25 | [武器]麻痺20(LV30)[防具]反痺20(LV30)[装飾]応報15(LV30) | |||
| 9 | 妖刀『八俣遠呂智』 | 武器 | 75 | 貫撃10 | 闇纏15 | - | 【射程3】 |
| 10 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 11 | 桜の枝 | 装飾 | 167 | 舞護15 | 体力10 | - | |
| 12 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 13 | 古ぼけた外套 | 法衣 | 30 | 敏捷10 | - | 幸運10 | |
| 14 | 鬼憑きの鎖 | 武器 | 180 | 疫病15 | - | - | 【射程1】 |
| 15 | |||||||
| 16 | 梅干しおにぎり | 料理 | 39 | 攻撃5 | 防御5 | 器用5 | |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 22 | 呪詛/邪気/闇 |
| 具現 | 15 | 創造/召喚 |
| 武器 | 62 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 7 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 6 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| カース | 6 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| 決3 | フィジカルブースター | 5 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| ペレル | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| ラトゥンブロウ | 7 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
| アシスト | 5 | 0 | 50 | 自:束縛+自従全:AT・DX増 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:メガネ | 5 | 0 | 100 | 味:DX・AG増(5T) | |
| パワーブースター | 5 | 0 | 40 | 自従:AT・DF・DX・AG・HL増(3T) | |
| 決3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| 決3 | ダークネス | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| 決3 | アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 |
| コラプション | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&祝福消費で闇撃 | |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| 決2 | ワンオンキル | 6 | 0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 |
| 決3 | ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 |
| ディープフリーズ | 5 | 0 | 110 | 敵:凍結 | |
| ディバウア | 5 | 0 | 80 | 自従傷:喰LV増 | |
| アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| 決3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| 決3 | サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
| アブソーブ | 6 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| アウトレイジ | 5 | 0 | 200 | 自:AT・闇特性・光耐性・闇耐性増 | |
| サモン:シャドウ | 5 | 5 | 400 | 自:シャドウ召喚 | |
| ウィザー | 8 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 | |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| 決3 | ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 決3 | 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |
| 敗柳残花 | 6 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 修復 | 5 | 3 | 0 | 【被HP回復後】自:守護 | |
| 闇の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
| 集気 | 5 | 4 | 0 | 【通常攻撃後】自:次与ダメ増 | |
| 贖罪山羊 | 5 | 5 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「サモン」が含まれるなら、自従全:身代 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
なんだかんだやる (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
勇気を出してください! (ブレイブハート) |
0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| 決3 |
サモン:サーヴァント (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
| 決3 |
おぼろげな標 (クリエイト:グレイル) |
0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
|
ここは僕に任せて先に行け! (ファーマシー) |
0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
|
サモン:ウォリアー (サモン:ウォリアー) |
5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| 決3 |
百足の呪い (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
悪霊纏い (アウトレイジ) |
0 | 200 | 自:AT・闇特性・光耐性・闇耐性増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]集気 | [ 1 ]カタルシス | [ 3 ]ファイアボルト |
| [ 3 ]ヘイルカード | [ 1 ]コロージョン | [ 1 ]ディム |
| [ 3 ]パージ | [ 1 ]ワールウィンド | [ 3 ]敗柳残花 |
| [ 2 ]レッドショック | [ 3 ]ヒートイミッター | [ 3 ]パワフルヒール |

PL / 緑野