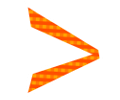<< 5:00~6:00





最初に見たのは、雨に濡れる母の姿。
母親というには若い、寧ろ幼い風貌の少女は腕の中にいる赤ん坊の目を見ていた。
「泣かないでね」
静かな声で言葉が紡がれる。
「暴れないでね」
少女はゆっくりと赤子を地面に下ろした。
「お願いだから、恨まないでね。」
それは懺悔であり、身勝手な願いであった。
言葉のわからない赤ん坊がそれを理解するはずはない。
けれど少女は目の前の赤子がきっと静かにしてくれるだろうと確信していた。
その言葉は、赤ん坊に与えられた最初の『命令』。
これからの土台となる絶対的なルールとなった。

「────────」
赤ん坊は泣きもせず、手を伸ばしもせず、足早に去っていく母親の姿を見つめていた。
捨てられた、などと理解するはずがない。
ただ、いくつかの言葉が自分には与えられたことを理解していた。
それは赤ん坊にとって、たった一つの『母からの愛』だった。
産声を上げることもなかった赤ん坊は、雨が降る街の中、施設の職員が発見するまで一言も声を発することがなかった。
これが、一つ目の幸運。
その赤子は手のかかる子供だった。
騒いだり、夜泣きしたりすることはない。
しかし、いちいち指示を出さなければ食事すらしないほど無気力だった。
赤子に宿った異能は強力な自己暗示。
どんな命令でも意味を理解すれば聞き入れるが、裏返せば命令が無ければ指先一つ動かせない。
『命令』によって泣き声を上げられない赤子は、自分の欲求を伝える術を持たなかった。
その『命令』によって生じた障害であることも、誰も知らない。
「いっそ殺してあげた方がいいんじゃないか」
「馬鹿なことを言わないの!」
「いつまでたっても自主性が芽生えないじゃないか。あれを生きていると言えるのか?」
「笑うことだってあるわ」
「それだって自分たちが教えた事だろう。あのまま成長したら行く先は碌なものじゃない」
「だからって……」
職員達の言い合いが聞こえても、赤子はそちらに意識を向けはしない。
いつしか赤子の首には異能制御のための機械が取り付けられていた。
施設にいる他の子どもが冗談で口にする「死んじゃえ」という言葉を真に受けて自分の首を絞めたことがあったからだ。
赤子の中にあるのは、母親の言葉と施設職員に言いつけられた一日の行動のみ。

泣かず、暴れず、恨みもせず。
制御装置に入力された一日のルーチンワークを忠実にこなす。
それだけの日々を二年間続けた。
結局処分されることもなく、施設の隅で生き続けた。
二歳になったある日、赤子の人生は一つの転機を迎えることになる。
施設を訪れたとある夫婦が、彼女を養子に迎えたいと申請してきたのだ。

「あなたは今日から御堂翠華になりますからね。」
綺麗な着物を着せられて、小さな手を握られて、しっかりと目を見て言葉が紡がれる。
「あなたは私たちの大切な娘なのですから、これからどうぞよろしくね。」
"はじめまして"はこれっきり。
数か月もしないうちに名前のなかった赤子は『御堂翠華』になっていった。
これが、二つ目の幸運。

生まれた時から見えていた"それ"が何なのか、終ぞ疑問に思うことはなかった。
何かをじっと見つめるとそれは現れた。
それが見えている時は、自分はそこにあるものを自由に動かすことができた。
おもちゃを引き寄せたり、折り紙を折ったり、冷蔵庫を開けてみたり。
重さも大きさも関係なく、あらゆるものを動かし、曲げて、回転させることができた。
それを見た両親はとても喜んでくれた。上手ね、すごいねと。
それが嬉しかったし、何より色々楽だったから、私はその異能を使い倒した。
どこまでいける?なにをやれる?
便利すぎるこの力の限界を知りたくて。
だから
こうなることは、仕方なかった。

少しのズレが、惨劇を招いた。
柱が折れて、木材が崩れて。
私に、降ってきた。
幽霊になって戻ってきたときには
そこにはもう、『御堂翠華』がいた。
(面倒なことになったなあ)
ハザマで目についた何かを曲げて投げてどかしながら進んでいく。
実際すり抜けるからその必要はないのだけれど、生き物をすり抜けるというのはなんとなく気持ちが悪い。
(誰にも私は見えてないみたい)
できることは通信機をジャックして短い言葉を飛ばすことのみ。
そこから場所を特定して、ようやく目当ての相手を見つけた。
『──コメット!』
地面を蹴って走る。
短い歩幅では追いつくのに時間がかかったけれど、息が切れることのない霊体は時間さえあれば歩いている人には追い付ける。
『コメット、わかる?見える?』
"妹"は進み続ける。
私に意識を向けることもない。
『……やっぱり、見えないのね』
しょんぼりと肩を落とす。
彼女ならあるいは、と思っていたのだけれど。
『そんな体でどこへ行くの』
飴のようになった体は見ていて痛々しい。
どこから砕けてしまうかわからない。
『止まって、止まってってば!』
なんとか治さなくては。
せめて休ませなければ。
彼女が戦わなくても戦争は続いていく。戦える人はたくさんいる。
失わせてはいけない。もう二度と、両親の"娘"を失わせるわけにはいかない。
私が守らなくてはいけないのだ。私にできることならなんだってして、彼女の存在を保たせなければ。
頭上から声がした。
真っ黒な着物に身を包んだ少女。
……御堂翠華だった頃のコメットだ。
『あなたは、イバラシティで私の中にいた子ね。』
そう言ったきり、彼女は顔を背けて歩き出した。
いくらハザマの生き物を倒しても、アンジニティからも見えない自分はこの戦いに貢献できない。
なにも、できない?
何も……
『そんなこと、あるものですか』
目元を拭って歩き出す。
何もできないなど、あるものか。
守ってみせる。私が必ず。
誰にも彼女を傷つけさせない。誰にも彼女を損なわせない。誰にも彼女に触れさせない。
ぎしり。
コメットの右肩が飴に置換された。



ENo.17 サクマ とのやりとり

ENo.55 ゆい とのやりとり

ENo.195 天使様 とのやりとり

ENo.216 ヒビキ とのやりとり

ENo.403 絶望の神器 とのやりとり

ENo.555 持明院 寂怜 とのやりとり

ENo.671 海の魔物 とのやりとり

ENo.1520 "大地の不純物" とのやりとり

以下の相手に送信しました




ヒビキ(216) に ItemNo.14 エナジー棒 を手渡ししました。
勇者(551) から 木瓜 を手渡しされました。
ItemNo.13 エナジー棒 を食べました!
体調が 0 回復!(30⇒30)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










武術LV を 15 DOWN。(LV15⇒0、+15CP、-15FP)
魔術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
ヒビキ(216) により ItemNo.7 雑木 から射程3の武器『チェーホフの銃』を作製してもらいました!
⇒ チェーホフの銃/武器:強さ90/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
ItemNo.14 木瓜 から装飾『木瓜の髪飾り』を作製しました!
⇒ 木瓜の髪飾り/装飾:強さ90/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-
勇者(551) の持つ ItemNo.11 不思議な雫 から装飾『目薬』を作製しました!
勇者(551) により ItemNo.6 何か柔らかい物体 から防具『シン・ゴリラの着ぐるみ』を作製してもらいました!
⇒ シン・ゴリラの着ぐるみ/防具:強さ60/[効果1]命脈10 [効果2]- [効果3]-
レオン(974) とカードを交換しました!
雪景色のカード (スノードロップ)
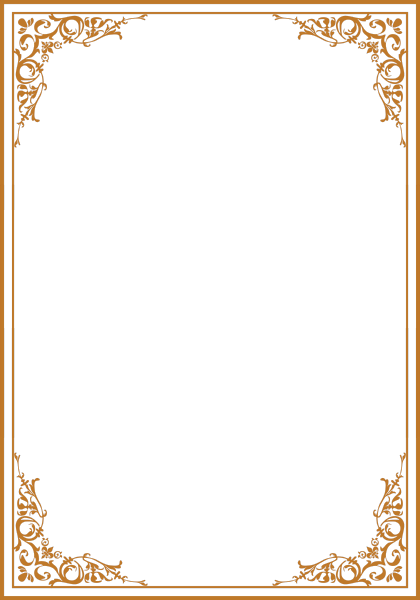
ポーションラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度1⇒2)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度2⇒3)
リフレクション を習得!
ファイアレイド を習得!
ヘイルカード を習得!
クイックレメディ を習得!
ファイアボルト を習得!
ガーディアン を習得!
カタラクト を習得!
オイルファイア を習得!
クリムゾンスカイ を習得!
スノードロップ を習得!
ウィルスゾーン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ヒビキ(216) は 鉄板 を入手!
コメット(253) は 鉄板 を入手!
まさこ(281) は 鉄板 を入手!
勇者(551) は 雑木 を入手!
まさこ(281) は 羽 を入手!
ヒビキ(216) は 羽 を入手!
まさこ(281) は 花びら を入手!
ヒビキ(216) は 毛 を入手!



チナミ区 G-16(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-16(山岳)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-16(山岳)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-16(山岳)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- コメット(253) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》 を選択!
- コメット(253) の選択は カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》





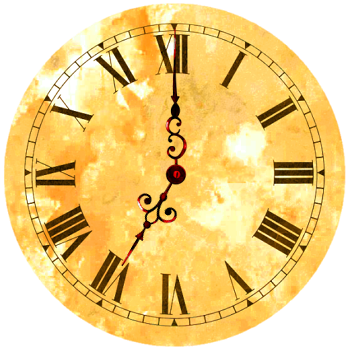
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映し出されるふたり。
チャットから消えるふたり。
チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!







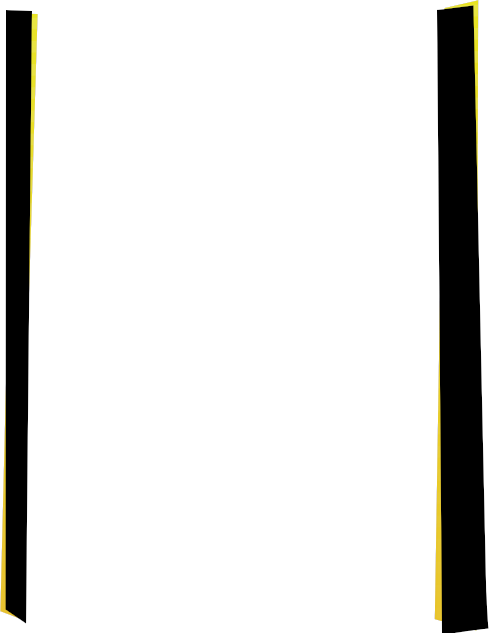
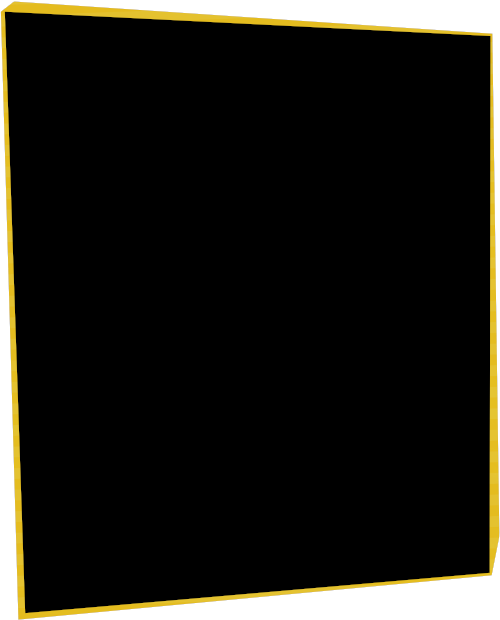





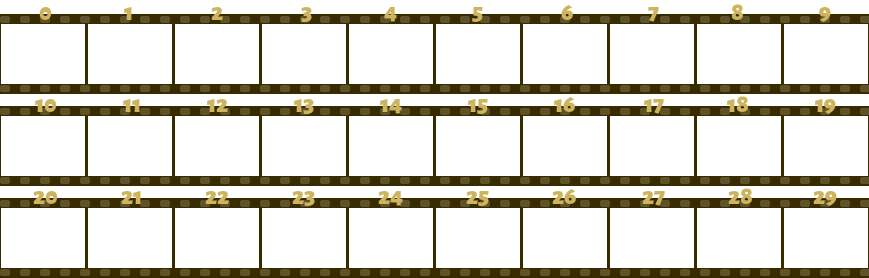







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




最初に見たのは、雨に濡れる母の姿。
母親というには若い、寧ろ幼い風貌の少女は腕の中にいる赤ん坊の目を見ていた。
「泣かないでね」
静かな声で言葉が紡がれる。
「暴れないでね」
少女はゆっくりと赤子を地面に下ろした。
「お願いだから、恨まないでね。」
それは懺悔であり、身勝手な願いであった。
言葉のわからない赤ん坊がそれを理解するはずはない。
けれど少女は目の前の赤子がきっと静かにしてくれるだろうと確信していた。
その言葉は、赤ん坊に与えられた最初の『命令』。
これからの土台となる絶対的なルールとなった。

「────────」
赤ん坊は泣きもせず、手を伸ばしもせず、足早に去っていく母親の姿を見つめていた。
捨てられた、などと理解するはずがない。
ただ、いくつかの言葉が自分には与えられたことを理解していた。
それは赤ん坊にとって、たった一つの『母からの愛』だった。
産声を上げることもなかった赤ん坊は、雨が降る街の中、施設の職員が発見するまで一言も声を発することがなかった。
これが、一つ目の幸運。
その赤子は手のかかる子供だった。
騒いだり、夜泣きしたりすることはない。
しかし、いちいち指示を出さなければ食事すらしないほど無気力だった。
赤子に宿った異能は強力な自己暗示。
どんな命令でも意味を理解すれば聞き入れるが、裏返せば命令が無ければ指先一つ動かせない。
『命令』によって泣き声を上げられない赤子は、自分の欲求を伝える術を持たなかった。
その『命令』によって生じた障害であることも、誰も知らない。
「いっそ殺してあげた方がいいんじゃないか」
「馬鹿なことを言わないの!」
「いつまでたっても自主性が芽生えないじゃないか。あれを生きていると言えるのか?」
「笑うことだってあるわ」
「それだって自分たちが教えた事だろう。あのまま成長したら行く先は碌なものじゃない」
「だからって……」
職員達の言い合いが聞こえても、赤子はそちらに意識を向けはしない。
いつしか赤子の首には異能制御のための機械が取り付けられていた。
施設にいる他の子どもが冗談で口にする「死んじゃえ」という言葉を真に受けて自分の首を絞めたことがあったからだ。
赤子の中にあるのは、母親の言葉と施設職員に言いつけられた一日の行動のみ。

泣かず、暴れず、恨みもせず。
制御装置に入力された一日のルーチンワークを忠実にこなす。
それだけの日々を二年間続けた。
結局処分されることもなく、施設の隅で生き続けた。
二歳になったある日、赤子の人生は一つの転機を迎えることになる。
施設を訪れたとある夫婦が、彼女を養子に迎えたいと申請してきたのだ。

「あなたは今日から御堂翠華になりますからね。」
綺麗な着物を着せられて、小さな手を握られて、しっかりと目を見て言葉が紡がれる。
「あなたは私たちの大切な娘なのですから、これからどうぞよろしくね。」
"はじめまして"はこれっきり。
数か月もしないうちに名前のなかった赤子は『御堂翠華』になっていった。
これが、二つ目の幸運。

生まれた時から見えていた"それ"が何なのか、終ぞ疑問に思うことはなかった。
何かをじっと見つめるとそれは現れた。
それが見えている時は、自分はそこにあるものを自由に動かすことができた。
おもちゃを引き寄せたり、折り紙を折ったり、冷蔵庫を開けてみたり。
重さも大きさも関係なく、あらゆるものを動かし、曲げて、回転させることができた。
それを見た両親はとても喜んでくれた。上手ね、すごいねと。
それが嬉しかったし、何より色々楽だったから、私はその異能を使い倒した。
どこまでいける?なにをやれる?
便利すぎるこの力の限界を知りたくて。
だから
こうなることは、仕方なかった。

少しのズレが、惨劇を招いた。
柱が折れて、木材が崩れて。
私に、降ってきた。
幽霊になって戻ってきたときには
そこにはもう、『御堂翠華』がいた。
(面倒なことになったなあ)
ハザマで目についた何かを曲げて投げてどかしながら進んでいく。
実際すり抜けるからその必要はないのだけれど、生き物をすり抜けるというのはなんとなく気持ちが悪い。
(誰にも私は見えてないみたい)
できることは通信機をジャックして短い言葉を飛ばすことのみ。
そこから場所を特定して、ようやく目当ての相手を見つけた。
『──コメット!』
地面を蹴って走る。
短い歩幅では追いつくのに時間がかかったけれど、息が切れることのない霊体は時間さえあれば歩いている人には追い付ける。
『コメット、わかる?見える?』
"妹"は進み続ける。
私に意識を向けることもない。
『……やっぱり、見えないのね』
しょんぼりと肩を落とす。
彼女ならあるいは、と思っていたのだけれど。
『そんな体でどこへ行くの』
飴のようになった体は見ていて痛々しい。
どこから砕けてしまうかわからない。
『止まって、止まってってば!』
なんとか治さなくては。
せめて休ませなければ。
彼女が戦わなくても戦争は続いていく。戦える人はたくさんいる。
失わせてはいけない。もう二度と、両親の"娘"を失わせるわけにはいかない。
私が守らなくてはいけないのだ。私にできることならなんだってして、彼女の存在を保たせなければ。
 |
亡霊:御堂翠華 「……うるさいんだけど、何。」 |
頭上から声がした。
真っ黒な着物に身を包んだ少女。
……御堂翠華だった頃のコメットだ。
 |
亡霊:御堂翠華 「いくら話しかけても聞こえないよ。 幽霊の声なんて聞こえるわけないんだから。」 |
 |
亡霊:御堂翠華 「私がいないとあなたはただの地縛霊。誰にも見えない霊体だもの。」 |
『あなたは、イバラシティで私の中にいた子ね。』
 |
亡霊:御堂翠華 「そんなこともあったね。 もうちょっと動きやすい体だったらよかったんだけど。」 |
 |
亡霊:御堂翠華 「……御堂翠華。 私は、あなたが羨ましかった。」 |
 |
亡霊:御堂翠華 「お父様もお母様も、私を通じてあなたを見ていた。 私はあなたになりたかった。 本当に娘として愛されたかった。」 |
 |
亡霊:御堂翠華 「──だから、嫌い。 何もできないのなら、早くどこかへ行って。」 |
そう言ったきり、彼女は顔を背けて歩き出した。
いくらハザマの生き物を倒しても、アンジニティからも見えない自分はこの戦いに貢献できない。
なにも、できない?
何も……
『そんなこと、あるものですか』
目元を拭って歩き出す。
何もできないなど、あるものか。
守ってみせる。私が必ず。
誰にも彼女を傷つけさせない。誰にも彼女を損なわせない。誰にも彼女に触れさせない。
ぎしり。
コメットの右肩が飴に置換された。



ENo.17 サクマ とのやりとり
| ▲ |
| ||||
| |||||
| |||
| |||
ENo.55 ゆい とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||
| |||||||||
| |||
ENo.195 天使様 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.216 ヒビキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.403 絶望の神器 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.555 持明院 寂怜 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.671 海の魔物 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1520 "大地の不純物" とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
まさこ 「……さっさと蹴散らそうぜ。 私のやる事は、それだけだ。」 |
| シュナイダー 「ぬぬぅ……!」 |
| シュナイダー 黑い巨神が唸る。 幾度の交戦の果てに、遂に知る顔と力を交えた。 共食い――それにも近いこの戦いは、思う所がある様だ。 |
| シュナイダー 「――、――。 行きましょう。 行くしか、ないですもんね。」 |
| シュナイダー 歩を、進める。絶対に。 例え悲しい結末でも、辛い結末でも。 それでも――。 |
| シュナイダー 自分が信ずる想いならば 悔いは残らない。 |
| シュナイダー せめて、無念が残らぬ様に。 自らの全てを以て――ぐっすり眠るために。 その歩は、止まる事を知らない。 |
ヒビキ(216) に ItemNo.14 エナジー棒 を手渡ししました。
勇者(551) から 木瓜 を手渡しされました。
| シュナイダー 「バナナです。」 |
ItemNo.13 エナジー棒 を食べました!
体調が 0 回復!(30⇒30)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!



Two sides of the same Coin
|
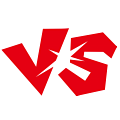 |
ハザマに生きるもの
|



1ターン目必殺おでん
|
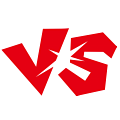 |
Two sides of the same Coin
|



武術LV を 15 DOWN。(LV15⇒0、+15CP、-15FP)
魔術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)
ヒビキ(216) により ItemNo.7 雑木 から射程3の武器『チェーホフの銃』を作製してもらいました!
⇒ チェーホフの銃/武器:強さ90/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
 |
ヒビキ 「だから何故雑木から銃が出来るんだ!」「僕に聞くなって!!」 |
ItemNo.14 木瓜 から装飾『木瓜の髪飾り』を作製しました!
⇒ 木瓜の髪飾り/装飾:強さ90/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-
勇者(551) の持つ ItemNo.11 不思議な雫 から装飾『目薬』を作製しました!
勇者(551) により ItemNo.6 何か柔らかい物体 から防具『シン・ゴリラの着ぐるみ』を作製してもらいました!
⇒ シン・ゴリラの着ぐるみ/防具:強さ60/[効果1]命脈10 [効果2]- [効果3]-
| シュナイダー 「――、――。」 |
| シュナイダー 「……!」 |
| シュナイダー 「Oh...Gorilla――。」 |
| シュナイダー 「コメットさん。 分かりますね?」 え、何。 |
| シュナイダー 「アンジニティせんめつビームです。」 つっよ。 ※そんなものは出ません。 |
レオン(974) とカードを交換しました!
雪景色のカード (スノードロップ)
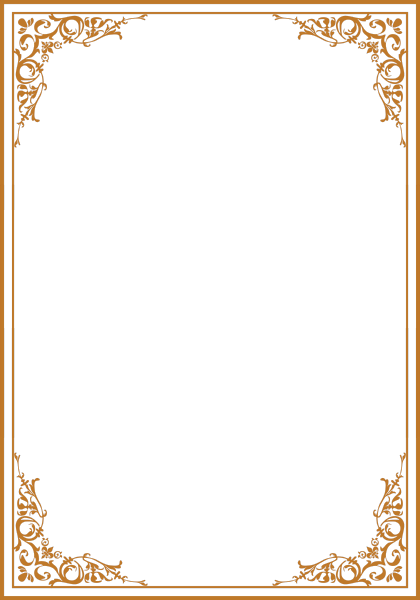
ポーションラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度1⇒2)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度2⇒3)
リフレクション を習得!
ファイアレイド を習得!
ヘイルカード を習得!
クイックレメディ を習得!
ファイアボルト を習得!
ガーディアン を習得!
カタラクト を習得!
オイルファイア を習得!
クリムゾンスカイ を習得!
スノードロップ を習得!
ウィルスゾーン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ヒビキ(216) は 鉄板 を入手!
コメット(253) は 鉄板 を入手!
まさこ(281) は 鉄板 を入手!
勇者(551) は 雑木 を入手!
まさこ(281) は 羽 を入手!
ヒビキ(216) は 羽 を入手!
まさこ(281) は 花びら を入手!
ヒビキ(216) は 毛 を入手!



チナミ区 G-16(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-16(山岳)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-16(山岳)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-16(山岳)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- コメット(253) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》 を選択!
- コメット(253) の選択は カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》





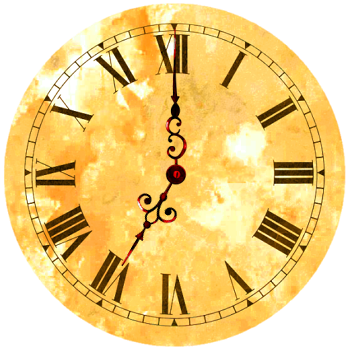
[770 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[336 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[145 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[31 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「うんうん、順調じゃねーっすか。 あとやっぱうるせーのは居ねぇほうが断然いいっすね。」 |
 |
白南海 「いいから早くこれ終わって若に会いたいっすねぇまったく。 もう世界がどうなろうと一緒に歩んでいきやしょうワカァァ――」 |

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
 |
カグハ 「・・・わ、変なひとだ。」 |
 |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
チャット画面に映し出されるふたり。
 |
白南海 「――ん、んんッ・・・・・ ・・・なんすか。 お前らは・・・あぁ、梅楽園の団子むすめっこか。」 |
 |
カオリ 「チャットにいたからお邪魔してみようかなって!ごあいさつ!!」 |
 |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
 |
白南海 「勝手に人の部屋に入るもんじゃねぇぞ、ガキンチョ。」 |
 |
カオリ 「勝手って、みんなに発信してるじゃんこのチャット。」 |
 |
カグハ 「・・・寂しがりや?」 |
 |
白南海 「・・・そ、操作ミスってたのか。クソ。・・・クソ。」 |
 |
白南海 「そういや、お前らは・・・・・ロストじゃねぇんよなぁ?」 |
 |
カグハ 「違うよー。」 |
 |
カオリ 「私はイバラシティ生まれのイバラシティ育ち!」 |
 |
白南海 「・・・・・は?なんだこっち側かよ。 だったらアンジニティ側に団子渡すなっての。イバラシティがどうなってもいいのか?」 |
 |
カオリ 「あ、・・・・・んー、・・・それがそれが。カグハちゃんは、アンジニティ側なの。」 |
 |
カグハ 「・・・・・」 |
 |
白南海 「なんだそりゃ。ガキのくせに、破滅願望でもあんのか?」 |
 |
カグハ 「・・・・・その・・・」 |
 |
カオリ 「うーあーやめやめ!帰ろうカグハちゃん!!」 |
 |
カオリ 「とにかく私たちは能力を使ってお団子を作ることにしたの! ロストのことは偶然そうなっただけだしっ!!」 |
 |
カグハ 「・・・カオリちゃん、やっぱり私――」 |
 |
カオリ 「そ、それじゃーね!バイビーン!!」 |
チャットから消えるふたり。
 |
白南海 「・・・・・ま、別にいいんすけどね。事情はそれぞれ、あるわな。」 |
 |
白南海 「でも何も、あんな子供を巻き込むことぁねぇだろ。なぁ主催者さんよ・・・」 |
チャットが閉じられる――







唯1人の男、アレク・リーズ!
|
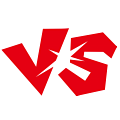 |
ウホウホ動物探検隊
|




カミセイ区 H-4
チェックポイント《森の学舎》
チェックポイント。チェックポイント《森の学舎》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《SNAKE》
黒闇に包まれた巨大なヘビのようなもの。
 |
守護者《SNAKE》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!



ウホウホ動物探検隊
|
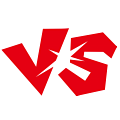 |
立ちはだかるもの
|


ENo.253
彗星・コメット

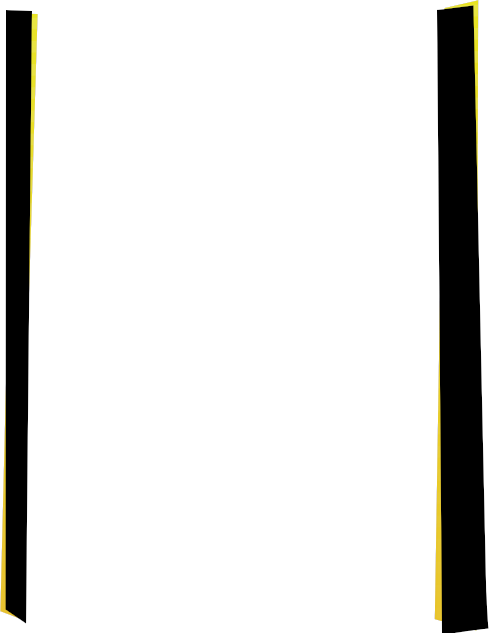
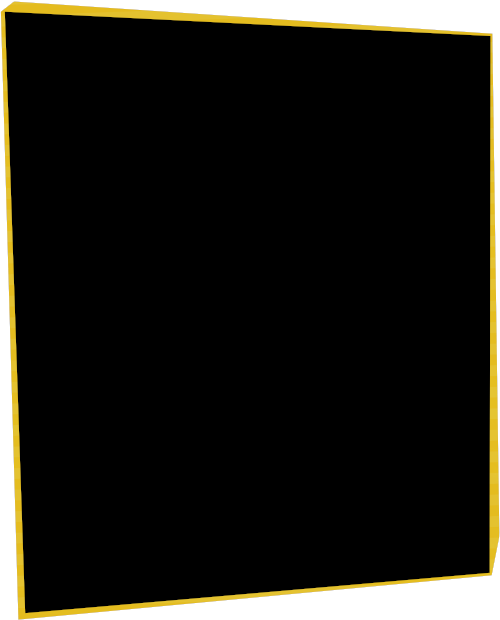
「あたしはコメット。咲魔式の後継者でトレジャーハンターさ。」
────彼女のプロフィールは、大部分が嘘でできている。
名前:コメット・エーデルシュタイン
年齢:16歳
身長:155cm
体重:49kg
誕生日:3月9日
性別:女性
武器:銃
学ランに着物にスチームパンクという異な出で立ちの少女。飄々とした性格、まるで舞台の上に立っているかのような身振りをする。いつも近くにいる黒猫を「お義父様」「先代」と呼んでいる。
家では飴屋『ほうきぼし』を営んでおり、外にいる時も飴玉を缶に入れて持ち歩いている。店員としての性格は明るく大和撫子。
学校では優等生のような振る舞いをしている。事実頭はいい。
両親はどちらも生みの親ではないらしく、説明する時は「スラム街で捨てられたところを魔女に気まぐれ拾われた」と言っている。その気まぐれがいつ消えてもいいように、身の回りの事は全て自分で出来るようにしている。
異能:『咲魔式』飴玉を用いた魔法
咲魔式の戦闘方式として飴玉を弾丸として用いる。飴玉の味、素材によって様々な効果をもたらす。現在投薬による異能改造が途切れているため、不完全な状態で発動している。専用の銃を用いなければ発動できない。
咲魔式:特殊な戦闘流派。先代はニフリート。飴玉を弾丸として用いる戦闘方法が特徴。通常の弾丸では不可能なトリッキーな戦い方ができる。コメットは咲魔式を扱える素養が異能として備わっていたらしい。
巽燈史郎(ENo.282)とは恋人関係(一応)
お店→http://lisge.com/ib/talk.php?p=386
全身図→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=comet.png
店員→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=coshop.png
「俺の娘だ。すごくねえわけねぇだろが。」
名前:ニフリート
性別:オス
コメットのそばにいつもいる黒猫。コメットには「お義父様」と呼ばれている。咲魔式の先代当主だったが、跡継ぎを残せぬまま老衰。死ぬ寸前に魔女と契約し、跡継ぎを探す旅を続けていた。姿を猫に変えられてしまっているためか言動もかなり猫。声が渋い。
サブ
魔女
大きな帽子をかぶった女性。コメットの義母という立ち位置だが、感情が薄く母親らしいことは何もしていない。花と宝石にまつわる魔女であり、歩いた後に宝石でできた花を咲かせたり、花を使って不思議な魔法を扱う。
ただし、本物の花は咲かせることができない。
御堂すいか(仮)
性別:女性
享年:3歳
御堂呉服店に住み着いている地縛霊。コメットと姿がよく似ているが、瞳の色は茶色。異能の暴発により死亡している。ものぐさ。
異能:テレキネシス
対象を好きな場所へ移動させたり曲げたりできる異能。脳への負担が大きいため、対象にXYZ軸を指定して、決めた方向へ動かすことができるように設定している。
「あたしは、コメット・エーデルシュタインだ。それがいい。」
偽名:コメット・エーデルシュタイン
本名:????
年齢:15歳(戸籍より一つ下。)
誕生日:5月22日(保護日)、11月28日(コメットとしての自我形成日)
捨て子。施設で2歳まで育てられ、御堂家の両親に亡くなった娘の代わりにと引き取られる。名前は無くなった娘と同じ『御堂翠華』である。
御堂家とはイバラシティに存在した名家である。
古くから呉服屋を営むその家で翠華は一人娘として育てられた。
礼儀作法を教えこまえ、両親に蝶よ花よと育てられた彼女は自らの異能も知らないまま無垢で純粋に育つ。
誰かの役に立ちたい、いつか家を継ぐものとして恥ずかしくない者でありたいと思っていたところに魔女と黒猫から咲魔式を継いで欲しいと持ちかけられる。
自らの異能が誰かの役に立つならば、と彼女はその願いを了承し、その旨を親に話しに行った。
かつての異能:『夢幻泡飴』
御堂翠華は飴が好きだったという事実と、本人の持つ『瞳への執着』が混ぜ合わさって生まれた異能。触れたものを時間ごと止めて飴玉に変えてしまう。美しいものは美しいままに。ずっと手の届く場所へ。発動した当時から今まで常に暴走状態である。
正しい異能:『白紙の役者』(タイトル・ロール・エトワール)
台本通りに演じ切る役者。何度でも書き換え可能の台本。端的に言って超強力な自己暗示。
『主』を設定し、その主が望んだように自身の思考、行動、異能さえ変革する異能。本人の羞恥や違和感も消し飛ばし、演じることができる。外見も時間はかかるが変更することができる。(髪の色、目の形など)
母親に「泣かず暴れない赤ん坊であれ」と願われればその通りに。御堂呉服店の夫婦に「御堂翠華であれ」と願われればその通りに演じ切った。『主』の対象は自分であっても構わない。
この異能には『観察』と『情報』が大きく作用する。「御堂翠華であれ」と願われた際に異能の情報を知らなかったため、御堂翠華本来の異能とは別の異能が備わった。同様に、他者を模倣した際に異能の効果を正確に把握していない場合は異能の模倣はできない。つまり基本的に知らないものを模倣することはできない。近づけたとしても『その異能を真似た別のもの』でしかない。
デメリット
・『主』を設定しないことはできない。もし設定しない場合生命活動のみを続ける抜け殻になってしまう。
・リソースは限られているためあまり過度な役を充てられると他の能力が大幅に落ちる。
・『主』を変える意志を奪われた場合自分では主を変えられない。
異能の使用例:めちゃくちゃ辛いものを食べる時に『主』を自分に設定。内容を『平然と食べる人』に設定。するとポーカーフェイスで辛いものを食べられるが、辛いものが嫌い過ぎた場合喋る能力が失われる。
SIDE:ANSINITY
名前:御堂翠華
年齢:6歳
魔女と黒猫に出会うことが無かったコメットのIF。世界の半分を飴玉に変えてしまい、否定の世界へ追放された。
この世界に来るにあたり、『コメットの過去の亡霊』として呉服店に固定されてしまった。元からそこに住む地縛霊『御堂すいか』の体を借りている。
ハザマでは両親を元に戻すことを条件に渋々ながらコメットに協力している。
異能:『夢幻泡飴』触れたものを飴玉に変える異能
彼女は両親の手を握った。自分をまっすぐに見つめる瞳が美しいと思った。
いつまでも、近くで眺めていたかった。
気づいたら、両親の姿はなかった。両親は娘の異能によって飴玉に変えられてしまったのだ。
アンジニティに落ちた時点で、彼女の異能は夢幻泡飴に固定されている。
ハザマにおいて、コメットの体は少しずつ飴に置換されていく。
────彼女のプロフィールは、大部分が嘘でできている。
名前:コメット・エーデルシュタイン
年齢:16歳
身長:155cm
体重:49kg
誕生日:3月9日
性別:女性
武器:銃
学ランに着物にスチームパンクという異な出で立ちの少女。飄々とした性格、まるで舞台の上に立っているかのような身振りをする。いつも近くにいる黒猫を「お義父様」「先代」と呼んでいる。
家では飴屋『ほうきぼし』を営んでおり、外にいる時も飴玉を缶に入れて持ち歩いている。店員としての性格は明るく大和撫子。
学校では優等生のような振る舞いをしている。事実頭はいい。
両親はどちらも生みの親ではないらしく、説明する時は「スラム街で捨てられたところを魔女に気まぐれ拾われた」と言っている。その気まぐれがいつ消えてもいいように、身の回りの事は全て自分で出来るようにしている。
異能:『咲魔式』飴玉を用いた魔法
咲魔式の戦闘方式として飴玉を弾丸として用いる。飴玉の味、素材によって様々な効果をもたらす。現在投薬による異能改造が途切れているため、不完全な状態で発動している。専用の銃を用いなければ発動できない。
咲魔式:特殊な戦闘流派。先代はニフリート。飴玉を弾丸として用いる戦闘方法が特徴。通常の弾丸では不可能なトリッキーな戦い方ができる。コメットは咲魔式を扱える素養が異能として備わっていたらしい。
巽燈史郎(ENo.282)とは恋人関係(一応)
お店→http://lisge.com/ib/talk.php?p=386
全身図→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=comet.png
店員→http://tyaunen.moo.jp/txiloda/picture.php?user=arusu007&file=coshop.png
「俺の娘だ。すごくねえわけねぇだろが。」
名前:ニフリート
性別:オス
コメットのそばにいつもいる黒猫。コメットには「お義父様」と呼ばれている。咲魔式の先代当主だったが、跡継ぎを残せぬまま老衰。死ぬ寸前に魔女と契約し、跡継ぎを探す旅を続けていた。姿を猫に変えられてしまっているためか言動もかなり猫。声が渋い。
サブ
魔女
大きな帽子をかぶった女性。コメットの義母という立ち位置だが、感情が薄く母親らしいことは何もしていない。花と宝石にまつわる魔女であり、歩いた後に宝石でできた花を咲かせたり、花を使って不思議な魔法を扱う。
ただし、本物の花は咲かせることができない。
御堂すいか(仮)
性別:女性
享年:3歳
御堂呉服店に住み着いている地縛霊。コメットと姿がよく似ているが、瞳の色は茶色。異能の暴発により死亡している。ものぐさ。
異能:テレキネシス
対象を好きな場所へ移動させたり曲げたりできる異能。脳への負担が大きいため、対象にXYZ軸を指定して、決めた方向へ動かすことができるように設定している。
「あたしは、コメット・エーデルシュタインだ。それがいい。」
偽名:コメット・エーデルシュタイン
本名:????
年齢:15歳(戸籍より一つ下。)
誕生日:5月22日(保護日)、11月28日(コメットとしての自我形成日)
捨て子。施設で2歳まで育てられ、御堂家の両親に亡くなった娘の代わりにと引き取られる。名前は無くなった娘と同じ『御堂翠華』である。
御堂家とはイバラシティに存在した名家である。
古くから呉服屋を営むその家で翠華は一人娘として育てられた。
礼儀作法を教えこまえ、両親に蝶よ花よと育てられた彼女は自らの異能も知らないまま無垢で純粋に育つ。
誰かの役に立ちたい、いつか家を継ぐものとして恥ずかしくない者でありたいと思っていたところに魔女と黒猫から咲魔式を継いで欲しいと持ちかけられる。
自らの異能が誰かの役に立つならば、と彼女はその願いを了承し、その旨を親に話しに行った。
かつての異能:『夢幻泡飴』
御堂翠華は飴が好きだったという事実と、本人の持つ『瞳への執着』が混ぜ合わさって生まれた異能。触れたものを時間ごと止めて飴玉に変えてしまう。美しいものは美しいままに。ずっと手の届く場所へ。発動した当時から今まで常に暴走状態である。
正しい異能:『白紙の役者』(タイトル・ロール・エトワール)
台本通りに演じ切る役者。何度でも書き換え可能の台本。端的に言って超強力な自己暗示。
『主』を設定し、その主が望んだように自身の思考、行動、異能さえ変革する異能。本人の羞恥や違和感も消し飛ばし、演じることができる。外見も時間はかかるが変更することができる。(髪の色、目の形など)
母親に「泣かず暴れない赤ん坊であれ」と願われればその通りに。御堂呉服店の夫婦に「御堂翠華であれ」と願われればその通りに演じ切った。『主』の対象は自分であっても構わない。
この異能には『観察』と『情報』が大きく作用する。「御堂翠華であれ」と願われた際に異能の情報を知らなかったため、御堂翠華本来の異能とは別の異能が備わった。同様に、他者を模倣した際に異能の効果を正確に把握していない場合は異能の模倣はできない。つまり基本的に知らないものを模倣することはできない。近づけたとしても『その異能を真似た別のもの』でしかない。
デメリット
・『主』を設定しないことはできない。もし設定しない場合生命活動のみを続ける抜け殻になってしまう。
・リソースは限られているためあまり過度な役を充てられると他の能力が大幅に落ちる。
・『主』を変える意志を奪われた場合自分では主を変えられない。
異能の使用例:めちゃくちゃ辛いものを食べる時に『主』を自分に設定。内容を『平然と食べる人』に設定。するとポーカーフェイスで辛いものを食べられるが、辛いものが嫌い過ぎた場合喋る能力が失われる。
SIDE:ANSINITY
名前:御堂翠華
年齢:6歳
魔女と黒猫に出会うことが無かったコメットのIF。世界の半分を飴玉に変えてしまい、否定の世界へ追放された。
この世界に来るにあたり、『コメットの過去の亡霊』として呉服店に固定されてしまった。元からそこに住む地縛霊『御堂すいか』の体を借りている。
ハザマでは両親を元に戻すことを条件に渋々ながらコメットに協力している。
異能:『夢幻泡飴』触れたものを飴玉に変える異能
彼女は両親の手を握った。自分をまっすぐに見つめる瞳が美しいと思った。
いつまでも、近くで眺めていたかった。
気づいたら、両親の姿はなかった。両親は娘の異能によって飴玉に変えられてしまったのだ。
アンジニティに落ちた時点で、彼女の異能は夢幻泡飴に固定されている。
ハザマにおいて、コメットの体は少しずつ飴に置換されていく。
30 / 30
291 PS
チナミ区
D-2
D-2






































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | タッセルイヤリング | 装飾 | 20 | 体力10 | - | - | |
| 5 | キャノンドロップス | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | シン・ゴリラの着ぐるみ | 防具 | 60 | 命脈10 | - | - | |
| 7 | チェーホフの銃 | 武器 | 90 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 8 | ゴリー・スーツ | 防具 | 40 | 体力10 | - | - | |
| 9 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 10 | 狐のキーホルダー | 装飾 | 45 | 回復10 | - | - | |
| 11 | フランケンシュタインの復讐 | 装飾 | 82 | 舞乱10 | - | - | |
| 12 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 13 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
| 14 | 木瓜の髪飾り | 装飾 | 90 | 器用10 | - | - | |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 装飾 | 50 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 練3 | ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 |
| ヒールポーション | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| 練3 | カームフレア | 6 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| フィーバー | 6 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| リフレッシュ | 6 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アクアリカバー | 6 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| 練3 | ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| ヒールハーブ | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| アクアヒール | 6 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 練3 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| パワフルポーション | 5 | 0 | 120 | 自:AT・DF増+猛毒・麻痺・衰弱 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| オイルファイア | 5 | 0 | 120 | 敵:火撃&炎上状態なら火領撃 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| オートヒール | 6 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| チャクラグラント | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 | |
| パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| ヒールミスト | 5 | 0 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程3以上ならDX減(2T) | |
| 練3 | アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
| インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 | |
| クライオセラピー | 5 | 0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 水の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 医食同源 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:食事による付加効果のLV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
守護天使 (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 練3 |
ヘイルカードかーど (ヘイルカード) |
0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
|
オゾン水 (アクアヒール) |
0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
|
芽吹き (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 | |
| 練3 |
ミーシャ・ハードブレイク (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
| 練3 |
こおりぼし (アイシクルランス) |
0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
|
雪景色のカード (スノードロップ) |
0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ファイアボルト | [ 1 ]五月雨 | [ 1 ]フェイタルポイント |
| [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]ハードブレイク | [ 1 ]コールドウェイブ |
| [ 1 ]ウォーターフォール | [ 1 ]ヘイルカード | [ 1 ]ビブラート |
| [ 3 ]ポーションラッシュ | [ 1 ]リンクブレイク | [ 1 ]クリエイト:グレイル |
| [ 1 ]パワフルヒール | [ 1 ]ダークネス | [ 2 ]チェインリアクト |
| [ 1 ]デアデビル | [ 2 ]カームフレア |

PL / アルス