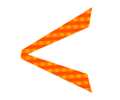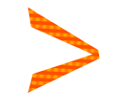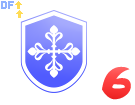<< 1:00~2:00




講堂には、既に人が多く集まっていた。
殆どは子供であったが、中には大人も混ざっている。子供が多いのは、当然のことだ。子供たちは毎日『講堂』に来ることが義務付けられている。大人として認められたのであれば、それが10日に1度で許されるようになる。
『橙』は極力 前の方に、『黒』は不自然で無い範囲で後ろの方に それぞれ陣取る。
『橙』は左右を見る。どちらも自分より年下、特に左には 教育を受け始めたばかりくらいの 6つか7つ程度の年頃の子供で、左右の手を灰まみれにしている。
「(灰数えの役、それも今日が初めてか)」
左の子供がガタガタ震える中、『橙』は淡々と考える。灰数えとは、まだ調和竜信仰が上手く植え付けられていないうちに課せられる、早朝の苦行である。何をするのかと言えば至極単純、文字通り灰を数えるだけである。数えた数の成否は問われない。数え方にも決まりは無い。意味等、無い。
ある程度成長してから、この苦行に意味が無かったと知る。そのころには、『無意味であることが意義』だと教えられる。最初のうちに限った話だが、調和竜の意志を受け取るために 疑問を思い浮かべるような知性を『破壊する』必要があるのだと。
大半の人間は、それを素晴らしいと表現した。だからこそ『橙』は、
「(……もっと違う手で、信仰を伝えることは出来ないのか)」
そんなことを、言葉に出来る筈無い。
信仰を広めること自体に異論はなかったが。
背後からは、会話が聞こえる。
『橙』は、耳を傾ける。ここは最も多くの年齢、職業の人間が集まる。普段聞けない会話が聞こえる。
「聞いた? さっきの通達」
「また『竜殺し』が出たそうですね」
「調和竜がそんな役目を与えるなんて……」
「愚か者。調和竜はこの国の平和を考えて役目をくれる。国を乱すような、ましてや調和竜に背くような役割を与える筈がありません。つまり彼らは勝手に背いて勝手に荒らしまわっていることになります」
「しかし、調和竜は僕たちひとりひとりに見合った役割を与えている。反逆因子になるような輩が現れる筈がない」
「ええ、あなたの言う通り、反逆因子が生まれる筈は無いのです。調和竜はこの国の平和のために、人々に役目を与えている」
「だが、この現実は何だ? 実際に『竜殺し』は存在して、実際に『守護者』が被害に遭っているだろう。そして 勝手に背くような人間が存在しない以上、『竜殺し』は調和竜によって 与えられた役割のひとつとしか……」
「何を言っているのですか、反逆因子が生まれる筈なんてありません。調和竜はこの国の平和のために……」
『橙』はこの辺りで、背後の会話から意識を背けた。破綻した、それも似たような会話が繰り返されるばかりで、これ以上は身にならないと感じたから。
『竜殺し』とは、予てより存在する反逆集団だ。『神子』や『守護者』等、竜に近しい役割を持つ者に対して繰り返し攻撃を仕掛けている。『竜殺し』と呼ばれてはいるが、実際に竜を殺した実績があるわけではない。それは彼らの最終目標だ。それは愚かなことであると、この国の人間は殆どに周知されている。
別の場所から、違う会話も聞こえてくる。視線を動かせば、頭からつま先まで灰まみれの服を着た 小柄な人間。おそらく、『灰掻き』だ。
「ケホ、ケホ、……なにかきこえるね」
「きこえる。りゅうごろし?」
「りゅうごろしってなあに?」
「わたし、わかんない」
「ぼく、知ってるよ! さっき、神子さまからきいたんだ。りゅうごろしっていうのは、ごあいさつ!」
「ごあいさつ?……ケホッ、ケホッ」
「そう、ごあいさつ。だから、『中』ではたらく人たちは、ひとと会ったら りゅうごろしって言うんだ!」
「へぇー。マロンは ケホッ、かしこいなあ。……ん、ん。わたしも、ごあいさつ、する。 りゅうごろしー」
「りゅうごろしー」
会話を聞いて、間違いなく『灰掻き』だと確信する。
彼らは『内側』の情報を一部統制していると。そんな噂を耳にしたことがある。また、ひとり 頻繁に咳き込んでいる声がした。これも、『灰掻き』の特徴。
しかしここで、違和感を覚える『橙』だ。『灰掻き』は職業だ、つまり彼らは皆 一人前と認められた存在で、『橙』よりも年上の可能性がある。
それにしては、妙に会話が幼いような。
それだけではない。マロンと呼ばれていた1人は先ほど『神子さまからきいた』と言っていた。頻繁に咳き込んでいたものは、それを忘れてしまったかのように マロンは賢い と評していた。
それが何を意味しているのか、『橙』には分からなかった。
それ以上考えることも、許されなかった。――今日の『神子』の、準備が終わったのだ。
『神子』によっては、それを始める前に 演説をする者もいるのだが、ネージュという神子はそういった時間を好まないらしい。講堂が静かになったタイミングで、書物を開く。
「――灰被る国の民 全てへと向けて、色無き竜は仰せになった」
講堂の空気が青く染まった、そんな感覚がした。
無論、実際に空気が染まったとは限らない。しかしその場にいる人間にとって、それが事実か幻か どうでもいいことなのだ。
ただ、心を無にして その言葉を受け止める。
『橙』も、委ねている。いつものように。考えることを放棄して。
そうする、筈だったのだ。
「灰被る国の外に御座す4柱の竜どもは、今なお 争いを続ける。衰えれば狂い、栄えれば暴れ、何れにせよ人の世を蝕む。よって、4竜の上に立つ 色無き竜は この灰被る国を興した。―― いつ調和が乱れても、正せるように。『英雄』を世に出せるように。そこから 色無き竜は『調和竜』とも呼ばれた」
読み上げ始めてそれほど経たずして、『橙』のすぐ左にいた子供が蹲った。
それはひどく目立つ動きだ。なにせ、今は皆 『神子』の言葉を聞くことに夢中になっていた。それだけではない。言葉を聞く以外のことを今 やってもいいのだと、言ってくれる者は誰もいない。だから、動く者はいない。
「おい、大丈夫か」
『橙』にも、どうして自分がそうしたのか 分からない。
「嘗ては『点繋ぐ英雄』の生誕を待つのみであった。しかし、外に住まう黒き竜は幾度となく立ち上がり続け、終いには英雄が生まれるよりも早く調和を乱すに至った。故に色無き竜は、灰被る国を『英雄の国』と定めた。英雄で在れ、英雄と成れ」
そうしている間にも、神子の言葉は続いている。
『橙』はその子供を助けなくては、そんな感情が塗りつぶされようとしている。
分からない。どうして話しかけた。
助けたいということにわざわざ理由が無くてはいけないのか。
人が苦しむところは苦手なだけ、そのためにはどんな手を使ったって、
今は駄目だ、『神子』の言葉を聴かなくては。
苦しんでいる、助けなくては、
『神子』の言葉を聴かなくては。
思考が乱れ、今度は『橙』が膝をついた。
「誰か、……、くそ、『守護者』か『癒し手』は、いないのか……!?」
叫んだつもりだったが、あまりに小さな声しか出ない。
喩え叫ぶことが出来ていたとしても、動く者はいない筈だと、知っている。
それでも今出来るのはそれだけだ。
やがて、誰かが 子供を抱きかかえていく姿が見えた。
「――僕と違って、もう遅いんだよ。人参。テメェはそこでぼんやり頭融かしてりゃいい」
そんな声が聞こえた気がした。黒い髪をしていた気がするが、顔はよく見ていない。
誰であろうとどうでもいい。
抗うことをやめれば思考の乱れも消えたし、そもそもどうして抗おうとしたのかも考えられなくなっていた。
せんのう
あの子供はどうなったのか、無事なのか。そんな感情は 信仰 にかき消された。



ENo.9 タマキ とのやりとり

ENo.181 ガガミネ とのやりとり

ENo.388 ユイノ とのやりとり

ENo.428 晴 とのやりとり

ENo.434 ピザ子 とのやりとり

ENo.526 悠吏 とのやりとり

ENo.565 戌亥縫 とのやりとり

以下の相手に送信しました













武術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
シエ(11) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『calida印のジャンボパフェ』をつくってもらいました!
⇒ calida印のジャンボパフェ/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
シエ(11) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『カルビ肉』をつくってもらいました!
⇒ カルビ肉/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
仏の男(950) とカードを交換しました!
ペッカー光るやつ (カレイドスコープ)


プロテクション を研究しました!(深度0⇒1)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
ヴィガラスチャージ を研究しました!(深度1⇒2)
チャージ を習得!
カウンター を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調16⇒15)
採集はできませんでした。
- 一穂(3) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



講堂には、既に人が多く集まっていた。
殆どは子供であったが、中には大人も混ざっている。子供が多いのは、当然のことだ。子供たちは毎日『講堂』に来ることが義務付けられている。大人として認められたのであれば、それが10日に1度で許されるようになる。
『橙』は極力 前の方に、『黒』は不自然で無い範囲で後ろの方に それぞれ陣取る。
『橙』は左右を見る。どちらも自分より年下、特に左には 教育を受け始めたばかりくらいの 6つか7つ程度の年頃の子供で、左右の手を灰まみれにしている。
「(灰数えの役、それも今日が初めてか)」
左の子供がガタガタ震える中、『橙』は淡々と考える。灰数えとは、まだ調和竜信仰が上手く植え付けられていないうちに課せられる、早朝の苦行である。何をするのかと言えば至極単純、文字通り灰を数えるだけである。数えた数の成否は問われない。数え方にも決まりは無い。意味等、無い。
ある程度成長してから、この苦行に意味が無かったと知る。そのころには、『無意味であることが意義』だと教えられる。最初のうちに限った話だが、調和竜の意志を受け取るために 疑問を思い浮かべるような知性を『破壊する』必要があるのだと。
大半の人間は、それを素晴らしいと表現した。だからこそ『橙』は、
「(……もっと違う手で、信仰を伝えることは出来ないのか)」
そんなことを、言葉に出来る筈無い。
信仰を広めること自体に異論はなかったが。
背後からは、会話が聞こえる。
『橙』は、耳を傾ける。ここは最も多くの年齢、職業の人間が集まる。普段聞けない会話が聞こえる。
「聞いた? さっきの通達」
「また『竜殺し』が出たそうですね」
「調和竜がそんな役目を与えるなんて……」
「愚か者。調和竜はこの国の平和を考えて役目をくれる。国を乱すような、ましてや調和竜に背くような役割を与える筈がありません。つまり彼らは勝手に背いて勝手に荒らしまわっていることになります」
「しかし、調和竜は僕たちひとりひとりに見合った役割を与えている。反逆因子になるような輩が現れる筈がない」
「ええ、あなたの言う通り、反逆因子が生まれる筈は無いのです。調和竜はこの国の平和のために、人々に役目を与えている」
「だが、この現実は何だ? 実際に『竜殺し』は存在して、実際に『守護者』が被害に遭っているだろう。そして 勝手に背くような人間が存在しない以上、『竜殺し』は調和竜によって 与えられた役割のひとつとしか……」
「何を言っているのですか、反逆因子が生まれる筈なんてありません。調和竜はこの国の平和のために……」
『橙』はこの辺りで、背後の会話から意識を背けた。破綻した、それも似たような会話が繰り返されるばかりで、これ以上は身にならないと感じたから。
『竜殺し』とは、予てより存在する反逆集団だ。『神子』や『守護者』等、竜に近しい役割を持つ者に対して繰り返し攻撃を仕掛けている。『竜殺し』と呼ばれてはいるが、実際に竜を殺した実績があるわけではない。それは彼らの最終目標だ。それは愚かなことであると、この国の人間は殆どに周知されている。
別の場所から、違う会話も聞こえてくる。視線を動かせば、頭からつま先まで灰まみれの服を着た 小柄な人間。おそらく、『灰掻き』だ。
「ケホ、ケホ、……なにかきこえるね」
「きこえる。りゅうごろし?」
「りゅうごろしってなあに?」
「わたし、わかんない」
「ぼく、知ってるよ! さっき、神子さまからきいたんだ。りゅうごろしっていうのは、ごあいさつ!」
「ごあいさつ?……ケホッ、ケホッ」
「そう、ごあいさつ。だから、『中』ではたらく人たちは、ひとと会ったら りゅうごろしって言うんだ!」
「へぇー。マロンは ケホッ、かしこいなあ。……ん、ん。わたしも、ごあいさつ、する。 りゅうごろしー」
「りゅうごろしー」
会話を聞いて、間違いなく『灰掻き』だと確信する。
彼らは『内側』の情報を一部統制していると。そんな噂を耳にしたことがある。また、ひとり 頻繁に咳き込んでいる声がした。これも、『灰掻き』の特徴。
しかしここで、違和感を覚える『橙』だ。『灰掻き』は職業だ、つまり彼らは皆 一人前と認められた存在で、『橙』よりも年上の可能性がある。
それにしては、妙に会話が幼いような。
それだけではない。マロンと呼ばれていた1人は先ほど『神子さまからきいた』と言っていた。頻繁に咳き込んでいたものは、それを忘れてしまったかのように マロンは賢い と評していた。
それが何を意味しているのか、『橙』には分からなかった。
それ以上考えることも、許されなかった。――今日の『神子』の、準備が終わったのだ。
『神子』によっては、それを始める前に 演説をする者もいるのだが、ネージュという神子はそういった時間を好まないらしい。講堂が静かになったタイミングで、書物を開く。
「――灰被る国の民 全てへと向けて、色無き竜は仰せになった」
講堂の空気が青く染まった、そんな感覚がした。
無論、実際に空気が染まったとは限らない。しかしその場にいる人間にとって、それが事実か幻か どうでもいいことなのだ。
ただ、心を無にして その言葉を受け止める。
『橙』も、委ねている。いつものように。考えることを放棄して。
そうする、筈だったのだ。
「灰被る国の外に御座す4柱の竜どもは、今なお 争いを続ける。衰えれば狂い、栄えれば暴れ、何れにせよ人の世を蝕む。よって、4竜の上に立つ 色無き竜は この灰被る国を興した。―― いつ調和が乱れても、正せるように。『英雄』を世に出せるように。そこから 色無き竜は『調和竜』とも呼ばれた」
読み上げ始めてそれほど経たずして、『橙』のすぐ左にいた子供が蹲った。
それはひどく目立つ動きだ。なにせ、今は皆 『神子』の言葉を聞くことに夢中になっていた。それだけではない。言葉を聞く以外のことを今 やってもいいのだと、言ってくれる者は誰もいない。だから、動く者はいない。
「おい、大丈夫か」
『橙』にも、どうして自分がそうしたのか 分からない。
「嘗ては『点繋ぐ英雄』の生誕を待つのみであった。しかし、外に住まう黒き竜は幾度となく立ち上がり続け、終いには英雄が生まれるよりも早く調和を乱すに至った。故に色無き竜は、灰被る国を『英雄の国』と定めた。英雄で在れ、英雄と成れ」
そうしている間にも、神子の言葉は続いている。
『橙』は
分からない。どうして話しかけた。
人が苦しむところは苦手なだけ、そのためには
今は駄目だ、『神子』の言葉を聴かなくては。
『神子』の言葉を聴かなくては。
思考が乱れ、今度は『橙』が膝をついた。
「誰か、……、くそ、『守護者』か『癒し手』は、いないのか……!?」
叫んだつもりだったが、あまりに小さな声しか出ない。
喩え叫ぶことが出来ていたとしても、動く者はいない筈だと、知っている。
それでも今出来るのはそれだけだ。
やがて、誰かが 子供を抱きかかえていく姿が見えた。
「――僕と違って、もう遅いんだよ。人参。テメェはそこでぼんやり頭融かしてりゃいい」
そんな声が聞こえた気がした。黒い髪をしていた気がするが、顔はよく見ていない。
誰であろうとどうでもいい。
抗うことをやめれば思考の乱れも消えたし、そもそもどうして抗おうとしたのかも考えられなくなっていた。
せんのう



ENo.9 タマキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.181 ガガミネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.388 ユイノ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.428 晴 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.434 ピザ子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.526 悠吏 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.565 戌亥縫 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
一穂 「はじめまして。僕は宮田一穂(みやた かずほ)と言います。 主に特筆すべきと思われる能力として、ほぼ完全な記憶力があります。異能は記憶を物体に焼きつけ、知性体がその物体に触れると記憶を自分のことのように感じる、というものです。 その他戦闘上のスキルとしましては、CQCや銃器の訓練を受けております」 |
 |
と、少年は淡々と自己紹介をして、 |
 |
一穂 「どうかよろしくお願いいたします」 |
 |
お辞儀を一つした。 |
 |
不幸喰らい 「ずっと気になっていたけど、あのパーティ名考えたの誰だ……?」 |
 |
冴 「あ、それボクだよ。良くない? 程よく緊張解けそうで」 |
 |
不幸喰らい 「締まらない……」 |





防衛がんばるぞい
|
 |
黄昏の星々・紅
|



武術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
シエ(11) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『calida印のジャンボパフェ』をつくってもらいました!
⇒ calida印のジャンボパフェ/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
 |
シエ 「やっべ盛りすぎた」 |
シエ(11) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『カルビ肉』をつくってもらいました!
⇒ カルビ肉/料理:強さ40/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
 |
シエ 「???????」 |
仏の男(950) とカードを交換しました!
ペッカー光るやつ (カレイドスコープ)


プロテクション を研究しました!(深度0⇒1)
ポーションラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
ヴィガラスチャージ を研究しました!(深度1⇒2)
チャージ を習得!
カウンター を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調16⇒15)
採集はできませんでした。
- 一穂(3) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







防衛がんばるぞい
|
 |
TeamNo.111
|


ENo.546
リオネル・サンドリヨン



イラスト1:リオネル(イバラの姿)
イラスト2:リオネル(ハザマでの姿)(有償にて依頼しました!ありがとうございます!)
イラスト3:サブキャラ冴
■メインキャラ
リオネル・サンドリヨン(Lionel・Cendrillon)
相良伊橋高校2年4組
195cm 91Kg 11月6日生まれ
性別:男
髪:夕焼け色、ハーフアップ
目:銀色
他の特徴:そばかす
好き:ちわわ(Eno.180)、和食、友人との雑談、家族
嫌い:蜂蜜、空腹、普通自動車、善意を盾にして脅す奴、理由の分からぬ喪失
微妙:ディストピアSF(でも読んじゃう)
こんな見た目だが母国語は日本語である。得意科目も現代文である。英語とフランス語の日常会話が可能。
好きな科目は世界史と体育。苦手な科目は数学。嫌いな科目は英語(成績はなかなか)。ド文系。
将来の夢とか未定。焦る。とりあえず進学してそこから先は後で考えることにしている。
性格はだいぶ真面目な方。気性穏やかで、臆病な本質ゆえに争いごとは得意ではない。それでも、仲間が傍にいるのであればいかなる窮地でも共に在ろうとし、仲間が貶められることがあれば相応に激昂し、仲間に危機が迫れば周りを驚かせるような行動に出ることもある。
過去に色々あったようで、どちらかというと抱え込みやすい気質。しかし、色々な人との出会いを経て、少しずつ改めようとしている。
カラミティ イーター
異能≪不幸喰らい≫
・誰かの代わりに『不幸』を引き受けることができる。
・発動のためには、その『不幸』を何らかの形で認識する必要があり、『不幸喰らい所持者』の認識と実情に齟齬があると発動が不完全になる。
・異能が発動した際『蜜のような味』がする。異能の使用後、食欲が失せることもある。
・異能『所持』の代償で不幸体質になっている。異能『使用』の代償で、不幸が悪化する。それは誰かの代わりに受けた『不幸』とまた別である。この不幸は基本的に『不幸喰らい所持者』に向けられる。例外もある。
■サブキャラ
恒川 冴(ヒサシガワ サエ)
貝米継高校1年
170cm 55~59㎏で頻繁に変動 3月24日生まれ
性別:男
髪:上は鳶色、下だけ空色
目:髪と同様
他の特徴:シンプルなイヤーカフ、右手首のミサンガ
好き:自由、時間帯問わず晴れた空、甘いもの、卵料理
嫌い:煮干し、束縛、勉強、度を超えた努力、家族
微妙:自分自身
我が道を突き進む高校生。基本的にひねくれ者で、何かに従うという行為を嫌う。ただし従わないことによるデメリットが大きければ従うこともある。面倒ごとは嫌いな割に 目の前で誰かの危機が迫っていれば助太刀くらいはしようと考えるし、一度決めたことはそうそう曲げない。表情の変化は少ない方だし 自身の感情に疎い部分も見られるが、割と普通の少年っぽい部分もあるかもしれない。
イデア クラフト
異能≪無形象り≫
・形の存在しないものを具現化する。それは武器や鎖 等々になる。具現化したものを砕くと一時的にそれが弱体化する。
・具現化するのは『誰かに紐づいたもの』でなければならない。
・発動対象の『名前』および『同意』が必要。
・代償は体力。使うと疲れる。何か食べて眠れば治る。代償の徴収タイミングは、異能の効果が切れた時。
・トリガーは『恒川冴が 具現化したいものを 左手を使って文字に記す』こと。
・記した文字が裂かれると異能の効果が切れる。
・よく使うのは『欲望』と『理念』。最近物騒なので毎日この二つは具現化して指輪にしている。
■サブキャラ(敵)
恒川 昇(ヒサシガワ ノボル)
リオネルと同学年
180cm 69㎏ 4月10日生まれ
性別:男
髪:黒
目:上が黒、下が緑
好き:自分、両親、自分以外を見下す瞬間
嫌い:弟、自分が見下されること
リオネルの元友人?であり、冴の兄。こっそりイバラシティに来て、弟を何らかの形で『駄目』にしようと目論んでいる。
異能は不明。有無を含めて不明。
・・・。
『不幸喰らいの英雄』は、ある世界に伝わる『御伽噺』だ。
平和だった国に災厄が訪れ、その災厄を英雄が全て『喰らい』一か所に集め、その英雄をどこかの世界に放り出す。これにより、再び国は平和になった。
そんな、英雄という名の生贄の物語。
それは断じて全てが真実というわけではないが、同時に『ただの御伽噺』と切り捨てていいものではない筈だった。しかし人々は、それが作り話だと思い込んだ。過ちは繰り返され、平和になった国に再び災厄が訪れた。
サンドリヨン
色の無い竜は、傘下にある『灰被る国』より素質ある若者を選んだ。
彼は争いを好まぬ穏やかな気質をしていた。
彼は他者の痛みを自分の痛みとして捉えるほどの『善良』な人間であった。
彼は守護者と呼ばれる 治安維持にまつわる仕事を与えられており、荒事に慣れていた。
彼の名は、リオネルといった。
彼はその力で各地の不幸を喰らい宿し、その身をもって銀の竜に捧げるシメイを課された。
彼はそのシメイを引き受け。
それが果たされることは、無かった。
・・・。
リオネル・サンドリヨンの正体はアンジニティの咎人である。アンジニティとしての姿は人にあらず、『四肢に鎖をつけ、体内に瘴気を宿した硝子の竜』のような出で立ちをしており、負傷しても欠損しても時間を置くことで再生する。
その力を使うことで、病を、傷を、痛みを、怒りを、悲しみを、時には争いそのものを『喰らい』腹を満たす化け物。
争いごとがあるたびに近寄ってくることから、災厄の象徴のような扱いを受けているかもしれない。
『不幸を喰らう』際には腹を満たすだけでなく、その不幸を硝子の竜が引き受けているというのに。
否定される前、滅亡に瀕したとある国を救うシメイを賜った。侵略を阻止することもまたシメイの延長線上にあると考えていたが、今はそれがエゴでしかないとハッキリ自覚している。
自覚した上で、立ち止まることが出来ずにいる。
時折、傷を『喰らう』という形でイバラシティに与する者の治療を行う姿が見られるかもしれない。自らの姿が人間から見て異質であると自覚し、守ると決めた者たちから敵対される覚悟を決めて。
・・・。
ハザマの地にて。
リオネルは防御、支援を。
恒川冴は攻撃、妨害を担当する。
つまりはどちらも『防衛』の参加者である。
イラスト2:リオネル(ハザマでの姿)(有償にて依頼しました!ありがとうございます!)
イラスト3:サブキャラ冴
■メインキャラ
リオネル・サンドリヨン(Lionel・Cendrillon)
相良伊橋高校2年4組
195cm 91Kg 11月6日生まれ
性別:男
髪:夕焼け色、ハーフアップ
目:銀色
他の特徴:そばかす
好き:ちわわ(Eno.180)、和食、友人との雑談、家族
嫌い:蜂蜜、空腹、普通自動車、善意を盾にして脅す奴、理由の分からぬ喪失
微妙:ディストピアSF(でも読んじゃう)
こんな見た目だが母国語は日本語である。得意科目も現代文である。英語とフランス語の日常会話が可能。
好きな科目は世界史と体育。苦手な科目は数学。嫌いな科目は英語(成績はなかなか)。ド文系。
将来の夢とか未定。焦る。とりあえず進学してそこから先は後で考えることにしている。
性格はだいぶ真面目な方。気性穏やかで、臆病な本質ゆえに争いごとは得意ではない。それでも、仲間が傍にいるのであればいかなる窮地でも共に在ろうとし、仲間が貶められることがあれば相応に激昂し、仲間に危機が迫れば周りを驚かせるような行動に出ることもある。
過去に色々あったようで、どちらかというと抱え込みやすい気質。しかし、色々な人との出会いを経て、少しずつ改めようとしている。
カラミティ イーター
異能≪不幸喰らい≫
・誰かの代わりに『不幸』を引き受けることができる。
・発動のためには、その『不幸』を何らかの形で認識する必要があり、『不幸喰らい所持者』の認識と実情に齟齬があると発動が不完全になる。
・異能が発動した際『蜜のような味』がする。異能の使用後、食欲が失せることもある。
・異能『所持』の代償で不幸体質になっている。異能『使用』の代償で、不幸が悪化する。それは誰かの代わりに受けた『不幸』とまた別である。この不幸は基本的に『不幸喰らい所持者』に向けられる。例外もある。
■サブキャラ
恒川 冴(ヒサシガワ サエ)
貝米継高校1年
170cm 55~59㎏で頻繁に変動 3月24日生まれ
性別:男
髪:上は鳶色、下だけ空色
目:髪と同様
他の特徴:シンプルなイヤーカフ、右手首のミサンガ
好き:自由、時間帯問わず晴れた空、甘いもの、卵料理
嫌い:煮干し、束縛、勉強、度を超えた努力、家族
微妙:自分自身
我が道を突き進む高校生。基本的にひねくれ者で、何かに従うという行為を嫌う。ただし従わないことによるデメリットが大きければ従うこともある。面倒ごとは嫌いな割に 目の前で誰かの危機が迫っていれば助太刀くらいはしようと考えるし、一度決めたことはそうそう曲げない。表情の変化は少ない方だし 自身の感情に疎い部分も見られるが、割と普通の少年っぽい部分もあるかもしれない。
イデア クラフト
異能≪無形象り≫
・形の存在しないものを具現化する。それは武器や鎖 等々になる。具現化したものを砕くと一時的にそれが弱体化する。
・具現化するのは『誰かに紐づいたもの』でなければならない。
・発動対象の『名前』および『同意』が必要。
・代償は体力。使うと疲れる。何か食べて眠れば治る。代償の徴収タイミングは、異能の効果が切れた時。
・トリガーは『恒川冴が 具現化したいものを 左手を使って文字に記す』こと。
・記した文字が裂かれると異能の効果が切れる。
・よく使うのは『欲望』と『理念』。最近物騒なので毎日この二つは具現化して指輪にしている。
■サブキャラ(敵)
恒川 昇(ヒサシガワ ノボル)
リオネルと同学年
180cm 69㎏ 4月10日生まれ
性別:男
髪:黒
目:上が黒、下が緑
好き:自分、両親、自分以外を見下す瞬間
嫌い:弟、自分が見下されること
リオネルの元友人?であり、冴の兄。こっそりイバラシティに来て、弟を何らかの形で『駄目』にしようと目論んでいる。
異能は不明。有無を含めて不明。
・・・。
『不幸喰らいの英雄』は、ある世界に伝わる『御伽噺』だ。
平和だった国に災厄が訪れ、その災厄を英雄が全て『喰らい』一か所に集め、その英雄をどこかの世界に放り出す。これにより、再び国は平和になった。
そんな、英雄という名の生贄の物語。
それは断じて全てが真実というわけではないが、同時に『ただの御伽噺』と切り捨てていいものではない筈だった。しかし人々は、それが作り話だと思い込んだ。過ちは繰り返され、平和になった国に再び災厄が訪れた。
サンドリヨン
色の無い竜は、傘下にある『灰被る国』より素質ある若者を選んだ。
彼は争いを好まぬ穏やかな気質をしていた。
彼は他者の痛みを自分の痛みとして捉えるほどの『善良』な人間であった。
彼は守護者と呼ばれる 治安維持にまつわる仕事を与えられており、荒事に慣れていた。
彼の名は、リオネルといった。
彼はその力で各地の不幸を喰らい宿し、その身をもって銀の竜に捧げるシメイを課された。
彼はそのシメイを引き受け。
それが果たされることは、無かった。
・・・。
リオネル・サンドリヨンの正体はアンジニティの咎人である。アンジニティとしての姿は人にあらず、『四肢に鎖をつけ、体内に瘴気を宿した硝子の竜』のような出で立ちをしており、負傷しても欠損しても時間を置くことで再生する。
その力を使うことで、病を、傷を、痛みを、怒りを、悲しみを、時には争いそのものを『喰らい』腹を満たす化け物。
争いごとがあるたびに近寄ってくることから、災厄の象徴のような扱いを受けているかもしれない。
『不幸を喰らう』際には腹を満たすだけでなく、その不幸を硝子の竜が引き受けているというのに。
否定される前、滅亡に瀕したとある国を救うシメイを賜った。侵略を阻止することもまたシメイの延長線上にあると考えていたが、今はそれがエゴでしかないとハッキリ自覚している。
自覚した上で、立ち止まることが出来ずにいる。
時折、傷を『喰らう』という形でイバラシティに与する者の治療を行う姿が見られるかもしれない。自らの姿が人間から見て異質であると自覚し、守ると決めた者たちから敵対される覚悟を決めて。
・・・。
ハザマの地にて。
リオネルは防御、支援を。
恒川冴は攻撃、妨害を担当する。
つまりはどちらも『防衛』の参加者である。
15 / 30
50 PS
チナミ区
I-16
I-16






































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 古びた足枷 | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 罪悪滔天 | 武器 | 20 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | calida印のジャンボパフェ | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | カルビ肉 | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 9 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 5 | 拘束/罠/リスク |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 防具 | 30 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 其の『欲望』で砕け (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 『欲望』を翻す (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 其の『理念』で刻め (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 『理念』で薙ぐ (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 『傷喰らい』 (ヒール) | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 『恐怖』は命綱 (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 『欲望』で絶つ (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 『欲望』は撓る (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 其の『欲望』で狙え (ストライク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| 『理念』の剣よ、降れ (アサルト) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| 其の『理念』を降らす (クリエイト:タライ) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| 竜の翼、硝子の盾 (リフレクション) | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 決2 | 『弱さ』に背け (デアデビル) | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 |
| 其の『理念』は堅牢なりて (クリエイト:シールド) | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| 絡め取る『欲望』の鎖 (コンテイン) | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| 阻む『欲望』の鎖 (クリエイト:チェーン) | 5 | 0 | 100 | 敵3:攻撃&束縛+自:AG減(1T) | |
| 守護者の護るべきは何れ (カプリシャスナイト) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&護衛 | |
| 研ぎ澄ませ、空色の剣 (クリエイト:ウィング) | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 『矛先喰らい』 (ガーディアン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| カウンター | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 『弱さ』を砕く (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 竜守の盾 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 『鈍さ』を捨てる (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 其は嘗ての願い (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 其は調和竜の呪縛 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 『不幸喰らいの英雄』 (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 『気配』を砕く (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]アリア | [ 2 ]ヴィガラスチャージ | [ 1 ]プロテクション |
| [ 1 ]コンセントレイト | [ 1 ]ポーションラッシュ |

PL / logi_minamo