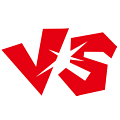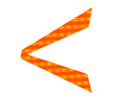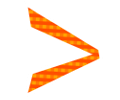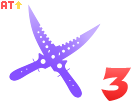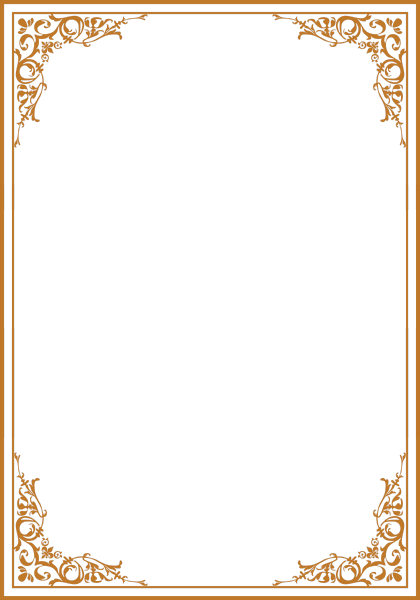<< 9:00~10:00




あまりにも胡散臭い男性の誘いについて、授業を受けながら考える。
今のところ、話したいだけとは言っているが本当にそれだけで社会的に問題がなければ学校経由で呼び出してくるはずだ。直接来た理由がある。職員室を通せない理由。
正体を隠したい、大事にしたくない背景がある。私について調べたのなら、シェリーについて調べたのかもしれない。最適解を知る異能、それによって所属組織を知られる可能性を避けた。
……という可能性でしかない。
先日、ミツフネ先輩に異能を封じられる危険性を経験させてもらったばかりだ。わざわざ危険に飛び込む事もない。まずは一度断ってみよう。後々の対応はその時の反応で決める。
そう結論付けて授業に意識を向ける。
──
放課後、授業を終えて校門に赴けば話しかけてきた男性が待っていた。
疲れた様子もなく、こちらに手を挙げて、
「やぁ、先生同伴くらいは考えてたけども、一人かい?」
……私は一人で物事を抱える癖があるかもしれない。
脳内せおりさんが「剣ヶ峰さんは危機感が足りないよ! 宮森さんくらいに!」と叱責し、脳内宮森さんが「なんで私を巻き込んだの!?」と抗議する。ごめんなさい、宮森さん。
内心で一人で来た事を反省し、表情へ出さないよう意識しながら返す。
「友達には話してきていますので、私に何かあれば相応の事はありますよ」
こちらの返答に、男はニヤリと口を広げて笑う。君の意図は分かっているよ、とでも言っているような笑いだ。
「なるほど、友達。イノカク部の先輩方に頼らないという事は僕が敵性ではないと思っている?」
「イノカク部の友達かもしれませんよ」
「まぁ……そうだね。それで同行してくれるのかい?」
「場所によります」
「最寄りの喫茶店かな。信頼出来ないなら君が指定してくれてもいい」
ツクナミ区の喫茶店なら一通り行った事がある。人が変わっていたら分かるはずだ。わざわざそんな事をする相手なら、間違いなく敵性だ。対応がはっきりする。
「いえ、そちらの案内で結構です。行きましょう」
男の表情に笑みが浮かび、脳内せおりさんが一層激怒した。
──
案内された喫茶店は何度か入った事のある喫茶店だった。静かな喫茶店で、年老いたマスターが一人で切り盛りしている。男はマスターに挨拶をすると、奥まったテーブル席へ腰を下ろす。
「君は雑談から入った方がいいタイプ? それとも本題から入った方がいいタイプかな」
「そこは調べておかなかったんですか?」
「運営しているチャンネルではいきなり本題から入るタイプ、即ゲームを始めていた事は分かってるよ」
「……年頃の乙女なんですが、プライバシーを何処まで調べ上げているんでしょう」
「以前友人と下着ショップに入るまでは適正サイズではないものを使っていた事くらいは」
「対戦ありがとうございました」
「待った。申し訳ない、調べた事は謝罪するよ。仕事なんだ」
心底嫌そうな視線を抗議の意味で送る。相手は両手を合わせて頭を下げる。なんとなく親しみを感じる仕草ではあるが、男の胡散臭い雰囲気で印象は相殺だ。
「まずは名乗らせてもらおう。僕はとある組織に所属している人間で、コードネーム……は君に言ってもしょうがない。本名は伊勢 時雨(イセ シグレ)」
「本当に本名なんですか? 剣ヶ峰 楓子です」
「本当に本名。調べてくれてもいいけど、死んでる事になってるからあまり意味は無いと思う。本題を言わせてもらえば、所属している組織から君を迎えるように指令を受けてる」
切りだしてきた内容に、若干驚く。組織に迎える?
「君の異能は非常に強力だ。僕達はこう見えて世界平和の為に各地へ飛んでいるんだが、戦闘も発生するからね。強力な異能者である君を迎えたく思う……というわけさ」
「……おっしゃる事は、分からなくはないですが。未成年を戦わせる組織ですか?」
「そうだね、そこは否定出来ない。戦闘で当たる相手が人間だけではないから良い、という事でもないからね」
「……えっと、幽霊とか、鬼みたいな妖怪ですか?」
「話が早いね。日本はそういう類も多いけど、独自組織が多いから僕達が出る事は少ないよ」
「日本以外は……」
「宗教系組織が強い。まぁ実際に君が来てくれたらそういう所には当たらないよ。対人間はうちとしても本業ではない」
そこまで言うと、マスターが珈琲を二つテーブルへ置いて戻っていく。男は角砂糖を四つ入れて珈琲を飲み始めた。四つて、すごい甘党だ。しかし、勧誘の話ばかりしているが気になるのはそこじゃない。
「あの、五月の件は……」
「あぁ」
男はすっかり忘れていたと言わんばかりの調子で続ける。
「僕たちの組織に協力してくれている天文台で、非常に強力な視覚妨害を検知してね。もしやついに異星文明かと出元を探っていたんだけど。あの夜、視覚妨害が弱まったタイミングがあって一通りを拝見した。
それで君の存在を確認した……から勧誘に来たというわけさ」
「あの、自分で言うのもなんですが、非常に危険な異能だと思うんですよ。捕縛するという意見は出なかったんですか?」
「勿論、出た。でもうちの部長が待ったをかけた」
「何故?」
男は再び珈琲を飲んだ。胡散臭い笑みから、懐かしい思い出を語るような笑みになる。
「君の両親は、僕の同僚、部長の部下。うちに居たんだよ」
はい?
「私の両親が?」
「そう。秋子さんと風太と一緒に仕事をしたものだよ」
両親の名前は間違っていない。しかし、少し調べればわかる事だ。
「調べればわかると思ってる。秋子さんは困ったときに顎へ指を当てる癖があった。風太は右袖で鼻を拭く癖があって秋子さんによく叱られていた。合ってる?」
「……合ってます」
「個人の癖はなかなか文章化されない。証明として妥当だと思うけど、どうだい?」
誘いは分かった。両親の事は、一旦保留しよう。
両親が居たから無条件に信用していいという事は無い。
『その通りだよ剣ヶ峰さん!』 ありがとうございます、脳内せおりさん。ストーカー対策会議しておいてよかったですね。
「お話は分かりました。でもすぐに決められる話ではないと思います。
保留にさせてもらいます、構いませんよね」
「勿論。これで即ついてこられたら僕としては少し不安になる所だったからね」
珈琲を一気に飲み空にして立ち上がる。支払いは相手に任せて店を出ようとするが、特に止められる事は無かった。
両親の仕事。
異能を生かせはする仕事だけども……。
正直、あまり気乗りしない。



ENo.161 ミツフネ とのやりとり

ENo.229 神の力 とのやりとり

ENo.392 キングモロバ とのやりとり

ENo.403 絶望の神器 とのやりとり

ENo.1491 透 とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。










すると梅の香りとは別の、何か甘い香りが漂ってくる・・・
香りを追ってゆくと、梅の花に囲まれた売店がある。
そこに、店員?と思われるふたり。


こちらに気づく。
どうやら団子を作っているようだ。

空中に突然現れるミヨチン。
お団子を受け取り、早速ひとくち。
両手でピースサインをするふたり。
団子を食べて嬉しそうなミヨチン。
笑みを浮かべる。
ピョンっとジャンプすると、空中で姿を消した。
・・・・・身体の奥から、少し力が湧き出る感覚。
各CP・FPが2増加した!



ウィル(72) から SIG 320 を受け取りました。
幻術LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV65⇒70、-5CP)
不幸喰らい(546) により ItemNo.13 蛍石 から防具『対刃コート』を作製してもらいました!
⇒ 対刃コート/防具:強さ160/[効果1]舞朧15 [効果2]- [効果3]-
不幸喰らい(546) の持つ ItemNo.6 ガラス瓶 から装飾『古びた鎖』を作製しました!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
MISSION - 未発生:
- フーコ(1072) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園(同行者が達成済み)





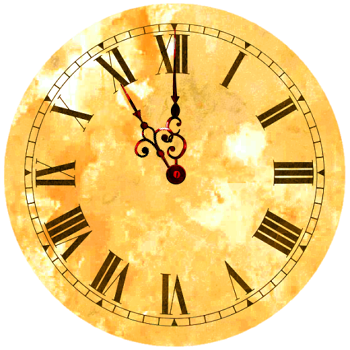
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
チャットが閉じられる――







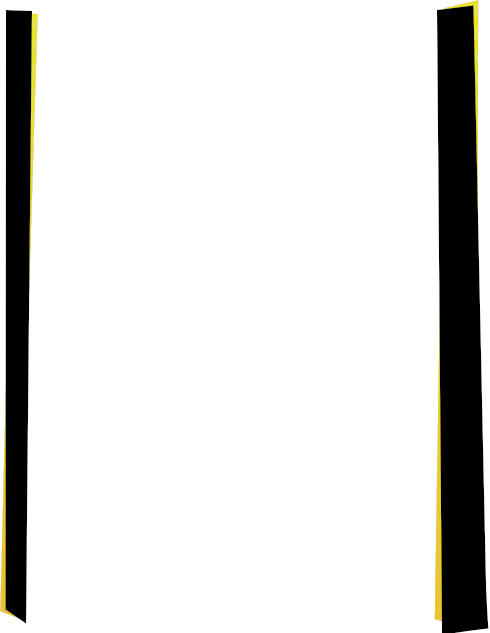
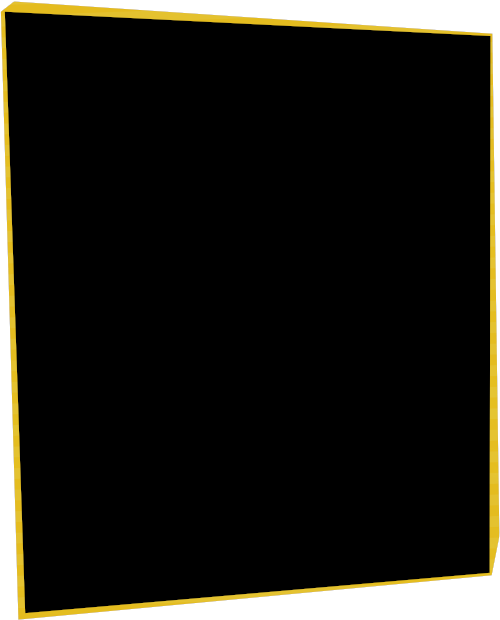





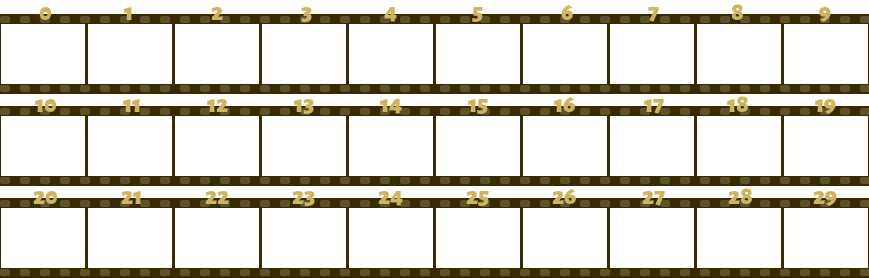







































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



あまりにも胡散臭い男性の誘いについて、授業を受けながら考える。
今のところ、話したいだけとは言っているが本当にそれだけで社会的に問題がなければ学校経由で呼び出してくるはずだ。直接来た理由がある。職員室を通せない理由。
正体を隠したい、大事にしたくない背景がある。私について調べたのなら、シェリーについて調べたのかもしれない。最適解を知る異能、それによって所属組織を知られる可能性を避けた。
……という可能性でしかない。
先日、ミツフネ先輩に異能を封じられる危険性を経験させてもらったばかりだ。わざわざ危険に飛び込む事もない。まずは一度断ってみよう。後々の対応はその時の反応で決める。
そう結論付けて授業に意識を向ける。
──
放課後、授業を終えて校門に赴けば話しかけてきた男性が待っていた。
疲れた様子もなく、こちらに手を挙げて、
「やぁ、先生同伴くらいは考えてたけども、一人かい?」
……私は一人で物事を抱える癖があるかもしれない。
脳内せおりさんが「剣ヶ峰さんは危機感が足りないよ! 宮森さんくらいに!」と叱責し、脳内宮森さんが「なんで私を巻き込んだの!?」と抗議する。ごめんなさい、宮森さん。
内心で一人で来た事を反省し、表情へ出さないよう意識しながら返す。
「友達には話してきていますので、私に何かあれば相応の事はありますよ」
こちらの返答に、男はニヤリと口を広げて笑う。君の意図は分かっているよ、とでも言っているような笑いだ。
「なるほど、友達。イノカク部の先輩方に頼らないという事は僕が敵性ではないと思っている?」
「イノカク部の友達かもしれませんよ」
「まぁ……そうだね。それで同行してくれるのかい?」
「場所によります」
「最寄りの喫茶店かな。信頼出来ないなら君が指定してくれてもいい」
ツクナミ区の喫茶店なら一通り行った事がある。人が変わっていたら分かるはずだ。わざわざそんな事をする相手なら、間違いなく敵性だ。対応がはっきりする。
「いえ、そちらの案内で結構です。行きましょう」
男の表情に笑みが浮かび、脳内せおりさんが一層激怒した。
──
案内された喫茶店は何度か入った事のある喫茶店だった。静かな喫茶店で、年老いたマスターが一人で切り盛りしている。男はマスターに挨拶をすると、奥まったテーブル席へ腰を下ろす。
「君は雑談から入った方がいいタイプ? それとも本題から入った方がいいタイプかな」
「そこは調べておかなかったんですか?」
「運営しているチャンネルではいきなり本題から入るタイプ、即ゲームを始めていた事は分かってるよ」
「……年頃の乙女なんですが、プライバシーを何処まで調べ上げているんでしょう」
「以前友人と下着ショップに入るまでは適正サイズではないものを使っていた事くらいは」
「対戦ありがとうございました」
「待った。申し訳ない、調べた事は謝罪するよ。仕事なんだ」
心底嫌そうな視線を抗議の意味で送る。相手は両手を合わせて頭を下げる。なんとなく親しみを感じる仕草ではあるが、男の胡散臭い雰囲気で印象は相殺だ。
「まずは名乗らせてもらおう。僕はとある組織に所属している人間で、コードネーム……は君に言ってもしょうがない。本名は伊勢 時雨(イセ シグレ)」
「本当に本名なんですか? 剣ヶ峰 楓子です」
「本当に本名。調べてくれてもいいけど、死んでる事になってるからあまり意味は無いと思う。本題を言わせてもらえば、所属している組織から君を迎えるように指令を受けてる」
切りだしてきた内容に、若干驚く。組織に迎える?
「君の異能は非常に強力だ。僕達はこう見えて世界平和の為に各地へ飛んでいるんだが、戦闘も発生するからね。強力な異能者である君を迎えたく思う……というわけさ」
「……おっしゃる事は、分からなくはないですが。未成年を戦わせる組織ですか?」
「そうだね、そこは否定出来ない。戦闘で当たる相手が人間だけではないから良い、という事でもないからね」
「……えっと、幽霊とか、鬼みたいな妖怪ですか?」
「話が早いね。日本はそういう類も多いけど、独自組織が多いから僕達が出る事は少ないよ」
「日本以外は……」
「宗教系組織が強い。まぁ実際に君が来てくれたらそういう所には当たらないよ。対人間はうちとしても本業ではない」
そこまで言うと、マスターが珈琲を二つテーブルへ置いて戻っていく。男は角砂糖を四つ入れて珈琲を飲み始めた。四つて、すごい甘党だ。しかし、勧誘の話ばかりしているが気になるのはそこじゃない。
「あの、五月の件は……」
「あぁ」
男はすっかり忘れていたと言わんばかりの調子で続ける。
「僕たちの組織に協力してくれている天文台で、非常に強力な視覚妨害を検知してね。もしやついに異星文明かと出元を探っていたんだけど。あの夜、視覚妨害が弱まったタイミングがあって一通りを拝見した。
それで君の存在を確認した……から勧誘に来たというわけさ」
「あの、自分で言うのもなんですが、非常に危険な異能だと思うんですよ。捕縛するという意見は出なかったんですか?」
「勿論、出た。でもうちの部長が待ったをかけた」
「何故?」
男は再び珈琲を飲んだ。胡散臭い笑みから、懐かしい思い出を語るような笑みになる。
「君の両親は、僕の同僚、部長の部下。うちに居たんだよ」
はい?
「私の両親が?」
「そう。秋子さんと風太と一緒に仕事をしたものだよ」
両親の名前は間違っていない。しかし、少し調べればわかる事だ。
「調べればわかると思ってる。秋子さんは困ったときに顎へ指を当てる癖があった。風太は右袖で鼻を拭く癖があって秋子さんによく叱られていた。合ってる?」
「……合ってます」
「個人の癖はなかなか文章化されない。証明として妥当だと思うけど、どうだい?」
誘いは分かった。両親の事は、一旦保留しよう。
両親が居たから無条件に信用していいという事は無い。
『その通りだよ剣ヶ峰さん!』 ありがとうございます、脳内せおりさん。ストーカー対策会議しておいてよかったですね。
「お話は分かりました。でもすぐに決められる話ではないと思います。
保留にさせてもらいます、構いませんよね」
「勿論。これで即ついてこられたら僕としては少し不安になる所だったからね」
珈琲を一気に飲み空にして立ち上がる。支払いは相手に任せて店を出ようとするが、特に止められる事は無かった。
両親の仕事。
異能を生かせはする仕事だけども……。
正直、あまり気乗りしない。



ENo.161 ミツフネ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.229 神の力 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.392 キングモロバ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.403 絶望の神器 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1491 透 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。









チナミ区 O-16 周辺:梅楽園
梅の木たちを退けながら進んでいく。すると梅の香りとは別の、何か甘い香りが漂ってくる・・・
香りを追ってゆくと、梅の花に囲まれた売店がある。
そこに、店員?と思われるふたり。

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
こちらに気づく。
 |
カオリ 「カグハちゃんカグハちゃん!お客さんだよぉー!!お客さんっ!!」 |
 |
カグハ 「はいお団子。カオリちゃん、具。」 |
 |
カオリ 「はいはーい!」 |
 |
カオリ 「・・・って、だからお客さんだってばーっ!!!!」 |
 |
カグハ 「うん、見えるよ。」 |
どうやら団子を作っているようだ。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
 |
ミヨチン 「おぉぉ!?これは匂いでわかる美味美味感♪」 |
空中に突然現れるミヨチン。
 |
カグハ 「わー・・・・・すごい。」 |
 |
カオリ 「うぎゃー!!なにやつぅぅーっ!!!!」 |
 |
ミヨチン 「怖いもの見たみたいなリアクション、やめてほしいっすねぇ。」 |
 |
ミヨチン 「ハイパーサイキックパワーJK☆ミヨチンっすよぉー!!」 |
 |
カオリ 「サイキック!すごい・・・!!!!」 |
 |
カグハ 「サイキック・・・・・なのかな、これ。」 |
 |
ミヨチン 「っとゆーわけで!お団子ひとつ、くださいなー!!」 |
 |
カオリ 「あ、はーい!どうぞっ!!」 |
お団子を受け取り、早速ひとくち。
 |
ミヨチン 「――これはこれはこれは!すごいっすねぇー!!超美味しいっすよぉぉ!!!!モッチモチ!!ちびっこふたりでこれ作れるならもう天下取れるっすねぇ!!」 |
 |
カオリ 「うちらの団子はサイキョーだから!」 |
 |
カグハ 「うん、サイキョー。」 |
両手でピースサインをするふたり。
団子を食べて嬉しそうなミヨチン。
 |
ミヨチン 「大!満!足ッ!!サイキョーっすねぇここ!!」 |
 |
ミヨチン 「これはいいトモダチができたっす! また今度、何かお願いしてもいいっすかー?にひひ・・・っ」 |
笑みを浮かべる。
 |
ミヨチン 「それじゃミヨチンはまた探検に!まったねーっ!!」 |
ピョンっとジャンプすると、空中で姿を消した。
・・・・・身体の奥から、少し力が湧き出る感覚。
各CP・FPが2増加した!



ウィル(72) から SIG 320 を受け取りました。
 |
指定された場所には軍用らしきコンテナが置かれている。 開けると中には拳銃と弾薬、必要最低限の使い方を記した紙が入っている。 |
幻術LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV65⇒70、-5CP)
不幸喰らい(546) により ItemNo.13 蛍石 から防具『対刃コート』を作製してもらいました!
⇒ 対刃コート/防具:強さ160/[効果1]舞朧15 [効果2]- [効果3]-
 |
冴 「たしかソラコーの民研で見た人だ……。 連れが防具を見繕ったみたいだから使ってよ」 |
 |
連れである硝子の竜は、離れた場所にいる……。 警戒させるといけないので、イバラ住みの仲間に受け渡しを頼んでいた。 |
不幸喰らい(546) の持つ ItemNo.6 ガラス瓶 から装飾『古びた鎖』を作製しました!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
MISSION - 未発生:
- フーコ(1072) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園(同行者が達成済み)





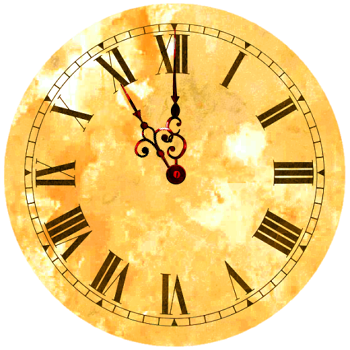
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
白南海 「・・・・・おや、どうしました?まだ恐怖心が拭えねぇんすか?」 |
 |
エディアン 「・・・何を澄ました顔で。窓に勧誘したの、貴方ですよね。」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!! 俺これ嫌っすよぉぉ!!最初は世界を救うカッケー役割とか思ってたっすけどッ!!」 |
 |
エディアン 「わかわかわかわか・・・・・何を今更なっさけない。 そんなにワカが恋しいんです?そんなに頼もしいんです?」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
 |
白南海 「それはもう!若はとんでもねぇ器の持ち主でねぇッ!!」 |
 |
エディアン 「突然元気になった・・・・・」 |
 |
白南海 「俺が頼んだラーメンに若は、若のチャーシューメンのチャーシューを1枚分けてくれたんすよッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・。・・・・他には?」 |
 |
白南海 「俺が501円のを1000円で買おうとしたとき、そっと1円足してくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・あとは?」 |
 |
白南海 「俺が車道側歩いてたら、そっと車道側と代わってくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・うーん。他の、あります?」 |
 |
白南海 「俺がアイスをシングルかダブルかで悩ん――」 |
 |
エディアン 「――あー、もういいです。いいでーす。」 |
 |
白南海 「・・・お分かりいただけましたか?若の素晴らしさ。」 |
 |
エディアン 「えぇぇーとってもーーー。」 |
 |
白南海 「いやー若の話をすると気分が良くなりますァ!」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「・・・あーうるさい。帰りますよ?帰りますからねー。」 |
チャットが閉じられる――





ENo.1072
剣ヶ峰 楓子

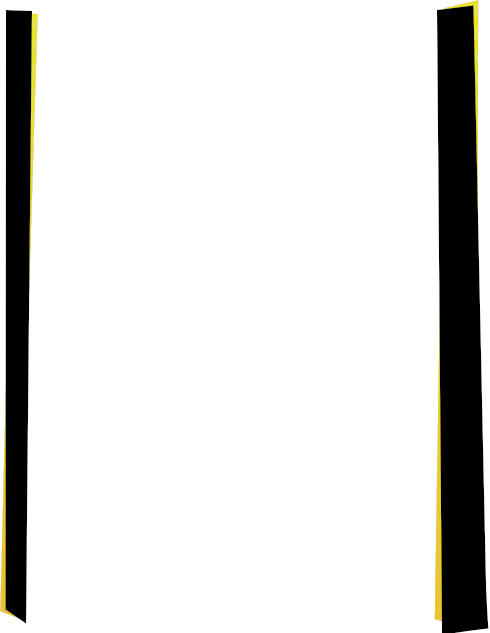
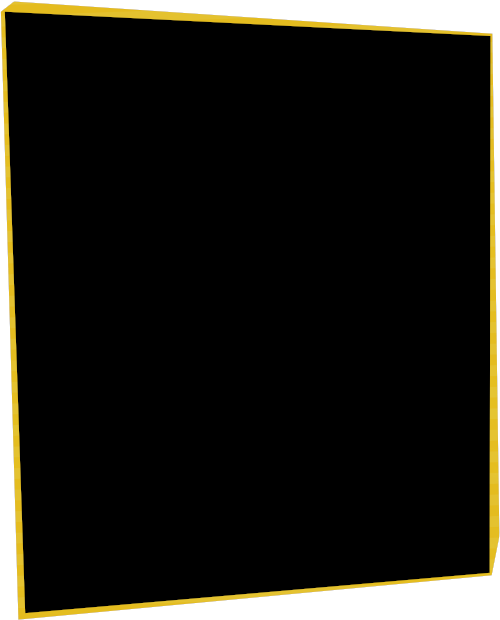
◆剣ヶ峰楓子(ツルギガミネ フウコ)
─年齢:16歳の高校一年生。→進級により2年1組へ。
─身長:150cm、
─体重:56kg。
─好きなものはコンビニで売ってるカフェオレ、フレーク混じりのプロテインバー。
─嫌いなものはこんにゃくゼリー。食べた気がしないから。
─好きな授業は道徳。(正解が無いので好きに言えるから)
─嫌いな授業は国語。(作者の気持ちが分からないから) ※ただし成績は良い。
実は隠れ巨乳である事がクラスメイトのS・S女史の証言により判明した。
好きな映画はアンドリューNDR114。正直よく覚えていないが、ラストシーンで感動した事だけ覚えてる。最近見た映画はテッド(1の方)。テッドが裂けるシーンで泣いた。
ゲームで情操教育をした、好きなゲームはmother2と桃鉄。
◆剣風チャンネル
イバチューブで「剣風チャンネル」というゲーム実況チャンネルを3年ほど運営しており、幅広く古いゲームから新しいゲームまで実況する。
毎晩21時から2時間ほどゲーム配信をして、最後の20分に「剣風ラジオ」を開いている。視聴者数は10人くらいだったが、先日とあるアイドルが話題に出した事により盛大にバズり、登録者は5万を超え収益化が通るまでになった。
視聴者数が平均300人を超えるようになったが、相変わらずコアなゲーマーしかいつかないので雰囲気は変わっていない。
知ってる設定はお好きにどうぞ、喜びます。
◆異能 雷光の隣人(ホワイトナイト) 2020/1/30更新時
本人曰く、「雷電を自身の延長とする」能力。
・常時発動型。自身で発電も可能で、コンセントから電を補充する事も出来るが、あまり意味はない。
・他人の異能による電撃ではダメージが入る。
・スマホの充電も可能。家電製品へ供給する電圧を理解しているのでキャンプでも家電を扱える。
・雷の剣や腕を形成し、自由に扱う事が出来る。
・飛行が可能。その際に慣性を無視したような動きをする。
・エネルギー切れを経験した事が無い。
・致命傷を負った場合、体が光の粒子に分解され、雷と共に再集結して治癒された状態で現れる。
『雷の異能』では説明出来ない用途が多く見られる。彼女が扱っているのは本来の異能ではなく、その一面に過ぎないの可能性が高い。
また、この異能を剣ヶ峰楓子本人に承諾を得ずにコピーに類する行為で使用した場合、強い反動(デメリットは本人の異能に類する、無い場合は強い痛み)が発生する。
◆来歴
イバラシティに来た理由は、親族に家を追い出されたから、である。彼女の両親は幼い頃に遺産を残して亡くなった。その遺産は親族が管理し、彼女自身は家政婦の世話で育った。
毎日一人ゲームに逃避する。しかし、逃避した先で彼女は人間の善性を学んだ。多くのゲームが人生の素晴らしさを彼女に教え、親族を恨むより未来を考える方へ彼女を導いた。
だから高校進学に伴い、親族の夫婦に家を渡すよう言われた時、彼女は「構いませんよ。遺産の一部は頂いていきますけど」と言って学生寮への引っ越し手続きを決めた。
剣ヶ峰楓子は恨まない。未来を見る。
●追記
彼女の世話をしていた家政婦とは、イバラシティに来る前のeno73 シェリル・ウィステリアである。
よく懐いていたはずだが、楓子は記憶の家政婦とシェリル先生を同一視していなかったが、蘇生異能による記憶障害であり、現在は解消されている。
●イラスト関連
キャラクターデザイン、アイコンNo0-9:佐伯さん(@ep_707a)
アイコンNo10-16:ちるきゅーさん(@cir_ram)
アイコンNo20-24:himeNoさん(@himeno_teiki)
◆サブキャラクター
サダメ・トラオム
http://lisge.com/ib/prof.php?id=c4uNXq5w1Fr6ad4ddafbf8020b03badb2b63b87f5be
─年齢:16歳の高校一年生。→進級により2年1組へ。
─身長:150cm、
─体重:56kg。
─好きなものはコンビニで売ってるカフェオレ、フレーク混じりのプロテインバー。
─嫌いなものはこんにゃくゼリー。食べた気がしないから。
─好きな授業は道徳。(正解が無いので好きに言えるから)
─嫌いな授業は国語。(作者の気持ちが分からないから) ※ただし成績は良い。
実は隠れ巨乳である事がクラスメイトのS・S女史の証言により判明した。
好きな映画はアンドリューNDR114。正直よく覚えていないが、ラストシーンで感動した事だけ覚えてる。最近見た映画はテッド(1の方)。テッドが裂けるシーンで泣いた。
ゲームで情操教育をした、好きなゲームはmother2と桃鉄。
◆剣風チャンネル
イバチューブで「剣風チャンネル」というゲーム実況チャンネルを3年ほど運営しており、幅広く古いゲームから新しいゲームまで実況する。
毎晩21時から2時間ほどゲーム配信をして、最後の20分に「剣風ラジオ」を開いている。視聴者数は10人くらいだったが、先日とあるアイドルが話題に出した事により盛大にバズり、登録者は5万を超え収益化が通るまでになった。
視聴者数が平均300人を超えるようになったが、相変わらずコアなゲーマーしかいつかないので雰囲気は変わっていない。
知ってる設定はお好きにどうぞ、喜びます。
◆異能 雷光の隣人(ホワイトナイト) 2020/1/30更新時
本人曰く、「雷電を自身の延長とする」能力。
・常時発動型。自身で発電も可能で、コンセントから電を補充する事も出来るが、あまり意味はない。
・他人の異能による電撃ではダメージが入る。
・スマホの充電も可能。家電製品へ供給する電圧を理解しているのでキャンプでも家電を扱える。
・雷の剣や腕を形成し、自由に扱う事が出来る。
・飛行が可能。その際に慣性を無視したような動きをする。
・エネルギー切れを経験した事が無い。
・致命傷を負った場合、体が光の粒子に分解され、雷と共に再集結して治癒された状態で現れる。
『雷の異能』では説明出来ない用途が多く見られる。彼女が扱っているのは本来の異能ではなく、その一面に過ぎないの可能性が高い。
また、この異能を剣ヶ峰楓子本人に承諾を得ずにコピーに類する行為で使用した場合、強い反動(デメリットは本人の異能に類する、無い場合は強い痛み)が発生する。
◆来歴
イバラシティに来た理由は、親族に家を追い出されたから、である。彼女の両親は幼い頃に遺産を残して亡くなった。その遺産は親族が管理し、彼女自身は家政婦の世話で育った。
毎日一人ゲームに逃避する。しかし、逃避した先で彼女は人間の善性を学んだ。多くのゲームが人生の素晴らしさを彼女に教え、親族を恨むより未来を考える方へ彼女を導いた。
だから高校進学に伴い、親族の夫婦に家を渡すよう言われた時、彼女は「構いませんよ。遺産の一部は頂いていきますけど」と言って学生寮への引っ越し手続きを決めた。
剣ヶ峰楓子は恨まない。未来を見る。
●追記
彼女の世話をしていた家政婦とは、イバラシティに来る前のeno73 シェリル・ウィステリアである。
よく懐いていたはずだが、楓子は記憶の家政婦とシェリル先生を同一視していなかったが、蘇生異能による記憶障害であり、現在は解消されている。
●イラスト関連
キャラクターデザイン、アイコンNo0-9:佐伯さん(@ep_707a)
アイコンNo10-16:ちるきゅーさん(@cir_ram)
アイコンNo20-24:himeNoさん(@himeno_teiki)
◆サブキャラクター
サダメ・トラオム
http://lisge.com/ib/prof.php?id=c4uNXq5w1Fr6ad4ddafbf8020b03badb2b63b87f5be
30 / 30
567 PS
チナミ区
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | イヤリング | 装飾 | 45 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 9 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]回復10(LV20) | |||
| 10 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 11 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 12 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 13 | 対刃コート | 防具 | 160 | 舞朧15 | - | - | |
| 14 | ブレスレット | 装飾 | 187 | 復活15 | - | - | |
| 15 | スマホカバー | 装飾 | 112 | 器用15 | - | - | |
| 16 | 楔石 | 素材 | 25 | [武器]地撃15(LV30)[防具]道連10(LV20)[装飾]復活15(LV25) | |||
| 17 | 燐灰石 | 素材 | 25 | [武器]攻撃25(LV35)[防具]奪命20(LV35)[装飾]災20(LV30) | |||
| 18 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 19 | SIG 320 | 武器 | 100 | 体力15 | 攻撃15 | - | 【射程1】 |
| 20 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 21 | 禁断じゃない果実 | 食材 | 5 | [効果1]攻撃5(LV5)[効果2]防御5(LV5)[効果3]器用5(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 30 | 夢幻/精神/光 |
| 変化 | 25 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 15 | 範囲/法則/結界 |
| 装飾 | 70 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| サンダーショット | 8 | 0 | 80 | 敵貫:光撃&麻痺 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ビューティーフォーム | 5 | 0 | 120 | 自:魅了特性・舞魅LV増 | |
| ピュリフィケーション | 5 | 0 | 50 | 敵味腐:SP増+腐食状態なら、精確光撃&腐食を猛毒化 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ディム | 7 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ムーンサルトプレス | 7 | 0 | 120 | 敵:光撃&MSP減 | |
| リリーフ | 5 | 0 | 70 | 味傷3:HP増+祝福 | |
| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |
| サンダーフォーム | 5 | 0 | 140 | 自:光特性・麻痺LV増 | |
| パージ | 5 | 0 | 120 | 敵列:粗雑SP光撃 | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| ディバインランス | 5 | 0 | 150 | 敵傷:光痛撃&朦朧&自:朦朧 | |
| ミラージュ | 5 | 0 | 140 | 敵列2:SP光撃 | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 | |
| 練2 | カレイドスコープ | 7 | 0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 |
| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| クリスタルウォール | 5 | 0 | 240 | 味全:DF・LK増&祝福消費で反射 | |
| グランドレイジ | 5 | 0 | 250 | 敵味全:地撃 | |
| スポイル | 5 | 0 | 180 | 敵:SP光痛撃&DX奪取 | |
| リフレクトバリア | 5 | 3 | 300 | 自:衰弱+味全:反射 | |
| 練2 | アルシナシオン | 5 | 2 | 300 | 敵:SP光撃&魅了状態ならDX・AG奪取 |
| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 光の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 | |
| 神威 | 5 | 3 | 0 | 【被HP回復後】自:祝福 | |
| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |
| 結界 | 5 | 3 | 0 | 【HP回復後】対:守護+環境変調を守護化 | |
| 魔晶作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で装飾「魔晶」を選択できる。魔晶は効果3に充填LVが付加される。 | |
| 光輝燦然 | 5 | 5 | 0 | 【通常攻撃後】敵:10連鎖光撃 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]イグニス | [ 3 ]イレイザー | [ 3 ]ハードブレイク |

PL / 嶺上律菜(鉄剣)