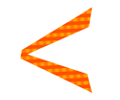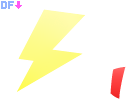<< 0:00~1:00




(今回の日記はEno.148,494,515のスターゲイザーズの皆さん、Eno.301,473,911の熾す魂火メンバーと合わせてお読み頂くことを推奨しております)
一時間。それを区切りに意識が明滅し、覚醒する。
これまでのイバラシティでの日常の記憶が、再び脳内に流れ込んできた。
それはまるで、見ていた夢を反芻するかのように。
クリスマスパーティーのこと。大晦日のこと。正月のこと。
学園の冬休みをイバラシティの住民たちと過ごした記憶が、走馬灯のように思い出されていた。
――大丈夫。この記憶があれば、まだ戦える。
嗚呼、なんて不便なんだ。“ひとのこころ”というものは。
裏切るのも、嘘を吐くのも、慣れっこだった筈なのに。
今ではずきずきと胸が痛んで、息をするのも苦しくなった。
けれど。
けれど、たとえ誰にも信じて貰えなくなったとしても、この幸せな記憶があれば、きっと……耐えられる。
だから――
歩く。歩く。Cross+Roseの位置情報だけを頼りに、荒廃した世界を急ぐ。
イデオローグは疲弊していた。妹のおまもりも無ければ、治癒の異能を操る手駒もいない。
清浄な空気の中でしか生きることの出来ない身体は、独りでは旅路さえままならない不便なものだ。
それでも、前へ進まなければならない理由があった。
Cross+Roseの示す座標はそう遠くない。
次元タクシーを降りて必死に身体を引き摺っていると、背後で後続のタクシーが停車する音がした。
慌ただしく下車してきた二つの足音と共に振り返れば、其処にいたのは――
「……結城!」
「『剣道三倍段《トリスメギストス》』ッ!!」
天文部の部長、胡桃沢命。
そして白銀の甲冑を纏った騎士、蛇乃目双刃。
双刃の方は既に臨戦態勢となり、命を庇うように前へ出て盾を構えていた。
「バツ、お前」
甲冑の奥から聞こえる、少しくぐもった声。
何やら逡巡したような様子で一呼吸置いて、騎士は続ける。
「まさか、アンジニティじゃねぇよな?」
己を疑う問い。
分かっていたことだ。そうなるように、イデオローグは仕向けていたのだから。
自身を無条件に信用してくれる相手ほど、見せたくもない真実に近づいてしまう。
だからこそ――嘘をついてでも、自分への猜疑心を高めておく必要があったのだ。
剣呑な雰囲気の中、イデオローグはゆっくりと口を開いた。
自らの口から問いへの答えは返すことなく、双刃越しに命をじっと見つめる。
取引は既に済ませた。あとは、伸るか反るか――友の一人を信じるだけだった。
結城伐都となる以前は、息をするように人を騙して生きてきた。
其処に良心の呵責を覚えることなど無かったし、誰かを信じることなども無かった。
そんな自分が今はどうだ?
たった二人に向けられる疑いが、今は何よりも鋭い刃のように感じた。
「安心しろ、結城は結城だ」
静寂を打ち破るように口を開いたのは、命だった。
背後から落ち着かせるように双刃の肩を軽く叩くと、そのまま前へ出てイデオローグへと語り掛ける。
「歩けるか?」
無理なら肩を貸す。そう申し出る少年の表情は、幾つもの感情が綯い交ぜになったようだった。
位置情報を頼りに辿り着いた先では、妹と幼馴染が身を寄せ合っていた。
しかし、付いてきたおまけは――考え得る限り、最悪のものだった。
アンジニティという地獄に在って、なお危険視されていた怪物の一角。
吸血鬼オニキス。力を以って君臨する狂える王。
それが今、妹たちへの道を阻む壁としてそこに立っていた。
周囲では焦げ臭いにおいを放つナレハテの遺骸が、未だにぶすぶすと音を立てている。
更に状況を悪化させたのは、双刃の行動だった。
カイトシールドを構えて突撃の体勢に入り、吸血鬼へと斬り掛かってしまったのだ。
「うぉおおおお!!!」
恐らくオニキスから巳羽たちを救おうとしたのだろう。しかし、相手が悪すぎる。
怪人に出来ることは、フタバがまぐれでもオニキスを打倒することを祈るくらいだった。
しかし――現実は、そう甘くはない。
「ぅぉりゃぁ!」
身体能力を何倍にも増した騎士の初撃は確かに吸血鬼を捉えた筈だった。だが、剣が斬り裂いたのは。
「爆ぜろ」
オニキスを形取っていた陽炎が二つに分かたれた途端、爆炎と化して双刃へ迫った。
其処に逃げ場は存在しない。どれほど身体能力を高めていようが関係なく、その炎は容赦なく騎士の身を焼き、弾き飛ばした。
「がァッ!!!」
「フタバ!」
吹き飛ばされた双刃を案じてか、命が思わず声を上げる。
イデオローグに肩を貸していた為に、援護に飛び出すことが出来なかったのだ。
「結城はここにいてくれ」
そう言って一度怪人を地面に下ろせば、彼もまた異能による情報処理の精度を高めるべく一歩前に出る。
命の持つ異能、『天体観測《スターゲイザー》』は『解析』に特化した能力だ。
『魔術』に類する権能を操るオニキスとまともにやり合おうとするならば、その力は必要不可欠だった。
「大丈夫か!?」
「大丈夫だ、戦える!」
命の問いかけに応える双刃の声は、苦痛を噛み殺しつつも戦意は失われてはいない。
個々の戦力差こそ未だに絶望的だが、彼らは熾盛天晴学園天文部、“スターゲイザーズ”だ。
これまでに培われてきた密な連携が嵌ることがあるのなら、もしかすれば――
そんな希望を抱いてしまう。
「もう少し時間を稼いでくれ。本体は見えないが、炎はもうすぐ終わる!」
「っしゃー!オラァ!!」
そのやり取りを皮切りに、再び双刃がオニキスへと斬り掛かっていった。
致命傷を受けないように双刃があしらわれることで、命の解析の時間を稼いでいく。
互いの信頼の上にのみ成り立ちうるその戦術は、数分後ついに実を結ぶこととなった。
何度目かの剣撃に合わせて、後方からリリィが現れたのだ。
まるで心が通じ合っているかのように、三人の連携が始まる。
騎士への迎撃に放たれた炎が、命の異能によって打ち消された。
その隙を見逃さないとばかりにリリィの異能がオニキスに一瞬の眩暈を起こし、そして。
「――ッ!!」
双刃の剣は、それでもオニキスを断つまでは至らなかった。
黒衣の袖口だけが、僅かに斬り裂かれている。
「足りねえな」
辺りで燻っていた炎が、再び燃え上がった。
もはや先ほどまでの火焔とは訳が違う。
イデオローグさえも見たことのなかった、彼の本来の力の一端。
それは生を与えられた大蛇の如く、一切を飲み込まんと大口を開いていた。
分かっていた結果だった。
戦闘の心得があるとは言えど、スターゲイザーズは一介の高校生に過ぎない。
感応の力がどれだけ増幅されていても、あの吸血鬼に同じ手は二度通用しない。
身体能力を更に何倍も強めたところで、それを活かす戦術はまだ組み立てられてはいない。
そして解析の力をどれほど高めても――何もかもが未知の相手には、圧倒的に時間が足りない。
先の連携で討ち取ることが出来なかった時点で、自分たちは負けたのだ。
あるいは、オニキスに邂逅したその瞬間に、全てをかなぐり捨ててでも命たちに真実を告げていたならば、結果は変わっていたのかもしれないが。
言うことを聞かない身体に鞭打って、無理やりにでも立ち上がろうとする。
肩を貸してくれる相手はもういない。自らの血溜まりに沈む己に出来ることは何もない。
けれど。
けれど、それでも。
身体が動いていた。
手にした携帯から、音楽が流れている。
静かに燃え上がるようなオルタナティブ・ロックが、それに込められた異能の暗示が――
イデオローグに、不屈の意志と地を踏みしめる生彩を与えたのだ。
絶対絶命の状況下にあるスターゲイザーズと獄炎を手繰る吸血鬼との間に、ゆらりと怪人が立ちはだかる。
一切を焼き尽くさんとしていた大蛇の動きが、停止する。
それはきっと、オニキスにとって怪人の行動が不可解だったからだ。
「…………!」
吸血鬼は、イデオローグを識っている。
だからこそ、理解出来る筈が無いのだ。
より多くの利益の為なら、どんな弱者も謀ってきた天魔外道。
愛を知らぬが故に愛を憎み、献身という言葉を唾棄する悪党。
それが今、己の全てを投げ打ってそこに立っているのだから。
そう。理解など出来よう筈もない。
其処には何の利益も無く、其処には何の合理も無い。
何よりこの行動に度肝を抜いているのは、イデオローグ本人なのだから!
「――待ってください!」
この時生まれた一瞬で、飛び込んで来た少女がいた。
結城伐都にとっては幼馴染の少女であった、早生さきだ。
「この人は! さっき私とみゅーちゃんを助けてくれました!」
錯乱した訳ではない。狂乱している訳でもない。
ただ彼女は自分の身命を賭して、この戦いを止める為に大蛇の前に立ちはだかっていた。
「この人たちは! 私たちの友達で、先輩です!」
差し迫っている炎に噎せ込み、目に涙を溜めながらも、さきは両者の誤解を正そうとしているのだ。
そして大蛇の目前へと駆け寄る影は、もう一つあった。
「──この馬鹿兄ッ!!」
さきと共に先ほどまで向こうにいた筈の、結城巳羽だ。
怪人へ飛びつくや否や、大蛇から少しでも引き離さんと向かって反対の方向へ引き倒す。
華奢な体躯のイデオローグでは抗う術もなく、無様に地面へ転がって。
そのまま掌中に何かを無理やりに握らされると、そのまま再び地面に放り出される。
イバラシティの住民が持つ異能は、ハザマで強化される。その法則は巳羽においても例外ではないらしい。
乱暴な渡し方ではあったものの、おまもりに込められた祈りは確かに怪人の消えゆく灯火を繋ぎ止めていた――
石を押し付けてすぐ、少女は身を翻して吸血鬼へと相対する。
「炎を、消して下さい。彼らをこれ以上攻撃しないで。でなければあなたは、"イバラシティ"を一人失うことになる」
炎へと、一歩。また一歩。
恐怖にかられる筈の煉獄の中、巳羽はただ歩み続ける。
「わたしは、選びます。ここで生き残るためなら」
さきの隣へ至るまで、ついぞ一度も足を止めることなく。
「あなたを利用し、利用されることを選ぶ」
それはまるで、首を差し出すかのように。
けれどその瞳には、操り人形でも駒でもない、少女自身の、人としての熱が、確かに宿っていた。
最後の力を振り絞って、右手を伸ばす。
けれど、その手は届かない。虚しく空を切った右手の鉤爪だけが、再びゆっくりと地に墜ちた。
そうして。
少女の覚悟の結果を見届けることなく、怪人の意識はやがて闇へと堕ちていく――



ENo.7 七坂 とのやりとり

ENo.148 ツナグ とのやりとり

ENo.277 探偵とアイドル とのやりとり

ENo.1111 仁枝 とのやりとり

ENo.1256 グレーデル とのやりとり

以下の相手に送信しました
















使役LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
オニキス(301) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から射程1の武器『ブラックオニキス』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
さき(911) の持つ ItemNo.6 何か柔らかい物体 から射程1の武器『少し汚れたビー玉』を作製しました!
さき(911) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『まんまるちょこ』をつくってもらいました!
⇒ まんまるちょこ/料理:強さ35/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
さき(911) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『さんかくちょこ』をつくってもらいました!
⇒ さんかくちょこ/料理:強さ35/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
アカイホノオ(1305) とカードを交換しました!
マスクライド:ホノオ (ガーディアン)

アリア を研究しました!(深度0⇒1)
アリア を研究しました!(深度1⇒2)
アリア を研究しました!(深度2⇒3)
魅惑 を習得!
ブルーゲイル を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



オニキス(301) は パンの耳 を入手!
巳羽(473) は 吸い殻 を入手!
イデオローグ(474) は 吸い殻 を入手!
さき(911) は パンの耳 を入手!
オニキス(301) は ねばねば を入手!
イデオローグ(474) は 毛 を入手!
イデオローグ(474) は 不思議な石 を入手!
オニキス(301) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
イデオローグ(474) のもとに 道端ガムマン がゆっくりと近づいてきます。



チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



(今回の日記はEno.148,494,515のスターゲイザーズの皆さん、Eno.301,473,911の熾す魂火メンバーと合わせてお読み頂くことを推奨しております)
一時間。それを区切りに意識が明滅し、覚醒する。
これまでのイバラシティでの日常の記憶が、再び脳内に流れ込んできた。
それはまるで、見ていた夢を反芻するかのように。
クリスマスパーティーのこと。大晦日のこと。正月のこと。
学園の冬休みをイバラシティの住民たちと過ごした記憶が、走馬灯のように思い出されていた。
――大丈夫。この記憶があれば、まだ戦える。
嗚呼、なんて不便なんだ。“ひとのこころ”というものは。
裏切るのも、嘘を吐くのも、慣れっこだった筈なのに。
今ではずきずきと胸が痛んで、息をするのも苦しくなった。
けれど。
けれど、たとえ誰にも信じて貰えなくなったとしても、この幸せな記憶があれば、きっと……耐えられる。
だから――
歩く。歩く。Cross+Roseの位置情報だけを頼りに、荒廃した世界を急ぐ。
イデオローグは疲弊していた。妹のおまもりも無ければ、治癒の異能を操る手駒もいない。
清浄な空気の中でしか生きることの出来ない身体は、独りでは旅路さえままならない不便なものだ。
それでも、前へ進まなければならない理由があった。
 |
イデオローグ 「巳羽……待ってろよ……。 兄ちゃんが……必ず、助けるからな……」 |
Cross+Roseの示す座標はそう遠くない。
次元タクシーを降りて必死に身体を引き摺っていると、背後で後続のタクシーが停車する音がした。
慌ただしく下車してきた二つの足音と共に振り返れば、其処にいたのは――
「……結城!」
「『剣道三倍段《トリスメギストス》』ッ!!」
天文部の部長、胡桃沢命。
そして白銀の甲冑を纏った騎士、蛇乃目双刃。
双刃の方は既に臨戦態勢となり、命を庇うように前へ出て盾を構えていた。
「バツ、お前」
甲冑の奥から聞こえる、少しくぐもった声。
何やら逡巡したような様子で一呼吸置いて、騎士は続ける。
「まさか、アンジニティじゃねぇよな?」
己を疑う問い。
分かっていたことだ。そうなるように、イデオローグは仕向けていたのだから。
自身を無条件に信用してくれる相手ほど、見せたくもない真実に近づいてしまう。
だからこそ――嘘をついてでも、自分への猜疑心を高めておく必要があったのだ。
 |
イデオローグ 「――ナッツ。それに、騎士様」 |
剣呑な雰囲気の中、イデオローグはゆっくりと口を開いた。
 |
イデオローグ 「おれがアンジニティか、だって? 答えるまでもない。……ナッツの異能なら分かる筈だ。そうだろ」 |
自らの口から問いへの答えは返すことなく、双刃越しに命をじっと見つめる。
取引は既に済ませた。あとは、伸るか反るか――友の一人を信じるだけだった。
 |
イデオローグ 「(皮肉なもんだ。嘘なんかをつき通す為に、人を信じなきゃならないとは)」 |
結城伐都となる以前は、息をするように人を騙して生きてきた。
其処に良心の呵責を覚えることなど無かったし、誰かを信じることなども無かった。
そんな自分が今はどうだ?
たった二人に向けられる疑いが、今は何よりも鋭い刃のように感じた。
「安心しろ、結城は結城だ」
静寂を打ち破るように口を開いたのは、命だった。
背後から落ち着かせるように双刃の肩を軽く叩くと、そのまま前へ出てイデオローグへと語り掛ける。
「歩けるか?」
無理なら肩を貸す。そう申し出る少年の表情は、幾つもの感情が綯い交ぜになったようだった。
 |
イデオローグ 「(――なんてこった、最悪だ……!)」 |
位置情報を頼りに辿り着いた先では、妹と幼馴染が身を寄せ合っていた。
しかし、付いてきたおまけは――考え得る限り、最悪のものだった。
 |
イデオローグ 「(今のおれは結城伐都だぞ!? “ヤツのことを知っている筈がねえ”…… これじゃあ、迂闊に動けないじゃねえかッ!!)」 |
アンジニティという地獄に在って、なお危険視されていた怪物の一角。
吸血鬼オニキス。力を以って君臨する狂える王。
それが今、妹たちへの道を阻む壁としてそこに立っていた。
周囲では焦げ臭いにおいを放つナレハテの遺骸が、未だにぶすぶすと音を立てている。
更に状況を悪化させたのは、双刃の行動だった。
カイトシールドを構えて突撃の体勢に入り、吸血鬼へと斬り掛かってしまったのだ。
「うぉおおおお!!!」
恐らくオニキスから巳羽たちを救おうとしたのだろう。しかし、相手が悪すぎる。
怪人に出来ることは、フタバがまぐれでもオニキスを打倒することを祈るくらいだった。
しかし――現実は、そう甘くはない。
「ぅぉりゃぁ!」
身体能力を何倍にも増した騎士の初撃は確かに吸血鬼を捉えた筈だった。だが、剣が斬り裂いたのは。
「爆ぜろ」
オニキスを形取っていた陽炎が二つに分かたれた途端、爆炎と化して双刃へ迫った。
其処に逃げ場は存在しない。どれほど身体能力を高めていようが関係なく、その炎は容赦なく騎士の身を焼き、弾き飛ばした。
「がァッ!!!」
「フタバ!」
吹き飛ばされた双刃を案じてか、命が思わず声を上げる。
イデオローグに肩を貸していた為に、援護に飛び出すことが出来なかったのだ。
「結城はここにいてくれ」
そう言って一度怪人を地面に下ろせば、彼もまた異能による情報処理の精度を高めるべく一歩前に出る。
命の持つ異能、『天体観測《スターゲイザー》』は『解析』に特化した能力だ。
『魔術』に類する権能を操るオニキスとまともにやり合おうとするならば、その力は必要不可欠だった。
「大丈夫か!?」
「大丈夫だ、戦える!」
命の問いかけに応える双刃の声は、苦痛を噛み殺しつつも戦意は失われてはいない。
個々の戦力差こそ未だに絶望的だが、彼らは熾盛天晴学園天文部、“スターゲイザーズ”だ。
これまでに培われてきた密な連携が嵌ることがあるのなら、もしかすれば――
そんな希望を抱いてしまう。
「もう少し時間を稼いでくれ。本体は見えないが、炎はもうすぐ終わる!」
「っしゃー!オラァ!!」
そのやり取りを皮切りに、再び双刃がオニキスへと斬り掛かっていった。
致命傷を受けないように双刃があしらわれることで、命の解析の時間を稼いでいく。
互いの信頼の上にのみ成り立ちうるその戦術は、数分後ついに実を結ぶこととなった。
何度目かの剣撃に合わせて、後方からリリィが現れたのだ。
まるで心が通じ合っているかのように、三人の連携が始まる。
騎士への迎撃に放たれた炎が、命の異能によって打ち消された。
その隙を見逃さないとばかりにリリィの異能がオニキスに一瞬の眩暈を起こし、そして。
「――ッ!!」
双刃の剣は、それでもオニキスを断つまでは至らなかった。
黒衣の袖口だけが、僅かに斬り裂かれている。
「足りねえな」
辺りで燻っていた炎が、再び燃え上がった。
もはや先ほどまでの火焔とは訳が違う。
イデオローグさえも見たことのなかった、彼の本来の力の一端。
それは生を与えられた大蛇の如く、一切を飲み込まんと大口を開いていた。
分かっていた結果だった。
戦闘の心得があるとは言えど、スターゲイザーズは一介の高校生に過ぎない。
感応の力がどれだけ増幅されていても、あの吸血鬼に同じ手は二度通用しない。
身体能力を更に何倍も強めたところで、それを活かす戦術はまだ組み立てられてはいない。
そして解析の力をどれほど高めても――何もかもが未知の相手には、圧倒的に時間が足りない。
先の連携で討ち取ることが出来なかった時点で、自分たちは負けたのだ。
あるいは、オニキスに邂逅したその瞬間に、全てをかなぐり捨ててでも命たちに真実を告げていたならば、結果は変わっていたのかもしれないが。
 |
イデオローグ 「ちき、しょう……!」 |
言うことを聞かない身体に鞭打って、無理やりにでも立ち上がろうとする。
肩を貸してくれる相手はもういない。自らの血溜まりに沈む己に出来ることは何もない。
けれど。
けれど、それでも。
身体が動いていた。
手にした携帯から、音楽が流れている。
静かに燃え上がるようなオルタナティブ・ロックが、それに込められた異能の暗示が――
イデオローグに、不屈の意志と地を踏みしめる生彩を与えたのだ。
絶対絶命の状況下にあるスターゲイザーズと獄炎を手繰る吸血鬼との間に、ゆらりと怪人が立ちはだかる。
 |
イデオローグ 「おまえの相手は――このおれだ」 |
一切を焼き尽くさんとしていた大蛇の動きが、停止する。
それはきっと、オニキスにとって怪人の行動が不可解だったからだ。
「…………!」
吸血鬼は、イデオローグを識っている。
だからこそ、理解出来る筈が無いのだ。
より多くの利益の為なら、どんな弱者も謀ってきた天魔外道。
愛を知らぬが故に愛を憎み、献身という言葉を唾棄する悪党。
それが今、己の全てを投げ打ってそこに立っているのだから。
 |
イデオローグ 「(ああ、くそッ! おれは何をやってるんだ!? なんなんだよ、これは! この胸の中の、熱いもんはッ!!)」 |
そう。理解など出来よう筈もない。
其処には何の利益も無く、其処には何の合理も無い。
何よりこの行動に度肝を抜いているのは、イデオローグ本人なのだから!
「――待ってください!」
この時生まれた一瞬で、飛び込んで来た少女がいた。
結城伐都にとっては幼馴染の少女であった、早生さきだ。
「この人は! さっき私とみゅーちゃんを助けてくれました!」
錯乱した訳ではない。狂乱している訳でもない。
ただ彼女は自分の身命を賭して、この戦いを止める為に大蛇の前に立ちはだかっていた。
「この人たちは! 私たちの友達で、先輩です!」
差し迫っている炎に噎せ込み、目に涙を溜めながらも、さきは両者の誤解を正そうとしているのだ。
そして大蛇の目前へと駆け寄る影は、もう一つあった。
「──この馬鹿兄ッ!!」
さきと共に先ほどまで向こうにいた筈の、結城巳羽だ。
怪人へ飛びつくや否や、大蛇から少しでも引き離さんと向かって反対の方向へ引き倒す。
華奢な体躯のイデオローグでは抗う術もなく、無様に地面へ転がって。
 |
イデオローグ 「おわ!?」 |
そのまま掌中に何かを無理やりに握らされると、そのまま再び地面に放り出される。
イバラシティの住民が持つ異能は、ハザマで強化される。その法則は巳羽においても例外ではないらしい。
乱暴な渡し方ではあったものの、おまもりに込められた祈りは確かに怪人の消えゆく灯火を繋ぎ止めていた――
石を押し付けてすぐ、少女は身を翻して吸血鬼へと相対する。
「炎を、消して下さい。彼らをこれ以上攻撃しないで。でなければあなたは、"イバラシティ"を一人失うことになる」
炎へと、一歩。また一歩。
恐怖にかられる筈の煉獄の中、巳羽はただ歩み続ける。
「わたしは、選びます。ここで生き残るためなら」
さきの隣へ至るまで、ついぞ一度も足を止めることなく。
「あなたを利用し、利用されることを選ぶ」
それはまるで、首を差し出すかのように。
けれどその瞳には、操り人形でも駒でもない、少女自身の、人としての熱が、確かに宿っていた。
 |
イデオローグ 「巳、羽――」 |
最後の力を振り絞って、右手を伸ばす。
けれど、その手は届かない。虚しく空を切った右手の鉤爪だけが、再びゆっくりと地に墜ちた。
 |
イデオローグ 「(守ってもらうばっかりなのって、こんなにダセぇんだなあ……)」 |
そうして。
少女の覚悟の結果を見届けることなく、怪人の意識はやがて闇へと堕ちていく――



ENo.7 七坂 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.148 ツナグ とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
| |||||||
ENo.277 探偵とアイドル とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.1111 仁枝 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1256 グレーデル とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
特に後ろのやり取りには干渉せず、ただ黙々と一行を先導している。……が、後ろでふわふわしている伐都の方を見て、はっ、と嘲笑を浮かべた気がした。 |
 |
巳羽 「さっちゃん、暫くそのままでお願いね。 ……この馬鹿も、流石に空は泳げないだろうし」 |
 |
気を失ってからというもの、怪人はさきの異能で身体を浮かされて 宙をふわふわと漂い続けている。まるで宇宙遊泳のようだ。 意識を取り戻してもそれは変わらず、風船か何かのように連れられている。 |
 |
バツ 「……あのう、さきー? さきさんやー? そろそろ降ろしてくんない?」 |
 |
バツ 「なんか巳羽まで全然口利いてくれないし……。 うう、まじでおれだけ良いトコ無しだな、トホホ……」 |
 |
さき 「みゅーちゃんりょ。無茶した病人さんはおとなしくー」 |





はぐれPPP
|
 |
熾す魂火、絶えぬ火光
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 2 増加!
影響力が 2 増加!



使役LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
オニキス(301) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から射程1の武器『ブラックオニキス』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
さき(911) の持つ ItemNo.6 何か柔らかい物体 から射程1の武器『少し汚れたビー玉』を作製しました!
さき(911) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『まんまるちょこ』をつくってもらいました!
⇒ まんまるちょこ/料理:強さ35/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
 |
さき 「ええとね、これがまるいので。」 |
さき(911) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『さんかくちょこ』をつくってもらいました!
⇒ さんかくちょこ/料理:強さ35/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
 |
さき 「こっちは三角!」 |
アカイホノオ(1305) とカードを交換しました!
マスクライド:ホノオ (ガーディアン)

アリア を研究しました!(深度0⇒1)
アリア を研究しました!(深度1⇒2)
アリア を研究しました!(深度2⇒3)
魅惑 を習得!
ブルーゲイル を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



オニキス(301) は パンの耳 を入手!
巳羽(473) は 吸い殻 を入手!
イデオローグ(474) は 吸い殻 を入手!
さき(911) は パンの耳 を入手!
オニキス(301) は ねばねば を入手!
イデオローグ(474) は 毛 を入手!
イデオローグ(474) は 不思議な石 を入手!
オニキス(301) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
イデオローグ(474) のもとに 道端ガムマン がゆっくりと近づいてきます。



チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――







熾す魂火、絶えぬ火光
|
 |
ミナモニティ
|


ENo.474
結城伐都



結城 伐都(ゆうき ばっと)
愛称はバツ。熾盛天晴学園の高等部に在籍。
不健康そうな隈の深い目、細い身体に吐血癖。
制服を肩に羽織るようにして着ている猫背の男。
無造作ヘアに赤黒ブロックチェック柄のバンダナを巻いている。
熾盛天晴学園の昼の校内放送『ハレ高Balmy hour』のDJであり、イバラシティ内のクラブハウスでDJをやることも多い。
お祭り好きの情報通であり、面白そうな気配を嗅ぎ付ければ方々に顔を出す。
生徒会にも広報として席を連ねており、内申の為に日々雑用をこなしている。
中等部に巳羽という妹がいる。兄妹仲は良好。
異能:『踊る阿呆に見る阿呆(バッド・トリップ・ダイブ)』
精神干渉系異能。『使役』に分類されるこの能力は、音楽に暗示を乗せる力を持っている。
「かけた音楽で気分をアゲたりサゲたり出来る、便利な異能だよ」とは本人の弁。
人間の精神に深く作用させるには対象者の合意が必要であり、そういった運用はなかなか難しいらしい。
というのは、侵略の為に創られたイバラシティの中だけの架空の存在である。
その正体は、蝙蝠と人間の特徴を併せ持った異種族。
澄んだ空気の中でしか生きられぬ脆弱な身体を持つ代わりに、彼らは『心を惑わす音を操る』という権能を持っていた。
ある時は力を危険視されて狩り立てられ、ある時はその力を独占すべく囚われ、他の全ての同胞が命を落としても、この個体だけは逃げ延びた。
いつしかヒトに付けられた名前は、虚構の扇動者――イデオローグ。
それは最早、他に同族を持たぬ彼の種族名であり、個体名である。
イデオローグは生まれ落ちた世界から否定され、数年ほど前にアンジニティへ堕ちてきた。
それ以降、彼は人を騙し、裏切り、常に強者へと媚び諂うことで生き延びてきた。
正義を知らぬ彼に貫くべき道義はなく、愛を知らぬ彼に守るものはない。
もしもかの世界であなたが彼を見かけたことがあるのならば、強者として利用され裏切られていたり、略奪の対象として襲われていたり、あるいは返り討ちにしていたことも、あるのかもしれない。
異能:『冒涜の奏者(ディフェム・プレーヤー)』
精神干渉系異能。『使役』に分類されるこの能力は、“心を惑わす音”を操る力を持つ。
この異能は対象の『猜疑心』が強ければ強いほど効果を強めるというもので、信頼されていればされているほどその効果は弱まってしまう。
弱点は強靭な精神。過酷な世界であっても揺らぐことの無い強固な意志を持つ相手にはこの力は通用しないことが多い。
あるいは、ハザマで強化された異能を持つイバラシティの市民に対しても、生来の抵抗力を以ってして無効化される恐れがある。
また、結城伐都の人格と共に生まれた異能である『踊る阿呆に見る阿呆』は併用が可能。
こちらは逆に対象者の信頼、信用が必要となる。
幻覚を見せたり洗脳したりといったことは出来ないものの、プラシーボ効果を過剰に強化して治癒能力を高めたり、味方同士と認識している相手の異能を強化することが出来る。
☆ハザマでのチャットについて
あなたがハザマ世界において不安を抱いている状態で通信を繋げば、“冒涜の奏者”は彼に「結城伐都」の姿を纏わせてVR空間に出現させるでしょう。
あなたがハザマ世界においても強靭な精神を持った状態で通信を繋ぐ、あるいは元々イデオローグの存在を知っているならば、“冒涜の奏者”はその力を十全に発揮出来ずに「イデオローグ」としてVR空間に出現します。
愛称はバツ。熾盛天晴学園の高等部に在籍。
不健康そうな隈の深い目、細い身体に吐血癖。
制服を肩に羽織るようにして着ている猫背の男。
無造作ヘアに赤黒ブロックチェック柄のバンダナを巻いている。
熾盛天晴学園の昼の校内放送『ハレ高Balmy hour』のDJであり、イバラシティ内のクラブハウスでDJをやることも多い。
お祭り好きの情報通であり、面白そうな気配を嗅ぎ付ければ方々に顔を出す。
生徒会にも広報として席を連ねており、内申の為に日々雑用をこなしている。
中等部に巳羽という妹がいる。兄妹仲は良好。
異能:『踊る阿呆に見る阿呆(バッド・トリップ・ダイブ)』
精神干渉系異能。『使役』に分類されるこの能力は、音楽に暗示を乗せる力を持っている。
「かけた音楽で気分をアゲたりサゲたり出来る、便利な異能だよ」とは本人の弁。
人間の精神に深く作用させるには対象者の合意が必要であり、そういった運用はなかなか難しいらしい。
というのは、侵略の為に創られたイバラシティの中だけの架空の存在である。
その正体は、蝙蝠と人間の特徴を併せ持った異種族。
澄んだ空気の中でしか生きられぬ脆弱な身体を持つ代わりに、彼らは『心を惑わす音を操る』という権能を持っていた。
ある時は力を危険視されて狩り立てられ、ある時はその力を独占すべく囚われ、他の全ての同胞が命を落としても、この個体だけは逃げ延びた。
いつしかヒトに付けられた名前は、虚構の扇動者――イデオローグ。
それは最早、他に同族を持たぬ彼の種族名であり、個体名である。
イデオローグは生まれ落ちた世界から否定され、数年ほど前にアンジニティへ堕ちてきた。
それ以降、彼は人を騙し、裏切り、常に強者へと媚び諂うことで生き延びてきた。
正義を知らぬ彼に貫くべき道義はなく、愛を知らぬ彼に守るものはない。
もしもかの世界であなたが彼を見かけたことがあるのならば、強者として利用され裏切られていたり、略奪の対象として襲われていたり、あるいは返り討ちにしていたことも、あるのかもしれない。
異能:『冒涜の奏者(ディフェム・プレーヤー)』
精神干渉系異能。『使役』に分類されるこの能力は、“心を惑わす音”を操る力を持つ。
この異能は対象の『猜疑心』が強ければ強いほど効果を強めるというもので、信頼されていればされているほどその効果は弱まってしまう。
弱点は強靭な精神。過酷な世界であっても揺らぐことの無い強固な意志を持つ相手にはこの力は通用しないことが多い。
あるいは、ハザマで強化された異能を持つイバラシティの市民に対しても、生来の抵抗力を以ってして無効化される恐れがある。
また、結城伐都の人格と共に生まれた異能である『踊る阿呆に見る阿呆』は併用が可能。
こちらは逆に対象者の信頼、信用が必要となる。
幻覚を見せたり洗脳したりといったことは出来ないものの、プラシーボ効果を過剰に強化して治癒能力を高めたり、味方同士と認識している相手の異能を強化することが出来る。
☆ハザマでのチャットについて
あなたがハザマ世界において不安を抱いている状態で通信を繋げば、“冒涜の奏者”は彼に「結城伐都」の姿を纏わせてVR空間に出現させるでしょう。
あなたがハザマ世界においても強靭な精神を持った状態で通信を繋ぐ、あるいは元々イデオローグの存在を知っているならば、“冒涜の奏者”はその力を十全に発揮出来ずに「イデオローグ」としてVR空間に出現します。
20 / 30
27 PS
チナミ区
N-6
N-6






































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | Weasel | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 黒手袋 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | まんまるちょこ | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | さんかくちょこ | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 15 | 空間/時間/風 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 武器 | 25 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 強撃 (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 痛撃 (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| トリックプレイ (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 怪音波 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| キュー (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| インスパイア (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 襲爪撃 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| ジャグリング (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 決1 | ソニックブーム (ウィンドカッター) | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 |
| キャスリング (サステイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| バッド・トリップ・ダイブ (ヴィガラスチャージ) | 5 | 0 | 100 | 味全:次与ダメ増 | |
| アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| ブルーゲイル | 5 | 0 | 80 | 敵従傷:風撃+凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| アンプリファイア (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| ウーファー (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| アップテンポ (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| スローテンポ (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| ヒーリング (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 陽動 (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 悪知恵 (隠者) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]アリア | [ 3 ]ヒールハーブ |

PL / せい