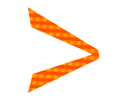<< 0:00~1:00




右目は過去を、左眼は未来を見ている。だから片目を隠す奴はそのどちらかから目を背けている。
どこで読んだ記事だったかは忘れた。右目に眼帯をしている身として鼻で嗤ったのは覚えている。
過去も未来もことさら大事にした覚えはないし、刹那主義を自認しているからには最優先は『今』だと即答できる。しかしだからと言って、目を背けているとはずいぶんな言い草だと思う。
そもそも、自分のこの眼は見え過ぎるから隠しているのだ。となれば自分は過去に囚われやすい男ということになる。
……いや、必ずしも間違いではないか。過去のある出来事一つが、どうしようもなく今の自分を形成しているのは認めよう。少し前までは意識すらしていなかったこと、一人の少女に吐き出してやっと分かった自分のこと。
Cross+Roseで精査したところ、彼女はこの戦争に巻き込まれていないらしい。少なからぬ安心を覚えたのは確かだ。
それは、もちろん殺し合いに巻き込まれていないこと(負ければ強制退去に違いないが)と、もう一つ。
「……重いんだって」
「えー。でもあるきたくない」

やたらとべたべたしてくる背中の女……厳密には女性体を取ってるだけの無性だが、ともかくこいつに嫉妬されてしまうかもしれなかったからだ。
話は幾らか遡って、味方も見えないハザマのある場所で足を止めたところからだ。
俺は、先程からずっと自分の後を付いて回ってきている謎の物体を、いよいよ無視できなくなっていた。
大まかな形状は球体。地球に擬えるなら、北半球が金属質で南半球が岩肌。北半球に入った幾つかの幾何学的なラインからは光が漏れ、南半球にはこれまた金属光沢のある足(手?)が二本脇からぶら下がっていた。
そして、赤道ど真ん中にある三角形が滑るような赤い光を湛えている。
うむ、正体不明だ。磨きまくった泥団子の妖精に見えないこともない。
「何だお前」
「み」
投げた誰何を受けた玉ッコロは、返事らしい返事をせずにただふよふよと浮くばかり。
待てど暮らせどリアクションは絶無で、がしがしと頭を掻いて溜息を零した。
「……言葉も話せねえし、いよいよ分かんねえぞ。通信でも使って剣野にでもに訊くか?」
訳の分からんモノは適当に魔術認定して大魔導士に放り投げるべし。相良伊橋高校での処世術だ。今考えた。
今、自分の何倍も友人たちを気にかけているであろう彼に、果たして本当に投げかけるべき問いかどうかは疑問だ。だがこのまんまつけ回されたのでは気になって仕方ないのである。せめて正体のヒントくらいは欲しい。
Cross+Roseを起動するために空を見上げる。思えばこいつも相当不思議な機能だ。異能の街で不可思議の原理を問うほどのナンセンスはあまりないが、しかし何をどうすればハザマ中の全員と通信が出来るようになるのか。
いっそイバラシティでも普通に使えるようにならねえかな、と他愛もないことを考えながら検索している最中、どすんと背中に鈍い衝撃。正体は見なくても分かった。
「俺今忙しいんだよ。遊び相手なら、ほら、向こうのヤンキー見えるか? あれにでも相手してもらって来い。……そもそも日本語分かんのかお前」
応答はない。せめて球体の中央に誂えられた赤い三角を不規則にでも明滅させてくれればこちらとしても会話している気にもなるのだが、変化なくじっとりと薄く発光するばかりだ。
そのくせがしがしと体当たりだけはかましてくるのだからいよいよ参る。
何がしたいのか、何をして欲しいのか、何のために俺に付きまとっているのか。これっぽっちも分からないから、手の打ちようがない。
そのヒントを得るための通信の邪魔をされないよう、左手を挟んでぐいと力任せに押し退ける。
「お前に構ってる暇ないんだって──あ、オイコラ何してんだお前」
噛まれた。
いや、口が分からないから"噛まれた"が正しい表現なのかは知らない。ともかく、北半球と南半球が僅かに分かたれ、俺の手を結構強めに挟んだ。
結構本気で引っこ抜こうとしても全然動かない。しかも三角形の頂点が刺さって結構痛い。
まさかアンジニティか、と呆れと戦慄がないまぜになった複雑な感情を抱いて、それから直ぐに左手は帰って来た。少々血が出たくらいの怪我で、侵略行為にしては随分控えめだった。
結局この行為も何なのか。顔を押さえつけられて怒ったのか。果たしてお前に感情はあるのか。
そんな畳み掛けてくる疑問は、すぐさま消し飛ぶことになる。
何しろ、性別不詳どころか有機生命体ですらない玉ッコロが眩く光ったかと思えば、
「……あ、う。うー……よし」
「いやよしじゃねえけど!?」
褐色肌の美女に化けていたのだから。

幻覚かと思って思わず美女の頬をぺちぺち叩いてみた。叩き返されたから実体を持つ本物だと悟った。石や金属を整えたような硬質ではなく、張りと弾力のある肌だということも分かった。
「わ、訳が分かんねえ……何より腰入った右ストレートはやり過ぎじゃない? 手足生えたからってはしゃぎ過ぎだろオイ」
「そっちがきがいをくわえるのがよくない」
「しかも喋んの? さっきまでのなんちゃってマスコットめいた鳴き声はどうしたんだよ」
「にほんごはいまおぼえたから」
それ、と指差されるのは出血した左手で、血を吸ったから理解したとでも言いたげだ。
……いや、まさかその通りなのか。だとするとあの姿は、いったい何から抽出されたものなのか。性癖か。
「いやでも胸以外はそんなに」
「いまうまれたばかりでも、さいていなかんがえをしてるのくらいわかるよ」
元が泥団子の妖精なのを知っているから、女性の見た目をしている相手の割に発言に遠慮が無くなっていた。
何はともあれ、言葉が通じるようになったのは幸いだ。意思疎通は人間を社会性動物足らしむ根幹、一番の発明品と言っても差し支えないだろう。民俗文化研究部(民俗文化を研究していない)の長たる自分が言うのだから間違いない。
「……で、結局お前何なの?」
再三の問い。彼女の答えは、
「わたし? わたしは、あなた」
シンプルで、理解に苦しむものだった。
非常に遅くなってしまったが。
この話は、一つの街を廻る戦争の片隅で紐を解かれた、一栄斗の自己究明の物語だ。



ENo.658 天弖 とのやりとり

以下の相手に送信しました












具現LV を 15 DOWN。(LV20⇒5、+15CP、-15FP)
合成LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
防具LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
杏子(451) の持つ ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物発生!駄物 を入手!
杏子(451) により ItemNo.4 何か柔らかい物体 から射程1の武器『鉄芯』を作製してもらいました!
⇒ 鉄芯/武器:強さ35/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ハザマ風味七草粥』をつくりました!
⇒ ハザマ風味七草粥/料理:強さ20/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]-/特殊アイテム
つぼみ(901) とカードを交換しました!
芽吹つぼみのカード (オートヒール)


オートヒール を研究しました!(深度0⇒1)
オートヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
ストーンブラスト を習得!
アイアンナックル を習得!
クリエイト:シールド を習得!
クリエイト:ホーネット を習得!
チャージ を習得!
ブルーム を習得!
ブランチ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 K-5(隔壁)には移動できません。






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



右目は過去を、左眼は未来を見ている。だから片目を隠す奴はそのどちらかから目を背けている。
どこで読んだ記事だったかは忘れた。右目に眼帯をしている身として鼻で嗤ったのは覚えている。
過去も未来もことさら大事にした覚えはないし、刹那主義を自認しているからには最優先は『今』だと即答できる。しかしだからと言って、目を背けているとはずいぶんな言い草だと思う。
そもそも、自分のこの眼は見え過ぎるから隠しているのだ。となれば自分は過去に囚われやすい男ということになる。
……いや、必ずしも間違いではないか。過去のある出来事一つが、どうしようもなく今の自分を形成しているのは認めよう。少し前までは意識すらしていなかったこと、一人の少女に吐き出してやっと分かった自分のこと。
Cross+Roseで精査したところ、彼女はこの戦争に巻き込まれていないらしい。少なからぬ安心を覚えたのは確かだ。
それは、もちろん殺し合いに巻き込まれていないこと(負ければ強制退去に違いないが)と、もう一つ。
「……重いんだって」
「えー。でもあるきたくない」

やたらとべたべたしてくる背中の女……厳密には女性体を取ってるだけの無性だが、ともかくこいつに嫉妬されてしまうかもしれなかったからだ。
話は幾らか遡って、味方も見えないハザマのある場所で足を止めたところからだ。
俺は、先程からずっと自分の後を付いて回ってきている謎の物体を、いよいよ無視できなくなっていた。
大まかな形状は球体。地球に擬えるなら、北半球が金属質で南半球が岩肌。北半球に入った幾つかの幾何学的なラインからは光が漏れ、南半球にはこれまた金属光沢のある足(手?)が二本脇からぶら下がっていた。
そして、赤道ど真ん中にある三角形が滑るような赤い光を湛えている。
うむ、正体不明だ。磨きまくった泥団子の妖精に見えないこともない。
「何だお前」
「み」
投げた誰何を受けた玉ッコロは、返事らしい返事をせずにただふよふよと浮くばかり。
待てど暮らせどリアクションは絶無で、がしがしと頭を掻いて溜息を零した。
「……言葉も話せねえし、いよいよ分かんねえぞ。通信でも使って剣野にでもに訊くか?」
訳の分からんモノは適当に魔術認定して大魔導士に放り投げるべし。相良伊橋高校での処世術だ。今考えた。
今、自分の何倍も友人たちを気にかけているであろう彼に、果たして本当に投げかけるべき問いかどうかは疑問だ。だがこのまんまつけ回されたのでは気になって仕方ないのである。せめて正体のヒントくらいは欲しい。
Cross+Roseを起動するために空を見上げる。思えばこいつも相当不思議な機能だ。異能の街で不可思議の原理を問うほどのナンセンスはあまりないが、しかし何をどうすればハザマ中の全員と通信が出来るようになるのか。
いっそイバラシティでも普通に使えるようにならねえかな、と他愛もないことを考えながら検索している最中、どすんと背中に鈍い衝撃。正体は見なくても分かった。
「俺今忙しいんだよ。遊び相手なら、ほら、向こうのヤンキー見えるか? あれにでも相手してもらって来い。……そもそも日本語分かんのかお前」
応答はない。せめて球体の中央に誂えられた赤い三角を不規則にでも明滅させてくれればこちらとしても会話している気にもなるのだが、変化なくじっとりと薄く発光するばかりだ。
そのくせがしがしと体当たりだけはかましてくるのだからいよいよ参る。
何がしたいのか、何をして欲しいのか、何のために俺に付きまとっているのか。これっぽっちも分からないから、手の打ちようがない。
そのヒントを得るための通信の邪魔をされないよう、左手を挟んでぐいと力任せに押し退ける。
「お前に構ってる暇ないんだって──あ、オイコラ何してんだお前」
噛まれた。
いや、口が分からないから"噛まれた"が正しい表現なのかは知らない。ともかく、北半球と南半球が僅かに分かたれ、俺の手を結構強めに挟んだ。
結構本気で引っこ抜こうとしても全然動かない。しかも三角形の頂点が刺さって結構痛い。
まさかアンジニティか、と呆れと戦慄がないまぜになった複雑な感情を抱いて、それから直ぐに左手は帰って来た。少々血が出たくらいの怪我で、侵略行為にしては随分控えめだった。
結局この行為も何なのか。顔を押さえつけられて怒ったのか。果たしてお前に感情はあるのか。
そんな畳み掛けてくる疑問は、すぐさま消し飛ぶことになる。
何しろ、性別不詳どころか有機生命体ですらない玉ッコロが眩く光ったかと思えば、
「……あ、う。うー……よし」
「いやよしじゃねえけど!?」
褐色肌の美女に化けていたのだから。

タウ
泥団子の妖精(仮)。
乳がデカい。
乳がデカい。
幻覚かと思って思わず美女の頬をぺちぺち叩いてみた。叩き返されたから実体を持つ本物だと悟った。石や金属を整えたような硬質ではなく、張りと弾力のある肌だということも分かった。
「わ、訳が分かんねえ……何より腰入った右ストレートはやり過ぎじゃない? 手足生えたからってはしゃぎ過ぎだろオイ」
「そっちがきがいをくわえるのがよくない」
「しかも喋んの? さっきまでのなんちゃってマスコットめいた鳴き声はどうしたんだよ」
「にほんごはいまおぼえたから」
それ、と指差されるのは出血した左手で、血を吸ったから理解したとでも言いたげだ。
……いや、まさかその通りなのか。だとするとあの姿は、いったい何から抽出されたものなのか。性癖か。
「いやでも胸以外はそんなに」
「いまうまれたばかりでも、さいていなかんがえをしてるのくらいわかるよ」
元が泥団子の妖精なのを知っているから、女性の見た目をしている相手の割に発言に遠慮が無くなっていた。
何はともあれ、言葉が通じるようになったのは幸いだ。意思疎通は人間を社会性動物足らしむ根幹、一番の発明品と言っても差し支えないだろう。民俗文化研究部(民俗文化を研究していない)の長たる自分が言うのだから間違いない。
「……で、結局お前何なの?」
再三の問い。彼女の答えは、
「わたし? わたしは、あなた」
シンプルで、理解に苦しむものだった。
非常に遅くなってしまったが。
この話は、一つの街を廻る戦争の片隅で紐を解かれた、一栄斗の自己究明の物語だ。



ENo.658 天弖 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
ニノマエ 「……しかし。こいつどうしよう」 |
 |
タウ 「?」 |







具現LV を 15 DOWN。(LV20⇒5、+15CP、-15FP)
合成LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
防具LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
杏子(451) の持つ ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物発生!駄物 を入手!
杏子(451) により ItemNo.4 何か柔らかい物体 から射程1の武器『鉄芯』を作製してもらいました!
⇒ 鉄芯/武器:強さ35/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
杏子 「……ハイ、出来ました。センパイの異能なら上手く扱えると思います!表面がザラついているものは磁化させてあるので上手く使ってくださいね。健闘を祈ります!」 |
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ハザマ風味七草粥』をつくりました!
⇒ ハザマ風味七草粥/料理:強さ20/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]-/特殊アイテム
 |
ニノマエ 「……食えんのかコレ?」 |
 |
タウ 「……へんなにおいがする」 |
つぼみ(901) とカードを交換しました!
芽吹つぼみのカード (オートヒール)


オートヒール を研究しました!(深度0⇒1)
オートヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
ストーンブラスト を習得!
アイアンナックル を習得!
クリエイト:シールド を習得!
クリエイト:ホーネット を習得!
チャージ を習得!
ブルーム を習得!
ブランチ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 K-5(隔壁)には移動できません。






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――





ENo.46
一栄斗



【名前】一 栄斗(ニノマエ・エイト)
【年齢】17 【性別】男
【身長/体重】179cm/67kg
【学校】相良伊橋高校2年特進科・民俗文化研究部部長・生徒会執行部副会長
「やっべ、良いこと思い付いた……やっぱ俺天才だわ」
余裕綽綽泰然自若、ヒトを食ったような軽薄な態度で常を過ごす悪ガキ。
ブレザーの代わりに黒いパーカーを羽織っている。
大抵のことは努力せずとも熟せる天才肌で、そのため特進科にいるのに授業を聞き流しがち。恐らく先生がたからの心証はあまりよくない。
彼が立ち上げた民俗文化研究部は、『学校に勝手出来る部屋が欲しいから』立ち上げられており、名前の通りの活動を行うことはごく稀。
【年齢】17 【性別】男
【身長/体重】179cm/67kg
【学校】相良伊橋高校2年特進科・民俗文化研究部部長・生徒会執行部副会長
「やっべ、良いこと思い付いた……やっぱ俺天才だわ」
余裕綽綽泰然自若、ヒトを食ったような軽薄な態度で常を過ごす悪ガキ。
ブレザーの代わりに黒いパーカーを羽織っている。
大抵のことは努力せずとも熟せる天才肌で、そのため特進科にいるのに授業を聞き流しがち。恐らく先生がたからの心証はあまりよくない。
彼が立ち上げた民俗文化研究部は、『学校に勝手出来る部屋が欲しいから』立ち上げられており、名前の通りの活動を行うことはごく稀。
25 / 30
26 PS
チナミ区
J-5
J-5







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 鉄芯 | 武器 | 35 | 治癒10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 6 | ハザマ風味七草粥 | 料理 | 20 | 器用10 | 敏捷10 | - | |
| 7 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]耐疫10(LV30)[防具]体力10(LV30)[装飾]強靭10(LV30) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 防具 | 5 | 防具作製に影響 |
| 合成 | 10 | 合成に影響 |
| 料理 | 10 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ブランチ | 5 | 0 | 100 | 敵:地痛撃&領域値[地]3以上なら、敵傷:地領痛撃 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 駄物発生 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『合成』で、合成成功時に自分にアイテム「駄物」が手に入る。(実験除く、1更新1つまで) |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストーンブラスト | [ 1 ]キュアブリーズ | [ 1 ]チャージ |
| [ 2 ]オートヒール | [ 1 ]イレイザー |

PL / 空気頭の蛞蝓