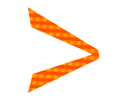<< 0:00~1:00




ブランブル女学院でクリスマスミサが終わると冬休み期間に突入する。
二週間足らずの短い期間ではあるが、家族と一緒に年末年始を過ごすとても大切な時期である。
大多数の生徒がそうであるように、降雪夜道もまた実家へと帰ってきていた。
「お父様は……お許しくださったのよね……この、時期なのに」
いくつもの感情が入り混じった表情で、手元の手紙を眺めている。
それが届いたのは数日前のこと。
書いていたのは聖が知り合った友達の事と、ここ数か月の成果の事。それと……帰省の許可について。
もっとも、それについてはいくつもの条件が課されていた。
そのどれもが夜道には納得できるもので、
そして、一年経とうとも未だ変わらない、冷たい現実を突き付けてくるものだった。
街はまだクリスマスムードが抜けきらないようだ。
イバラシティを抜けて隣の町へ。そしてそのまた隣へ。
それほど長い距離ではないものの、夜道にとっては遠く遠く離れた距離に感じていた。
今まで何度も引っ越しをして、新しい住居へと移り渡ってきていたが、今の一人の環境にはいつまで経っても慣れることはなく。
……彼女が共に暮らす誰かを思うと、その気持ちもまた一段と強くなるようだった。
電車のアナウンスが停車駅を告げる。
1年前から変わらない最寄り駅。
夜道に馴染みのない最寄り駅。
気持ちに躊躇する所がないわけではない。
けれど、それ以上に、会いたい気持ちの方がそれの何倍も、何十倍も、強かった。
例え、どんな条件が不随していたとしても……家族に会えるのならば、何を対価としても惜しくはない。
降雪夜道はそういう少女なのだから。
「お土産は……これで良かったかしら。お母様は和菓子が好きだから……。
お父様は甘いの苦手なのよね。ふふっ、甘いお菓子なのに苦そうなお顔をして、それでも口にしてくださるのよね。
……懐かしい、ですわ。本当に……。もう、あれから一年、ですのね」
坂道を下りながら思い出を思い返していく。お父様が居て、お母様が居て。当たり前の日々を過ごす自身の姿。
けれど、今は一人別の街に居て、初めての学校で違う自分を演じている。
それが苦であると感じたことはないけれど、決して寂しいと感じない訳ではなかった。
色褪せない思い出。切なく胸を締め付ける思い出。
優しい笑顔。悲しい笑顔。
夜道の大好きだったかつての日々。夜道ではいられないかつての日々。
……到着した家の表札には確かに降雪の文字。
昼間なので玄関の扉は開いているだろう。
夜道は、静かに門の前にあるチャイムを鳴らした。
ビー。
無機質な機械音。家の中で微かな物音。
パタパタとスリッパの音が鳴って、そして──
「はい。お待たせー。まぁ、ヨミちゃん!大きくなったわね!さあ、あがって、あがって!今ちょうどクッキーが焼きあがった所なの!」
……ああ。
扉を開けて出迎えてくれたのは、降雪夜道の母の姿で。
お母さんが私に笑顔を向けてくれている
「ご無沙汰しております。桔梗おば様。まぁ、クッキーですの? うふふ、とっても楽しみですわ。
それでは、お邪魔致しますわね。……おじ様はどちらに?」
お淑やかに一礼をして微笑んで。家の中へと招き入れられる。父の姿が見えないことを不思議に思って尋ねてみた。父と会うのも久しぶりになる。少しソワソワした気持ちになってしまうのも仕方ないだろう。
「どうぞ、あがって、あがってー?
あー、あの人ねー。久しぶりのお客様だからって、お家のお掃除を張り切っちゃったみたいなの。大掃除だーっていって。ふふ、子供みたいでしょう? 興味のない振りをしていても、自分が一番楽しみにしているのよ。
今はまだ部屋で休んでいるわ。お昼前に起こしてくれーって言っててね。でも、ヨミちゃんが来たっていえば飛び起きてくるわよ、きっと」
クスクスと、楽しそうに笑いながら廊下を先導する母の姿。
明るくて、楽しくて。涙が出そうになるくらい、幸せそうな姿だった。
「まあ。いいえ、お休みになられているのでしたら、起こしてしまうのは忍びないですわ」
「いいの、いいの!今回のこともあの人から言い出したんでしょう?
それに、可愛らしいお嬢さんが来てくれるだけでとっても有難いんだから。
ヨミちゃんこそ大丈夫なの?この時期は忙しいんでしょう?」
心配そうにこちらを見つめる瞳は優しい色をしていて。
「ふふ、大丈夫ですわ。今年は喪中ですから、ご心配には及びませんの。
それと、つまらないものですけれど……」
話題を変えるようにして紙袋を持ち上げる。イバラシティで有名な和菓子屋の店名が入っており、それを見た母が瞳を輝かせて微笑んだ。
「あらあら!気を遣わせちゃったわね。ありがとう、ヨミちゃん。
あ、荷物はその辺りに置いといて、自分の家みたいに寛いでいてね?」
紙袋を手に取って、そのまま台所に向かおうとする背に、夜道は声を掛ける。
「……あ、僕もお手伝い致しますわ。何か出来ることはありますか?」
「えぇ~、お客様だから良いのに~。……でも、嬉しいわ。ありがとう。
それじゃ、せっかくだからお昼ご飯の準備もあるし、手伝って貰っちゃおうかなっ?」
夜道は笑みを浮かべて頷くと、手を洗ったりしてから台所で待つ母の元へ向かっていった。
二人で他愛のないおしゃべりをしながら、母の手料理を教わりつつ一品一品料理を完成させて。
気が付くとあっという間にお昼になっていた。
二階から父が降りてきたときも、夜道はきちんとヨミお嬢様のままで居られた。
それが、母に会う条件のひとつだったからだ。
「ヨミちゃん。よく来たね。……大丈夫かい? あまり、顔色が良くないみたいだけど」
心配して声を掛けてくる姿に、笑って答える。
「大丈夫ですわ。これくらいでしたら、全然……。
おじ様こそ、大丈夫ですの? 聞きましたわよ? 大掃除を張り切りすぎたって」
「あはは、僕ももう歳かな、なんて。慣れないことはするものじゃないね」
「ふふ、よくお言いになりますわ。お二人ともまだまだお若く見えますのに」
父も母も40近い年齢だが、20代に思えるほどに若々しい。
そんな話をしていると母が声を掛けてくる。
「ほら、二人とも。立ち話なんかしてないで早く席に着いて。
今日はヨミちゃんがお料理を手伝ってくれたのよ」
「へぇ。それは楽しみだな。
今日のメニューはなんだい?」
「ふふ、えっと──」
「──あの子が生きていたら、こんな感じだったのかしら」
ぼそりと零れ出た母の言葉。
夜道は自然な動作で、出来る限りの悲しい笑みを浮かべて、
「……いいえ、おば様。あの子が──慕が生きていたら、きっともっと楽しかったですわ」
今は亡き、偽りの幼馴染の話を切り出した。
「……そうかしら。ううん、きっとそうね。
ねぇ、ヨミちゃん。
娘の話をまた聞かせて?
あの子は、学校ではどんな様子で、どんな話をして……どんな風に笑っていたかしら」
……そうして食事の席での話が始まる。
母は笑って、喜んで。父は穏やかな笑顔でその様子を見守ってくれていた。
そして、夜道は──
-----Hazama Side-----
「グゥゥゥウウウウ……」
獣のような唸り声が、木の隙間を通って漏れ出ている。
蹲るようにして倒れているのは一本の樹で出来た歪な彫像。
「ウォォォオオアアアアアア!!!」
叫ぼうとも暴れようとも、樹にはあるはずのない《心》が、軋みをあげて焼いてくる。
燃え上がるのは黒い黒い、闇夜のような漆黒の炎のような情動で。
ただの樹にはそれがどういった感情なのか判別付けることなど出来はしないが、ただ一つの事実だけは理解できていた。
これが、この感情こそがヒトの持つ恐ろしさなのだと。
存在が軋むほどに、理解をしていた。



ENo.42 はふり とのやりとり

ENo.107 メリル/ベル/稔 とのやりとり

ENo.138 スバル とのやりとり

ENo.183 黒い兵士 とのやりとり

ENo.301 オニキス とのやりとり

ENo.555 持明院 寂怜 とのやりとり

ENo.985 瑠璃子 とのやりとり

以下の相手に送信しました














幻術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
蹲る肉塊(251) により ItemNo.3 不思議な装飾 に ItemNo.1 不思議な武器 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
???(1473) により ItemNo.3 駄物 から射程3の武器『強迫観念』を作製してもらいました!
⇒ 強迫観念/武器:強さ35/[効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程3】/特殊アイテム
雫玖(210) とカードを交換しました!
《天よりの焔》 (イグニス)

ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ライトニング を習得!
アトラクト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



蹲る肉塊(251) は 何かの殻 を入手!
だれかのおうさま(366) は 何かの殻 を入手!
嬉野聖(399) は 何かの殻 を入手!
持明院 寂怜(555) は 何かの殻 を入手!
だれかのおうさま(366) は 甲殻 を入手!
だれかのおうさま(366) は ボロ布 を入手!
蹲る肉塊(251) は 不思議な石 を入手!
持明院 寂怜(555) は ボロ布 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
だれかのおうさま(366) のもとに オオザリガニ が微笑を浮かべて近づいてきます。
だれかのおうさま(366) のもとに 歩行石壁 が恥ずかしそうに近づいてきます。



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 蹲る肉塊(251) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- だれかのおうさま(366) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 持明院 寂怜(555) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



ブランブル女学院でクリスマスミサが終わると冬休み期間に突入する。
二週間足らずの短い期間ではあるが、家族と一緒に年末年始を過ごすとても大切な時期である。
大多数の生徒がそうであるように、降雪夜道もまた実家へと帰ってきていた。
「お父様は……お許しくださったのよね……この、時期なのに」
いくつもの感情が入り混じった表情で、手元の手紙を眺めている。
それが届いたのは数日前のこと。
書いていたのは聖が知り合った友達の事と、ここ数か月の成果の事。それと……帰省の許可について。
もっとも、それについてはいくつもの条件が課されていた。
そのどれもが夜道には納得できるもので、
そして、一年経とうとも未だ変わらない、冷たい現実を突き付けてくるものだった。
街はまだクリスマスムードが抜けきらないようだ。
イバラシティを抜けて隣の町へ。そしてそのまた隣へ。
それほど長い距離ではないものの、夜道にとっては遠く遠く離れた距離に感じていた。
今まで何度も引っ越しをして、新しい住居へと移り渡ってきていたが、今の一人の環境にはいつまで経っても慣れることはなく。
……彼女が共に暮らす誰かを思うと、その気持ちもまた一段と強くなるようだった。
電車のアナウンスが停車駅を告げる。
1年前から変わらない最寄り駅。
夜道に馴染みのない最寄り駅。
気持ちに躊躇する所がないわけではない。
けれど、それ以上に、会いたい気持ちの方がそれの何倍も、何十倍も、強かった。
例え、どんな条件が不随していたとしても……家族に会えるのならば、何を対価としても惜しくはない。
降雪夜道はそういう少女なのだから。
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
「お土産は……これで良かったかしら。お母様は和菓子が好きだから……。
お父様は甘いの苦手なのよね。ふふっ、甘いお菓子なのに苦そうなお顔をして、それでも口にしてくださるのよね。
……懐かしい、ですわ。本当に……。もう、あれから一年、ですのね」
坂道を下りながら思い出を思い返していく。お父様が居て、お母様が居て。当たり前の日々を過ごす自身の姿。
けれど、今は一人別の街に居て、初めての学校で違う自分を演じている。
それが苦であると感じたことはないけれど、決して寂しいと感じない訳ではなかった。
色褪せない思い出。切なく胸を締め付ける思い出。
優しい笑顔。悲しい笑顔。
夜道の大好きだったかつての日々。夜道ではいられないかつての日々。
……到着した家の表札には確かに降雪の文字。
昼間なので玄関の扉は開いているだろう。
夜道は、静かに門の前にあるチャイムを鳴らした。
ビー。
無機質な機械音。家の中で微かな物音。
パタパタとスリッパの音が鳴って、そして──
「はい。お待たせー。まぁ、ヨミちゃん!大きくなったわね!さあ、あがって、あがって!今ちょうどクッキーが焼きあがった所なの!」
……ああ。
扉を開けて出迎えてくれたのは、降雪夜道の母の姿で。
「ご無沙汰しております。桔梗おば様。まぁ、クッキーですの? うふふ、とっても楽しみですわ。
それでは、お邪魔致しますわね。……おじ様はどちらに?」
お淑やかに一礼をして微笑んで。家の中へと招き入れられる。父の姿が見えないことを不思議に思って尋ねてみた。父と会うのも久しぶりになる。少しソワソワした気持ちになってしまうのも仕方ないだろう。
「どうぞ、あがって、あがってー?
あー、あの人ねー。久しぶりのお客様だからって、お家のお掃除を張り切っちゃったみたいなの。大掃除だーっていって。ふふ、子供みたいでしょう? 興味のない振りをしていても、自分が一番楽しみにしているのよ。
今はまだ部屋で休んでいるわ。お昼前に起こしてくれーって言っててね。でも、ヨミちゃんが来たっていえば飛び起きてくるわよ、きっと」
クスクスと、楽しそうに笑いながら廊下を先導する母の姿。
明るくて、楽しくて。涙が出そうになるくらい、幸せそうな姿だった。
「まあ。いいえ、お休みになられているのでしたら、起こしてしまうのは忍びないですわ」
「いいの、いいの!今回のこともあの人から言い出したんでしょう?
それに、可愛らしいお嬢さんが来てくれるだけでとっても有難いんだから。
ヨミちゃんこそ大丈夫なの?この時期は忙しいんでしょう?」
心配そうにこちらを見つめる瞳は優しい色をしていて。
「ふふ、大丈夫ですわ。今年は喪中ですから、ご心配には及びませんの。
それと、つまらないものですけれど……」
話題を変えるようにして紙袋を持ち上げる。イバラシティで有名な和菓子屋の店名が入っており、それを見た母が瞳を輝かせて微笑んだ。
「あらあら!気を遣わせちゃったわね。ありがとう、ヨミちゃん。
あ、荷物はその辺りに置いといて、自分の家みたいに寛いでいてね?」
紙袋を手に取って、そのまま台所に向かおうとする背に、夜道は声を掛ける。
「……あ、僕もお手伝い致しますわ。何か出来ることはありますか?」
「えぇ~、お客様だから良いのに~。……でも、嬉しいわ。ありがとう。
それじゃ、せっかくだからお昼ご飯の準備もあるし、手伝って貰っちゃおうかなっ?」
夜道は笑みを浮かべて頷くと、手を洗ったりしてから台所で待つ母の元へ向かっていった。
二人で他愛のないおしゃべりをしながら、母の手料理を教わりつつ一品一品料理を完成させて。
気が付くとあっという間にお昼になっていた。
二階から父が降りてきたときも、夜道はきちんとヨミお嬢様のままで居られた。
それが、母に会う条件のひとつだったからだ。
「ヨミちゃん。よく来たね。……大丈夫かい? あまり、顔色が良くないみたいだけど」
心配して声を掛けてくる姿に、笑って答える。
「大丈夫ですわ。これくらいでしたら、全然……。
おじ様こそ、大丈夫ですの? 聞きましたわよ? 大掃除を張り切りすぎたって」
「あはは、僕ももう歳かな、なんて。慣れないことはするものじゃないね」
「ふふ、よくお言いになりますわ。お二人ともまだまだお若く見えますのに」
父も母も40近い年齢だが、20代に思えるほどに若々しい。
そんな話をしていると母が声を掛けてくる。
「ほら、二人とも。立ち話なんかしてないで早く席に着いて。
今日はヨミちゃんがお料理を手伝ってくれたのよ」
「へぇ。それは楽しみだな。
今日のメニューはなんだい?」
「ふふ、えっと──」
「──あの子が生きていたら、こんな感じだったのかしら」
ぼそりと零れ出た母の言葉。
夜道は自然な動作で、出来る限りの悲しい笑みを浮かべて、
「……いいえ、おば様。あの子が──慕が生きていたら、きっともっと楽しかったですわ」
今は亡き、偽りの幼馴染の話を切り出した。
「……そうかしら。ううん、きっとそうね。
ねぇ、ヨミちゃん。
娘の話をまた聞かせて?
あの子は、学校ではどんな様子で、どんな話をして……どんな風に笑っていたかしら」
……そうして食事の席での話が始まる。
母は笑って、喜んで。父は穏やかな笑顔でその様子を見守ってくれていた。
そして、夜道は──
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
-----Hazama Side-----
「グゥゥゥウウウウ……」
獣のような唸り声が、木の隙間を通って漏れ出ている。
蹲るようにして倒れているのは一本の樹で出来た歪な彫像。
「ウォォォオオアアアアアア!!!」
叫ぼうとも暴れようとも、樹にはあるはずのない《心》が、軋みをあげて焼いてくる。
燃え上がるのは黒い黒い、闇夜のような漆黒の炎のような情動で。
ただの樹にはそれがどういった感情なのか判別付けることなど出来はしないが、ただ一つの事実だけは理解できていた。
これが、この感情こそがヒトの持つ恐ろしさなのだと。
存在が軋むほどに、理解をしていた。



ENo.42 はふり とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.107 メリル/ベル/稔 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.138 スバル とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.183 黒い兵士 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.301 オニキス とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.555 持明院 寂怜 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.985 瑠璃子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



| 蹲る肉塊 「ゴホン…ィギ、協力、か…いカニも人間らシイ。 だが、ダからこそそノ提案に乗ロウ。 お前達ガ何を望み侵略するか知らンが、俺ノ骸ヲ好キに使エ。 俺も此処で大暴レしなければならん理由ガある。」 |
 |
潜竜 「……!?」 |
 |
潜竜 「……まぁいいや。傭兵部隊黒昼夢所属、潜竜だ。 人手が要るんだろ?報酬次第じゃ多少の無茶くらいしてやらんでもねぇ。」 |
 |
病葉 「ご安心ください、安心安全アンジニティです。」 |
 |
嬉野聖 「……あぁ? なに、お前たち。その見てくれで本当に協力する気なの? 協力して欲しいのならまずは力を示して見せてよ。 ほら。丁度良いのが目の前に居るだろう?」 |
 |
嬉野聖 「まあ!か弱い女の子に戦わせる気ですの? そういうのは男の子の役目ですわよ!さあ、GO、GO♪ 金が欲しいのなら僕がいくらでも支払って差し上げますわっ!」 |
 |
持明院 寂怜 「さて……即席の寄り合い所帯だけれど、上手くいくといいね。 私は持明院。見ての通りただの人だが…… 君たちと同じ、歴としたアンジニティさ。どうか力を貸しておくれ?」 |



(*‘∀‘)僕たちイバラシティを守り隊(*‘∀‘)
|
 |
ハザマに生きるもの
|



クロマティックステラ
|
 |
(*‘∀‘)僕たちイバラシティを守り隊(*‘∀‘)
|



幻術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
蹲る肉塊(251) により ItemNo.3 不思議な装飾 に ItemNo.1 不思議な武器 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
| 蹲る肉塊 「縺帙a縺ヲ蜷帙↓濶ッ縺?エ?譚舌↓縺ェ縺」縺ヲ縺?∪縺吶h縺?↓」 |
???(1473) により ItemNo.3 駄物 から射程3の武器『強迫観念』を作製してもらいました!
⇒ 強迫観念/武器:強さ35/[効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程3】/特殊アイテム
 |
??? 「たい……か……(聞き取りづらい枯れた声ながら男は確かに約定を果たした)」 |
雫玖(210) とカードを交換しました!
《天よりの焔》 (イグニス)

ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ライトニング を習得!
アトラクト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



蹲る肉塊(251) は 何かの殻 を入手!
だれかのおうさま(366) は 何かの殻 を入手!
嬉野聖(399) は 何かの殻 を入手!
持明院 寂怜(555) は 何かの殻 を入手!
だれかのおうさま(366) は 甲殻 を入手!
だれかのおうさま(366) は ボロ布 を入手!
蹲る肉塊(251) は 不思議な石 を入手!
持明院 寂怜(555) は ボロ布 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
だれかのおうさま(366) のもとに オオザリガニ が微笑を浮かべて近づいてきます。
だれかのおうさま(366) のもとに 歩行石壁 が恥ずかしそうに近づいてきます。



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 蹲る肉塊(251) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- だれかのおうさま(366) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 持明院 寂怜(555) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――



(*‘∀‘)僕たちイバラシティを守り隊(*‘∀‘)
|
 |
ハザマに生きるもの
|




小学生と保護者一同(異世界転生済)
|
 |
(*‘∀‘)僕たちイバラシティを守り隊(*‘∀‘)
|


ENo.399
嬉野 聖



PN:嬉野 聖(うれしの ひじり)
書評サイト『ユグドバイブル』の管理人
書評サイト『ユグドバイブル』
中高生の読書家にひっそりと知られる書評サイト。
細かくカテゴリ毎に分けられており、気に入った本の類似書籍を検索するのに便利な機能が多数盛り込まれている。
現役女子校生管理人としてネットでインタビューなども受けており、知名度は高くないがインターネットをよく見る読書好きであれば管理人『嬉野 聖』の名前を知っているかもしれない。
本名:降雪 夜道(コウセツ ヨミ)
ブランブル女学院高等部1-2、図書委員、文芸部所属
女性、15歳、167cm、47kg
外面はですます口調のお淑やかなお嬢様だが、内面はとても明るくツッコミ気質
SNS等ではハイテンションな関西弁で捲し立てるため、なかなか同一人物と信じてもらえない
笑いの沸点が低く、何気ないことでツボに刺さり、本で口元を隠しながら笑いをこらえたりする
静かに本を読んでいれば知的で深窓の令嬢然とした装いのため、
彼女を知る友人達からは残念文学少女と言われている。
関西弁のクラスメイトがいないため標準語を使っているが、慣れているのは関西弁。うっかり地が出ることも
中学までは別の街に居たため、イバラシティに古い知り合いは居ないようだ
【第一回更新後の情報】
本人が言う異能[本の虫]は、読書することで身体機能を強化するもの
知り合いには気軽にその事を伝えるだろう
ちょこっと力が強くなる程度で、リンゴを握りつぶすことはできない。らしい
≪一部の学校関係者等に伝わっている情報≫
降雪夜道は身体機能が常人の半分以下
それを補うために異能が必要で、歩きながらの読書も黙認されている
【第二回更新後の情報】
夜道は両親と離れて暮らしている。
母桔梗は夜道を死んだ娘の親友だと思い込んでいるようだ。
整合性を保つ為に大量の薬を服用している。
■ハザマ体
降雪夜道を形作っている樹木。全体的に薄い緑だが、髪や一部皮膚などが焦げ茶色に枯れている。
肌はヒトのようだが色が緑っぽく、よく見れば苔むした樹皮だとわかるだろう。
顔は笑みを形作っているが……中身は腐っており、異臭がする。
服はブランブル女学院の物をどこかから調達して着込んでいる。
裸足で、眼鏡は樹で作っておりレンズがなく歪。
□雨野 恋人(あまの こいと)
身長154、体重51、年齢24、女性
相良伊橋高校の情報処理教諭
透明な雨が常に頭上から降り注いでおり、いつも髪や服が濡れている(建物の中ではしっとりと濡れる程度)
おっとりとした性格で、怒ることはあまりない
https://00m.in/BJ8wH
** プロフ及びアイコンは全て有償依頼で描いてもらったものになります。素敵なイラストをありがとうございますっ **
書評サイト『ユグドバイブル』の管理人
書評サイト『ユグドバイブル』
中高生の読書家にひっそりと知られる書評サイト。
細かくカテゴリ毎に分けられており、気に入った本の類似書籍を検索するのに便利な機能が多数盛り込まれている。
現役女子校生管理人としてネットでインタビューなども受けており、知名度は高くないがインターネットをよく見る読書好きであれば管理人『嬉野 聖』の名前を知っているかもしれない。
本名:降雪 夜道(コウセツ ヨミ)
ブランブル女学院高等部1-2、図書委員、文芸部所属
女性、15歳、167cm、47kg
外面はですます口調のお淑やかなお嬢様だが、内面はとても明るくツッコミ気質
SNS等ではハイテンションな関西弁で捲し立てるため、なかなか同一人物と信じてもらえない
笑いの沸点が低く、何気ないことでツボに刺さり、本で口元を隠しながら笑いをこらえたりする
静かに本を読んでいれば知的で深窓の令嬢然とした装いのため、
彼女を知る友人達からは残念文学少女と言われている。
関西弁のクラスメイトがいないため標準語を使っているが、慣れているのは関西弁。うっかり地が出ることも
中学までは別の街に居たため、イバラシティに古い知り合いは居ないようだ
【第一回更新後の情報】
本人が言う異能[本の虫]は、読書することで身体機能を強化するもの
知り合いには気軽にその事を伝えるだろう
ちょこっと力が強くなる程度で、リンゴを握りつぶすことはできない。らしい
≪一部の学校関係者等に伝わっている情報≫
降雪夜道は身体機能が常人の半分以下
それを補うために異能が必要で、歩きながらの読書も黙認されている
【第二回更新後の情報】
夜道は両親と離れて暮らしている。
母桔梗は夜道を死んだ娘の親友だと思い込んでいるようだ。
整合性を保つ為に大量の薬を服用している。
■ハザマ体
降雪夜道を形作っている樹木。全体的に薄い緑だが、髪や一部皮膚などが焦げ茶色に枯れている。
肌はヒトのようだが色が緑っぽく、よく見れば苔むした樹皮だとわかるだろう。
顔は笑みを形作っているが……中身は腐っており、異臭がする。
服はブランブル女学院の物をどこかから調達して着込んでいる。
裸足で、眼鏡は樹で作っておりレンズがなく歪。
□雨野 恋人(あまの こいと)
身長154、体重51、年齢24、女性
相良伊橋高校の情報処理教諭
透明な雨が常に頭上から降り注いでおり、いつも髪や服が濡れている(建物の中ではしっとりと濡れる程度)
おっとりとした性格で、怒ることはあまりない
https://00m.in/BJ8wH
** プロフ及びアイコンは全て有償依頼で描いてもらったものになります。素敵なイラストをありがとうございますっ **
21 / 30
56 PS
チナミ区
I-10
I-10









| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 何かの殻 | 素材 | 15 | [武器]凍結10(LV20)[防具]反盲10(LV25)[装飾]防御15(LV25) | |||
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 強迫観念 | 武器 | 35 | - | - | - | 【射程3】 |
| 4 | 錆びついた牙飾り | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 苔むした樹皮 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 5 | 夢幻/精神/光 |
| 響鳴 | 20 | 歌唱/音楽/振動 |
| 装飾 | 25 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| アトラクト | 5 | 0 | 50 | 自:HATE・連続増 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| エファヴェセント | 5 | 0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]アクアヒール |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]サモン:サーヴァント | [ 1 ]ハードブレイク |

PL / yukkki