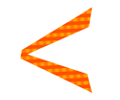<< 0:00~1:00




期末テスト期間が過ぎて、冬休みがやってきた。
今回の数学のテストは赤点を免れたから補習もない。
1年生の頃は赤点ばかりだった私もすこしは成長できてるのかなあ。
同じ寮に住んでいる人の中には帰省する人もいるけど、私は今年も寮に残る組。
キラキラと輝くイルミネーション。心弾む曲があちこちで流れるクリスマス。
久しぶりに顔を合わせてあれやこれやと語らう親戚。
家族で団らんのひとときを過ごし、新たな一年を清らかな気持ちで迎えるお正月。
サンタを信じて待つ子供たち。
お年玉をもらってはしゃぐ子供たち。
……あの日からずっと。冬休みは、毎年いつもちょっぴり憂鬱で。
愛用している紺色のスクールバッグが、どさりと足元に落ちる。
教科書、ノート、花柄の布で包まれたお弁当箱、菓子や美術作品を作る際にときどき使っているクロッキー帖、うさぎのマスコットが付いたお気に入りのシャープペンシル、ドーナツやチョコレートなどの小包装菓子……チャックが開いたままの口から、中身が地面に豪快に飛び散った。
「ひ、」
それらには微塵も興味を示さず、先刻まで今にも飛びかからんとしていた血のように赤いドロドロとした化物は一転、今度はじりじりと、獲物が逃げ道を失った事実を確信したかの如く緩慢な動きで少女に這いよっていく。
あれに触れたら即死? それともヘビに狙われたカエルのように、あのゼリー状の体で丸呑みされる? あるいは酸に似た性質をしていて、皮膚からすこしずつ溶かされる?
痛み
――――それとも。あれに触れればいつまでも終わらない現実という夢から目が覚める?
化物の動きが遅くなったのは、追い詰められた自分の感覚が狂ったからなのではないかと思うほど。
「…………ぁ」
悲鳴は声にすらならない。尻餅をついて、逃れるように退いた身体と手。その爪先に、こつん、と重量を持ったものがぶつかった。
軽い外装、ゆらりと波打つ中身。茶入りのペットボトル。その液体が――――少女の指先が触れた瞬間に、明らかに変色した。
―――触れた感触のもとを辿る。
ペットボトルが視界に入った瞬間、ぞわり、と悪寒に襲われた。
見間違いだと思いたかった。けれど、
嫌な予感。不快な感覚。きっと、この現象は。
いつもよりも、もっとずっと程度の酷いやつだと直感的にわかった。
……それが、私の異能によるものだから。
この際、なりふりかまっていられない。この窮地を脱しなければいけない―――
「ア゛ア゛ア゛ア゛ァァ………」
少女が動きを止めても化物の様子は変わらない。悲しそうに。苦しそうに。辛そうに。恨めしそうに。地を這う呻き声と共にゆっくりと近づいてくる。まるで、助けを乞うかのように。
その距離数メートル。20センチメートル。10、8、7―――…………
「――――……ッ!!」
少女はペットボトルを握ってキャップを捻ると、この空間の空のように赤黒く変色した中身を目の前に勢いよくぶちまけた。
「……っは…………はぁ、……ひぁ……」
触れれば夢から覚めるかもしれない。そんな淡い期待よりも、眼前に差し迫った悲観的観測の方が優った。反射的に体が動いてしまった。
ペットボトルの中の液体をぶち撒けてスライムが怯んだ隙に、少女は鞄を拾い上げて応戦した。幾度か思い切りぶつけたのちに、スライムは後味の悪い悲鳴を残してようやく動かなくなった。
どろりと溶けた赤黒い水溜りは染みを残して徐々に地面に吸収されていく。まるで何も存在しなかったかのように。
「………ふえぇええぇぇ………けほっ、けほ……」
戦闘前と同様、地面にぺたりとへたりこむと少女は数度咳き込んだ。目じりにはうっすらと涙が浮かんでいる。
「けほっ……」
これからどうするべきか。ここでこのまま何もせずにいるか、動くべきか―――
―――……ザ、 ピピッ ……ザザッ
迷う少女のもとに、ノイズ混じりの通信が届く。それらを聞いた後で。途方に暮れながら、少女はふらりと歩き出す。自らの拠り所を、求めるかのように。



ENo.546 不幸喰らい とのやりとり

ENo.968 緋染の白花 とのやりとり

ENo.1159 万智花 とのやりとり

以下の相手に送信しました













使役LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
イルハ(324) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『拾ったフライパン』を作製してもらいました!
⇒ 拾ったフライパン/武器:強さ35/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
スズネ(724) とカードを交換しました!
地質調査 (グランドクラッシャー)

グランドクラッシャー を研究しました!(深度0⇒1)
グランドクラッシャー を研究しました!(深度1⇒2)
グランドクラッシャー を研究しました!(深度2⇒3)
ガードフォーム を習得!
ヒールポーション を習得!
ラトゥンブロウ を習得!
ポイズン を習得!
ウィークネス を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



泥蘇光悪渡(150) は 韮 を入手!
イルハ(324) は 花びら を入手!
ユイノ(388) は 花びら を入手!
晴(428) は 美味しい草 を入手!
晴(428) は 毛 を入手!
イルハ(324) は 不思議な石 を入手!
イルハ(324) は 不思議な雫 を入手!
ユイノ(388) は 美味しい果実 を入手!



チナミ区 D-9(草原)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 泥蘇光悪渡(150) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 晴(428) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



期末テスト期間が過ぎて、冬休みがやってきた。
今回の数学のテストは赤点を免れたから補習もない。
1年生の頃は赤点ばかりだった私もすこしは成長できてるのかなあ。
同じ寮に住んでいる人の中には帰省する人もいるけど、私は今年も寮に残る組。
キラキラと輝くイルミネーション。心弾む曲があちこちで流れるクリスマス。
久しぶりに顔を合わせてあれやこれやと語らう親戚。
家族で団らんのひとときを過ごし、新たな一年を清らかな気持ちで迎えるお正月。
サンタを信じて待つ子供たち。
お年玉をもらってはしゃぐ子供たち。
……あの日からずっと。冬休みは、毎年いつもちょっぴり憂鬱で。
◆◇◆
愛用している紺色のスクールバッグが、どさりと足元に落ちる。
教科書、ノート、花柄の布で包まれたお弁当箱、菓子や美術作品を作る際にときどき使っているクロッキー帖、うさぎのマスコットが付いたお気に入りのシャープペンシル、ドーナツやチョコレートなどの小包装菓子……チャックが開いたままの口から、中身が地面に豪快に飛び散った。
「ひ、」
それらには微塵も興味を示さず、先刻まで今にも飛びかからんとしていた血のように赤いドロドロとした化物は一転、今度はじりじりと、獲物が逃げ道を失った事実を確信したかの如く緩慢な動きで少女に這いよっていく。
あれに触れたら即死? それともヘビに狙われたカエルのように、あのゼリー状の体で丸呑みされる? あるいは酸に似た性質をしていて、皮膚からすこしずつ溶かされる?
痛み
――――それとも。あれに触れればいつまでも終わらない現実という夢から目が覚める?
化物の動きが遅くなったのは、追い詰められた自分の感覚が狂ったからなのではないかと思うほど。
「…………ぁ」
悲鳴は声にすらならない。尻餅をついて、逃れるように退いた身体と手。その爪先に、こつん、と重量を持ったものがぶつかった。
軽い外装、ゆらりと波打つ中身。茶入りのペットボトル。その液体が――――少女の指先が触れた瞬間に、明らかに変色した。
―――触れた感触のもとを辿る。
ペットボトルが視界に入った瞬間、ぞわり、と悪寒に襲われた。
見間違いだと思いたかった。けれど、
嫌な予感。不快な感覚。きっと、この現象は。
いつもよりも、もっとずっと程度の酷いやつだと直感的にわかった。
……それが、私の異能によるものだから。
この際、なりふりかまっていられない。この窮地を脱しなければいけない―――
「ア゛ア゛ア゛ア゛ァァ………」
少女が動きを止めても化物の様子は変わらない。悲しそうに。苦しそうに。辛そうに。恨めしそうに。地を這う呻き声と共にゆっくりと近づいてくる。まるで、助けを乞うかのように。
その距離数メートル。20センチメートル。10、8、7―――…………
「――――……ッ!!」
少女はペットボトルを握ってキャップを捻ると、この空間の空のように赤黒く変色した中身を目の前に勢いよくぶちまけた。
◆◆◆
「……っは…………はぁ、……ひぁ……」
触れれば夢から覚めるかもしれない。そんな淡い期待よりも、眼前に差し迫った悲観的観測の方が優った。反射的に体が動いてしまった。
ペットボトルの中の液体をぶち撒けてスライムが怯んだ隙に、少女は鞄を拾い上げて応戦した。幾度か思い切りぶつけたのちに、スライムは後味の悪い悲鳴を残してようやく動かなくなった。
どろりと溶けた赤黒い水溜りは染みを残して徐々に地面に吸収されていく。まるで何も存在しなかったかのように。
「………ふえぇええぇぇ………けほっ、けほ……」
戦闘前と同様、地面にぺたりとへたりこむと少女は数度咳き込んだ。目じりにはうっすらと涙が浮かんでいる。
「けほっ……」
これからどうするべきか。ここでこのまま何もせずにいるか、動くべきか―――
―――……ザ、 ピピッ ……ザザッ
迷う少女のもとに、ノイズ混じりの通信が届く。それらを聞いた後で。途方に暮れながら、少女はふらりと歩き出す。自らの拠り所を、求めるかのように。
The Evening2.



ENo.546 不幸喰らい とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.968 緋染の白花 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
| |||
ENo.1159 万智花 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| 泥蘇光悪渡 「伊藤君ッ!!!岬ッ!!無事で良かった!!一緒に生きて…イバラシティ帰ッぞッッッ!!!!」 |
| 泥蘇光悪渡 「え?姫園?…そっか、信じる事にするぜ。味方だッつーなら俺らに力を貸してくれッ!!」 |
| 泥蘇光悪渡 「 大丈夫。俺はヒーロー泥蘇光悪渡・悪漢(ディスコード・バッドガイ)だぜ!!!ヤレるッつーのッッ!!!」 |
 |
イーサン 「···皆無事で良かった。異形の身ではあるが、今の余はお前達の側に在る。出来うる限りの力を貸そう。」 |
 |
イーサン 「···カガラ、無理はするなよ。」 |
 |
イーサン 「晴、結乃。この姿ですまないが、よろしく頼むぞ。」 |
 |
結乃 「岬は元気だよ~。さっきの赤いどろどろにはびっくりしたけど……。」 |
 |
結乃 「アゲハくんと晴くん~、それとー……ええっと~……」 |
 |
結乃 「……イーサンさん~! みんなとこうしてお顔を合わせることができて、ほっとひと安心~。」 |
 |
結乃 「でもでも、危なくなったら逃げよー。逃げるは恥だが役に立つ! だよ~。」 |
 |
晴 「みんなが無事でよかった。俺も同じ気持ちだよ。」 |
 |
晴 「なんとかやってけるだろうし。俺も頑張る。直接戦えはしないけど・・・援護するよ。」 |
 |
晴 「それで最初のお願いだ。あそこにいる奴を・・・十神を倒してくれ!」 |





神も仏もあるもんか
|
 |
アンアンアンヂニチィ
|



使役LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
百薬LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
イルハ(324) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『拾ったフライパン』を作製してもらいました!
⇒ 拾ったフライパン/武器:強さ35/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
イーサン 「よし!!これなら良かろう!?」 |
スズネ(724) とカードを交換しました!
地質調査 (グランドクラッシャー)

グランドクラッシャー を研究しました!(深度0⇒1)
グランドクラッシャー を研究しました!(深度1⇒2)
グランドクラッシャー を研究しました!(深度2⇒3)
ガードフォーム を習得!
ヒールポーション を習得!
ラトゥンブロウ を習得!
ポイズン を習得!
ウィークネス を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



泥蘇光悪渡(150) は 韮 を入手!
イルハ(324) は 花びら を入手!
ユイノ(388) は 花びら を入手!
晴(428) は 美味しい草 を入手!
晴(428) は 毛 を入手!
イルハ(324) は 不思議な石 を入手!
イルハ(324) は 不思議な雫 を入手!
ユイノ(388) は 美味しい果実 を入手!



チナミ区 D-9(草原)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 泥蘇光悪渡(150) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 晴(428) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――







TRICK SHOT
|
 |
神も仏もあるもんか
|


ENo.388
岬 結乃



岬 結乃<Misaki Yuino>
Sex:Female Height:162cm Weight:54kg
相良伊橋高校の2年生。文系クラス。
イバラシティ外の出身で、現在は学生寮で一人暮らしをしている。
言語系が得意な反面、理数系は苦手。運動音痴。
なお、水泳の授業は1年の頃から一貫して見学・教室自習組。
部活は美術部所属で、絵画よりも造形に力を入れている。
昼休みは校舎内よりも、外のベンチや屋上などで過ごしていることが多い。
散歩やショッピングが趣味で、放課後にふらふら散策している姿を見かけることもあるだろう。
特に焼き菓子が好物で、カバンの中には常に菓子類が入っている。
誰にでもふわ~っと近寄っていって手持ちの菓子を差し出す、そんな性格。
自分の異能に関して積極的に話すことはなく、
尋ねられても、多くの場合は「秘密」「内緒」と答えている。
それでも粘り強く聞いてきたほんの一部の相手には、「猫と話すことのできる異能」と答えているようだ。
寮の自室→http://lisge.com/ib/act_place.php?p=552
連絡先→http://lisge.com/ib/talk.php?p=810
◇◆◇◆◇
・既知設定と交流歓迎。遅レス、置きレス多めです。
・テストプレイでの出来事は引き継いでいたりいなかったり。
・何かありましたらお気軽にCross+Roseからご連絡下さい。
*テストプレイ時の、トークの一部のログはこちらに(※名前で整理していません)→https://onedrive.live.com/?authkey=%21APkjo5tAwn%5F%5FsOA&id=17ED7F25C157639F%21765&cid=17ED7F25C157639F
プロフィール画像は二種。
バンダナとエプロン姿の素敵なイラストは、Eno.103のPL様に描いていただきました!
Sex:Female Height:162cm Weight:54kg
相良伊橋高校の2年生。文系クラス。
イバラシティ外の出身で、現在は学生寮で一人暮らしをしている。
言語系が得意な反面、理数系は苦手。運動音痴。
なお、水泳の授業は1年の頃から一貫して見学・教室自習組。
部活は美術部所属で、絵画よりも造形に力を入れている。
昼休みは校舎内よりも、外のベンチや屋上などで過ごしていることが多い。
散歩やショッピングが趣味で、放課後にふらふら散策している姿を見かけることもあるだろう。
特に焼き菓子が好物で、カバンの中には常に菓子類が入っている。
誰にでもふわ~っと近寄っていって手持ちの菓子を差し出す、そんな性格。
自分の異能に関して積極的に話すことはなく、
尋ねられても、多くの場合は「秘密」「内緒」と答えている。
それでも粘り強く聞いてきたほんの一部の相手には、「猫と話すことのできる異能」と答えているようだ。
寮の自室→http://lisge.com/ib/act_place.php?p=552
連絡先→http://lisge.com/ib/talk.php?p=810
◇◆◇◆◇
・既知設定と交流歓迎。遅レス、置きレス多めです。
・テストプレイでの出来事は引き継いでいたりいなかったり。
・何かありましたらお気軽にCross+Roseからご連絡下さい。
*テストプレイ時の、トークの一部のログはこちらに(※名前で整理していません)→https://onedrive.live.com/?authkey=%21APkjo5tAwn%5F%5FsOA&id=17ED7F25C157639F%21765&cid=17ED7F25C157639F
プロフィール画像は二種。
バンダナとエプロン姿の素敵なイラストは、Eno.103のPL様に描いていただきました!
21 / 30
42 PS
チナミ区
D-13
D-13






































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 拾ったフライパン | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 相良伊橋高校の制服 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | キャラメルシュークリーム | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 9 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 15 | 呪詛/邪気/闇 |
| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 25 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| かばんスイング (ブレイク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 古語辞典アタック (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒールグミ (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 謎の液体入りスプレー (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| ペレル | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]コントラスト | [ 1 ]ブレス | [ 1 ]パワフルヒール |
| [ 3 ]グランドクラッシャー |

PL / 姫桜