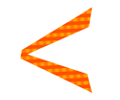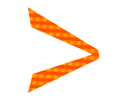<< 0:00~1:00





――未来の俺に向けて、俺というものを定義しておこうと思う。
いつか俺が何かの間違いを犯したときに、いつか完全に化物に成り下がる前に、俺というものを定義し、記載し、記録しておくことが必要だと感じた。
俺は正気を容易に手放し、人を殺める怪物である。その認識を抱えたまま生きていくのは、少なくとも今の俺には難しいものである。そう判断する。文章で記されているから、今これを書いている俺は、大変冷静であるように見えているだろう。答えはそうではない。己が人を殺め、それどころかそれを喰らっていく怪物であることを、強く畏怖している。可能ならば向き合うことを放棄したいが、そうもいかないだろう。俺はいつか、致命的な過ちを犯すに違いない。いつかの俺のために、俺の傍にいるひとのために、俺はこれらのことを記しておく義務がある。故にこうして筆を取り、この世界で最も劣化に強いと思われるインクを使用して書き記している。実質己の肉体に自分自身で彫り物をしているような気分だが、幸いなことに“紙”にはなんの感覚もない。
そもそも、俺が『ほとんど生きている人間に近いもの』を形作れているということが、まず奇跡なのだ。そのことを改めて周知しておく必要はあるだろう。俺は、俺がこのようにあることを当たり前のように思ってはならない。己が存在がまず奇跡であることを、もう二度とは成し得ない神業であることを、強く認識していなければならない。実際、奇跡、魔術、それ以上の何かで、この肉体は構成された。有機物ではあるが、生物ではない。植物繊維を抽出し、それを水中に分散させ、水の媒介により、薄く平らになるように絡み合わせて造ったもの(それによらない合成方法が主流だった世界に住んでいたが、その件については今は割愛する)。それをさらに複数枚束ねたもの。即ち『本』として定義されるもの。それが、今の俺の正体である。
俺は『本』である。本の世界の中で得た肉体は、己に本であるという制約を課した。即ち、記録物としての側面である。故に、俺は今まで体験してきたあらゆる事象を記録している。ただし、一般的な人間の記憶能力に限界があるように、例えば必要な情報を検索し使用するとき、俺は何かしらの記憶を一旦しまい込まなければならない。机の上が散らかっていれば、まともに物が置けないことと同じようなものである。故に、俺の記憶は基本的に、人間とほぼ同様の振る舞いをし、『記録』と『記憶』は別のものとして定義されている。以下にその二つの定義を記す。
『記憶』は、俺が人間として覚えていることだ。例えば昨日何を食べたか、何を誰と話したか、そのようなものが挙げられる。基本的に古く、印象の少ない『記憶』から『記録』として格納されていく。だから俺は、人間と同じように物事を覚え、忘れる。本の形をしていない俺――即ち、“人間としての咲良乃スズヒコ”である俺は、基本的にそれに違和感がないように振る舞う。だから例えば、俺が努めて忘れようと振る舞ったものや、興味のなかったものは、他のものより疾く忘れられていくだろう。
『記録』は、俺の本としての側面である。即ち、俺そのものに刻みつけられているものである。即ち、一度『記録』されたものは、よほどのことがない限り不可逆だ。本のページを破ることはできるだろうが、俺が同様にページを破るという行為を受けられるかどうか、この文章を書いている時点では一度も試行していない。故に、これを思い出すことがあったら、加筆を求める。
さて、『記憶』と『記録』を自在に入れ替えることができれば、それが最も効率的であり、理に適っているのは間違いないことは、恐らくざっと目を通しただけの人間にでも分かるだろう。だが、この能力は世界によって大きく制限を受け、また同一世界での滞在時間に影響を受けることが分かっている。つまり、ある程度その世界に馴染まなければ、そもそも『記録』にアクセスすることすらできない。この能力は単なる便利なお道具箱ではない。故に俺は危惧している。
常人は、永く生きていることに耐えられる精神構造をしていない。俺はそう思っている。そも、俺の精神面があまり強くないというのは、すでにかつての己の行動で十分すぎるほど示されている。正気の人間は職場ごと焼身自殺など図らないからだ。より適切な道があったのにも関わらず、その道を選択することができない。視野の狭くなった知性を持った生物は、もはや己しか信用できなくなるのだ。これは経験談に基づく記述である。これを読んでいるのがあなたであるのなら、何を指しているか、すぐに理解が及ぶだろう。
ここまで長々と書き連ねてきたが、要するに、俺は今現在、俺のことを『いつ爆発するか分からない爆弾である』と称するしかないのである。現時点の情報でも俺がそう思うのだから、恐らく俺という爆弾は、いつか爆発するだろう。それがどのような形であれ。恐らくは、驚くほど救いようのない形で。
故にこうして書き連ねており、可能であればこれを『覚えているうちに託しておく』ことができれば、最も最善だろう。だが、俺は恐らく『ページを破る』という行為を、自発的には行わないだろう。本にそのようなことをしてはいけない、という教育を受けてきたからだ。本は学びの象徴であり、それを破壊することは、学徒だった俺にはきっとできない。
そうではなくなっていたときは、もう俺は正気ではないということになるだろう。それが俺への、今の俺が出せる結論である。
では、俺が正気を保っていられなくなったときどうすればよいのか、問題はそこに集約するだろう。けれどもこれに対しては、対症療法を取るしかないだろう。もう、そうなってしまったら、手遅れなのだ。そうならない方がいいことは、もちろん俺とて分かっている。だからこうして、俺は『記録』をしているのだ。永遠なんて存在するはずがないし、先に記した通り、常人は永い時間への抵抗力を持たないに等しい。時間が解決するという言葉があるが、それは常識的な範囲内の時間だ。死後評価された偉人たちや、研究者たちのように、暴いてみてようやく判明する事実もあるのだ。
さて、俺が忘れてしまっているのなら、誰かに思い出させてもらうしかない。そのために、俺はこうして記している。全てを一人で片付けられるほど、人間ができているとは思っていない。全てを一人でどうにかできるのなら、そもそも連れ立っている必要はなかったのだ。それほどまでに完成された存在であったなら、当に一人でいることを選んでおり、この文章の全てが不要である。
親愛なるフェデルタ・アートルムへ。
これを読んだとき、あなたがやることは、自ずと分かるかと思う。
自分のことを自分でできないような人間で、申し訳ない。
もっと簡潔に記載せよ、という文句は、後から聞かせて欲しい。
記載するとき、どうしても真面目な文章でないと、自分がぞわぞわしてしまうのだ。
咲良乃スズヒコ 2016.9.29
追:
覚えのないページが出てきたので処分を検討したが、価値があるものであると判断する。
文章の癖・筆記の癖からして己の文字であることは間違いない。存在の共有を試みたいが、人間とは忘れる生き物である。もっと根本的なアプローチを検討する必要がある。
今これを断片としてもらい、所持させることには大きなリスクがある。紛失などがあった場合、俺は全くの対処法を持たない。幸いにしてもうしばらくこの世界には存在できそうなため、より効率的な方法を検討する。
2017.3.9

結論から言うと、俺たちは罪人だと認定され、そして否定された。
俺たちが、少なくとも俺が、正しいと信じて組み上げて来たものは、真正面から否定された。
怒り狂うしかなかった。
「――考えたことある?」
内側から燃えている。比喩でなく、この身を焦がしたるは嫉妬の炎。執念、妄執、何とも違わない怒り。“吉野暁海”という限りなく恵まれた存在を、拒否することすらできず、抗うことすら叶わず、一方的に。そう、一方的に植え付けていった。
何がワールドスワップだ。何が侵略だ。
この街の一部を改変し、辻褄を合わせ、ごく自然に、巧妙に。それがあの“吉野暁海”だというのなら、そのワールドスワップとやらはザル中のザルで、コンタミ上等、当然ラテの手袋もなしだ。実験の試行回数としてカウントすることそのものが勿体ない。
「辻褄合わせというのは」
獣が、荒れた大地の土を引っ掻く音。
「もっと、正確で、的確でないと」
見下ろす何か。あまりにも小さく思えた。
「辻褄合わせって、言わないんだよ!!」
もし、それが意図的であったのなら。もし、それがそれなりに考えられた結果だとしたら。ああ、それこそ、この身を燻ぶらせる薄暗い情念が、あまりにも激しく火を噴いてしまう。
俺はそこまで望まれていた存在ではなかったし、恵まれていた存在でもなかったし、何もかもがあてつけのようにこの身を焼くのだ。己が道にあったのは陰惨な田舎の冷たい目と、そこから逃れるための足掻きと、逃れた先ですら降り注いだ冷たい目だ。運が悪かった、と言えばそうかもしれない。時勢に振り回され、人々が異物を排除するのは、必然の流れとして歴史に存在する。運が悪かっただけだ。そう言うにしては、――そう語るためには、“理想の姿を鏡写しにしたように存在されている”。あまりにも。あまりにも、吉野暁海という存在は、無防備で、無遠慮で、――恵まれている。
「……、……。よし、いい子だ。もう少し念入りにすり潰して」
かつて、己がその身を変えて戦っていた獣は、ここでは別のものとして召喚ができるらしい。それはそれで便利だが、どうやら感覚は共有しているらしく、前足で念入りに潰しているよく分からない生き物の、肉のような、スライムのような感触も、土を削っていく爪の感触も、確かにその手の中にあった。
これは利点でもあり、欠点でもある。誰かの後ろに隠れて戦うようなことはできない。武道の心得がなくはないから、後ろに退くつもりはさらさらない。ただ、感覚を共有しているのなら、自分以上のリーチの長さと、頑丈さを活かさない手はない。
「……臭うなあ、相変わらず」
彼は喫煙者だった。
いつでもどこでも同じ銘柄を吸うことは難しかったが、煙草にも好みの味だの、何だの、そういう物はあるらしい。それらは葉の配合量や、成分に依るものだから、“似たようなもの”を常に吸っていた。だから、纏うにおいも、そう変わらなかった。
「……そら、進め。……あまりいいことになってないようにも見える」
目視。異能が強化される場所にあっては、スズヒコの視力は強化される。眼鏡が必要ないどころか、遠くまで見えすぎて困るくらいだ。例えば今のような。
見知らぬ少年と、男と、自分の探し人。その近くで、潰しきれていない赤い生き物が、今にも再形成しようとしていた。
「――走れ」
この世界がどこだろうと、何だろうと、どうだっていい。どうなっても構わない。
ただ、ずっと問いかけ続けてくる声に、選択肢の少なすぎる答えに、“どこでもない”とだけ答え続けることしかできないのだ。
獣の咆哮。それから、爪を振り下ろす音。再び念入りに潰される、ただただ憐れな生き物。己の名前を聞き止め、咲良乃スズヒコはハザマの大地に飛び降りた。



ENo.151 ガズエット とのやりとり

ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.687 音和姉弟 とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。









武術LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
響鳴LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
変化LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
メリーナ(646) により ItemNo.5 不思議な石 から魔晶『異本の栞』を作製してもらいました!
⇒ 異本の栞/魔晶:強さ17/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]充填5/特殊アイテム
メリーナ(646) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『レタスサンド』をつくりました!
潤(39) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ふわふわ卵のカツ丼』をつくりました!
獣(333) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『とろーり不思議なホットサンド』をつくりました!
葵(548) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『厚切り肉のフシギ焼き』をつくってもらいました!
⇒ 厚切り肉のフシギ焼き/料理:強さ35/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
かすみ(1311) とカードを交換しました!
ハートブレイクショット (ハードブレイク)

マナポーション を研究しました!(深度0⇒1)
マナポーション を研究しました!(深度1⇒2)
マナポーション を研究しました!(深度2⇒3)
ガードフォーム を習得!
リフレクション を習得!
カームソング を習得!
プロテクション を習得!
ミラー&ミラー を習得!
ディベスト を習得!
ガーディアン を習得!
ワイドプロテクション を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は パンの耳 を入手!
スズヒコ(244) は 美味しくない草 を入手!
グノウ(909) は 美味しくない草 を入手!
迦楼羅(931) は パンの耳 を入手!
スズヒコ(244) は 毛 を入手!
迦楼羅(931) は ねばねば を入手!
グノウ(909) は 毛 を入手!
フェデルタ(165) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 大黒猫 が軽快なステップで近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 道端ガムマン がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ヤンキー が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 迦楼羅(931) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――





























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




――未来の俺に向けて、俺というものを定義しておこうと思う。
いつか俺が何かの間違いを犯したときに、いつか完全に化物に成り下がる前に、俺というものを定義し、記載し、記録しておくことが必要だと感じた。
俺は正気を容易に手放し、人を殺める怪物である。その認識を抱えたまま生きていくのは、少なくとも今の俺には難しいものである。そう判断する。文章で記されているから、今これを書いている俺は、大変冷静であるように見えているだろう。答えはそうではない。己が人を殺め、それどころかそれを喰らっていく怪物であることを、強く畏怖している。可能ならば向き合うことを放棄したいが、そうもいかないだろう。俺はいつか、致命的な過ちを犯すに違いない。いつかの俺のために、俺の傍にいるひとのために、俺はこれらのことを記しておく義務がある。故にこうして筆を取り、この世界で最も劣化に強いと思われるインクを使用して書き記している。実質己の肉体に自分自身で彫り物をしているような気分だが、幸いなことに“紙”にはなんの感覚もない。
そもそも、俺が『ほとんど生きている人間に近いもの』を形作れているということが、まず奇跡なのだ。そのことを改めて周知しておく必要はあるだろう。俺は、俺がこのようにあることを当たり前のように思ってはならない。己が存在がまず奇跡であることを、もう二度とは成し得ない神業であることを、強く認識していなければならない。実際、奇跡、魔術、それ以上の何かで、この肉体は構成された。有機物ではあるが、生物ではない。植物繊維を抽出し、それを水中に分散させ、水の媒介により、薄く平らになるように絡み合わせて造ったもの(それによらない合成方法が主流だった世界に住んでいたが、その件については今は割愛する)。それをさらに複数枚束ねたもの。即ち『本』として定義されるもの。それが、今の俺の正体である。
俺は『本』である。本の世界の中で得た肉体は、己に本であるという制約を課した。即ち、記録物としての側面である。故に、俺は今まで体験してきたあらゆる事象を記録している。ただし、一般的な人間の記憶能力に限界があるように、例えば必要な情報を検索し使用するとき、俺は何かしらの記憶を一旦しまい込まなければならない。机の上が散らかっていれば、まともに物が置けないことと同じようなものである。故に、俺の記憶は基本的に、人間とほぼ同様の振る舞いをし、『記録』と『記憶』は別のものとして定義されている。以下にその二つの定義を記す。
『記憶』は、俺が人間として覚えていることだ。例えば昨日何を食べたか、何を誰と話したか、そのようなものが挙げられる。基本的に古く、印象の少ない『記憶』から『記録』として格納されていく。だから俺は、人間と同じように物事を覚え、忘れる。本の形をしていない俺――即ち、“人間としての咲良乃スズヒコ”である俺は、基本的にそれに違和感がないように振る舞う。だから例えば、俺が努めて忘れようと振る舞ったものや、興味のなかったものは、他のものより疾く忘れられていくだろう。
『記録』は、俺の本としての側面である。即ち、俺そのものに刻みつけられているものである。即ち、一度『記録』されたものは、よほどのことがない限り不可逆だ。本のページを破ることはできるだろうが、俺が同様にページを破るという行為を受けられるかどうか、この文章を書いている時点では一度も試行していない。故に、これを思い出すことがあったら、加筆を求める。
さて、『記憶』と『記録』を自在に入れ替えることができれば、それが最も効率的であり、理に適っているのは間違いないことは、恐らくざっと目を通しただけの人間にでも分かるだろう。だが、この能力は世界によって大きく制限を受け、また同一世界での滞在時間に影響を受けることが分かっている。つまり、ある程度その世界に馴染まなければ、そもそも『記録』にアクセスすることすらできない。この能力は単なる便利なお道具箱ではない。故に俺は危惧している。
常人は、永く生きていることに耐えられる精神構造をしていない。俺はそう思っている。そも、俺の精神面があまり強くないというのは、すでにかつての己の行動で十分すぎるほど示されている。正気の人間は職場ごと焼身自殺など図らないからだ。より適切な道があったのにも関わらず、その道を選択することができない。視野の狭くなった知性を持った生物は、もはや己しか信用できなくなるのだ。これは経験談に基づく記述である。これを読んでいるのがあなたであるのなら、何を指しているか、すぐに理解が及ぶだろう。
ここまで長々と書き連ねてきたが、要するに、俺は今現在、俺のことを『いつ爆発するか分からない爆弾である』と称するしかないのである。現時点の情報でも俺がそう思うのだから、恐らく俺という爆弾は、いつか爆発するだろう。それがどのような形であれ。恐らくは、驚くほど救いようのない形で。
故にこうして書き連ねており、可能であればこれを『覚えているうちに託しておく』ことができれば、最も最善だろう。だが、俺は恐らく『ページを破る』という行為を、自発的には行わないだろう。本にそのようなことをしてはいけない、という教育を受けてきたからだ。本は学びの象徴であり、それを破壊することは、学徒だった俺にはきっとできない。
そうではなくなっていたときは、もう俺は正気ではないということになるだろう。それが俺への、今の俺が出せる結論である。
では、俺が正気を保っていられなくなったときどうすればよいのか、問題はそこに集約するだろう。けれどもこれに対しては、対症療法を取るしかないだろう。もう、そうなってしまったら、手遅れなのだ。そうならない方がいいことは、もちろん俺とて分かっている。だからこうして、俺は『記録』をしているのだ。永遠なんて存在するはずがないし、先に記した通り、常人は永い時間への抵抗力を持たないに等しい。時間が解決するという言葉があるが、それは常識的な範囲内の時間だ。死後評価された偉人たちや、研究者たちのように、暴いてみてようやく判明する事実もあるのだ。
さて、俺が忘れてしまっているのなら、誰かに思い出させてもらうしかない。そのために、俺はこうして記している。全てを一人で片付けられるほど、人間ができているとは思っていない。全てを一人でどうにかできるのなら、そもそも連れ立っている必要はなかったのだ。それほどまでに完成された存在であったなら、当に一人でいることを選んでおり、この文章の全てが不要である。
親愛なるフェデルタ・アートルムへ。
これを読んだとき、あなたがやることは、自ずと分かるかと思う。
自分のことを自分でできないような人間で、申し訳ない。
もっと簡潔に記載せよ、という文句は、後から聞かせて欲しい。
記載するとき、どうしても真面目な文章でないと、自分がぞわぞわしてしまうのだ。
咲良乃スズヒコ 2016.9.29
追:
覚えのないページが出てきたので処分を検討したが、価値があるものであると判断する。
文章の癖・筆記の癖からして己の文字であることは間違いない。存在の共有を試みたいが、人間とは忘れる生き物である。もっと根本的なアプローチを検討する必要がある。
今これを断片としてもらい、所持させることには大きなリスクがある。紛失などがあった場合、俺は全くの対処法を持たない。幸いにしてもうしばらくこの世界には存在できそうなため、より効率的な方法を検討する。
2017.3.9

結論から言うと、俺たちは罪人だと認定され、そして否定された。
俺たちが、少なくとも俺が、正しいと信じて組み上げて来たものは、真正面から否定された。
怒り狂うしかなかった。
「――考えたことある?」
内側から燃えている。比喩でなく、この身を焦がしたるは嫉妬の炎。執念、妄執、何とも違わない怒り。“吉野暁海”という限りなく恵まれた存在を、拒否することすらできず、抗うことすら叶わず、一方的に。そう、一方的に植え付けていった。
何がワールドスワップだ。何が侵略だ。
この街の一部を改変し、辻褄を合わせ、ごく自然に、巧妙に。それがあの“吉野暁海”だというのなら、そのワールドスワップとやらはザル中のザルで、コンタミ上等、当然ラテの手袋もなしだ。実験の試行回数としてカウントすることそのものが勿体ない。
「辻褄合わせというのは」
獣が、荒れた大地の土を引っ掻く音。
「もっと、正確で、的確でないと」
見下ろす何か。あまりにも小さく思えた。
「辻褄合わせって、言わないんだよ!!」
もし、それが意図的であったのなら。もし、それがそれなりに考えられた結果だとしたら。ああ、それこそ、この身を燻ぶらせる薄暗い情念が、あまりにも激しく火を噴いてしまう。
俺はそこまで望まれていた存在ではなかったし、恵まれていた存在でもなかったし、何もかもがあてつけのようにこの身を焼くのだ。己が道にあったのは陰惨な田舎の冷たい目と、そこから逃れるための足掻きと、逃れた先ですら降り注いだ冷たい目だ。運が悪かった、と言えばそうかもしれない。時勢に振り回され、人々が異物を排除するのは、必然の流れとして歴史に存在する。運が悪かっただけだ。そう言うにしては、――そう語るためには、“理想の姿を鏡写しにしたように存在されている”。あまりにも。あまりにも、吉野暁海という存在は、無防備で、無遠慮で、――恵まれている。
「……、……。よし、いい子だ。もう少し念入りにすり潰して」
かつて、己がその身を変えて戦っていた獣は、ここでは別のものとして召喚ができるらしい。それはそれで便利だが、どうやら感覚は共有しているらしく、前足で念入りに潰しているよく分からない生き物の、肉のような、スライムのような感触も、土を削っていく爪の感触も、確かにその手の中にあった。
これは利点でもあり、欠点でもある。誰かの後ろに隠れて戦うようなことはできない。武道の心得がなくはないから、後ろに退くつもりはさらさらない。ただ、感覚を共有しているのなら、自分以上のリーチの長さと、頑丈さを活かさない手はない。
「……臭うなあ、相変わらず」
彼は喫煙者だった。
いつでもどこでも同じ銘柄を吸うことは難しかったが、煙草にも好みの味だの、何だの、そういう物はあるらしい。それらは葉の配合量や、成分に依るものだから、“似たようなもの”を常に吸っていた。だから、纏うにおいも、そう変わらなかった。
「……そら、進め。……あまりいいことになってないようにも見える」
目視。異能が強化される場所にあっては、スズヒコの視力は強化される。眼鏡が必要ないどころか、遠くまで見えすぎて困るくらいだ。例えば今のような。
見知らぬ少年と、男と、自分の探し人。その近くで、潰しきれていない赤い生き物が、今にも再形成しようとしていた。
「――走れ」
この世界がどこだろうと、何だろうと、どうだっていい。どうなっても構わない。
ただ、ずっと問いかけ続けてくる声に、選択肢の少なすぎる答えに、“どこでもない”とだけ答え続けることしかできないのだ。
獣の咆哮。それから、爪を振り下ろす音。再び念入りに潰される、ただただ憐れな生き物。己の名前を聞き止め、咲良乃スズヒコはハザマの大地に飛び降りた。



ENo.151 ガズエット とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.687 音和姉弟 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| フェデルタ 「……争え、とか言う割にはあっちにいけこっちにいけって……回りくどいんだよな」 |
あまり馴れ合うつもりはないからな、というオーラを放っている。 |
 |
(アレは、おろおろしている!) |
 |
迦楼羅 「(スズヒコが作ってくれたサンドイッチを食べている、ただし野菜が抜かれている)」 |
ItemNo.7 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。





痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
 |
侵攻災害区域
|



武術LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
響鳴LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
変化LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
メリーナ(646) により ItemNo.5 不思議な石 から魔晶『異本の栞』を作製してもらいました!
⇒ 異本の栞/魔晶:強さ17/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]充填5/特殊アイテム
 |
メリーナ 「取引ありがとう。そちらの依頼の品も持ってきたよ。 こんな感じでいいかな?」 |
メリーナ(646) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『レタスサンド』をつくりました!
潤(39) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ふわふわ卵のカツ丼』をつくりました!
獣(333) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『とろーり不思議なホットサンド』をつくりました!
葵(548) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『厚切り肉のフシギ焼き』をつくってもらいました!
⇒ 厚切り肉のフシギ焼き/料理:強さ35/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム
 |
「依頼をありがとう、お客さん。 加工方法はおまかせということで、 手持ちの肉と組み合わせての提供となるよ。」 |
 |
「ざっくり説明すると、塩と寝かせた肉を厚く切って、 不思議な食材をまぶしながらしっかり中まで火を通したものだ。 少し不思議な香りがするね、この食材は。 肉の臭みはうまく消し去ってくれるようだ。 厚く切っているので食べ応えは保証するけど、もし塩味が強かったら申し訳ない。 希望があれば、次は塩抜きした上で提供するよ。」 |
 |
「それじゃあ、ご武運を。」 |
かすみ(1311) とカードを交換しました!
ハートブレイクショット (ハードブレイク)

マナポーション を研究しました!(深度0⇒1)
マナポーション を研究しました!(深度1⇒2)
マナポーション を研究しました!(深度2⇒3)
ガードフォーム を習得!
リフレクション を習得!
カームソング を習得!
プロテクション を習得!
ミラー&ミラー を習得!
ディベスト を習得!
ガーディアン を習得!
ワイドプロテクション を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は パンの耳 を入手!
スズヒコ(244) は 美味しくない草 を入手!
グノウ(909) は 美味しくない草 を入手!
迦楼羅(931) は パンの耳 を入手!
スズヒコ(244) は 毛 を入手!
迦楼羅(931) は ねばねば を入手!
グノウ(909) は 毛 を入手!
フェデルタ(165) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 大黒猫 が軽快なステップで近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 道端ガムマン がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ヤンキー が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
採集はできませんでした。
- 迦楼羅(931) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



食究会
|
 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|


ENo.244
鈴のなる夢



ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
21 / 30
28 PS
チナミ区
N-6
N-6










| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 水の護り | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 異本の栞 | 魔晶 | 17 | 幸運10 | - | 充填5 | |
| 6 | 厚切り肉のフシギ焼き | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]耐疫10(LV30)[防具]体力10(LV30)[装飾]強靭10(LV30) | |||
| 8 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 25 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| 練3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 5 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]マナポーション |

PL / 紙箱みど