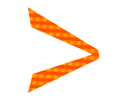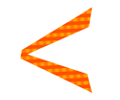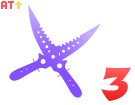<< 0:00~1:00




この手は金色の血で染まっている
再び筆を握ることはない
しかし、イバラシティに住む僕は絵を描いている
かつて僕が『高校生』だった頃のように

これは地鴉公園のクリスマスイルミネーション開催時に描いた絵。
狛狗がくれたアイディアをもとに『幸運の象徴』として作り上げたイルミネーション。
その中でもハイキングコースを彩る『幸せの青い鳥』をイメージした電飾を思って描いたものだ。
僕はこの絵、そしてイルミネーションについて……2人に謝らなくてはならない。
僕はこの絵を幸運の象徴と言ったな。
タイトルは『祝福に翔ぶ』
キラキラと輝く光の世界。光の中で祝福され、幸せな青い鳥の姿。
幸せな青い鳥は、誰の手にも落ちることなく、光の中を行く……と。
これはそんなものじゃない。
この絵に描かれた青い鳥は……
僕はそんなものを君に渡そうとしている。
でも、少なくともあちらの僕は、君がこの絵を好きと言ってくれたことが、ただ嬉しかったんだ。
お前がくれた『青い鳥』というアイディアを僕は、
無意識のうちに、僕が持つ最も不吉な光景として解釈してしまったらしい。
僕が表現したこの光景は、
『幸せの青い鳥』なんかじゃなくて……
でも、少なくともあちらの僕は、心から君に幸運が訪れてほしいと願ってこれを提案した。
それだけは、本当なんだ……
この光景は

忘れることのない

侵略の日
侵略。
その言葉を聞くたびあの世界のことを思い出す。
あの世界とは僕の故郷のことだ。否定の世界に堕ちる前、僕がいた世界。
今、あの世界はどうなっているのだろう。
新たな侵略に蝕まれてなどはいないだろうか。
あの時怯えた顔をした住人たちは、今も息災でやっているだろうか。
あの世界の"作者"は僕の手で殺してしまったから、今なお守護者がいないのでは……なんて心配をしてしまう。
それとも、既に新たな守護者が誕生しているだろうか。
イバラシティに警察や、多くのヒーローたちが存在するように……
あの世界……『理想絵』は、美しい色をした絵画だった。
価値観を上塗りできない程、見惚れるに値する絵画だった。
でも、あれはどんなに美しくとも、作ってはならなかったもの。
だからあの絵を描いた者の創造を全力で否定し、剣を交え、呪詛を吐き、殺す。
美への賞賛を、憚りを超えた怒りを。
僕は全て飲み込んで『悪』を成し遂げたのだ。
今になってこの名前を呼ぶなんて。どうかしている。
でも呼んでみてわかった。
呼んでも何も変わらない、何も思わない、何も感じない。
……ということは、僕はまだあの人のことが好きだということだろう。
この名前を最後に呼んでから既に20年以上。
もはやあの世界で過ごした時よりも、否定の世界で黙した時の方が長いのか。
……ひどい話だ。
今、再び『僕の住む街』に侵略の手が舞い降りているなんて。
選択を迫られている。再び僕は侵略と向き合っている。
師匠はよく言っていた。前を向いて、息を吸って、吐く。
僕たちはそれだけで生きていると言える。
でも、それができることが一番大変で、立派なことなんだと。
名声はいらない。安息は夢の中だけでいい。この牢獄の中で黙するだけでかまわない。
……そんなことを思ったとしても、現実は楽に運ばない。
僕は僕が息をするための生き方を、ありとあらゆる手で探さなければならないし、
たとえ誰かをおびやかしたとしても、そうすることでしか息できないなら、躊躇してはならない。
躊躇すれば、自分が息をできなくなるからだ。
『イバラシティ』に侵略を図るつもりは毛頭なくても、
イバラシティを守ると宣言する程、説得力のある生き方なんてしてない。
…………
……………………
心の中で繰り返す。僕は戦わない。
いや、戦えないんだ僕は。この装甲はもう動かないのだから。
何を今更迷うことがあるのか。
僕はいったい、何を迷っているのか。
今食べているのは味付け干し肉。
これは師匠から教わった最初の加工法。原点にして頂点……と僕は勝手に思っている。
日持ちもするし、持ち運びに適しているし、風通しに気を使いながら面倒をみるのも可愛げがあって最高。
おすすめの食べ方は、熱した酒につけてふやかして、何度も咀嚼する。
もとが味のない肉であれば、咀嚼することでようやく味を感じることができる。
味付けに使うのは秘伝の味付け粉。
こなの原料は企業秘密だけど、その味は保証できるものだ。
桑は未成年だけど……飲める水を持っていないからそこは我慢してもらうしか仕方がない。
戦う気がなくても桑をかくまっている以上、僕は言い訳しようなく『イバラ側』にしか見えない。
……ああ、どうしたものか。



ENo.16 狐嵐華丸 とのやりとり

ENo.528 ひさめ とのやりとり

以下の相手に送信しました












魔術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
フェデルタ(165) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『肉切り包丁(戦闘用)』を作製してもらいました!
⇒ 肉切り包丁(戦闘用)/武器:強さ35/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
不在の少女(466) により ItemNo.5 不思議な石 から法衣『鎖帷子』を作製してもらいました!
⇒ 鎖帷子/法衣:強さ17/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]幸運5/特殊アイテム
スズヒコ(244) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『厚切り肉のフシギ焼き』をつくりました!
不在の少女(466) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『やわらかフシギサラミ』をつくりました!
ツバキ(805) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ひき肉のクロケット』をつくりました!
竹取の翁(1391) とカードを交換しました!
飛び出す竹 (ピットトラップ)

カームフレア を研究しました!(深度1⇒2)
カームフレア を研究しました!(深度2⇒3)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアボルト を習得!
コンセントレイト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)
採集はできませんでした。
- 葵(548) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



この手は金色の血で染まっている
再び筆を握ることはない
しかし、イバラシティに住む僕は絵を描いている
かつて僕が『高校生』だった頃のように

これは地鴉公園のクリスマスイルミネーション開催時に描いた絵。
狛狗がくれたアイディアをもとに『幸運の象徴』として作り上げたイルミネーション。
その中でもハイキングコースを彩る『幸せの青い鳥』をイメージした電飾を思って描いたものだ。
僕はこの絵、そしてイルミネーションについて……2人に謝らなくてはならない。
 |
「まず、河万里。」 |
僕はこの絵を幸運の象徴と言ったな。
タイトルは『祝福に翔ぶ』
キラキラと輝く光の世界。光の中で祝福され、幸せな青い鳥の姿。
幸せな青い鳥は、誰の手にも落ちることなく、光の中を行く……と。
これはそんなものじゃない。
この絵に描かれた青い鳥は……
僕はそんなものを君に渡そうとしている。
でも、少なくともあちらの僕は、君がこの絵を好きと言ってくれたことが、ただ嬉しかったんだ。
 |
「そして……狛狗。」 |
お前がくれた『青い鳥』というアイディアを僕は、
無意識のうちに、僕が持つ最も不吉な光景として解釈してしまったらしい。
僕が表現したこの光景は、
『幸せの青い鳥』なんかじゃなくて……
でも、少なくともあちらの僕は、心から君に幸運が訪れてほしいと願ってこれを提案した。
それだけは、本当なんだ……
この光景は

忘れることのない

侵略の日
侵略。
その言葉を聞くたびあの世界のことを思い出す。
あの世界とは僕の故郷のことだ。否定の世界に堕ちる前、僕がいた世界。
今、あの世界はどうなっているのだろう。
新たな侵略に蝕まれてなどはいないだろうか。
あの時怯えた顔をした住人たちは、今も息災でやっているだろうか。
あの世界の"作者"は僕の手で殺してしまったから、今なお守護者がいないのでは……なんて心配をしてしまう。
それとも、既に新たな守護者が誕生しているだろうか。
イバラシティに警察や、多くのヒーローたちが存在するように……
 |
「変な話だ。自分でおびやかしておいて、今更心配なんて。」 |
あの世界……『理想絵』は、美しい色をした絵画だった。
価値観を上塗りできない程、見惚れるに値する絵画だった。
でも、あれはどんなに美しくとも、作ってはならなかったもの。
だからあの絵を描いた者の創造を全力で否定し、剣を交え、呪詛を吐き、殺す。
美への賞賛を、憚りを超えた怒りを。
僕は全て飲み込んで『悪』を成し遂げたのだ。
 |
「……瀬奈」 |
今になってこの名前を呼ぶなんて。どうかしている。
でも呼んでみてわかった。
呼んでも何も変わらない、何も思わない、何も感じない。
……ということは、僕はまだあの人のことが好きだということだろう。
この名前を最後に呼んでから既に20年以上。
もはやあの世界で過ごした時よりも、否定の世界で黙した時の方が長いのか。
……ひどい話だ。
今、再び『僕の住む街』に侵略の手が舞い降りているなんて。
選択を迫られている。再び僕は侵略と向き合っている。
師匠はよく言っていた。前を向いて、息を吸って、吐く。
僕たちはそれだけで生きていると言える。
でも、それができることが一番大変で、立派なことなんだと。
名声はいらない。安息は夢の中だけでいい。この牢獄の中で黙するだけでかまわない。
……そんなことを思ったとしても、現実は楽に運ばない。
僕は僕が息をするための生き方を、ありとあらゆる手で探さなければならないし、
たとえ誰かをおびやかしたとしても、そうすることでしか息できないなら、躊躇してはならない。
躊躇すれば、自分が息をできなくなるからだ。
『イバラシティ』に侵略を図るつもりは毛頭なくても、
イバラシティを守ると宣言する程、説得力のある生き方なんてしてない。
…………
……………………
心の中で繰り返す。僕は戦わない。
いや、戦えないんだ僕は。この装甲はもう動かないのだから。
何を今更迷うことがあるのか。
僕はいったい、何を迷っているのか。
 |
話は変わるが、これは未だに目覚めない同級生。 |
 |
「桑のやつ、起きないな。酒が冷めちゃうよ。」 |
今食べているのは味付け干し肉。
これは師匠から教わった最初の加工法。原点にして頂点……と僕は勝手に思っている。
日持ちもするし、持ち運びに適しているし、風通しに気を使いながら面倒をみるのも可愛げがあって最高。
おすすめの食べ方は、熱した酒につけてふやかして、何度も咀嚼する。
もとが味のない肉であれば、咀嚼することでようやく味を感じることができる。
味付けに使うのは秘伝の味付け粉。
こなの原料は企業秘密だけど、その味は保証できるものだ。
桑は未成年だけど……飲める水を持っていないからそこは我慢してもらうしか仕方がない。
 |
「それに、ずっと一箇所に留まっているのは危ないよな……」 |
戦う気がなくても桑をかくまっている以上、僕は言い訳しようなく『イバラ側』にしか見えない。
……ああ、どうしたものか。



ENo.16 狐嵐華丸 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.528 ひさめ とのやりとり
| ▲ |
| ||||
以下の相手に送信しました



 |
「行くしかない、か。」 |







魔術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
フェデルタ(165) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『肉切り包丁(戦闘用)』を作製してもらいました!
⇒ 肉切り包丁(戦闘用)/武器:強さ35/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
| フェデルタ 「なんの肉刻むつもりかしらねえけど、あんまり振り回すなよ」 |
不在の少女(466) により ItemNo.5 不思議な石 から法衣『鎖帷子』を作製してもらいました!
⇒ 鎖帷子/法衣:強さ17/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]幸運5/特殊アイテム
 |
「おまたせしました、鎖帷子でーす。ここで装備……」 |
 |
「んん……もしかしてバケツ奏者の先輩ですか?」 |
スズヒコ(244) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『厚切り肉のフシギ焼き』をつくりました!
不在の少女(466) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『やわらかフシギサラミ』をつくりました!
ツバキ(805) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ひき肉のクロケット』をつくりました!
竹取の翁(1391) とカードを交換しました!
飛び出す竹 (ピットトラップ)

カームフレア を研究しました!(深度1⇒2)
カームフレア を研究しました!(深度2⇒3)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアボルト を習得!
コンセントレイト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)
採集はできませんでした。
- 葵(548) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――





ENo.548
銭田 葵



========================
※サブキャラの「桑 レイル」は、数更新を終えたのち、
転校という名のロスト予定です。
交流の際はご注意ください。
========================
■ハザマにおける銭田葵
『これからも絵を描いていられますように』
『何事もなく息災でいられますように』
かつて思い描いた2つの願いを、とうの昔に失った者。
絵描きとしての筆は折った。
世の平穏を守る、戦士としての羽根も手折られた。
夢も未来も涙も心も枯れ果てた。
狂気の瞳、生ける屍、敗北の徒。
その余生は牢獄にて、できることなら慎ましやかに。
***
銭田葵はアンジニティの住人である。
年齢は30を優に超え、身長は自販機よりでかい。
特徴的だったツートンカラーな髪色は見られず、
その瞳孔は常にかっぴらかれている。
職業は絵描きではない、戦士でもない。
筋だらけで味もなく、不味くて仕方ないような肉を、
骨ばかりで身がなく、臭みばかり際立つような魚を、
それなりに食えるレベルにする程度の食肉加工屋である。
依頼を受ければ"どんな肉であれ"加工する。
倫理に反する物だとしても請け負うだろう。
え、肉と全く関係ないお菓子とか作ってほしいって?
食肉加工屋だよ???まあ、やるけどさ!
なお、加工技術は異能の類ではなく、
長年手に職をつけた結果の賜物である。
アンジニティの侵略にも、イバラシティの防衛にも
参加する気がなく、基本的に戦いを拒んでいる。
しかし、身を投じてしまえば戦わねばならないことも
理解しており、誰かを守るために
体が勝手に動いてしまうこともある。
真の意味で『戦いを拒んでいる』かは怪しい。
生身の人間だが、人外の多いアンジニティにおいても
撹乱・逃走を重ねて生き残れる程度の身体能力を持つ。
身体能力の基盤となるのは
『播谷流現代忍術』を駆使した体術である。
ちなみに弟はいない。むしろ兄が1人いた。
***
どうやら、葵の傍には《何か》が憑き纏っている。
《何か》の正体は不明だが、ときに葵の傍に具現する。
炎のように揺らめく《絵画》として。
***
以下、イバラシティにおける情報
========================
■銭田 葵(ゼンダ アオイ)
メインPC [icon0〜9]
学校関係者の既知設定OK。
身長165cm 体重55kg
タニモリ区のイバラ創藍高校に通う高校1年生。
絵を描くことに生きている。
放課後は画材費のためにバイトをしたり、
キャンバスを抱えてどこかに繰り出すばかりである。
家族構成は父と母の3人暮らし。
かつて弟がいたが、数年前に事故で亡くなっている。
父は町工場の長を務め、母もその補佐をしているが、
葵はあまり興味を示さない。
異能:ゴーストレーダー
幽霊や怪奇現象、それらの類の存在を察知することがある。
相手から語りかけてくる場合、
その声を聞き、会話することも可能。
怪奇からの寄り添いを強く受けるとき、頭髪が空色に光る。
***
父の職場が『町工場』というのは世間的な隠れ蓑である。
工場の奥では密かに戦闘用装甲兵器を開発しているという。
葵もまた父より装甲『カクジャック』を
預かった試験要員である。
工場の跡継ぎとしては期待されていないが、
戦士としての力こそが唯一の父とのつながりと感じ、
受け入れている。
***
いつもどこにいる?
地鴉公園(オオキタ区)
http://lisge.com/ib/talk.php?s=249
イバラ創藍高校(タニモリ区)
http://lisge.com/ib/talk.php?s=227
銭田葵宛IBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1987
銭田葵の拠点 @水上都市(チナミ区)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2595
町工場(ソロール用プレイス)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3002
暗躍する鋼鴉(戦闘用プレイス)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2998
========================
■桑 レイル(クワ レイル)
期間限定サブキャラ [icon10〜16]
学校関係者の既知設定OK。
タニモリ区のイバラ創藍高校に通う高校1年生。
葵の同級生。
========================
■大福 寿(ダイフク ヒサシ)
サブキャラ [icon17]
地鴉公園に入りびたるホームレス。
ボロボロのスーツ、割れたメガネ、
ただ飯を求めてさまよう。
========================
■ロジン・アンバー
サブキャラ [icon18〜21]
地鴉公園の創立者にしてオーナー。
自称公園デザイナーだが、
彼の作る公園にはなぜか謎の墓地がある。
緑色のスーツに、金髪の男性。
香水をつけているのか、
爽やかなハチミツのような香りを漂わせる。
カレーに目がない。
口の中を見るとどうも黄色っぽい気がするが、
本人によればカレーの食い過ぎとのことだ。
========================
■店長
サブキャラ [icon22]
地鴉公園にあるカレー屋の店長。
ファッションがいやにスケている。
※サブキャラの「桑 レイル」は、数更新を終えたのち、
転校という名のロスト予定です。
交流の際はご注意ください。
========================
■ハザマにおける銭田葵
『これからも絵を描いていられますように』
『何事もなく息災でいられますように』
かつて思い描いた2つの願いを、とうの昔に失った者。
絵描きとしての筆は折った。
世の平穏を守る、戦士としての羽根も手折られた。
夢も未来も涙も心も枯れ果てた。
狂気の瞳、生ける屍、敗北の徒。
その余生は牢獄にて、できることなら慎ましやかに。
***
銭田葵はアンジニティの住人である。
年齢は30を優に超え、身長は自販機よりでかい。
特徴的だったツートンカラーな髪色は見られず、
その瞳孔は常にかっぴらかれている。
職業は絵描きではない、戦士でもない。
筋だらけで味もなく、不味くて仕方ないような肉を、
骨ばかりで身がなく、臭みばかり際立つような魚を、
それなりに食えるレベルにする程度の食肉加工屋である。
依頼を受ければ"どんな肉であれ"加工する。
倫理に反する物だとしても請け負うだろう。
え、肉と全く関係ないお菓子とか作ってほしいって?
食肉加工屋だよ???まあ、やるけどさ!
なお、加工技術は異能の類ではなく、
長年手に職をつけた結果の賜物である。
アンジニティの侵略にも、イバラシティの防衛にも
参加する気がなく、基本的に戦いを拒んでいる。
しかし、身を投じてしまえば戦わねばならないことも
理解しており、誰かを守るために
体が勝手に動いてしまうこともある。
真の意味で『戦いを拒んでいる』かは怪しい。
生身の人間だが、人外の多いアンジニティにおいても
撹乱・逃走を重ねて生き残れる程度の身体能力を持つ。
身体能力の基盤となるのは
『播谷流現代忍術』を駆使した体術である。
ちなみに弟はいない。むしろ兄が1人いた。
***
どうやら、葵の傍には《何か》が憑き纏っている。
《何か》の正体は不明だが、ときに葵の傍に具現する。
炎のように揺らめく《絵画》として。
***
以下、イバラシティにおける情報
========================
■銭田 葵(ゼンダ アオイ)
メインPC [icon0〜9]
学校関係者の既知設定OK。
身長165cm 体重55kg
タニモリ区のイバラ創藍高校に通う高校1年生。
絵を描くことに生きている。
放課後は画材費のためにバイトをしたり、
キャンバスを抱えてどこかに繰り出すばかりである。
家族構成は父と母の3人暮らし。
かつて弟がいたが、数年前に事故で亡くなっている。
父は町工場の長を務め、母もその補佐をしているが、
葵はあまり興味を示さない。
異能:ゴーストレーダー
幽霊や怪奇現象、それらの類の存在を察知することがある。
相手から語りかけてくる場合、
その声を聞き、会話することも可能。
怪奇からの寄り添いを強く受けるとき、頭髪が空色に光る。
***
父の職場が『町工場』というのは世間的な隠れ蓑である。
工場の奥では密かに戦闘用装甲兵器を開発しているという。
葵もまた父より装甲『カクジャック』を
預かった試験要員である。
工場の跡継ぎとしては期待されていないが、
戦士としての力こそが唯一の父とのつながりと感じ、
受け入れている。
***
いつもどこにいる?
地鴉公園(オオキタ区)
http://lisge.com/ib/talk.php?s=249
イバラ創藍高校(タニモリ区)
http://lisge.com/ib/talk.php?s=227
銭田葵宛IBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=1987
銭田葵の拠点 @水上都市(チナミ区)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2595
町工場(ソロール用プレイス)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3002
暗躍する鋼鴉(戦闘用プレイス)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2998
========================
■桑 レイル(クワ レイル)
期間限定サブキャラ [icon10〜16]
学校関係者の既知設定OK。
タニモリ区のイバラ創藍高校に通う高校1年生。
葵の同級生。
========================
■大福 寿(ダイフク ヒサシ)
サブキャラ [icon17]
地鴉公園に入りびたるホームレス。
ボロボロのスーツ、割れたメガネ、
ただ飯を求めてさまよう。
========================
■ロジン・アンバー
サブキャラ [icon18〜21]
地鴉公園の創立者にしてオーナー。
自称公園デザイナーだが、
彼の作る公園にはなぜか謎の墓地がある。
緑色のスーツに、金髪の男性。
香水をつけているのか、
爽やかなハチミツのような香りを漂わせる。
カレーに目がない。
口の中を見るとどうも黄色っぽい気がするが、
本人によればカレーの食い過ぎとのことだ。
========================
■店長
サブキャラ [icon22]
地鴉公園にあるカレー屋の店長。
ファッションがいやにスケている。
20 / 30
35 PS
チナミ区
N-6
N-6





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 肉切り包丁(戦闘用) | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 鎖帷子 | 法衣 | 17 | 防御10 | - | 幸運5 | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 9 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 解析 | 15 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 25 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]カームフレア | [ 2 ]アクアヒール | [ 1 ]リビルド |

PL / たしなみがい