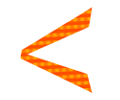<< 0:00~0:00





廊下を歩く足音。空中に浮かび上がるホログラムのディスプレイに触れ、フォルダの階層をひとつずつ降りていく。奥まった位置に存在している、『第二次響奏世界侵入計画』という文字が、特に踊るわけでもなく、そこに忽然と存在していた。
大日向深知はその気である。そして、理系の人間――中でも純理学の人間は、後先のことを考えないことが大抵だ。そこに興味深い事象を発見したら、まず徹底してそれを荒らし回る。四方八方から観察し、暴き、捌く。紫筑大学第四学群神秘研究科怪異対策類実務班はそのためだけに存在しているわけではない。大日向の欠けは紫筑にとって大きな損失だが、それ以上に創峰のためになる、と正面を切って紫筑学長に言い切ったらしい大日向の肝の据わり具合というか、大日向の思考にはついていけない。し、ついていく気もない。その二つ名の通り“最強大天才”、頭脳も能力も桁違いだ。
「実務班、点呼!」
揃っている面子の中で、一番学年が上である男が口を開いた。
「M1。第二チーム、西村一騎」
「B4……同じく第二チーム、宮城野陽華」
「M2、第五……あっ違う四になったんだ。第四チーム、二ノ平悠」
「はーい第五のB1!紀野いずも!」
「M1、第四チーム。西村一海」
「第五。D3、クレール・シルヴェスト……これで全員か?」
反応は芳しくない。誰もが知らされていないからだ。
先行して響奏の世界イバラシティに入り込んだ大日向深知からの要請はただひとつで、西村一騎を中心とした少人数チームを編成し、自分をアンカーにして世界間転移を発動させ、イバラシティへ来い、という、簡潔で分かりやすい無茶振りだった。
世界は積層構造である。その理論をぶち上げた大日向深知の兄、大日向深景の言うに曰く、コツを掴みさえすれば世界の距離は大幅に縮まるだろう、と。これは横の移動を表していて、つまり各種輸送に世界間転移を応用させれば、大量の燃料も、そもそも大型の貨物も必要なくなる。一瞬世界の裏を経由するだけでそれを可能にしようというのが、理系は理系でも人の役に立とうとする、大日向深景の思想だった。では、横の移動ではなく、縦の移動は?
縦の移動とは即ち、侵略行為である。大日向深知は、純然たる好奇心で侵略行動をする。そのために人を集められるだけの地位と権限が、彼女にはある。
「少数精鋭、と言った感じですね……」
「だろうな。向こうが先入りしてる以上、ゴミは連れてけねえ」
怪異対策類実務班には、縦の移動に慣れなければならない理由があった。彼らが恒常的に相手をする何かは、大抵が縦の移動を習得している。あるいは、縦の移動を得意とする。
殺し損ねた怪異がどこに逃げていったのか、そしてどこで力を蓄え、再び出没するのか、それらの謎を解く鍵が、積層構造間の縦の移動だった。これを解き明かして以降、紫筑大学の怪異捕縛・破壊レートは大きな上昇を見せている。それでも完全で完璧な、というわけにはいかず、実務班の少数精鋭がこうして選出され、『大日向深知そのものをアンカーとした』転移実験を行おうとしている。
そこに【光をその手に】西村一騎がいる理由は、混在チーム長のクレール・シルヴェストしか知らない。
「では改めて。西村一騎・宮城野陽華は『創峰大学』。俺含むその他四人は散会し、各自自由行動」
「はいセンパーイ!別に一人じゃなくてもいいんですよね?」
「あんたは一人で行くな。ニノ平」
「承知してます。手はずは整えてあります」
「さっすがー」
「えーっなんで!っていうかそもそも、自由行動って何ですかあ。あたし全然聞いてませんけどお!」
「現地で分かるだろ。ぐだぐだ喋ってんじゃねえ」
紫筑大学地下。
公の場として広く取られた空間のど真ん中を軽く踏むと、起動コンソールがふっと現れる。模擬戦闘の場として使われることの多い足元に幾何学的な文様が走っていく。
「アンカー・響奏の世界大日向深知。スタートアップ、セット。計六名登録済、開始」
今はまだ、何の補助もなしに自発的な縦の移動を行える人間はほぼいない。あの大日向兄妹ですらそうなのだから、世界という壁はとことんまでに分厚い。分厚い壁にピンポイントで穴を開け、そこを滞りなく通っていく。それだけだ、と言う割に、それだけが大掛かりなのだ。
その意味を、今はまだ、一人しか知らない。
「それではお前ら、あとは静粛に」
世界が切り取られる。その中の存在を、別の世界にねじ込むために。
『さあ、来い、こちら側へ!!』
――それはまあ、一言で言うならクソ、もうちょっと形容するならしっちゃかめっちゃかだった。六人もまとめて縦に通すな、あるいはせめて一人ずつにしろ。
ありとあらゆる荷物が散らばっていたり、転移酔いで木の陰でゲロゲロに吐いているやつがいたり、もう散々だ。いや、想定通りではある。
「……紀野が立てるようになったら出るぞ。そこまで座標がズレてるわけではないから、歩けばすぐだ」
「あの、待ってください」
肩を揺さぶられる女性。ぴくりともしない女性。
――そう、それでいい。
「一海さんが……一海さん、が」
「ああ、一海ならここにいますよ」
二卵性だと聞いていた割には、良く似た顔をした双子だった。【書き尽くす炎】西村一騎と、【識り尽くす氷】西村一海。金髪に染めた垂れ目の男と、その辺にいそうなオタク(自称していた)の垂れ目の女。
目を閉じすらせず、ぐったりと起き上がらないままの片割れの傍で、何てこともないように一騎は言った。
「いやっ……そうじゃなくて!この状況はあきらかに――」
「ええ、ですから私が一海です」
「……は?」
「え?」
背の高い男がさも当然のようにそう名乗り、クレールたち一行が凍りつく。吐いていたのが落ち着いて戻ってきたいずもが、そうなんだ~!!と大声を上げて、言った。
「西村パイセンと西村さん、入れ替わっちゃったってことすか!?」
「そうですね」
一海の対応は基本的に冷たい。見た目よりも遥かに雄弁に、その中身が一海であることを示され、クレールは手を叩いた。
「説明は大日向のチビに全て任せてある。少なくとも今の段階では“八割方成功した”と言える」
「……もしかして、事前にあなただけ知らされていた、というやつですか。また」
「厳密に言うと俺だけではないよ。当事者もそれなりに知っている必要がある。まあ、全部は多分俺だけだろう」
「その通りですね。私もクソ兄をちょっとアレするというアレしか聞いておりませんもんで」
「よく、それで、承諾できますね……」
「金には替えられませんからね」
これ以降紫筑の名前を出さぬように、と言われた一行は、静かに頷いた。
ここに存在しているのは紫筑大学ではない。この世界には紫筑大学は存在しない。その代わりに存在しているのが――創峰大学。
奇遇にも紫筑大学と同じように広大なキャンパスを持ち、奇遇にも積層構造の同じ辺りに存在している――つまり地図上で一致する。そこの、ほぼ同じ場所に構えられていた研究室を調べ上げ、先入りして空き部屋に架空の研究室をぶち上げたのが大日向深知だ。
響奏の世界『イバラシティ』が、否定の世界『アンジニティ』からの侵略対象になっていること。その侵略は世界そのものではなく、侵略の試合会場が別に設けられていること。それらの情報を、積層構造の一枚である『イバラシティ』から抜き取って帰還した大日向深知が、開口一番に告げたのは、
『ボクらも侵略者になるぞ!!』
だった。よく覚えている。
何事もなかったかのように紛れ込む住人として。学生生活を送る学生として。そこにいる“奴”を、狩るために。
不思議なことに、おおよそ建物の配置も構造も同じで、クレールたちは一切迷わずに目的の場所に辿り着けていた。
『大日向研究室』と書かれたプレートの下に、大量の生物系のポスターやチラシが貼られていた。
二度ノック。誰かが代わりに「失礼します!」と言ってくれた。ドアを開ける。
「入れ!」
甲高い元気な声。間違えようがなかった。
大日向深知。紫筑――おっと。今は創峰大学の――元の立場を考えると恐らく講師だろうか。大きな机に大量に資料を積み上げ、体躯に見合わぬ椅子に、クッションを何枚か積んで座っていた。
「……ミス・大日向。救護室などは?」
「ふむ。その口振りだとうまく放り出せたとみた。必要ない。ボクの自室に運ぶ予定だ」
「自室というと……」
「この世界で実際に住んでいる部屋」
「なるほど。なら、いいでしょう」
一騎(中身は一海)が抱えている、ぐったりとしたまま動かない一海を見、大日向は満足そうに頷いた。扉を閉めろ、と促す声がする。
扉が閉められる。狭い室内に背の高い男が三人もいる。スリッパを脱ぎ捨て、机の上に立ってようやく彼らを見下ろせる大日向は、ぴっと指を立て、そして宣言した。
「これより第二次響奏世界侵入計画改め、【哀歌の更新】追走・撃破計画を開始とする!!」
シンとする室内。その言葉の意味を、全員がよく知っていた。
「対象の釣り餌として【光をその手に】そのものを使用。回収は双子という特性を利用して【識り尽くす氷】西村一海に一任した。同時に互いの肉体を入れ替えることで、対象に『西村一海である』ことを誤認させる。これは恐らく成功している」
「……はい。質問です。何故成功していると言い切れるのでしょう」
「これもまた双子の特性である。西村」
「はい。よく言われますが、双子が魂を分けたものだとか、そのへんの奴ですね」
魂分割論には懐疑的だと一海は言ったが、少なくとも能力“は”分けられているということが直近の研究で示唆されている。一卵性ほど顕著だという。
生まれ持った能力についてどのように遺伝するかというのは、紫筑の第四学群では大変大きな研究課題になっている。双子の片方だけが大きな力を持つ事例がよく見られるが、双子を探すことは難しい。
「私たちは生物学的には普通に二人で二人ですが、能力学的にはそうではない。……で、合ってますよね?」
「その通りだ。本能よりもより深い場所で、何かがあれば反応が出るはずだ。そしてその時が、真に我々が動くべきタイミングである」
故に端末は常に持ち歩くように、と続けて、大日向は西村に続きを促した。
「……まあつまり今何もないし、“俺”を【哀歌の行進】が捕まえないこともありえないんですね。ですので、何かあるまでは情報収集したり、観光したり、情報収集したり……」
「観光していいの!?」
「紀野!!」
「もちろん構わんさ!君たちは公費で旅行をしていると言っても過言ではない!」
理論を理解するのは難しくとも、感覚で今何をするべきか、くらいは分かる。
自分たちの出る幕はまだ先で、それまでに刃を研いでおけ。羽を伸ばせ。そういうことだ。
「やったー!!クレセン~!!甘いもの開拓しましょうよ~!!」
「ハァ!?同チームのとやってろ!!おい!!ニノ平!!」
「ああ、すいません……俺、唯一の整備班兼任なんで……」
「カス!!」
「今学生控室を手配している。すぐ横だ。適時好きなものを調達してセットアップしろ。ボクからはひとまず以上だ」
机の上から大日向が降りたのを合図にして、学生たちは一斉に動き出した。
『そんな簡単にうまくいくと思うなよ』



ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.426 よいこ とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.889 さまよう夜風 とのやりとり

以下の相手に送信しました










エナジー棒(30 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
エナジー棒(30 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お魚(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お野菜(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
リオ(1334) により ItemNo.4 不思議な牙 から防具『水の護り』を作製してもらいました!
⇒ 水の護り/防具:強さ30/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
グノウ(909) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ありあわせサラダサンド』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『野菜たっぷりたまごサンド』をつくりました!
音和姉弟(687) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『火を通した何か』をつくりました!
かすみ(1311) とカードを交換しました!
けだまタックル (ピンポイント)

クリエイト:メガネ を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:メガネ を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:メガネ を研究しました!(深度2⇒3)
ストライク を習得!
エチュード を習得!
マーチ を習得!
チャージ を習得!
ビブラート を習得!
ブレイブハート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(山岳)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(山岳)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
フェデルタ(165) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- 迦楼羅(931) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――


















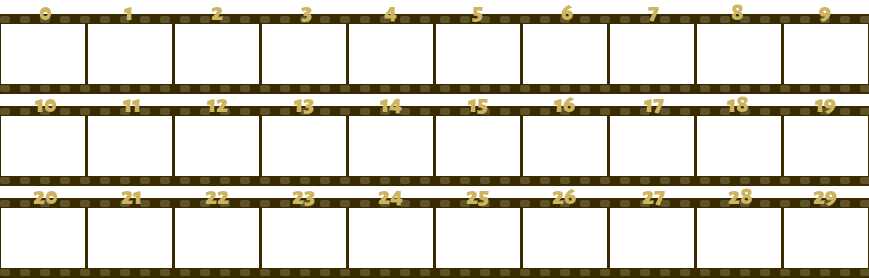







































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




廊下を歩く足音。空中に浮かび上がるホログラムのディスプレイに触れ、フォルダの階層をひとつずつ降りていく。奥まった位置に存在している、『第二次響奏世界侵入計画』という文字が、特に踊るわけでもなく、そこに忽然と存在していた。
大日向深知はその気である。そして、理系の人間――中でも純理学の人間は、後先のことを考えないことが大抵だ。そこに興味深い事象を発見したら、まず徹底してそれを荒らし回る。四方八方から観察し、暴き、捌く。紫筑大学第四学群神秘研究科怪異対策類実務班はそのためだけに存在しているわけではない。大日向の欠けは紫筑にとって大きな損失だが、それ以上に創峰のためになる、と正面を切って紫筑学長に言い切ったらしい大日向の肝の据わり具合というか、大日向の思考にはついていけない。し、ついていく気もない。その二つ名の通り“最強大天才”、頭脳も能力も桁違いだ。
「実務班、点呼!」
揃っている面子の中で、一番学年が上である男が口を開いた。
「M1。第二チーム、西村一騎」
「B4……同じく第二チーム、宮城野陽華」
「M2、第五……あっ違う四になったんだ。第四チーム、二ノ平悠」
「はーい第五のB1!紀野いずも!」
「M1、第四チーム。西村一海」
「第五。D3、クレール・シルヴェスト……これで全員か?」
反応は芳しくない。誰もが知らされていないからだ。
先行して響奏の世界イバラシティに入り込んだ大日向深知からの要請はただひとつで、西村一騎を中心とした少人数チームを編成し、自分をアンカーにして世界間転移を発動させ、イバラシティへ来い、という、簡潔で分かりやすい無茶振りだった。
世界は積層構造である。その理論をぶち上げた大日向深知の兄、大日向深景の言うに曰く、コツを掴みさえすれば世界の距離は大幅に縮まるだろう、と。これは横の移動を表していて、つまり各種輸送に世界間転移を応用させれば、大量の燃料も、そもそも大型の貨物も必要なくなる。一瞬世界の裏を経由するだけでそれを可能にしようというのが、理系は理系でも人の役に立とうとする、大日向深景の思想だった。では、横の移動ではなく、縦の移動は?
縦の移動とは即ち、侵略行為である。大日向深知は、純然たる好奇心で侵略行動をする。そのために人を集められるだけの地位と権限が、彼女にはある。
「少数精鋭、と言った感じですね……」
「だろうな。向こうが先入りしてる以上、ゴミは連れてけねえ」
怪異対策類実務班には、縦の移動に慣れなければならない理由があった。彼らが恒常的に相手をする何かは、大抵が縦の移動を習得している。あるいは、縦の移動を得意とする。
殺し損ねた怪異がどこに逃げていったのか、そしてどこで力を蓄え、再び出没するのか、それらの謎を解く鍵が、積層構造間の縦の移動だった。これを解き明かして以降、紫筑大学の怪異捕縛・破壊レートは大きな上昇を見せている。それでも完全で完璧な、というわけにはいかず、実務班の少数精鋭がこうして選出され、『大日向深知そのものをアンカーとした』転移実験を行おうとしている。
そこに【光をその手に】西村一騎がいる理由は、混在チーム長のクレール・シルヴェストしか知らない。
「では改めて。西村一騎・宮城野陽華は『創峰大学』。俺含むその他四人は散会し、各自自由行動」
「はいセンパーイ!別に一人じゃなくてもいいんですよね?」
「あんたは一人で行くな。ニノ平」
「承知してます。手はずは整えてあります」
「さっすがー」
「えーっなんで!っていうかそもそも、自由行動って何ですかあ。あたし全然聞いてませんけどお!」
「現地で分かるだろ。ぐだぐだ喋ってんじゃねえ」
紫筑大学地下。
公の場として広く取られた空間のど真ん中を軽く踏むと、起動コンソールがふっと現れる。模擬戦闘の場として使われることの多い足元に幾何学的な文様が走っていく。
「アンカー・響奏の世界大日向深知。スタートアップ、セット。計六名登録済、開始」
今はまだ、何の補助もなしに自発的な縦の移動を行える人間はほぼいない。あの大日向兄妹ですらそうなのだから、世界という壁はとことんまでに分厚い。分厚い壁にピンポイントで穴を開け、そこを滞りなく通っていく。それだけだ、と言う割に、それだけが大掛かりなのだ。
その意味を、今はまだ、一人しか知らない。
「それではお前ら、あとは静粛に」
世界が切り取られる。その中の存在を、別の世界にねじ込むために。
『さあ、来い、こちら側へ!!』
――それはまあ、一言で言うならクソ、もうちょっと形容するならしっちゃかめっちゃかだった。六人もまとめて縦に通すな、あるいはせめて一人ずつにしろ。
ありとあらゆる荷物が散らばっていたり、転移酔いで木の陰でゲロゲロに吐いているやつがいたり、もう散々だ。いや、想定通りではある。
「……紀野が立てるようになったら出るぞ。そこまで座標がズレてるわけではないから、歩けばすぐだ」
「あの、待ってください」
肩を揺さぶられる女性。ぴくりともしない女性。
――そう、それでいい。
「一海さんが……一海さん、が」
「ああ、一海ならここにいますよ」
二卵性だと聞いていた割には、良く似た顔をした双子だった。【書き尽くす炎】西村一騎と、【識り尽くす氷】西村一海。金髪に染めた垂れ目の男と、その辺にいそうなオタク(自称していた)の垂れ目の女。
目を閉じすらせず、ぐったりと起き上がらないままの片割れの傍で、何てこともないように一騎は言った。
「いやっ……そうじゃなくて!この状況はあきらかに――」
「ええ、ですから私が一海です」
「……は?」
「え?」
背の高い男がさも当然のようにそう名乗り、クレールたち一行が凍りつく。吐いていたのが落ち着いて戻ってきたいずもが、そうなんだ~!!と大声を上げて、言った。
「西村パイセンと西村さん、入れ替わっちゃったってことすか!?」
「そうですね」
一海の対応は基本的に冷たい。見た目よりも遥かに雄弁に、その中身が一海であることを示され、クレールは手を叩いた。
「説明は大日向のチビに全て任せてある。少なくとも今の段階では“八割方成功した”と言える」
「……もしかして、事前にあなただけ知らされていた、というやつですか。また」
「厳密に言うと俺だけではないよ。当事者もそれなりに知っている必要がある。まあ、全部は多分俺だけだろう」
「その通りですね。私もクソ兄をちょっとアレするというアレしか聞いておりませんもんで」
「よく、それで、承諾できますね……」
「金には替えられませんからね」
これ以降紫筑の名前を出さぬように、と言われた一行は、静かに頷いた。
ここに存在しているのは紫筑大学ではない。この世界には紫筑大学は存在しない。その代わりに存在しているのが――創峰大学。
奇遇にも紫筑大学と同じように広大なキャンパスを持ち、奇遇にも積層構造の同じ辺りに存在している――つまり地図上で一致する。そこの、ほぼ同じ場所に構えられていた研究室を調べ上げ、先入りして空き部屋に架空の研究室をぶち上げたのが大日向深知だ。
響奏の世界『イバラシティ』が、否定の世界『アンジニティ』からの侵略対象になっていること。その侵略は世界そのものではなく、侵略の試合会場が別に設けられていること。それらの情報を、積層構造の一枚である『イバラシティ』から抜き取って帰還した大日向深知が、開口一番に告げたのは、
『ボクらも侵略者になるぞ!!』
だった。よく覚えている。
何事もなかったかのように紛れ込む住人として。学生生活を送る学生として。そこにいる“奴”を、狩るために。
不思議なことに、おおよそ建物の配置も構造も同じで、クレールたちは一切迷わずに目的の場所に辿り着けていた。
『大日向研究室』と書かれたプレートの下に、大量の生物系のポスターやチラシが貼られていた。
二度ノック。誰かが代わりに「失礼します!」と言ってくれた。ドアを開ける。
「入れ!」
甲高い元気な声。間違えようがなかった。
大日向深知。紫筑――おっと。今は創峰大学の――元の立場を考えると恐らく講師だろうか。大きな机に大量に資料を積み上げ、体躯に見合わぬ椅子に、クッションを何枚か積んで座っていた。
「……ミス・大日向。救護室などは?」
「ふむ。その口振りだとうまく放り出せたとみた。必要ない。ボクの自室に運ぶ予定だ」
「自室というと……」
「この世界で実際に住んでいる部屋」
「なるほど。なら、いいでしょう」
一騎(中身は一海)が抱えている、ぐったりとしたまま動かない一海を見、大日向は満足そうに頷いた。扉を閉めろ、と促す声がする。
扉が閉められる。狭い室内に背の高い男が三人もいる。スリッパを脱ぎ捨て、机の上に立ってようやく彼らを見下ろせる大日向は、ぴっと指を立て、そして宣言した。
「これより第二次響奏世界侵入計画改め、【哀歌の更新】追走・撃破計画を開始とする!!」
シンとする室内。その言葉の意味を、全員がよく知っていた。
「対象の釣り餌として【光をその手に】そのものを使用。回収は双子という特性を利用して【識り尽くす氷】西村一海に一任した。同時に互いの肉体を入れ替えることで、対象に『西村一海である』ことを誤認させる。これは恐らく成功している」
「……はい。質問です。何故成功していると言い切れるのでしょう」
「これもまた双子の特性である。西村」
「はい。よく言われますが、双子が魂を分けたものだとか、そのへんの奴ですね」
魂分割論には懐疑的だと一海は言ったが、少なくとも能力“は”分けられているということが直近の研究で示唆されている。一卵性ほど顕著だという。
生まれ持った能力についてどのように遺伝するかというのは、紫筑の第四学群では大変大きな研究課題になっている。双子の片方だけが大きな力を持つ事例がよく見られるが、双子を探すことは難しい。
「私たちは生物学的には普通に二人で二人ですが、能力学的にはそうではない。……で、合ってますよね?」
「その通りだ。本能よりもより深い場所で、何かがあれば反応が出るはずだ。そしてその時が、真に我々が動くべきタイミングである」
故に端末は常に持ち歩くように、と続けて、大日向は西村に続きを促した。
「……まあつまり今何もないし、“俺”を【哀歌の行進】が捕まえないこともありえないんですね。ですので、何かあるまでは情報収集したり、観光したり、情報収集したり……」
「観光していいの!?」
「紀野!!」
「もちろん構わんさ!君たちは公費で旅行をしていると言っても過言ではない!」
理論を理解するのは難しくとも、感覚で今何をするべきか、くらいは分かる。
自分たちの出る幕はまだ先で、それまでに刃を研いでおけ。羽を伸ばせ。そういうことだ。
「やったー!!クレセン~!!甘いもの開拓しましょうよ~!!」
「ハァ!?同チームのとやってろ!!おい!!ニノ平!!」
「ああ、すいません……俺、唯一の整備班兼任なんで……」
「カス!!」
「今学生控室を手配している。すぐ横だ。適時好きなものを調達してセットアップしろ。ボクからはひとまず以上だ」
机の上から大日向が降りたのを合図にして、学生たちは一斉に動き出した。
『そんな簡単にうまくいくと思うなよ』



ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.426 よいこ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.889 さまよう夜風 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
以下の相手に送信しました



| 両手を見て立ち尽くしている。 |





エナジー棒(30 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
エナジー棒(30 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お魚(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お野菜(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
リオ(1334) により ItemNo.4 不思議な牙 から防具『水の護り』を作製してもらいました!
⇒ 水の護り/防具:強さ30/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
リオ 「どれ。...間に合わせで申し訳ないが。術式ならどちらかと言うと得意なはず、なのだが。。。ままならんものだな。。。」 |
グノウ(909) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『ありあわせサラダサンド』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『野菜たっぷりたまごサンド』をつくりました!
音和姉弟(687) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『火を通した何か』をつくりました!
かすみ(1311) とカードを交換しました!
けだまタックル (ピンポイント)

クリエイト:メガネ を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:メガネ を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:メガネ を研究しました!(深度2⇒3)
ストライク を習得!
エチュード を習得!
マーチ を習得!
チャージ を習得!
ビブラート を習得!
ブレイブハート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ひと仕事っと。一服してから次行くかねぇ。」 |
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(山岳)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(山岳)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
フェデルタ(165) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- 迦楼羅(931) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――







痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
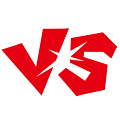 |
侵攻災害区域
|


ENo.244
鈴のなる夢



▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
創峰大学第二学群生物学科2年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M1)、宮城野陽華(B4)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
25 / 30
5 PS
チナミ区
J-5
J-5









| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 水の護り | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 料理 | 20 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| 決2 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ブレイブハート | 5 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ |

PL / 紙箱みど