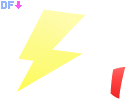<< 5:00




ヒトが、最初から嫌いだったわけじゃない。
むしろ、ヒトにはちょっとした親近感を抱いていたものだ。
マモノの中の弱者と、怪獣の中の弱者。
似たような存在にシンパシーを抱くのは、怪獣であっても想像に難くない。
彼らは、領地もなくはぐれ怪獣に成り下がっていた小生にとってなにより近しい存在だった。
書物もたくさん読んだ。ヒトの何事も記録に残したがる習性は面白いと思った。
植物や社会に関する本に、特に興味を示したものだ。
ようやく得た領地は厳しい環境だったことから住処の砦を訪れる人間はさほどいなかったが、
かつて歌謡いや行商人が訪れたときには、丁重にもてなした覚えもある。
――そう。とうに、昔の話だ。
シンパシーを感じた者達に心を許した結果が、あの灼け朽ちた砦だ。炎に捲かれた街だ。
蹂躙された、土地と民だ。
ヒトを恨んで、何が悪い。
だが……
*
イバラシティの面影を残した廃墟を歩く。
傾いたビルに、やけに見慣れた人影を見た。
あれは……雲谷千晴?
思わず自分の目を疑った。
おかしい。しかし、あれは間違いなくあのヒトの娘だ。
ここに訪れるイバラシティのヒトは限定されているという。
それも大体、戦力となるヒトが集っているはずだ。
異能を持たない、戦力となり得るはずもない彼女が、いるはずもない。
これは、罠か?いや、誰が罠を仕掛けるというのだ?
……どうせここから当分、脅威は無いだろう。
何より、時間が惜しい。
先に進むセンパイ共をよそに、人影を追いかける。
歪んだ建物を、直角に曲がる。
焦り。確かにそれもある。
それにあれの慰めのひとつである以上、動向を探る必要がある。
……ヒトの言う情、というものも少なからずあるのかもしれない。
だが言ってしまえば、自分が滑稽に思えてしょうがなくなる。
決して口になどするものか、決して。
瓦礫を軽く飛び越えると、住宅地の十字路に差し掛かった。
そこにあったのは、『2つ』の、影。
その影のひとつが自分の姿を認めるや否や、首に何か剣のような、鋭いものを突きつけてくる。
ヘマをした。
煙霧で姿を覆っていたものの、気配に勘付かれては元も子もない。
おまけに寸分違わず喉元に当てにきているときた。
観念して、すっと目の前の霧を晴らす。
その先で蹲る自分を見ていたのは、
熱線のごとく熱く、しかし冷水のように冷ややかに貫く視線。
……妹の、雲谷千晴だ。
* *
夕焼け空が、綺麗だった。
夏も近付いて、昼は随分と長くなった。
そんな日の夕方、電話がかかってきた。
相手はお母さんだった。
自分から受話器を取ったのは、いつぶりだろう?
えっ……?
何を言っているのだろう、お母さんは。
煙兄はここにいるじゃない。
一緒に暮らしているじゃない、いやだわ。
――そんな思考と反して、額からはおびただしい汗が流れていく。
……嫌な予感がする。
ごとん。
受話器が零れ落ちた音だけが、千晴1人だけの部屋に鮮明に響き渡った。
一瞬の静寂。
次いで少女の悲痛な絶叫が、アパートの一室に轟いた。
* * *
「チハル……?」
呼び慣れた名だ。
だが、発した一言が自分から出た声には到底思えなかった。
それ以上に驚くべきは、理解が追い付かないような目の前の状況にあった。
霧が晴れると共に、得物を突きつけた相手の顔もよく見えるようになった。
騎士よろしく千晴の前に立ちはだかる人物……その顔を、自分はよく知っていたのだ。
いや、当たり前にも程がある。
だってあれは……イバラシティでの自分なのだから。
全身黒尽くめで、髪型の特徴的な部分こそ消失しているが、間違いない。
どうして自分であるはずの……雲谷煙次が此処にいる?
「……っ、……!」
首元に熱を感じる。
視線を戻せば、いつのまにか突き付けられていたものが、喉に深々と差し込まれている。
気付かなかったのは、痛みはそれほど無かったからだ。
代わりに身体全体が怠さを訴える。強烈な睡魔が襲い掛かってきた。
相変わらず視線を向けていた千晴の瞳が、口元の微笑みと共に煌々と光る。
それと同時に、背後で何かが煌めきを放った。
それは太陽のようで、また違う。
中心部は紅く輝いているものの、そこから発するプロミネンスは黒々として、
妖しい光を見せながら揺らいでいた。
「お兄ちゃんはここにいる。ねえ、そうでしょう。お兄ちゃん」
千晴は、いつの間にか影のような色をした長身の男の背に寄りかかっていた。
その問いに、肯定も、否定も出来ない。
ただ何か、どうしようもない違和感が胸のうちから湧き上がる。
違和感があっても、それを正すことは出来ない。
手は届かない。
指が、空を掴む。
取りこぼしたパイプは遥か遠くの地面にある。
主の加護は、あまりにも遠い。
地面に倒れ伏して、目を、閉じる。
瞼を閉じてしまえば、もう開くことは出来ない。
視界は闇だけになって、声は遠くなる。
やがて自分が何処にいるのかも、分からなくなる。
「……おやすみなさい」
意識が遠のいて行く中で、そんな声を掛けられた気がした。




ENo.118 アリヒト とのやりとり

ENo.121 ミチ とのやりとり

ENo.167 うさ子 とのやりとり

ENo.503 清 とのやりとり

ENo.664 闇のおえかき とのやりとり

ENo.931 伊舎那 とのやりとり

ENo.1039 夢の残り香 とのやりとり

ENo.1132 玲瓏 とのやりとり

以下の相手に送信しました

















チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



ケムルス(116) は ド根性雑草 を入手!
ミチ(121) は 石英 を入手!
シュエン(902) は 石英 を入手!
マリナ(913) は 雑木 を入手!
ミチ(121) は 美味しい草 を入手!
マリナ(913) は 羽 を入手!
シュエン(902) は 羽 を入手!
シュエン(902) は 剛毛 を入手!
マリナ(913) は 何か柔らかい物体 を入手!
シュエン(902) は 何か柔らかい物体 を入手!
マリナ(913) は 何か柔らかい物体 を入手!



オーク社長(1531) とカードを交換しました!
課長召還 (サモン:ガーゴイル)

クラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
クラッシュ を研究しました!(深度1⇒2)
クラッシュ を研究しました!(深度2⇒3)



特に移動せずその場に留まることにしました。
MISSION - 未発生:
- ケムルス(116) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- ミチ(121) の選択は ヒノデ区 D-9:落書き広場(ベースキャンプ外のため無効)





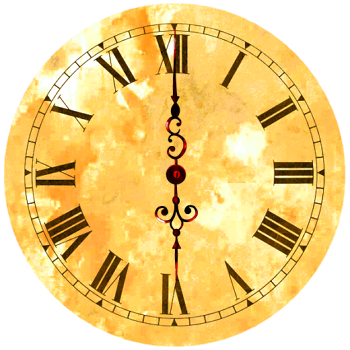
―― ハザマ時間が紡がれる。


ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
声は淡々と、話を続ける。
声はそこで終わる。
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



ヒトが、最初から嫌いだったわけじゃない。
むしろ、ヒトにはちょっとした親近感を抱いていたものだ。
マモノの中の弱者と、怪獣の中の弱者。
似たような存在にシンパシーを抱くのは、怪獣であっても想像に難くない。
彼らは、領地もなくはぐれ怪獣に成り下がっていた小生にとってなにより近しい存在だった。
書物もたくさん読んだ。ヒトの何事も記録に残したがる習性は面白いと思った。
植物や社会に関する本に、特に興味を示したものだ。
ようやく得た領地は厳しい環境だったことから住処の砦を訪れる人間はさほどいなかったが、
かつて歌謡いや行商人が訪れたときには、丁重にもてなした覚えもある。
――そう。とうに、昔の話だ。
シンパシーを感じた者達に心を許した結果が、あの灼け朽ちた砦だ。炎に捲かれた街だ。
蹂躙された、土地と民だ。
ヒトを恨んで、何が悪い。
だが……
*
イバラシティの面影を残した廃墟を歩く。
傾いたビルに、やけに見慣れた人影を見た。
あれは……雲谷千晴?
思わず自分の目を疑った。
おかしい。しかし、あれは間違いなくあのヒトの娘だ。
ここに訪れるイバラシティのヒトは限定されているという。
それも大体、戦力となるヒトが集っているはずだ。
異能を持たない、戦力となり得るはずもない彼女が、いるはずもない。
これは、罠か?いや、誰が罠を仕掛けるというのだ?
……どうせここから当分、脅威は無いだろう。
何より、時間が惜しい。
先に進むセンパイ共をよそに、人影を追いかける。
歪んだ建物を、直角に曲がる。
焦り。確かにそれもある。
それにあれの慰めのひとつである以上、動向を探る必要がある。
……ヒトの言う情、というものも少なからずあるのかもしれない。
だが言ってしまえば、自分が滑稽に思えてしょうがなくなる。
決して口になどするものか、決して。
瓦礫を軽く飛び越えると、住宅地の十字路に差し掛かった。
そこにあったのは、『2つ』の、影。
その影のひとつが自分の姿を認めるや否や、首に何か剣のような、鋭いものを突きつけてくる。
ヘマをした。
煙霧で姿を覆っていたものの、気配に勘付かれては元も子もない。
おまけに寸分違わず喉元に当てにきているときた。
観念して、すっと目の前の霧を晴らす。
その先で蹲る自分を見ていたのは、
熱線のごとく熱く、しかし冷水のように冷ややかに貫く視線。
……妹の、雲谷千晴だ。
* *
夕焼け空が、綺麗だった。
夏も近付いて、昼は随分と長くなった。
そんな日の夕方、電話がかかってきた。
相手はお母さんだった。
自分から受話器を取ったのは、いつぶりだろう?
 |
千晴 「お母さん、久しぶり!」 |
 |
母親 「そんな事より、まだ帰ってくるつもり無いの?」 |
 |
千晴 「もう、お母さんたらせっかちね。 夏休みになったら2人で一緒にお家帰ってくるから」 |
 |
母親 「え、2人?……千晴ったら、もう彼氏作ったの? 呼ぶのはいいけど、先にどういう人か紹介してよね」 |
 |
千晴 「え、ええ!?違うわよお母さん! 私にはまだ、そんな人いないってば!!」 |
 |
母親 「あら、そうなの?まあいいけど……なるべく早く帰ってきなさい。 お兄ちゃん、千晴が返ってこないと哀しむわよ。 高校生になった千晴を、早く見たいと思ってるんだから──」 |
えっ……?
何を言っているのだろう、お母さんは。
煙兄はここにいるじゃない。
一緒に暮らしているじゃない、いやだわ。
――そんな思考と反して、額からはおびただしい汗が流れていく。
……嫌な予感がする。
 |
千晴 「お母さん? 何を……言っているの……?」 |
 |
母親 「まさか……忘れたなんて、冗談でも止めなさいよ!? 日付を見れば分かるでしょう? もうすぐ、煙次の13回忌──」 |
ごとん。
受話器が零れ落ちた音だけが、千晴1人だけの部屋に鮮明に響き渡った。
一瞬の静寂。
次いで少女の悲痛な絶叫が、アパートの一室に轟いた。
* * *
「チハル……?」
呼び慣れた名だ。
だが、発した一言が自分から出た声には到底思えなかった。
それ以上に驚くべきは、理解が追い付かないような目の前の状況にあった。
霧が晴れると共に、得物を突きつけた相手の顔もよく見えるようになった。
騎士よろしく千晴の前に立ちはだかる人物……その顔を、自分はよく知っていたのだ。
いや、当たり前にも程がある。
だってあれは……イバラシティでの自分なのだから。
全身黒尽くめで、髪型の特徴的な部分こそ消失しているが、間違いない。
どうして自分であるはずの……雲谷煙次が此処にいる?
「……っ、……!」
首元に熱を感じる。
視線を戻せば、いつのまにか突き付けられていたものが、喉に深々と差し込まれている。
気付かなかったのは、痛みはそれほど無かったからだ。
代わりに身体全体が怠さを訴える。強烈な睡魔が襲い掛かってきた。
相変わらず視線を向けていた千晴の瞳が、口元の微笑みと共に煌々と光る。
それと同時に、背後で何かが煌めきを放った。
それは太陽のようで、また違う。
中心部は紅く輝いているものの、そこから発するプロミネンスは黒々として、
妖しい光を見せながら揺らいでいた。
「お兄ちゃんはここにいる。ねえ、そうでしょう。お兄ちゃん」
千晴は、いつの間にか影のような色をした長身の男の背に寄りかかっていた。
その問いに、肯定も、否定も出来ない。
ただ何か、どうしようもない違和感が胸のうちから湧き上がる。
違和感があっても、それを正すことは出来ない。
手は届かない。
指が、空を掴む。
取りこぼしたパイプは遥か遠くの地面にある。
主の加護は、あまりにも遠い。
地面に倒れ伏して、目を、閉じる。
瞼を閉じてしまえば、もう開くことは出来ない。
視界は闇だけになって、声は遠くなる。
やがて自分が何処にいるのかも、分からなくなる。
「……おやすみなさい」
意識が遠のいて行く中で、そんな声を掛けられた気がした。

雲谷 千晴
相楽伊橋高校に通う、高校3年生。
彼女が異能を発現させたのは、3歳の頃だった。
彼女が異能を発現させたのは、3歳の頃だった。



ENo.118 アリヒト とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||||
| |||||||||
ENo.121 ミチ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.167 うさ子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.503 清 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.664 闇のおえかき とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.931 伊舎那 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||||
ENo.1039 夢の残り香 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1132 玲瓏 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
ケムルス 「……?」 |



創峰大選抜・突貫野郎G(enius)チーム
|
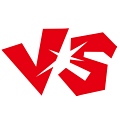 |
ハザマに生きるもの
|



創峰大選抜・突貫野郎G(enius)チーム
|
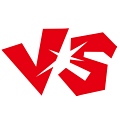 |
DV研究会
|



チナミ区 H-15:釣り堀
創峰大選抜・突貫野郎G(enius)チーム
|
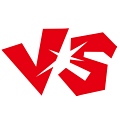 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 H-15:釣り堀
 |
マイケル 「上出来ですね。それでは、どうぞどうぞ。」 |
チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



ケムルス(116) は ド根性雑草 を入手!
ミチ(121) は 石英 を入手!
シュエン(902) は 石英 を入手!
マリナ(913) は 雑木 を入手!
ミチ(121) は 美味しい草 を入手!
マリナ(913) は 羽 を入手!
シュエン(902) は 羽 を入手!
シュエン(902) は 剛毛 を入手!
マリナ(913) は 何か柔らかい物体 を入手!
シュエン(902) は 何か柔らかい物体 を入手!
マリナ(913) は 何か柔らかい物体 を入手!



オーク社長(1531) とカードを交換しました!
課長召還 (サモン:ガーゴイル)

クラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)
クラッシュ を研究しました!(深度1⇒2)
クラッシュ を研究しました!(深度2⇒3)



特に移動せずその場に留まることにしました。
MISSION - 未発生:
- ケムルス(116) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- ミチ(121) の選択は ヒノデ区 D-9:落書き広場(ベースキャンプ外のため無効)





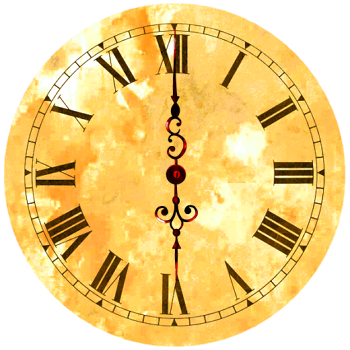
―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「……時計台に呼ばれてしまいましたが、はてさて。」 |
 |
エディアン 「なーんか、嫌な予感がします。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
 |
エディアン 「ほら……ほらぁ……。」 |
 |
榊 「どういうことでしょうねぇ。」 |
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝してます。」 |
 |
エディアン 「……ワールドスワップの能力者さんですよね。 機会を与えてくれて、感謝していますよ?」 |
 |
榊 「お姿は拝めないんですかねぇ。私は興味津々桃色片想いなのですが。」 |
声は淡々と、話を続ける。
 |
声 「どうやらこのワールドスワップ、時計の進みが狂っているようです。 特殊な因子を含めてしまった為と能力が訴えます。その因子が――」 |
 |
声 「――榊さん、貴方のようですね。何か、心当たりは?」 |
 |
榊 「大いにございます!特殊な世界の住人ゆえ、私は今や特異な存在なのでしょう。 妻に『貴方は変人』とよく言われていましたが、そういうことでしたか!納得ですッ」 |
 |
榊 「では、役目を果たすのは難しいということでよろしいですか?」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
榊 「……? ……どうしました?」 |
 |
声 「……仕切り直し、世界線を変更する、と能力が言ってきます。 貴方が案内役にならない世界線。イバラシティも、アンジニティも、新たなものになる……と。」 |
 |
エディアン 「……そ、そんなことまでできてしまう能力? ワールドスワップという名の範疇を超えてません?」 |
 |
榊 「世界線を別のものと交換する……と考えるなら、ギリギリ……ですかね。 というか、スワップから外れた現象は既に起こっていますが。」 |
 |
声 「これは能力ではなく、……呪い。呪いという言葉が合う。 今まで勝手に発動した数度、自分への利はない。制御下にない、把握できない、呪い。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「ハザマへの次の転送時間に、ハザマに転送される代わりに、世界線が変更される。 そして、案内役も、転送対象も、変わる。」 |
 |
声 「変わるものは、多いだろう。しかし変わらぬものも、あるだろう。」 |
 |
エディアン 「別の世界線、ですものね。 ……どうせなら私がアンジニティにいない世界線がいいんですけど。」 |
 |
榊 「……なるほど、奇妙な枝の正体は世界線操作者でしたかッ! 少なくとも私が案内役となれない世界線になるのですね、残念です。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「連絡は終わり。さようなら。」 |
声はそこで終わる。
 |
榊 「さて…… とても短い間ではありましたが、 エディアンさん、皆様、お付き合いありがとうございました!」 |
 |
エディアン 「お別れですか。悪人顔っぽくて敵視しやすい相手だったんですけどねー。」 |
 |
榊 「こんな素敵な笑顔を悪人顔呼ばわりとは、失礼な娘さんです。 なるほどアンジニティにいらっしゃるわけですねぇ。」 |
 |
エディアン 「……うるっさいですね。事情は人それぞれあるんですよ、色々!」 |
 |
榊 「……それでは、」 |
 |
エディアン 「……それでは、」 |
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
 |
榊 「お疲れ様でした。」 |
 |
エディアン 「お疲れ様でしたー!」 |

ENo.116
雲谷 煙次/ケムルス



---怪獣は平和ビトの夢を見るか?---
◯雲谷 煙次(くもや えんじ)/イバラサイド
創峰大学の学生、20歳。所属は第一学部社会学主専攻。
身長188cmの長身の男。
ヘビースモーカーであり、大学の煙探知機を鳴らしてはよく怒られている。しかしそんな注意も意に介さないのか、だいぶ自由気ままにキャンパスライフを過ごしているようだ。
成績は中の上下を行ったり来たりするレベル。
人の多い場所を好むのか、よく人混みの中にいることが多い。
現在は雲林園荘の201号室で、千晴という高校生の妹と一緒に暮らしている。
後ろ髪の寝癖が直らないことが悩み。
バイトは最近見つかった。
異能:煙の主【ロード・スモーカー】
煙を発するもの(タバコなど)を口にくわえている間、発した煙を意のままに操る異能。自由に動かすのみならず、色や匂いといった性質を”ひとつだけ”変えることも可能。
一応自ら発したもの以外も操れるが、制御がかなり難しいらしい。
〈よくいる場所〉
・創峰大学 ・雲林園荘 ・トラマルマート@御子柴ビルヂング
その他、ツクナミ区のいろいろな場所(の予定)
* * *
●ケムルス/ハザマサイド
煙公爵ケムルス。
元の世界より追放され、アンジニティに流れ着いてきた怪獣。雲谷 煙次の本来の姿。
普段の身長は125cm程度と小学生並み。(巨大化もできるとは本人談)
かつていた世界の創造主・至天より授かったパイプ『栄滅のブライアー』を用いて、煙を自在に操る。
その煙は、周囲の空間すら制圧し、あらゆるものを支配するほどの力を持つという。
追放された経緯から人間があまり好きではないが、とある事情からイバラシティの側につくこととなった。
* * *
・雲谷 千晴(サブ)
相良伊橋高校、1-5の生徒。16歳。
煙次のことを『煙兄』と呼ぶ。
◯雲谷 煙次(くもや えんじ)/イバラサイド
創峰大学の学生、20歳。所属は第一学部社会学主専攻。
身長188cmの長身の男。
ヘビースモーカーであり、大学の煙探知機を鳴らしてはよく怒られている。しかしそんな注意も意に介さないのか、だいぶ自由気ままにキャンパスライフを過ごしているようだ。
成績は中の上下を行ったり来たりするレベル。
人の多い場所を好むのか、よく人混みの中にいることが多い。
現在は雲林園荘の201号室で、千晴という高校生の妹と一緒に暮らしている。
後ろ髪の寝癖が直らないことが悩み。
バイトは最近見つかった。
異能:煙の主【ロード・スモーカー】
煙を発するもの(タバコなど)を口にくわえている間、発した煙を意のままに操る異能。自由に動かすのみならず、色や匂いといった性質を”ひとつだけ”変えることも可能。
一応自ら発したもの以外も操れるが、制御がかなり難しいらしい。
〈よくいる場所〉
・創峰大学 ・雲林園荘 ・トラマルマート@御子柴ビルヂング
その他、ツクナミ区のいろいろな場所(の予定)
* * *
●ケムルス/ハザマサイド
煙公爵ケムルス。
元の世界より追放され、アンジニティに流れ着いてきた怪獣。雲谷 煙次の本来の姿。
普段の身長は125cm程度と小学生並み。(巨大化もできるとは本人談)
かつていた世界の創造主・至天より授かったパイプ『栄滅のブライアー』を用いて、煙を自在に操る。
その煙は、周囲の空間すら制圧し、あらゆるものを支配するほどの力を持つという。
追放された経緯から人間があまり好きではないが、とある事情からイバラシティの側につくこととなった。
* * *
・雲谷 千晴(サブ)
相良伊橋高校、1-5の生徒。16歳。
煙次のことを『煙兄』と呼ぶ。
6 / 30
384 PS
チナミ区
H-15
H-15



































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 封熱のキャラバッシュ | 武器 | 33 | 器用10 | 混乱10 | - | 【射程3】 |
| 2 | どうでもよさげな物体 | 素材 | 10 | [武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2) | |||
| 3 | カソレザージャケット | 防具 | 42 | 加速10 | - | - | |
| 4 | 金の飾りボタン | 装飾 | 33 | 器用10 | 火纏10 | - | |
| 5 | 黒臙脂の外套 | 防具 | 33 | 敏捷10 | 道連10 | - | |
| 6 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV20)[防具]体力10(LV5)[装飾]防御10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) | |||
| 9 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 10 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 11 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 12 | 泡煙のミアシャム | 武器 | 39 | 炎上10 | - | - | 【射程3】 |
| 13 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]火纏10(LV25)[防具]鎮痛10(LV15)[装飾]復活10(LV15) | |||
| 14 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV20)[防具]体力10(LV5)[装飾]防御10(LV15) | |||
| 15 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]火纏10(LV25)[防具]鎮痛10(LV15)[装飾]復活10(LV15) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 制約 | 2 | 拘束/罠/リスク |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 装飾 | 32 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻勢『アンバサドリス』 (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 直情『ダビドフ』 (ピンポイント) | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 反芻『プリメロス』 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 拡散『アニベルサリオ』 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| 快方『ルスティカ』 (ヒール) | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 火煙『オレンジドリーム』 (ティンダー) | 6 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| シャイン | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 | |
| 虚脱『テイクユアタイム』 (リストリクト) | 6 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増 | |
| セイクリッドファイア | 5 | 0 | 80 | 敵:火撃&光撃 | |
| 妖炎『ファイヤーダンス』 (ファイアダンス) | 6 | 0 | 80 | 敵:2連火撃&炎上、領域値[火]3以上なら、更に火撃&炎上 | |
| マジックポーション | 5 | 0 | 60 | 自:祝福 | |
| ハルシネイト | 5 | 0 | 90 | 敵列:光撃&混乱 | |
| 痺煙『スタンウェル』 (パラライズ) | 5 | 0 | 60 | 敵:麻痺 | |
| 熱撃『バルカンディライト』 (ファイアボール) | 6 | 0 | 180 | 敵全:火撃 | |
| 縛煙『カスク No.1』 (キャプチャー) | 5 | 0 | 70 | 自:束縛LV増 | |
| 腐宴『オルスボブラック』 (コロージョン) | 5 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 | |
| 幻煙『イングリッシュサマー』 (ミラージュ) | 5 | 0 | 140 | 味列:守護 | |
| 雲隠『ハイドパーク』 (ボムトラップ) | 6 | 0 | 150 | 敵列:罠《爆弾》LV増 ※【自分行動前】自:領域値[火]3以上[水]2以下なら、火撃(1回のみ) | |
| 煙硝『ガスライト』 (オイルファイア) | 5 | 0 | 100 | 敵:攻撃&炎上状態なら火撃(対象の領域値[火]が高いほど威力増)) | |
| 痺煙『ゴールドラッシュ』 (スタンスモーク) | 5 | 0 | 60 | 敵列:麻痺 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 煙炎天にみなぎりて (器用) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 水疾走る煙 (敏捷) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 煙霞の痼疾 (回復) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 煙硝火 (体力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 煙火中の人 (幸運) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 光特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:光属性スキルのHP増効果に光特性が影響 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
星条旗よ永遠なれ (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
繧ュ繝・繧「繝?ぅ繧ク繝シ繧コ (キュアディジーズ) |
0 | 70 | 味肉2:HP増&肉体変調減 | |
|
やる気が出なかったごめんね☆ (クリエイト:ウェポン) |
0 | 60 | 味:追撃LV・次与ダメ増 | |
|
パワーアシスト (ストレングス) |
0 | 100 | 自:AT増 | |
|
バーストオフ (ウィンドリング) |
0 | 80 | 味全:AG増(2T) | |
|
課長召還 (サモン:ガーゴイル) |
0 | 400 | 自:ガーゴイル召喚 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]アクアヒール | [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]クラッシュ |
| [ 3 ]バトルソング | [ 3 ]チャージ |

PL / アサツキ(@runa1134)