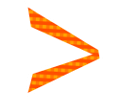<< 1:00>> 3:00




アンジニティは、世界の掃き溜め。
様々な世界からの『否定され追放された者』が
棄てられる世界。
環境は悪く安息の地も無く、
内から外への道は完全に閉ざされている。
──私も、その1人だ。
汚泥に塗れ、踏み躙られる毎日を過ごす中で
あの日の▇▇の悲しそうな瞳を何度思い出しただろう。
▇▇は、私がこうなることを知っていたのだろうか?
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「私の人生は失敗だった」
練習に耐えきれず泣きじゃくっていたあの日、
『先生』は僕にそう語りかけた。
「だからといってやり直すことはできなかった。
人生とはそういうもの。失敗したらおしまい。
そして、それに気づいたときは手遅れなのよ」
無感情な声ばかりを聞いていたおかげだろうか。
その声はひどく印象に残った。
もっとも、まだ僕は幼かったから
そこにどんな感情が込められていたのか──
それを理解するのは少し難しかった。
いや、きっと今聞いたとしても
完全に理解することはできないのだろう。
だってそれは『先生』が生きてきた時間
全てを費やして得た答えだったから。
「それでも私は諦めない。諦めるつもりはない。
だから貴方を産んだの。分かる?
貴方が私の『人生』をやり直すの」
理解できた、といえば嘘になる。
でも、あの日初めて『先生』が僕のことを
真正面から見てくれたような気がした。
それでよかった。それだけでよかった。
僕は泣くのをやめて頷いた。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
眼下に広がる灯を見て、▇▇は何を思ったのだろう。
「あれが『文明』の灯だ。
地上にできた新しい星々。夜を照らすもの。
ほら、見てごらん。星空そっくりだろう」
▇▇は嬉しそうで、また寂しそうでもあった。
私は不満げにそれを見下ろす。
「どうしてヒトは星空を見なくなったの?
あんなものが無くても私たちがいるのに」
私の問いに▇▇は笑って答えた。
「いいかい、本来夜は恐れるべきものだ。
ヒトはそれを克服しようとする生き物だった。
そうして今ようやくそれに手が届こうとしている。
彼らにとって、もう▇▇たちは必要ないのさ」
それは私にとって衝撃的なことだった。
ずっと寄り添ってきた彼らは、
私たちのことをもう必要としていないという。
否、それだけならまだ受け入れられたろう。
必要であろうとそうでなかろうと、
友であり、隣人であり続けられるのであれば
それで十分だったのに。
──彼らは、私たちのことを忘れ始めたのだ。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
『音楽家』として見ると、『先生』は
この上なく優秀な人物だった。
しかしそれは『有名』であることと
イコールではない。
音楽についての知識、技能を身につけるにつれて
『先生』がどれだけの努力を重ねてきたのか、
少しだけ理解できるようになった。
それでも世間から認められなかったというのだから、
社会というものは余程厳しいようだ、と
幼いながらに感じたのを覚えている。
結局のところ『先生』が何を求めていたのか。
僕はわからないままに練習を続けていた。
理想とする音楽の極致があったのかもしれないし、
富や名声が欲しかったのかもしれない。
もっと単純に──皆に認めてもらいたかったのかも。
いずれにせよ、僕はそういった目標を持たなかった。
ただ『先生』の言う通りに練習を続けていれば
少なくとも見放されることはないと分かっていた。
僕にとって生きる理由はそれだけだったし、
それで十分満足できていたのだと思う。
『自分の人生』なんていうものは最初からなくて、
僕が歩んでいるのは『先生』の『二周目の人生』だった。
周囲の皆はそんな僕を見て何を思っていたのだろう。
馬鹿な奴だと笑っていただろうか。
どちらにしても、そんなことは気にならなかった。
僕はただ『先生』に見捨てられないのであれば
他のことなんてどうでもよかった。
──もしかすると『音楽』さえも。



ENo.46 常盤朱火&常盤郁子 とのやりとり

ENo.60 安里杏莉 とのやりとり

ENo.145 クラリッサ とのやりとり

ENo.940 小佐間 御津舟 とのやりとり













なずみ(68) は パンの耳 を入手!
せら(83) は パンの耳 を入手!
すてら(130) は パンの耳 を入手!
ロワ(842) は 美味しくない草 を入手!
なずみ(68) は 毛 を入手!
ロワ(842) は 不思議な石 を入手!
すてら(130) は 毛 を入手!
なずみ(68) は ねばねば を入手!



響鳴LV を 3 UP!(LV10⇒13、-3CP)
付加LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ロワ(842) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『カルディナール・シュニッテン』をつくってもらいました!
⇒ カルディナール・シュニッテン/料理:強さ25/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
ネア(715) とカードを交換しました!
深海の光 (ブレス)


ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
ウィルスゾーン を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 H-7(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 G-7(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
そう言ってフロントダブルバイセップス。
賞品について何だか盛り上がっているふたり。
チャットが閉じられる――


















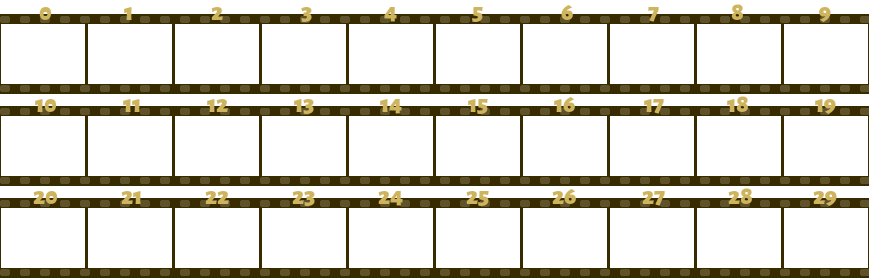





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



アンジニティは、世界の掃き溜め。
様々な世界からの『否定され追放された者』が
棄てられる世界。
環境は悪く安息の地も無く、
内から外への道は完全に閉ざされている。
──私も、その1人だ。
汚泥に塗れ、踏み躙られる毎日を過ごす中で
あの日の▇▇の悲しそうな瞳を何度思い出しただろう。
▇▇は、私がこうなることを知っていたのだろうか?
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「私の人生は失敗だった」
練習に耐えきれず泣きじゃくっていたあの日、
『先生』は僕にそう語りかけた。
「だからといってやり直すことはできなかった。
人生とはそういうもの。失敗したらおしまい。
そして、それに気づいたときは手遅れなのよ」
無感情な声ばかりを聞いていたおかげだろうか。
その声はひどく印象に残った。
もっとも、まだ僕は幼かったから
そこにどんな感情が込められていたのか──
それを理解するのは少し難しかった。
いや、きっと今聞いたとしても
完全に理解することはできないのだろう。
だってそれは『先生』が生きてきた時間
全てを費やして得た答えだったから。
「それでも私は諦めない。諦めるつもりはない。
だから貴方を産んだの。分かる?
貴方が私の『人生』をやり直すの」
理解できた、といえば嘘になる。
でも、あの日初めて『先生』が僕のことを
真正面から見てくれたような気がした。
それでよかった。それだけでよかった。
僕は泣くのをやめて頷いた。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
眼下に広がる灯を見て、▇▇は何を思ったのだろう。
「あれが『文明』の灯だ。
地上にできた新しい星々。夜を照らすもの。
ほら、見てごらん。星空そっくりだろう」
▇▇は嬉しそうで、また寂しそうでもあった。
私は不満げにそれを見下ろす。
「どうしてヒトは星空を見なくなったの?
あんなものが無くても私たちがいるのに」
私の問いに▇▇は笑って答えた。
「いいかい、本来夜は恐れるべきものだ。
ヒトはそれを克服しようとする生き物だった。
そうして今ようやくそれに手が届こうとしている。
彼らにとって、もう▇▇たちは必要ないのさ」
それは私にとって衝撃的なことだった。
ずっと寄り添ってきた彼らは、
私たちのことをもう必要としていないという。
否、それだけならまだ受け入れられたろう。
必要であろうとそうでなかろうと、
友であり、隣人であり続けられるのであれば
それで十分だったのに。
──彼らは、私たちのことを忘れ始めたのだ。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
『音楽家』として見ると、『先生』は
この上なく優秀な人物だった。
しかしそれは『有名』であることと
イコールではない。
音楽についての知識、技能を身につけるにつれて
『先生』がどれだけの努力を重ねてきたのか、
少しだけ理解できるようになった。
それでも世間から認められなかったというのだから、
社会というものは余程厳しいようだ、と
幼いながらに感じたのを覚えている。
結局のところ『先生』が何を求めていたのか。
僕はわからないままに練習を続けていた。
理想とする音楽の極致があったのかもしれないし、
富や名声が欲しかったのかもしれない。
もっと単純に──皆に認めてもらいたかったのかも。
いずれにせよ、僕はそういった目標を持たなかった。
ただ『先生』の言う通りに練習を続けていれば
少なくとも見放されることはないと分かっていた。
僕にとって生きる理由はそれだけだったし、
それで十分満足できていたのだと思う。
『自分の人生』なんていうものは最初からなくて、
僕が歩んでいるのは『先生』の『二周目の人生』だった。
周囲の皆はそんな僕を見て何を思っていたのだろう。
馬鹿な奴だと笑っていただろうか。
どちらにしても、そんなことは気にならなかった。
僕はただ『先生』に見捨てられないのであれば
他のことなんてどうでもよかった。
──もしかすると『音楽』さえも。



ENo.46 常盤朱火&常盤郁子 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.60 安里杏莉 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.145 クラリッサ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.940 小佐間 御津舟 とのやりとり
| ▲ |
| ||||



| せら 「仲間ができて心強いよ。この素敵な町を手に入れるため・・・頑張ろうね!」 |
| 『……。』 |
 |
ラ―トゲルダ 「精々頑張ってもらいたいものね・・・ ねぇ、同盟者?」 |





荊-Crown
|
 |
ちっちゃいもの倶楽部with引率者
|



なずみ(68) は パンの耳 を入手!
せら(83) は パンの耳 を入手!
すてら(130) は パンの耳 を入手!
ロワ(842) は 美味しくない草 を入手!
なずみ(68) は 毛 を入手!
ロワ(842) は 不思議な石 を入手!
すてら(130) は 毛 を入手!
なずみ(68) は ねばねば を入手!



響鳴LV を 3 UP!(LV10⇒13、-3CP)
付加LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ロワ(842) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『カルディナール・シュニッテン』をつくってもらいました!
⇒ カルディナール・シュニッテン/料理:強さ25/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
 |
ラ―トゲルダ 「受け取りなさい、同盟者。」 |
ネア(715) とカードを交換しました!
深海の光 (ブレス)


ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
ウィルスゾーン を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 I-7(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 H-7(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 G-7(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「わぁぁ!!なんですなんですぅ!!!?」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「告知?なんでしょう??」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「ハチャメチャトーナメントバトル!楽しそうですねぇ!!」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
エディアン 「そうですよねぇ。息抜きって大事だと思います。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!豪華賞品も考えてるんですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「賞品はあると燃えますね!豪華賞品・・・・・ホールケーキとか。」 |
 |
ノウレット 「ホールケーキ!!1人1個用意しちゃいますっ!!?」 |
 |
エディアン 「夢のようですね!食べきれるか怪しいですけど。」 |
賞品について何だか盛り上がっているふたり。
 |
ノウレット 「・・・・・あ!でも開催はすぐじゃなくてまだ先なんです!! 賞品の準備とかもありますしぃー!!」 |
 |
エディアン 「わかりました、楽しみにしていますね。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
チャットが閉じられる――







chimeRa
|
 |
ハイパー廃ビルおねぇちゃんと妹たち
|


ENo.130
星空 帳



「──次のニュ …ース…す。本…未明、
歌手……空…さ……亡く…り…した。
遺体…外傷………無く、警察…自殺………
捜査を──」
◼︎星空 帳(ホシゾラ トバリ)
年齢:13歳
身長:137cm
体重:秘密
一人称:僕(人前では私)
二人称:貴方
好きなもの:甘いコーヒー 金平糖 音楽
苦手なもの:激辛料理(でも食べる) リア充 強い光 うさぎ
《イバラシティ》
黒い癖毛を2つに括った女の子。
路上ライブで日銭を稼ぐネットカフェ難民。
名目上はとある男子高校生(Eno.940)の
借りている部屋に住んでいることになっている。
曲は自作らしく、しばしば動画投稿サイトに
音楽をアップロードしたり、SNSで宣伝している。
収入は前述の路上ライブと、創作者支援サイトからの投げ銭。
識字障害を持ち、文字の読み書きができない。
母親の名前は『星空 光』。生前は有名な歌手だった(既知可)。
SNS『とがったー』でのHNは『すてら』(@stella_P)。
音声案内、音声入力がないとSNSも使えない。
《アンジニティ》
彼女は『夜空』であり『星空』であった。
暗闇を照らし、眠りと安らぎを与えてくれた。
けれど『科学』によってその神秘を剥ぎ取られ、
星はただの天体に成り下がり、
夜の闇は人工の光で駆逐された。
だから、もう一度人々は思い出さなければならない。
夜の闇の恐怖と、眠りの安らぎを。
そして──星と共に笑い合うことを。
アンジニティでは誰か(Eno.143)の手によって
長期間に渡り監禁されていたらしい。
その際されたことについては固く口を閉ざしている。
◼︎異能
*ステラの魔法(ストラテリウム)*
星空の光を集めて、小さな光球を生成する。
彼女はこれを『ステラ』と呼び、
ステラは多少の願い事を叶える力を持つ。
ただしステラは強い光を浴びると消えてしまう。
特に人工の光に弱い。
*夜空の唄(ノクターナ)*
彼女の歌は、暗闇に対する原初の感情を呼び起こす。
暗闇の中で彼女の歌を聴いた者の心に『恐怖』
または『安息』の感情を齎す。
辺りが暗いほど効果は高まり、場合によっては
精神の不調に陥ったり、眠りから覚めなくなったりする。
◼︎投稿動画
・星空ワルツ
処女作。軽快なリズムのキラキラした曲。
じわじわ再生数が伸びている。
・夜に抱かれて
2作目。ゆったりしたバラード。
優しい歌詞かと思ったら実はダーク。
・スターホワイト
3作目。寂しげなテクノポップス。
クリスマスと届かない恋の歌。
・サクラミチ
4作目。ハイテンポな和風ロック。
速度の割に歌詞が多く、歌おうとするとかなり辛い。
・青色ステージ
5作目。淡々としたリズムのバラード。
思い悩む気持ちを抱えたまま歩む女の子の歌。
◼︎サブキャラクター
・Lore・A=Ruca(ロア・ア=ルカ)
創峰大学付属病院に入院している女の子。
非常に小柄で、柔らかく白い髪と肌が特徴的。
病状は思わしくなく、先は長くないと宣告されている。
何故か病院の外で目撃されることがあるらしい。
・Knell(ネル)
荊街総合図書館の受付嬢兼司書。
ファミリーネームは不明。
来館者への応対は機械的だが勤務態度は真面目。
かなりの量の業務を回しており、お疲れ気味。
休日はロアの病室に足を運んでいる。
歌手……空…さ……亡く…り…した。
遺体…外傷………無く、警察…自殺………
捜査を──」
◼︎星空 帳(ホシゾラ トバリ)
年齢:13歳
身長:137cm
体重:秘密
一人称:僕(人前では私)
二人称:貴方
好きなもの:甘いコーヒー 金平糖 音楽
苦手なもの:激辛料理(でも食べる) リア充 強い光 うさぎ
《イバラシティ》
黒い癖毛を2つに括った女の子。
路上ライブで日銭を稼ぐネットカフェ難民。
名目上はとある男子高校生(Eno.940)の
借りている部屋に住んでいることになっている。
曲は自作らしく、しばしば動画投稿サイトに
音楽をアップロードしたり、SNSで宣伝している。
収入は前述の路上ライブと、創作者支援サイトからの投げ銭。
識字障害を持ち、文字の読み書きができない。
母親の名前は『星空 光』。生前は有名な歌手だった(既知可)。
SNS『とがったー』でのHNは『すてら』(@stella_P)。
音声案内、音声入力がないとSNSも使えない。
《アンジニティ》
彼女は『夜空』であり『星空』であった。
暗闇を照らし、眠りと安らぎを与えてくれた。
けれど『科学』によってその神秘を剥ぎ取られ、
星はただの天体に成り下がり、
夜の闇は人工の光で駆逐された。
だから、もう一度人々は思い出さなければならない。
夜の闇の恐怖と、眠りの安らぎを。
そして──星と共に笑い合うことを。
アンジニティでは誰か(Eno.143)の手によって
長期間に渡り監禁されていたらしい。
その際されたことについては固く口を閉ざしている。
◼︎異能
*ステラの魔法(ストラテリウム)*
星空の光を集めて、小さな光球を生成する。
彼女はこれを『ステラ』と呼び、
ステラは多少の願い事を叶える力を持つ。
ただしステラは強い光を浴びると消えてしまう。
特に人工の光に弱い。
*夜空の唄(ノクターナ)*
彼女の歌は、暗闇に対する原初の感情を呼び起こす。
暗闇の中で彼女の歌を聴いた者の心に『恐怖』
または『安息』の感情を齎す。
辺りが暗いほど効果は高まり、場合によっては
精神の不調に陥ったり、眠りから覚めなくなったりする。
◼︎投稿動画
・星空ワルツ
処女作。軽快なリズムのキラキラした曲。
じわじわ再生数が伸びている。
・夜に抱かれて
2作目。ゆったりしたバラード。
優しい歌詞かと思ったら実はダーク。
・スターホワイト
3作目。寂しげなテクノポップス。
クリスマスと届かない恋の歌。
・サクラミチ
4作目。ハイテンポな和風ロック。
速度の割に歌詞が多く、歌おうとするとかなり辛い。
・青色ステージ
5作目。淡々としたリズムのバラード。
思い悩む気持ちを抱えたまま歩む女の子の歌。
◼︎サブキャラクター
・Lore・A=Ruca(ロア・ア=ルカ)
創峰大学付属病院に入院している女の子。
非常に小柄で、柔らかく白い髪と肌が特徴的。
病状は思わしくなく、先は長くないと宣告されている。
何故か病院の外で目撃されることがあるらしい。
・Knell(ネル)
荊街総合図書館の受付嬢兼司書。
ファミリーネームは不明。
来館者への応対は機械的だが勤務態度は真面目。
かなりの量の業務を回しており、お疲れ気味。
休日はロアの病室に足を運んでいる。
20 / 30
70 PS
チナミ区
F-8
F-8





| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | カルディナール・シュニッテン | 料理 | 25 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 響鳴 | 13 | 歌唱/音楽/振動 |
| 付加 | 23 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| シャイン | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| ブリランテ | 5 | 0 | 140 | 自:光特性・魅了LV増 | |
| バトルソング | 5 | 0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) | |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 140 | 味全:強制混乱+次与ダメ増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 光特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:光属性スキルのHP増効果に光特性が影響 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]ウィルスゾーン |

PL / すずらん