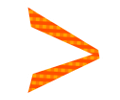<< 2:00>> 4:00




『侵略』。
そんな言葉を聞いたのはいつだったか。
そんな言葉を言い始めたのは誰だったか。
私には『侵略』なんてどうでも良くて、
ただこの狂った世界から逃げ出せる可能性があるなら
それに縋りたいと考えていただけだ。
ただ、幸いと言うべきなのか。
『侵略』というひとつの到達点を与えられた
この世界の住民たちは、目的こそバラバラでも
なんとなく方向性を持ってまとまり始めた。
そこで、私はようやく考える余裕を得ることができた。
私は何がしたかったのだろう。
私は何を求めていたのだろう。
覚えているのは、ひとつだけ。
あの日の願いを。あの日の誓いを。
もう一度彼らの隣に寄り添うために。
私は、文明の灯を消そう。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
少なくとも、僕は『才能』に恵まれていたわけではない。
だからこそ、それを埋めるための『努力』が必要で。
『努力』の過程で躓くのは当たり前のことだった。
ただ、その『当たり前』がどうも『先生』には
我慢ならないことだったらしい。
腹を殴られ、背中を焼かれる日々は苦しかったけれど、
『先生』はきっと僕よりも苦しんでいたのだと思う。
夜中、トイレで泣きながら吐いている『先生』を見て、
僕に何かできることはないか、と何度も考えた。
もちろん、出来ることなんてひとつしかない。
『先生』の理想の音を奏でさえすれば良いんだ。
たったそれだけのことなのに。
それがこんなにも難しいなんて。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
文明の灯に照らされて、星はその光を掻き消され、
その名前を忘れられて消えていった。
ひとつ、またひとつと同胞が消える度、
私は『忘れないで』と叫んでは泣いた。
でも、もう私の声は届かない。
「どうしてこんなひどいことをするの?」
耐えきれなくなって私は▇▇に詰め寄った。
▇▇は、ただ悲しそうに笑うだけだった。
「『神秘』の終わりは得てしてそういうものだ。
▇▇たちが辿るのは大いなる道のひとつに過ぎないんだ」
私には理解出来なかった。
どうすれば私たちは消えずに済む?
どうすればまた彼らに寄り添える?
ああ、簡単なことじゃないか。
それが私たちを否定するのなら。
私は、文明の灯を消そう。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
別に、辛いことばかりして生きてきたわけじゃない。
僕にだって楽しみな時間はあった。
星空の下で待ち合わせるその時間。
僕はそれが楽しみで1日を頑張れる。
目を閉じて、耳を澄ませる。
舗装された道路を駆ける音、弾んだ息遣い。
ほら、彼女の足音が聞こえてきた。
「──ごめん、遅くなった!結構待った?」
「うん、ちょっとだけね?」
帽子の下から溢れる長い髪。
きらきらと輝く瞳は宝石のようだ。
『先生』が寝静まった真夜中の自由時間。
僕たちはこうしてこっそり集まっていた。
「今日はね、お菓子を持ってきたんだ」
弾けるような笑顔を見せる彼女の名前は▇▇▇。
僕の、たったひとりの友人だ。



ENo.676 小野瀬百葉 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 カルディナール・シュニッテン を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










なずみ(68) は 韮 を入手!
せら(83) は 花びら を入手!
すてら(130) は 韮 を入手!
ラ―トゲルダ(842) は 花びら を入手!
ラ―トゲルダ(842) は 毛 を入手!
すてら(130) は 毛 を入手!
せら(83) は 毛 を入手!
なずみ(68) は 美味しい果実 を入手!



響鳴LV を 3 UP!(LV13⇒16、-3CP)
付加LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
なずみ(68) により ItemNo.9 ねばねば から射程3の武器『とばりさんねばねば』を作製してもらいました!
⇒ とばりさんねばねば/武器:強さ34/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
なずみ(68) の持つ ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.5 何か柔らかい物体 を付加しました!
ラ―トゲルダ(842) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『マラコフトルテ』をつくってもらいました!
⇒ マラコフトルテ/料理:強さ36/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
イタズ(35) とカードを交換しました!
薬草 (ヒールハーブ)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
クレイジーチューン を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 D-8(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 D-9(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 D-11(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
Cross+Rose内が梅の花に囲まれた景色となる。

エディアンが香りの元へと振り向くと――

満開の梅のなか、小さな屋台を構え、窮屈そうにベビーカステラを焼く大きな鬼がいる。
鬼の口へと放り込まれる。
口をもぐもぐさせながら、無愛想に返事をする。
屋台の前ではしゃぐエディアン。
チャットが閉じられる――


















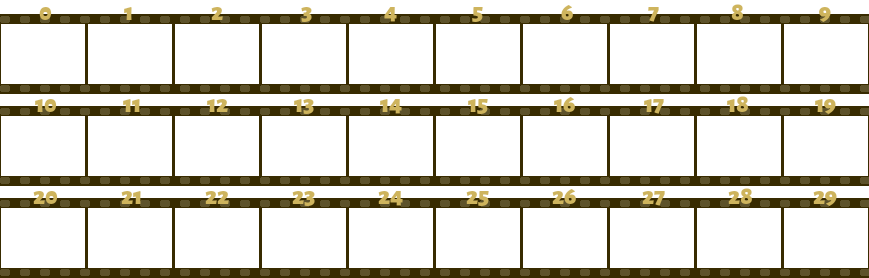





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



『侵略』。
そんな言葉を聞いたのはいつだったか。
そんな言葉を言い始めたのは誰だったか。
私には『侵略』なんてどうでも良くて、
ただこの狂った世界から逃げ出せる可能性があるなら
それに縋りたいと考えていただけだ。
ただ、幸いと言うべきなのか。
『侵略』というひとつの到達点を与えられた
この世界の住民たちは、目的こそバラバラでも
なんとなく方向性を持ってまとまり始めた。
そこで、私はようやく考える余裕を得ることができた。
私は何がしたかったのだろう。
私は何を求めていたのだろう。
覚えているのは、ひとつだけ。
あの日の願いを。あの日の誓いを。
もう一度彼らの隣に寄り添うために。
私は、文明の灯を消そう。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
少なくとも、僕は『才能』に恵まれていたわけではない。
だからこそ、それを埋めるための『努力』が必要で。
『努力』の過程で躓くのは当たり前のことだった。
ただ、その『当たり前』がどうも『先生』には
我慢ならないことだったらしい。
腹を殴られ、背中を焼かれる日々は苦しかったけれど、
『先生』はきっと僕よりも苦しんでいたのだと思う。
夜中、トイレで泣きながら吐いている『先生』を見て、
僕に何かできることはないか、と何度も考えた。
もちろん、出来ることなんてひとつしかない。
『先生』の理想の音を奏でさえすれば良いんだ。
たったそれだけのことなのに。
それがこんなにも難しいなんて。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
文明の灯に照らされて、星はその光を掻き消され、
その名前を忘れられて消えていった。
ひとつ、またひとつと同胞が消える度、
私は『忘れないで』と叫んでは泣いた。
でも、もう私の声は届かない。
「どうしてこんなひどいことをするの?」
耐えきれなくなって私は▇▇に詰め寄った。
▇▇は、ただ悲しそうに笑うだけだった。
「『神秘』の終わりは得てしてそういうものだ。
▇▇たちが辿るのは大いなる道のひとつに過ぎないんだ」
私には理解出来なかった。
どうすれば私たちは消えずに済む?
どうすればまた彼らに寄り添える?
ああ、簡単なことじゃないか。
それが私たちを否定するのなら。
私は、文明の灯を消そう。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
別に、辛いことばかりして生きてきたわけじゃない。
僕にだって楽しみな時間はあった。
星空の下で待ち合わせるその時間。
僕はそれが楽しみで1日を頑張れる。
目を閉じて、耳を澄ませる。
舗装された道路を駆ける音、弾んだ息遣い。
ほら、彼女の足音が聞こえてきた。
「──ごめん、遅くなった!結構待った?」
「うん、ちょっとだけね?」
帽子の下から溢れる長い髪。
きらきらと輝く瞳は宝石のようだ。
『先生』が寝静まった真夜中の自由時間。
僕たちはこうしてこっそり集まっていた。
「今日はね、お菓子を持ってきたんだ」
弾けるような笑顔を見せる彼女の名前は▇▇▇。
僕の、たったひとりの友人だ。



ENo.676 小野瀬百葉 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
なずみ 「……行きましょう、か。」 |
 |
ラ―トゲルダ 「どうかしたのかしら?同盟者。 ・・・手を下すのを躊躇っているのなら、私が手を貸してあげましょうか? ・・・一瞬で終わるわ。」 |
ItemNo.6 カルディナール・シュニッテン を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(20⇒21)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!



ハイパー廃ビルおねぇちゃんと妹たち
|
 |
ハザマに生きるもの
|



チームまのもの
|
 |
ハイパー廃ビルおねぇちゃんと妹たち
|



なずみ(68) は 韮 を入手!
せら(83) は 花びら を入手!
すてら(130) は 韮 を入手!
ラ―トゲルダ(842) は 花びら を入手!
ラ―トゲルダ(842) は 毛 を入手!
すてら(130) は 毛 を入手!
せら(83) は 毛 を入手!
なずみ(68) は 美味しい果実 を入手!



響鳴LV を 3 UP!(LV13⇒16、-3CP)
付加LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
なずみ(68) により ItemNo.9 ねばねば から射程3の武器『とばりさんねばねば』を作製してもらいました!
⇒ とばりさんねばねば/武器:強さ34/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
 |
なずみ 「やたらねばねばしてるけど……一応、武器、です。」 |
なずみ(68) の持つ ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.5 何か柔らかい物体 を付加しました!
ラ―トゲルダ(842) により ItemNo.7 不思議な食材 から料理『マラコフトルテ』をつくってもらいました!
⇒ マラコフトルテ/料理:強さ36/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
 |
ラ―トゲルダ 「受け取りなさい、同盟者。」 |
イタズ(35) とカードを交換しました!
薬草 (ヒールハーブ)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
クレイジーチューン を研究しました!(深度0⇒1)



チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 D-8(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 D-9(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 D-11(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
Cross+Rose内が梅の花に囲まれた景色となる。
 |
エディアン 「皆さんこんにちはー!! 私はいま、梅楽園に来ていまーす!」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
エディアン 「・・・・・何か匂いますね。(くんくん・・・) ・・・これは!・・・パンケーキの香りッ」 |
エディアンが香りの元へと振り向くと――

ベニ
二本の角を持つ体格の良い赤い大鬼。怖い顔。
ネジリハチマキを頭に巻き、ボロボロの法被を着ている。
ネジリハチマキを頭に巻き、ボロボロの法被を着ている。
 |
ベニ 「残念、こいつはベビーカステラだ。」 |
満開の梅のなか、小さな屋台を構え、窮屈そうにベビーカステラを焼く大きな鬼がいる。
 |
エディアン 「ベビーカステラ!?私も食べてみ――」 |
 |
ベニ 「残念、品切れだよ。」 |
鬼の口へと放り込まれる。
 |
エディアン 「・・・・・。・・・何なんですか? ただ美味しいものを見せつけたい人ですか?」 |
 |
ベニ 「ああそうさ、羨ましいだろ。」 |
口をもぐもぐさせながら、無愛想に返事をする。
 |
エディアン 「・・・どうしてこんなところでこんなことを?」 |
 |
ベニ 「あー、あんたエディ・・・アン?だったな。俺はベニだ。イバラじゃアカツカという名だった。 あちらの生活がクセになっちまったようで、同じように梅楽園でこれを焼いちまってる。」 |
 |
エディアン 「そうですか・・・ それにしても、よく道具や素材がありましたねぇ。」 |
 |
ベニ 「残骸を根気強く漁ってみろ。イバラシティの物が深く埋もれていたりする。 何故か新鮮な食い物だったりな。アンジニティに比べりゃここハザマすら天国だ。」 |
 |
ベニ 「俺の住処ら辺にも食材が在ったようで、いま仲間に運ばせている。 届いたらどんどん焼いてやる。飢えてっだろ、アンジニティ連中は。」 |
 |
エディアン 「本当ですか!?それは楽しみですっ!! 準備ができたらまたこうして連絡してくださいね!絶対行きますッ!!」 |
屋台の前ではしゃぐエディアン。
 |
ベニ 「・・・あいよ、よろしくよろしく。あー、有料だから金は用意しとけよ。」 |
 |
エディアン 「はい!皆さんもぜひぜひ訪れてみてくださいねぇ!! それでは、また来週・・・じゃなくって―― また1時間後っ!!」 |
チャットが閉じられる――







ちーむまのもの!
|
 |
ハイパー廃ビルおねぇちゃんと妹たち
|


ENo.130
星空 帳



「──次のニュ …ース…す。本…未明、
歌手……空…さ……亡く…り…した。
遺体…外傷………無く、警察…自殺………
捜査を──」
◼︎星空 帳(ホシゾラ トバリ)
年齢:13歳
身長:137cm
体重:秘密
一人称:僕(人前では私)
二人称:貴方
好きなもの:甘いコーヒー 金平糖 音楽
苦手なもの:激辛料理(でも食べる) リア充 強い光 うさぎ
《イバラシティ》
黒い癖毛を2つに括った女の子。
路上ライブで日銭を稼ぐネットカフェ難民。
名目上はとある男子高校生(Eno.940)の
借りている部屋に住んでいることになっている。
曲は自作らしく、しばしば動画投稿サイトに
音楽をアップロードしたり、SNSで宣伝している。
収入は前述の路上ライブと、創作者支援サイトからの投げ銭。
識字障害を持ち、文字の読み書きができない。
母親の名前は『星空 光』。生前は有名な歌手だった(既知可)。
SNS『とがったー』でのHNは『すてら』(@stella_P)。
音声案内、音声入力がないとSNSも使えない。
《アンジニティ》
彼女は『夜空』であり『星空』であった。
暗闇を照らし、眠りと安らぎを与えてくれた。
けれど『科学』によってその神秘を剥ぎ取られ、
星はただの天体に成り下がり、
夜の闇は人工の光で駆逐された。
だから、もう一度人々は思い出さなければならない。
夜の闇の恐怖と、眠りの安らぎを。
そして──星と共に笑い合うことを。
アンジニティでは誰か(Eno.143)の手によって
長期間に渡り監禁されていたらしい。
その際されたことについては固く口を閉ざしている。
◼︎異能
*ステラの魔法(ストラテリウム)*
星空の光を集めて、小さな光球を生成する。
彼女はこれを『ステラ』と呼び、
ステラは多少の願い事を叶える力を持つ。
ただしステラは強い光を浴びると消えてしまう。
特に人工の光に弱い。
*夜空の唄(ノクターナ)*
彼女の歌は、暗闇に対する原初の感情を呼び起こす。
暗闇の中で彼女の歌を聴いた者の心に『恐怖』
または『安息』の感情を齎す。
辺りが暗いほど効果は高まり、場合によっては
精神の不調に陥ったり、眠りから覚めなくなったりする。
◼︎投稿動画
・星空ワルツ
処女作。軽快なリズムのキラキラした曲。
じわじわ再生数が伸びている。
・夜に抱かれて
2作目。ゆったりしたバラード。
優しい歌詞かと思ったら実はダーク。
・スターホワイト
3作目。寂しげなテクノポップス。
クリスマスと届かない恋の歌。
・サクラミチ
4作目。ハイテンポな和風ロック。
速度の割に歌詞が多く、歌おうとするとかなり辛い。
・青色ステージ
5作目。淡々としたリズムのバラード。
思い悩む気持ちを抱えたまま歩む女の子の歌。
◼︎サブキャラクター
・Lore・A=Ruca(ロア・ア=ルカ)
創峰大学付属病院に入院している女の子。
非常に小柄で、柔らかく白い髪と肌が特徴的。
病状は思わしくなく、先は長くないと宣告されている。
何故か病院の外で目撃されることがあるらしい。
・Knell(ネル)
荊街総合図書館の受付嬢兼司書。
ファミリーネームは不明。
来館者への応対は機械的だが勤務態度は真面目。
かなりの量の業務を回しており、お疲れ気味。
休日はロアの病室に足を運んでいる。
歌手……空…さ……亡く…り…した。
遺体…外傷………無く、警察…自殺………
捜査を──」
◼︎星空 帳(ホシゾラ トバリ)
年齢:13歳
身長:137cm
体重:秘密
一人称:僕(人前では私)
二人称:貴方
好きなもの:甘いコーヒー 金平糖 音楽
苦手なもの:激辛料理(でも食べる) リア充 強い光 うさぎ
《イバラシティ》
黒い癖毛を2つに括った女の子。
路上ライブで日銭を稼ぐネットカフェ難民。
名目上はとある男子高校生(Eno.940)の
借りている部屋に住んでいることになっている。
曲は自作らしく、しばしば動画投稿サイトに
音楽をアップロードしたり、SNSで宣伝している。
収入は前述の路上ライブと、創作者支援サイトからの投げ銭。
識字障害を持ち、文字の読み書きができない。
母親の名前は『星空 光』。生前は有名な歌手だった(既知可)。
SNS『とがったー』でのHNは『すてら』(@stella_P)。
音声案内、音声入力がないとSNSも使えない。
《アンジニティ》
彼女は『夜空』であり『星空』であった。
暗闇を照らし、眠りと安らぎを与えてくれた。
けれど『科学』によってその神秘を剥ぎ取られ、
星はただの天体に成り下がり、
夜の闇は人工の光で駆逐された。
だから、もう一度人々は思い出さなければならない。
夜の闇の恐怖と、眠りの安らぎを。
そして──星と共に笑い合うことを。
アンジニティでは誰か(Eno.143)の手によって
長期間に渡り監禁されていたらしい。
その際されたことについては固く口を閉ざしている。
◼︎異能
*ステラの魔法(ストラテリウム)*
星空の光を集めて、小さな光球を生成する。
彼女はこれを『ステラ』と呼び、
ステラは多少の願い事を叶える力を持つ。
ただしステラは強い光を浴びると消えてしまう。
特に人工の光に弱い。
*夜空の唄(ノクターナ)*
彼女の歌は、暗闇に対する原初の感情を呼び起こす。
暗闇の中で彼女の歌を聴いた者の心に『恐怖』
または『安息』の感情を齎す。
辺りが暗いほど効果は高まり、場合によっては
精神の不調に陥ったり、眠りから覚めなくなったりする。
◼︎投稿動画
・星空ワルツ
処女作。軽快なリズムのキラキラした曲。
じわじわ再生数が伸びている。
・夜に抱かれて
2作目。ゆったりしたバラード。
優しい歌詞かと思ったら実はダーク。
・スターホワイト
3作目。寂しげなテクノポップス。
クリスマスと届かない恋の歌。
・サクラミチ
4作目。ハイテンポな和風ロック。
速度の割に歌詞が多く、歌おうとするとかなり辛い。
・青色ステージ
5作目。淡々としたリズムのバラード。
思い悩む気持ちを抱えたまま歩む女の子の歌。
◼︎サブキャラクター
・Lore・A=Ruca(ロア・ア=ルカ)
創峰大学付属病院に入院している女の子。
非常に小柄で、柔らかく白い髪と肌が特徴的。
病状は思わしくなく、先は長くないと宣告されている。
何故か病院の外で目撃されることがあるらしい。
・Knell(ネル)
荊街総合図書館の受付嬢兼司書。
ファミリーネームは不明。
来館者への応対は機械的だが勤務態度は真面目。
かなりの量の業務を回しており、お疲れ気味。
休日はロアの病室に足を運んでいる。
16 / 30
109 PS
チナミ区
D-11
D-11






| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]活力10(LV10)[防具]体力10(LV10)[装飾]舞撃10(LV20) | |||
| 7 | マラコフトルテ | 料理 | 36 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 8 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 9 | とばりさんねばねば | 武器 | 34 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 11 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 響鳴 | 16 | 歌唱/音楽/振動 |
| 付加 | 26 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| シャイン | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| ブリランテ | 5 | 0 | 140 | 自:光特性・魅了LV増 | |
| バトルソング | 6 | 0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) | |
| 決3 | クレイジーチューン | 6 | 0 | 140 | 味全:強制混乱+次与ダメ増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 6 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 光特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:光属性スキルのHP増効果に光特性が影響 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
エーレンベルク (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
イバラキッス! (エアスラスト) |
0 | 60 | 敵:4連風撃 | |
|
薬草 (ヒールハーブ) |
0 | 80 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 2 ]ヒールポーション | [ 1 ]ウィルスゾーン |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]クレイジーチューン |

PL / すずらん