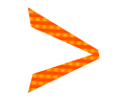<< 0:00>> 2:00




──星は冥きを照らすモノ
故に彼の地に救いの手を
流れ墜ちて 燃え尽きるその日まで
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
流れ星は、墜ちる先を選べない。
光満ちる世界のソラを翔けた星々は
誰の目にも留まらずただ燃え尽きるのみ。
だからこそ、その澱みきった昏いソラを見て
私は確かに高揚していたのだと思う。
誰かがこの光芒を目にしたのならば
それは確かな希望になるに違いない、と。
私がこのセカイに『墜ちた』のではなく
『堕とされた』と理解するのは──
それからずっと、ずっと先のこと。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「他人に甘えるな、自分を甘やかすな」
頭上から聞き慣れた言葉が降ってくる。
僕は俯き、手を膝において、じんじんと痛む頭で
何度も、何度もその言葉を反芻した。
──『先生』は厳しい人だ。
自分にも、他人にも、実の娘にだって。
別に機嫌が悪いわけじゃない。いつもこうだ。
『先生』が僕を叱るには明確な基準があって、
ただ僕はその境界を探るのがうまくなかった。
「もう一度最初からやりなおし。
一度で理解しなさいとは言いません。
ただし、二度目は一度目に劣らないように。」
鍵盤に指が触れる。
今日一日休まず弾いていたというのに
その感触は未だ冷たく、硬かった。
まるで、拒絶されているみたいだ。
余計なことを考えてしまった所為だろう。
僅かに音が乱れた──
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「『神秘』って何ですか?」
ずっと昔、私は▇▇にそう尋ねたことがある。
▇▇は少し困ったような顔をして答えてくれた。
「例えば、キミたちは『星』だ。
これは間違いのない『真実』で、
キミたちもそれをよく知っている。
人間はどうだろう。
彼らはキミたちのことを知らない。
では、人間は『星』のことを何も知らないのか。
そんなことはない。
彼らは彼らで『星』に準えた物語をたくさん、
もしかすると▇▇よりもたくさん知っている。
彼らにとってはその物語こそが『真実』だ。
キミたちの知るセカイと彼らの知るセカイ。
そこには『真実』の差異が存在する。
どちらが間違いということもなく、
異なる『真実』は同居することができる。
『神秘』とはその境界たる『未知』のことだ。
異なる『真実』を覆い隠し、
セカイを正しいカタチに定義するモノだよ。」
私はその話を聞いてもよく分からなくて。
ただ、▇▇が困ったような表情で
私を撫でてくれたその感触はよく覚えていた。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
柔らかいベッドの上で横になって、
僕はじっと天井を眺めていた。
つまらないミスをしてしまったお陰で
僕は『先生』に酷く怒られる羽目になった。
焼けた背中がじりじりと痛む。
一見綺麗に片付いて見えるこの部屋は
ただ単に物が少ないだけ。
僕が生まれる前は真っ白だったはずの天井には
転々と黒い染みが見えた。
もしも白と黒が反対だったなら
きっと星空みたいに綺麗だったのかな。
白い空の黒い星をを繋ぎ合わせて
架空の星座を描いて遊ぶ。
僕は星が好きだ。晴れた夜の空が好きだ。
音楽を除けば、きっと唯一好きなもの。
小さい頃、僕がそう話した夜に
『先生』は一編の楽譜をくれた。
星をモチーフにした変奏曲。
元々は違う意味を持っていた曲らしいけれど、
僕はそれが嬉しくて、繰り返し練習した。
『先生』が及第点をくれた初めての曲。
気づけば僕はピアノに向かい、
またその曲を奏でていた。
──きらきら 光る お空の 星よ



特に何もしませんでした。








幻術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
あやめ(205) とカードを交換しました!
スナイプ (ピンポイント)

シャイン を習得!
ビブラート を習得!
ブリランテ を習得!
光特性回復 を習得!
バトルソング を習得!
クレイジーチューン を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 I-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
せら(83) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
エディアンからのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



──星は冥きを照らすモノ
故に彼の地に救いの手を
流れ墜ちて 燃え尽きるその日まで
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
流れ星は、墜ちる先を選べない。
光満ちる世界のソラを翔けた星々は
誰の目にも留まらずただ燃え尽きるのみ。
だからこそ、その澱みきった昏いソラを見て
私は確かに高揚していたのだと思う。
誰かがこの光芒を目にしたのならば
それは確かな希望になるに違いない、と。
私がこのセカイに『墜ちた』のではなく
『堕とされた』と理解するのは──
それからずっと、ずっと先のこと。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「他人に甘えるな、自分を甘やかすな」
頭上から聞き慣れた言葉が降ってくる。
僕は俯き、手を膝において、じんじんと痛む頭で
何度も、何度もその言葉を反芻した。
──『先生』は厳しい人だ。
自分にも、他人にも、実の娘にだって。
別に機嫌が悪いわけじゃない。いつもこうだ。
『先生』が僕を叱るには明確な基準があって、
ただ僕はその境界を探るのがうまくなかった。
「もう一度最初からやりなおし。
一度で理解しなさいとは言いません。
ただし、二度目は一度目に劣らないように。」
鍵盤に指が触れる。
今日一日休まず弾いていたというのに
その感触は未だ冷たく、硬かった。
まるで、拒絶されているみたいだ。
余計なことを考えてしまった所為だろう。
僅かに音が乱れた──
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
「『神秘』って何ですか?」
ずっと昔、私は▇▇にそう尋ねたことがある。
▇▇は少し困ったような顔をして答えてくれた。
「例えば、キミたちは『星』だ。
これは間違いのない『真実』で、
キミたちもそれをよく知っている。
人間はどうだろう。
彼らはキミたちのことを知らない。
では、人間は『星』のことを何も知らないのか。
そんなことはない。
彼らは彼らで『星』に準えた物語をたくさん、
もしかすると▇▇よりもたくさん知っている。
彼らにとってはその物語こそが『真実』だ。
キミたちの知るセカイと彼らの知るセカイ。
そこには『真実』の差異が存在する。
どちらが間違いということもなく、
異なる『真実』は同居することができる。
『神秘』とはその境界たる『未知』のことだ。
異なる『真実』を覆い隠し、
セカイを正しいカタチに定義するモノだよ。」
私はその話を聞いてもよく分からなくて。
ただ、▇▇が困ったような表情で
私を撫でてくれたその感触はよく覚えていた。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
柔らかいベッドの上で横になって、
僕はじっと天井を眺めていた。
つまらないミスをしてしまったお陰で
僕は『先生』に酷く怒られる羽目になった。
焼けた背中がじりじりと痛む。
一見綺麗に片付いて見えるこの部屋は
ただ単に物が少ないだけ。
僕が生まれる前は真っ白だったはずの天井には
転々と黒い染みが見えた。
もしも白と黒が反対だったなら
きっと星空みたいに綺麗だったのかな。
白い空の黒い星をを繋ぎ合わせて
架空の星座を描いて遊ぶ。
僕は星が好きだ。晴れた夜の空が好きだ。
音楽を除けば、きっと唯一好きなもの。
小さい頃、僕がそう話した夜に
『先生』は一編の楽譜をくれた。
星をモチーフにした変奏曲。
元々は違う意味を持っていた曲らしいけれど、
僕はそれが嬉しくて、繰り返し練習した。
『先生』が及第点をくれた初めての曲。
気づけば僕はピアノに向かい、
またその曲を奏でていた。
──きらきら 光る お空の 星よ



特に何もしませんでした。







幻術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
あやめ(205) とカードを交換しました!
スナイプ (ピンポイント)

シャイン を習得!
ビブラート を習得!
ブリランテ を習得!
光特性回復 を習得!
バトルソング を習得!
クレイジーチューン を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 I-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
せら(83) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「1時間が経過しましたね。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャットで時間が伝えられる。
 |
エディアン 「ナレハテとの戦闘、お疲れ様でした! 相手を戦闘不能にすればいいようですねぇ。」 |
 |
エディアン 「さてさて。皆さんにご紹介したい方がいるんです。 ――はぁい、こちらです!こちらでーっす!!」 |
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
エディアン 「陣営に関わらず連れて行ってくれるようですのでどんどん利用しましょー!! ドライバーさんは中立ってことですよね?」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
エディアン 「たくさん・・・ 同じ顔がいっぱいいるんですかねぇ・・・。 ここはまだ、分からないことだらけです。」 |
 |
エディアン 「それでは再びの1時間、頑張りましょう! 新情報を得たらご連絡しますね。ファイトー!!オーッ!!」 |
エディアンからのチャットが閉じられる――







TeamNo.83
|
 |
ファッションファッションモンスター
|


ENo.130
星空 帳



「──次のニュ …ース…す。本…未明、
歌手……空…さ……亡く…り…した。
遺体…外傷………無く、警察…自殺………
捜査を──」
◼︎星空 帳(ホシゾラ トバリ)
年齢:13歳
身長:137cm
体重:秘密
一人称:僕(人前では私)
二人称:貴方
好きなもの:甘いコーヒー 金平糖 音楽
苦手なもの:激辛料理(でも食べる) リア充 強い光 うさぎ
《イバラシティ》
黒い癖毛を2つに括った女の子。
路上ライブで日銭を稼ぐネットカフェ難民。
名目上はとある男子高校生(Eno.940)の
借りている部屋に住んでいることになっている。
曲は自作らしく、しばしば動画投稿サイトに
音楽をアップロードしたり、SNSで宣伝している。
収入は前述の路上ライブと、創作者支援サイトからの投げ銭。
識字障害を持ち、文字の読み書きができない。
母親の名前は『星空 光』。生前は有名な歌手だった(既知可)。
SNS『とがったー』でのHNは『すてら』(@stella_P)。
音声案内、音声入力がないとSNSも使えない。
《アンジニティ》
彼女は『夜空』であり『星空』であった。
暗闇を照らし、眠りと安らぎを与えてくれた。
けれど『科学』によってその神秘を剥ぎ取られ、
星はただの天体に成り下がり、
夜の闇は人工の光で駆逐された。
だから、もう一度人々は思い出さなければならない。
夜の闇の恐怖と、眠りの安らぎを。
そして──星と共に笑い合うことを。
アンジニティでは誰か(Eno.143)の手によって
長期間に渡り監禁されていたらしい。
その際されたことについては固く口を閉ざしている。
◼︎異能
*ステラの魔法(ストラテリウム)*
星空の光を集めて、小さな光球を生成する。
彼女はこれを『ステラ』と呼び、
ステラは多少の願い事を叶える力を持つ。
ただしステラは強い光を浴びると消えてしまう。
特に人工の光に弱い。
*夜空の唄(ノクターナ)*
彼女の歌は、暗闇に対する原初の感情を呼び起こす。
暗闇の中で彼女の歌を聴いた者の心に『恐怖』
または『安息』の感情を齎す。
辺りが暗いほど効果は高まり、場合によっては
精神の不調に陥ったり、眠りから覚めなくなったりする。
◼︎投稿動画
・星空ワルツ
処女作。軽快なリズムのキラキラした曲。
じわじわ再生数が伸びている。
・夜に抱かれて
2作目。ゆったりしたバラード。
優しい歌詞かと思ったら実はダーク。
・スターホワイト
3作目。寂しげなテクノポップス。
クリスマスと届かない恋の歌。
・サクラミチ
4作目。ハイテンポな和風ロック。
速度の割に歌詞が多く、歌おうとするとかなり辛い。
◼︎サブキャラクター
・Lore・A=Ruca(ロア・ア=ルカ)
創峰大学付属病院に入院している女の子。
非常に小柄で、柔らかく白い髪と肌が特徴的。
病状は思わしくなく、先は長くないと宣告されている。
何故か病院の外で目撃されることがあるらしい。
・Knell(ネル)
荊街総合図書館の受付嬢兼司書。
ファミリーネームは不明。
来館者への応対は機械的だが勤務態度は真面目。
かなりの量の業務を回しており、お疲れ気味。
休日はロアの病室に足を運んでいる。
歌手……空…さ……亡く…り…した。
遺体…外傷………無く、警察…自殺………
捜査を──」
◼︎星空 帳(ホシゾラ トバリ)
年齢:13歳
身長:137cm
体重:秘密
一人称:僕(人前では私)
二人称:貴方
好きなもの:甘いコーヒー 金平糖 音楽
苦手なもの:激辛料理(でも食べる) リア充 強い光 うさぎ
《イバラシティ》
黒い癖毛を2つに括った女の子。
路上ライブで日銭を稼ぐネットカフェ難民。
名目上はとある男子高校生(Eno.940)の
借りている部屋に住んでいることになっている。
曲は自作らしく、しばしば動画投稿サイトに
音楽をアップロードしたり、SNSで宣伝している。
収入は前述の路上ライブと、創作者支援サイトからの投げ銭。
識字障害を持ち、文字の読み書きができない。
母親の名前は『星空 光』。生前は有名な歌手だった(既知可)。
SNS『とがったー』でのHNは『すてら』(@stella_P)。
音声案内、音声入力がないとSNSも使えない。
《アンジニティ》
彼女は『夜空』であり『星空』であった。
暗闇を照らし、眠りと安らぎを与えてくれた。
けれど『科学』によってその神秘を剥ぎ取られ、
星はただの天体に成り下がり、
夜の闇は人工の光で駆逐された。
だから、もう一度人々は思い出さなければならない。
夜の闇の恐怖と、眠りの安らぎを。
そして──星と共に笑い合うことを。
アンジニティでは誰か(Eno.143)の手によって
長期間に渡り監禁されていたらしい。
その際されたことについては固く口を閉ざしている。
◼︎異能
*ステラの魔法(ストラテリウム)*
星空の光を集めて、小さな光球を生成する。
彼女はこれを『ステラ』と呼び、
ステラは多少の願い事を叶える力を持つ。
ただしステラは強い光を浴びると消えてしまう。
特に人工の光に弱い。
*夜空の唄(ノクターナ)*
彼女の歌は、暗闇に対する原初の感情を呼び起こす。
暗闇の中で彼女の歌を聴いた者の心に『恐怖』
または『安息』の感情を齎す。
辺りが暗いほど効果は高まり、場合によっては
精神の不調に陥ったり、眠りから覚めなくなったりする。
◼︎投稿動画
・星空ワルツ
処女作。軽快なリズムのキラキラした曲。
じわじわ再生数が伸びている。
・夜に抱かれて
2作目。ゆったりしたバラード。
優しい歌詞かと思ったら実はダーク。
・スターホワイト
3作目。寂しげなテクノポップス。
クリスマスと届かない恋の歌。
・サクラミチ
4作目。ハイテンポな和風ロック。
速度の割に歌詞が多く、歌おうとするとかなり辛い。
◼︎サブキャラクター
・Lore・A=Ruca(ロア・ア=ルカ)
創峰大学付属病院に入院している女の子。
非常に小柄で、柔らかく白い髪と肌が特徴的。
病状は思わしくなく、先は長くないと宣告されている。
何故か病院の外で目撃されることがあるらしい。
・Knell(ネル)
荊街総合図書館の受付嬢兼司書。
ファミリーネームは不明。
来館者への応対は機械的だが勤務態度は真面目。
かなりの量の業務を回しており、お疲れ気味。
休日はロアの病室に足を運んでいる。
25 / 30
50 PS
チナミ区
I-6
I-6





| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 付加 | 20 | 装備品への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| シャイン | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 |
| ブリランテ | 5 | 0 | 140 | 自:光特性・魅了LV増 |
| バトルソング | 5 | 0 | 180 | 味列:AT・運増(3T) |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 140 | 味全:強制混乱+次与ダメ増 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |
| 光特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:光属性スキルのHP増効果に光特性が影響 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / すずらん