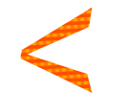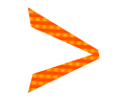<< 0:00>> 2:00




Once Upon a Time
──“昔々、あるところに”。
『──と云う切り出しは物語の常套句だけれど、さ。
ものがたり
実際のトコロ、この“侵略”、上手くいくと想うかい? “僕”よ』
ここではない、どこか。今ではない、いつか。
暗い、昏い、地平の果てを、ぼうやりと眺めながら。
“彼”は、問う。
(……知らないよ、別に。
その益体のない雑談は、今必要なモノなのかい)
返す視線は、冷ややかに、彼を見つめて。
──“彼”は、そう。
当たり前のように、“会話”を、紡いでいた。
『冗句さ冗句、そう冷たい目で見ないでくれよ。
どうにもまだ、“あちら”の記憶が抜けきっていなくてね』
呆れたように、目を竦める彼。
おどけるように、溜め息をこぼす彼。
ごく、当然のように。
まるで、“先ほどまでのことなんて、何も記憶がないように”。
愉快そうに会話を弾ませる──“彼”は。
(だから止めようって云ったんだよ。“あんな器”を創るのは。
僕たちが“あれ”の中に入れば、どうなるかくらい検討は付いただろう)
『なかなか面白い冗句じゃないか、“僕”も。
出す口は僕が預かってるんだから、入れられる茶々なんてないだろうにさ』
(……良く言うね、“僕”も。
“視線を感じた”事なんて、ありもしない癖に)
誰の姿も、留まらない。誰の声も、届かない。
“狭間の世界”の、始まりで。
ふたり
ただのひとり、ゆっくりと、問答を重ねてゆく。
『そこはお互いさまって奴だろう。“僕”。
“僕”は“そういうもの”なんだから、言ったところで仕方がない、無益な争いだ』
(──“仕方がない”、か。
そうだね、これは無為な争いだ。そこは同意するけれど)
『そうさ。“仕方のないこと”なんだ。
僕が、こうして生まれたのも。僕が、あれを創ったのも』
目のない“彼”が、謳うように、口を開く。
それはまるで、舞台演劇で、ようやく自分の出番が訪れた。
歓喜に満ちた、役者のように。
『──佳いかい、“僕”。
role
世の中には、得てして役割と云うモノがある』
(僕が居て、“僕”が居て。
“この世界”があって、“あちらの世界”があって)
観客はいない。 まだ、誰もいない、孤独な世界。
ひとり舞台のひとり芝居を眺める役者の視線は、まるで。
失望の物語を描いた台本のように、ただ静かに。
『……そう。そう云うコトさ。
全ての人間が影法師であるのなら、世界にはすべからく台本があると云うコト』
(そうだね。逸脱することは赦されないことだ。
異端こそが、世界の悪徳の始まりだ)
『“器”の僕も、云っていたじゃないか。
“原罪”がなければ、“天使”は“人間”にはならなかった』
(……妙な言い回しだね。本当にそれは“僕”なのか疑問だけれど。
けれどまぁ、概ねにおいてその通りだ)
誰の視線もない。誰のこえも届かない、始まりの世界で。
“彼”は“ふたり”。本番前の、読み合わせをするように。
『──では“僕”よ。ここで問いのいちだ。
もし仮に、“世界”そのものが、“異端”であるのなら。
僕たちは“それ”を、“どう”するべきだろうか?』
(……問いになってないよ。“僕”。
“在るべきものは、在るべきところへ”。
“異端”が“悪徳”だと云うのなら。
Just Justice
“適当性”の確保こそが、“正義”の命題であるべきだ)
『そうだね。それは仕方のないことだ。
けれど、それは“世界”を敵に回す道だよ?
それでも“僕”は、役者に徹するべきなのかな』
(回答拒否。
“世界を敵に回すために、僕は生まれたのだから”)
弾む、跳ねる、愉快そうな、こえの彩。
読み合わせと呼ぶには、些か感情の篭ったその声は。
きっと、どうでも良いのだろう。
観客なんて居なくても。 誰に理解されずとも。
『──あは。 あっは。
そうだね、その通りだ。
“世界”なんて前提、最初から必要なかった』
“観客”は、ここにいて。 “理解者”が、ここにいるのなら。
(そうさ。
だって、“世界”は、“ここにある”のだから)
あとは、ただ。 演じ終えるだけの、物語。
(──さぁ、始めようか)
『あぁ、始めよう──』
そう。 だから。
これは、きっと。
『誰にも、触れられない』 「誰にも、触れさせたりしない」
(僕たちの) (僕たちだけの)
『(
A侵 生N
G略 存I
N戦 協I
T争 奏Y
を
』)
curtain call
──閉幕



特に何もしませんでした。








武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
碓氷(123) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『題名のない晩餐《グルマンテ》』をつくりました!
アイアンカイザー(99) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『淡き鋼鉄の楽園《シャングリラ》』をつくろうとしましたが、相手から取引生産許可が出ていませんでした。
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『題名のない晩餐会《グルマンティ》』をつくりました!
⇒ 題名のない晩餐会《グルマンティ》/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
カオル(217) とカードを交換しました!
水の癒し (ヒール)

ヒーリングソング を研究しました!(深度0⇒1)
ヒーリングソング を研究しました!(深度1⇒2)
ヒーリングソング を研究しました!(深度2⇒3)
エキサイト を習得!
ヒールポーション を習得!
アドレナリン を習得!
イレイザー を習得!
コロージョン を習得!
変調特性 を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 I-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
かこ(19) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



Once Upon a Time
──“昔々、あるところに”。
『──と云う切り出しは物語の常套句だけれど、さ。
ものがたり
実際のトコロ、この“侵略”、上手くいくと想うかい? “僕”よ』
ここではない、どこか。今ではない、いつか。
暗い、昏い、地平の果てを、ぼうやりと眺めながら。
“彼”は、問う。
(……知らないよ、別に。
その益体のない雑談は、今必要なモノなのかい)
返す視線は、冷ややかに、彼を見つめて。
──“彼”は、そう。
当たり前のように、“会話”を、紡いでいた。
『冗句さ冗句、そう冷たい目で見ないでくれよ。
どうにもまだ、“あちら”の記憶が抜けきっていなくてね』
呆れたように、目を竦める彼。
おどけるように、溜め息をこぼす彼。
ごく、当然のように。
まるで、“先ほどまでのことなんて、何も記憶がないように”。
愉快そうに会話を弾ませる──“彼”は。
(だから止めようって云ったんだよ。“あんな器”を創るのは。
僕たちが“あれ”の中に入れば、どうなるかくらい検討は付いただろう)
『なかなか面白い冗句じゃないか、“僕”も。
出す口は僕が預かってるんだから、入れられる茶々なんてないだろうにさ』
(……良く言うね、“僕”も。
“視線を感じた”事なんて、ありもしない癖に)
誰の姿も、留まらない。誰の声も、届かない。
“狭間の世界”の、始まりで。
ふたり
ただのひとり、ゆっくりと、問答を重ねてゆく。
『そこはお互いさまって奴だろう。“僕”。
“僕”は“そういうもの”なんだから、言ったところで仕方がない、無益な争いだ』
(──“仕方がない”、か。
そうだね、これは無為な争いだ。そこは同意するけれど)
『そうさ。“仕方のないこと”なんだ。
僕が、こうして生まれたのも。僕が、あれを創ったのも』
目のない“彼”が、謳うように、口を開く。
それはまるで、舞台演劇で、ようやく自分の出番が訪れた。
歓喜に満ちた、役者のように。
『──佳いかい、“僕”。
role
世の中には、得てして役割と云うモノがある』
(僕が居て、“僕”が居て。
“この世界”があって、“あちらの世界”があって)
観客はいない。 まだ、誰もいない、孤独な世界。
ひとり舞台のひとり芝居を眺める役者の視線は、まるで。
失望の物語を描いた台本のように、ただ静かに。
『……そう。そう云うコトさ。
全ての人間が影法師であるのなら、世界にはすべからく台本があると云うコト』
(そうだね。逸脱することは赦されないことだ。
異端こそが、世界の悪徳の始まりだ)
『“器”の僕も、云っていたじゃないか。
“原罪”がなければ、“天使”は“人間”にはならなかった』
(……妙な言い回しだね。本当にそれは“僕”なのか疑問だけれど。
けれどまぁ、概ねにおいてその通りだ)
誰の視線もない。誰のこえも届かない、始まりの世界で。
“彼”は“ふたり”。本番前の、読み合わせをするように。
『──では“僕”よ。ここで問いのいちだ。
もし仮に、“世界”そのものが、“異端”であるのなら。
僕たちは“それ”を、“どう”するべきだろうか?』
(……問いになってないよ。“僕”。
“在るべきものは、在るべきところへ”。
“異端”が“悪徳”だと云うのなら。
Just Justice
“適当性”の確保こそが、“正義”の命題であるべきだ)
『そうだね。それは仕方のないことだ。
けれど、それは“世界”を敵に回す道だよ?
それでも“僕”は、役者に徹するべきなのかな』
(回答拒否。
“世界を敵に回すために、僕は生まれたのだから”)
弾む、跳ねる、愉快そうな、こえの彩。
読み合わせと呼ぶには、些か感情の篭ったその声は。
きっと、どうでも良いのだろう。
観客なんて居なくても。 誰に理解されずとも。
『──あは。 あっは。
そうだね、その通りだ。
“世界”なんて前提、最初から必要なかった』
“観客”は、ここにいて。 “理解者”が、ここにいるのなら。
(そうさ。
だって、“世界”は、“ここにある”のだから)
あとは、ただ。 演じ終えるだけの、物語。
(──さぁ、始めようか)
『あぁ、始めよう──』
そう。 だから。
これは、きっと。
『誰にも、触れられない』 「誰にも、触れさせたりしない」
(僕たちの) (僕たちだけの)
『(
A侵 生N
G略 存I
N戦 協I
T争 奏Y
を
』)
curtain call
──閉幕



特に何もしませんでした。







武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
碓氷(123) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『題名のない晩餐《グルマンテ》』をつくりました!
アイアンカイザー(99) の持つ ItemNo.6 不思議な食材 から料理『淡き鋼鉄の楽園《シャングリラ》』をつくろうとしましたが、相手から取引生産許可が出ていませんでした。
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『題名のない晩餐会《グルマンティ》』をつくりました!
⇒ 題名のない晩餐会《グルマンティ》/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
 |
†.† 「……さて、作ってみたは佳いけれど。何せ料理をしたコトなんて、河川敷に生えていた野蒜《マンドラゴラ》のおひたし程度が精々だったからね。 とりあえず今回は料理が形になっただけでも褒められるべきだとボクは想うのだけれど──いやその、怒らないで聞いて欲しいんだ。そうこれは悠久の道程を征くボクらに捧ぐ題名のない晩餐会。食材は虚無と虚空だけだけれど、ここからもう少しマシにはなると想うから、今回はこれで我慢してほしい。うん」 |
カオル(217) とカードを交換しました!
水の癒し (ヒール)

ヒーリングソング を研究しました!(深度0⇒1)
ヒーリングソング を研究しました!(深度1⇒2)
ヒーリングソング を研究しました!(深度2⇒3)
エキサイト を習得!
ヒールポーション を習得!
アドレナリン を習得!
イレイザー を習得!
コロージョン を習得!
変調特性 を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 I-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
かこ(19) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――



ファッションファッションモンスター
|
 |
ハザマに生きるもの
|




TeamNo.83
|
 |
ファッションファッションモンスター
|


ENo.464
†.†《─ラスト・ピリオド─》



名前:
†.†《ラスト・ピリオド》 (自己申告)
身長:
世界の終焉を告げる円環蛇よりなお大きく (自己申告)
体重:
黙示禄の喇叭を鳴らす天使の翅のごと軽やかに (自己申告)
種族:
悠久の刻を裂く†──堕天聖──† (自己申告)
好きなもの:
†──禁断の果実──† (自己申告)
本当に好きなもの:
痛々しい鎖などのついたグッズ、えいひれ、このわた
「──来寇せし堕天使は、闇にも似た漆黒を奏で
浸食の泥を呑む杯は、翼の輝きを抱いて眠る──」
■イバラシティ
《天使》を自称する、ちょっとお年頃な感じの17歳。
人より少しだけ†覚醒の刻†が遅れたためか、
かなり重症にこじらせてしてしまった、†悲しみの堕とし仔†。
とは申せど、“その1点”を除けば、
人付き合いが好きで、少しだけ寂しがりな普通の青年である。
ただ、当人はあまりそう思われる事を好まないらしく、
“荘厳にして冷徹”を自称し、
結構な確率で奇行に走ることが多いようだ。
“†古代魔法語†”を理解してくれるニンゲンが
“このセカイ”にはあまり多くないのが、
もっぱらの悩みの種らしい。
■アンジニティ
Coming Soon────
†.†《ラスト・ピリオド》 (自己申告)
身長:
世界の終焉を告げる円環蛇よりなお大きく (自己申告)
体重:
黙示禄の喇叭を鳴らす天使の翅のごと軽やかに (自己申告)
種族:
悠久の刻を裂く†──堕天聖──† (自己申告)
好きなもの:
†──禁断の果実──† (自己申告)
本当に好きなもの:
痛々しい鎖などのついたグッズ、えいひれ、このわた
「──来寇せし堕天使は、闇にも似た漆黒を奏で
浸食の泥を呑む杯は、翼の輝きを抱いて眠る──」
■イバラシティ
《天使》を自称する、ちょっとお年頃な感じの17歳。
人より少しだけ†覚醒の刻†が遅れたためか、
かなり重症にこじらせてしてしまった、†悲しみの堕とし仔†。
とは申せど、“その1点”を除けば、
人付き合いが好きで、少しだけ寂しがりな普通の青年である。
ただ、当人はあまりそう思われる事を好まないらしく、
“荘厳にして冷徹”を自称し、
結構な確率で奇行に走ることが多いようだ。
“†古代魔法語†”を理解してくれるニンゲンが
“このセカイ”にはあまり多くないのが、
もっぱらの悩みの種らしい。
■アンジニティ
Coming Soon────
25 / 30
50 PS
チナミ区
I-6
I-6





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 題名のない晩餐会《グルマンティ》 | 料理 | 30 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 20 | 料理に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増 |
| アドレナリン | 5 | 0 | 80 | 自:AT増(4T)+麻痺か衰弱状態なら、連続増+麻痺・衰弱減 |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| コロージョン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |
| 変調特性 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体・精神変調特性増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ヒーリングソング |

PL / さばーーば