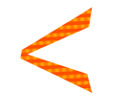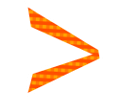<< 1:00>> 3:00




『──どうにも慣れないな、この感じは』
(記憶に連続性がないと云うのは、存外、不便なものだね。
思い返すことが多すぎて、いささか管理に支障が出てしまいそうだ)
『不要な想起、不当な記憶。
何の役にも立たない癖に、数だけは積みあがる。 困ったものだよ。
そんなもの──ここでは。
何の役にも、立たないって云うのに』
生暖かい風が、金糸の髪を揺らした。
地平の果てまで、“何もない”。
無貌の荒野を見据えるその瞳は、泥のように塗り潰されていて。
──小さく零れる溜め息は、いったい、“どちら”から零れたものだったのだろう。
ひと呼吸、ひと狭間の退屈すらも潰しきれぬほど、怠惰に満ちたこの世界では。
残念なことに、“思考を巡らせる”時間だけは、履いて捨てるほど、あるものだから。
『──でさ、“僕”。
当然、“覚えてる”んだろう?
ものの見事に、器の方は、打ちのめされた訳だけれど』
(当然のことさ。
“あれ”は、僕達の予定を外れてはいけないんだ。
愛だの恋だの、うつつを抜かすのは構わないとは云え。
妙な感情を学習されても困るからね)
『人形もどきの異能然り、桃髪の小娘然り。
……あの、溝色の目をした、泥のようなおとこ然り。
木偶は木偶らしくしてれば、安寧のまま生きられたのに。
“背中を推された”とは、佳く云ったものだよ。
崖から転げ落ちるほか、道がないって分かってたくせに』
(莫迦だからね。
莫迦は学習しないから、夢を観るんだ。
浪漫だとか愛とかユメだとか、カタチのないものに、よくよく縋りたがるものさ)
──分かってはいた。
実のない話だということも。
毒にはなれど、薬にはならない話だということも。
けれど。流れるひと刹那。
無言で、無為に過ごせるほどには。
この身体は、この心は。
孤独に、耐えられるようにはできていないものだから。
『……さて。“それはさておき”だ、僕。
僕は今、少々虫の居所が悪いのだけれど』
(──奇遇だね。“僕”
器とは云え、アレは“僕”であり、僕なんだ。
多少、感情が惹かれるのは、致し方のないことだろう)
『これだから、余計な感情を持たせるのは嫌なんだ。
“器”の時間と違って、僕らにはやるべきことがあるって云うのに』
(そう熱るなよ、“僕”。
溜まった鬱憤は、こっちで晴らせば佳いじゃないか)
『……やれやれだよ、全く。
ここまでが“役割”だって云うのなら、主さまも、人が悪いことだ』
──そう。
僕ら
彼らは知っていた。
《管理者》と云うのは、何時だって。
ひとりでは、成り立たない役割なのだということを。
(まぁ、何をごねても。明けても暮れても何も出ないぜ。
その意気を、傍にぶつけたほうが、幾分か生産的なことができると提案するよ。
ほら、ちょうどいい。
あそこに、手ごろな“鬱憤晴らし”がいるじゃあないか──)



ENo.60 安里杏莉 とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。










かこ(19) は パンの耳 を入手!
アイアンカイザー(99) は パンの耳 を入手!
碓氷(123) は 吸い殻 を入手!
†.†(464) は パンの耳 を入手!
かこ(19) は 毛 を入手!
かこ(19) は 毛 を入手!
碓氷(123) は ねばねば を入手!
碓氷(123) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
かこ(19) のもとに 道端ガムマン がものすごい勢いで駆け寄ってきます。



武術LV を 3 UP!(LV10⇒13、-3CP)
料理LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
碓氷(123) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程5の武器『端無き果実』を作製してもらいました!
⇒ 端無き果実/武器:強さ33/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程5】/特殊アイテム
ヴィズ(163) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『《虚ろの孤島》』を作製してもらいました!
⇒ 《虚ろの孤島》/装飾:強さ33/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
福司(407) とカードを交換しました!
【呪】 (ヴェノム)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
イレイザー を研究しました!(深度2⇒3)



チナミ区 J-6(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















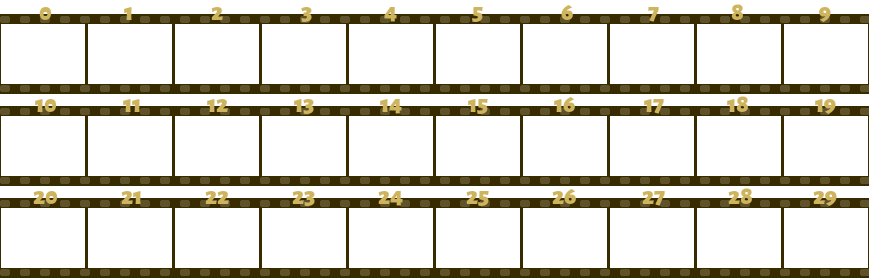





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



『──どうにも慣れないな、この感じは』
(記憶に連続性がないと云うのは、存外、不便なものだね。
思い返すことが多すぎて、いささか管理に支障が出てしまいそうだ)
『不要な想起、不当な記憶。
何の役にも立たない癖に、数だけは積みあがる。 困ったものだよ。
そんなもの──ここでは。
何の役にも、立たないって云うのに』
生暖かい風が、金糸の髪を揺らした。
地平の果てまで、“何もない”。
無貌の荒野を見据えるその瞳は、泥のように塗り潰されていて。
──小さく零れる溜め息は、いったい、“どちら”から零れたものだったのだろう。
ひと呼吸、ひと狭間の退屈すらも潰しきれぬほど、怠惰に満ちたこの世界では。
残念なことに、“思考を巡らせる”時間だけは、履いて捨てるほど、あるものだから。
『──でさ、“僕”。
当然、“覚えてる”んだろう?
ものの見事に、器の方は、打ちのめされた訳だけれど』
(当然のことさ。
“あれ”は、僕達の予定を外れてはいけないんだ。
愛だの恋だの、うつつを抜かすのは構わないとは云え。
妙な感情を学習されても困るからね)
『人形もどきの異能然り、桃髪の小娘然り。
……あの、溝色の目をした、泥のようなおとこ然り。
木偶は木偶らしくしてれば、安寧のまま生きられたのに。
“背中を推された”とは、佳く云ったものだよ。
崖から転げ落ちるほか、道がないって分かってたくせに』
(莫迦だからね。
莫迦は学習しないから、夢を観るんだ。
浪漫だとか愛とかユメだとか、カタチのないものに、よくよく縋りたがるものさ)
──分かってはいた。
実のない話だということも。
毒にはなれど、薬にはならない話だということも。
けれど。流れるひと刹那。
無言で、無為に過ごせるほどには。
この身体は、この心は。
孤独に、耐えられるようにはできていないものだから。
『……さて。“それはさておき”だ、僕。
僕は今、少々虫の居所が悪いのだけれど』
(──奇遇だね。“僕”
器とは云え、アレは“僕”であり、僕なんだ。
多少、感情が惹かれるのは、致し方のないことだろう)
『これだから、余計な感情を持たせるのは嫌なんだ。
“器”の時間と違って、僕らにはやるべきことがあるって云うのに』
(そう熱るなよ、“僕”。
溜まった鬱憤は、こっちで晴らせば佳いじゃないか)
『……やれやれだよ、全く。
ここまでが“役割”だって云うのなら、主さまも、人が悪いことだ』
──そう。
僕ら
彼らは知っていた。
《管理者》と云うのは、何時だって。
ひとりでは、成り立たない役割なのだということを。
(まぁ、何をごねても。明けても暮れても何も出ないぜ。
その意気を、傍にぶつけたほうが、幾分か生産的なことができると提案するよ。
ほら、ちょうどいい。
あそこに、手ごろな“鬱憤晴らし”がいるじゃあないか──)



ENo.60 安里杏莉 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。



ファッションファッションモンスター
|
 |
ハザマに生きるもの
|



ファッションファッションモンスター
|
 |
大和魂菓子十字騎士団
|



かこ(19) は パンの耳 を入手!
アイアンカイザー(99) は パンの耳 を入手!
碓氷(123) は 吸い殻 を入手!
†.†(464) は パンの耳 を入手!
かこ(19) は 毛 を入手!
かこ(19) は 毛 を入手!
碓氷(123) は ねばねば を入手!
碓氷(123) は 不思議な石 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
かこ(19) のもとに 道端ガムマン がものすごい勢いで駆け寄ってきます。



武術LV を 3 UP!(LV10⇒13、-3CP)
料理LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
碓氷(123) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程5の武器『端無き果実』を作製してもらいました!
⇒ 端無き果実/武器:強さ33/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程5】/特殊アイテム
ヴィズ(163) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『《虚ろの孤島》』を作製してもらいました!
⇒ 《虚ろの孤島》/装飾:強さ33/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
ヴィズ 「ふむ……こんなもんじゃな」 |
福司(407) とカードを交換しました!
【呪】 (ヴェノム)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
イレイザー を研究しました!(深度2⇒3)



チナミ区 J-6(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-6(山岳)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――



ファッションファッションモンスター
|
 |
ハザマに生きるもの
|




ファッションファッションモンスター
|
 |
TeamNo.769
|


ENo.464
†.†《─ラスト・ピリオド─》



名前:
†.†《ラスト・ピリオド》 (自己申告)
身長:
世界の終焉を告げる円環蛇よりなお大きく (自己申告)
体重:
黙示禄の喇叭を鳴らす天使の翅のごと軽やかに (自己申告)
種族:
悠久の刻を裂く†──堕天聖──† (自己申告)
好きなもの:
†──禁断の果実──† (自己申告)
本当に好きなもの:
痛々しい鎖などのついたグッズ、えいひれ、このわた
「──来寇せし堕天使は、闇にも似た漆黒を奏で
浸食の泥を呑む杯は、翼の輝きを抱いて眠る──」
■イバラシティ
《天使》を自称する、ちょっとお年頃な感じの17歳。
人より少しだけ†覚醒の刻†が遅れたためか、
かなり重症にこじらせてしてしまった、†悲しみの堕とし仔†。
とは申せど、“その1点”を除けば、
人付き合いが好きで、少しだけ寂しがりな普通の青年である。
ただ、当人はあまりそう思われる事を好まないらしく、
“荘厳にして冷徹”を自称し、
結構な確率で奇行に走ることが多いようだ。
“†古代魔法語†”を理解してくれるニンゲンが
“このセカイ”にはあまり多くないのが、
もっぱらの悩みの種らしい。
■アンジニティ
Coming Soon────
†.†《ラスト・ピリオド》 (自己申告)
身長:
世界の終焉を告げる円環蛇よりなお大きく (自己申告)
体重:
黙示禄の喇叭を鳴らす天使の翅のごと軽やかに (自己申告)
種族:
悠久の刻を裂く†──堕天聖──† (自己申告)
好きなもの:
†──禁断の果実──† (自己申告)
本当に好きなもの:
痛々しい鎖などのついたグッズ、えいひれ、このわた
「──来寇せし堕天使は、闇にも似た漆黒を奏で
浸食の泥を呑む杯は、翼の輝きを抱いて眠る──」
■イバラシティ
《天使》を自称する、ちょっとお年頃な感じの17歳。
人より少しだけ†覚醒の刻†が遅れたためか、
かなり重症にこじらせてしてしまった、†悲しみの堕とし仔†。
とは申せど、“その1点”を除けば、
人付き合いが好きで、少しだけ寂しがりな普通の青年である。
ただ、当人はあまりそう思われる事を好まないらしく、
“荘厳にして冷徹”を自称し、
結構な確率で奇行に走ることが多いようだ。
“†古代魔法語†”を理解してくれるニンゲンが
“このセカイ”にはあまり多くないのが、
もっぱらの悩みの種らしい。
■アンジニティ
Coming Soon────
20 / 30
70 PS
チナミ区
N-6
N-6





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 端無き果実 | 武器 | 33 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程5】 |
| 5 | 《虚ろの孤島》 | 装飾 | 33 | [効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 題名のない晩餐会《グルマンティ》 | 料理 | 30 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 13 | 身体/武器/物理 |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 23 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増 | |
| アドレナリン | 5 | 0 | 80 | 自:AT増(4T)+麻痺か衰弱状態なら、連続増+麻痺・衰弱減 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| コロージョン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 変調特性 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体・精神変調特性増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ヒーリングソング | [ 3 ]イレイザー |

PL / さばーーば