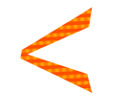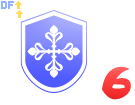<< 1:00>> 3:00




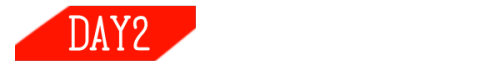
雨の音、冷たい空気。──ブレーキ音、そして衝突音。
ひどい雨の降るあの冬の始まりの日。
わたしはあの瞬間、総てを失ったのだった。
伸ばした手は届かなかった。
この手が触れたのは、あの子の手なんかじゃなくて。
生温い──血の感触だった。
指先が赤く染まる。血と、脂の臭いがする。
頭がどくどくと鳴る。目の前がぐらぐらと揺らぐ。
危ない、そんなことを叫ぶことは出来無かった。
例えば、声があったなら。
もっと、違う能力があったなら。
あそこにいたのが、わたしじゃなかったら。
あの子じゃなくて、わたしがそうなっていたら。
わたしを突き飛ばさなければ、ううん。
わたしさえ、いなければ。
「──────ッ!」
殴りつけた地面は硬くて、冷たくて。
そんなことをしても、もう何の意味もない。
あの日、わたしは静かに慟哭した。
わたしの声は、誰にも届かない。
わたしの手は、何にも救えない。
わたしは、失うのが怖くなった。
……………………。
ふわりと、朝の光がわたしの覚醒を促した。
目を擦りながら体を起こす。
──何の、夢を見ていたっけ。
思い出せずに首を傾げた。
思い出せないことには慣れていたから、いつもの通り諦めた。
わたしの記憶は空っぽだ。
自分の名前と、家族と一部の情報以外何も持っていない。
幸いにも、もともと学校にはあまり行っていなかったらしく、
適当に振舞っても不自然さを指摘されることは無かった。
月日は流れていく。
わたしは特に誰とも仲良くなることも、何かに没頭することもなく生きていた。
高校2年を過ぎてもそれは同じで、退屈で味気ない日々を送っていた、
それは別に苦痛じゃなかったし、何かに興味があるわけでもなかったから。
どうでもよかった。誰かも、何かも、自分も。
空っぽなのは記憶だけじゃなかった。
根岸こがねという人物は、空白で出来ている。
底無しの空白。何を落としても、何の音も響かない。
その空白に何かを詰め込みたいとも思わず、
ただただ適当に日々を消費していた。
特別な物語なんて普通の人間に訪れるはずはない。
わかりきった事実で、目の前の現実だ。
──ただ、一点を除いて。
目の前に、同じ顔の人物がいる。
違うのは黒子の位置ぐらい。
わたしの記憶が消えて暫く。
ある日突然彼女は現れたのだ、わたしの前に。
そして、こう言った。
──私と、ゲームをしよう。
ゲームの内容は酷く簡単だった。
わたしは、頷いた。頷くしかなかったから。
「ねえ、最近どうよ」
彼女はいつも通り楽しそうに笑って、わたしに言う。
彼女はわたしと違って楽しそうだ。
学校なんて行きたくないしあんたが行ってよ、そう言って制服を押し付けて。
空っぽなわたしが決してできない顔で笑う。
「ふぅん」
わたしの返答を鼻で笑って、彼女は枕元の目覚まし時計を手に取る。
日曜日、朝の9時。彼女が決まって、わたしの様子を見に来る日。
その日付と時間が彼女の手の中に収まっている。
もしかしたら、わたしもとっくに彼女の掌の上にいるのかもしれない。
そう、思った。
──やがて、時が流れて。
時計塔で彼と出会った。教室でみんなと話した。
喫茶店でクラスメイトと談笑して、寮で恋の話をした。
星空を見ながら彼女と話して、近くまで一緒に帰った。
彼にお節介を焼いて、彼と屋上で喧嘩別れをした。
以前とは比べられない色のある日々。
楽しいけれど、ひどく罪悪感に駆られた。
わたしは、嘘を吐いている、
わたしは、自分が本当に根岸こがねなのか、分かっていないのに。
なのに何も思っていない顔で、その名を名乗って“根岸こがね”の日々を生きている。
それは正しい事なの?
もしも、もしもわたしが本当はそうじゃなかったら?
わたしは、そんな怯えの中で生きている。
……この、不気味な空の下でさえ。


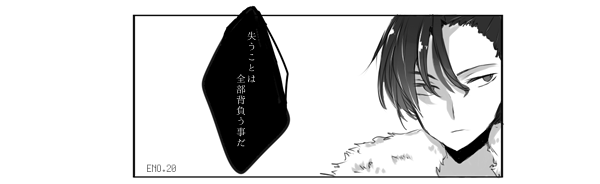


※交流して頂いた方をお借りしております。
問題等御座いましたらお声掛け頂けると幸いです



ENo.464 †.†《─ラスト・ピリオド─》 とのやりとり

ENo.539 天宮寺 咲那 とのやりとり

以下の相手に送信しました














めぐみ&心(543) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『メッセージウィンドウ』を作製しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。
冷(1142) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『メッセージウィンドウ』を作製しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。
深紀(1081) とカードを交換しました!
ディヴォーションバインド (キャプチャー)

ヒーリングソング を研究しました!(深度0⇒1)
バトルソング を研究しました!(深度0⇒1)
バトルソング を研究しました!(深度1⇒2)



チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調21⇒20)
めぐみ&心(543) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















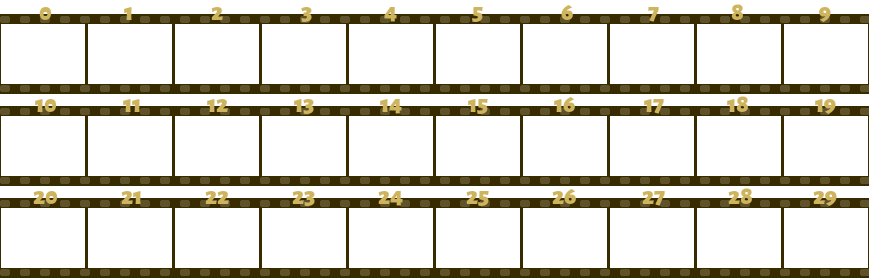





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK.



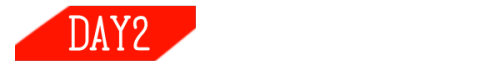
雨の音、冷たい空気。──ブレーキ音、そして衝突音。
ひどい雨の降るあの冬の始まりの日。
わたしはあの瞬間、総てを失ったのだった。
伸ばした手は届かなかった。
この手が触れたのは、あの子の手なんかじゃなくて。
生温い──血の感触だった。
指先が赤く染まる。血と、脂の臭いがする。
頭がどくどくと鳴る。目の前がぐらぐらと揺らぐ。
危ない、そんなことを叫ぶことは出来無かった。
例えば、声があったなら。
もっと、違う能力があったなら。
あそこにいたのが、わたしじゃなかったら。
あの子じゃなくて、わたしがそうなっていたら。
わたしを突き飛ばさなければ、ううん。
わたしさえ、いなければ。
「──────ッ!」
殴りつけた地面は硬くて、冷たくて。
そんなことをしても、もう何の意味もない。
あの日、わたしは静かに慟哭した。
わたしの声は、誰にも届かない。
わたしの手は、何にも救えない。
わたしは、失うのが怖くなった。
……………………。
ふわりと、朝の光がわたしの覚醒を促した。
目を擦りながら体を起こす。
──何の、夢を見ていたっけ。
思い出せずに首を傾げた。
思い出せないことには慣れていたから、いつもの通り諦めた。
わたしの記憶は空っぽだ。
自分の名前と、家族と一部の情報以外何も持っていない。
幸いにも、もともと学校にはあまり行っていなかったらしく、
適当に振舞っても不自然さを指摘されることは無かった。
月日は流れていく。
わたしは特に誰とも仲良くなることも、何かに没頭することもなく生きていた。
高校2年を過ぎてもそれは同じで、退屈で味気ない日々を送っていた、
それは別に苦痛じゃなかったし、何かに興味があるわけでもなかったから。
どうでもよかった。誰かも、何かも、自分も。
空っぽなのは記憶だけじゃなかった。
根岸こがねという人物は、空白で出来ている。
底無しの空白。何を落としても、何の音も響かない。
その空白に何かを詰め込みたいとも思わず、
ただただ適当に日々を消費していた。
特別な物語なんて普通の人間に訪れるはずはない。
わかりきった事実で、目の前の現実だ。
──ただ、一点を除いて。
目の前に、同じ顔の人物がいる。
違うのは黒子の位置ぐらい。
わたしの記憶が消えて暫く。
ある日突然彼女は現れたのだ、わたしの前に。
そして、こう言った。
──私と、ゲームをしよう。
ゲームの内容は酷く簡単だった。
わたしは、頷いた。頷くしかなかったから。
「ねえ、最近どうよ」
彼女はいつも通り楽しそうに笑って、わたしに言う。
彼女はわたしと違って楽しそうだ。
学校なんて行きたくないしあんたが行ってよ、そう言って制服を押し付けて。
空っぽなわたしが決してできない顔で笑う。
「ふぅん」
わたしの返答を鼻で笑って、彼女は枕元の目覚まし時計を手に取る。
日曜日、朝の9時。彼女が決まって、わたしの様子を見に来る日。
その日付と時間が彼女の手の中に収まっている。
もしかしたら、わたしもとっくに彼女の掌の上にいるのかもしれない。
そう、思った。
──やがて、時が流れて。
時計塔で彼と出会った。教室でみんなと話した。
喫茶店でクラスメイトと談笑して、寮で恋の話をした。
星空を見ながら彼女と話して、近くまで一緒に帰った。
彼にお節介を焼いて、彼と屋上で喧嘩別れをした。
以前とは比べられない色のある日々。
楽しいけれど、ひどく罪悪感に駆られた。
わたしは、嘘を吐いている、
わたしは、自分が本当に根岸こがねなのか、分かっていないのに。
なのに何も思っていない顔で、その名を名乗って“根岸こがね”の日々を生きている。
それは正しい事なの?
もしも、もしもわたしが本当はそうじゃなかったら?
わたしは、そんな怯えの中で生きている。
……この、不気味な空の下でさえ。


氷の溶ける音、静かな音楽。
呆れたような、優しい顔で彼女は笑った。
呆れたような、優しい顔で彼女は笑った。
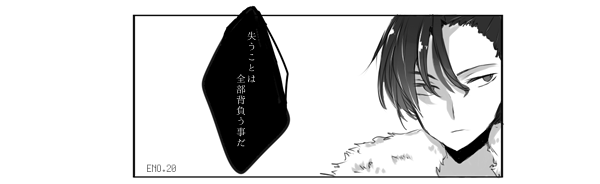
伸ばした手、去っていく背中。
彼は酷く暗い眼をしていた。
彼は酷く暗い眼をしていた。

星空の下、夜の空気。
彼女は、硝子玉のような目でわたしを見ていた。
彼女は、硝子玉のような目でわたしを見ていた。

展望台、冷たい空気の中。
彼は言葉を探すように、口を閉ざした。
彼は言葉を探すように、口を閉ざした。
どうか、まだ誰も気付かないで。
そう2人は願った。
どうか、私にこの日々をください。
片方は祈った。
どうか、この日々が続くように。
片方は思った。
同じ顔の2人はまだ、誰にも何も明かさずに。
同じ顔で、笑っている。
そう2人は願った。
どうか、私にこの日々をください。
片方は祈った。
どうか、この日々が続くように。
片方は思った。
同じ顔の2人はまだ、誰にも何も明かさずに。
同じ顔で、笑っている。
※交流して頂いた方をお借りしております。
問題等御座いましたらお声掛け頂けると幸いです



ENo.464 †.†《─ラスト・ピリオド─》 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.539 天宮寺 咲那 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
根岸 「前回は待ち合わせ場所間違えてごめんね!よろしく~」 |









めぐみ&心(543) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『メッセージウィンドウ』を作製しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。
冷(1142) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『メッセージウィンドウ』を作製しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。
深紀(1081) とカードを交換しました!
ディヴォーションバインド (キャプチャー)

ヒーリングソング を研究しました!(深度0⇒1)
バトルソング を研究しました!(深度0⇒1)
バトルソング を研究しました!(深度1⇒2)



チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調21⇒20)
めぐみ&心(543) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――







TeamNo.543
|
 |
アンジニチィ
|


ENo.421
根岸 こがね



※同じ顔をしたPC二人組、という特殊な設定のPCです。
根岸こがね(ねぎし-)/153cm/女
左目に泣き黒子。相良伊橋高校二年生。2-2に所属している。
高校はサボりがちなので校内で見かけることは少ない。
殆ど喋らず、コミュニケーションは専ら異能で作り出すメッセージウィンドウに頼り切っている。声が出ない。
目つきは悪いが基本的には社交的。
時々怠惰。結構よく喋る(ウィンドウに表示される量が多い)。
写真を撮るのが趣味。
よくカメラを持っていろいろな場所をうろうろしている。
ツクナミ区/高校辺りによく出没。
【異能について】
メッセージウィンドウが出る。
実体化させれば盾にも鈍器にもなるし座れる。
あと普通に文字が表示されます。
[]内描写/台詞はメッセージウィンドウに表示されている内容です。
【既知ロールについて】
適当に既知っぽい感じの話を振ってもらえたら合わせます。
・何らかの理由で話さない
・教室ではあまり見かけない
あたりを知っている前提で振って頂けるとスムーズです。
苦手な話題など特にないので適当に遊んで頂けると嬉しいです。
不穏RPも、当PCにいい印象を持ってないよ!も大丈夫です。
返信速度はまちまち。
あと別ツリーだと同じ場所でも別の時間軸扱いしたりします。
───────────
根岸こがね(ねぎし-)/153cm
右目に泣き黒子。お喋りで、最近は絵を描きはじめた。
学校には通っておらず、適当にいろいろなところに立ち寄ってはスケッチをしている。
白黒はっきりつけるのが好きで短気。
言いたいことははっきりと言うタイプ。
よくスケッチブックを持ってうろうろしている。
出現場所は色々。ツクナミにはあまりいない。
【異能について】
メッセージウィンドウが出る。
実体化させれば盾にも鈍器にもなるし座れる。
あと普通に文字が表示されます。
[]内描写/台詞はメッセージウィンドウに表示されている内容です。
____________________________
どちらも根岸こがねを名乗り、互いのことを知っている。
何方が偽物で、何方が本物かも、互いに知っている。
もし、二人の両方と知り合って会話を重ねることが出来れば、
何方が本物の根岸こがねか知る機会があるかもしれない。
連絡先(IBALINE)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2269
住んでいるところ(寮)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=839
※交流して頂いた方(台詞等)を日記にてお借りする場合があります。
問題等御座いましたらお声掛け頂けると幸いです。
根岸こがね(ねぎし-)/153cm/女
左目に泣き黒子。相良伊橋高校二年生。2-2に所属している。
高校はサボりがちなので校内で見かけることは少ない。
殆ど喋らず、コミュニケーションは専ら異能で作り出すメッセージウィンドウに頼り切っている。声が出ない。
目つきは悪いが基本的には社交的。
時々怠惰。結構よく喋る(ウィンドウに表示される量が多い)。
写真を撮るのが趣味。
よくカメラを持っていろいろな場所をうろうろしている。
ツクナミ区/高校辺りによく出没。
【異能について】
メッセージウィンドウが出る。
実体化させれば盾にも鈍器にもなるし座れる。
あと普通に文字が表示されます。
[]内描写/台詞はメッセージウィンドウに表示されている内容です。
【既知ロールについて】
適当に既知っぽい感じの話を振ってもらえたら合わせます。
・何らかの理由で話さない
・教室ではあまり見かけない
あたりを知っている前提で振って頂けるとスムーズです。
苦手な話題など特にないので適当に遊んで頂けると嬉しいです。
不穏RPも、当PCにいい印象を持ってないよ!も大丈夫です。
返信速度はまちまち。
あと別ツリーだと同じ場所でも別の時間軸扱いしたりします。
───────────
根岸こがね(ねぎし-)/153cm
右目に泣き黒子。お喋りで、最近は絵を描きはじめた。
学校には通っておらず、適当にいろいろなところに立ち寄ってはスケッチをしている。
白黒はっきりつけるのが好きで短気。
言いたいことははっきりと言うタイプ。
よくスケッチブックを持ってうろうろしている。
出現場所は色々。ツクナミにはあまりいない。
【異能について】
メッセージウィンドウが出る。
実体化させれば盾にも鈍器にもなるし座れる。
あと普通に文字が表示されます。
[]内描写/台詞はメッセージウィンドウに表示されている内容です。
____________________________
どちらも根岸こがねを名乗り、互いのことを知っている。
何方が偽物で、何方が本物かも、互いに知っている。
もし、二人の両方と知り合って会話を重ねることが出来れば、
何方が本物の根岸こがねか知る機会があるかもしれない。
連絡先(IBALINE)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=2269
住んでいるところ(寮)
http://lisge.com/ib/talk.php?p=839
※交流して頂いた方(台詞等)を日記にてお借りする場合があります。
問題等御座いましたらお声掛け頂けると幸いです。
20 / 30
71 PS
チナミ区
F-8
F-8





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | メッセージウィンドウ | 防具 | 30 | [効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| ウィンドスピア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:風痛撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増+護衛 | |
| センスデンジャー | 5 | 0 | 80 | 味列:AG増 | |
| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒーリングソング | [ 2 ]バトルソング |

PL / 鍋