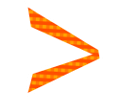<< 1:00>> 3:00




「なるほど、検査の結果を見るにお前の異能は変化型。
でも変化できるのはどうやら鳥獣だけ。魚や虫への変化は不可……と」
夕陽の差す部屋で、羽柴の言葉と紙にペンを走らせる音だけが響く。
美和はベッドの上に座り、腕のかさぶたを爪の先で掻きながら、ただ黙って話を聞いていた。
自室に椅子なんてものはないので、羽柴は床に直接座って美和を見上げている。
「怪我の具合は?」
「……俺は、平気」
少し嫌味っぽく一人称を強調した。
自分の能力によって怪我をした被害者――その一人は今まさに目の前にいる。
彼の腕や首に巻かれた包帯、体中に未だ残る痣が自分のしたことの重大さを物語っているようだった。
だから、自分が痛いとか辛いとか言うことが筋違いなのは、十分わかっていた。
流石に床に直接座るのは疲れるのだろう。羽柴は軽く体勢を直して小さく息を吐いた。
「突然のことで、一番驚いているのがお前ってことは俺だってわかっているつもりだ。
それに、こういう事は珍しくない。お前以外にも、そういう子供をたくさん見てきたよ」
そう言ってペンを動かすのをやめ、手帳の間に挟んで床に置くと真っ直ぐ俺を見てきた。
俺はその目から逃げるように顔を逸してしまう。
「下手したら、人殺しになってたかもしんねーけど?」
「でもそうはならなかった。俺が止めたからな。今後も俺が見てるから大丈夫だ。
能力のコントロールができるよう、卒業まで協力する。
キツイなら学校にはしばらく来る必要もない……まあお前はもともとサボりがちだったけどな。
ただ経過見るのにちょくちょくこっちに来る。親御さんも了承済みだ。
宿題も持ってくからちゃんとやれよ、引っ越すとはいえ一応高校には行くんだろ」
「………そういうの、"施設"の人間がやればよくね」
重い口からでた施設という単語――通称、異能力矯正センター。
近くの島にある施設で、《能力制御と社会復帰の支援》を謳っており、能力の暴走により被害を出したり、
人格に問題のある未成年の能力者が一定期間入所する場所だ。
――本来ならば、俺もそこに送られるはずだった。
「ばか言え。俺が施設の元職員で、直接未成年能力者のケアができるからって、
施設送りを止めるよう言ったんだぞ。あんなとこ行っても、お前なら能力を抑えつけられて余計暴走するのがオチだ」
「……そりゃどーも」
もちろん施設に行きたかったわけじゃない。
ただ自分の能力のせいで大怪我をした教師に、自分のメンタルケアを任せるというのは居心地が悪いというだけだ。
「俺のことなんてほっときゃいいのに」
「ま、こればっかりは俺の性分でね」
羽柴はなんでもないというようにそう言いのけ、床から立ち上がった。
「とにかく、今は怪我を治すことに専念しろよな。能力の制御はそれからだ。
後悔してるなら、この先また後悔しないよう俺の言う通りやってみるんだ」














ミツ(140) は 何かの殻 を入手!
カオル(217) は 何かの殻 を入手!
美和(568) は ぬめぬめ を入手!
サナエ(928) は ボロ布 を入手!
サナエ(928) は ねばねば を入手!
ミツ(140) は ねばねば を入手!
美和(568) は 甲殻 を入手!
美和(568) は ねばねば を入手!



付加LV を 2 DOWN。(LV20⇒18、+2CP、-2FP)
合成LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
フジハル(354) の持つ ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、どうでもよさげな物体 に変化させました!
ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
サナエ(928) の持つ ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成し、どうでもよさげな物体 に変化させました!
サナエ(928) により ItemNo.1 どうでもよさげな物体 から射程1の武器『ピアス』を作製してもらいました!
⇒ ピアス/武器:強さ33/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ヤシロ(932) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『貝柱だしの海鮮塩ラーメン』をつくってもらいました!
⇒ 貝柱だしの海鮮塩ラーメン/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
禍根(300) とカードを交換しました!
テストカード2 (ピンポイント)

パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
ペネトレイト を研究しました!(深度0⇒1)



特に何もしませんでした。






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
チャットが閉じられる――


















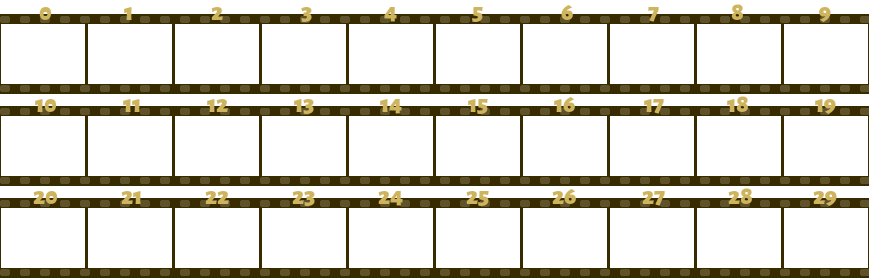





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「なるほど、検査の結果を見るにお前の異能は変化型。
でも変化できるのはどうやら鳥獣だけ。魚や虫への変化は不可……と」
夕陽の差す部屋で、羽柴の言葉と紙にペンを走らせる音だけが響く。
美和はベッドの上に座り、腕のかさぶたを爪の先で掻きながら、ただ黙って話を聞いていた。
自室に椅子なんてものはないので、羽柴は床に直接座って美和を見上げている。
「怪我の具合は?」
「……俺は、平気」
少し嫌味っぽく一人称を強調した。
自分の能力によって怪我をした被害者――その一人は今まさに目の前にいる。
彼の腕や首に巻かれた包帯、体中に未だ残る痣が自分のしたことの重大さを物語っているようだった。
だから、自分が痛いとか辛いとか言うことが筋違いなのは、十分わかっていた。
流石に床に直接座るのは疲れるのだろう。羽柴は軽く体勢を直して小さく息を吐いた。
「突然のことで、一番驚いているのがお前ってことは俺だってわかっているつもりだ。
それに、こういう事は珍しくない。お前以外にも、そういう子供をたくさん見てきたよ」
そう言ってペンを動かすのをやめ、手帳の間に挟んで床に置くと真っ直ぐ俺を見てきた。
俺はその目から逃げるように顔を逸してしまう。
「下手したら、人殺しになってたかもしんねーけど?」
「でもそうはならなかった。俺が止めたからな。今後も俺が見てるから大丈夫だ。
能力のコントロールができるよう、卒業まで協力する。
キツイなら学校にはしばらく来る必要もない……まあお前はもともとサボりがちだったけどな。
ただ経過見るのにちょくちょくこっちに来る。親御さんも了承済みだ。
宿題も持ってくからちゃんとやれよ、引っ越すとはいえ一応高校には行くんだろ」
「………そういうの、"施設"の人間がやればよくね」
重い口からでた施設という単語――通称、異能力矯正センター。
近くの島にある施設で、《能力制御と社会復帰の支援》を謳っており、能力の暴走により被害を出したり、
人格に問題のある未成年の能力者が一定期間入所する場所だ。
――本来ならば、俺もそこに送られるはずだった。
「ばか言え。俺が施設の元職員で、直接未成年能力者のケアができるからって、
施設送りを止めるよう言ったんだぞ。あんなとこ行っても、お前なら能力を抑えつけられて余計暴走するのがオチだ」
「……そりゃどーも」
もちろん施設に行きたかったわけじゃない。
ただ自分の能力のせいで大怪我をした教師に、自分のメンタルケアを任せるというのは居心地が悪いというだけだ。
「俺のことなんてほっときゃいいのに」
「ま、こればっかりは俺の性分でね」
羽柴はなんでもないというようにそう言いのけ、床から立ち上がった。
「とにかく、今は怪我を治すことに専念しろよな。能力の制御はそれからだ。
後悔してるなら、この先また後悔しないよう俺の言う通りやってみるんだ」





 |
ミツ 「ん、4人揃ったかな?まぁおれは大体知ってるような顔ばっかだけど。 おれ、妙名ミツ。こっちはバカ犬のみか」 自己紹介! |
 |
「…よく分からないけど、襲い掛かってくるやつは全部蹴散らせばいいのかな? 流石に一人で勝ち抜くのは厳しいな!味方や協力者は積極的に増やすべきだねえ」 |
 |
「…………」 ミツの言葉に不服そうながらも静かに鼻を鳴らす。 |





chimeRa
|
 |
鵺 -nue-
|



ミツ(140) は 何かの殻 を入手!
カオル(217) は 何かの殻 を入手!
美和(568) は ぬめぬめ を入手!
サナエ(928) は ボロ布 を入手!
サナエ(928) は ねばねば を入手!
ミツ(140) は ねばねば を入手!
美和(568) は 甲殻 を入手!
美和(568) は ねばねば を入手!



付加LV を 2 DOWN。(LV20⇒18、+2CP、-2FP)
合成LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
フジハル(354) の持つ ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、どうでもよさげな物体 に変化させました!
ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
サナエ(928) の持つ ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成し、どうでもよさげな物体 に変化させました!
サナエ(928) により ItemNo.1 どうでもよさげな物体 から射程1の武器『ピアス』を作製してもらいました!
⇒ ピアス/武器:強さ33/[効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ヤシロ(932) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『貝柱だしの海鮮塩ラーメン』をつくってもらいました!
⇒ 貝柱だしの海鮮塩ラーメン/料理:強さ33/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
 |
(ほかほかだ) |
禍根(300) とカードを交換しました!
テストカード2 (ピンポイント)

パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を研究しました!(深度0⇒1)
ペネトレイト を研究しました!(深度0⇒1)



特に何もしませんでした。






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |
 |
榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |
 |
ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |
シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
榊 「告知・・・・・ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!!」 |
 |
榊 「・・・・・」 |
 |
ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |
 |
榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |
 |
ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |
 |
ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
 |
榊 「・・・はぁい。」 |
チャットが閉じられる――







chimeRa
|
 |
ハイパー廃ビルおねぇちゃんと妹たち
|


ENo.568
獅童 美和



獅童美和(シドウ ミカズ)
175cm/16歳/男
地方出身のヤンキー。とある事情によりイバラシティへ引っ越してきた。
マガサ区にある轟木工業高校へ進学。父と2人暮らし。
好きなものはメンチカツと豚骨ラーメンと乳酸飲料。軽度の喫煙者。
短気で無愛想だが、気を許した相手にはかまってちゃんになる傾向がある。
近くに住んでいる従姉である沙和子によく世話になっており、バーガーショップで一緒にバイト中。
喧嘩っ早く口が悪いが、仲間思いでやたらつるみたがる。
素直でないとこはあるが、すぐ顔にでたりとわかりやすい。ただ笑うことはない。頭はあまりよくないが、無駄に運動神経がいい脳筋。
すぐ手が出るため、喧嘩も多く生傷が絶えない。
能力については中学生頃に発動。まだ使いこなせていない。
≪スキンウォーカー≫
動物の能力を使用したり、動物に変身する能力。
变化する度合いや能力についてはある程度調節が可能だが、まだ完全にコントロールできていない部分があるため、急激な感情の変化(驚き、激怒など)によっては、無意識に一部が獣化したりすることもある(耳が飛び出したり、牙・爪が生えるなど)
まとめ:https://shidowmikazu.tumblr.com/
175cm/16歳/男
地方出身のヤンキー。とある事情によりイバラシティへ引っ越してきた。
マガサ区にある轟木工業高校へ進学。父と2人暮らし。
好きなものはメンチカツと豚骨ラーメンと乳酸飲料。軽度の喫煙者。
短気で無愛想だが、気を許した相手にはかまってちゃんになる傾向がある。
近くに住んでいる従姉である沙和子によく世話になっており、バーガーショップで一緒にバイト中。
喧嘩っ早く口が悪いが、仲間思いでやたらつるみたがる。
素直でないとこはあるが、すぐ顔にでたりとわかりやすい。ただ笑うことはない。頭はあまりよくないが、無駄に運動神経がいい脳筋。
すぐ手が出るため、喧嘩も多く生傷が絶えない。
能力については中学生頃に発動。まだ使いこなせていない。
≪スキンウォーカー≫
動物の能力を使用したり、動物に変身する能力。
变化する度合いや能力についてはある程度調節が可能だが、まだ完全にコントロールできていない部分があるため、急激な感情の変化(驚き、激怒など)によっては、無意識に一部が獣化したりすることもある(耳が飛び出したり、牙・爪が生えるなど)
まとめ:https://shidowmikazu.tumblr.com/
25 / 30
90 PS
チナミ区
G-8
G-8





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | ピアス | 武器 | 33 | [効果1]器用10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | ||||
| 4 | 犬牙 | 武器 | 30 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程2】 |
| 5 | 怒り爪 | 装飾 | 30 | [効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 貝柱だしの海鮮塩ラーメン | 料理 | 33 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV25)[装飾]加速10(LV25) |
| 9 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]活力10(LV15) |
| 10 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 18 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 合成 | 5 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 決1 | エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 80 | 自:DF増(2T) | |
| アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 | |
| アドバンテージ | 5 | 0 | 80 | 敵:攻撃&AT奪取 | |
| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】[スキル使用設定不要]生産行動『効果付加』時、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]ペネトレイト | [ 3 ]ヒールハーブ |
| [ 1 ]パワフルヒール |

PL / るか