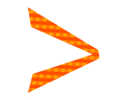<< 3:00~4:00




異形の姿を前にしても、その女、花勝見真菰は逃げる素振りを見せなかった。
それが奇妙に映ったのか、怪物は赤い目を僅かに細めた。
真菰は、自分の異能が身を守るのに全く役立たないことをよくわかっていた。
自分が次の数瞬で稼げる距離を、この怪物が軽々と超えてくるだろうことも。その爪が掠りでもすれば、自分の命などあっけなく絶たれるだろうことも。
怪物の体躯を見た瞬間に、わかってしまった。
だから、その場から動かなかった。
言葉を交わして時間を稼ぎ、逃げる隙を探す。
それが今、自分と自分の世界のために。自分がとれる最善の手段だと判断したからだ。
「……藻噛くん」
震えを押し殺して、努めて冷静に声をかける。
怪物の耳がぴくりと動く。生物らしい反応があることに、僅かに。ほんの僅かに安堵する。
「さっき、君の部屋で話したこと。覚えているかい?
そう、もしも侵略の噂が本当で、自分が侵略者だったとしたら、って話さ」
今にして思えばあの時、この話題を選んだのは、予感があったのかもしれない。
「見たところ君は侵略者で間違いないようだけど……ねえ、藻噛くん。
君はあの世界を手に入れて、どうしたいんだ。
そもそも、君は一体何なんだ?」
平静を装って問いかける。こちらを見る、この怪物の目には少なくとも知性が感じられる。
花勝見真菰は背を向けて全速力で逃げ出すことと、会話から情報を引き出しつつ隙を探ることを天秤にかけて、後者を選び取った。
「…………」
そんな真菰の思惑を知ってか知らずか、怪物は嘲笑うように口の端を引き上げた。長い腕を地面につくと、素早く鼻先で真菰の体を突き倒す。
ヒメシャガの花がいくつか千切れて舞い、虚空に消える。
「うぐ、」
咄嗟に避けることもできず尻餅をついたところに、怪物の顔がのしかかるように近付いた。無造作に体の左横に置かれた巨大な手が、倒れた真菰の腕を巻き込む。
次の瞬間、身を屈めた怪物の重量が真菰の左腕を圧し潰した。
「―――ッッ!!!!」
「……ああ、すみません。腕、踏んでましたね」
場違いなほど淡々とそう言って、怪物はぺろりと掌を舐めた。
暗赤色の舌で指にへばりついた肉と血を舐め取って、その顔が真菰を見下ろす。
「それで、何でしたっけ。
『何故侵略をするのか』と『俺が何なのか』……でしたか。
どうせ時間稼ぎのつもりだったんでしょうけど、聞きたいですか? 答え。
それとも、早く済ませた方がいいですかね」
巨大な頭部が斜めに傾ぐ。それはまるで人間が首を傾げるような仕草の、あの後輩が時折見せる癖の、醜悪なパロディだった。
藻噛叢馬は花勝見真菰の異能を知っている。
彼女の異能が脅威でないことを、この怪物は知っている。
単純な暴力で叩き潰せる相手を逃がすつもりも、生かしておくつもりもない。
潰したのが足でなかったのは、或いは無意識の慢心だったのかもしれないが。どちらにしろ状況はそう変わらない。
「ひ、」
飄々とした佇まい、超然として捉えどころのない、隙のない冷静沈着な女。
そう見えるように意識的に装っていても、花勝見真菰の精神は普通の範疇に収まる人間のそれだ。
不自由らしい不自由もなく生きてきた、ごく普通に恵まれた環境で育った学生だ。
だから、目の前にある死に、今この瞬間身を苛む痛みに、耐えられなかった。
それを齎す相手が知己であることを想定していたつもりでも。それなりに好ましく思っていた人間の顔と声をした怪物を、ただの人間は受け入れられなかった。
平静を装い続けることが、できなかった。
噴き出した汗で体中がじっとりと濡れている。視界が涙で霞む。噛み締めた唇からは血の味がした。
震える脚で立ち上がろうと藻掻いても、這って逃げようと身を捩っても、すぐ上に怪物の顔があるせいでそれも叶わない。潰された左腕の痛みが、その気力すらも奪っていく。
――死ぬ。殺される。
心臓が掴まれるような恐ろしい予感に、真菰は顔が引き攣るのを自覚した。
「いいですね、その顔」
平坦な声が降ってくる。その声は紛れもなく後輩のもので、その台詞も聞いた覚えがある。
いっそ似ているだけの別物だったら、まだマシだったのかもしれない。
けれど、怪物が話せば話すほど、似ていると思ってしまう。
この醜悪な怪物は紛れもなくあの後輩なのだと、わかってしまう。
「やっぱり答えることにします。
俺は人食いの怪物なので、答えたら先輩を食べますけど、最後まで聞いていてくださいね」
そう宣言して、怪物は鼻先を真菰の喉元に押しつけた。
赤く艶やかな眼球に、涙でぐしゃぐしゃになった真菰の顔が映っている。
「侵略の理由なんて簡単です。俺はイバラシティの海が欲しい。
俺は海で生まれたから、海に帰りたいんです。アンジニティの海じゃない、美しい海に」
――"時々、俺の帰る場所はあの海なんじゃないかって思うんです"。
それは、いつか聞いた後輩の言葉だ。
淡々とした温度のない声が、怪物が話す度に吐き散らされる、噎せ返るような海の臭気に重なる。
「俺が何なのかについては、説明するのは難しいんですけど」
怪物は少し考えるような素振りを見せた。
その言葉の切り方が、改めて言葉を紡ぐ前の息遣いが、どうしようもなく似ている。
「……やめてくれ」
だから。
「先輩には俺の研究、少し話したことあるんで知ってますよね。
――海の怪異。怪物。伝説。
俺のいた世界では、もう誰も信じないし、畏れない。俺達は忘れられたんです。
笑えますよね。俺達を生み出したのは人間自身だっていうのに」
「もう……やめて、」
それ以上、その声で話さないでくれ。そう、思ってしまう。
「消えたくなくて、あちこちに逃げましたよ。
まだ海を畏れる人間のいる場所を探して、探して、辿り着いた先でそこにいたものと混ざって、それでも消えたくなくて。ずっと、ずっと走って、泳いできたんです。
……でも、結局は忘れられた。
それが俺の、元の世界での最期です」
懇願めいた細い声を無視して、ぺた、と馬のような耳を伏せてから。
怪物は自嘲するように唇を歪めた。
「あの世界で忘れられた、海の怪異の寄せ集め。そんなところですかね。
――だから」
真菰を見下ろす、濡れたような赤い瞳がぎらつく。
大きく横に裂けた口から涎がとめどなく溢れて、落ちて、滴った。
「恐れろ。怖れろ。畏れろ。
溺れるような顔を見せろ。
その細い腕でもっと、もっと藻掻いて見せろ」
怪物は真菰の顔を覗き込む。
恐怖に歪んだその表情に、歯を剥き出して獰猛に笑う。
これは人とは相容れない化け物だと。
人を畏れさせてこその人でなしだと。
まるでそれが存在意義だとでも言うように。
「ああ、その顔だ。その顔がもっと見たい。
先輩の感じている恐怖こそが、俺の存在を補強してくれるんです」
真菰の体に怪物の手がかかる。女の首を絞めるように、細い体を掴む。
万力のような力で締め上げられて、体中のあちこちで骨が軋む。
「ひぎッ……ぃ、やだ、やめ、いたぃ、……っあ、ああ、ぁ……ぅ……」
その痛みは途切れかけていた真菰の意識を無理やり引き戻し、文字通り絞り出すような悲鳴を上げさせた。
「ふ……っ、ふ、ぅ、っく、うう、……」
そうだ、なにか言わなくては。少しでも、この時間を引き延ばさなければ。
――終わらせてほしい。終わらせてほしい。こんなのはもうたくさんだ。
誰かの助けは期待していない。
そんなものを求めるなら、最初から背を向けて逃げ出していた。
――痛い、痛い、いたい、くるしい、こわい、しにたくない、
侵略の噂が本当で、侵略者達があの愛しい世界を侵そうとしているならば。
目の前の怪物が、本能に従ってあの世界を侵略しようと言うのならば。
――だってわたしは、やっとゆめがかなって、これからやりたいことだってたくさんあって、
――でも、でも、でも!
このままこうして、この怪物を少しでもここに引き留めておくことが、きっと私にできる最善だ。
潰れそうな意識の中で、花勝見真菰は恐怖から目を逸らすように、それだけを考えようとしていた。
食い込んだナイフのような爪は容易く肉を裂く。痛みが決意を、覚悟を、鈍らせる。
それでも、そんなことはお構いなしに、最期の時はやってくる。
「ねえ、もっとよく見せてください」
体のどこかで、致命的な何かが折れる音がした。
――ああ、いまのことばも、どこかできいた。
ぼんやりとそう思ったのを最後に、真菰の意識はぷっつりと途絶えた。
***
「……あちら側の記憶が流れてくるたび、腹が減って仕方がなかった」
花勝見真菰の体をあらかた喰い終わった後、手についた血を舐めながら怪物は呟いた。
花畑のように咲いていたヒメシャガは、もう花弁一枚も残っていない。
ただ伝承通りに打ち捨てられた臓物の一部だけが、乾きかけた表面を晒している。
「それに、そう、あちら側の俺の真似も、なかなかうまくいった」
地面に顔を近づけて、残った血や肉の欠片を探しながら、今しがた喰った女の顔を思い返す。
怪物は藻噛叢馬の知己と話す上で、声色を、話し方を、呼び方を、口癖を、意識的に真似ていた。そのことが相手の心理にどう影響するのか、量るために。
対面した状態で試したのは初めてだったが、あの女の様子を見るに、それなりに効果的だったようだ。問題はあの口調がどうにも面倒臭いというところだが、まあ仕方ない。
「しかし、つい興奮して話しすぎたな。まあ、喰ったから同じか」
自分というものの成り立ちについて、あそこまで話すつもりはなかった。
それはこの成れ果ての怪異が舐めた、敗北と屈辱の歴史だ。

――美しい海馬の棲む海辺は消えた。

――荒れ狂う赤き人馬は島を追われた。

――船乗りが恐れた魔の海域にあったのは、ただ漂うだけの噂のみ。
畏れられなくなった怪異の寄せ集めは、この地で再び息を吹き返した。
そこに恐怖する人間がいる限り、その歩みが止まることはない。
***
――狭間での時間が終わる。
それは一瞬にも満たない時間。
人間ひとり、喰い殺した怪物の記憶は表には残らない。
それは藻噛叢馬が知ることのない出来事だ。
・・・・・・・・・・
だから今この瞬間、無意識に指先を舐めたことの意味を、男が理解することはない。
「……そういえば先輩、さっき何か言いかけてたな」
先程出て行った彼女の言葉をふと、思い出す。
――"君のところの教授"。
第二学群海洋生物学専攻教授、斑目水緒について。
「……まあ、いいか」
自分には関係ないことだ。そう決めつけて、思考の端から追い出して、それっきり。
――それは確かに、一人と一匹にとっての分岐点だった。



ENo.71 りりこ とのやりとり

ENo.158 不浄の滝 とのやりとり

ENo.173 タウラシアス とのやりとり

ENo.593 Hǝɯɐʇᴉʇǝ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 シーフードドリアもどき を食べました!
体調が 0 回復!(30⇒30)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



不浄の滝(158) から 10 PS 受け取りました。
セオリ(801) に 5 PS 送付しました。
駄石(50 PS)を購入しました。
武術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
セオリ(801) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
不浄の滝(158) の持つ ItemNo.8 韮 から防具『虚ろの鎖』を作製しました!
グラウティア(184) とカードを交換しました!
大咆哮 (ブレイブハート)
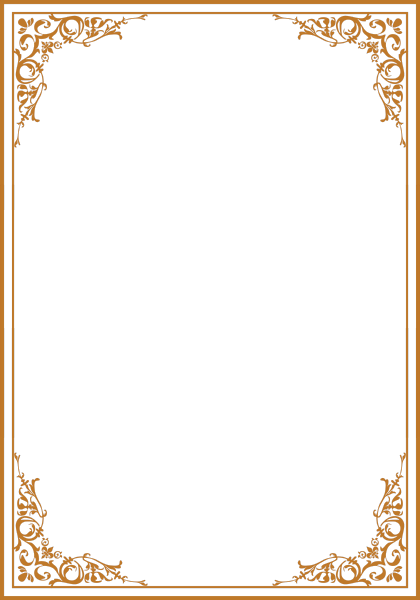
ナース を研究しました!(深度0⇒1)
ナース を研究しました!(深度1⇒2)
ナース を研究しました!(深度2⇒3)
イレイザー を習得!
チャクラグラント を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



悪意の魔女(103) は 毛 を入手!
悪意の魔女(103) は 毛 を入手!
ナックラヴィー(502) は ボロ布 を入手!
悪意の魔女(103) は ボロ布 を入手!
悪意の魔女(103) は 皮 を入手!
ダーシャ(1232) は 皮 を入手!
悪意の魔女(103) は 皮 を入手!
ナックラヴィー(502) は 皮 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
悪意の魔女(103) のもとに 大黒猫 が空を見上げなから近づいてきます。
悪意の魔女(103) のもとに 歩行軍手 が泣きながら近づいてきます。



次元タクシーに乗り チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 に転送されました!
悪意の魔女(103) がパーティから離脱しました!
タウラシアス(173) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 K-16(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 L-15(草原)に移動!(体調26⇒25)
タウラシアス(173) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- タウラシアス(173) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- タウラシアス(173) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- ナックラヴィー(502) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)





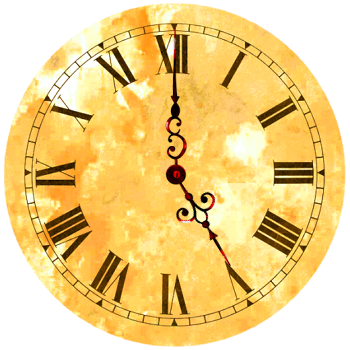
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。

ノウレットから遠く離れる白南海。
遠く離れた白南海を手招く。
チャットが閉じられる――











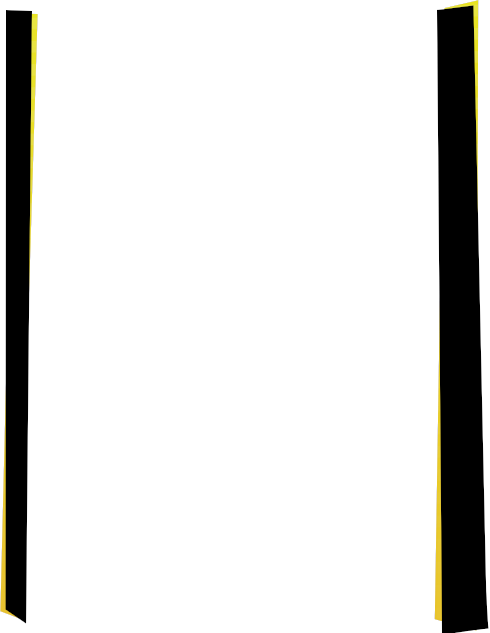
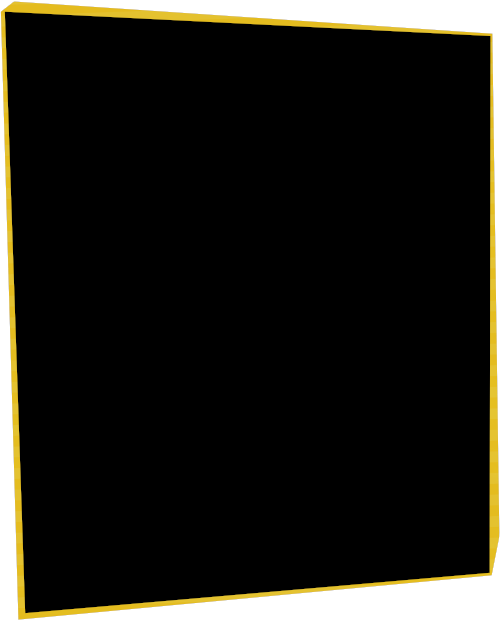





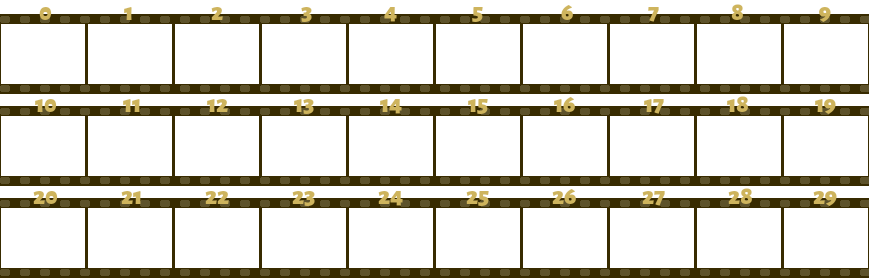







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



異形の姿を前にしても、その女、花勝見真菰は逃げる素振りを見せなかった。
それが奇妙に映ったのか、怪物は赤い目を僅かに細めた。
真菰は、自分の異能が身を守るのに全く役立たないことをよくわかっていた。
自分が次の数瞬で稼げる距離を、この怪物が軽々と超えてくるだろうことも。その爪が掠りでもすれば、自分の命などあっけなく絶たれるだろうことも。
怪物の体躯を見た瞬間に、わかってしまった。
だから、その場から動かなかった。
言葉を交わして時間を稼ぎ、逃げる隙を探す。
それが今、自分と自分の世界のために。自分がとれる最善の手段だと判断したからだ。
「……藻噛くん」
震えを押し殺して、努めて冷静に声をかける。
怪物の耳がぴくりと動く。生物らしい反応があることに、僅かに。ほんの僅かに安堵する。
「さっき、君の部屋で話したこと。覚えているかい?
そう、もしも侵略の噂が本当で、自分が侵略者だったとしたら、って話さ」
今にして思えばあの時、この話題を選んだのは、予感があったのかもしれない。
「見たところ君は侵略者で間違いないようだけど……ねえ、藻噛くん。
君はあの世界を手に入れて、どうしたいんだ。
そもそも、君は一体何なんだ?」
平静を装って問いかける。こちらを見る、この怪物の目には少なくとも知性が感じられる。
花勝見真菰は背を向けて全速力で逃げ出すことと、会話から情報を引き出しつつ隙を探ることを天秤にかけて、後者を選び取った。
「…………」
そんな真菰の思惑を知ってか知らずか、怪物は嘲笑うように口の端を引き上げた。長い腕を地面につくと、素早く鼻先で真菰の体を突き倒す。
ヒメシャガの花がいくつか千切れて舞い、虚空に消える。
「うぐ、」
咄嗟に避けることもできず尻餅をついたところに、怪物の顔がのしかかるように近付いた。無造作に体の左横に置かれた巨大な手が、倒れた真菰の腕を巻き込む。
次の瞬間、身を屈めた怪物の重量が真菰の左腕を圧し潰した。
「―――ッッ!!!!」
「……ああ、すみません。腕、踏んでましたね」
場違いなほど淡々とそう言って、怪物はぺろりと掌を舐めた。
暗赤色の舌で指にへばりついた肉と血を舐め取って、その顔が真菰を見下ろす。
「それで、何でしたっけ。
『何故侵略をするのか』と『俺が何なのか』……でしたか。
どうせ時間稼ぎのつもりだったんでしょうけど、聞きたいですか? 答え。
それとも、早く済ませた方がいいですかね」
巨大な頭部が斜めに傾ぐ。それはまるで人間が首を傾げるような仕草の、あの後輩が時折見せる癖の、醜悪なパロディだった。
藻噛叢馬は花勝見真菰の異能を知っている。
彼女の異能が脅威でないことを、この怪物は知っている。
単純な暴力で叩き潰せる相手を逃がすつもりも、生かしておくつもりもない。
潰したのが足でなかったのは、或いは無意識の慢心だったのかもしれないが。どちらにしろ状況はそう変わらない。
「ひ、」
飄々とした佇まい、超然として捉えどころのない、隙のない冷静沈着な女。
そう見えるように意識的に装っていても、花勝見真菰の精神は普通の範疇に収まる人間のそれだ。
不自由らしい不自由もなく生きてきた、ごく普通に恵まれた環境で育った学生だ。
だから、目の前にある死に、今この瞬間身を苛む痛みに、耐えられなかった。
それを齎す相手が知己であることを想定していたつもりでも。それなりに好ましく思っていた人間の顔と声をした怪物を、ただの人間は受け入れられなかった。
平静を装い続けることが、できなかった。
噴き出した汗で体中がじっとりと濡れている。視界が涙で霞む。噛み締めた唇からは血の味がした。
震える脚で立ち上がろうと藻掻いても、這って逃げようと身を捩っても、すぐ上に怪物の顔があるせいでそれも叶わない。潰された左腕の痛みが、その気力すらも奪っていく。
――死ぬ。殺される。
心臓が掴まれるような恐ろしい予感に、真菰は顔が引き攣るのを自覚した。
「いいですね、その顔」
平坦な声が降ってくる。その声は紛れもなく後輩のもので、その台詞も聞いた覚えがある。
いっそ似ているだけの別物だったら、まだマシだったのかもしれない。
けれど、怪物が話せば話すほど、似ていると思ってしまう。
この醜悪な怪物は紛れもなくあの後輩なのだと、わかってしまう。
「やっぱり答えることにします。
俺は人食いの怪物なので、答えたら先輩を食べますけど、最後まで聞いていてくださいね」
そう宣言して、怪物は鼻先を真菰の喉元に押しつけた。
赤く艶やかな眼球に、涙でぐしゃぐしゃになった真菰の顔が映っている。
「侵略の理由なんて簡単です。俺はイバラシティの海が欲しい。
俺は海で生まれたから、海に帰りたいんです。アンジニティの海じゃない、美しい海に」
――"時々、俺の帰る場所はあの海なんじゃないかって思うんです"。
それは、いつか聞いた後輩の言葉だ。
淡々とした温度のない声が、怪物が話す度に吐き散らされる、噎せ返るような海の臭気に重なる。
「俺が何なのかについては、説明するのは難しいんですけど」
怪物は少し考えるような素振りを見せた。
その言葉の切り方が、改めて言葉を紡ぐ前の息遣いが、どうしようもなく似ている。
「……やめてくれ」
だから。
「先輩には俺の研究、少し話したことあるんで知ってますよね。
――海の怪異。怪物。伝説。
俺のいた世界では、もう誰も信じないし、畏れない。俺達は忘れられたんです。
笑えますよね。俺達を生み出したのは人間自身だっていうのに」
「もう……やめて、」
それ以上、その声で話さないでくれ。そう、思ってしまう。
「消えたくなくて、あちこちに逃げましたよ。
まだ海を畏れる人間のいる場所を探して、探して、辿り着いた先でそこにいたものと混ざって、それでも消えたくなくて。ずっと、ずっと走って、泳いできたんです。
……でも、結局は忘れられた。
それが俺の、元の世界での最期です」
懇願めいた細い声を無視して、ぺた、と馬のような耳を伏せてから。
怪物は自嘲するように唇を歪めた。
「あの世界で忘れられた、海の怪異の寄せ集め。そんなところですかね。
――だから」
真菰を見下ろす、濡れたような赤い瞳がぎらつく。
大きく横に裂けた口から涎がとめどなく溢れて、落ちて、滴った。
「恐れろ。怖れろ。畏れろ。
溺れるような顔を見せろ。
その細い腕でもっと、もっと藻掻いて見せろ」
怪物は真菰の顔を覗き込む。
恐怖に歪んだその表情に、歯を剥き出して獰猛に笑う。
これは人とは相容れない化け物だと。
人を畏れさせてこその人でなしだと。
まるでそれが存在意義だとでも言うように。
「ああ、その顔だ。その顔がもっと見たい。
先輩の感じている恐怖こそが、俺の存在を補強してくれるんです」
真菰の体に怪物の手がかかる。女の首を絞めるように、細い体を掴む。
万力のような力で締め上げられて、体中のあちこちで骨が軋む。
「ひぎッ……ぃ、やだ、やめ、いたぃ、……っあ、ああ、ぁ……ぅ……」
その痛みは途切れかけていた真菰の意識を無理やり引き戻し、文字通り絞り出すような悲鳴を上げさせた。
「ふ……っ、ふ、ぅ、っく、うう、……」
そうだ、なにか言わなくては。少しでも、この時間を引き延ばさなければ。
――終わらせてほしい。終わらせてほしい。こんなのはもうたくさんだ。
誰かの助けは期待していない。
そんなものを求めるなら、最初から背を向けて逃げ出していた。
――痛い、痛い、いたい、くるしい、こわい、しにたくない、
侵略の噂が本当で、侵略者達があの愛しい世界を侵そうとしているならば。
目の前の怪物が、本能に従ってあの世界を侵略しようと言うのならば。
――だってわたしは、やっとゆめがかなって、これからやりたいことだってたくさんあって、
――でも、でも、でも!
このままこうして、この怪物を少しでもここに引き留めておくことが、きっと私にできる最善だ。
潰れそうな意識の中で、花勝見真菰は恐怖から目を逸らすように、それだけを考えようとしていた。
食い込んだナイフのような爪は容易く肉を裂く。痛みが決意を、覚悟を、鈍らせる。
それでも、そんなことはお構いなしに、最期の時はやってくる。
「ねえ、もっとよく見せてください」
体のどこかで、致命的な何かが折れる音がした。
――ああ、いまのことばも、どこかできいた。
ぼんやりとそう思ったのを最後に、真菰の意識はぷっつりと途絶えた。
***
「……あちら側の記憶が流れてくるたび、腹が減って仕方がなかった」
花勝見真菰の体をあらかた喰い終わった後、手についた血を舐めながら怪物は呟いた。
花畑のように咲いていたヒメシャガは、もう花弁一枚も残っていない。
ただ伝承通りに打ち捨てられた臓物の一部だけが、乾きかけた表面を晒している。
「それに、そう、あちら側の俺の真似も、なかなかうまくいった」
地面に顔を近づけて、残った血や肉の欠片を探しながら、今しがた喰った女の顔を思い返す。
怪物は藻噛叢馬の知己と話す上で、声色を、話し方を、呼び方を、口癖を、意識的に真似ていた。そのことが相手の心理にどう影響するのか、量るために。
対面した状態で試したのは初めてだったが、あの女の様子を見るに、それなりに効果的だったようだ。問題はあの口調がどうにも面倒臭いというところだが、まあ仕方ない。
「しかし、つい興奮して話しすぎたな。まあ、喰ったから同じか」
自分というものの成り立ちについて、あそこまで話すつもりはなかった。
それはこの成れ果ての怪異が舐めた、敗北と屈辱の歴史だ。

アハ・イシュケ
馬のかたちをした海の魔物。
人慣れした美しい馬の姿で現れるが、本性は獰猛な捕食者である。
人慣れした美しい馬の姿で現れるが、本性は獰猛な捕食者である。
――美しい海馬の棲む海辺は消えた。

ナックラヴィー
スコットランドはオークニー諸島に伝わる、赤い肌の半人半馬。
異様に長い両腕で人や家畜を絞め殺す怪異。
真水を忌み嫌う。
異様に長い両腕で人や家畜を絞め殺す怪異。
真水を忌み嫌う。
――荒れ狂う赤き人馬は島を追われた。
サルガッソー海
『藻海』。『粘りつく海』。『船の墓場』。
北大西洋に位置する、多くの船が沈んだ『魔の海域』。
ただし、事実としてそういった記録は残っていない。
北大西洋に位置する、多くの船が沈んだ『魔の海域』。
ただし、事実としてそういった記録は残っていない。
――船乗りが恐れた魔の海域にあったのは、ただ漂うだけの噂のみ。
畏れられなくなった怪異の寄せ集めは、この地で再び息を吹き返した。
そこに恐怖する人間がいる限り、その歩みが止まることはない。
***
――狭間での時間が終わる。
それは一瞬にも満たない時間。
人間ひとり、喰い殺した怪物の記憶は表には残らない。
それは藻噛叢馬が知ることのない出来事だ。
・・・・・・・・・・
だから今この瞬間、無意識に指先を舐めたことの意味を、男が理解することはない。
「……そういえば先輩、さっき何か言いかけてたな」
先程出て行った彼女の言葉をふと、思い出す。
――"君のところの教授"。
第二学群海洋生物学専攻教授、斑目水緒について。
「……まあ、いいか」
自分には関係ないことだ。そう決めつけて、思考の端から追い出して、それっきり。
――それは確かに、一人と一匹にとっての分岐点だった。



ENo.71 りりこ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.158 不浄の滝 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.173 タウラシアス とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.593 Hǝɯɐʇᴉʇǝ とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



| シーラ 「待ちなさい、ダーシャ… …“守護者”ですって―― 石橋は叩いてわたらないと!長生きの秘訣よね 魔物を呼ぶわ。」 |
| 魔女は髪飾りを手に持ち、とがった部分で魔法陣を描き出す。 |
 |
「・・・・・・・・ ・・・・・・・・・」 |
| シーラ 「 今に魔物が寄って来る―― ほら!」 「…あら?刻印がないわ。わたしの魔物じゃない…? … もしかして。 あははは、まあいいのだわ。 ねえ、あなたがた人間の言葉はわかるかしら。 はじめまして、わたしは魔女のドーラ・シーラ。 すこしお時間いただけます? あなた方にお見せするわ、 なぜ魔物と魔女というものがなぜ親しいのか…」 |
 |
タウラシアス 「斧に当たっても文句は言うなよ?不用意に近付いたお前らが悪いんだぜ」 |
| 「…………おまえ、」 ヒトの女と見て匂いを嗅ごうと屈みかけて、ぴたりと止まった。 そのまま一歩、二歩と後じさり、不可解そうに騎士の方を見る。 |
| 「……おまえ、よくこんなのと行動を共にしているな」 女の持つ得体の知れない雰囲気が気に喰わないのか、うろうろと遠巻きにしている…… |
 |
ただ魔女の傍に控えている。 |
ItemNo.7 シーフードドリアもどき を食べました!
「作った奴の方がうまそうなんだよなァ……」 |
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





魔女と騎士
|
 |
かすかちゃん’sハーレム
|



チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
魔女と騎士
|
 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



不浄の滝(158) から 10 PS 受け取りました。
| 清 「はい、お金。食べ物じゃなくてごめんなさいね。 わたしは暫く一緒に行けないから、 食べ物を買う足しにでもしておいて」 |
| 清 「ああ、道を作りに行くんです。 一人二人は、先行偵察って必要でしょう? 深谷がいるから、こっちは大丈夫」 「……また、そのうちに。運が良ければまた会いましょう」 |
セオリ(801) に 5 PS 送付しました。
駄石(50 PS)を購入しました。
武術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
セオリ(801) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
不浄の滝(158) の持つ ItemNo.8 韮 から防具『虚ろの鎖』を作製しました!
グラウティア(184) とカードを交換しました!
大咆哮 (ブレイブハート)
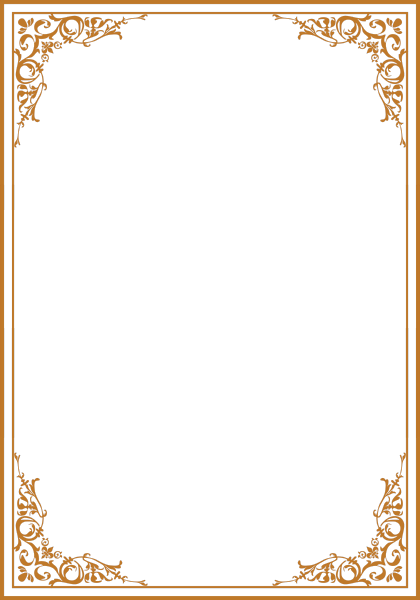
ナース を研究しました!(深度0⇒1)
ナース を研究しました!(深度1⇒2)
ナース を研究しました!(深度2⇒3)
イレイザー を習得!
チャクラグラント を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



悪意の魔女(103) は 毛 を入手!
悪意の魔女(103) は 毛 を入手!
ナックラヴィー(502) は ボロ布 を入手!
悪意の魔女(103) は ボロ布 を入手!
悪意の魔女(103) は 皮 を入手!
ダーシャ(1232) は 皮 を入手!
悪意の魔女(103) は 皮 を入手!
ナックラヴィー(502) は 皮 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
悪意の魔女(103) のもとに 大黒猫 が空を見上げなから近づいてきます。
悪意の魔女(103) のもとに 歩行軍手 が泣きながら近づいてきます。



次元タクシーに乗り チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ほら降りた降りた。次の客が待ってんだわ。」 |
悪意の魔女(103) がパーティから離脱しました!
タウラシアス(173) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 K-16(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 L-15(草原)に移動!(体調26⇒25)
タウラシアス(173) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- タウラシアス(173) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- タウラシアス(173) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- ナックラヴィー(502) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)





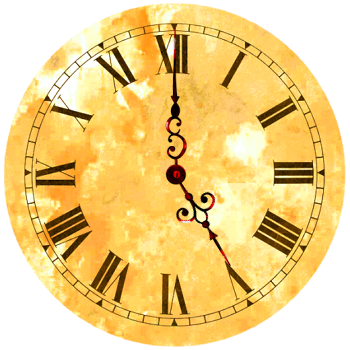
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「ん・・・・・」 |
 |
エディアン 「これは・・・・・」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「なんでしょうこれ!変な情報が映し出されてますねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・つーか何でまた一緒の部屋入ってるんですかね。」 |
 |
エディアン 「いいじゃないですかぁ!案外ヒマじゃないですか?案内役。」 |
 |
白南海 「私はひとりがいいんです、が、ね。」 |
 |
エディアン 「くッッらいですねぇ・・・・・クール気取りですか一匹狼気取りですか、まったく。」 |
 |
白南海 「うっせーオンナが嫌いなだけです。」 |
 |
エディアン 「・・・そういう発言、嫌われますよぉ?」 |
 |
白南海 「貴方も、ね。」 |
 |
エディアン 「――さて、まぁいいとしてこのログ?は何なんですかねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・・・仕方ねぇですね。・・・おーい、クソ妖精ー。」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!ノウレットはいつでも貴方の背後から―――ッ!!」 |
 |
エディアン 「あぁなるほどノウレットちゃん!」 |
 |
エディアン 「・・・っていうかクソ妖精って――」 |
 |
ノウレット 「あだ名をいただいちゃいました☆」 |
 |
白南海 「――ほれ、Cross+Roseに変な情報出てんぞ説明しろ。」 |
 |
ノウレット 「うおおぉぉぉ頼られてます!?もしかして頼られてますッ!!?」 |
ノウレットから遠く離れる白南海。
 |
ノウレット 「どうして離れていくんですッ!!!?」 |
 |
ノウレット 「これはですねぇ!チェックポイント開放者数の情報ですっ!!」 |
 |
エディアン 「えぇえぇ、それはまぁそうかなーとは。右側の1000って数字はなんでしょう? もしかして開放できる人数が限られてる・・・とか?」 |
 |
ノウレット 「いえいえー!開放は皆さんできますよーっ!! これはハザマにいる全員に新たな力を与えるという情報です!!」 |
 |
エディアン 「新たな力・・・?」 |
 |
ノウレット 「そうでぇっす!!各チェックポイントの開放者数が増えるほど、対応する力が強く与えられます! 1000というのは1000人より上は1000人として扱うってことです!!」 |
 |
エディアン 「なるほどなるほど。これ・・・・・敵も味方も、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!全部が全部、ハザマの全員でーす!!」 |
 |
エディアン 「具体的に、どんな力が与えられるんです?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・はーい、大丈夫ですよー。」 |
 |
エディアン 「これは言葉からイメージして実感してみるしかないですかね。 出てくる敵にも力が・・・・・気をつけないといけませんね。」 |
 |
エディアン 「・・・・・白南海さーん!聞きましたよー。」 |
遠く離れた白南海を手招く。
 |
白南海 「――まぁ聞こえていたわけですが。離れても音量変わらなかったわけですが。」 |
 |
エディアン 「・・・ノウレットちゃんの音量調整できますよ?コンフィグで。」 |
 |
白南海 「・・・・・ぁー、よくわかんねぇめんどくせぇ。」 |
 |
エディアン 「まったく、こういうのダメな人ですか。右上のここから・・・ほら、音量設定。あるでしょ。 それから・・・・・あぁ違いますって!それだとチャッ――」 |
チャットが閉じられる――









ENo.502
藻噛 叢馬

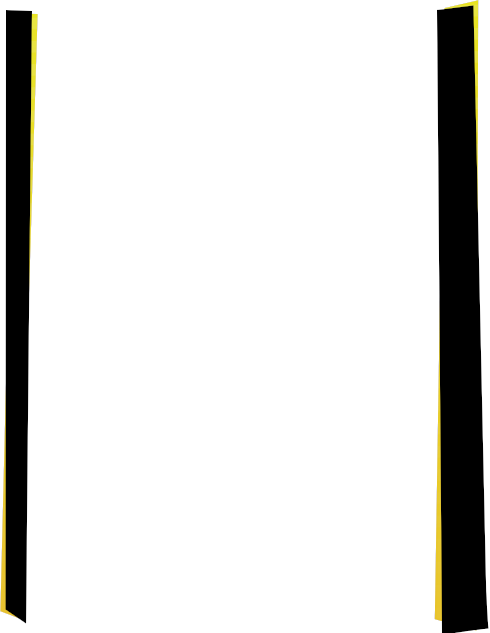
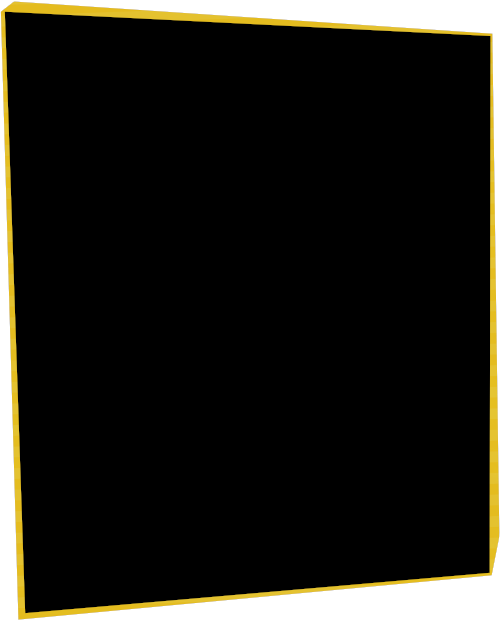
藻噛 叢馬(もがみ そうま)
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。
長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
人の噂が噂を呼び、死の海域と畏れられた美しい海《サルガッソー海》。
忘れ去られ、"否定"された海の怪異が寄り集まったばけもの。
それがこの怪物の正体である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。
長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
人の噂が噂を呼び、死の海域と畏れられた美しい海《サルガッソー海》。
忘れ去られ、"否定"された海の怪異が寄り集まったばけもの。
それがこの怪物の正体である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
25 / 30
231 PS
チナミ区
L-15
L-15




















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 海棲馬の蹄 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 幻想藻の鬣 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | わたあめ | 料理 | 45 | 治癒13 | 充填13 | 増幅13 | |
| 7 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]幸運10(LV20) | |||
| 8 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]朦朧10(LV20)[防具]体力10(LV10)[装飾]増勢10(LV25) | |||
| 9 | 巻き込んだ石ころ | 魔晶 | 20 | 幸運10 | - | 充填6 | |
| 10 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 13 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 防具 | 40 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| 決2 | クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| 決3 | クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| デッドライン | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| 決1 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| チャクラグラント | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 異形の膂力 (猛攻) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 怪物の体躯 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 否定への憤怒 (攻勢) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 幻想海・サルガッソー (五月雨) | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
夢喰花 (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
≪s@4dw≫ (ダークネス) |
0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
|
塩弾 (ストーンブラスト) |
0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
|
大咆哮 (ブレイブハート) |
0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ナース | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]ノーマライズ |
| [ 3 ]リザレクション | [ 3 ]ファーマシー |

PL / こか