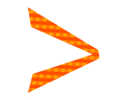<< 3:00~4:00





百物語 4話『怪馬』

『怪馬』イバラシティサイド
幼いころから、繰り返し見る夢があった。
白い空間を馬車が走っていて、私がそれを眺めている。
夢の中は物理法則がうやむやで、念じれば、馬車を追い越す速さで走ることが出来た。
荷車を引く馬――この世の物とは思えない玉虫色の馬は、首の先に人間の顔がついている。
その人間の顔とは、大抵私の良く知っている人だった。誰の顔か認識した瞬間目が覚めるのがお決まりだ。
言葉にすると大層不気味だけれど、夢の中の私はそれを気味が悪いとは思わなかった。
不思議というのは、ここからだ。
その夢をみたあと、馬の顔になっていた人と私とは、決まって離れ離れになるのだった。
ひっこしだったり習い事をやめたり…この夢はいつもその予兆だった。
「今日、久しぶりにその夢を見たの」
「家族なのに?転勤とか、まさか死ぬって事はないだろうけれど…」
「縁起でもないこと言わないでよ、本当に。体調は今はいいの?」
「ここしばらくは驚くくらいいいけどねえ…」
紛れもない、最愛の夫の顔を見た。
これまで、寂しい予兆とは言えど害という害はないものだったし、馬の夢の事は余り気にせずに生きてきた。
しかし今回ばかりはどうにも気がかりだった。
夫と別れることはないだろうし、転職や引っ越し…他のどんな理由でも、家族がはなればなれにはならない。
それに夫には持病がある。病気があるから職場だって転勤なんて負担のかかることは直ぐに命じたりはしないだろうし、
…病気。悪い想像が頭から離れない。
それで、私は幾年ぶりかに母校を訪れていた。
この場所には、女学生だけが知る『不思議な存在』がいた。
「カラスヨ カラス、ナゼニトブ ワタミヲ カワズト オモウテカ」
旧校舎裏、百葉箱。その前に立ってカラスの羽根を振りながら、呪文を唱える。すると――
「よばれてとびでてどろろろろ~っ
…あら!ずいぶんオトナになって。
最期にあったのは、卒業式の日以来かしら。」
「ごきげんよう、『百葉箱のしぃらさん』」
・・・
「なるほど。
ありがとう、それはギバ子さんね。
でも、悪さをしたわけではないのね?」
事のあらましを話し終って、私はこくりと肯く。
「予知をしたことは…あなたにとってもいい事かも。
たとえば、あなたのダーリンが、浮気をして
あなたがもう別れたい!ってなるとか?」
「ありえない!二度と会えなくなる方が嫌。
心配なのは、彼の心臓に病気があるってことなのよ。
ずいぶん前から移植の順番待ちをしているのに。
ねえしぃらさん。彼はいま病気が悪化したり、しないよね?
それだけ解かれば、安心なんだけど…」
「わたしには未来は解らない。
ギバ子さんも、知らせをしているだけだから。
でも、それとは別に。
わたしに願いをかけるというなら、願いをかなえてあげることはできるわ」
学生時代、『百葉箱のしぃらさん』は、願掛けの場所でもあった。
だけど、恐ろしいうわさもあったから、本当に願い事をする人は少なかった。
「それって本当なの?しぃらさんは、願い事を叶えてくれるの?」
「どうかしら。」
「夫の病気をよくして欲しいっていったら、
お医者さんにもできないのに、おばけなんかに出来るっていうの?」
「さあ、どうかしら。」
しぃらさんはスカートを翻し、はぐらかすようにくすくす笑う。
「あなたたち、一生一緒にいたいのね。」
「そうよ」
「どんなことを犠牲に出来る?」
「どんなことを…?」
「それはたとえば、あなたが
記憶を失うとか、こころを失ったとしても?」
言葉に詰まる。
「そうすれば、彼の命は助けられるとしたら、あなたは差し出すものかしら」
「……
なら、できるわ。本当に、できるというなら。」
「そう!」
しぃらさんはぽんと手をたたいて、嬉しそうに古びたフラスコを取り出した。
薬品の瓶をあけ、わたしの眼前につきつける。
「この薬を嗅いで。スーッと、思い切り鼻で吸い込んでね」
スー、嗅ぐと、ミントを100倍に濃くしたような刺激的な感覚があった。
鼻の粘膜が刺激されたからか、制御できずに涙があふれる。
5秒と経たず、ぐらりと視界がかしいだ。
「しぃらさん、これは…?」
「これは、脳を壊死させるための薬なの」
「――えっ」
「…、…」
「…」
・・・
道路で倒れていた妻は、頭を轢かれ、一刻の猶予を争う事態だったらしい。
血染めの保険証を握りしめていた。
保険証。そしてその裏面の、臓器提供欄。
心臓が脈打つたびに息が苦しくなる。掻きむしりたくなる。どうしてこんなことになったのか、
10年先も、20年先も、一生今日の事を思い出すことになる。

『怪馬』アンジニティサイド
「強くなりたい」
馬のいななきを聞いた。
幼い頃世話をした仔馬たちのしくしくした手触りを、香ばしいにおいを思い出していた。
魔物と人が闘争を続けるこの大陸で、私の生まれ育った村は特に危険な土地にあった。
目と鼻の先にある精霊の森はふかく、魔物たちの繁殖の地と言い伝えられていた。
私たちが退けば、他のだれかの故郷が前線となる。思えばこそ、私達はどうしても、そこにとどまり戦う必要があった。
小さな石造りの家に、明かりがさす。
「強くなりたいんだ。」
私がそう告げると、この家のあるじ――魔女は微笑んだ。
はじめに『強くなるためにどんなことまでしたいか』と唇をすぼめて、魔女は言った。
どんなことまで?
『そうね、私にしてあげられることと言ったら。
こういうのがあるわ。ただの魔法石じゃないのよ。
いくつかの魔法式が組み込んであるの。
あなたは光と水から魔力を産み出し、馬よりも早く走れるわ。
右肩の左後ろあたりをちょちょいっと切開してこれを埋め込む…
外科的な手術というの、西洋の技術なのよ。おねえさん、かまわない?』
埃っぽい宝石箱から、水晶がひとつぶ取り出される。
私はそれを求めた。
魔女の寝台に横たわり目をつぶる。身体を触られ、持ち上げられ、折り曲げられ
呪いの言葉を聞いたと思ったら、次に目を開けた時にはもう手術は終わっていた。
ほんの少し、いぼのような違和感はあったものの
鏡を借りて確かめても、ごく小さな水晶は目立つわけでもない。
満足のいく手術だった。春のことだった。
私は村に帰り、馬たちと駆けた。
彼らと同じ目線で、同じ速さで駆けられる、さわやかな気持ちだった。
それもつかの間、魔物が現れ平穏をみだせば、私は飛んで駆けていった戦った。
それにしても、この水晶は私を大変助けてくれた。
きっかけは、魚を捕りに行った村人が2名、湖で魔物に殺されたことだった。
「私はもっと強くりたい」
私はふたたび、魔女を訪ねた。
『そうね、私がしてあげられることと言ったら。』
魔女は物置から、両の手にフルフルと震えるやわらかい壺のようなものを持って来た。
『魔導器よ。これを、あなたの肺がある部分にとりつけるの。
これで水の中にも深く潜れるし、深い土の中でも酸欠になることがないわ。
また、外科的な手術が必要になるのだけど』
私はそれを求めた。
また、水晶の時のようなものだろう。はた目には変化がわからず、見返りは甚大。
ふたたび、私は魔女の寝台に横たわった。そしてまた、目を開けた時には手術は終わっていた。
鏡を借りてたしかめる。
縫い後は残っているものの、闘いの日々で沢山傷を受けた体では、気になるほどでもない。
――だが鏡越しに、私はあるものに気付いた、
魔女の家の流し台にある、臓物――
肺がある部分にとりつける、とは、健康な肺を摘出して取りつけるという事だったのか、
私はあおざめて、しかし、事を問いただせなかった。彼女はそれがさも、当たり前という風でいる。
これが、都市の魔術師の間では当たり前の技術なのかもしれない。
私は村に帰り、湖へ潜った。
思ったよりも随分…かなり息苦しかったが、たしかに、水中で息絶えることがない。
たしかにこの魔導器は私を助けてくれた。
きっかけは火を吹く魔物のせいで、村に面する森が火事になったことだった。
私はみたび、魔女を訪ねた。
「私はもっともっと強くなりたい」
『そうね、私がしてあげられることと言ったら。』
魔女は私の手を引いて、身をかがめれば大人一人は入れるくらいの、大きな釜のもとに案内した。
釜のうちは黒々と光る粘性の液体に満ちていて、においからは、油だと思われた。
『マジックオイルよ。これを塗り込んで、あなたの皮膚を火に強くする。
火を吹く魔物をおそれることがなくなるし、森火事の中にも入っていける』
私はそれを求めた。
今度は外科的な手術はないらしい。薬を塗ったくらいで変わるなら。
私は魔女の釜の中に沈んだ。目を開けた時には、私は魔女の寝台の上だった。
身体の違和感を感じ、首を持ち上げ体を見る、
…
……ない、何度やり直しても腕が、つるりと、杭のようにまろく途絶えて、私の手がない。
『あら、目が覚めたのね。本当に良かった。もう、目覚めないかと…
うふふ、ごめんなさい。申し上げにくいんだけれど、
思ったよりも薬の効き目がつよくて…ちょっとだけ溶けてしまったみたい』
「どうしてくれる!?」
私は恐怖に操られて怒鳴り散らした、息が整わない。こんなことって。
魔女は抱えていた包みをほどいて私に添えた。
『安心して、かわりに丁度よいものがあるの。
魔道具の義肢よ。怪我の功名かも。あなたのお望み通り、もっともっとつよくなれるわ』
魔女の用意した義手は不適当に大きく、私の体はいびつに、傾いた。
床につきそうなごつごつとした腕を握りしめ、心の中で何か、
さびれ、ほろほろと朽ちていくものをかんじた。
魔女を殺しても構わなかった。
『ねえ、バランスが悪いと思わない?足を長くした方がいいのではないかしら
足を切り落として、足も義足にそろえるのはどう?』
私は…
私はそれを求めた。
目が覚めた時、私は最早人間ではなかった。
いびつな奇怪だった。下半身はは6本足の馬のようで、相対的に腕の長さには会った。
皮膚が溶けたせいだろうか。いつのまにか、壊死したようなドス黒い色と、血管模様とが胸の全面に浮き上がっていた。
魔女の家を飛び出すと、私は二度と帰らないと思った。
私が駆けると、コロリとささやかな音を立てて最初の水晶が床に落ちた。
私は振り返らなかった。
もはや私は帰れないだろう。構わない。なら構わない。
ただ強くしてくれ、強くなりたい。強くなって、魔物と戦おう。
森の奥へと駆けて、駆けて、駆けまどう私に精霊があわれむように呟いた
『お前騙されたんだねえ、ここらの魔物はみんな、魔女のいいなりさ。
昔にいた魔物たちはみんな、一掃とばかり殺されてしまった。
今いる魔物たちは、お前と同じに、みんなあの魔女の作ったものなのに。』



ENo.205 ミツ とのやりとり

ENo.813 玲子 とのやりとり

ENo.1232 ダーシャ とのやりとり

以下の相手に送信しました




ダーシャ(1232) に ItemNo.7 肉の龍脈 を手渡ししました。
ダーシャ(1232) から 不思議な雫 を手渡しされました。












六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



歩行軍手 をエイドとして招き入れました!
駄石(50 PS)を購入しました。
駄石(50 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
付加LV を 10 DOWN。(LV35⇒25、+10CP、-10FP)
合成LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
ItemNo.1 老魔女の遺言書 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成し、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
ダーシャ(1232) の持つ ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.3 黒鎧 を合成し、駄物 に変化させました!
ItemNo.7 不思議な雫 に ItemNo.9 不思議な雫 を合成し、何か固い物体 に変化させました!
⇒ 何か固い物体/素材:強さ15/[武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20)
森(1047) により ItemNo.6 ネジ から装飾『スピリチュアルピラミッド』を作製してもらいました!
⇒ スピリチュアルピラミッド/装飾:強さ75/[効果1]舞乱10 [効果2]- [効果3]-
ダーシャ(1232) により ItemNo.7 何か固い物体 から射程2の武器『魔法のフラスコ』を作製してもらいました!
⇒ 魔法のフラスコ/武器:強さ75/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程2】
しらきり(1182) とカードを交換しました!
陰りし記憶の兵 (サモン:ウォリアー)
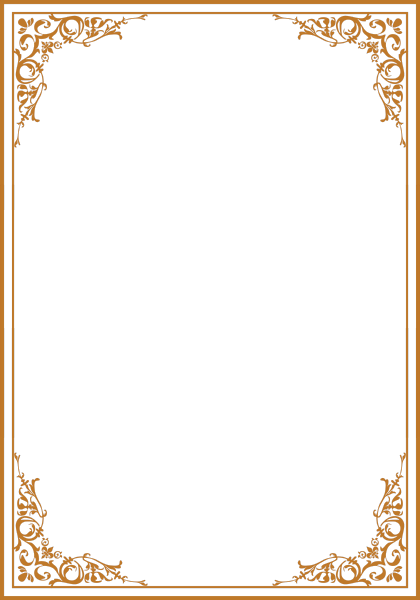
ダウンフォール を研究しました!(深度0⇒1)
ダウンフォール を研究しました!(深度1⇒2)
ダウンフォール を研究しました!(深度2⇒3)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



悪意の魔女(103) は 毛 を入手!
悪意の魔女(103) は 毛 を入手!
ナックラヴィー(502) は ボロ布 を入手!
悪意の魔女(103) は ボロ布 を入手!
悪意の魔女(103) は 皮 を入手!
ダーシャ(1232) は 皮 を入手!
悪意の魔女(103) は 皮 を入手!
ナックラヴィー(502) は 皮 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
悪意の魔女(103) のもとに 大黒猫 が空を見上げなから近づいてきます。
悪意の魔女(103) のもとに 歩行軍手 が泣きながら近づいてきます。



次元タクシーに乗り チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 に転送されました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 K-16(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 L-15(草原)に移動!(体調26⇒25)
ダーシャ(1232) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- 悪意の魔女(103) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- ダーシャ(1232) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- 悪意の魔女(103) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- ダーシャ(1232) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)





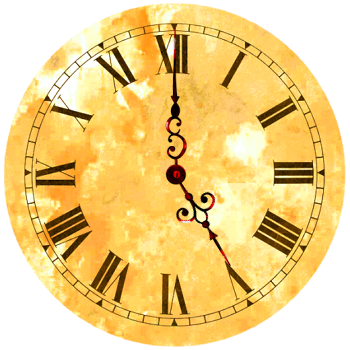
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にふたりの姿が映る。

ノウレットから遠く離れる白南海。
遠く離れた白南海を手招く。
チャットが閉じられる――









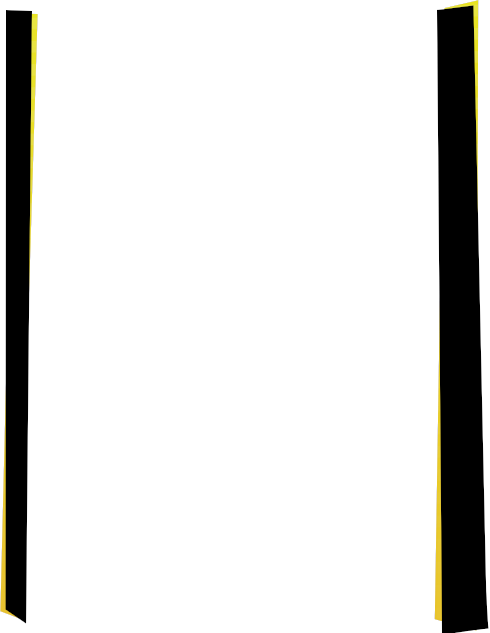
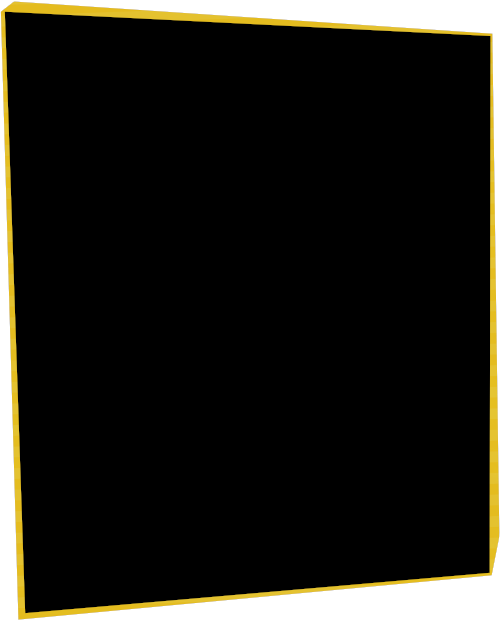





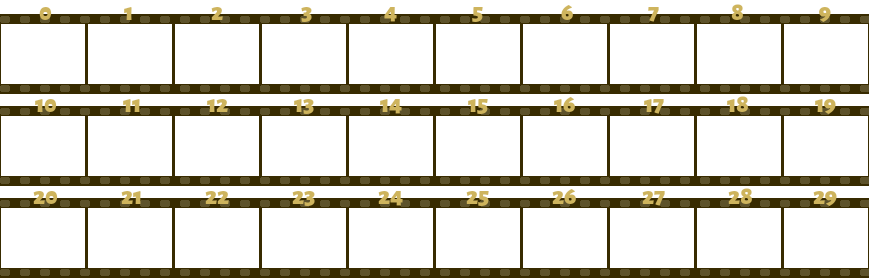




































No.1 魔法陣『錘』 (種族:ピクシー)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



※※ 注意 ※※
『コワイ話』です。胸の悪くなる描写があります。全体的にこのページの文章類は、あまり読まない方が良いです。

『DoRa・SiRa』
【日記等まとめ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/akui.html
『コワイ話』です。胸の悪くなる描写があります。全体的にこのページの文章類は、あまり読まない方が良いです。

『DoRa・SiRa』
【日記等まとめ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/akui.html

百物語 4話『怪馬』

『怪馬』イバラシティサイド
幼いころから、繰り返し見る夢があった。
白い空間を馬車が走っていて、私がそれを眺めている。
夢の中は物理法則がうやむやで、念じれば、馬車を追い越す速さで走ることが出来た。
荷車を引く馬――この世の物とは思えない玉虫色の馬は、首の先に人間の顔がついている。
その人間の顔とは、大抵私の良く知っている人だった。誰の顔か認識した瞬間目が覚めるのがお決まりだ。
言葉にすると大層不気味だけれど、夢の中の私はそれを気味が悪いとは思わなかった。
不思議というのは、ここからだ。
その夢をみたあと、馬の顔になっていた人と私とは、決まって離れ離れになるのだった。
ひっこしだったり習い事をやめたり…この夢はいつもその予兆だった。
「今日、久しぶりにその夢を見たの」
「家族なのに?転勤とか、まさか死ぬって事はないだろうけれど…」
「縁起でもないこと言わないでよ、本当に。体調は今はいいの?」
「ここしばらくは驚くくらいいいけどねえ…」
紛れもない、最愛の夫の顔を見た。
これまで、寂しい予兆とは言えど害という害はないものだったし、馬の夢の事は余り気にせずに生きてきた。
しかし今回ばかりはどうにも気がかりだった。
夫と別れることはないだろうし、転職や引っ越し…他のどんな理由でも、家族がはなればなれにはならない。
それに夫には持病がある。病気があるから職場だって転勤なんて負担のかかることは直ぐに命じたりはしないだろうし、
…病気。悪い想像が頭から離れない。
それで、私は幾年ぶりかに母校を訪れていた。
この場所には、女学生だけが知る『不思議な存在』がいた。
「カラスヨ カラス、ナゼニトブ ワタミヲ カワズト オモウテカ」
旧校舎裏、百葉箱。その前に立ってカラスの羽根を振りながら、呪文を唱える。すると――
「よばれてとびでてどろろろろ~っ
…あら!ずいぶんオトナになって。
最期にあったのは、卒業式の日以来かしら。」
「ごきげんよう、『百葉箱のしぃらさん』」
・・・
「なるほど。
ありがとう、それはギバ子さんね。
でも、悪さをしたわけではないのね?」
事のあらましを話し終って、私はこくりと肯く。
「予知をしたことは…あなたにとってもいい事かも。
たとえば、あなたのダーリンが、浮気をして
あなたがもう別れたい!ってなるとか?」
「ありえない!二度と会えなくなる方が嫌。
心配なのは、彼の心臓に病気があるってことなのよ。
ずいぶん前から移植の順番待ちをしているのに。
ねえしぃらさん。彼はいま病気が悪化したり、しないよね?
それだけ解かれば、安心なんだけど…」
「わたしには未来は解らない。
ギバ子さんも、知らせをしているだけだから。
でも、それとは別に。
わたしに願いをかけるというなら、願いをかなえてあげることはできるわ」
学生時代、『百葉箱のしぃらさん』は、願掛けの場所でもあった。
だけど、恐ろしいうわさもあったから、本当に願い事をする人は少なかった。
「それって本当なの?しぃらさんは、願い事を叶えてくれるの?」
「どうかしら。」
「夫の病気をよくして欲しいっていったら、
お医者さんにもできないのに、おばけなんかに出来るっていうの?」
「さあ、どうかしら。」
しぃらさんはスカートを翻し、はぐらかすようにくすくす笑う。
「あなたたち、一生一緒にいたいのね。」
「そうよ」
「どんなことを犠牲に出来る?」
「どんなことを…?」
「それはたとえば、あなたが
記憶を失うとか、こころを失ったとしても?」
言葉に詰まる。
「そうすれば、彼の命は助けられるとしたら、あなたは差し出すものかしら」
「……
なら、できるわ。本当に、できるというなら。」
「そう!」
しぃらさんはぽんと手をたたいて、嬉しそうに古びたフラスコを取り出した。
薬品の瓶をあけ、わたしの眼前につきつける。
「この薬を嗅いで。スーッと、思い切り鼻で吸い込んでね」
スー、嗅ぐと、ミントを100倍に濃くしたような刺激的な感覚があった。
鼻の粘膜が刺激されたからか、制御できずに涙があふれる。
5秒と経たず、ぐらりと視界がかしいだ。
「しぃらさん、これは…?」
「これは、脳を壊死させるための薬なの」
「――えっ」
「…、…」
「…」
・・・
道路で倒れていた妻は、頭を轢かれ、一刻の猶予を争う事態だったらしい。
血染めの保険証を握りしめていた。
保険証。そしてその裏面の、臓器提供欄。
心臓が脈打つたびに息が苦しくなる。掻きむしりたくなる。どうしてこんなことになったのか、
10年先も、20年先も、一生今日の事を思い出すことになる。

『怪馬』アンジニティサイド
「強くなりたい」
馬のいななきを聞いた。
幼い頃世話をした仔馬たちのしくしくした手触りを、香ばしいにおいを思い出していた。
魔物と人が闘争を続けるこの大陸で、私の生まれ育った村は特に危険な土地にあった。
目と鼻の先にある精霊の森はふかく、魔物たちの繁殖の地と言い伝えられていた。
私たちが退けば、他のだれかの故郷が前線となる。思えばこそ、私達はどうしても、そこにとどまり戦う必要があった。
小さな石造りの家に、明かりがさす。
「強くなりたいんだ。」
私がそう告げると、この家のあるじ――魔女は微笑んだ。
はじめに『強くなるためにどんなことまでしたいか』と唇をすぼめて、魔女は言った。
どんなことまで?
『そうね、私にしてあげられることと言ったら。
こういうのがあるわ。ただの魔法石じゃないのよ。
いくつかの魔法式が組み込んであるの。
あなたは光と水から魔力を産み出し、馬よりも早く走れるわ。
右肩の左後ろあたりをちょちょいっと切開してこれを埋め込む…
外科的な手術というの、西洋の技術なのよ。おねえさん、かまわない?』
埃っぽい宝石箱から、水晶がひとつぶ取り出される。
私はそれを求めた。
魔女の寝台に横たわり目をつぶる。身体を触られ、持ち上げられ、折り曲げられ
呪いの言葉を聞いたと思ったら、次に目を開けた時にはもう手術は終わっていた。
ほんの少し、いぼのような違和感はあったものの
鏡を借りて確かめても、ごく小さな水晶は目立つわけでもない。
満足のいく手術だった。春のことだった。
私は村に帰り、馬たちと駆けた。
彼らと同じ目線で、同じ速さで駆けられる、さわやかな気持ちだった。
それもつかの間、魔物が現れ平穏をみだせば、私は飛んで駆けていった戦った。
それにしても、この水晶は私を大変助けてくれた。
きっかけは、魚を捕りに行った村人が2名、湖で魔物に殺されたことだった。
「私はもっと強くりたい」
私はふたたび、魔女を訪ねた。
『そうね、私がしてあげられることと言ったら。』
魔女は物置から、両の手にフルフルと震えるやわらかい壺のようなものを持って来た。
『魔導器よ。これを、あなたの肺がある部分にとりつけるの。
これで水の中にも深く潜れるし、深い土の中でも酸欠になることがないわ。
また、外科的な手術が必要になるのだけど』
私はそれを求めた。
また、水晶の時のようなものだろう。はた目には変化がわからず、見返りは甚大。
ふたたび、私は魔女の寝台に横たわった。そしてまた、目を開けた時には手術は終わっていた。
鏡を借りてたしかめる。
縫い後は残っているものの、闘いの日々で沢山傷を受けた体では、気になるほどでもない。
――だが鏡越しに、私はあるものに気付いた、
魔女の家の流し台にある、臓物――
肺がある部分にとりつける、とは、健康な肺を摘出して取りつけるという事だったのか、
私はあおざめて、しかし、事を問いただせなかった。彼女はそれがさも、当たり前という風でいる。
これが、都市の魔術師の間では当たり前の技術なのかもしれない。
私は村に帰り、湖へ潜った。
思ったよりも随分…かなり息苦しかったが、たしかに、水中で息絶えることがない。
たしかにこの魔導器は私を助けてくれた。
きっかけは火を吹く魔物のせいで、村に面する森が火事になったことだった。
私はみたび、魔女を訪ねた。
「私はもっともっと強くなりたい」
『そうね、私がしてあげられることと言ったら。』
魔女は私の手を引いて、身をかがめれば大人一人は入れるくらいの、大きな釜のもとに案内した。
釜のうちは黒々と光る粘性の液体に満ちていて、においからは、油だと思われた。
『マジックオイルよ。これを塗り込んで、あなたの皮膚を火に強くする。
火を吹く魔物をおそれることがなくなるし、森火事の中にも入っていける』
私はそれを求めた。
今度は外科的な手術はないらしい。薬を塗ったくらいで変わるなら。
私は魔女の釜の中に沈んだ。目を開けた時には、私は魔女の寝台の上だった。
身体の違和感を感じ、首を持ち上げ体を見る、
…
……ない、何度やり直しても腕が、つるりと、杭のようにまろく途絶えて、私の手がない。
『あら、目が覚めたのね。本当に良かった。もう、目覚めないかと…
うふふ、ごめんなさい。申し上げにくいんだけれど、
思ったよりも薬の効き目がつよくて…ちょっとだけ溶けてしまったみたい』
「どうしてくれる!?」
私は恐怖に操られて怒鳴り散らした、息が整わない。こんなことって。
魔女は抱えていた包みをほどいて私に添えた。
『安心して、かわりに丁度よいものがあるの。
魔道具の義肢よ。怪我の功名かも。あなたのお望み通り、もっともっとつよくなれるわ』
魔女の用意した義手は不適当に大きく、私の体はいびつに、傾いた。
床につきそうなごつごつとした腕を握りしめ、心の中で何か、
さびれ、ほろほろと朽ちていくものをかんじた。
魔女を殺しても構わなかった。
『ねえ、バランスが悪いと思わない?足を長くした方がいいのではないかしら
足を切り落として、足も義足にそろえるのはどう?』
私は…
私はそれを求めた。
目が覚めた時、私は最早人間ではなかった。
いびつな奇怪だった。下半身はは6本足の馬のようで、相対的に腕の長さには会った。
皮膚が溶けたせいだろうか。いつのまにか、壊死したようなドス黒い色と、血管模様とが胸の全面に浮き上がっていた。
魔女の家を飛び出すと、私は二度と帰らないと思った。
私が駆けると、コロリとささやかな音を立てて最初の水晶が床に落ちた。
私は振り返らなかった。
もはや私は帰れないだろう。構わない。なら構わない。
ただ強くしてくれ、強くなりたい。強くなって、魔物と戦おう。
森の奥へと駆けて、駆けて、駆けまどう私に精霊があわれむように呟いた
『お前騙されたんだねえ、ここらの魔物はみんな、魔女のいいなりさ。
昔にいた魔物たちはみんな、一掃とばかり殺されてしまった。
今いる魔物たちは、お前と同じに、みんなあの魔女の作ったものなのに。』



ENo.205 ミツ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.813 玲子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1232 ダーシャ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| シーラ 「待ちなさい、ダーシャ… …“守護者”ですって―― 石橋は叩いてわたらないと!長生きの秘訣よね 魔物を呼ぶわ。」 |
| 魔女は髪飾りを手に持ち、とがった部分で魔法陣を描き出す。 |
 |
「・・・・・・・・ ・・・・・・・・・」 |
| シーラ 「 今に魔物が寄って来る―― ほら!」 「…あら?刻印がないわ。わたしの魔物じゃない…? … もしかして。 あははは、まあいいのだわ。 ねえ、あなたがた人間の言葉はわかるかしら。 はじめまして、わたしは魔女のドーラ・シーラ。 すこしお時間いただけます? あなた方にお見せするわ、 なぜ魔物と魔女というものがなぜ親しいのか…」 |
 |
タウラシアス 「斧に当たっても文句は言うなよ?不用意に近付いたお前らが悪いんだぜ」 |
| 「…………おまえ、」 ヒトの女と見て匂いを嗅ごうと屈みかけて、ぴたりと止まった。 そのまま一歩、二歩と後じさり、不可解そうに騎士の方を見る。 |
| 「……おまえ、よくこんなのと行動を共にしているな」 女の持つ得体の知れない雰囲気が気に喰わないのか、うろうろと遠巻きにしている…… |
 |
ただ魔女の傍に控えている。 |
ダーシャ(1232) に ItemNo.7 肉の龍脈 を手渡ししました。
ダーシャ(1232) から 不思議な雫 を手渡しされました。
 |
物言わず差し出す。 |





魔女と騎士
|
 |
かすかちゃん’sハーレム
|



チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
魔女と騎士
|
 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



歩行軍手 をエイドとして招き入れました!
駄石(50 PS)を購入しました。
駄石(50 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
エナジー棒(30 PS)を購入しました。
付加LV を 10 DOWN。(LV35⇒25、+10CP、-10FP)
合成LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
ItemNo.1 老魔女の遺言書 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成し、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
| シーラ 「ラム酒がてにはいるなんて!ついてるのだわ。 …ひさしぶりに老魔女さまの遺言書の通りにやってみようかしら~っ?」 |
ダーシャ(1232) の持つ ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.3 黒鎧 を合成し、駄物 に変化させました!
ItemNo.7 不思議な雫 に ItemNo.9 不思議な雫 を合成し、何か固い物体 に変化させました!
⇒ 何か固い物体/素材:強さ15/[武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20)
2滴のふしぎなしずく。くすんだ魔女の鍋はギラギラと不思議な魔光をはなつ。 |
森(1047) により ItemNo.6 ネジ から装飾『スピリチュアルピラミッド』を作製してもらいました!
⇒ スピリチュアルピラミッド/装飾:強さ75/[効果1]舞乱10 [効果2]- [効果3]-
 |
《おれにはただの三角形にしか思えんのだがな》 |
ダーシャ(1232) により ItemNo.7 何か固い物体 から射程2の武器『魔法のフラスコ』を作製してもらいました!
⇒ 魔法のフラスコ/武器:強さ75/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程2】
 |
かち、と硝子の鳴る音。 |
しらきり(1182) とカードを交換しました!
陰りし記憶の兵 (サモン:ウォリアー)
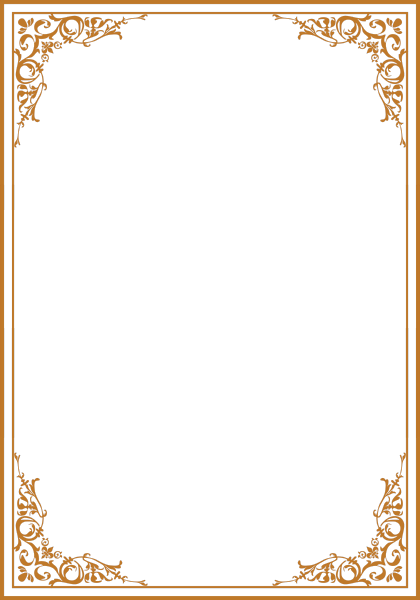
ダウンフォール を研究しました!(深度0⇒1)
ダウンフォール を研究しました!(深度1⇒2)
ダウンフォール を研究しました!(深度2⇒3)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



悪意の魔女(103) は 毛 を入手!
悪意の魔女(103) は 毛 を入手!
ナックラヴィー(502) は ボロ布 を入手!
悪意の魔女(103) は ボロ布 を入手!
悪意の魔女(103) は 皮 を入手!
ダーシャ(1232) は 皮 を入手!
悪意の魔女(103) は 皮 を入手!
ナックラヴィー(502) は 皮 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
悪意の魔女(103) のもとに 大黒猫 が空を見上げなから近づいてきます。
悪意の魔女(103) のもとに 歩行軍手 が泣きながら近づいてきます。



次元タクシーに乗り チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「・・・はい到着ぅ。気をつけて行きな。」 |
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 K-16(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 L-15(草原)に移動!(体調26⇒25)
ダーシャ(1232) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- 悪意の魔女(103) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- ダーシャ(1232) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- 悪意の魔女(103) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
- ダーシャ(1232) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)





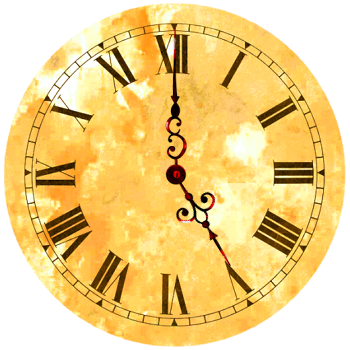
[625 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[223 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「ん・・・・・」 |
 |
エディアン 「これは・・・・・」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「なんでしょうこれ!変な情報が映し出されてますねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・つーか何でまた一緒の部屋入ってるんですかね。」 |
 |
エディアン 「いいじゃないですかぁ!案外ヒマじゃないですか?案内役。」 |
 |
白南海 「私はひとりがいいんです、が、ね。」 |
 |
エディアン 「くッッらいですねぇ・・・・・クール気取りですか一匹狼気取りですか、まったく。」 |
 |
白南海 「うっせーオンナが嫌いなだけです。」 |
 |
エディアン 「・・・そういう発言、嫌われますよぉ?」 |
 |
白南海 「貴方も、ね。」 |
 |
エディアン 「――さて、まぁいいとしてこのログ?は何なんですかねぇ。」 |
 |
白南海 「・・・・・仕方ねぇですね。・・・おーい、クソ妖精ー。」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!ノウレットはいつでも貴方の背後から―――ッ!!」 |
 |
エディアン 「あぁなるほどノウレットちゃん!」 |
 |
エディアン 「・・・っていうかクソ妖精って――」 |
 |
ノウレット 「あだ名をいただいちゃいました☆」 |
 |
白南海 「――ほれ、Cross+Roseに変な情報出てんぞ説明しろ。」 |
 |
ノウレット 「うおおぉぉぉ頼られてます!?もしかして頼られてますッ!!?」 |
ノウレットから遠く離れる白南海。
 |
ノウレット 「どうして離れていくんですッ!!!?」 |
 |
ノウレット 「これはですねぇ!チェックポイント開放者数の情報ですっ!!」 |
 |
エディアン 「えぇえぇ、それはまぁそうかなーとは。右側の1000って数字はなんでしょう? もしかして開放できる人数が限られてる・・・とか?」 |
 |
ノウレット 「いえいえー!開放は皆さんできますよーっ!! これはハザマにいる全員に新たな力を与えるという情報です!!」 |
 |
エディアン 「新たな力・・・?」 |
 |
ノウレット 「そうでぇっす!!各チェックポイントの開放者数が増えるほど、対応する力が強く与えられます! 1000というのは1000人より上は1000人として扱うってことです!!」 |
 |
エディアン 「なるほどなるほど。これ・・・・・敵も味方も、ですか?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!全部が全部、ハザマの全員でーす!!」 |
 |
エディアン 「具体的に、どんな力が与えられるんです?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・はーい、大丈夫ですよー。」 |
 |
エディアン 「これは言葉からイメージして実感してみるしかないですかね。 出てくる敵にも力が・・・・・気をつけないといけませんね。」 |
 |
エディアン 「・・・・・白南海さーん!聞きましたよー。」 |
遠く離れた白南海を手招く。
 |
白南海 「――まぁ聞こえていたわけですが。離れても音量変わらなかったわけですが。」 |
 |
エディアン 「・・・ノウレットちゃんの音量調整できますよ?コンフィグで。」 |
 |
白南海 「・・・・・ぁー、よくわかんねぇめんどくせぇ。」 |
 |
エディアン 「まったく、こういうのダメな人ですか。右上のここから・・・ほら、音量設定。あるでしょ。 それから・・・・・あぁ違いますって!それだとチャッ――」 |
チャットが閉じられる――







ENo.103
百葉箱のしぃらさん

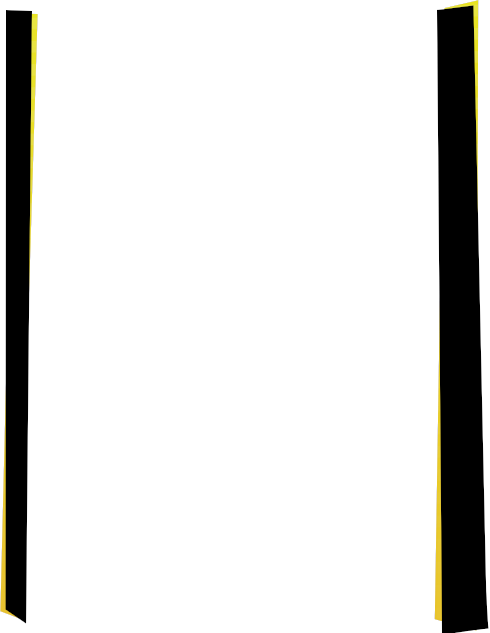
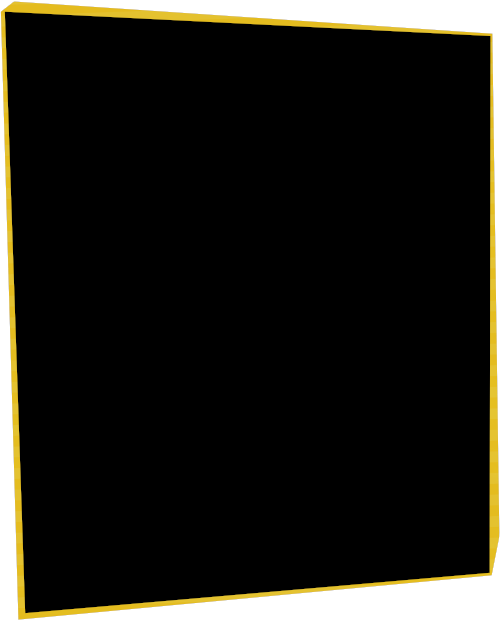
【 #荊街七不思議企画 】
http://dolch.bitter.jp/sira/ib/7fusigi.html
========================
ブランブル女学院、旧高等部裏
いつもじっとりと日影になる
薄暗い場所に佇む
古びた百葉箱の前に立って
片手に抜け落ちたカラスの羽根をいちまいかかげて
もう片手で逆十字を切りながら、こう唱えてごらん。
「カラスヨ カラス ナゼニ トブ
ワガミヲ カワズト オモウテカ」
そうすると
『百葉箱のしいらさん』があらわれて――
========================
イバラシティ版『トイレの花子さん』的怪異。
呼び出した人間と同じくらいの年頃で現れる。アイコンが幼い?絵柄のせいね。
スポット・百葉箱へ!http://lisge.com/ib/talk.php?p=373
【設定画など】https://karasuyokarasu.tumblr.com/
【アンジティ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/profdora.html
◆◇【悪意の魔女 ドーラ・シーラ】◇◆
魔法と魔物が存在する原始的なファンタジー世界、祝譚の世界≪ナタリス≫にて、魔物に知恵を与えていた科学者魔女。彼女の行いにより魔物は知力を増し人間にちかづき・人間はそれに対抗しようと武力を高め魔物にちかづき、人と魔物の戦は激化していった。
魔女の目的は人類の進化実験。彼女は研究のメインテーマに選ぶほどに、人類を愛している。
“まあ、言葉を尽くすのもそもそもナンセンスじゃないか。黒い物質を見つけたら『この世でもっとも黒い物質を新たに見つけ出せないだろうか』と ときめく、酸をみつけたら『この世でもっとも強い酸を新たに作り出せないだろうか』とときめく。科学者とはそんなもの。それが彼女のサイエンス、そしてマジック、その切実なときめきは、恋にも闘争心にもまさる、夢見心地な好奇心。とっても素敵な人類の進化をはじめましょう。”
(SICXLIVES-かつて否定の世界アンジニティが舞台だった別ゲームから継続参加)
http://dolch.bitter.jp/sira/ib/7fusigi.html
========================
ブランブル女学院、旧高等部裏
いつもじっとりと日影になる
薄暗い場所に佇む
古びた百葉箱の前に立って
片手に抜け落ちたカラスの羽根をいちまいかかげて
もう片手で逆十字を切りながら、こう唱えてごらん。
「カラスヨ カラス ナゼニ トブ
ワガミヲ カワズト オモウテカ」
そうすると
『百葉箱のしいらさん』があらわれて――
========================
イバラシティ版『トイレの花子さん』的怪異。
呼び出した人間と同じくらいの年頃で現れる。アイコンが幼い?絵柄のせいね。
スポット・百葉箱へ!http://lisge.com/ib/talk.php?p=373
【設定画など】https://karasuyokarasu.tumblr.com/
【アンジティ】http://dolch.bitter.jp/sira/ib/profdora.html
◆◇【悪意の魔女 ドーラ・シーラ】◇◆
魔法と魔物が存在する原始的なファンタジー世界、祝譚の世界≪ナタリス≫にて、魔物に知恵を与えていた科学者魔女。彼女の行いにより魔物は知力を増し人間にちかづき・人間はそれに対抗しようと武力を高め魔物にちかづき、人と魔物の戦は激化していった。
魔女の目的は人類の進化実験。彼女は研究のメインテーマに選ぶほどに、人類を愛している。
“まあ、言葉を尽くすのもそもそもナンセンスじゃないか。黒い物質を見つけたら『この世でもっとも黒い物質を新たに見つけ出せないだろうか』と ときめく、酸をみつけたら『この世でもっとも強い酸を新たに作り出せないだろうか』とときめく。科学者とはそんなもの。それが彼女のサイエンス、そしてマジック、その切実なときめきは、恋にも闘争心にもまさる、夢見心地な好奇心。とっても素敵な人類の進化をはじめましょう。”
(SICXLIVES-かつて否定の世界アンジニティが舞台だった別ゲームから継続参加)
25 / 30
96 PS
チナミ区
L-15
L-15





































No.1 魔法陣『錘』 (種族:ピクシー)
 |
|
「まずはピクシーを一匹。 個体の選別は、できるだけ幸せなものが良いです、後に治癒魔法の質に関わります。材料は、魔嘱蛾6匹、オチカレハ10枚、マホローム、銀色ミミズの頭部、ジュニパーベリー、3倍希釈の魔法薬 精神強化薬少々。材料を集めたら、まずはピクシーの手足をペンチでねじりきり、はずします。事前に冷蔵庫に30分ほど入れてひやしておくと、痛みが少なくおすすめです。…」 ドーラ・シーラによって改造されたピクシー。明るい赤髪の色素は恐怖に抜け落ち、肌は石化の魔法で冷たくかたい。今はふわふわとした、蛾の羽根の集合体のようなボール状の生き物。 //////// 魔法陣『錘』-潰れ目妖精・薬草カカシ・ハナナギトカゲ・イエロースライムのセット。 |
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| キュアブリーズ | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 風特性回復 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:風属性スキルのHP増効果に風特性が影響 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]
No.2 歩行軍手 (種族:歩行軍手) |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| マナ | 5 | 0 | 10 | 自:消費SP減 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 背水 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど被攻撃ダメージ減 | |
| 決1 | 強打 | 5 | 4 | 0 | 【自分行動前】自:次与ダメ増 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 3 | カラスのフン | 大砲 | 40 | 束縛10 | - | - | 【射程4】 |
| 4 | 図録『大陸西哺乳類解剖図』 | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 血錆びたサーベル | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程2】 |
| 6 | スピリチュアルピラミッド | 装飾 | 75 | 舞乱10 | - | - | |
| 7 | 魔法のフラスコ | 武器 | 75 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 8 | 血濡れたみつあみ | 防具 | 45 | 命脈10 | - | - | |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 11 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]幸運10(LV20) | |||
| 12 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]幸運10(LV20) | |||
| 13 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 17 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 18 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 使役 | 15 | エイド/援護 |
| 響鳴 | 15 | 歌唱/音楽/振動 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 25 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 合成 | 15 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 初級魔法『エアロブレイク』 (ブレイク) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 初級魔法『ウィンドスピア』 (ピンポイント) | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 初級魔法『トルナド』 (クイック) | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 初級魔法『エアロブラスト』 (ブラスト) | 6 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 神経系再結合『感覚器鈍磨』 (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 神経系再結合『多幸感』 (ドレイン) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 魔導具『フェロモン撒布器』 (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 烏百羽・金切声 (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| ペレル | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| アシスト | 5 | 0 | 50 | 自:束縛+自従全:AT・DX増 | |
| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| シュリーク | 5 | 0 | 50 | 敵貫:朦朧+自:混乱 | |
| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |
| クレイジーチューン | 5 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| サモン:ウォリアー | 7 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| モラール | 5 | 0 | 210 | 味全:DX増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| シーラの眷属『下級木偶』 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| シーラの眷属『潰れ目精霊』 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| シーラの眷属『くずキマイラ』 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| シーラの眷属『ハナナギトカゲ』 (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| シーラの眷属『土くれゴーレム』 (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| シーラの眷属『銀のドナテラ』 (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| シーラの眷属『マジョ草』 (隠者) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魔女のくちびる (召喚強化) | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 魔女のひとみ (魅惑) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| カリスマ (狂歌乱舞) | 5 | 5 | 0 | 【スキル使用後】自:混乱+自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増(2T) |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
石の欠けた部分 (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
グンニョリの煙 (ウィークネス) |
0 | 80 | 敵:衰弱 | |
|
幸房 (アブソーブ) |
0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
|
謎の光発生装置 (サモン:ウィスプ) |
5 | 300 | 自:ウィスプ召喚(複数可) | |
|
陰りし記憶の兵 (サモン:ウォリアー) |
5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]アサルト | [ 2 ]ストーンブラスト | [ 3 ]イレイザー |
| [ 2 ]ストライク | [ 1 ]ティンダー | [ 3 ]ダウンフォール |
| [ 3 ]クリエイト:グレイル |

PL / 宮沢