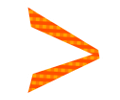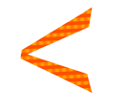<< 2:00~3:00




「悪いけど、私が卒業したら連絡先は消してくれ」
いつものようにシャワーを借りた後。
身支度を整えながら、花勝見真菰(はながつみ まこも)は部屋の主にそう声を投げた。
「君とはお互い利害が一致してたし、必要以上に干渉も束縛もしてこないところ、私としてもすごく楽なんだけどさ。
終わりにしよう」
最初は確か、そう、専攻を跨いだ飲み会の帰りだった。教授同士が知り合いだとか、そんな話だった。
論文の進捗が思わしくなく自棄になっていた私が飲みすぎて、まあ、酔った勢いだったと思う。
たまたま隣の席になった相手が全く酔っていなかったのが妙にかちんときて、うざったらしく絡んでいたところまでは覚えているのだが。
気がついたら朝で、この磯臭い部屋にいて、全身のだるさと頭痛が酷かった。
酒癖が悪い自覚は、まあある。
「……わかりました。多分、先輩が卒業する頃には忘れてると思うんで、今消しますね」
淡々とした声が返ってくる。ぽちぽちと携帯を操作する音も。今時珍しく、この後輩はガラケーユーザーだ。
「君は正直だね、ホント」
悪気がないのはわかっている。彼なりに気を回した結果だろう。
藻噛叢馬はそういう男だ。良くも悪くも、人に対して執着がない。
「私ね、海外の研究所に行くんだ。だから君ともお別れだ」
彼だから話したかった、というわけではない。
誰かに聞いてほしかった、というのはあるのかもしれない。何せようやく念願叶って、来年度の春から憧れの製薬研究所に籍を置くことになったのだ。そのために努力も根回しもしてきたし、多少危ない橋も渡ったのだから。
そもそも付き合っているかと言われればそうではないし、改めて別れの言葉を告げるのも何だか妙な気がしたが。
こういうけじめはきちんとつけておきたい派だ。
「そうなんですか。おめでとうございます」
「なんかさあ……もうちょっとそれらしく祝ってくれよ」
「……よかったですね。てっきり結婚するのかと思ってました」
こちらを見て、少し考えるように視線を脇にやってから、真顔でそんなことを言うものだから、ついおかしくて笑ってしまう。本当にデリカシーがない後輩だ。
「フッ、まあそれも悪くないかなと思ってたんだけどさ。
あいつ、結婚したら家庭に入って欲しいとか言うもんだから、ついその場でサヨナラしてしまったよ。この私にそれを言うかね」
所謂『本命の彼氏』だった男の話。
まさかバレンタインデーにフラれるとは思わなかったことだろう。
言われるまでそういう奴だと見抜けなかった私も私だが、まあ手早く忘れるとしよう。
「ところでさ。
侵略の噂ってあるだろ。あれ、どう思う?
もしも自分が侵略者だったら、とか、考えたことあるかい?」
それは話題を変えるために選んだ、他愛のないただの世間話。そのつもりだった。
「……どちら側でも、やることは変わらないでしょう。
生物は本能に従って行動する。俺も、きっとそうします」
「へえ、てっきりくだらないとか言うと思ったけど。ちょっと意外だな」
「仮定の話ですよ。どちらにしろ、答えは決まっているんですから、考えるだけ時間の無駄です」
彼の答えはいつも彼なりの理論に基づいていて、簡潔で、無駄がない。
それは長所と言えばそうだが、人によってはつまらない男と映るのだろう。
個人的には好感の持てる姿勢だし、研究分野が同じだったらもっと一緒にいてもいいかな、くらいには思っているが。生憎畑違いだ。
「なるほどね。その変に真面目というか……遊びがないっていうのかな。
そういうところ、直したらもうちょっとモテるんじゃない? 余計なお世話だろうけれどね」
実際のところ彼がどう思っているのか、深海の澱みのような目からは何の表情も読み取れない。
「……ああ、そういえば君のところの教授、」
温度のない目がこちらを見る。一瞬迷って、やっぱり言うのはやめた。
「いや……何でもないよ。
じゃ、そろそろ行くね。もう会うこともないだろうけど、元気で」
狭い玄関に脱ぎ散らかしておいたヒールを引っかけるように履いて、ひらひらと部屋の中に向かって手を振った。
後輩から返事はないし、見送りにも来ない。
――そういう雑なところがモテないんだぞ。
そう独りごちながら、薄暗い部屋を後にした。
外に出た瞬間、水面から顔を出したような心地になるのも、きっとこれが最後なんだろう。
***
「……やっぱりマジなんだよね、あの噂」
ハザマの地に呼び出された白衣の女は、やれやれと独りごちた。その足元には幻のようなヒメシャガの花が咲き乱れている。普段なら数分で消えるその花は、ここでは少しだけ長く保つ。
「異能が強化されたらしいのはいいけど、これじゃ身を守るには心もとないな。
というか、私みたいな非戦闘要員をここに呼ぶかね、普通」
これまで何度かこの荒廃した世界に呼び出された。
白南海とかいう胡散臭い男から色々と説明を受けた時はまだ半信半疑だったが、その後襲ってきた気味の悪い敵性生物(なんだろう、多分。だって襲ってきたし)からどうにか逃げ切った後はもう、信じるしかないという諦めの境地だった。
そう、逃げ切った。倒してはいない。
何故ならこの異能は全く戦闘向きではない。つかの間の花を咲かせるだけの、はったりにも少々心もとないささやかな異能。
そんな能力者をここに呼ぶとか、ふざけているとしか思えない。
だから、誰とも合流していない。足手纏いになることは目に見えているからだ。
「君もそう思うだろ」
背後の気配には気付いていた。
近付いてくる足音が人のものではないことにも、周囲に立ち込め始めた強い潮の臭いにも。
噎せ返るようなその臭気が、澱んだ海の香りを濃縮したようなそれが、あの大柄な後輩の部屋の空気に少し似ていることにも。
お世辞にも良いとは言えない空気を吸って、ゆっくりと吐く。
落ち着け、と口の中だけで呟いて、女は振り返った。
「……藻噛くん、なんだよね」
目の前に立つ巨大な生き物を見上げる。
剥かれた肉のような色の肌をした人の上半身と、蒼毛の馬の体。そのどちらも自分の知る常識的な大きさを優に超えるサイズで、なまじ人に近い部分があるのが余計に不気味だ。海藻のような鬣と尾は、風もないのに獲物を探すようにざわざわと蠢いている。
そんな趣味の悪い寄せ集めのような怪物が、簾のような鬣の間から覗く赤い一つ目で女を見つめていた。
「君はそちら側で……どうやら私はこちら側。そういうことなんだよね」
――君のことは、少しは知っているつもりだったのにな。
そんな思いは、言葉にしないまま。




ENo.93 Eva とのやりとり

ENo.273 闇 とのやりとり

ENo.498 土塊と黄花 とのやりとり

ENo.520 灰郎 とのやりとり

以下の相手に送信しました












具現LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
武術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
命術LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
防具LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ダーシャ(1232) の持つ ItemNo.1 駄物 から防具『黒鱗』を作製しました!
ぺちか(34) の持つ ItemNo.10 不思議な雫 から防具『くまのわたわた』を作製しました!
ぺちか(34) により ItemNo.6 美味しい草 から料理『わたあめ』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 3 4 2 = 9 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ わたあめ/料理:強さ45/[効果1]治癒13 [効果2]充填13 [効果3]増幅13
シオガマ(1249) とカードを交換しました!
塩弾 (ストーンブラスト)

リザレクション を研究しました!(深度0⇒1)
リザレクション を研究しました!(深度1⇒2)
リザレクション を研究しました!(深度2⇒3)
チャージ を習得!
アクアブランド を習得!
水の祝福 を習得!
アイシクルランス を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





タウラシアス(173) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 B-4(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
悪意の魔女(103) からパーティに勧誘されました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- 悪意の魔女(103) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- タウラシアス(173) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 悪意の魔女(103) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- タウラシアス(173) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ナックラヴィー(502) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ダーシャ(1232) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














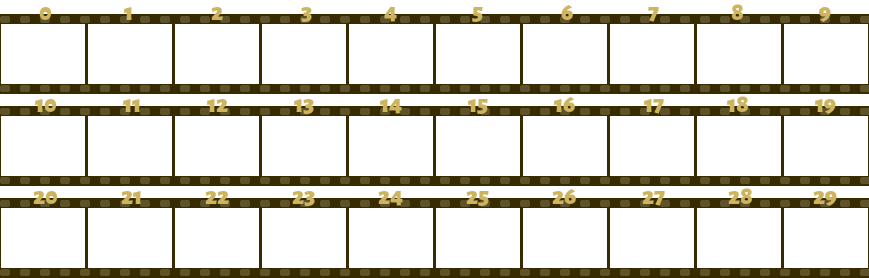







































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「悪いけど、私が卒業したら連絡先は消してくれ」
いつものようにシャワーを借りた後。
身支度を整えながら、花勝見真菰(はながつみ まこも)は部屋の主にそう声を投げた。
「君とはお互い利害が一致してたし、必要以上に干渉も束縛もしてこないところ、私としてもすごく楽なんだけどさ。
終わりにしよう」
最初は確か、そう、専攻を跨いだ飲み会の帰りだった。教授同士が知り合いだとか、そんな話だった。
論文の進捗が思わしくなく自棄になっていた私が飲みすぎて、まあ、酔った勢いだったと思う。
たまたま隣の席になった相手が全く酔っていなかったのが妙にかちんときて、うざったらしく絡んでいたところまでは覚えているのだが。
気がついたら朝で、この磯臭い部屋にいて、全身のだるさと頭痛が酷かった。
酒癖が悪い自覚は、まあある。
「……わかりました。多分、先輩が卒業する頃には忘れてると思うんで、今消しますね」
淡々とした声が返ってくる。ぽちぽちと携帯を操作する音も。今時珍しく、この後輩はガラケーユーザーだ。
「君は正直だね、ホント」
悪気がないのはわかっている。彼なりに気を回した結果だろう。
藻噛叢馬はそういう男だ。良くも悪くも、人に対して執着がない。
「私ね、海外の研究所に行くんだ。だから君ともお別れだ」
彼だから話したかった、というわけではない。
誰かに聞いてほしかった、というのはあるのかもしれない。何せようやく念願叶って、来年度の春から憧れの製薬研究所に籍を置くことになったのだ。そのために努力も根回しもしてきたし、多少危ない橋も渡ったのだから。
そもそも付き合っているかと言われればそうではないし、改めて別れの言葉を告げるのも何だか妙な気がしたが。
こういうけじめはきちんとつけておきたい派だ。
「そうなんですか。おめでとうございます」
「なんかさあ……もうちょっとそれらしく祝ってくれよ」
「……よかったですね。てっきり結婚するのかと思ってました」
こちらを見て、少し考えるように視線を脇にやってから、真顔でそんなことを言うものだから、ついおかしくて笑ってしまう。本当にデリカシーがない後輩だ。
「フッ、まあそれも悪くないかなと思ってたんだけどさ。
あいつ、結婚したら家庭に入って欲しいとか言うもんだから、ついその場でサヨナラしてしまったよ。この私にそれを言うかね」
所謂『本命の彼氏』だった男の話。
まさかバレンタインデーにフラれるとは思わなかったことだろう。
言われるまでそういう奴だと見抜けなかった私も私だが、まあ手早く忘れるとしよう。
「ところでさ。
侵略の噂ってあるだろ。あれ、どう思う?
もしも自分が侵略者だったら、とか、考えたことあるかい?」
それは話題を変えるために選んだ、他愛のないただの世間話。そのつもりだった。
「……どちら側でも、やることは変わらないでしょう。
生物は本能に従って行動する。俺も、きっとそうします」
「へえ、てっきりくだらないとか言うと思ったけど。ちょっと意外だな」
「仮定の話ですよ。どちらにしろ、答えは決まっているんですから、考えるだけ時間の無駄です」
彼の答えはいつも彼なりの理論に基づいていて、簡潔で、無駄がない。
それは長所と言えばそうだが、人によってはつまらない男と映るのだろう。
個人的には好感の持てる姿勢だし、研究分野が同じだったらもっと一緒にいてもいいかな、くらいには思っているが。生憎畑違いだ。
「なるほどね。その変に真面目というか……遊びがないっていうのかな。
そういうところ、直したらもうちょっとモテるんじゃない? 余計なお世話だろうけれどね」
実際のところ彼がどう思っているのか、深海の澱みのような目からは何の表情も読み取れない。
「……ああ、そういえば君のところの教授、」
温度のない目がこちらを見る。一瞬迷って、やっぱり言うのはやめた。
「いや……何でもないよ。
じゃ、そろそろ行くね。もう会うこともないだろうけど、元気で」
狭い玄関に脱ぎ散らかしておいたヒールを引っかけるように履いて、ひらひらと部屋の中に向かって手を振った。
後輩から返事はないし、見送りにも来ない。
――そういう雑なところがモテないんだぞ。
そう独りごちながら、薄暗い部屋を後にした。
外に出た瞬間、水面から顔を出したような心地になるのも、きっとこれが最後なんだろう。
***
「……やっぱりマジなんだよね、あの噂」
ハザマの地に呼び出された白衣の女は、やれやれと独りごちた。その足元には幻のようなヒメシャガの花が咲き乱れている。普段なら数分で消えるその花は、ここでは少しだけ長く保つ。
「異能が強化されたらしいのはいいけど、これじゃ身を守るには心もとないな。
というか、私みたいな非戦闘要員をここに呼ぶかね、普通」
これまで何度かこの荒廃した世界に呼び出された。
白南海とかいう胡散臭い男から色々と説明を受けた時はまだ半信半疑だったが、その後襲ってきた気味の悪い敵性生物(なんだろう、多分。だって襲ってきたし)からどうにか逃げ切った後はもう、信じるしかないという諦めの境地だった。
そう、逃げ切った。倒してはいない。
何故ならこの異能は全く戦闘向きではない。つかの間の花を咲かせるだけの、はったりにも少々心もとないささやかな異能。
そんな能力者をここに呼ぶとか、ふざけているとしか思えない。
だから、誰とも合流していない。足手纏いになることは目に見えているからだ。
「君もそう思うだろ」
背後の気配には気付いていた。
近付いてくる足音が人のものではないことにも、周囲に立ち込め始めた強い潮の臭いにも。
噎せ返るようなその臭気が、澱んだ海の香りを濃縮したようなそれが、あの大柄な後輩の部屋の空気に少し似ていることにも。
お世辞にも良いとは言えない空気を吸って、ゆっくりと吐く。
落ち着け、と口の中だけで呟いて、女は振り返った。
「……藻噛くん、なんだよね」
目の前に立つ巨大な生き物を見上げる。
剥かれた肉のような色の肌をした人の上半身と、蒼毛の馬の体。そのどちらも自分の知る常識的な大きさを優に超えるサイズで、なまじ人に近い部分があるのが余計に不気味だ。海藻のような鬣と尾は、風もないのに獲物を探すようにざわざわと蠢いている。
そんな趣味の悪い寄せ集めのような怪物が、簾のような鬣の間から覗く赤い一つ目で女を見つめていた。
「君はそちら側で……どうやら私はこちら側。そういうことなんだよね」
――君のことは、少しは知っているつもりだったのにな。
そんな思いは、言葉にしないまま。

花勝見 真菰
創峰大学第二学群製薬化学専攻に籍を置く大学院生。
異能:知る人なしの夢幻花
(しるひとなしのファントム・アイリス)
ハザマで怪物に出遭ってしまった。
異能:知る人なしの夢幻花
(しるひとなしのファントム・アイリス)
ハザマで怪物に出遭ってしまった。



ENo.93 Eva とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.273 闇 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.498 土塊と黄花 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.520 灰郎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました



 |
桶いっぱいの生肉をこれ見よがしに振り回す ブンブン ブンブン |







具現LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
武術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
命術LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
防具LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ダーシャ(1232) の持つ ItemNo.1 駄物 から防具『黒鱗』を作製しました!
ぺちか(34) の持つ ItemNo.10 不思議な雫 から防具『くまのわたわた』を作製しました!
ぺちか(34) により ItemNo.6 美味しい草 から料理『わたあめ』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 3 4 2 = 9 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ わたあめ/料理:強さ45/[効果1]治癒13 [効果2]充填13 [効果3]増幅13
 |
ぺちか 「ʕ▪ⓧ▪ʔ」 |
シオガマ(1249) とカードを交換しました!
塩弾 (ストーンブラスト)

リザレクション を研究しました!(深度0⇒1)
リザレクション を研究しました!(深度1⇒2)
リザレクション を研究しました!(深度2⇒3)
チャージ を習得!
アクアブランド を習得!
水の祝福 を習得!
アイシクルランス を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





タウラシアス(173) がパーティから離脱しました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 B-4(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
悪意の魔女(103) からパーティに勧誘されました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- 悪意の魔女(103) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- タウラシアス(173) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 悪意の魔女(103) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- タウラシアス(173) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ナックラヴィー(502) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ダーシャ(1232) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







魔女と騎士と牛と馬
|
 |
かすかちゃん’sハーレム
|




チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



魔女と騎士と牛と馬
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.502
藻噛 叢馬



藻噛 叢馬(もがみ そうま)
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。または、長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
どちらも元の世界では忘れ去られた海に棲む水妖の一種であり、人を喰う怪異である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。または、長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
どちらも元の世界では忘れ去られた海に棲む水妖の一種であり、人を喰う怪異である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
30 / 30
149 PS
チナミ区
B-4
B-4




















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 海棲馬の蹄 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 幻想藻の鬣 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | わたあめ | 料理 | 45 | 治癒13 | 充填13 | 増幅13 | |
| 7 | シーフードドリアもどき | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]朦朧10(LV20)[防具]体力10(LV10)[装飾]増勢10(LV25) | |||
| 9 | 巻き込んだ石ころ | 魔晶 | 20 | 幸運10 | - | 充填6 | |
| 10 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 防具 | 35 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| 練3 | クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| デッドライン | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 異形の膂力 (猛攻) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 怪物の体躯 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 否定への憤怒 (攻勢) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 幻想海・サルガッソー (五月雨) | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ノーマライズ | [ 3 ]リザレクション | [ 3 ]マナポーション |
| [ 3 ]ファーマシー |

PL / こか