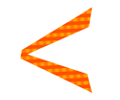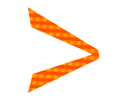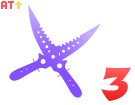<< 0:00~1:00




「調子はどうかね」
「視野が急に広くなってまだ違和感はある……体も動かしにくい」
人体実験から数週間が経過した。何の因果か実験は成功してしまい、ミュータント候補生としてその身をやつしている。射撃場で『動作テスト』を行っていると背後から白衣の男に声を掛けられた。
眼は向けていないから服装は分からないが、いつもの声からしていつもの服装の人だろうと思った。
仮称『白衣の男』に目線をやらないまま的に向けて銃を構え、人体を模したパネルにマシンガンを叩きこむ。
トリガーを強く握り込んでやると、軽い感触とは裏腹に大きな反動が体を襲う。締め撃ちされた弾丸は的から少し上向きの方向に飛んで行った。
「良き兵士の育成には健全な肉体が不可欠だ。食育、美容、健康維持。カーボ・ローディングという手もある。しかしそれらはコストがかかる。時間も金も」
「ドクター、私は博士ではないから専門的なことは分かりません」
次の的に向けて射撃を行う。適宜修正を行い、握りしめた手を緩くする。今度はきちんと的に中った。ふ、と息を吐いて煙を噴き出したバレルを手入れしつつ振り返る。
やはりというべきか。白衣を着た初老の男は腰に手を当てた態勢で休憩用のベンチに座り込んでいた。
「注射一本だ。栄養源を直接摂取させた方が楽に違いない。経口摂取に頼らず栄養を注入するだけで良い。増幅剤を摂取した君は短期間で栄養を十分に補給し、年相応の見た目になった」
銃を構える少女は、10に満たないながらも最初に蹲っていた時と比べて見られる容姿になった。
ミリタリージャケットとに包まれた体はすっかり平均的な体重と見た目になり、茫洋とした眼はしっかりと開かれ背筋も伸びた。
ぼさぼさだったボブヘアもしっかりと整えられているが、これは先輩の女性士官候補が繕ってくれたものである。
口数が少なかった受け答えも応答程度なら問題なく出来るようになり、テストを経た後は実地訓練に向かうとのことで調整を行っていた。
「頭髪の張りも良くなったし、皮と骨ばかりだった肉も一気に増したから重たくなっただろうがね。それが人体だ。人は容易に肥え、また痩せることが出来る。出来てしまう。耐えられてしまう。実に難儀とは思わんかね」
「……死ににくい、という意味でしょうか」
「それもある。こうして心苦しい人体実験をしなければ生き残れない世も末だ」
主導している人間が何を悲観するのだろう。そうした実験の犠牲者を何人使い棄てたというのか。心にもない事を言うと少女は心の中でごちて次の銃火器を持つ。自分の背丈に程近いアサルトライフルだ。
常通り構えて撃つ。しかし反動が大きすぎたのか三点バーストを一度撃っただけでよろけて背後に転んでしまった。
最後に真上へ放たれた銃弾が跳弾し、自分の頬を掠めて地面を抉って行った。自然と汗が噴き出る。
今、自分は死にかけた。何の感慨も無く、走馬燈を思い描く暇すらない儘。冗談みたいに死にかけた。赤色の瞳がゆらゆらと揺れる。自然と涙で瞳が濡れ始めた。
「あ……ァ……」
「腕と目だけで銃を使うな。腰を据えろ、肩の力も入れ過ぎている。童には荷が重いだろうが、出来なければ死ぬぞ」
「……」
怯えている暇はない。鬼のような指導をしてくる兵士がいないことに感謝した。それでも背後から諫める声色を受ければ自然と立ち上がり、大きく掛け声を上げて再度銃を構え始める。
フラッシュが三回チラついた。足元が浮き上がるが、何とか銃身を固定したまま射撃することに成功した。
「もう少し肉体強化を図るか。その顔のままではアンバランスだが、増幅剤を使う副作用は確実に受けるだろうがね。
細胞の活性化を行わせるには生み出す以外に他所から取ってくるという手があってな。顔は少し幼さが残るが、これが一番手っ取り早い。
首から下の成長を促進させる代わりに顔立ちはあまり変わらなくなるよう改造してみよう。痕は残さんと保証するぞ」
提案を受けても、意思確認をしても、少女には拒否することは出来ない。
「分かりました、ドクター。手術はいつ頃」
「肉体の調整とサイボーグ化の癒着を鑑みて、3日後だ。所定の時間になったらメディカルルームへ来るように」
「はい、ドクター」
ではまた様子を見に来る。そう言った彼の背に向けて、今度は少女が声をかけて止める。
「ひとつ質問したいことがあります」
「許可しよう」
「……ドクターは従軍経験がおありなのでしょうか」
先の銃を指導する口振りがあまりに手慣れていたものだから。弱点を見抜き、叡智をひけらかすというのは経験則があってのことだ。
姿勢を正し、彼を見上げながら少女は問う。彼はこそばゆいとばかりに頬を掻いてからひとつ笑った。
「今よりもぬるい戦争状態の時にね。3年程戦地で過ごした。理学派の出で銃なぞ撃ったことも無いのにいけしゃあしゃあと、どつき回されながら撃ちまくった」
「人を殺したことはあるのでしょうか」
「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる。長く銃を手に取っているとな、撃った後に当たったという感覚が把握できるようになる。遠く離れているぞ、数百はくだらない遠い場所相手にだ。それでも手に取るように分かる。
お前の眼は視野の補強に加えて敵を確実に殺したと分かるようにセンサーを植え付けているが、経験があればそういうのも不要になる。ともあれば才能だったのかもしれない」
「……殺しの才能でしょうか」
純真な赤色の瞳は真っ直ぐ彼を見据えている。屈託なく怯えも無い、真実と向き合おうとするかのように真剣だった。
「もしかしたらあったかもしれないが今はこうして好き勝手実験三昧をしている。
いいかね、このように閉塞的な環境でも出来る事ややれることは数多存在する。今は候補生として戦地に赴くことは確定しているが、それ以外にも道はある可能性はある」
「私は実験体としてのみの生を受けたのではないのでしょうか」
「選択余儀の無い事象だっただけだ。戦地で華々しい活躍をすれば人らしい生活が出来るやもしれんし、ここの生活に甘んじて受け入れるもよし。死んだらそれまでだ」
では失礼する、と男は一礼して射撃演習場から立ち去って行った。
自分が今手に持つ銃を一瞥する。まだまだ少女の矮躯が扱いには重たすぎて、扱うのも一苦労な代物。
未だ演習ばかりで人を殺せるかも分からない。その才能があるかも不明。明日の事も何もかもが未知数で、手術の最中に死ぬ可能性とてある。
一体どういう希望や選択が出来るというのだろうか。
少女は鬱憤を晴らすようにアサルトライフルを構え、射撃練習に打ち込むことにするのだった。
――あと2150日だ。
赤色の雲が世界を覆っていた。
この世界に着た直後はまだ晴れ間が見えていたのに、今はすっかり太陽が影も形もなくなってしまった。廃墟となっているチナミ区は沿岸にほど近い場所だ。この場所では銃火器も錆びてしまうということで、東へ進み山を越えてヒノデ区へと向かうことにした。
10年前から世話になっているドクターが言うには、己の体は細胞が活性化しやすく、死ににくいらしい。そうなるように調整したからと言っていたが、兎角己の体は常に健康的で若々しく、裂傷を受けても即時再生を始める程度には体は強くなったという。
カロリーコントロールを行えば肉体は伸縮自在といっていい程に容易く、維持コストも安い。人間を止めるようなことが出来れば強化兵士としては誉れ高い存在になることだろう。そこまでやる心算も、その改造に同意する意向も五年前には示すことは最後まで無かったが。ともあれば今も同じ心境である。
アーカイブ化している記憶データを薬液のように注射する感覚が頭を駆け巡る。ひどく気分が悪くなるが、戦闘と移動の合間の休息時間にやっておかねば10年分のロードというのはあまりに長すぎる。直近の記憶と最古の記憶を同時にインプットしていくと少々こんがらがりそうになるが、もとよりそのための異能『マルチクライアント』である。記憶データの配列は常に最適化され、正しい位置へと収納されていく。
時間をかけてやっと必要分のデータを飲み込むと、えずくような感覚と共に大きく嘆息する。気分を晴らすために天を見上げても、やはり厚い雲に覆われてばかりで気分が晴れるような光景は何もなかった。
気を取り直して立ち上がる。先行しているドローン部隊は敵影の姿を確認していないが、目視でも確認を怠らず、銃を構えながら山間部へと入り込む。
いつどこで誰が待ち伏せしているかも分からない。慎重に歩みを進めて、会敵したらトリガーを引く。
――出来るのか、己に。
昨日まで挨拶をした隣人が、笑いあった友が、愛する者が己に武器を突きつけてきたらそれに反応できるのか。
一人でいるとどうしても無為な自問自答を重ねてしまう。直近の記憶のアーカイブは他人の記録映像を見ることに等しく、己ではない己の記憶を俯瞰的に見せられているようなものなのだ。
あちらのシルバーキャットとこちらのシルバーキャットは別物で、こちらの方が傭兵として絆されず、冷静に対処できるはずである。
確証はない。まだここでは撃ったことが無い。5年過ごしたという記憶と共に親しい者に銃を向けて殺せるのかは分からない。親しい者を作らなかった己には何一つとして分からない。
「引き金を引いてから考えろ」
敵が現れたら殺す。襲い掛かったら容赦なくナイフを突き立てる。傭兵は迷う必要なんてない。
考えるより行動を。行動をするなら理知的な思考をせよ。
硬く強張った手先に構えた銃を握り直す。今度は手を沿えるようにするだけでグリップを握る。
『腕と目だけで銃を使うな。腰を据えろ、肩の力も入れ過ぎている。童には荷が重いだろうが、出来なければ死ぬぞ』
――ドクターの言葉を思い出し更に銃を構え直す。基本に立ち返り、原初へ至り、シルバーキャットという存在を再定義する。イバラシティのシルバーキャットはここにはいない。
ハザマのシルバーキャットは記憶を抱きかかえるだけのユニットだ。傭兵だ。それを忘れるな。
シルバーキャットは息を深く吸い込んでから吐き出すと、止まっていた歩みを再び進めるのだった。



ENo.195 天使様 とのやりとり

ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり

ENo.671 海の魔物 とのやりとり

以下の相手に送信しました












響鳴LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
具現LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
クロ(1253) とカードを交換しました!
☆ミ (アリア)


アクアシェル を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアボルト を研究しました!(深度1⇒2)
ファーマシー を研究しました!(深度1⇒2)
召喚強化 を習得!
祈誓 を習得!
サモン:サーヴァント を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



シルバーキャット(748) は 美味しくない草 を入手!
玲子(813) は 美味しくない草 を入手!
シルバーキャット(748) は 不思議な石 を入手!
シルバーキャット(748) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
シルバーキャット(748) のもとに 歩行石壁 が空を見上げなから近づいてきます。



特に移動せずその場に留まることにしました。
結(1510) をパーティに勧誘しました!
仁(1511) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- 玲子(813) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 結(1510) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――













硝煙の匂いをレモングラスの香水で紛らわす。
不条理に曝されても女は兵士として生きている。
無垢な顔立ちのまま、少女兵は此度も武器を取る。
その名は銀色の猫。数多の機械を操る科学の結晶。
少女の己を殺し、猫のように気儘に戦場を駆ける。
「敵対者を補足。猫の目は貴様を逃さない。
一匹たりとも逃がさない。徹底的に潰す。
侵略者よ、せめて敗走する権利は与えてやろう。
猫のテリトリーに立ち入ったこと、後悔して死ね」
【シルバーキャット】
女性/20歳(経歴詐称により27歳になっている)/177cm
【容姿】
10代後半程度の童顔。
銀髪のセミロングの髪。赤色の瞳。肌は透き通るような白さ。
白いVネックシャツと、ネイビー色の丈の短いキュロット。
カーキ色のミリタリージャケット。
ドッグタグを首から下げている。
【設定】
紛争地域のアンダーグラウンド出身。戦災孤児。
傭兵派遣会社『ブレーン・トルーパー社』に所属する。
主に市街・都市部への潜入・偵察を担当している。
今回はイバラシティに迫りくる危機(アンジニティ)を調査する為にブランブル女学院の保健・体育教師として潜り込んで来た。
潜入時の年齢は15歳。この5年間、ワールドスワップが始まるまでイバラシティを己の縄張りとして張り込み過ごしてきた。
思考速度と視神経を著しく引き上げられており、機械を自在に支配できる改造人間。
寡黙で冷徹な性格。希薄な感情の持ち主で大人しい。
ハザマではより冷酷な一面が浮き彫りになる。イバラシティで過ごした5年間の記憶を必要がある場合のみ落とし込み、深く関わりすぎた人物に対しても情を抱かない範疇で記憶操作している。
この影響でこちら側の精神年齢は10代で止まっている。
武器は銃とドローン、ロボット兵器。
特に市街戦に特化した戦闘スタイルで閉所・暗所は非常に有利。
遠近ともに殺人術に長けており、対人や包囲戦には滅法強い。
【所有ドローン】
ライオン:敵地工作用無人偵察機。クワッドコプター。
ジャガー:対電子戦用無人偵察機。戦闘機型
ピューマ:対市街調査用無人キャタピラ型兵器。戦車型
チーター:対人型用無人多脚型兵器。ベレッタM84を配備。
【異能】
・マルチクライアント
複数の機械を並行して操作できる能力。
自分は椅子に座りながらパソコンで検索しつつ、スマホでソシャゲを遊び、ドローンでコーヒーを持ってこさせるなどの使い方が出来る。
当人は戦場においてあらゆる盤面に配置した上記のドローンを大量に展開して戦闘・戦闘補助・輸送・偵察・監視を同時に行うことに利用する。
この能力が発動している間は、自分と操られている機械の眼(レンズ)が赤色に発光する。
【サブキャラクター】
天津風ヒトミのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=yfpP56Knt690e3ae4e8b6c5809bdc71325dbdb6a6d5
北野ソムクのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=P0IQAju3UlJ536e97d523c04fd97df74518e05b99cf
----
キャラクターイラスト:osisio様
アイコンイラスト:どぷり様













































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



「調子はどうかね」
「視野が急に広くなってまだ違和感はある……体も動かしにくい」
人体実験から数週間が経過した。何の因果か実験は成功してしまい、ミュータント候補生としてその身をやつしている。射撃場で『動作テスト』を行っていると背後から白衣の男に声を掛けられた。
眼は向けていないから服装は分からないが、いつもの声からしていつもの服装の人だろうと思った。
仮称『白衣の男』に目線をやらないまま的に向けて銃を構え、人体を模したパネルにマシンガンを叩きこむ。
トリガーを強く握り込んでやると、軽い感触とは裏腹に大きな反動が体を襲う。締め撃ちされた弾丸は的から少し上向きの方向に飛んで行った。
「良き兵士の育成には健全な肉体が不可欠だ。食育、美容、健康維持。カーボ・ローディングという手もある。しかしそれらはコストがかかる。時間も金も」
「ドクター、私は博士ではないから専門的なことは分かりません」
次の的に向けて射撃を行う。適宜修正を行い、握りしめた手を緩くする。今度はきちんと的に中った。ふ、と息を吐いて煙を噴き出したバレルを手入れしつつ振り返る。
やはりというべきか。白衣を着た初老の男は腰に手を当てた態勢で休憩用のベンチに座り込んでいた。
「注射一本だ。栄養源を直接摂取させた方が楽に違いない。経口摂取に頼らず栄養を注入するだけで良い。増幅剤を摂取した君は短期間で栄養を十分に補給し、年相応の見た目になった」
銃を構える少女は、10に満たないながらも最初に蹲っていた時と比べて見られる容姿になった。
ミリタリージャケットとに包まれた体はすっかり平均的な体重と見た目になり、茫洋とした眼はしっかりと開かれ背筋も伸びた。
ぼさぼさだったボブヘアもしっかりと整えられているが、これは先輩の女性士官候補が繕ってくれたものである。
口数が少なかった受け答えも応答程度なら問題なく出来るようになり、テストを経た後は実地訓練に向かうとのことで調整を行っていた。
「頭髪の張りも良くなったし、皮と骨ばかりだった肉も一気に増したから重たくなっただろうがね。それが人体だ。人は容易に肥え、また痩せることが出来る。出来てしまう。耐えられてしまう。実に難儀とは思わんかね」
「……死ににくい、という意味でしょうか」
「それもある。こうして心苦しい人体実験をしなければ生き残れない世も末だ」
主導している人間が何を悲観するのだろう。そうした実験の犠牲者を何人使い棄てたというのか。心にもない事を言うと少女は心の中でごちて次の銃火器を持つ。自分の背丈に程近いアサルトライフルだ。
常通り構えて撃つ。しかし反動が大きすぎたのか三点バーストを一度撃っただけでよろけて背後に転んでしまった。
最後に真上へ放たれた銃弾が跳弾し、自分の頬を掠めて地面を抉って行った。自然と汗が噴き出る。
今、自分は死にかけた。何の感慨も無く、走馬燈を思い描く暇すらない儘。冗談みたいに死にかけた。赤色の瞳がゆらゆらと揺れる。自然と涙で瞳が濡れ始めた。
「あ……ァ……」
「腕と目だけで銃を使うな。腰を据えろ、肩の力も入れ過ぎている。童には荷が重いだろうが、出来なければ死ぬぞ」
「……」
怯えている暇はない。鬼のような指導をしてくる兵士がいないことに感謝した。それでも背後から諫める声色を受ければ自然と立ち上がり、大きく掛け声を上げて再度銃を構え始める。
フラッシュが三回チラついた。足元が浮き上がるが、何とか銃身を固定したまま射撃することに成功した。
「もう少し肉体強化を図るか。その顔のままではアンバランスだが、増幅剤を使う副作用は確実に受けるだろうがね。
細胞の活性化を行わせるには生み出す以外に他所から取ってくるという手があってな。顔は少し幼さが残るが、これが一番手っ取り早い。
首から下の成長を促進させる代わりに顔立ちはあまり変わらなくなるよう改造してみよう。痕は残さんと保証するぞ」
提案を受けても、意思確認をしても、少女には拒否することは出来ない。
「分かりました、ドクター。手術はいつ頃」
「肉体の調整とサイボーグ化の癒着を鑑みて、3日後だ。所定の時間になったらメディカルルームへ来るように」
「はい、ドクター」
ではまた様子を見に来る。そう言った彼の背に向けて、今度は少女が声をかけて止める。
「ひとつ質問したいことがあります」
「許可しよう」
「……ドクターは従軍経験がおありなのでしょうか」
先の銃を指導する口振りがあまりに手慣れていたものだから。弱点を見抜き、叡智をひけらかすというのは経験則があってのことだ。
姿勢を正し、彼を見上げながら少女は問う。彼はこそばゆいとばかりに頬を掻いてからひとつ笑った。
「今よりもぬるい戦争状態の時にね。3年程戦地で過ごした。理学派の出で銃なぞ撃ったことも無いのにいけしゃあしゃあと、どつき回されながら撃ちまくった」
「人を殺したことはあるのでしょうか」
「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる。長く銃を手に取っているとな、撃った後に当たったという感覚が把握できるようになる。遠く離れているぞ、数百はくだらない遠い場所相手にだ。それでも手に取るように分かる。
お前の眼は視野の補強に加えて敵を確実に殺したと分かるようにセンサーを植え付けているが、経験があればそういうのも不要になる。ともあれば才能だったのかもしれない」
「……殺しの才能でしょうか」
純真な赤色の瞳は真っ直ぐ彼を見据えている。屈託なく怯えも無い、真実と向き合おうとするかのように真剣だった。
「もしかしたらあったかもしれないが今はこうして好き勝手実験三昧をしている。
いいかね、このように閉塞的な環境でも出来る事ややれることは数多存在する。今は候補生として戦地に赴くことは確定しているが、それ以外にも道はある可能性はある」
「私は実験体としてのみの生を受けたのではないのでしょうか」
「選択余儀の無い事象だっただけだ。戦地で華々しい活躍をすれば人らしい生活が出来るやもしれんし、ここの生活に甘んじて受け入れるもよし。死んだらそれまでだ」
では失礼する、と男は一礼して射撃演習場から立ち去って行った。
自分が今手に持つ銃を一瞥する。まだまだ少女の矮躯が扱いには重たすぎて、扱うのも一苦労な代物。
未だ演習ばかりで人を殺せるかも分からない。その才能があるかも不明。明日の事も何もかもが未知数で、手術の最中に死ぬ可能性とてある。
一体どういう希望や選択が出来るというのだろうか。
少女は鬱憤を晴らすようにアサルトライフルを構え、射撃練習に打ち込むことにするのだった。
――あと2150日だ。
赤色の雲が世界を覆っていた。
この世界に着た直後はまだ晴れ間が見えていたのに、今はすっかり太陽が影も形もなくなってしまった。廃墟となっているチナミ区は沿岸にほど近い場所だ。この場所では銃火器も錆びてしまうということで、東へ進み山を越えてヒノデ区へと向かうことにした。
10年前から世話になっているドクターが言うには、己の体は細胞が活性化しやすく、死ににくいらしい。そうなるように調整したからと言っていたが、兎角己の体は常に健康的で若々しく、裂傷を受けても即時再生を始める程度には体は強くなったという。
カロリーコントロールを行えば肉体は伸縮自在といっていい程に容易く、維持コストも安い。人間を止めるようなことが出来れば強化兵士としては誉れ高い存在になることだろう。そこまでやる心算も、その改造に同意する意向も五年前には示すことは最後まで無かったが。ともあれば今も同じ心境である。
アーカイブ化している記憶データを薬液のように注射する感覚が頭を駆け巡る。ひどく気分が悪くなるが、戦闘と移動の合間の休息時間にやっておかねば10年分のロードというのはあまりに長すぎる。直近の記憶と最古の記憶を同時にインプットしていくと少々こんがらがりそうになるが、もとよりそのための異能『マルチクライアント』である。記憶データの配列は常に最適化され、正しい位置へと収納されていく。
時間をかけてやっと必要分のデータを飲み込むと、えずくような感覚と共に大きく嘆息する。気分を晴らすために天を見上げても、やはり厚い雲に覆われてばかりで気分が晴れるような光景は何もなかった。
気を取り直して立ち上がる。先行しているドローン部隊は敵影の姿を確認していないが、目視でも確認を怠らず、銃を構えながら山間部へと入り込む。
いつどこで誰が待ち伏せしているかも分からない。慎重に歩みを進めて、会敵したらトリガーを引く。
――出来るのか、己に。
昨日まで挨拶をした隣人が、笑いあった友が、愛する者が己に武器を突きつけてきたらそれに反応できるのか。
一人でいるとどうしても無為な自問自答を重ねてしまう。直近の記憶のアーカイブは他人の記録映像を見ることに等しく、己ではない己の記憶を俯瞰的に見せられているようなものなのだ。
あちらのシルバーキャットとこちらのシルバーキャットは別物で、こちらの方が傭兵として絆されず、冷静に対処できるはずである。
確証はない。まだここでは撃ったことが無い。5年過ごしたという記憶と共に親しい者に銃を向けて殺せるのかは分からない。親しい者を作らなかった己には何一つとして分からない。
「引き金を引いてから考えろ」
敵が現れたら殺す。襲い掛かったら容赦なくナイフを突き立てる。傭兵は迷う必要なんてない。
考えるより行動を。行動をするなら理知的な思考をせよ。
硬く強張った手先に構えた銃を握り直す。今度は手を沿えるようにするだけでグリップを握る。
『腕と目だけで銃を使うな。腰を据えろ、肩の力も入れ過ぎている。童には荷が重いだろうが、出来なければ死ぬぞ』
――ドクターの言葉を思い出し更に銃を構え直す。基本に立ち返り、原初へ至り、シルバーキャットという存在を再定義する。イバラシティのシルバーキャットはここにはいない。
ハザマのシルバーキャットは記憶を抱きかかえるだけのユニットだ。傭兵だ。それを忘れるな。
シルバーキャットは息を深く吸い込んでから吐き出すと、止まっていた歩みを再び進めるのだった。



ENo.195 天使様 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.545 ハルキ/ユイカ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.671 海の魔物 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
玲子 「キャット先生がいてくれてよかった! ボク、しっかりお手伝いするからね!」 |
 |
玲子 「あ、でもボク、戦ってる時はちょっと怖い姿になるかも。レーコは人に見せても教えてもダメっていつも言ってるけど、今は危ないから特別だって。先生、怖いの大丈夫?」 |







響鳴LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
具現LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
クロ(1253) とカードを交換しました!
☆ミ (アリア)


アクアシェル を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアボルト を研究しました!(深度1⇒2)
ファーマシー を研究しました!(深度1⇒2)
召喚強化 を習得!
祈誓 を習得!
サモン:サーヴァント を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



シルバーキャット(748) は 美味しくない草 を入手!
玲子(813) は 美味しくない草 を入手!
シルバーキャット(748) は 不思議な石 を入手!
シルバーキャット(748) は 毛 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
シルバーキャット(748) のもとに 歩行石壁 が空を見上げなから近づいてきます。



特に移動せずその場に留まることにしました。
結(1510) をパーティに勧誘しました!
仁(1511) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- 玲子(813) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 結(1510) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――







砲火後加害授業中
|
 |
常夜の魔手
|


ENo.748
シルバーキャット



硝煙の匂いをレモングラスの香水で紛らわす。
不条理に曝されても女は兵士として生きている。
無垢な顔立ちのまま、少女兵は此度も武器を取る。
その名は銀色の猫。数多の機械を操る科学の結晶。
少女の己を殺し、猫のように気儘に戦場を駆ける。
「敵対者を補足。猫の目は貴様を逃さない。
一匹たりとも逃がさない。徹底的に潰す。
侵略者よ、せめて敗走する権利は与えてやろう。
猫のテリトリーに立ち入ったこと、後悔して死ね」
【シルバーキャット】
女性/20歳(経歴詐称により27歳になっている)/177cm
【容姿】
10代後半程度の童顔。
銀髪のセミロングの髪。赤色の瞳。肌は透き通るような白さ。
白いVネックシャツと、ネイビー色の丈の短いキュロット。
カーキ色のミリタリージャケット。
ドッグタグを首から下げている。
【設定】
紛争地域のアンダーグラウンド出身。戦災孤児。
傭兵派遣会社『ブレーン・トルーパー社』に所属する。
主に市街・都市部への潜入・偵察を担当している。
今回はイバラシティに迫りくる危機(アンジニティ)を調査する為にブランブル女学院の保健・体育教師として潜り込んで来た。
潜入時の年齢は15歳。この5年間、ワールドスワップが始まるまでイバラシティを己の縄張りとして張り込み過ごしてきた。
思考速度と視神経を著しく引き上げられており、機械を自在に支配できる改造人間。
寡黙で冷徹な性格。希薄な感情の持ち主で大人しい。
ハザマではより冷酷な一面が浮き彫りになる。イバラシティで過ごした5年間の記憶を必要がある場合のみ落とし込み、深く関わりすぎた人物に対しても情を抱かない範疇で記憶操作している。
この影響でこちら側の精神年齢は10代で止まっている。
武器は銃とドローン、ロボット兵器。
特に市街戦に特化した戦闘スタイルで閉所・暗所は非常に有利。
遠近ともに殺人術に長けており、対人や包囲戦には滅法強い。
【所有ドローン】
ライオン:敵地工作用無人偵察機。クワッドコプター。
ジャガー:対電子戦用無人偵察機。戦闘機型
ピューマ:対市街調査用無人キャタピラ型兵器。戦車型
チーター:対人型用無人多脚型兵器。ベレッタM84を配備。
【異能】
・マルチクライアント
複数の機械を並行して操作できる能力。
自分は椅子に座りながらパソコンで検索しつつ、スマホでソシャゲを遊び、ドローンでコーヒーを持ってこさせるなどの使い方が出来る。
当人は戦場においてあらゆる盤面に配置した上記のドローンを大量に展開して戦闘・戦闘補助・輸送・偵察・監視を同時に行うことに利用する。
この能力が発動している間は、自分と操られている機械の眼(レンズ)が赤色に発光する。
【サブキャラクター】
天津風ヒトミのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=yfpP56Knt690e3ae4e8b6c5809bdc71325dbdb6a6d5
北野ソムクのプロフィールへ
http://lisge.com/ib/prof.php?id=P0IQAju3UlJ536e97d523c04fd97df74518e05b99cf
----
キャラクターイラスト:osisio様
アイコンイラスト:どぷり様
25 / 30
30 PS
チナミ区
J-5
J-5







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | サタデーナイトスペシャル | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 腐り落ちたドッグタグ | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]耐疫10(LV30)[防具]体力10(LV30)[装飾]強靭10(LV30) | |||
| 9 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 具現 | 15 | 創造/召喚 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 武器 | 25 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| アシスト | 5 | 0 | 50 | 自:束縛+自従全:AT・DX増 | |
| クリエイト:パワードスピーカー | 5 | 0 | 130 | 自:魅了LV増 | |
| シュリーク | 5 | 0 | 50 | 敵貫:朦朧+自:混乱 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 祈誓 | 5 | 3 | 0 | 【通常攻撃後】自:祝福消費でDF・LK増(2T) |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]アクアシェル | [ 2 ]ファイアボルト | [ 2 ]ファーマシー |

PL / えーや