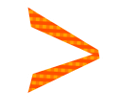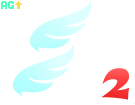<< 3:00>> 5:00




03 / 03:00
物心ついた時から、わたしの側にはお母さんだけがいた。
お屋敷に、あの人とわたし。
二人で暮らすには大きすぎるくらいだったけれど、
フリージアの香る中庭の、芝生の上に寝転んで。
頭が痛くなるからと膝枕をしてもらった、いつかの思い出。
わたしは、そんなのんびりとした日々が好きだった。
たまに、黒い服を着た怖い人達が廊下を歩いていることがあった。
ただでさえ大きな家の中。自分以外の誰かがいたら、気になって仕方がない。
黒い人。白い人。
ふさふさの人。つるつるの人。
ヒゲの人。ツルツルの人。
何人も居るようだった。
毎日かわりばんこに廊下を歩き、いつもわたしの方を見て、
けれど声をかけようとするとどこかに行ってしまう。
わたしが大きくなっても、お屋敷にいる人は両手で数えられるほどだ。
わたし、お母さん、お父さん、お姉ちゃん、黒い服の人たち、メイドさん。
小さかった頃のわたしは、それが全てだと思っていた。
「お屋敷の外へ出てはいけない」と、お母さんは言う。
わたしはその言葉を、約束を破らずに、お屋敷の中を歩いて、走って、探検して、遊び回った。
ある時、お屋敷の地下まで迷い込んだわたしは、一際大きな扉のついた暗い部屋に入ったことがあった。
本棚と木箱が並んだ、不思議な部屋。そこはとても冷たくて、とても暗くて、とても怖かった。
ぶるぶると震えながらなんとか周りを見渡して、背の低い机の上に小さな桐の箱が置いてあることに気がついた。
その箱を持って自分の部屋に帰り、中を覗いた瞬間。
眼の前に、大きな"ワニ"が浮かんでいた。
◆ ◆ ◆
物心ついて間もない頃、ある男はわたしに言った。
「お前など、生まれるべきではなかった」
――と。
それは凡そ人の親が発していい言葉ではないはずで。
しかし、当時のわたしはその台詞と、捲し立てる男の形相とが頭にこびりついて、事あるごとに恐怖した。
そんなことを口走ったあの男と、それについて従う数年歳上の女は、わたしに対して何一つ反応することはない。
……当然だ。
女と男が混ざりあった身体に生まれただけでない。
人ならざる力までもこの身に宿した娘など、一体誰が可愛がれるというのだ。
客観的に見れば彼らの反応こそが正常で、母の行動こそが異常に映る。
双海の家系では特別珍しくもないそれら特徴を、二人が偶々受け継がずにいたというだけで、世界の常識は逆転する。
わたしの存在を認めようとしない連中は、『無視する』ことを選んだ。
剰え、使用人を通して必要以上の外出を制限し、唯一許された学校への通学に至っても真っ直ぐ下校するよう徹底された。
交友関係は殆ど無く、校内行事の参加など以ての外である。
あんな者たちでも、世間一般では"父"や"姉"と呼んでわたしと結びつけようとする。
不愉快という感情すら湧いてこない。
無視されるのであれば、こちらも無視すればよいと気がついたのは、入学から一年ばかり捻くれた後のことだ。
あの男の所為で少なからず歪んで育ったであろうことは否定しない。
家庭内におけるわたしの立場がどうなろうと、もはやどうでもよかった。
それでも母に迷惑を掛けて、無理をさせてやいないかと心を痛め。
何年も、何年も、"家族ごっこ"を続けてしまった。
恐らくは、わたしが何歳になろうと、その関係が続くはずだった。
あの男
ただ一つ――お父さんが母に手を上げさえしなければ。
◆ ◆ ◆
"ミクスタ"というのは、それを初めて見たその時に、ふと頭の中に浮かんだ名前だった。
ナ ナ カ マ ド
『Sorbus commixta』のもじりだと分かったのは、それからずっと先になる。
ぼんやりと薄く色付いていた頃の"ミクスタ"は、自分の部屋の中でのみ形を保つことができた。
扉や窓などのはっきりとした線を境に、室内という『海』を泳ぎ回る自由な生き物であった。
喋ったりはしない。手で触れられもしない。言っていることを理解出来ているのかも分からない。
ふよふよと浮かんだまま、こちらの呼びかけや動作に反応するように、じたばた手足を掻いて楽しませてくれた。
その一点だけで、わたしは"ミクスタ"に興味を抱いた。
一ヶ月、一年と過ぎていくにつれ、"ミクスタ"はわたしの部屋のみならず、廊下をも泳げるようになっていった。
母を始め他人に見られないよう気をつけながら、お屋敷という名の大海原に繰り出しては不思議な生き物について理解を深める。
まんまるで愛嬌のあるワニが新たに広がった世界を前に燥ぎ回る。
そんな姿を眺めるうち、わたしはこの奇妙な生き物と不可解な空間に、どうしようもなく惹かれていた。
あの男が母を傷付けた、いつかの夜。
"ミクスタ"が人の形を得て、確かな実体を持って現れたあの日。
連中
わたしは、家族が自分を避けていた理由の一端を漸く思い知った。
/ 04:00



ENo.102 守屋弓弦 とのやりとり

ENo.445 餅田 とのやりとり

ENo.709 ティーナ とのやりとり

ENo.922 黒木 蒔那 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.7 不思議なサラダ を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









夏鈴(6) は ド根性雑草 を入手!
七夏(89) は ネジ を入手!
結唯(110) は ド根性雑草 を入手!
一彩(548) は 吸い殻 を入手!
夏鈴(6) は 牙 を入手!
一彩(548) は 美味しい果実 を入手!
七夏(89) は 牙 を入手!
結唯(110) は 花びら を入手!



時空LV を 1 DOWN。(LV10⇒9、+1CP、-1FP)
領域LV を 1 DOWN。(LV16⇒15、+1CP、-1FP)
付加LV を 2 DOWN。(LV6⇒4、+2CP、-2FP)
使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
味噌ジル(362) とカードを交換しました!
自棄食い (ヒール)

ラッシュ を習得!
ウィンドリング を習得!
ラッキータイム を習得!



夏鈴(6) に移動を委ねました。
チナミ区 O-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 P-6(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 Q-6(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 Q-5(沼地)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 Q-4(沼地)に移動!(体調18⇒17)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



03 / 03:00
物心ついた時から、わたしの側にはお母さんだけがいた。
お屋敷に、あの人とわたし。
二人で暮らすには大きすぎるくらいだったけれど、
フリージアの香る中庭の、芝生の上に寝転んで。
頭が痛くなるからと膝枕をしてもらった、いつかの思い出。
わたしは、そんなのんびりとした日々が好きだった。
たまに、黒い服を着た怖い人達が廊下を歩いていることがあった。
ただでさえ大きな家の中。自分以外の誰かがいたら、気になって仕方がない。
黒い人。白い人。
ふさふさの人。つるつるの人。
ヒゲの人。ツルツルの人。
何人も居るようだった。
毎日かわりばんこに廊下を歩き、いつもわたしの方を見て、
けれど声をかけようとするとどこかに行ってしまう。
わたしが大きくなっても、お屋敷にいる人は両手で数えられるほどだ。
わたし、お母さん、
小さかった頃のわたしは、それが全てだと思っていた。
「お屋敷の外へ出てはいけない」と、お母さんは言う。
わたしはその言葉を、約束を破らずに、お屋敷の中を歩いて、走って、探検して、遊び回った。
ある時、お屋敷の地下まで迷い込んだわたしは、一際大きな扉のついた暗い部屋に入ったことがあった。
本棚と木箱が並んだ、不思議な部屋。そこはとても冷たくて、とても暗くて、とても怖かった。
ぶるぶると震えながらなんとか周りを見渡して、背の低い机の上に小さな桐の箱が置いてあることに気がついた。
その箱を持って自分の部屋に帰り、中を覗いた瞬間。
眼の前に、大きな"ワニ"が浮かんでいた。
◆ ◆ ◆
物心ついて間もない頃、ある男はわたしに言った。
「お前など、生まれるべきではなかった」
――と。
それは凡そ人の親が発していい言葉ではないはずで。
しかし、当時のわたしはその台詞と、捲し立てる男の形相とが頭にこびりついて、事あるごとに恐怖した。
そんなことを口走ったあの男と、それについて従う数年歳上の女は、わたしに対して何一つ反応することはない。
……当然だ。
女と男が混ざりあった身体に生まれただけでない。
人ならざる力までもこの身に宿した娘など、一体誰が可愛がれるというのだ。
客観的に見れば彼らの反応こそが正常で、母の行動こそが異常に映る。
双海の家系では特別珍しくもないそれら特徴を、二人が偶々受け継がずにいたというだけで、世界の常識は逆転する。
わたしの存在を認めようとしない連中は、『無視する』ことを選んだ。
剰え、使用人を通して必要以上の外出を制限し、唯一許された学校への通学に至っても真っ直ぐ下校するよう徹底された。
交友関係は殆ど無く、校内行事の参加など以ての外である。
あんな者たちでも、世間一般では"父"や"姉"と呼んでわたしと結びつけようとする。
不愉快という感情すら湧いてこない。
無視されるのであれば、こちらも無視すればよいと気がついたのは、入学から一年ばかり捻くれた後のことだ。
あの男の所為で少なからず歪んで育ったであろうことは否定しない。
家庭内におけるわたしの立場がどうなろうと、もはやどうでもよかった。
それでも母に迷惑を掛けて、無理をさせてやいないかと心を痛め。
何年も、何年も、"家族ごっこ"を続けてしまった。
恐らくは、わたしが何歳になろうと、その関係が続くはずだった。
あの男
ただ一つ――
◆ ◆ ◆
"ミクスタ"というのは、それを初めて見たその時に、ふと頭の中に浮かんだ名前だった。
ナ ナ カ マ ド
『Sorbus commixta』のもじりだと分かったのは、それからずっと先になる。
ぼんやりと薄く色付いていた頃の"ミクスタ"は、自分の部屋の中でのみ形を保つことができた。
扉や窓などのはっきりとした線を境に、室内という『海』を泳ぎ回る自由な生き物であった。
喋ったりはしない。手で触れられもしない。言っていることを理解出来ているのかも分からない。
ふよふよと浮かんだまま、こちらの呼びかけや動作に反応するように、じたばた手足を掻いて楽しませてくれた。
その一点だけで、わたしは"ミクスタ"に興味を抱いた。
一ヶ月、一年と過ぎていくにつれ、"ミクスタ"はわたしの部屋のみならず、廊下をも泳げるようになっていった。
母を始め他人に見られないよう気をつけながら、お屋敷という名の大海原に繰り出しては不思議な生き物について理解を深める。
まんまるで愛嬌のあるワニが新たに広がった世界を前に燥ぎ回る。
そんな姿を眺めるうち、わたしはこの奇妙な生き物と不可解な空間に、どうしようもなく惹かれていた。
あの男が母を傷付けた、いつかの夜。
"ミクスタ"が人の形を得て、確かな実体を持って現れたあの日。
連中
わたしは、
/ 04:00



ENo.102 守屋弓弦 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.445 餅田 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.709 ティーナ とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.922 黒木 蒔那 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.7 不思議なサラダ を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





Quartet
|
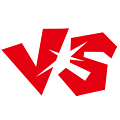 |
秘密結社『欠けた蜜蝋』
|



夏鈴(6) は ド根性雑草 を入手!
七夏(89) は ネジ を入手!
結唯(110) は ド根性雑草 を入手!
一彩(548) は 吸い殻 を入手!
夏鈴(6) は 牙 を入手!
一彩(548) は 美味しい果実 を入手!
七夏(89) は 牙 を入手!
結唯(110) は 花びら を入手!



時空LV を 1 DOWN。(LV10⇒9、+1CP、-1FP)
領域LV を 1 DOWN。(LV16⇒15、+1CP、-1FP)
付加LV を 2 DOWN。(LV6⇒4、+2CP、-2FP)
使役LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
味噌ジル(362) とカードを交換しました!
自棄食い (ヒール)

ラッシュ を習得!
ウィンドリング を習得!
ラッキータイム を習得!



夏鈴(6) に移動を委ねました。
チナミ区 O-6(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 P-6(道路)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 Q-6(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 Q-5(沼地)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 Q-4(沼地)に移動!(体調18⇒17)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――









ENo.89
双海七夏



名前/双海七夏 (ふたみ ななか)
性別/女
年齢/16歳→17歳
身長・体重/157cm 45kg
誕生日/1月27日
所属/相良伊橋高校二年五組、ファッションファッション部・民族文化研究部
住所/ツクナミ区 E-6 エクレールツクナミ702
( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2138 )
連絡先/個人宛IBALINE
( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2237 )
「コネクタがどれもこれも旧式じゃんか……よくこんなんで生活出来るなぁ」
「エロスこそ学業を乗り切る原動力。わざわざ登校するからには相応の対価を貰わなきゃあ」
「電子の海に溺れてみる?」
「からあげ……」
◆紹介◆
相良伊橋高二年の新学期に合わせて諸事情でイバラシティにやってきた高校生。ついてる。
電脳化しており、首の裏に接続用の端子がある。じっくり見ないと分からない感じ。通信中は何故かアホ毛がぴょこぴょこする。
制服のブレザーの内側に薄型のバッテリーや外付けのドライブを収納。見た目より重く校内ではたまに羽織る程度。
幼少期のあれやそれやでインドアが板についた。外に出たくない気持ちは強いものの、引きこもりというよりただの面倒臭がり。一度外出すれば一転して活発に歩き回る。要は電子機器に囲まれていたいだけ。
ネットサーフィンとオンラインゲーム、覗きが趣味。ハック、クラックはお手の物。
放課後や休日など時間が空いている時は街に繰り出し、食べ歩きやネットカフェ巡りに興じる。それとは別に、個人的な理由から「あるもの」を探して街を調べてもいる。
欲望に正直。女の子が好き。割と頻繁にいやらしいこと考えてる。たまに鼻血も出る。
好きな食べ物はホットドッグとフライドポテト、じゃがバター。ついで肉類、とりわけ鶏肉をよく食べる。
苦手な食べ物は辛いもの全般。イエローマスタードは平気。
一人称は「わたし」、二人称は「キミ」。他人を名前で呼ぶ時は呼び捨て。場合によってはあだ名を付ける。
◆能力◆
触れずに物を浮かせたり、自ら宙に舞ったりといった特異な力を持つ。世間一般で言うところの異能者。
後から力を加えない限りそれらはある程度の高さで浮遊した状態を維持し続ける。感覚としては無重量状態のそれだが、生物の体内で発生しうる各種変化は見られず、重力操作などとは異なる。
それとは別に、薄く色付いた透明なカードをどこからともなく取り出して、投擲したりナイフの代わりに使ったりもする。
が、これらは副次的に発生している現象であり、能力の本体・本質の部分は人前で見せようとしない。
手を抜いて楽したいとか他人を信用していないといった性質のものではなく、単純に対策が立てやすくタネが割れて周知されると困るから。
親しくなった相手には「火やら氷やら雷やら出すようなそういう派手なものでもなければ、怪力になったり傷がすぐ治ったりといったわかりやすいものでもないし、ましてや人と正面からやりあえる感じでもない」と自嘲気味に話すかもしれない。
その割には人前でふわふわ浮いたりする。
メタ的なおはなし
◆電脳について◆
Q.電脳化って何?
A.脳にマイクロマシンやナノマシンなどを注入し神経細胞とごにょごにょして脳と外部世界とを直接接続する技術。
俗に言うブレイン・マシン・インターフェース。
脳みそを取り出して機械にしました、というわけではない。
Q.電脳化すると何ができるの?
A.場所・環境を問わずネット上のあらゆる情報をリアルタイムに閲覧・検索・共有し、他者とのより正確なコミュニケーションが可能になる。
他にも手足を使わずに機械の操作ができたり、無線・有線関係なく端末を用いずに通信を行え、また電脳化している相手となら一部感覚の共有もできる。
見たものを写真・映像の両方で自由に記録する、専用の記憶装置に自分の記憶を移す、外部の必要な情報を抜き出して保管するなどして記憶力を増強したり、装置を経由して他人の記憶にアクセスし疑似体験するといったことも。
簡単に言えば、目に見えないほど小さなパソコンを自分の頭の中に作り上げる技術。
Q.割とずるくない?
A.異能だと認識されてもおかしくない。
元々外の街の最先端技術なので普通の人から見れば充分人間離れしているし、やれることの幾つかは法に触れかねない。
但しイバラシティ自体の電子化がそこまで進んでいないことと、携帯電話や無線通信に相乗りしている形になることを考慮するとスペックの半分も発揮できない。
手を使わずにやれるのは写真撮影とブラウジング、電話くらい。電子機器と直接繋がった場合はその限りでない。
Q.描写的には?
A.「こめかみを指でとんとん」「額に指をあてる」「顎に手を添える」など、七夏の癖でもあるアナクロな考える人的ポーズは大体通信中。
他にも「視界の隅に~」から始まり「ウィンドウ」や「表示」などを含む文章も同様。
Q."ミクスタ"?
A.七夏を補佐する人工知能の名前。
デフォルメされた緑色のワニのキャラクターとしての姿を取り、七夏の電脳内に常駐して彼女からの指示を実行する。
言葉を発することはない。イメージはデスクトップマスコット。もっと言えばネッ○ナビ。
性別/女
年齢/16歳→17歳
身長・体重/157cm 45kg
誕生日/1月27日
所属/相良伊橋高校二年五組、ファッションファッション部・民族文化研究部
住所/ツクナミ区 E-6 エクレールツクナミ702
( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2138 )
連絡先/個人宛IBALINE
( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2237 )
「コネクタがどれもこれも旧式じゃんか……よくこんなんで生活出来るなぁ」
「エロスこそ学業を乗り切る原動力。わざわざ登校するからには相応の対価を貰わなきゃあ」
「電子の海に溺れてみる?」
「からあげ……」
◆紹介◆
相良伊橋高二年の新学期に合わせて諸事情でイバラシティにやってきた高校生。ついてる。
電脳化しており、首の裏に接続用の端子がある。じっくり見ないと分からない感じ。通信中は何故かアホ毛がぴょこぴょこする。
制服のブレザーの内側に薄型のバッテリーや外付けのドライブを収納。見た目より重く校内ではたまに羽織る程度。
幼少期のあれやそれやでインドアが板についた。外に出たくない気持ちは強いものの、引きこもりというよりただの面倒臭がり。一度外出すれば一転して活発に歩き回る。要は電子機器に囲まれていたいだけ。
ネットサーフィンとオンラインゲーム、覗きが趣味。ハック、クラックはお手の物。
放課後や休日など時間が空いている時は街に繰り出し、食べ歩きやネットカフェ巡りに興じる。それとは別に、個人的な理由から「あるもの」を探して街を調べてもいる。
欲望に正直。女の子が好き。割と頻繁にいやらしいこと考えてる。たまに鼻血も出る。
好きな食べ物はホットドッグとフライドポテト、じゃがバター。ついで肉類、とりわけ鶏肉をよく食べる。
苦手な食べ物は辛いもの全般。イエローマスタードは平気。
一人称は「わたし」、二人称は「キミ」。他人を名前で呼ぶ時は呼び捨て。場合によってはあだ名を付ける。
◆能力◆
触れずに物を浮かせたり、自ら宙に舞ったりといった特異な力を持つ。世間一般で言うところの異能者。
後から力を加えない限りそれらはある程度の高さで浮遊した状態を維持し続ける。感覚としては無重量状態のそれだが、生物の体内で発生しうる各種変化は見られず、重力操作などとは異なる。
それとは別に、薄く色付いた透明なカードをどこからともなく取り出して、投擲したりナイフの代わりに使ったりもする。
が、これらは副次的に発生している現象であり、能力の本体・本質の部分は人前で見せようとしない。
手を抜いて楽したいとか他人を信用していないといった性質のものではなく、単純に対策が立てやすくタネが割れて周知されると困るから。
親しくなった相手には「火やら氷やら雷やら出すようなそういう派手なものでもなければ、怪力になったり傷がすぐ治ったりといったわかりやすいものでもないし、ましてや人と正面からやりあえる感じでもない」と自嘲気味に話すかもしれない。
その割には人前でふわふわ浮いたりする。
メタ的なおはなし
◆電脳について◆
Q.電脳化って何?
A.脳にマイクロマシンやナノマシンなどを注入し神経細胞とごにょごにょして脳と外部世界とを直接接続する技術。
俗に言うブレイン・マシン・インターフェース。
脳みそを取り出して機械にしました、というわけではない。
Q.電脳化すると何ができるの?
A.場所・環境を問わずネット上のあらゆる情報をリアルタイムに閲覧・検索・共有し、他者とのより正確なコミュニケーションが可能になる。
他にも手足を使わずに機械の操作ができたり、無線・有線関係なく端末を用いずに通信を行え、また電脳化している相手となら一部感覚の共有もできる。
見たものを写真・映像の両方で自由に記録する、専用の記憶装置に自分の記憶を移す、外部の必要な情報を抜き出して保管するなどして記憶力を増強したり、装置を経由して他人の記憶にアクセスし疑似体験するといったことも。
簡単に言えば、目に見えないほど小さなパソコンを自分の頭の中に作り上げる技術。
Q.割とずるくない?
A.異能だと認識されてもおかしくない。
元々外の街の最先端技術なので普通の人から見れば充分人間離れしているし、やれることの幾つかは法に触れかねない。
但しイバラシティ自体の電子化がそこまで進んでいないことと、携帯電話や無線通信に相乗りしている形になることを考慮するとスペックの半分も発揮できない。
手を使わずにやれるのは写真撮影とブラウジング、電話くらい。電子機器と直接繋がった場合はその限りでない。
Q.描写的には?
A.「こめかみを指でとんとん」「額に指をあてる」「顎に手を添える」など、七夏の癖でもあるアナクロな考える人的ポーズは大体通信中。
他にも「視界の隅に~」から始まり「ウィンドウ」や「表示」などを含む文章も同様。
Q."ミクスタ"?
A.七夏を補佐する人工知能の名前。
デフォルメされた緑色のワニのキャラクターとしての姿を取り、七夏の電脳内に常駐して彼女からの指示を実行する。
言葉を発することはない。イメージはデスクトップマスコット。もっと言えばネッ○ナビ。
17 / 30
142 PS
チナミ区
Q-4
Q-4











| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 5 | 『電脳回路の栞』 | 装飾 | 20 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 7 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 8 | 『電子海洋の衣』 | 防具 | 33 | 防御10 | - | - | |
| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 10 | 『電子海洋の衣』 | 防具 | 36 | 加速10 | - | - | |
| 11 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 12 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]器用10(LV15)[装飾]反撃10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 9 | 空間/時間/風 |
| 使役 | 5 | エイド/援護 |
| 領域 | 15 | 範囲/法則/結界 |
| 装飾 | 25 | 装飾作製に影響 |
| 付加 | 4 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ディスカード (ブレイク) | 7 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| トリック (ピンポイント) | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| ダブルヘッド (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| スラム (ブラスト) | 6 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 7 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 | |
| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| ウィンドリング | 5 | 0 | 80 | 味全:AG増(2T) | |
| ブロック | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増+護衛 | |
| ラッキータイム | 5 | 0 | 100 | 味全:LK増(3T) | |
| サイバースケイル (エアスラスト) | 5 | 0 | 60 | 敵:4連風撃 | |
| テリトリー | 6 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |
| ディープトルネード (トルネード) | 5 | 0 | 200 | 敵列:風撃(対象の領域値[風]が高いほど威力増) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ヒール (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 決3 |
おいしい水 (アクアヒール) |
0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
|
ソングオブマインド (バトルソング) |
0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) | |
|
自棄食い (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]アクアヒール | [ 1 ]イレイザー |
| [ 1 ]パワフルヒール | [ 1 ]イバラ | [ 1 ]ワイヤートラップ |

PL / かのしき