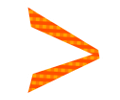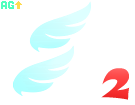<< 2:00>> 4:00




ハザマでの二時間が経過した。
アンジニティ陣営の襲撃から這う這うの体で逃げ出した一行は、道中見つけた人気の無い廃墟群に漸く身を落ち着けたのだった。
壱子という老人を伴ってはいるものの、彼女もまた異能の使い手。
その一端により『靴』という道具に熟達した彼女を交えた逃走自体は速いペースだった筈だ。
へたり込む老婆の消耗は当然であったし、結城兄妹もまた、瓦礫に背を預け呼吸を整えるのがやっとの有様だ。
そんな中唯一呼吸を乱すこともなく平然とした様子でいたのが吸血鬼である。
手近な残骸に腰かけて三者を一瞥すると、彼は容赦なく作戦会議の口火を切った。
「全員五体満足、大きな負傷はなし。というわけで話を続けるぞ」
オニキスが語ったのは、アンジニティという世界の仕組みだった。
無数に存在する分割世界の追放者を押し込めた監獄こそ、否定の世界アンジニティの正体なのだという。
ただ荒野が広がるだけの虚無の世界で、罪人たちが己の命を一日でも永らえさせんと鎬を削る場所。
それ故に侵略者として送り込まれた存在は、アンジニティの中でも『奪う側』に属する者であることは想像に難くない。
一通りの説明を終えたオニキスが他に聞きたいことはあるかと問うたところで、漸く壱子が息を整えながら口を開いた。
「……アンジニティ」
「最初の、あのわからない生物みたいなのと戦いなさいと言われるほうが、正直マシだったかもしれないわねえ」
言葉に混じる苦笑の色は、彼女が人間――少なくとも彼女はそう認識しているであろう者――との戦闘に乗り気ではないことを示していた。
勝たなければ、イバラシティの住人が追放される。アンジニティという牢獄の罪人たちを全て解き放つことになってしまう。
頭では理解していても、自分たちと同じ姿をした相手に武器を振るわねばならないというのは、あまりに残酷な話だった。
「その『侵略』に勝てば、すべて元通り、なのかしら」
「そうだ。勝てばいい。『元通り』にしたければ勝つしかない」
縋るように尋ねた老婆の言葉は、意外にも吸血鬼によって力強く肯定される。
勝てばいい。勝てばすべてが元通りになる。
難題ではあれど単純明快なその答えは、少しは場の雰囲気を明るくしたのだろう。
続いて巳羽も己の疑念を口にしていった。
「そんな彼らに、『喰われ』ないようにするには、どうしたら良いんでしょうか。……打ち勝つのは難しくても、勝利を渡さないようにする、方法」
普段であれば真っ先に質問を投げかけるであろう少年がそれまで一言も発することのなかったのは些か不審だったかもしれないが、幸い病弱な身だ。巳羽や壱子にとっては、乱れた息を整えていていたように映っていたことだろう。
壱子や巳羽に比べると随分と落ち着き払った様子で、伐都が質問に割って入った。
その証拠が、今の五体満足の結果だ。
本来であれば、勝負にさえならない筈なのだ。
だが、このゲームは一方的な『狩り』ではない。
あくまでこのハザマで行われるのは『争い』なのだ。
普通の人間は、そもそも相手が『敵』と言えど躊躇なく武器を振り下ろすことなど出来はしない。
無意識のうちに理性は力をセーブし、予想外の事象には衝撃を受け、付け焼刃の戦術や陣形などというものは簡単に瓦解してしまう。
それこそが、『慣れ』。アンジニティをアンジニティたらしめる要因であり、安穏としたイバラシティに生きる人々にはけして持ちえないものなのだ。
「はん。……そこのコウモリくんの言う通り、純粋な力という点ではお前らイバラシティは最早アンジニティとそう大して変わりはしない。経験の差は埋まりようがねえが、補うことはできるだろう」
吸血鬼は伐都の意見を肯定しながらも、だが、と続ける。
「――それだけじゃ、まだ足りねえな」
「慣れが冷静さを支え、その冷静さが観察の土台を作り、勝利への道標を作り出す。
……じゃあ、何故奴等はそこまで慣れた?」
「繰り返しになるが奴等は負け犬だ。だが、まだ生きている。世界から否定されて、牢獄送りになって、それでもまだ、こんなくだらねえゲームに乗じて脱出する気概を残してな」
それから少しの間を空けて、男は再び口を開いた。
アンジニティは己を『定義』していると。
絶対的な窮地、不可避の絶望、それらに屈さないだけの自我。
己に『かくあるべし』と課したことで揺るがぬそれが、イバラシティの人間との本質的な差なのだと。
何故戦うのか。ただの自己防衛に留まらないだけの理由が必要なのだ。
命の灯が尽きかけるその瞬間まで、闘志を燃やすだけの理由が。
「これは全部悪い夢で、目を閉じて朝が来れば『いつも通り』が返ってくるのだと。……そんな誘惑に抗うだけの『己自身』がてめえらにはあるのか、ってこった」
吸血鬼の紅い双眸が三者を見渡す。
その言葉がイバラシティの人間だけに向けた言葉ではないことは、伐都が一番よく分かっていた。
否定の世界を生き抜いたイデオローグという『己の定義』を、自ら投げ捨ていたのだから。
「今2時間と15分が経過した。残りは34時間。本格的な衝突になるのはおそらく後半戦、早くても20時間を経過してからになるだろう。そしてそんなところまで殻のついたひよこ共を連れ回すほど俺は間抜けじゃない」
「――10時間だ。開幕から10時間が経過するまでに己を定義しろ。それが俺からの最初の要求だ」
オニキスの説く内容は尤もだった。
覚悟を裏打ちする己の定義。それはあらゆる状況に挫けぬ為の杖となり、自身の魂火を絶やさぬ為の薪となる。
異能とは肉体のみならず、精神より出づるもの。それ故に、何を置いても自己の確立は避けては通れない道なのだ。
それがそう易々と実現出来ることでないことも明らかである。
しかし、結城伐都は知っていた。結城巳羽や都筑乙壱子の持つ心の一端を。その強さを。
心の強さとは、必ずしも冷酷であることや非情であることとイコールで結ばれるとは限らない。
彼女たちの持つ美徳は、むしろそれらとは正反対のものなのだ。
「不慣れで、わからなくて、覚悟を決めた人たちの前にあったら、確かにそれは、勝てるものも、勝てないわねえ」
「『かくあるべし』。難しい、ことねえ」
吸血鬼の言葉を反芻する老婆の様子は、それでも思考を手放してはいなかった。
その言葉は、自分自身にも言い聞かせるかのように。
出自こそアンジニティ側であり、先刻まではいやに冷静に状況を分析していたものの、少年に動揺が無いとは言えなかった。
過去の己を捨て、勝算の無い『自分以外の大切な人を失うかもしれない戦い』に身を投じることには、いくらかの不安を感じていたのだ。
それをどれだけ悟らせずにいられるのかは分からない。しかし、見え透いた空元気だとしても、少年はそう振る舞わずにはいられなかった。
悩みながらも言葉を紡ぎ出した少女に対し、見逃せないとばかりに吸血鬼が問う。
『ならどうするか』。アンジニティとの戦闘を避けるその間に、何を己に積み上げるのか。
少女に寄り添う訳でもなければ、踏みにじる訳でもない。オニキスの質問は至極単純なものだった。
そいつは案外いいセン行ってるかもしれないぜ」
このゲームは、『世界影響力』と呼ばれるパイを奪い合う競争だ。
それは敵対勢力に勝つことと、ハザマの生物を討伐することでのみ得ることができる。
問題は、『敵対勢力に勝つ』という部分なのだと、少年は説明を始めた。
早い段階で無策に当たり勝利を与えてしまえば、それだけアンジニティの陣営が持つ影響力が強めてしまうことになる。
勿論、逃げ続けてしまえば悪手となるが、勝算を得られるまでとあれば話は別だ。
少年の提案を肯定するように、老婆が同意の言葉と笑みを零す。
その表情には、子供たちが殺し合わずに済むことへの安堵の色が浮かんでいたようだった。
黙って聞いていた吸血鬼も、三人の出した結論に異論を挟むことはなかった。
「いいだろう。次は小娘が提案した方針に乗ってやる。いいか、常に己の意志で考え続けろ。この空間で確かなもんがあるとしたらそれだけだ。……10分後に行動再開」
「鬼の居ぬ間に楽しくお喋りしようが一向に構わねえが、大人しく休んだ方が賢明だぞ。僅かな時間で少しでも疲労を抜く方法を無理やりにでも覚えろ」
吸血鬼が何処ぞへと消えてから、少年は糸の切れた人形のように地面に倒れ込む。
他愛の無い話を誰より愛する彼も、今だけは少しでも眠りたかった。
2時間と25分経過。世界はまた、動き出す。



ENo.393 用瀬 樒 とのやりとり

ENo.723 小和泉 来夢 とのやりとり

ENo.1022 我孫子 智之 とのやりとり

以下の相手に送信しました











ザクロ(307) は 何かの殻 を入手!
巳羽(507) は ぬめぬめ を入手!
バツ(508) は ぬめぬめ を入手!
いちこ(1106) は アルミ缶 を入手!
巳羽(507) は 甲殻 を入手!
いちこ(1106) は 羽 を入手!
ザクロ(307) は 甲殻 を入手!
バツ(508) は ぬめぬめ を入手!
いちこ(1106) は ねばねば を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
バツ(508) のもとに オオザリガニ が漢字2文字を掲げて近づいてきます。
バツ(508) のもとに オオホタル が軽快なステップで近づいてきます。



ちわわ をエイドとして招き入れました!
使役LV を 2 DOWN。(LV18⇒16、+2CP、-2FP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
ザクロ(307) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
巳羽(507) により ItemNo.1 どうでもよさげな物体 から防具『おまもり+』を作製してもらいました!
⇒ おまもり+/防具:強さ36/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
巳羽(507) の持つ ItemNo.8 花びら から射程3の武器『散花模様の石』を作製しました!
ItemNo.40 から射程1の武器『無から生まれるパワー』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
ItemNo.30 から射程1の武器『無から生まれるパワー』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
カシマ(562) により ItemNo.8 毛 から装飾『愛用のバンダナ』を作製してもらいました!
⇒ 愛用のバンダナ/装飾:強さ36/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
たっきー(278) とカードを交換しました!
ブラッドバースト (エキサイト)

サモン:セイレーン を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:セイレーン を研究しました!(深度1⇒2)
アキュラシィ を研究しました!(深度0⇒1)
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
ドローバック を習得!



チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――


















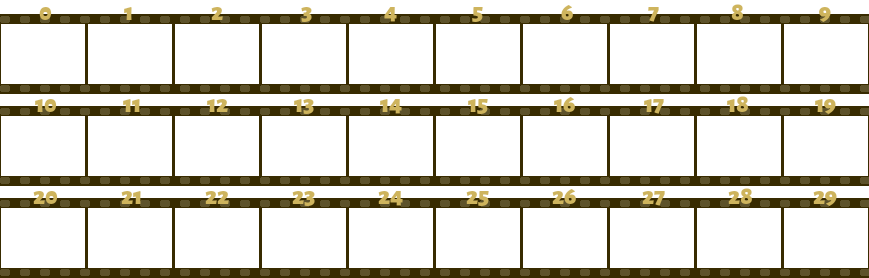


































No.1 ちわわ (種族:ちわわ)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



ハザマでの二時間が経過した。
アンジニティ陣営の襲撃から這う這うの体で逃げ出した一行は、道中見つけた人気の無い廃墟群に漸く身を落ち着けたのだった。
壱子という老人を伴ってはいるものの、彼女もまた異能の使い手。
その一端により『靴』という道具に熟達した彼女を交えた逃走自体は速いペースだった筈だ。
へたり込む老婆の消耗は当然であったし、結城兄妹もまた、瓦礫に背を預け呼吸を整えるのがやっとの有様だ。
そんな中唯一呼吸を乱すこともなく平然とした様子でいたのが吸血鬼である。
手近な残骸に腰かけて三者を一瞥すると、彼は容赦なく作戦会議の口火を切った。
「全員五体満足、大きな負傷はなし。というわけで話を続けるぞ」
オニキスが語ったのは、アンジニティという世界の仕組みだった。
無数に存在する分割世界の追放者を押し込めた監獄こそ、否定の世界アンジニティの正体なのだという。
ただ荒野が広がるだけの虚無の世界で、罪人たちが己の命を一日でも永らえさせんと鎬を削る場所。
それ故に侵略者として送り込まれた存在は、アンジニティの中でも『奪う側』に属する者であることは想像に難くない。
一通りの説明を終えたオニキスが他に聞きたいことはあるかと問うたところで、漸く壱子が息を整えながら口を開いた。
「……アンジニティ」
「最初の、あのわからない生物みたいなのと戦いなさいと言われるほうが、正直マシだったかもしれないわねえ」
言葉に混じる苦笑の色は、彼女が人間――少なくとも彼女はそう認識しているであろう者――との戦闘に乗り気ではないことを示していた。
勝たなければ、イバラシティの住人が追放される。アンジニティという牢獄の罪人たちを全て解き放つことになってしまう。
頭では理解していても、自分たちと同じ姿をした相手に武器を振るわねばならないというのは、あまりに残酷な話だった。
「その『侵略』に勝てば、すべて元通り、なのかしら」
「そうだ。勝てばいい。『元通り』にしたければ勝つしかない」
縋るように尋ねた老婆の言葉は、意外にも吸血鬼によって力強く肯定される。
勝てばいい。勝てばすべてが元通りになる。
難題ではあれど単純明快なその答えは、少しは場の雰囲気を明るくしたのだろう。
続いて巳羽も己の疑念を口にしていった。
「そんな彼らに、『喰われ』ないようにするには、どうしたら良いんでしょうか。……打ち勝つのは難しくても、勝利を渡さないようにする、方法」
 |
バツ 「負けないようにする為に出来ること。そいつはオニキスに訊くまでもないぜ、巳羽」 |
普段であれば真っ先に質問を投げかけるであろう少年がそれまで一言も発することのなかったのは些か不審だったかもしれないが、幸い病弱な身だ。巳羽や壱子にとっては、乱れた息を整えていていたように映っていたことだろう。
壱子や巳羽に比べると随分と落ち着き払った様子で、伐都が質問に割って入った。
 |
バツ 「よく考えてもみな。おれたちはこの世界へ来てから、随分と異能が強化されてるんだぜ。 ……まるで、アンジニティの奴らとは対等だと言わんばかりにね」 |
その証拠が、今の五体満足の結果だ。
本来であれば、勝負にさえならない筈なのだ。
だが、このゲームは一方的な『狩り』ではない。
あくまでこのハザマで行われるのは『争い』なのだ。
 |
バツ 「おれたちの明確な差は、争いに慣れているかどうか……その一点だけなのさ」 |
 |
バツ 「端的に言や、奴らは冷静だった。怖いくらいにさ。一方おれたちはどうだった? 見慣れねー異能、容赦なく向けられる敵意ってもんに浮足立って、連携どころじゃなかったよな。 つまるところ、勝敗を分けたのはそいつだと思うんだ」 |
普通の人間は、そもそも相手が『敵』と言えど躊躇なく武器を振り下ろすことなど出来はしない。
無意識のうちに理性は力をセーブし、予想外の事象には衝撃を受け、付け焼刃の戦術や陣形などというものは簡単に瓦解してしまう。
それこそが、『慣れ』。アンジニティをアンジニティたらしめる要因であり、安穏としたイバラシティに生きる人々にはけして持ちえないものなのだ。
 |
バツ 「だからこそ、今のおれたちには観察眼が必要なのさ。 これが対等な『ゲーム』である以上……必ず喰らい付く隙はある筈だ。 オニキスだってさっきの四人を相手に出来るほど万能じゃなかったんだ。 規格外の化け物なんて……きっと、このハザマには存在しない」 |
 |
バツ 「慌てちゃ駄目だ。隙を見せりゃカモにされちまう。 まずはよく見て……出来るだけ冷静に、落ち着いて敵の長所と短所を見極める。 そうすりゃ条件は互角の筈なんだ。 おれたちが目指すのは、まずそこだと思う。 難しいことかもだけど……やらなきゃ、生き残れねえ」 |
「はん。……そこのコウモリくんの言う通り、純粋な力という点ではお前らイバラシティは最早アンジニティとそう大して変わりはしない。経験の差は埋まりようがねえが、補うことはできるだろう」
吸血鬼は伐都の意見を肯定しながらも、だが、と続ける。
「――それだけじゃ、まだ足りねえな」
「慣れが冷静さを支え、その冷静さが観察の土台を作り、勝利への道標を作り出す。
……じゃあ、何故奴等はそこまで慣れた?」
「繰り返しになるが奴等は負け犬だ。だが、まだ生きている。世界から否定されて、牢獄送りになって、それでもまだ、こんなくだらねえゲームに乗じて脱出する気概を残してな」
それから少しの間を空けて、男は再び口を開いた。
アンジニティは己を『定義』していると。
絶対的な窮地、不可避の絶望、それらに屈さないだけの自我。
己に『かくあるべし』と課したことで揺るがぬそれが、イバラシティの人間との本質的な差なのだと。
何故戦うのか。ただの自己防衛に留まらないだけの理由が必要なのだ。
命の灯が尽きかけるその瞬間まで、闘志を燃やすだけの理由が。
「これは全部悪い夢で、目を閉じて朝が来れば『いつも通り』が返ってくるのだと。……そんな誘惑に抗うだけの『己自身』がてめえらにはあるのか、ってこった」
吸血鬼の紅い双眸が三者を見渡す。
その言葉がイバラシティの人間だけに向けた言葉ではないことは、伐都が一番よく分かっていた。
否定の世界を生き抜いたイデオローグという『己の定義』を、自ら投げ捨ていたのだから。
「今2時間と15分が経過した。残りは34時間。本格的な衝突になるのはおそらく後半戦、早くても20時間を経過してからになるだろう。そしてそんなところまで殻のついたひよこ共を連れ回すほど俺は間抜けじゃない」
「――10時間だ。開幕から10時間が経過するまでに己を定義しろ。それが俺からの最初の要求だ」
オニキスの説く内容は尤もだった。
覚悟を裏打ちする己の定義。それはあらゆる状況に挫けぬ為の杖となり、自身の魂火を絶やさぬ為の薪となる。
異能とは肉体のみならず、精神より出づるもの。それ故に、何を置いても自己の確立は避けては通れない道なのだ。
 |
バツ 「『刻限(タイムリミット)』は10時間目まで、か」 |
それがそう易々と実現出来ることでないことも明らかである。
しかし、結城伐都は知っていた。結城巳羽や都筑乙壱子の持つ心の一端を。その強さを。
心の強さとは、必ずしも冷酷であることや非情であることとイコールで結ばれるとは限らない。
彼女たちの持つ美徳は、むしろそれらとは正反対のものなのだ。
「不慣れで、わからなくて、覚悟を決めた人たちの前にあったら、確かにそれは、勝てるものも、勝てないわねえ」
「『かくあるべし』。難しい、ことねえ」
吸血鬼の言葉を反芻する老婆の様子は、それでも思考を手放してはいなかった。
 |
バツ 「そんな不安そうな顔すんなよ、二人とも。だいじょーぶだいじょーぶ。 あと八時間もあるんだぜ? おれたちなら、きっとやれるって」 |
その言葉は、自分自身にも言い聞かせるかのように。
出自こそアンジニティ側であり、先刻まではいやに冷静に状況を分析していたものの、少年に動揺が無いとは言えなかった。
過去の己を捨て、勝算の無い『自分以外の大切な人を失うかもしれない戦い』に身を投じることには、いくらかの不安を感じていたのだ。
それをどれだけ悟らせずにいられるのかは分からない。しかし、見え透いた空元気だとしても、少年はそう振る舞わずにはいられなかった。
 |
巳羽 「……冷静に観察する事、戦いに慣れること。あと8時間で、『己自身』を定義すること」 |
 |
巳羽 「この争いが避けられないのであれば。実戦の経験は、欲しいです。でも、正直今は、アンジニティには出会いたくない……」 |
悩みながらも言葉を紡ぎ出した少女に対し、見逃せないとばかりに吸血鬼が問う。
『ならどうするか』。アンジニティとの戦闘を避けるその間に、何を己に積み上げるのか。
少女に寄り添う訳でもなければ、踏みにじる訳でもない。オニキスの質問は至極単純なものだった。
 |
巳羽 「……こう言った状況に陥るのは初めての事なので、もっと良いやり方があるのなら、それに従うんですけど」 |
 |
巳羽 「ここに来ているイバラシティの人達に協力してもらって、戦ってみるのはどうかな、と……互いの経験になりますし、勝っても負けても、アンジニティが有利になる事はないから……」 |
 |
巳羽 「オニキスさんの話を聞く限り、アンジニティ側に私達みたいな、不慣れな人達はいないんでしょう? この後すぐ出会っても、正義のヒーローみたいに、次の話では逆転勝利、と言う風にはいかないと思って……」 |
 |
バツ 「……へえ、成る程。『練習試合』か。上手いこと考えたな。」 |
このゲームは、『世界影響力』と呼ばれるパイを奪い合う競争だ。
それは敵対勢力に勝つことと、ハザマの生物を討伐することでのみ得ることができる。
問題は、『敵対勢力に勝つ』という部分なのだと、少年は説明を始めた。
 |
バツ 「おれたちがこのままじゃ勝てないってんなら、勝てない間に相手を『勝たせない』……そいつも立派な戦術って訳だ。その間にイバラシティの奴ら同士で戦いの経験を積めるってんなら、そいつは『逃げ』にはならねえ」 |
早い段階で無策に当たり勝利を与えてしまえば、それだけアンジニティの陣営が持つ影響力が強めてしまうことになる。
勿論、逃げ続けてしまえば悪手となるが、勝算を得られるまでとあれば話は別だ。
| バツ 「おれの異能なら『手』を増やせる。そうだな、一時間から二時間……それくらいありゃ、少しは勝ち目も見えてくる筈だ。その間だけアンジニティの奴らとの戦いを避ける……ってことならどうだい?」 |
少年の提案を肯定するように、老婆が同意の言葉と笑みを零す。
その表情には、子供たちが殺し合わずに済むことへの安堵の色が浮かんでいたようだった。
黙って聞いていた吸血鬼も、三人の出した結論に異論を挟むことはなかった。
「いいだろう。次は小娘が提案した方針に乗ってやる。いいか、常に己の意志で考え続けろ。この空間で確かなもんがあるとしたらそれだけだ。……10分後に行動再開」
「鬼の居ぬ間に楽しくお喋りしようが一向に構わねえが、大人しく休んだ方が賢明だぞ。僅かな時間で少しでも疲労を抜く方法を無理やりにでも覚えろ」
吸血鬼が何処ぞへと消えてから、少年は糸の切れた人形のように地面に倒れ込む。
他愛の無い話を誰より愛する彼も、今だけは少しでも眠りたかった。
2時間と25分経過。世界はまた、動き出す。



ENo.393 用瀬 樒 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.723 小和泉 来夢 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.1022 我孫子 智之 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
以下の相手に送信しました







chimeRa
|
 |
熾す魂火
|



ザクロ(307) は 何かの殻 を入手!
巳羽(507) は ぬめぬめ を入手!
バツ(508) は ぬめぬめ を入手!
いちこ(1106) は アルミ缶 を入手!
巳羽(507) は 甲殻 を入手!
いちこ(1106) は 羽 を入手!
ザクロ(307) は 甲殻 を入手!
バツ(508) は ぬめぬめ を入手!
いちこ(1106) は ねばねば を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
バツ(508) のもとに オオザリガニ が漢字2文字を掲げて近づいてきます。
バツ(508) のもとに オオホタル が軽快なステップで近づいてきます。



ちわわ をエイドとして招き入れました!
使役LV を 2 DOWN。(LV18⇒16、+2CP、-2FP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
ザクロ(307) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
巳羽(507) により ItemNo.1 どうでもよさげな物体 から防具『おまもり+』を作製してもらいました!
⇒ おまもり+/防具:強さ36/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
巳羽(507) の持つ ItemNo.8 花びら から射程3の武器『散花模様の石』を作製しました!
ItemNo.40 から射程1の武器『無から生まれるパワー』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
ItemNo.30 から射程1の武器『無から生まれるパワー』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
カシマ(562) により ItemNo.8 毛 から装飾『愛用のバンダナ』を作製してもらいました!
⇒ 愛用のバンダナ/装飾:強さ36/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
 |
カシマ 「化繊で量産されるものではあるが。やはり愛用にするには素地のこだわりも必要だろう。」 |
 |
たっきー(278) とカードを交換しました!
ブラッドバースト (エキサイト)

サモン:セイレーン を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:セイレーン を研究しました!(深度1⇒2)
アキュラシィ を研究しました!(深度0⇒1)
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
ドローバック を習得!



チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――







サイコーbloody
|
 |
熾す魂火
|


ENo.508
結城 伐都



結城 伐都(ゆうき ばっと)
愛称はバツ。熾盛天晴学園2年3組に在籍。
不健康そうな隈の深い目、細い身体に吐血癖。
制服を肩に羽織るようにして着ている猫背の男。
無造作ヘアの上にバンダナを巻いている。
不良と呼ぶには貧弱で、病弱そうな見た目に反して緩く軽い。
熾盛天晴学園の昼の校内放送『ハレ高Balmy hour』のDJであり、イバラシティ内のクラブハウスでDJをやることも多い。
異能:『踊る阿呆に見る阿呆(バッド・トリップ・ダイブ)』
精神干渉系異能。『使役』に分類されるこの能力は、音楽に暗示を乗せる力を持っている。
イバラシティにおいてはこの能力は『自分のかけた音楽を聞いた相手が自然とノってしまう』という効果を発揮する。
ハザマにおいては一変し、この能力の本来の性質である『能力者の発した音を聞いた相手の精神に干渉し、幻覚を見せたり命令を聞かせる』といった効果へ変容する。
この能力は被術者の強い意志によって跳ね除けることが可能であり、人間やそれ以上の存在を相手にする場合は専ら弱らせた状態や合意を得た状態でなければ効果を適用できない。
ハザマでの姿
アンジニティからの侵略者としてイバラシティに現れた彼の正体は、蝙蝠の翼や耳などの特徴を持った人型の怪物『イデオローグ』。
放つ音波は精神に干渉し、格下の相手ならば傀儡へ変えてしまうことも可能。
アンジニティ時代は常に強い者につくための裏切り、弱者からの略奪を日常的に行ってきた悪名高い盗賊であり、憎む者も多い。
あなたがアンジニティの出身であるならば、彼に対して恨みを抱いているかもしれない。
暗示をもたらす音波を常に周囲に発することで、イデオローグはハザマ内でも自分の姿を結城伐都として見えるようにしている。
しかし、ハザマの強制力によって偽装は不完全になっており、身体の何処かは必ず怪物のまま。
その為、普段は伐都の姿の虚像を生み出すことで『異能で怪物を従えている結城伐都』であるかのように振る舞っている。
しかし、アンジニティの侵略者たちや解析の異能を持ったイバラシティの能力者たちならば、彼の正体を看破するのはそう難しくないだろう。
※既知設定歓迎です!
○サブキャラ
石蕗氷織(アイコン28)
熾盛天晴学園にて地学の授業を教えている教師。
天文部の顧問でもあり、28歳独身。
他人に適当なあだ名をつけて呼ぶのが趣味。
ミステリアスな雰囲気を醸し出してはいるものの、底は浅い。
所有している異能は『冷気』に関するものらしい。
かんなぎくん(アイコン29)
イバラシティの認可されていない非公式ゆるキャラ。
どうやら熾盛天晴学園の屋上に存在する神社に何やら関係のある存在らしいが、本人は特にそれについて自ら語ることはない。
何らかの異能によって着ぐるみそのものが命を宿して活動しており、専ら天文部の部室に居座って部員の皆と一緒に空に瞬く星を眺めている。
○よく出没するプレイス
熾盛天晴学園[カスミ区 O-10]
マンション『トライアングル』[カスミ区 Q-6]
IBALINE [リュウジン区 Q-20]
愛称はバツ。熾盛天晴学園2年3組に在籍。
不健康そうな隈の深い目、細い身体に吐血癖。
制服を肩に羽織るようにして着ている猫背の男。
無造作ヘアの上にバンダナを巻いている。
不良と呼ぶには貧弱で、病弱そうな見た目に反して緩く軽い。
熾盛天晴学園の昼の校内放送『ハレ高Balmy hour』のDJであり、イバラシティ内のクラブハウスでDJをやることも多い。
異能:『踊る阿呆に見る阿呆(バッド・トリップ・ダイブ)』
精神干渉系異能。『使役』に分類されるこの能力は、音楽に暗示を乗せる力を持っている。
イバラシティにおいてはこの能力は『自分のかけた音楽を聞いた相手が自然とノってしまう』という効果を発揮する。
ハザマにおいては一変し、この能力の本来の性質である『能力者の発した音を聞いた相手の精神に干渉し、幻覚を見せたり命令を聞かせる』といった効果へ変容する。
この能力は被術者の強い意志によって跳ね除けることが可能であり、人間やそれ以上の存在を相手にする場合は専ら弱らせた状態や合意を得た状態でなければ効果を適用できない。
ハザマでの姿
アンジニティからの侵略者としてイバラシティに現れた彼の正体は、蝙蝠の翼や耳などの特徴を持った人型の怪物『イデオローグ』。
放つ音波は精神に干渉し、格下の相手ならば傀儡へ変えてしまうことも可能。
アンジニティ時代は常に強い者につくための裏切り、弱者からの略奪を日常的に行ってきた悪名高い盗賊であり、憎む者も多い。
あなたがアンジニティの出身であるならば、彼に対して恨みを抱いているかもしれない。
暗示をもたらす音波を常に周囲に発することで、イデオローグはハザマ内でも自分の姿を結城伐都として見えるようにしている。
しかし、ハザマの強制力によって偽装は不完全になっており、身体の何処かは必ず怪物のまま。
その為、普段は伐都の姿の虚像を生み出すことで『異能で怪物を従えている結城伐都』であるかのように振る舞っている。
しかし、アンジニティの侵略者たちや解析の異能を持ったイバラシティの能力者たちならば、彼の正体を看破するのはそう難しくないだろう。
※既知設定歓迎です!
○サブキャラ
石蕗氷織(アイコン28)
熾盛天晴学園にて地学の授業を教えている教師。
天文部の顧問でもあり、28歳独身。
他人に適当なあだ名をつけて呼ぶのが趣味。
ミステリアスな雰囲気を醸し出してはいるものの、底は浅い。
所有している異能は『冷気』に関するものらしい。
かんなぎくん(アイコン29)
イバラシティの認可されていない非公式ゆるキャラ。
どうやら熾盛天晴学園の屋上に存在する神社に何やら関係のある存在らしいが、本人は特にそれについて自ら語ることはない。
何らかの異能によって着ぐるみそのものが命を宿して活動しており、専ら天文部の部室に居座って部員の皆と一緒に空に瞬く星を眺めている。
○よく出没するプレイス
熾盛天晴学園[カスミ区 O-10]
マンション『トライアングル』[カスミ区 Q-6]
IBALINE [リュウジン区 Q-20]
15 / 30
132 PS
チナミ区
K-14
K-14




































No.1 ちわわ (種族:ちわわ)
 |
|
|
||||||||||||



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | おまもり+ | 防具 | 36 | 治癒10 | - | - | |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | |||||||
| 4 | おまもり | 防具 | 25 | 防御10 | - | - | |
| 5 | ベトレイヤル | 武器 | 33 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | あったかお汁粉 | 料理 | 30 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 7 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV25)[装飾]加速10(LV25) | |||
| 8 | 愛用のバンダナ | 装飾 | 36 | 敏捷10 | - | - | |
| 9 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV25)[装飾]加速10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 使役 | 16 | エイド/援護 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 26 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 自傷命令 (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 自傷命令 (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| 自傷命令 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| 自傷命令 (ブラスト) | 6 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| プラシーボ (ヒール) | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練2 | エキサイト・サウンド (エキサイト) | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ラッシュ・ビート (ラッシュ) | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 | |
| 練1 | プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) |
| コンセントレイト・フォーサイト (リフレックス) | 5 | 0 | 80 | 味:AT・DX増(4T) | |
| アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 | |
| ドローバック | 5 | 0 | 80 | 敵:痛撃&麻痺 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 踊れ愚か者ども (魅惑) | 5 | 5 | 0 | 【常時】異能『使役』のLVに応じて、戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率が上昇 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
独りの街 (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
タイキック (ウィークポイント) |
0 | 140 | 敵:3連痛撃 | |
| 練2 |
ブラッドバースト (エキサイト) |
0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]エキサイト | [ 1 ]アキュラシィ | [ 3 ]サモン:ウルフ |
| [ 2 ]サモン:セイレーン |

PL / せい