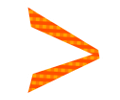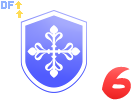<< 2:00>> 4:00




時間というのは残酷だ。最初に逃げた時もそうだったが、体力の衰えというのは激しく、老体にはこたえる。
――そう、敗北をしたから、先を行くオニキスを追いながら、再び逃走をしているのだ。
とはいえ、オニキスの指示がなければこうして生きて逃げられているのか、は、わからない。
息を一つ乱さず走り続ける青年を必死に追い、真っ先にへたり込んだのは紛れもなく壱子だった。
『――あれがアンジニティだ。』
否定された世界の住人。
荒廃という言葉では足りぬない、荒野の広がる監獄。
ここは世界を追い出された逸脱した世界であり、残っている侵略の加担者は『喰う側』であると。
「最初の、あのわからない生物みたいなのと戦いなさいと言われるほうが、
正直マシだったかもしれないわねえ」
アンジニティ。言葉で言えばそれだけの話であるが、それこそ目の前にいる巳羽や伐都とそう変わらない歳の少女たちの姿。オニキスの説明を聞きながら、古びたバス停を手に衝撃破で相手をたたきつけた音と感触は、離れない。
誰よりも先に倒れた力不足とはいえ、動揺もぬぐえない。けれどそれでも、一番最初、わけもわからずに走り抜けていた時よりは幾分冷静さを取り戻している。
「その『侵略』に勝てば、すべて元通り、なのかしら」
巳羽と伐都。まだ若い子達には変わらない日常がある。相変わらず難解なことはわからないが、
若い子達から日常を奪ってこの世界に閉じ込めるわけには、いかないのだ。
けれど――オニキス。ザクロ先生ではない。といった彼はどうなのだろうか、と。
問いかけた疑問には
『そうだ。勝てばいい。『元通り』にしたければ勝つしかない』
それは不正解ではないけれど、満点ではない答えだった。
疑問を抱かぬわけではない。けれど今のこの時点で尋ねたところでそれ以上の答えは返ってこないだろう。少なくともまだ政界への道筋が見えているのならばいいと、ほ、と息を一つつく。勝てば。さてその勝つ、が大変なのだけれど。
まさしく少女が問いかけたのが、それだ。
『そんな彼らに、『喰われ』ないようにするには、どうしたら良いんでしょうか。
……打ち勝つのは難しくても、勝利を渡さないようにする、方法。』
『負けないようにする為に出来ること。そいつはオニキスに訊くまでもないぜ、巳羽』
オニキスへの問いかけに返したのは、少女の兄だった。
この世界での自分たちの異能強化――これは気付いていた。でなければバス停の標識なんて重たいものを、自分がいとも簡単にふるえるわけはないのだ。そして争い、敵意への慣れがアンジニティに比べてないこと。観察眼が必要なこと――
立て続けに言われた言葉に、目を見張りなるほどと思うより先に、覚えたのは違和感だった。
あまりにも判断力が〝冷静すぎる"。
自分や巳羽と同じ立場であるにもかかわらず、その姿は年相応の落ち着きや判断力ではないような気がした。
が、今はそこは考えるべきではないと、オニキスの言葉ですぐさま隅へ追いやられる。
『――それだけじゃ、まだ足りねえな』
なぜ彼らがそこまで『慣れた』か。
『――アンジニティは己を『定義』している』
『絶対的な窮地、不可避の絶望、それらに屈さないだけの自我。信念、誇り、義務、なんだっていい。
上等も下等も高貴も粗野も関係ねえ。奴等はただ己にそう課してきた、"かくあるべし"と』
そう問いかけていくオニキスの言葉は答えを求めているわけではない間をもって。
最初あったときに「ザクロ先生」を真似て言った時にはあれは意図的であったのであろう。
今果たして意識的か無意識かはわからないけれど、彼の言葉はとても聞きやすい。本当に賢く鋭いと言ってしまえばそれまでだけれど、それは本当によくできた教師や人が、誰かに物事を教えたり問いかけたりするときにとても――似ていると、感じた。
『――10時間だ。開幕から10時間が経過するまでに己を定義しろ。それが俺からの最初の要求だ」
命が尽きかけたその時にまで戦う意思を持っていられるのかと、彼は言った。
つまりその刻限までに彼の言う『定義』なくしてこの先はない。
あくまでオニキスは『協力をしてくれている』のだから。確かにお荷物をもって歩く必要はどこにもないだろう。けれど、それがすぐに自分には浮かぶわけもなく言葉は出てこない。
「『かくあるべし』。難しい、ことねえ」
言い聞かせるようにつぶやく言葉。そして少女も、老婆同様すぐには答えは出てこないようだった。が。
『この争いが避けられないのであれば。実戦の経験は、欲しいです。
でも、正直今は、アンジニティには出会いたくない……』
出てきた言葉に思わず目を見張った。その言葉にではどうするかと問いかけるオニキス。
その様子をはらはらと見守っていたが、自分が思うよりも少女はよほど、しっかりとしていた。
『こに来ているイバラシティの人達に協力してもらって、戦ってみるのはどうかな、と……
互いの経験になりますし、勝っても負けても、アンジニティが有利になる事はないから……』
『……へえ、成る程。『練習試合』か。上手いこと考えたな。
そいつは案外いいセン行ってるかもしれないぜ』
おれたちならきっとやれる。にへら、と笑いながら言って見せるどこかカラ元気を感じる伐都だが、巳羽の提案に対するそれをすかさず助ける伐都に目を細める。
最初にかすかにふるえていた少女はいったいどこへ、と。
そして少年を見て思う。先の冷静さはどこへ。けれどこちらを気遣う言葉と――少女の提案に対しての、回転の速さ。この、この兄妹は。
自然と、目を細めてしまう。
若さゆえの柔軟さなのか、彼らの真っすぐさなのかはわからないけれど。歳を重ねた老婆にとって、思い悩みながらも様々な考えを、提案を、そして道を見つけ出せることが、とてもまぶしくみえた。少なくともそれは、もう己にはないものだ。
ええ、ええ、と賛成の言葉を発しながら、確かにこの霞んだ目を、ずっと開いておくことが自分に出来る一つなのかもしれないと、思った。
(掌の中、錆びついた鉄がどれほど軽く、どれほど重く感じても)












ザクロ(307) は 何かの殻 を入手!
巳羽(507) は ぬめぬめ を入手!
バツ(508) は ぬめぬめ を入手!
いちこ(1106) は アルミ缶 を入手!
巳羽(507) は 甲殻 を入手!
いちこ(1106) は 羽 を入手!
ザクロ(307) は 甲殻 を入手!
バツ(508) は ぬめぬめ を入手!
いちこ(1106) は ねばねば を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
バツ(508) のもとに オオザリガニ が漢字2文字を掲げて近づいてきます。
バツ(508) のもとに オオホタル が軽快なステップで近づいてきます。



幻術LV を 3 DOWN。(LV18⇒15、+3CP、-3FP)
武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
カシマ(562) により ItemNo.9 毛 から装飾『いちごのストラップ』を作製してもらいました!
⇒ いちごのストラップ/装飾:強さ36/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
らび(363) により ItemNo.5 バス停の標識 に ItemNo.8 韮 を付加してもらいました!
⇒ バス停の標識/武器:強さ30/[効果1]回復10 [効果2]活力10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ザクロ(307) の持つ ItemNo.11 美味しい草 から料理『草団子』をつくりました!
巳羽(507) の持つ ItemNo.9 美味しい果実 から料理『あったかフルーツスープ』をつくりました!
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『桜餅』をつくりました!
⇒ 桜餅/料理:強さ36/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
かすみん(1273) とカードを交換しました!
おためしカード (ウィンドリング)

ディム を研究しました!(深度0⇒1)
ディム を研究しました!(深度1⇒2)
アキュラシィ を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を習得!
アイスバインド を習得!
リフレクション を習得!



チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――


















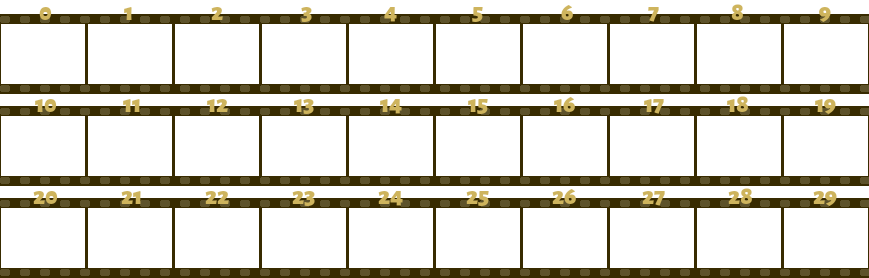





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



時間というのは残酷だ。最初に逃げた時もそうだったが、体力の衰えというのは激しく、老体にはこたえる。
――そう、敗北をしたから、先を行くオニキスを追いながら、再び逃走をしているのだ。
とはいえ、オニキスの指示がなければこうして生きて逃げられているのか、は、わからない。
息を一つ乱さず走り続ける青年を必死に追い、真っ先にへたり込んだのは紛れもなく壱子だった。
『――あれがアンジニティだ。』
否定された世界の住人。
荒廃という言葉では足りぬない、荒野の広がる監獄。
ここは世界を追い出された逸脱した世界であり、残っている侵略の加担者は『喰う側』であると。
「最初の、あのわからない生物みたいなのと戦いなさいと言われるほうが、
正直マシだったかもしれないわねえ」
アンジニティ。言葉で言えばそれだけの話であるが、それこそ目の前にいる巳羽や伐都とそう変わらない歳の少女たちの姿。オニキスの説明を聞きながら、古びたバス停を手に衝撃破で相手をたたきつけた音と感触は、離れない。
誰よりも先に倒れた力不足とはいえ、動揺もぬぐえない。けれどそれでも、一番最初、わけもわからずに走り抜けていた時よりは幾分冷静さを取り戻している。
「その『侵略』に勝てば、すべて元通り、なのかしら」
巳羽と伐都。まだ若い子達には変わらない日常がある。相変わらず難解なことはわからないが、
若い子達から日常を奪ってこの世界に閉じ込めるわけには、いかないのだ。
けれど――オニキス。ザクロ先生ではない。といった彼はどうなのだろうか、と。
問いかけた疑問には
『そうだ。勝てばいい。『元通り』にしたければ勝つしかない』
それは不正解ではないけれど、満点ではない答えだった。
疑問を抱かぬわけではない。けれど今のこの時点で尋ねたところでそれ以上の答えは返ってこないだろう。少なくともまだ政界への道筋が見えているのならばいいと、ほ、と息を一つつく。勝てば。さてその勝つ、が大変なのだけれど。
まさしく少女が問いかけたのが、それだ。
『そんな彼らに、『喰われ』ないようにするには、どうしたら良いんでしょうか。
……打ち勝つのは難しくても、勝利を渡さないようにする、方法。』
『負けないようにする為に出来ること。そいつはオニキスに訊くまでもないぜ、巳羽』
オニキスへの問いかけに返したのは、少女の兄だった。
この世界での自分たちの異能強化――これは気付いていた。でなければバス停の標識なんて重たいものを、自分がいとも簡単にふるえるわけはないのだ。そして争い、敵意への慣れがアンジニティに比べてないこと。観察眼が必要なこと――
立て続けに言われた言葉に、目を見張りなるほどと思うより先に、覚えたのは違和感だった。
あまりにも判断力が〝冷静すぎる"。
自分や巳羽と同じ立場であるにもかかわらず、その姿は年相応の落ち着きや判断力ではないような気がした。
が、今はそこは考えるべきではないと、オニキスの言葉ですぐさま隅へ追いやられる。
『――それだけじゃ、まだ足りねえな』
なぜ彼らがそこまで『慣れた』か。
『――アンジニティは己を『定義』している』
『絶対的な窮地、不可避の絶望、それらに屈さないだけの自我。信念、誇り、義務、なんだっていい。
上等も下等も高貴も粗野も関係ねえ。奴等はただ己にそう課してきた、"かくあるべし"と』
そう問いかけていくオニキスの言葉は答えを求めているわけではない間をもって。
最初あったときに「ザクロ先生」を真似て言った時にはあれは意図的であったのであろう。
今果たして意識的か無意識かはわからないけれど、彼の言葉はとても聞きやすい。本当に賢く鋭いと言ってしまえばそれまでだけれど、それは本当によくできた教師や人が、誰かに物事を教えたり問いかけたりするときにとても――似ていると、感じた。
『――10時間だ。開幕から10時間が経過するまでに己を定義しろ。それが俺からの最初の要求だ」
命が尽きかけたその時にまで戦う意思を持っていられるのかと、彼は言った。
つまりその刻限までに彼の言う『定義』なくしてこの先はない。
あくまでオニキスは『協力をしてくれている』のだから。確かにお荷物をもって歩く必要はどこにもないだろう。けれど、それがすぐに自分には浮かぶわけもなく言葉は出てこない。
「『かくあるべし』。難しい、ことねえ」
言い聞かせるようにつぶやく言葉。そして少女も、老婆同様すぐには答えは出てこないようだった。が。
『この争いが避けられないのであれば。実戦の経験は、欲しいです。
でも、正直今は、アンジニティには出会いたくない……』
出てきた言葉に思わず目を見張った。その言葉にではどうするかと問いかけるオニキス。
その様子をはらはらと見守っていたが、自分が思うよりも少女はよほど、しっかりとしていた。
『こに来ているイバラシティの人達に協力してもらって、戦ってみるのはどうかな、と……
互いの経験になりますし、勝っても負けても、アンジニティが有利になる事はないから……』
『……へえ、成る程。『練習試合』か。上手いこと考えたな。
そいつは案外いいセン行ってるかもしれないぜ』
おれたちならきっとやれる。にへら、と笑いながら言って見せるどこかカラ元気を感じる伐都だが、巳羽の提案に対するそれをすかさず助ける伐都に目を細める。
最初にかすかにふるえていた少女はいったいどこへ、と。
そして少年を見て思う。先の冷静さはどこへ。けれどこちらを気遣う言葉と――少女の提案に対しての、回転の速さ。この、この兄妹は。
自然と、目を細めてしまう。
若さゆえの柔軟さなのか、彼らの真っすぐさなのかはわからないけれど。歳を重ねた老婆にとって、思い悩みながらも様々な考えを、提案を、そして道を見つけ出せることが、とてもまぶしくみえた。少なくともそれは、もう己にはないものだ。
ええ、ええ、と賛成の言葉を発しながら、確かにこの霞んだ目を、ずっと開いておくことが自分に出来る一つなのかもしれないと、思った。
(掌の中、錆びついた鉄がどれほど軽く、どれほど重く感じても)



 |
バツ 「立ち止まってる時間はねえ。どんどん行こうぜ!」 |





chimeRa
|
 |
熾す魂火
|



ザクロ(307) は 何かの殻 を入手!
巳羽(507) は ぬめぬめ を入手!
バツ(508) は ぬめぬめ を入手!
いちこ(1106) は アルミ缶 を入手!
巳羽(507) は 甲殻 を入手!
いちこ(1106) は 羽 を入手!
ザクロ(307) は 甲殻 を入手!
バツ(508) は ぬめぬめ を入手!
いちこ(1106) は ねばねば を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
バツ(508) のもとに オオザリガニ が漢字2文字を掲げて近づいてきます。
バツ(508) のもとに オオホタル が軽快なステップで近づいてきます。



幻術LV を 3 DOWN。(LV18⇒15、+3CP、-3FP)
武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
カシマ(562) により ItemNo.9 毛 から装飾『いちごのストラップ』を作製してもらいました!
⇒ いちごのストラップ/装飾:強さ36/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
 |
カシマ 「ふふ、可愛らしくできましたかね。」 |
 |
らび(363) により ItemNo.5 バス停の標識 に ItemNo.8 韮 を付加してもらいました!
⇒ バス停の標識/武器:強さ30/[効果1]回復10 [効果2]活力10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
らび 「こーんなかんじ、ですかねー?」 |
ザクロ(307) の持つ ItemNo.11 美味しい草 から料理『草団子』をつくりました!
巳羽(507) の持つ ItemNo.9 美味しい果実 から料理『あったかフルーツスープ』をつくりました!
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『桜餅』をつくりました!
⇒ 桜餅/料理:強さ36/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10
 |
いちこ 「この食材は、いったいなんなんだろうねえ。なんにでもなるねえ?」 |
かすみん(1273) とカードを交換しました!
おためしカード (ウィンドリング)

ディム を研究しました!(深度0⇒1)
ディム を研究しました!(深度1⇒2)
アキュラシィ を研究しました!(深度0⇒1)
エキサイト を習得!
アイスバインド を習得!
リフレクション を習得!



チナミ区 K-10(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 K-11(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 K-12(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 K-13(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――







サイコーbloody
|
 |
熾す魂火
|


ENo.1106
都筑乙 壱子



もう本来定年は迎えている、定年どころじゃない気はする、
ハレ高の学食に居るおばあちゃん。
いちごさんではなくいちこさん。
学食で着てるエプロンや割烹着には生徒からもらった苺のワッペンがちょこんとついている。
もう腰は曲がり始めているけれどまだまだ現役を自称する。まあ学食の昼捌けるなら十分現役。
若い子達には食べなさい食べなさいと言うし教師にも食べれるうちに食べとけととりあえずお腹いっぱい食べたら何とかなる精神。
基本的におばあちゃんというおばあちゃん。さて。
※食堂の最年長おばぁちゃんなので既知設定歓迎です。
既知歓迎の人にはこっちも知ってる体で行くことがあります。
注文はいるとタイミングが合えば勝手にレスすることがあります。
ハレ高の学食に居るおばあちゃん。
いちごさんではなくいちこさん。
学食で着てるエプロンや割烹着には生徒からもらった苺のワッペンがちょこんとついている。
もう腰は曲がり始めているけれどまだまだ現役を自称する。まあ学食の昼捌けるなら十分現役。
若い子達には食べなさい食べなさいと言うし教師にも食べれるうちに食べとけととりあえずお腹いっぱい食べたら何とかなる精神。
基本的におばあちゃんというおばあちゃん。さて。
※食堂の最年長おばぁちゃんなので既知設定歓迎です。
既知歓迎の人にはこっちも知ってる体で行くことがあります。
注文はいるとタイミングが合えば勝手にレスすることがあります。
15 / 30
132 PS
チナミ区
K-14
K-14





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 少女のマフラー | 防具 | 31 | 治癒10 | - | - | |
| 2 | アルミ缶 | 素材 | 15 | [武器]攻撃15(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]防御10(LV15) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | お守りの石 | 防具 | 25 | 防御10 | - | - | |
| 5 | バス停の標識 | 武器 | 30 | 回復10 | 活力10 | - | 【射程1】 |
| 6 | 食堂のまかない | 料理 | 33 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 7 | 桜餅 | 料理 | 36 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 8 | |||||||
| 9 | いちごのストラップ | 装飾 | 36 | 敏捷10 | - | - | |
| 10 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]敏捷10(LV15)[防具]加速10(LV15)[装飾]貫撃10(LV15) | |||
| 11 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 幻術 | 15 | 夢幻/精神/光 |
| 料理 | 26 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練2 | エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| 練1 | アクアヒール | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| シャイン | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 | |
| アイスバインド | 5 | 0 | 80 | 敵:水撃&凍結 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 60 | 自:反射 | |
| ブレス | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増+祝福 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 光特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:光属性スキルのHP増効果に光特性が影響 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ヒールポーション | [ 1 ]アキュラシィ | [ 2 ]ディム |
| [ 3 ]バトルソング |

PL / のん