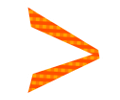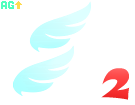<< 2:00>> 4:00




「ただいまー。」
辺りがすっかり暗くなる頃、扉を押し開けて帰宅を告げる。
「お帰り、遅かったわね。」
夕飯の支度をしていたのだろう、キッチンから顔を出した母が笑顔で出迎えてくれた。
パタパタとスリッパが軽い音を立てる。
低い位置で結わえられた自分と同じ黒い髪が、歩くのに合わせて機嫌よく揺れた。
「ごめん、連絡忘れてた。」
「いいのよ、最近楽しそうだからママも嬉しいし。
なんだか小さい頃の智之に戻ったみたい…。」
…笑顔のワケはそれだったのだろうか。小さい頃の自分。
思い当たるフシが無いわけでもないが、はぐらかすように曖昧に笑みを作る。
「そうかな…。」
「覚えてない?一日中遊んで帰ってきてたじゃない。ほら、転校したあの子と…。」
―転校したあの子―
忘れかけていた記憶が、ノイズを伴ってゆっくりと浮かび上がる。
深い、深い湖の底に沈んでいたそれが、水面に顔を出す。
…咄嗟にきつく目をつむり、頭を振った。
「あー…、カバン、置いてくるよ…。」
『あの子』の名前を思い出そうとする母の話を遮って、逃げ込むように自室へ滑り込んだ。

ゆっくりと目を開く。そろそろ見慣れてきただろうか、この薄気味悪いハザマの世界も。
ここで得た情報、知識。それらを反芻して飲み込んで、ようやく出てきたのは、
この侵略はなんてタチが悪いのだろうか。という感想だった。
きっと、誰が勝っても誰かが苦しむ。現実で知り合った人と戦う事になるかもしれない。
そしてそれは、自分がどう足掻こうともどうしようもない、どうにもならない。
どうすればいいのか。その結論は最後まで出なかった。
崩れた瓦礫の上に腰かけたまま、表情のない空を見上げる。
深として、生気を感じさせない街。同じように迷い込んだ人たちと距離をとってしまえば、
動くものは何もない。
―転校したあの子―
ハザマに来る直前の母との話題を思い出す。
あまりに静かだと、人は余計な事を考えるらしい。
幼い頃の記憶、ずっと、見ないフリをしていた思い出。

小さい頃ずっと遊んでいた友達、一番仲良くしていた友達。
なんてことはない。別れが辛くて、自分にだけ言い出せずに手紙だけ残して
いなくなってしまった。
転校なんてよくあるイベントだ。
それでも、徐々に人と関わるのが億劫になって、中学になる頃には自然と仲の良い友達を作らないようにしていた。
彼女の行動を恨んだわけじゃない。ただ幼心に受け止め切れず、感傷的になっていただけ。
親が教育熱心だったのは幸いだったかもしれない。
習い事で時間が合わないから、家が遠いから。
人と関わらない理由はいくらでも作れるし、一人遊びも得意だった。

目を瞑って、頭を振る。そうしてもう一度、目を開く。
動くもののない、生気のない世界。
何も変わらない、凪いだ水面のような世界。
高校へ入った後も大して変わらなかった。挨拶を交わして、ちょっとした雑談をする程度の関係。
学校に顔を出さないクラスメイトになんて、誰も興味を持たない。
…誰も。

穏やかな音が、凪いだ水面に波紋を作る。
…誰もいないはずだった。
ただ他人と少し壁を作って、少し距離を取ればいいだけだった。
みんなが楽しそうに集まっているのだって羨ましくない。
独りだって寂しくない。習い事だって勉強だってそつなくこなせる
……。

吐き出すように言い捨てて立ち上がった。
黒い髪が、風に攫われて揺れる。
波立つ水面のように。
「かっこ悪い。いつまで傷ついたフリしてるんだ。」
ピシャリと両手で頬を挟む。
そうして、ゆっくりと目を瞑って、大きく息を吸う。
水面に浮かび上がって、息継ぎをするように、深く深く。
久しぶりに学校に顔を出して、鍋の中を無茶苦茶にしながら楽しんだ闇鍋大会。
ルールもわからず、それでも笑いながら遊んだ麻雀。
先生まで巻き込んで、靴の中がぐずぐずになるまで戦った雪合戦。
全部、一歩踏み出したから手に入れた想い出で。
その一歩を踏み出させてくれたのは。
……。

きっと、誰が勝っても誰かが苦しむ。現実で知り合った人と戦う事になるかもしれない。
そしてそれは、自分がどう足掻こうともどうしようもない、どうにもならない。
だったらもう、難しく考えるのは止めだ。
イバラシティのために、自軍の勝利のために。
そんな事言われてもピンとこない。
ただ、自分の手の届く範囲の者を、大事なものを守る。
それぐらいなら、自分にもできる気がするんだ。
「大丈夫、”守るのは十八番”なんだ。」
自分に言い聞かせるように呟く。
風上へ足を向ける。黒い髪が流されて、開けた視界の先には金色に揺れる湖面が見えた。
いつか別れる時はまた来るけれど、きっと、以前とは違う別れ方ができるはず。
それまでは、どうかこの日常を守れますように。




ENo.180 雀部稲生 とのやりとり

ENo.723 小和泉 来夢 とのやりとり

以下の相手に送信しました














自然LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
具現LV を 3 UP!(LV8⇒11、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
雀部稲生(180) により ItemNo.9 ねばねば から射程1の武器『黒手袋』を作製してもらいました!
⇒ 黒手袋/武器:強さ36/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
雀部稲生(180) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『お守り』を作製しました!
メリーナ(221) とカードを交換しました!
水霊の癒し (アクアヒール)

サモン:ウルフ を研究しました!(深度1⇒2)
サモン:ウルフ を研究しました!(深度2⇒3)
イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を習得!
クリエイト:ハンマー を習得!
スパークス を習得!



チナミ区 G-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――
















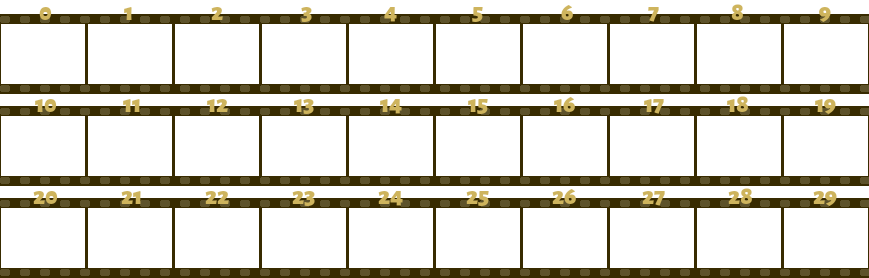





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「ただいまー。」
辺りがすっかり暗くなる頃、扉を押し開けて帰宅を告げる。
「お帰り、遅かったわね。」
夕飯の支度をしていたのだろう、キッチンから顔を出した母が笑顔で出迎えてくれた。
パタパタとスリッパが軽い音を立てる。
低い位置で結わえられた自分と同じ黒い髪が、歩くのに合わせて機嫌よく揺れた。
「ごめん、連絡忘れてた。」
「いいのよ、最近楽しそうだからママも嬉しいし。
なんだか小さい頃の智之に戻ったみたい…。」
…笑顔のワケはそれだったのだろうか。小さい頃の自分。
思い当たるフシが無いわけでもないが、はぐらかすように曖昧に笑みを作る。
「そうかな…。」
「覚えてない?一日中遊んで帰ってきてたじゃない。ほら、転校したあの子と…。」
―転校したあの子―
忘れかけていた記憶が、ノイズを伴ってゆっくりと浮かび上がる。
深い、深い湖の底に沈んでいたそれが、水面に顔を出す。
…咄嗟にきつく目をつむり、頭を振った。
「あー…、カバン、置いてくるよ…。」
『あの子』の名前を思い出そうとする母の話を遮って、逃げ込むように自室へ滑り込んだ。

ゆっくりと目を開く。そろそろ見慣れてきただろうか、この薄気味悪いハザマの世界も。
ここで得た情報、知識。それらを反芻して飲み込んで、ようやく出てきたのは、
この侵略はなんてタチが悪いのだろうか。という感想だった。
きっと、誰が勝っても誰かが苦しむ。現実で知り合った人と戦う事になるかもしれない。
そしてそれは、自分がどう足掻こうともどうしようもない、どうにもならない。
どうすればいいのか。その結論は最後まで出なかった。
崩れた瓦礫の上に腰かけたまま、表情のない空を見上げる。
深として、生気を感じさせない街。同じように迷い込んだ人たちと距離をとってしまえば、
動くものは何もない。
―転校したあの子―
ハザマに来る直前の母との話題を思い出す。
あまりに静かだと、人は余計な事を考えるらしい。
幼い頃の記憶、ずっと、見ないフリをしていた思い出。

小さい頃ずっと遊んでいた友達、一番仲良くしていた友達。
なんてことはない。別れが辛くて、自分にだけ言い出せずに手紙だけ残して
いなくなってしまった。
転校なんてよくあるイベントだ。
それでも、徐々に人と関わるのが億劫になって、中学になる頃には自然と仲の良い友達を作らないようにしていた。
彼女の行動を恨んだわけじゃない。ただ幼心に受け止め切れず、感傷的になっていただけ。
親が教育熱心だったのは幸いだったかもしれない。
習い事で時間が合わないから、家が遠いから。
人と関わらない理由はいくらでも作れるし、一人遊びも得意だった。

目を瞑って、頭を振る。そうしてもう一度、目を開く。
動くもののない、生気のない世界。
何も変わらない、凪いだ水面のような世界。
高校へ入った後も大して変わらなかった。挨拶を交わして、ちょっとした雑談をする程度の関係。
学校に顔を出さないクラスメイトになんて、誰も興味を持たない。
…誰も。

穏やかな音が、凪いだ水面に波紋を作る。
…誰もいないはずだった。
ただ他人と少し壁を作って、少し距離を取ればいいだけだった。
みんなが楽しそうに集まっているのだって羨ましくない。
独りだって寂しくない。習い事だって勉強だってそつなくこなせる
……。

吐き出すように言い捨てて立ち上がった。
黒い髪が、風に攫われて揺れる。
波立つ水面のように。
「かっこ悪い。いつまで傷ついたフリしてるんだ。」
ピシャリと両手で頬を挟む。
そうして、ゆっくりと目を瞑って、大きく息を吸う。
水面に浮かび上がって、息継ぎをするように、深く深く。
久しぶりに学校に顔を出して、鍋の中を無茶苦茶にしながら楽しんだ闇鍋大会。
ルールもわからず、それでも笑いながら遊んだ麻雀。
先生まで巻き込んで、靴の中がぐずぐずになるまで戦った雪合戦。
全部、一歩踏み出したから手に入れた想い出で。
その一歩を踏み出させてくれたのは。
……。

きっと、誰が勝っても誰かが苦しむ。現実で知り合った人と戦う事になるかもしれない。
そしてそれは、自分がどう足掻こうともどうしようもない、どうにもならない。
だったらもう、難しく考えるのは止めだ。
イバラシティのために、自軍の勝利のために。
そんな事言われてもピンとこない。
ただ、自分の手の届く範囲の者を、大事なものを守る。
それぐらいなら、自分にもできる気がするんだ。
「大丈夫、”守るのは十八番”なんだ。」
自分に言い聞かせるように呟く。
風上へ足を向ける。黒い髪が流されて、開けた視界の先には金色に揺れる湖面が見えた。
いつか別れる時はまた来るけれど、きっと、以前とは違う別れ方ができるはず。
それまでは、どうかこの日常を守れますように。




ENo.180 雀部稲生 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.723 小和泉 来夢 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| 雀部稲生 「やっぱ何回来ても変な場所やな。お前がしおらしなんのも分かるわ。」 |
| 雀部稲生 「…三回目でもまだ不安か?手えぐらいやったら繋いだんで???」 |
 |
我孫子 「はぁー、何回目だ、ここ…。いる時間は短いにしても神経すり減るよな…。」 |
 |
我孫子 「…………な、なぁ、しりとりしないか…? いや、別に黙ってると怖いとかじゃなくてほら…ヒマ…だし…?」 |









自然LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
具現LV を 3 UP!(LV8⇒11、-3CP)
防具LV を 3 UP!(LV23⇒26、-3CP)
雀部稲生(180) により ItemNo.9 ねばねば から射程1の武器『黒手袋』を作製してもらいました!
⇒ 黒手袋/武器:強さ36/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
 |
雀部稲生 「めっちゃねばねばする…。 こんなんでほんまに手袋なんか作れんの…やるけどやな…」 |
 |
雀部稲生 「…うわ待って。取れへんくなった。えっ待って!我孫子!助けて!!!」 |
雀部稲生(180) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『お守り』を作製しました!
メリーナ(221) とカードを交換しました!
水霊の癒し (アクアヒール)

サモン:ウルフ を研究しました!(深度1⇒2)
サモン:ウルフ を研究しました!(深度2⇒3)
イバラ を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を習得!
クリエイト:ハンマー を習得!
スパークス を習得!



チナミ区 G-12(道路)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-11(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 I-12(道路)に移動!(体調16⇒15)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――







ENo.1022
我孫子 智之



名前:あびこ としゆき
男 16歳 171cm 細身
熾盛天晴学園2年3組所属(やや不登校気味)
秘密結社「フリーパーソン」の最高責任者であり、唯一の結社員。だったが、最近人が増えたらしい。堕落した政府を憂い、選ばれた者達による新しい統治をするべきであると唱える選民思想の持ち主。
幼少期のIQテストで120を出した事を未だに誇っており、自分は選ばれた存在だと思っている。
親の所有していたビルの空き部屋を利用し、日々秘密結社の活動を続けている。主な活動内容は過激なマニフェストを考えること、結社のかっこいいロゴを考えること、かっこいい名刺を作る事。
(ただの中二病かまってちゃんくんです。)
異能:不可侵領域(バリア)。幼少期からサイズが成長していないので、バリア以外の場所を殴られると痛い。
丸めて棒状にすると鈍器にもなる。
■よくいるかもしれないプレイス
・熾盛天晴学園:SpotNo.122[カスミ区 O-10]
・第2アビコビル:SpotNo.369[カスミ区 R-8]
=================
■サブキャラ(アイコン11-18)
薬師寺ナツ子 ♀ 外見18歳程度 145cm
まじない雑貨屋まほろば堂(http://lisge.com/ib/talk.php?s=540)
の店主。想いの通ったモノにまじないをかける異能を使い、特別な力を持った雑貨を作ることができるアーティファクト使い。
しかし雑貨屋は道楽でやっているようで商売っ気が微塵もない。
放浪癖も相まって店は空けがちなこともしばしば。
自分の興味が赴くものに思考が占有されがちといえる。
ニーアップイラスト(https://blog-imgs-105.fc2.com/u/n/k/unkomxxx/20190105000715841.png)
男 16歳 171cm 細身
熾盛天晴学園2年3組所属(やや不登校気味)
秘密結社「フリーパーソン」の最高責任者であり、唯一の結社員。だったが、最近人が増えたらしい。堕落した政府を憂い、選ばれた者達による新しい統治をするべきであると唱える選民思想の持ち主。
幼少期のIQテストで120を出した事を未だに誇っており、自分は選ばれた存在だと思っている。
親の所有していたビルの空き部屋を利用し、日々秘密結社の活動を続けている。主な活動内容は過激なマニフェストを考えること、結社のかっこいいロゴを考えること、かっこいい名刺を作る事。
(ただの中二病かまってちゃんくんです。)
異能:不可侵領域(バリア)。幼少期からサイズが成長していないので、バリア以外の場所を殴られると痛い。
丸めて棒状にすると鈍器にもなる。
■よくいるかもしれないプレイス
・熾盛天晴学園:SpotNo.122[カスミ区 O-10]
・第2アビコビル:SpotNo.369[カスミ区 R-8]
=================
■サブキャラ(アイコン11-18)
薬師寺ナツ子 ♀ 外見18歳程度 145cm
まじない雑貨屋まほろば堂(http://lisge.com/ib/talk.php?s=540)
の店主。想いの通ったモノにまじないをかける異能を使い、特別な力を持った雑貨を作ることができるアーティファクト使い。
しかし雑貨屋は道楽でやっているようで商売っ気が微塵もない。
放浪癖も相まって店は空けがちなこともしばしば。
自分の興味が赴くものに思考が占有されがちといえる。
ニーアップイラスト(https://blog-imgs-105.fc2.com/u/n/k/unkomxxx/20190105000715841.png)
15 / 30
85 PS
チナミ区
I-12
I-12




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 黒いロングコート | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | 茹でたうずらをチョコで覆った何か | 料理 | 13 | - | - | - | |
| 8 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 9 | 黒手袋 | 武器 | 36 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 10 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) | |||
| 11 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 5 | 破壊/詠唱/火 |
| 具現 | 11 | 創造/召喚 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 防具 | 26 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 6 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| 障壁:乱れ撃ち (ストーンブラスト) | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 | |
| タライ (クリエイト:タライ) | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| 守護障壁 (プロテクション) | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| クリエイト:ハンマー | 5 | 0 | 100 | 敵:攻撃(対象の領域値[地]が高いほど威力増) | |
| スパークス | 5 | 0 | 60 | 敵全:精確火撃 | |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 100 | 敵:痛撃&(猛毒or麻痺) | |
| アイヴィー | 5 | 0 | 60 | 敵列:束縛 | |
| 不可侵領域 (クリエイト:バリケード) | 5 | 0 | 40 | 味傷:次受ダメ減+守護 | |
| 敵機選定 (テリトリー) | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |
| 守護者創造 (サモン:ガーゴイル) | 6 | 0 | 400 | 自:ガーゴイル召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【常時】異能『具現』のLVに応じて、自身の召喚するNPCが強化 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
グランドランサー (ブラスト) |
0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
|
守護 (エスコート) |
0 | 80 | 自:次受ダメ減+味列:護衛 | |
|
水霊の癒し (アクアヒール) |
0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]サモン:ウルフ | [ 1 ]イバラ | [ 3 ]サモン:ナレハテ |
| [ 1 ]ポーションラッシュ | [ 1 ]ヒールミスト |

PL / しおから