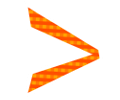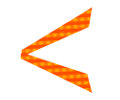<< 11:00~12:00




これはイバラシティではない、どこか別の世界の話だ。
ある大学で、学生の失踪が相次いだ。
心神喪失状態で発見された者。不審死を遂げた者。未だ行方不明のままの者。
共通点は皆同じサークル、オカルト研究会に所属していたということのみ。
そして最終的にその部長が姿を消した後、ぴたりと行方不明者は出なくなったという事実だけが、不気味な手触りともにそこにある。
***
「……あ、え……? なに……なんで、」
喘ぐような呟きが、まるで他人のもののようだ。
切りつけた姿勢のまま手首から先が消失した右手を、鼠森は呆然と見つめていた。
「あんたのそういう切り替えの早いところ、割と好きよ」
降ってきた声に視線だけを上げる。
黒い目を細めて、大曲晴人が嗤っている。
「ちょっと餌をちらつかせたらすぐ食いついちゃって……ホント、かわいいんだから」
出血はない。痛みもない。ただ、右の手首から先は何度確かめてもすっぱりと斬られたように、或いは喰われたようになくなっている。
震えながら大曲を見上げる。その足元、荒れた地面に落ちる黒く長い影の中に、何かがいる。
「な、なんですか、それぇ……」
男の影から、ぬるりと滑るように"そいつ"は現れた。

――猫だ。
大型犬程の大きさの、空間に空いた穴のように真っ黒な猫がじっと鼠森を見つめていた。いや、ただただ黒いその顔に目らしいものは見当たらない。目の代わりに、顔の真ん中に口のような穴が空いている。それなのに、見られている、という嫌な感覚だけがある。
「先輩、戦えないって言ってたじゃないですか……」
「そう簡単に手の内明かすわけないでしょ」
大曲は肩を竦め、薄笑いを浮かべて鼠森を見下ろした。
ぞく、と悪寒が背筋を駆け抜ける。
「ところで、『ドライバーさん』の話。本当なのかしらね?」
「は……?」
「知ってると思うけど……あたし、試してみないと気が済まないのよね」
それは、オカルト研究会で何度となく聞いた言葉だ。
新入部員を唆していわくつきの心霊スポットに踏み込ませたり、所謂"ヤバい"怪談の入った本を何食わぬ顔で薦めたり。そういった"実験"を試す度に、彼はそう言って薄く笑った。
別にそれは大曲晴人に限った話ではなく、部長を始めとしたサークルの中心メンバーはそんな連中ばかりだった。
そして鼠森も、それを止めるような人間ではなかった。寧ろ、起こった結果を眺めて楽しむ側だった。いつか自分を仲間はずれにした奴等も、同じような目に遭えばいい。そう思っていた。
――のんは大丈夫。
――のんには"耳"があるから、先輩達に気に入られてる。
ここなら、自分には価値がある。だから、仲間外れにもならないし、捨て駒にもならない。
そう思って、いたのに。
「影響度を稼げなかったら姿が変わるって、本当なのかしら。どんな風に変わるのか、あたしすっごく興味があるわ」
「……なに、待って……ねえ、嘘でしょ先輩、」
「手ぶらだと思ったら刃物が出てくるとか、油断も隙もないんだから。危ないからそっちの腕も寄越しなさい。うっかり死なれでもしたら台無しだから、脚は残しておくわね。がんばって走ってちょうだい」
「や、……やだ、やだやだやだ、おねがい、のん役に立つから、何でもするから……ッ」
「あら。イバラシティはもういらないの? 『同郷の先輩』を殺してでも手に入れたかったのに?」
冷や汗が止まらないまま、ただがくがくと頷く。
いらないわけない、でも化け物にもなりたくない。
とにかくこの場を凌げさえすれば、後でいくらでも、機会が、
「そうやって簡単に手のひら返してると、ろくな目に遭わないわよ。鼠森」
そんな考えを見透かしたように、大曲は昏い目を細めた。足元の猫がゆっくりと尾をくねらせて足音もなく一歩踏み出す、その動きに心臓が跳ねる。
思わず後退りしようとして、何かに蹴躓いて倒れた。無意識に体を支えようと伸ばした右手首の断面が、石だらけの地面をざりざりと滑る。肉が削れる痛みに、声にもならない悲鳴が洩れた。
「わかってやってるならいいけど。あんたはそうじゃないでしょ」
猫が近付いてくる。
「『自分だけは大丈夫』って、そう思ってるんでしょう?
何かあっても自分だけは助かる、そう思いたいわよね。でも、」
猫が近付いてくる。
「――結局『誰も助けてくれなかった』でしょ?」
大きく口を開けた猫が、目の前に立っている。
(――あれ、)
違和感。
猫の後ろに立つ男を見る。大曲晴人。
鼠森かのんがアンジニティに落ちた時、既に大曲はその世界にいなかった。
オカルト研究会のメンバーが一人また一人と姿を消した"事件"。
殺しても死ななそうだと言われていた大曲晴人があっさり消えて、鼠森を含めた下級生達は恐慌状態に陥った。
所謂"本物"に手を出してしまった、誰もがそう思った。それでも手を引こうとしなかった部長に逆らえずついてゆく者も、逃げ出す者もいたが。最終的にほぼ全員が多かれ少なかれあおりを食った。
鼠森かのんも例外ではなく、為すすべもなく怪異に呑まれて、気がつけばアンジニティにいた。
その寸前、必死で伸ばした手が振り払われたことも。
誰も助けてくれなかったことも。
最後に見たメンバー達の顔に浮かんでいた恐怖と焦燥と、自分は免れたのだという安堵も。
全部全部、ちゃんと覚えている。
だから。
だから、おかしいのだ。
先に消えた大曲晴人が、鼠森かのんが見捨てられたことを知っているのは。
「……のんより先にいなくなったのに、なんでそんなこと、知ってるんですか」
左腕だけで這うように後退しながら訊ねる。
時間を稼ぐ意図もあったが、それ以上に強烈な違和感に耐えられなかった。何かが、おかしい。
「……あら」
大曲は指先を細い顎に当てて、首を傾げた。サークル室で何度となく見た仕草。
・・・・・・・・・
「そういえば、あの時はそうだったかしらね」
うっかりしてたわ。何でもないようにそう呟くのが聞こえた次の瞬間、黒い猫と赤い口が衝撃とともに鼠森の視界を覆い尽くした。
***
両腕を失くした女が瓦礫だらけの地面に倒れている。
大曲はそのすぐ近く、大きめの瓦礫に足を組んで腰掛けて、『Cross+Rose』を操作していた。
「さてと、今の影響度は…………ま、サボってたんだし当然かしら」
意識を失っている様子の鼠森を一瞥する。
彼女を『倒した』ことで得られた影響度は、予想はしていたがそう多くはなかった。
「暫くここで遊んでてもいいけど、多分あんまり美味しくないのよね。
持ってる相手からの方が多く奪える、っていうのがまあ定石でしょうし」
影響度の低さが姿形に及ぼす影響は気になるが、自分も道連れになっていては世話ないわけで。鼠森の様子は定期的に『Cross+Rose』で確認するとして、まずは自分の影響度を上げることが優先だ。
はあ、とひとつ息を吐いて立ち上がると、鼠森の顔を覗き込んでいた猫が寄ってきて、顔なき顔で大曲を見上げた。
「あの街は確かに、居心地はよかったわ。元の世界と割と近いし……異能っていうのも面白い。あたしのは尖りすぎててちょっと使いにくかったけど」
猫のつるりとした黒い表面を見ながら呟く。
これは命令に従うというだけで、意思の疎通ができるようなものではない。だから、これはただの独り言だ。傍目には、猫に話しかけている男に見えるのだろうけれど。
「でもやっぱり、あの世界はあたしが戻りたい場所じゃない」
勿論、イバラシティでの日々は悪くはなかったのだ。
社畜としてこき使われる立場ではあったものの、収入もそれなりにあったし、甘いものを食べたり、服や靴を見たり、好きなだけ買い物をしたり。
"素"を出せる場は少なかったけれど、長く住んでいればそんな友人の何人かだって作れただろう。
それでも、あの世界が欲しいとは思わない。
大曲は欲しいものによく似た別物で満足するほど欲の薄い男でもないし、何よりも。
アンジニティで試したいことも、知りたいことも。
まだまだ尽きる気配がない。

大曲晴人は自分のためにしか動かない。
したいように、やりたいように、ただそれだけで生きてきた。
知りたいことを知るために。欲しいものを手に入れるために。
使えるものは何でも使って、邪魔なものは踏み台にして、涼しい顔をして生きてきた。
地獄に落ちろ、と怨嗟の目を向けられたことも一度や二度ではない。言われなくともいつかそうなるだろうとは思っていたし、わかった上でのこの状況だ。
だから今回も、したいようにするだけ。
「……どうせ夢なら、なんて」
影の中に猫を飼う男はひとり、荒れ果てた道を歩き出す。
「あたしらしくもないわね」



ENo.71 りりこ とのやりとり

ENo.93 Eva とのやりとり

ENo.173 タウラシアス とのやりとり

ENo.520 チャコール とのやりとり

以下の相手に送信しました




特に何もしませんでした。











六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



エナジー棒(30 PS)を購入しました。
お肉(50 PS)を購入しました。
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV77⇒82、-5CP)
タウラシアス(173) により ItemNo.4 海棲馬の蹄 に ItemNo.12 ボロ布 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
タウラシアス(173) により ItemNo.5 幻想藻の鬣 に ItemNo.22 ぬめぬめ を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
よもちゃん(1308) により ItemNo.1 幻想藻の揺鬣 に ItemNo.3 駄物 を付加してもらいました!
⇒ 幻想藻の揺鬣/法衣:強さ108/[効果1]水纏20 [効果2]活力10 [効果3]幸運15
かすかちゃん(591) とカードを交換しました!
ドリフのアレ (クリエイト:タライ)
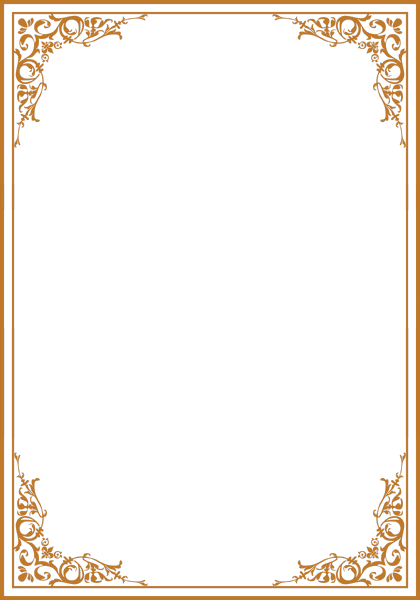
ディビジョン を研究しました!(深度0⇒1)
ディビジョン を研究しました!(深度1⇒2)
ディビジョン を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
マジックミサイル を習得!
アイスソーン を習得!
プチメテオカード を習得!
レイ を習得!
シャドウラーカー を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》 に転送されました!
タウラシアス(173) に移動を委ねました。
ヒノデ区 N-11(道路)に移動!(体調30⇒29)
ヒノデ区 N-12(森林)に移動!(体調29⇒28)
ヒノデ区 N-13(森林)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 O-13(山岳)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 P-13(山岳)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- タウラシアス(173) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- タウラシアス(173) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)





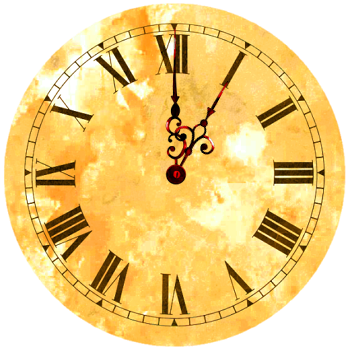
[845 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[409 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[460 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[150 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[311 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[202 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[149 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[68 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。


不機嫌そうな表情。
首を傾げる白南海。
ポケットから黒いハンカチを取り出す。
それを手で握り、すぐ手を開く。
すると、ハンカチが可愛い黒兎の人形に変わっている。
眼鏡をクイッと少し押し上げる。
咄嗟に腕を組み、身構える。
そう言ってチャットから抜けるエディアン。
チャットが閉じられる――










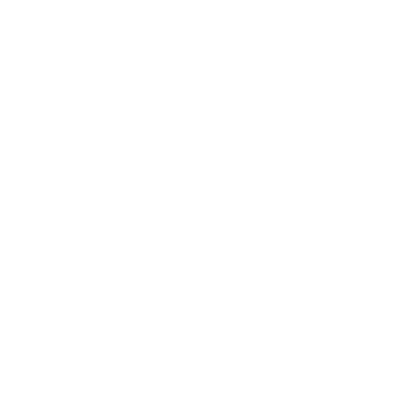
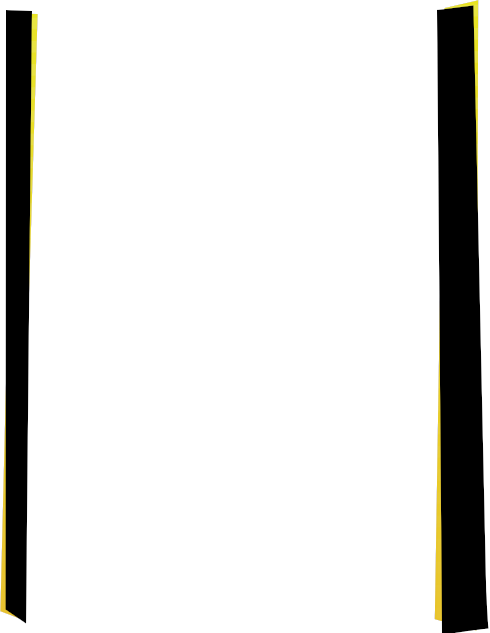
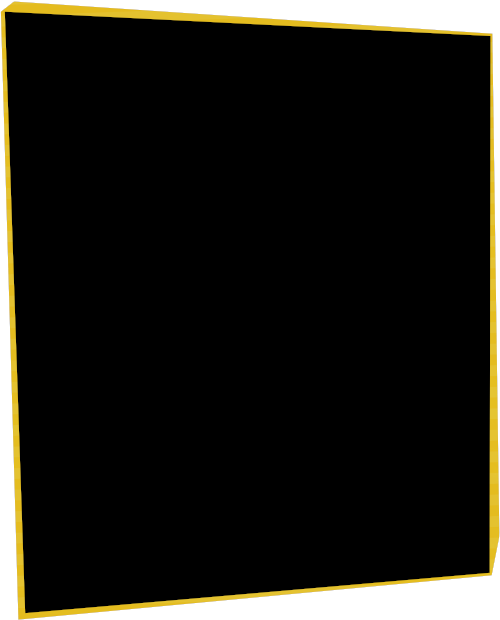





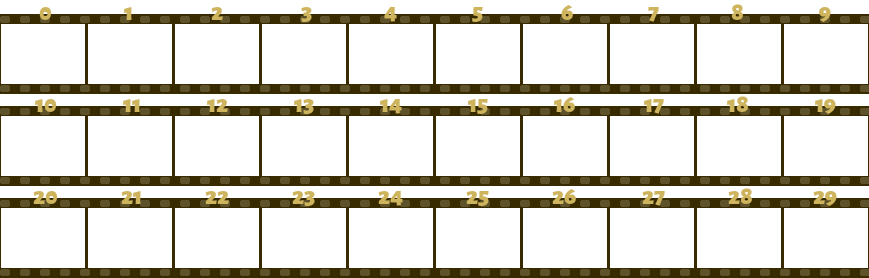







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



これはイバラシティではない、どこか別の世界の話だ。
ある大学で、学生の失踪が相次いだ。
心神喪失状態で発見された者。不審死を遂げた者。未だ行方不明のままの者。
共通点は皆同じサークル、オカルト研究会に所属していたということのみ。
そして最終的にその部長が姿を消した後、ぴたりと行方不明者は出なくなったという事実だけが、不気味な手触りともにそこにある。
***
「……あ、え……? なに……なんで、」
喘ぐような呟きが、まるで他人のもののようだ。
切りつけた姿勢のまま手首から先が消失した右手を、鼠森は呆然と見つめていた。
「あんたのそういう切り替えの早いところ、割と好きよ」
降ってきた声に視線だけを上げる。
黒い目を細めて、大曲晴人が嗤っている。
「ちょっと餌をちらつかせたらすぐ食いついちゃって……ホント、かわいいんだから」
出血はない。痛みもない。ただ、右の手首から先は何度確かめてもすっぱりと斬られたように、或いは喰われたようになくなっている。
震えながら大曲を見上げる。その足元、荒れた地面に落ちる黒く長い影の中に、何かがいる。
「な、なんですか、それぇ……」
男の影から、ぬるりと滑るように"そいつ"は現れた。

黒猫
――猫だ。
大型犬程の大きさの、空間に空いた穴のように真っ黒な猫がじっと鼠森を見つめていた。いや、ただただ黒いその顔に目らしいものは見当たらない。目の代わりに、顔の真ん中に口のような穴が空いている。それなのに、見られている、という嫌な感覚だけがある。
「先輩、戦えないって言ってたじゃないですか……」
「そう簡単に手の内明かすわけないでしょ」
大曲は肩を竦め、薄笑いを浮かべて鼠森を見下ろした。
ぞく、と悪寒が背筋を駆け抜ける。
「ところで、『ドライバーさん』の話。本当なのかしらね?」
「は……?」
「知ってると思うけど……あたし、試してみないと気が済まないのよね」
それは、オカルト研究会で何度となく聞いた言葉だ。
新入部員を唆していわくつきの心霊スポットに踏み込ませたり、所謂"ヤバい"怪談の入った本を何食わぬ顔で薦めたり。そういった"実験"を試す度に、彼はそう言って薄く笑った。
別にそれは大曲晴人に限った話ではなく、部長を始めとしたサークルの中心メンバーはそんな連中ばかりだった。
そして鼠森も、それを止めるような人間ではなかった。寧ろ、起こった結果を眺めて楽しむ側だった。いつか自分を仲間はずれにした奴等も、同じような目に遭えばいい。そう思っていた。
――のんは大丈夫。
――のんには"耳"があるから、先輩達に気に入られてる。
ここなら、自分には価値がある。だから、仲間外れにもならないし、捨て駒にもならない。
そう思って、いたのに。
「影響度を稼げなかったら姿が変わるって、本当なのかしら。どんな風に変わるのか、あたしすっごく興味があるわ」
「……なに、待って……ねえ、嘘でしょ先輩、」
「手ぶらだと思ったら刃物が出てくるとか、油断も隙もないんだから。危ないからそっちの腕も寄越しなさい。うっかり死なれでもしたら台無しだから、脚は残しておくわね。がんばって走ってちょうだい」
「や、……やだ、やだやだやだ、おねがい、のん役に立つから、何でもするから……ッ」
「あら。イバラシティはもういらないの? 『同郷の先輩』を殺してでも手に入れたかったのに?」
冷や汗が止まらないまま、ただがくがくと頷く。
いらないわけない、でも化け物にもなりたくない。
とにかくこの場を凌げさえすれば、後でいくらでも、機会が、
「そうやって簡単に手のひら返してると、ろくな目に遭わないわよ。鼠森」
そんな考えを見透かしたように、大曲は昏い目を細めた。足元の猫がゆっくりと尾をくねらせて足音もなく一歩踏み出す、その動きに心臓が跳ねる。
思わず後退りしようとして、何かに蹴躓いて倒れた。無意識に体を支えようと伸ばした右手首の断面が、石だらけの地面をざりざりと滑る。肉が削れる痛みに、声にもならない悲鳴が洩れた。
「わかってやってるならいいけど。あんたはそうじゃないでしょ」
猫が近付いてくる。
「『自分だけは大丈夫』って、そう思ってるんでしょう?
何かあっても自分だけは助かる、そう思いたいわよね。でも、」
猫が近付いてくる。
「――結局『誰も助けてくれなかった』でしょ?」
大きく口を開けた猫が、目の前に立っている。
(――あれ、)
違和感。
猫の後ろに立つ男を見る。大曲晴人。
鼠森かのんがアンジニティに落ちた時、既に大曲はその世界にいなかった。
オカルト研究会のメンバーが一人また一人と姿を消した"事件"。
殺しても死ななそうだと言われていた大曲晴人があっさり消えて、鼠森を含めた下級生達は恐慌状態に陥った。
所謂"本物"に手を出してしまった、誰もがそう思った。それでも手を引こうとしなかった部長に逆らえずついてゆく者も、逃げ出す者もいたが。最終的にほぼ全員が多かれ少なかれあおりを食った。
鼠森かのんも例外ではなく、為すすべもなく怪異に呑まれて、気がつけばアンジニティにいた。
その寸前、必死で伸ばした手が振り払われたことも。
誰も助けてくれなかったことも。
最後に見たメンバー達の顔に浮かんでいた恐怖と焦燥と、自分は免れたのだという安堵も。
全部全部、ちゃんと覚えている。
だから。
だから、おかしいのだ。
先に消えた大曲晴人が、鼠森かのんが見捨てられたことを知っているのは。
「……のんより先にいなくなったのに、なんでそんなこと、知ってるんですか」
左腕だけで這うように後退しながら訊ねる。
時間を稼ぐ意図もあったが、それ以上に強烈な違和感に耐えられなかった。何かが、おかしい。
「……あら」
大曲は指先を細い顎に当てて、首を傾げた。サークル室で何度となく見た仕草。
・・・・・・・・・
「そういえば、あの時はそうだったかしらね」
うっかりしてたわ。何でもないようにそう呟くのが聞こえた次の瞬間、黒い猫と赤い口が衝撃とともに鼠森の視界を覆い尽くした。
***
両腕を失くした女が瓦礫だらけの地面に倒れている。
大曲はそのすぐ近く、大きめの瓦礫に足を組んで腰掛けて、『Cross+Rose』を操作していた。
「さてと、今の影響度は…………ま、サボってたんだし当然かしら」
意識を失っている様子の鼠森を一瞥する。
彼女を『倒した』ことで得られた影響度は、予想はしていたがそう多くはなかった。
「暫くここで遊んでてもいいけど、多分あんまり美味しくないのよね。
持ってる相手からの方が多く奪える、っていうのがまあ定石でしょうし」
影響度の低さが姿形に及ぼす影響は気になるが、自分も道連れになっていては世話ないわけで。鼠森の様子は定期的に『Cross+Rose』で確認するとして、まずは自分の影響度を上げることが優先だ。
はあ、とひとつ息を吐いて立ち上がると、鼠森の顔を覗き込んでいた猫が寄ってきて、顔なき顔で大曲を見上げた。
「あの街は確かに、居心地はよかったわ。元の世界と割と近いし……異能っていうのも面白い。あたしのは尖りすぎててちょっと使いにくかったけど」
猫のつるりとした黒い表面を見ながら呟く。
これは命令に従うというだけで、意思の疎通ができるようなものではない。だから、これはただの独り言だ。傍目には、猫に話しかけている男に見えるのだろうけれど。
「でもやっぱり、あの世界はあたしが戻りたい場所じゃない」
勿論、イバラシティでの日々は悪くはなかったのだ。
社畜としてこき使われる立場ではあったものの、収入もそれなりにあったし、甘いものを食べたり、服や靴を見たり、好きなだけ買い物をしたり。
"素"を出せる場は少なかったけれど、長く住んでいればそんな友人の何人かだって作れただろう。
それでも、あの世界が欲しいとは思わない。
大曲は欲しいものによく似た別物で満足するほど欲の薄い男でもないし、何よりも。
アンジニティで試したいことも、知りたいことも。
まだまだ尽きる気配がない。

大曲 晴人
かつてある世界からアンジニティに落ちた男。
好きに生きているので人生が楽しい。
好きに生きているので人生が楽しい。
大曲晴人は自分のためにしか動かない。
したいように、やりたいように、ただそれだけで生きてきた。
知りたいことを知るために。欲しいものを手に入れるために。
使えるものは何でも使って、邪魔なものは踏み台にして、涼しい顔をして生きてきた。
地獄に落ちろ、と怨嗟の目を向けられたことも一度や二度ではない。言われなくともいつかそうなるだろうとは思っていたし、わかった上でのこの状況だ。
だから今回も、したいようにするだけ。
「……どうせ夢なら、なんて」
影の中に猫を飼う男はひとり、荒れ果てた道を歩き出す。
「あたしらしくもないわね」



ENo.71 りりこ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.93 Eva とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.173 タウラシアス とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.520 チャコール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



特に何もしませんでした。







ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
陸海空イバラ征服するなんて
|
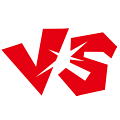 |
立ちはだかるもの
|



ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



エナジー棒(30 PS)を購入しました。
お肉(50 PS)を購入しました。
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 5 UP!(LV77⇒82、-5CP)
タウラシアス(173) により ItemNo.4 海棲馬の蹄 に ItemNo.12 ボロ布 を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
タウラシアス(173) により ItemNo.5 幻想藻の鬣 に ItemNo.22 ぬめぬめ を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
よもちゃん(1308) により ItemNo.1 幻想藻の揺鬣 に ItemNo.3 駄物 を付加してもらいました!
⇒ 幻想藻の揺鬣/法衣:強さ108/[効果1]水纏20 [効果2]活力10 [効果3]幸運15
| よもちゃん 「もってけー!」 |
かすかちゃん(591) とカードを交換しました!
ドリフのアレ (クリエイト:タライ)
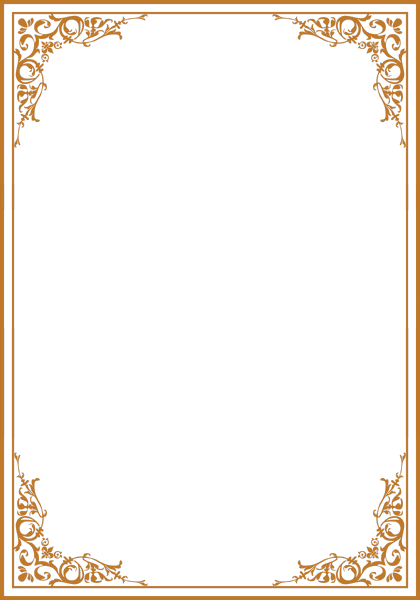
ディビジョン を研究しました!(深度0⇒1)
ディビジョン を研究しました!(深度1⇒2)
ディビジョン を研究しました!(深度2⇒3)
プリディクション を習得!
マジックミサイル を習得!
アイスソーン を習得!
プチメテオカード を習得!
レイ を習得!
シャドウラーカー を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「・・・はい到着ぅ。気をつけて行きな。」 |
タウラシアス(173) に移動を委ねました。
ヒノデ区 N-11(道路)に移動!(体調30⇒29)
ヒノデ区 N-12(森林)に移動!(体調29⇒28)
ヒノデ区 N-13(森林)に移動!(体調28⇒27)
ヒノデ区 O-13(山岳)に移動!(体調27⇒26)
ヒノデ区 P-13(山岳)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- タウラシアス(173) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- タウラシアス(173) の選択は ヒノデ区 M-11:チェックポイント《大通り》(ベースキャンプ外のため無効)





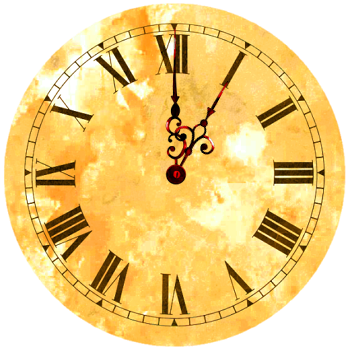
[845 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[409 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[460 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[150 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[311 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[202 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[149 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[68 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
白南海 「・・・ロストの情報をやたらと隠しやがるなワールドスワップ。 これも能力の範疇なのかねぇ・・・・・とんでもねぇことで。」 |
 |
白南海 「異能ならリスクも半端ねぇだろーが、なかにはトンデモ異能もありやがるしねぇ。」 |
不機嫌そうな表情。
 |
エディアン 「私、多くの世界を渡り歩いてますけど・・・ここまで大掛かりで影響大きくて滅茶苦茶なものは滅多に。」 |
 |
エディアン 「そういえば貴方はどんな異能をお持ちなんです?」 |
 |
白南海 「聞きたきゃまずてめぇからでしょ。」 |
 |
エディアン 「私の異能はビジーゴースト。一定の動作を繰り返し行わせる透明な自分のコピーを作る能力です。」 |
 |
白南海 「あっさり言うもんだ。そりゃなかなか便利そうじゃねぇか。」 |
 |
エディアン 「動作分の疲労は全部自分に来ますけどねー。便利ですよ、周回とか。」 |
 |
白南海 「集会・・・?」 |
 |
エディアン 「えぇ。」 |
首を傾げる白南海。
 |
エディアン 「――で、貴方は?」 |
 |
白南海 「ぁー・・・・・どうすっかね。」 |
ポケットから黒いハンカチを取り出す。
それを手で握り、すぐ手を開く。
すると、ハンカチが可愛い黒兎の人形に変わっている。
 |
エディアン 「わぁー!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・手品の異能ですかー!!合コンでモテモテですねー!!」 |
 |
白南海 「なに勝手に変な間つくって憐れんでんだおい。」 |
 |
白南海 「糸とかをだなー・・・・・好きにできる?まぁ簡単に言えばそんなだ。 結構使えんだよこれが、仕事でもな。」 |
 |
白南海 「それにこれだけじゃねぇしな、色々視えたり。」 |
眼鏡をクイッと少し押し上げる。
 |
エディアン 「え!何が視えるんです!?」 |
 |
白南海 「裸とか?」 |
 |
エディアン 「ぇ・・・・・」 |
咄嗟に腕を組み、身構える。
 |
白南海 「・・・嘘っすよ、秘密秘密。言っても何も得しねぇし。」 |
 |
エディアン 「ケチですねぇ。まぁ私も、イバラシティ生活の時の話ですけどねー。」 |
 |
白南海 「・・・・・は?」 |
 |
エディアン 「案外ひとを信じるんですねぇー、意外意外!」 |
そう言ってチャットから抜けるエディアン。
 |
白南海 「あぁ!?きったねぇだろそれ!クッソがッ!!おいいッ!!! ・・・アンジニティぶっ潰すッ!!!!」 |
チャットが閉じられる――









ENo.502
藻噛 叢馬
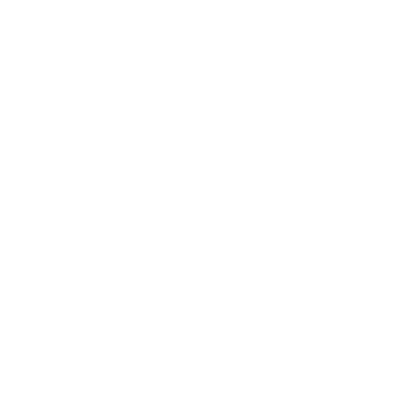
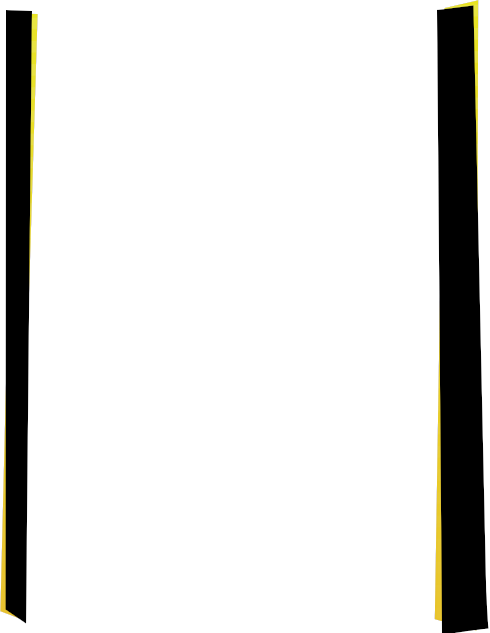
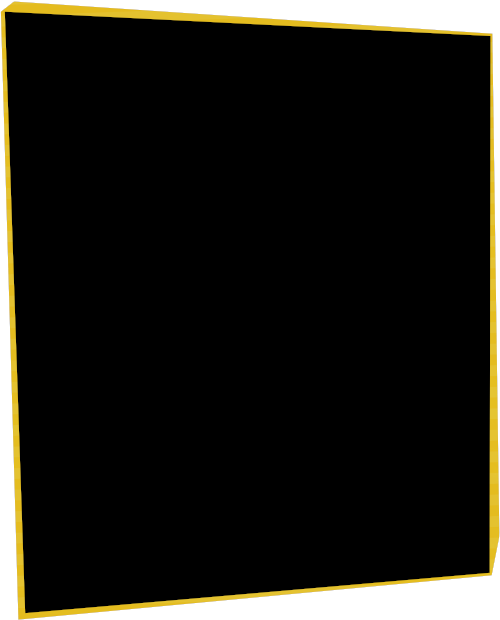
藻噛 叢馬(もがみ そうま)
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。
長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
人の噂が噂を呼び、死の海域と畏れられた美しい海《サルガッソー海》。
忘れ去られ、"否定"された海の怪異が寄り集まったばけもの。
それがこの怪物の正体である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒が一切効かない異能。
「別に解毒ができるわけじゃないし、人の役には立たない」。
聞かれればそうとだけ答えるが、実際は取り込んだ毒素を体内に溜め込み続ける異能である。
溜め込むという特性故か体外に出る体液には微量な毒素しか含まれていないが、血液や骨、臓器そのものは猛毒を帯びている。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
誰にも観測されていない瞬間の自分の状態を自由に決定できる。
条件を満たせば瞬間移動や致命傷からの復帰も可能。ただし、自分とその付属物(服や荷物)以外を対象にとることはできない。
これを利用するため、人気のない場所をいくつか把握している。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。
長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
人の噂が噂を呼び、死の海域と畏れられた美しい海《サルガッソー海》。
忘れ去られ、"否定"された海の怪異が寄り集まったばけもの。
それがこの怪物の正体である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒が一切効かない異能。
「別に解毒ができるわけじゃないし、人の役には立たない」。
聞かれればそうとだけ答えるが、実際は取り込んだ毒素を体内に溜め込み続ける異能である。
溜め込むという特性故か体外に出る体液には微量な毒素しか含まれていないが、血液や骨、臓器そのものは猛毒を帯びている。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
誰にも観測されていない瞬間の自分の状態を自由に決定できる。
条件を満たせば瞬間移動や致命傷からの復帰も可能。ただし、自分とその付属物(服や荷物)以外を対象にとることはできない。
これを利用するため、人気のない場所をいくつか把握している。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
25 / 30
1206 PS
ヒノデ
P-13
P-13




















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 幻想藻の揺鬣 | 法衣 | 108 | 水纏20 | 活力10 | 幸運15 | |
| 2 | 骨砕きの赫腕 | 武器 | 192 | 攻撃25 | 攻撃20 | - | 【射程1】 |
| 3 | 翠小石 | 素材 | 15 | [武器]風撃15(LV30)[防具]耐風20(LV30)[装飾]風柳20(LV35) | |||
| 4 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 5 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 6 | わたあめ | 料理 | 45 | 治癒13 | 充填13 | 増幅13 | |
| 7 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]幸運10(LV20) | |||
| 8 | 桜 | 素材 | 25 | [武器]祝福20(LV30)[防具]反魅15(LV25)[装飾]舞護15(LV30) | |||
| 9 | 巻き込んだ石ころ | 魔晶 | 20 | 幸運10 | - | 充填6 | |
| 10 | 薄紫の花びら | 装飾 | 82 | 復活10 | 増勢10 | - | |
| 11 | 紅小石 | 素材 | 15 | [武器]火撃15(LV30)[防具]耐火20(LV30)[装飾]舞痺20(LV35) | |||
| 12 | |||||||
| 13 | ボロ毛布 | 素材 | 20 | [武器]魔力15(LV30)[防具]耐水20(LV30)[装飾]防災20(LV30) | |||
| 14 | 幻想藻の尾 | 防具 | 90 | 耐疫10 | 活力10 | - | |
| 15 | 暴れ馬の黒蹄 | 武器 | 67 | 水纏10 | 治癒10 | - | 【射程1】 |
| 16 | たけのこ | 食材 | 20 | [効果1]貫撃10(LV15)[効果2]器用10(LV25)[効果3]深手20(LV35) | |||
| 17 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV25)[防具]強靭10(LV20)[装飾]耐狂10(LV20) | |||
| 18 | 高級黒肉のホットサンド | 料理 | 82 | 体力10 | 幸運10 | 活力10 | |
| 19 | くっついてきたフジツボ | 装飾 | 164 | 闇纏15 | 器用15 | - | |
| 20 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 21 | 蒼小石 | 素材 | 15 | [武器]水撃15(LV30)[防具]耐水20(LV30)[装飾]舞凍20(LV35) | |||
| 22 | |||||||
| 23 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 24 | お肉 | 食材 | 10 | [効果1]攻撃10(LV15)[効果2]防御10(LV25)[効果3]増幅10(LV35) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 2 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 25 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 幻術 | 5 | 夢幻/精神/光 |
| 呪術 | 25 | 呪詛/邪気/闇 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 防具 | 82 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| 決3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| 決3 | ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| カース | 6 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| 決3 | リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| 決3 | クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| サンダーボルト | 5 | 0 | 80 | 敵痺:光痛撃&麻痺 | |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |
| ボロウライフ | 6 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| フラワーバド | 5 | 0 | 70 | 敵3:地撃+自:束縛+3D6が15以上なら地撃LV増 | |
| プチメテオカード | 5 | 0 | 40 | 敵:粗雑地撃 | |
| 決3 | カタルシス | 5 | 0 | 60 | 敵強:SP光撃&強化を腐食化 |
| レイ | 5 | 0 | 30 | 敵貫:盲目 | |
| クリエイト:スパイク | 6 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 7 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
| 決3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| アクアヒール | 6 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 決3 | ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| 決1 | アクアブランド | 7 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ワンオンキル | 5 | 0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| ラディウス | 5 | 0 | 150 | 敵全:光撃+自:HP増&祝福消費で次与ダメ増 | |
| ディープフリーズ | 5 | 0 | 110 | 敵:凍結 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| コロージョン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 | |
| 決3 | マインドブレイク | 5 | 0 | 80 | 敵:SP闇撃&混乱 |
| 決3 | イレイザー | 6 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| チャクラグラント | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 | |
| グレイシア | 5 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| ウィザー | 5 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 | |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| アイシクルランス | 6 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| カレイドスコープ | 5 | 0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
| ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
| アイスエイジ | 5 | 0 | 300 | 敵:X連水領撃 ※X=対象の弱化ターン効果の数+1 | |
| ドレインライフ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&MHP奪取 | |
| ヘジテイション | 5 | 0 | 160 | 自:祝福消費でDX増(1T)+敵:SP闇痛撃&自失LV増 | |
| フィアスファング | 6 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
| コンフィデンス | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |
| ファルクス | 5 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |
| ヴァンピール | 6 | 0 | 150 | 敵:攻撃&魅了&自:HP増 | |
| スノーホワイト | 5 | 0 | 200 | 敵4:水痛撃&朦朧 | |
| ディープブルー | 6 | 0 | 200 | 敵:水撃&水特性増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 異形の膂力 (猛攻) | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 怪物の体躯 (堅守) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 否定への憤怒 (攻勢) | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |
| 幻想海・サルガッソー (五月雨) | 7 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 光の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |
| 泡沫 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP減+AG・LK・領域値[水]増 | |
| 凍縛陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど凍縛LV増 | |
| 神護 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:祝福・守護+領域値[光][闇]増+AT・DX減(1T) | |
| 精神力 | 6 | 4 | 0 | 【被攻撃命中後】自:SP増+SP10%以下なら復活LV増 | |
| 再活性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、HP・SP増&再活性消滅 | |
| 法衣作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で防具「法衣」を選択できる。法衣は効果3に幸運LVが付加される。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
夢喰花 (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
≪s@4dw≫ (ダークネス) |
0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
|
塩弾 (ストーンブラスト) |
0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
|
大咆哮 (ブレイブハート) |
0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| 決3 |
冥境止水 (ノーマライズ) |
0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 |
|
もっと深い海 (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
|
自傷 (ワンオンキル) |
0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 | |
|
ラプチャー (ラプチャー) |
2 | 200 | 敵傷:風痛撃&HP・DF減 | |
|
どっかーーーん!! (イクスプロージョン) |
0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 | |
|
気功渦 (チャクラグラント) |
2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 | |
|
ドリフのアレ (クリエイト:タライ) |
0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ブレッシングレイン | [ 3 ]ファーマシー | [ 3 ]マナポーション |
| [ 3 ]オラシオン | [ 3 ]リザレクション | [ 3 ]ノーマライズ |
| [ 3 ]サルベイション | [ 3 ]パーシステンス | [ 3 ]ノクターン |
| [ 3 ]ナース | [ 3 ]ヒーリングソング | [ 3 ]ディビジョン |
| [ 3 ]トニック |

PL / こか