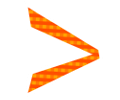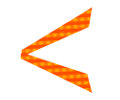<< 11:00~12:00




重い空気が満ちている。誰も一言も発するな、という合図を、皆が忠実に守り続けていた。
言い争う声の両方に聞き覚えがあり、そしてその片方は“ここにいる”。そのはずだった。片方は二ノ平悠だ。そしてもう一人は、いまここで電話に出たはずの“西村一騎”。
何が起こっているのか、何が始まったのか、全ては推測するしかなかった。大日向でさえそうだった。
『一向にお前が“そう”でなくても構わない。俺は探せる、何故なら運命があるから』
『……させないと言ったら、それはどうしますか』
『それは、お前たちのところにいる、ってことじゃないか。けれどどうしてだ、いるはずなのに何も感じない。――どこに隠した?』
『さあ?それこそ存じ上げません。』
『分かった。通信で教えてやる時間もこれで終わりだな』
電話が切れる。“西村一騎”はスマートフォンを拾い上げると、緩慢な動きで大日向の方へ向いた。彼ですら、今は厳密に言うと“西村一騎”ではない。
「……どうしますか?」
「しばし待て。人員を適切に割り振る。出る準備だけしろ」
それは鶴の一声だった。
一斉に散っていく創峰――いや、紫筑大学の学生たち。その背を見送り、大日向は自分のデスクに戻った。
大日向は、紫筑大学そのものをこの場所に結びつけている代償として、基本的に創峰大学の敷地内から出ることができない。故に全てを今回連れてきた学生たちに任せなければならない。それだけがただただ歯痒い。
彼の世界に派遣したパライバトルマリンにも動きらしい動きはなく(――要するに拠点にまだ戻っていないということなのだろう)、大日向は手持ち無沙汰だった。
故にやることができたのなら、それは願ってもないことだ。
「追い詰めてやるぞ……【透翅流星飛行】!」
ひとりきりになった部屋で、パソコンのモニターを見つめた。送られてくるデータを研究室のサーバーで、――ユッカ・ハリカリから支給された、積層世界間をまたぐ接続を可能にする特殊な無線通信を用いてアクセスした紫筑大学のサーバーで、即時分析をかける。
データをすぐに頭に入れて、思考する。どうして今【透翅流星飛行】が現れたのか。そもそも【透翅流星飛行】とはなんなのか……モニターのノイズ。かすかな糸口。
「……もし、いるか?ハリカリ。一つ頼まれてくれ」
「ええいますよ、いつでもね。いいお客様ですから」
何もなかったはずの空間に、いつの間にか男が立っている。
何の特徴もなさそうな男だ。それが、ユッカ・ハリカリのある意味での本性だ。“誰でもない”、故に誰かである。誰かであり続けている限り、本人に被害は及ばない、そう言い張る生粋の引きこもりだ。
「お代は高くつきますけどね。何用でしょう?」
「造作もなかろう。並行世界を調査して欲しい」
「……もうちょっと具体的にお願いしても?」
「料金を上げるつもりか?分かっているだろうに」
「全く傲慢なことだ。せいぜい【右手の幸運】の情報くらいで許してあげようと思っておりましたのに?」
「とっくに担保に入れたつもりでいたよ」
そして、その相手の仕方は、もう何度目か分からない。数えることはとうに忘れた。強い要求をあまり退けないということを、大日向深知はよく知っていた。後出しで高い報酬をふっかければいいということも。
諦めたように肩を竦めた男が、何も言わずに揺らめいて消えていく。そして、大日向のデスクの上に、いつの間にか『ハリカリ道具店』と書かれた領収書が落ちている。
二ノ平の救出に割り当てられたのは紀野とクレールのコンビだった。大日向は救出とは言っていたものの、“あの”二ノ平がそうそう簡単に転がされるわけがないと、二人とも思っていた。
特に、機械類が存在していればなおのことだ。二ノ平は数値計算ラボラトリにいるはずだった。
二ノ平悠という男は“機械が大量にある場所で真価を発揮する”。それは彼の能力がそのように定められていて、機械があればあるほど、その種類に応じて、ありとあらゆる能力を間接的に駆使することができる。【多脚百跡夜行】は、機械であれば何でも、自分の意のままにすることができる能力だ。それが故に万能で、それが故に欠点がある。幾重にも処理を走らせればオーバーヒートを起こすことは当然あるし、データを即時反映できても、それを理解していなければ意味がない。万能であることは、知識が伴っていなければ強みにはならない。【知識の坩堝】系統と区別されて記載されているのは、機械さえあれば理論上は全く際限なくあらゆる力を行使できるからだ。
「数値計算室の二ノ平パイセンならへーきなんじゃないっスか……?」
「そういう仮定で動くな。イレギュラーはいつだってある」
「ッス」
そこはいつも通りに静かだった。いつも通り静かなことが、これほど異様だっただろうか。本当にごく一抹の不安を握らされたまま、廊下に足を踏み入れた瞬間だった。
「お前、やっぱり同じところから来てない?」
静寂をばりばりと引き裂いて、男の“ようなもの”が飛び出してくる。
身に纏う金属光沢が流動的に位置を変え、その手は完全に繋がってはいなかった。――そして、その手に、二ノ平が常に能力を発動させるために身に着けているアームデバイスが握られている。
「俺、見たことあるもん。見たことあるよ、お前のこと。でも違う」
「二ノ平パイセン!!」
「すいません、下手を打ちました!せめてそれだけでも!」
揺れるプラチナブロンド。
鮮やかな空色の目。
顔から下を一切合切、人としての理から外した――男のようなもの。
「あたしは足止めだけだったらクッソ得意ですよぉ~ッ!!クレールパイセン!!」
「うるせえな」
【私が魚でここは海】、と力強く宣言された瞬間に、足元に水が押し寄せるような感覚が走る。人の歩みを止めるのは、膝下だけで十分なのだ。確かに困惑の表情を見せた男が、その腰の推定羽で飛ぶ前に、クレールは『弓』を引いた。
「置いていけ」
それは不可視だった。それは不可視のはずだった。けれど、到達する直前に明確に光として捉えられたのを見た。一瞬こちらを見た鮮やかな空色が、明確にクレールを嘲っていた。
「もういらねえから置いてくよ。お前らにも用はない」
「何のためにお前はここに来た?答えろ」
世界の壁が、耳障りな音を立てて引き裂かれていく。ショッキングピンクの爪の色。にやりと口元を歪めて、それは名乗るように言った。
「息子を探しに来たのさ。俺の運命が、ここにいるって告げているんだ!」
二発目を撃つより早く、その姿は世界の向こう側へと消えていた。

『こちら大日向。襲撃を掛けてきたのは【透翅流星飛行】と断定』
ある場所に向かって走りながら、西村と宮城野は通信を聞いていた。直接的な被害は今のところ不明、データに触れられた可能性あり、負傷者はなし――怪異【透翅流星飛行】。
西村一騎に酷似した外見と顔立ちを持つが、その髪色は染めたようではないこと。外見、および所作から怪異に分類されること。世界の裏側に潜り込み、身を潜めるすべを持つこと。本人自体の攻撃力は全く大したことがなく、適切な防御を繰り返していれば先に【透翅流星飛行】自身が消耗していくこと。目的は息子を探すことだということ。
『断じるには早いが、【透翅流星飛行】の言う息子はほぼ【右手の幸運】のことで間違いないだろう。結果的にボクの対【哀歌の行進】対策が功を奏しているうちに、告げよ』
遠かった。故に、この二人だった。
宮城野陽華の【捻じくれた深淵の鈴】は、規定されている座標に対してなら、即座に移動することのできる能力の持ち主だ。そのスキップの仕方は、世界の裏側を通ること。事前にいくつかの座標を取っておけば、そこに即座に移動し、それに対応する場所に現れることができる。
つまり大日向は、これを逆手に取って平然と自分たちを釣り餌にしているのだ。【透翅流星飛行】が世界の裏側に潜む能力を持つというのなら、“自分”を狙ってこないわけがない。
『件の神の手を煩わせるようなことでもないかもしれないが……』
「それ、要するに、釣りますって言ってますよね」
「……飛びますね……」
「ああいいですよ、一々許可を取らなくて」
積層構造世界論によって体系づけられた世界は、転がり落ちるのは簡単だが、登っていくことは大変だ。そこを飛び越えて登るためには、能力が必要だ。それが宮城野陽華の持っている能力の本来の使い方だ。
上に行けば行くほど高次世界となり、下に落ちれば落ちるほど低俗で劣悪な世界になるとされているが、その証明方法は立証されていない。そもそも自分の住んでいる世界以外の“世界”を知ろうとする人間が少ないからだ。大多数の人間は、自分が生きている世界だけが唯一だと思ったまま生まれ、生き、そして死ぬ。
「けど……」
「いいと言ったらいいんです。どうせ何が起こるか分かっているので」
積層構造世界論における世界と世界の狭間は、基本的に何もない。
星の輝きも空の色もない宇宙だと、一般の人間には説明する。宇宙の極点とも違う、無。どこの法則にも属さない無。そこに飛び込むことは、一般的に死を意味した。無から何かを探し当てることは、砂浜に落とした砂礫を探すこととほぼ同義だ。専門的な知識がなければ。
宮城野曰く、無の中にも地形や光源は存在し、それを知覚できればできるほど、世界の狭間において有利になる。そして彼女はその能力者で、紫筑で誰よりも無の中を見ることに長けていた。
だから、必然なのだ。

現実から転移した瞬間に、手が伸びてきていることは。

すぐに跳ね除けていた。予想できていたから、そうした。それ以上に、西村の心は揺れ動く。
(……どうして)
「……先輩……?」
「何でもない。……」
それは兄によく似ていた。無の中に佇む、辛うじて人型の男と分かる造形。特徴が、聞いていた【透翅流星飛行】と一致する。全てを閉ざし、凍てつく氷の中に閉じ込め、“西村一騎”はそれを見た。
「……お前は……」
「来るとは思っていましたけど、ドンピシャで合わせてくるとは思いませんでしたね。何の用ですか?」
「……」
耳に痛いほどの静謐の中、二人分だけの呼吸音がする。心臓が脈打つ音、血が流れる音すら聞こえてくるようだった。どちらが口を開くでもなく、ただ見つめ合っていた。
合図はごく一瞬。鮮やかな空色が細められた瞬間だった。
「お前は違う。俺の知っているユーインじゃない」
「ではお引取りいただけますか。邪魔なんですよ」
「邪魔なのはそちらじゃないか?どうして誰もが俺の運命を邪魔するんだ、悪いことではないはずなのに」
「――先輩!危ない!」
無の中で、確かに空を切る音がした。羽撃きの音がした。
かき消えるだとか、そういう次元のものではなかった。もっと別の力で、【透翅流星飛行】は、何かを仕掛けてきたようだった。それが何かすら、西村には知覚できないまま守られる。
飛び退った先で宮城野と同じ方向を見て、西村は目を瞬いた。何かが――無が砕かれている。それを煌々と蒼い炎の明かりが照らし、影を落としていた。
「ねえ、あなた……本意ではないことをさせないで。私は気まぐれだから、手が滑ってあなたを焼いてしまう」
神々しい獣が――上半身が鳥で、下半身が獅子の獣が、そこにいる。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.426 アストロイェライ とのやりとり

ENo.502 ナックラヴィー とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.14 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(13⇒14)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












グノウ(909) から 竹 を受け取りました。
命術LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
迦楼羅(931) により ItemNo.21 剛毛 に ItemNo.22 剛毛 を合成してもらい、白い塊 に変化させました!
⇒ 白い塊/素材:強さ20/[武器]閃光10(LV20)[防具]治癒10(LV10)[装飾]気合10(LV20)
ItemNo.20 枝豆 から料理『塩茹で枝豆』をつくりました!
⇒ 塩茹で枝豆/料理:強さ100/[効果1]復活15 [効果2]快癒15 [効果3]増幅15
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.18 何か固い物体 から料理『ずんだもち』をつくろうと思いましたが、食材じゃないことに何とか気づけました。
グノウ(909) の持つ ItemNo.14 シロツメクサの栞 に ItemNo.29 白詰草 を付加しました!
ユヅキ(118) とカードを交換しました!
かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー)
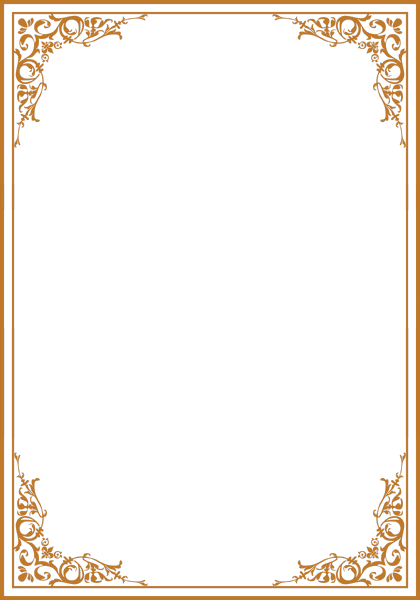
ミゼラブルメモリー を研究しました!(深度0⇒1)
ミゼラブルメモリー を研究しました!(深度1⇒2)
ミゼラブルメモリー を研究しました!(深度2⇒3)
コンフィデンス を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ペットボトル を入手!
スズヒコ(244) は 車前草 を入手!
グノウ(909) は ペットボトル を入手!
迦楼羅(931) は 車前草 を入手!
フェデルタ(165) は 蒼小石 を入手!
フェデルタ(165) は 翠小石 を入手!
フェデルタ(165) は 鉄くず を入手!
フェデルタ(165) は 橙小石 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 氷使い がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 風使い が泣きながら近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 暴走自転車 が微笑を浮かべて近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 岩投げ師 がゆっくりと近づいてきます。



マガサ区 C-2(道路)に移動!(体調14⇒13)
マガサ区 C-3(草原)に移動!(体調13⇒12)
マガサ区 D-3(森林)に移動!(体調12⇒11)
マガサ区 E-3(森林)に移動!(体調11⇒10)
マガサ区 F-3(森林)に移動!(体調10⇒9)





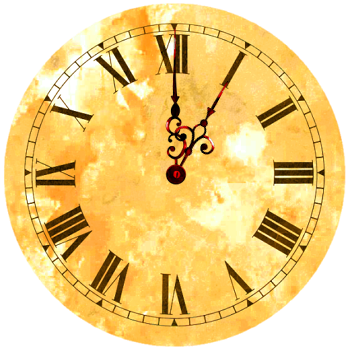
[845 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[409 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[460 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[150 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[311 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[202 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[149 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[68 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。


不機嫌そうな表情。
首を傾げる白南海。
ポケットから黒いハンカチを取り出す。
それを手で握り、すぐ手を開く。
すると、ハンカチが可愛い黒兎の人形に変わっている。
眼鏡をクイッと少し押し上げる。
咄嗟に腕を組み、身構える。
そう言ってチャットから抜けるエディアン。
チャットが閉じられる――













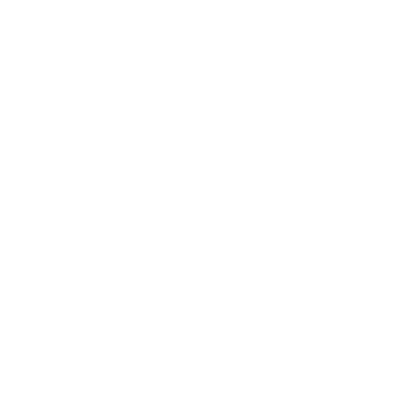
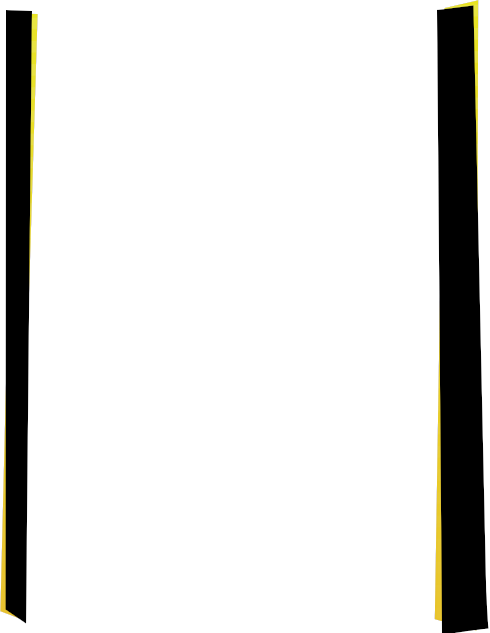
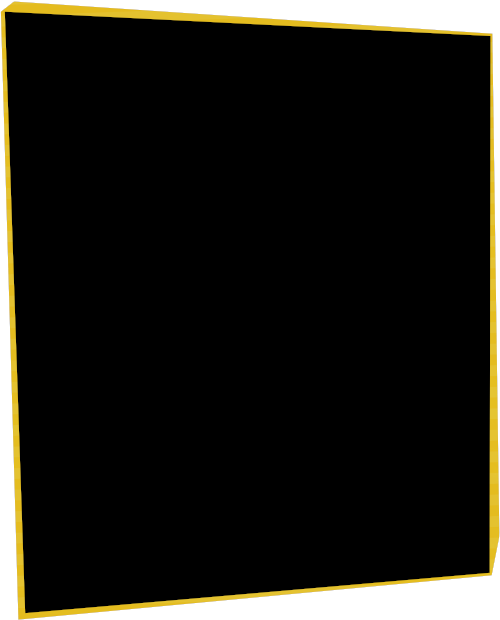





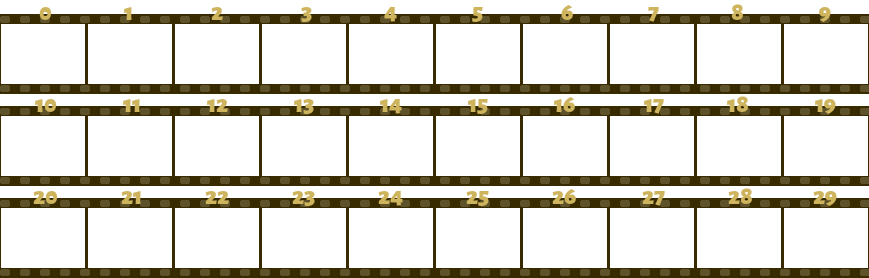









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



重い空気が満ちている。誰も一言も発するな、という合図を、皆が忠実に守り続けていた。
言い争う声の両方に聞き覚えがあり、そしてその片方は“ここにいる”。そのはずだった。片方は二ノ平悠だ。そしてもう一人は、いまここで電話に出たはずの“西村一騎”。
何が起こっているのか、何が始まったのか、全ては推測するしかなかった。大日向でさえそうだった。
『一向にお前が“そう”でなくても構わない。俺は探せる、何故なら運命があるから』
『……させないと言ったら、それはどうしますか』
『それは、お前たちのところにいる、ってことじゃないか。けれどどうしてだ、いるはずなのに何も感じない。――どこに隠した?』
『さあ?それこそ存じ上げません。』
『分かった。通信で教えてやる時間もこれで終わりだな』
電話が切れる。“西村一騎”はスマートフォンを拾い上げると、緩慢な動きで大日向の方へ向いた。彼ですら、今は厳密に言うと“西村一騎”ではない。
「……どうしますか?」
「しばし待て。人員を適切に割り振る。出る準備だけしろ」
それは鶴の一声だった。
一斉に散っていく創峰――いや、紫筑大学の学生たち。その背を見送り、大日向は自分のデスクに戻った。
大日向は、紫筑大学そのものをこの場所に結びつけている代償として、基本的に創峰大学の敷地内から出ることができない。故に全てを今回連れてきた学生たちに任せなければならない。それだけがただただ歯痒い。
彼の世界に派遣したパライバトルマリンにも動きらしい動きはなく(――要するに拠点にまだ戻っていないということなのだろう)、大日向は手持ち無沙汰だった。
故にやることができたのなら、それは願ってもないことだ。
「追い詰めてやるぞ……【透翅流星飛行】!」
ひとりきりになった部屋で、パソコンのモニターを見つめた。送られてくるデータを研究室のサーバーで、――ユッカ・ハリカリから支給された、積層世界間をまたぐ接続を可能にする特殊な無線通信を用いてアクセスした紫筑大学のサーバーで、即時分析をかける。
データをすぐに頭に入れて、思考する。どうして今【透翅流星飛行】が現れたのか。そもそも【透翅流星飛行】とはなんなのか……モニターのノイズ。かすかな糸口。
「……もし、いるか?ハリカリ。一つ頼まれてくれ」
「ええいますよ、いつでもね。いいお客様ですから」
何もなかったはずの空間に、いつの間にか男が立っている。
何の特徴もなさそうな男だ。それが、ユッカ・ハリカリのある意味での本性だ。“誰でもない”、故に誰かである。誰かであり続けている限り、本人に被害は及ばない、そう言い張る生粋の引きこもりだ。
「お代は高くつきますけどね。何用でしょう?」
「造作もなかろう。並行世界を調査して欲しい」
「……もうちょっと具体的にお願いしても?」
「料金を上げるつもりか?分かっているだろうに」
「全く傲慢なことだ。せいぜい【右手の幸運】の情報くらいで許してあげようと思っておりましたのに?」
「とっくに担保に入れたつもりでいたよ」
そして、その相手の仕方は、もう何度目か分からない。数えることはとうに忘れた。強い要求をあまり退けないということを、大日向深知はよく知っていた。後出しで高い報酬をふっかければいいということも。
諦めたように肩を竦めた男が、何も言わずに揺らめいて消えていく。そして、大日向のデスクの上に、いつの間にか『ハリカリ道具店』と書かれた領収書が落ちている。
二ノ平の救出に割り当てられたのは紀野とクレールのコンビだった。大日向は救出とは言っていたものの、“あの”二ノ平がそうそう簡単に転がされるわけがないと、二人とも思っていた。
特に、機械類が存在していればなおのことだ。二ノ平は数値計算ラボラトリにいるはずだった。
二ノ平悠という男は“機械が大量にある場所で真価を発揮する”。それは彼の能力がそのように定められていて、機械があればあるほど、その種類に応じて、ありとあらゆる能力を間接的に駆使することができる。【多脚百跡夜行】は、機械であれば何でも、自分の意のままにすることができる能力だ。それが故に万能で、それが故に欠点がある。幾重にも処理を走らせればオーバーヒートを起こすことは当然あるし、データを即時反映できても、それを理解していなければ意味がない。万能であることは、知識が伴っていなければ強みにはならない。【知識の坩堝】系統と区別されて記載されているのは、機械さえあれば理論上は全く際限なくあらゆる力を行使できるからだ。
「数値計算室の二ノ平パイセンならへーきなんじゃないっスか……?」
「そういう仮定で動くな。イレギュラーはいつだってある」
「ッス」
そこはいつも通りに静かだった。いつも通り静かなことが、これほど異様だっただろうか。本当にごく一抹の不安を握らされたまま、廊下に足を踏み入れた瞬間だった。
「お前、やっぱり同じところから来てない?」
静寂をばりばりと引き裂いて、男の“ようなもの”が飛び出してくる。
身に纏う金属光沢が流動的に位置を変え、その手は完全に繋がってはいなかった。――そして、その手に、二ノ平が常に能力を発動させるために身に着けているアームデバイスが握られている。
「俺、見たことあるもん。見たことあるよ、お前のこと。でも違う」
「二ノ平パイセン!!」
「すいません、下手を打ちました!せめてそれだけでも!」
揺れるプラチナブロンド。
鮮やかな空色の目。
顔から下を一切合切、人としての理から外した――男のようなもの。
「あたしは足止めだけだったらクッソ得意ですよぉ~ッ!!クレールパイセン!!」
「うるせえな」
【私が魚でここは海】、と力強く宣言された瞬間に、足元に水が押し寄せるような感覚が走る。人の歩みを止めるのは、膝下だけで十分なのだ。確かに困惑の表情を見せた男が、その腰の推定羽で飛ぶ前に、クレールは『弓』を引いた。
「置いていけ」
それは不可視だった。それは不可視のはずだった。けれど、到達する直前に明確に光として捉えられたのを見た。一瞬こちらを見た鮮やかな空色が、明確にクレールを嘲っていた。
「もういらねえから置いてくよ。お前らにも用はない」
「何のためにお前はここに来た?答えろ」
世界の壁が、耳障りな音を立てて引き裂かれていく。ショッキングピンクの爪の色。にやりと口元を歪めて、それは名乗るように言った。
「息子を探しに来たのさ。俺の運命が、ここにいるって告げているんだ!」
二発目を撃つより早く、その姿は世界の向こう側へと消えていた。

『こちら大日向。襲撃を掛けてきたのは【透翅流星飛行】と断定』
ある場所に向かって走りながら、西村と宮城野は通信を聞いていた。直接的な被害は今のところ不明、データに触れられた可能性あり、負傷者はなし――怪異【透翅流星飛行】。
西村一騎に酷似した外見と顔立ちを持つが、その髪色は染めたようではないこと。外見、および所作から怪異に分類されること。世界の裏側に潜り込み、身を潜めるすべを持つこと。本人自体の攻撃力は全く大したことがなく、適切な防御を繰り返していれば先に【透翅流星飛行】自身が消耗していくこと。目的は息子を探すことだということ。
『断じるには早いが、【透翅流星飛行】の言う息子はほぼ【右手の幸運】のことで間違いないだろう。結果的にボクの対【哀歌の行進】対策が功を奏しているうちに、告げよ』
遠かった。故に、この二人だった。
宮城野陽華の【捻じくれた深淵の鈴】は、規定されている座標に対してなら、即座に移動することのできる能力の持ち主だ。そのスキップの仕方は、世界の裏側を通ること。事前にいくつかの座標を取っておけば、そこに即座に移動し、それに対応する場所に現れることができる。
つまり大日向は、これを逆手に取って平然と自分たちを釣り餌にしているのだ。【透翅流星飛行】が世界の裏側に潜む能力を持つというのなら、“自分”を狙ってこないわけがない。
『件の神の手を煩わせるようなことでもないかもしれないが……』
「それ、要するに、釣りますって言ってますよね」
「……飛びますね……」
「ああいいですよ、一々許可を取らなくて」
積層構造世界論によって体系づけられた世界は、転がり落ちるのは簡単だが、登っていくことは大変だ。そこを飛び越えて登るためには、能力が必要だ。それが宮城野陽華の持っている能力の本来の使い方だ。
上に行けば行くほど高次世界となり、下に落ちれば落ちるほど低俗で劣悪な世界になるとされているが、その証明方法は立証されていない。そもそも自分の住んでいる世界以外の“世界”を知ろうとする人間が少ないからだ。大多数の人間は、自分が生きている世界だけが唯一だと思ったまま生まれ、生き、そして死ぬ。
「けど……」
「いいと言ったらいいんです。どうせ何が起こるか分かっているので」
積層構造世界論における世界と世界の狭間は、基本的に何もない。
星の輝きも空の色もない宇宙だと、一般の人間には説明する。宇宙の極点とも違う、無。どこの法則にも属さない無。そこに飛び込むことは、一般的に死を意味した。無から何かを探し当てることは、砂浜に落とした砂礫を探すこととほぼ同義だ。専門的な知識がなければ。
宮城野曰く、無の中にも地形や光源は存在し、それを知覚できればできるほど、世界の狭間において有利になる。そして彼女はその能力者で、紫筑で誰よりも無の中を見ることに長けていた。
だから、必然なのだ。

現実から転移した瞬間に、手が伸びてきていることは。

すぐに跳ね除けていた。予想できていたから、そうした。それ以上に、西村の心は揺れ動く。
(……どうして)
「……先輩……?」
「何でもない。……」
それは兄によく似ていた。無の中に佇む、辛うじて人型の男と分かる造形。特徴が、聞いていた【透翅流星飛行】と一致する。全てを閉ざし、凍てつく氷の中に閉じ込め、“西村一騎”はそれを見た。
「……お前は……」
「来るとは思っていましたけど、ドンピシャで合わせてくるとは思いませんでしたね。何の用ですか?」
「……」
耳に痛いほどの静謐の中、二人分だけの呼吸音がする。心臓が脈打つ音、血が流れる音すら聞こえてくるようだった。どちらが口を開くでもなく、ただ見つめ合っていた。
合図はごく一瞬。鮮やかな空色が細められた瞬間だった。
「お前は違う。俺の知っているユーインじゃない」
「ではお引取りいただけますか。邪魔なんですよ」
「邪魔なのはそちらじゃないか?どうして誰もが俺の運命を邪魔するんだ、悪いことではないはずなのに」
「――先輩!危ない!」
無の中で、確かに空を切る音がした。羽撃きの音がした。
かき消えるだとか、そういう次元のものではなかった。もっと別の力で、【透翅流星飛行】は、何かを仕掛けてきたようだった。それが何かすら、西村には知覚できないまま守られる。
飛び退った先で宮城野と同じ方向を見て、西村は目を瞬いた。何かが――無が砕かれている。それを煌々と蒼い炎の明かりが照らし、影を落としていた。
「ねえ、あなた……本意ではないことをさせないで。私は気まぐれだから、手が滑ってあなたを焼いてしまう」
神々しい獣が――上半身が鳥で、下半身が獅子の獣が、そこにいる。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.426 アストロイェライ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.502 ナックラヴィー とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.14 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(13⇒14)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





ミハクサマ親衛隊
|
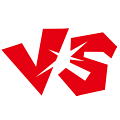 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 15 増加!
影響力が 15 増加!



グノウ(909) から 竹 を受け取りました。
 |
グノウ 「この間、たけのこを拾いましたから、竹もあるわけですね」 |
命術LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
迦楼羅(931) により ItemNo.21 剛毛 に ItemNo.22 剛毛 を合成してもらい、白い塊 に変化させました!
⇒ 白い塊/素材:強さ20/[武器]閃光10(LV20)[防具]治癒10(LV10)[装飾]気合10(LV20)
ItemNo.20 枝豆 から料理『塩茹で枝豆』をつくりました!
⇒ 塩茹で枝豆/料理:強さ100/[効果1]復活15 [効果2]快癒15 [効果3]増幅15
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.18 何か固い物体 から料理『ずんだもち』をつくろうと思いましたが、食材じゃないことに何とか気づけました。
グノウ(909) の持つ ItemNo.14 シロツメクサの栞 に ItemNo.29 白詰草 を付加しました!
ユヅキ(118) とカードを交換しました!
かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー)
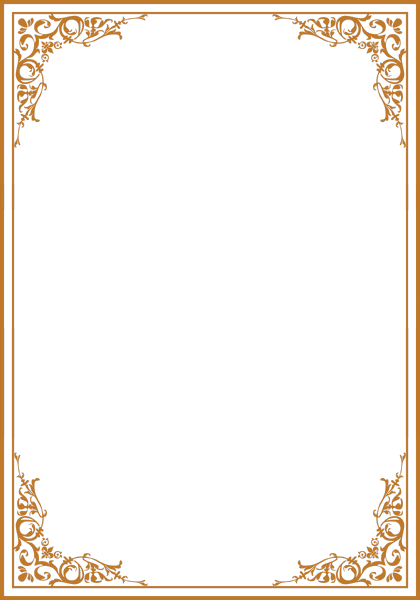
ミゼラブルメモリー を研究しました!(深度0⇒1)
ミゼラブルメモリー を研究しました!(深度1⇒2)
ミゼラブルメモリー を研究しました!(深度2⇒3)
コンフィデンス を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ペットボトル を入手!
スズヒコ(244) は 車前草 を入手!
グノウ(909) は ペットボトル を入手!
迦楼羅(931) は 車前草 を入手!
フェデルタ(165) は 蒼小石 を入手!
フェデルタ(165) は 翠小石 を入手!
フェデルタ(165) は 鉄くず を入手!
フェデルタ(165) は 橙小石 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに 氷使い がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 風使い が泣きながら近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 暴走自転車 が微笑を浮かべて近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに 岩投げ師 がゆっくりと近づいてきます。



マガサ区 C-2(道路)に移動!(体調14⇒13)
マガサ区 C-3(草原)に移動!(体調13⇒12)
マガサ区 D-3(森林)に移動!(体調12⇒11)
マガサ区 E-3(森林)に移動!(体調11⇒10)
マガサ区 F-3(森林)に移動!(体調10⇒9)





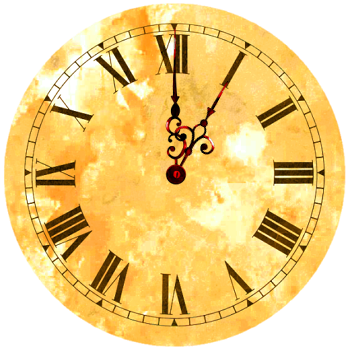
[845 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[409 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[460 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[150 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[311 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[202 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[149 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[68 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
白南海 「・・・ロストの情報をやたらと隠しやがるなワールドスワップ。 これも能力の範疇なのかねぇ・・・・・とんでもねぇことで。」 |
 |
白南海 「異能ならリスクも半端ねぇだろーが、なかにはトンデモ異能もありやがるしねぇ。」 |
不機嫌そうな表情。
 |
エディアン 「私、多くの世界を渡り歩いてますけど・・・ここまで大掛かりで影響大きくて滅茶苦茶なものは滅多に。」 |
 |
エディアン 「そういえば貴方はどんな異能をお持ちなんです?」 |
 |
白南海 「聞きたきゃまずてめぇからでしょ。」 |
 |
エディアン 「私の異能はビジーゴースト。一定の動作を繰り返し行わせる透明な自分のコピーを作る能力です。」 |
 |
白南海 「あっさり言うもんだ。そりゃなかなか便利そうじゃねぇか。」 |
 |
エディアン 「動作分の疲労は全部自分に来ますけどねー。便利ですよ、周回とか。」 |
 |
白南海 「集会・・・?」 |
 |
エディアン 「えぇ。」 |
首を傾げる白南海。
 |
エディアン 「――で、貴方は?」 |
 |
白南海 「ぁー・・・・・どうすっかね。」 |
ポケットから黒いハンカチを取り出す。
それを手で握り、すぐ手を開く。
すると、ハンカチが可愛い黒兎の人形に変わっている。
 |
エディアン 「わぁー!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・手品の異能ですかー!!合コンでモテモテですねー!!」 |
 |
白南海 「なに勝手に変な間つくって憐れんでんだおい。」 |
 |
白南海 「糸とかをだなー・・・・・好きにできる?まぁ簡単に言えばそんなだ。 結構使えんだよこれが、仕事でもな。」 |
 |
白南海 「それにこれだけじゃねぇしな、色々視えたり。」 |
眼鏡をクイッと少し押し上げる。
 |
エディアン 「え!何が視えるんです!?」 |
 |
白南海 「裸とか?」 |
 |
エディアン 「ぇ・・・・・」 |
咄嗟に腕を組み、身構える。
 |
白南海 「・・・嘘っすよ、秘密秘密。言っても何も得しねぇし。」 |
 |
エディアン 「ケチですねぇ。まぁ私も、イバラシティ生活の時の話ですけどねー。」 |
 |
白南海 「・・・・・は?」 |
 |
エディアン 「案外ひとを信じるんですねぇー、意外意外!」 |
そう言ってチャットから抜けるエディアン。
 |
白南海 「あぁ!?きったねぇだろそれ!クッソがッ!!おいいッ!!! ・・・アンジニティぶっ潰すッ!!!!」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
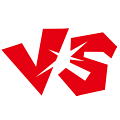 |
トレイターズ
|


ENo.244
鈴のなる夢
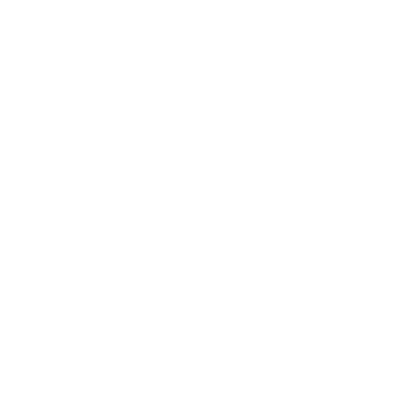
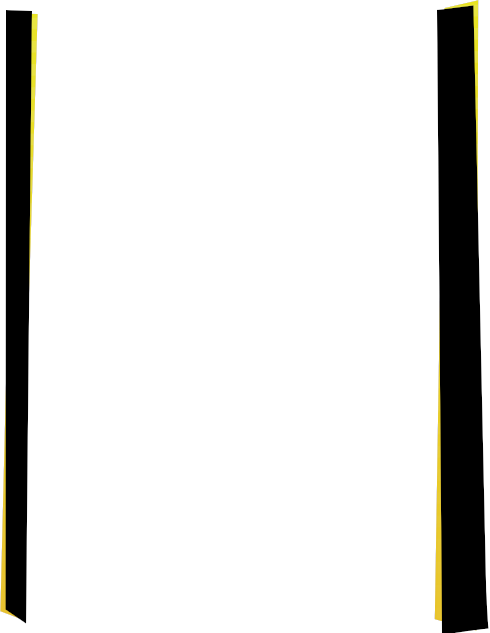
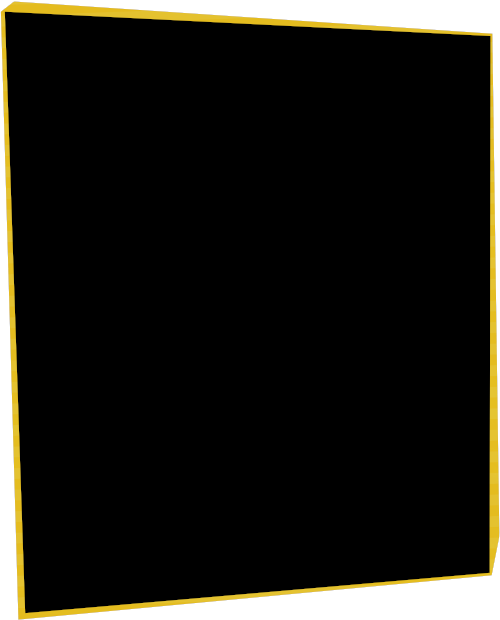
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
9 / 30
1084 PS
マガサ
F-3
F-3







痛撃友の会
4
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
2
アイコン60pxの会
1
#片道切符チャット
#交流歓迎
2
アンジ出身イバラ陣営の集い
2
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
3
カード報告会
8
とりあえず肉食う?
6



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | - | - | 【射程3】 |
| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |
| 5 | ポプラ | 素材 | 25 | [武器]追風15(LV35)[防具]耐災25(LV35)[装飾]風纏25(LV40) | |||
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | - | - | |
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | 風柳10 | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | 竹 | 素材 | 30 | [武器]致命20(LV40)[防具]加速20(LV35)[装飾]応報20(LV40) | |||
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 塩茹で枝豆 | 料理 | 100 | 復活15 | 快癒15 | 増幅15 | |
| 21 | 白い塊 | 素材 | 20 | [武器]閃光10(LV20)[防具]治癒10(LV10)[装飾]気合10(LV20) | |||
| 22 | 車前草 | 素材 | 25 | [武器]共鳴15(LV40)[防具]復活20(LV40)[装飾]治癒20(LV40) | |||
| 23 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
| 24 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
| 25 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 20 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 25 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 40 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 40 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 9 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| 練3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| 練3 | マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| 練3 | リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 |
| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| 練3 | ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 11 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| 練3 | スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 6 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| 練3 | セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| グレイシア | 7 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 6 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| 練3 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練3 | ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 |
| 練3 | イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 |
| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 | |
| 練3 | コンフィデンス | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 練3 | 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 |
| 治癒領域 | 7 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練3 |
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
|
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 | |
| 練3 |
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
|
弧 (ファルクス) |
0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
|
ギフトカード (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
|
かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー) |
5 | 500 | 自:エンペラー召喚 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]レーヴァテイン | [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]プチメテオカード |
| [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]プロテクション |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]ミゼラブルメモリー |
| [ 3 ]フレイムインパクト | [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]イディオータ |
| [ 3 ]クリエイト:モンスター |

PL / 紙箱みど