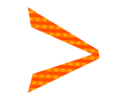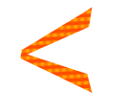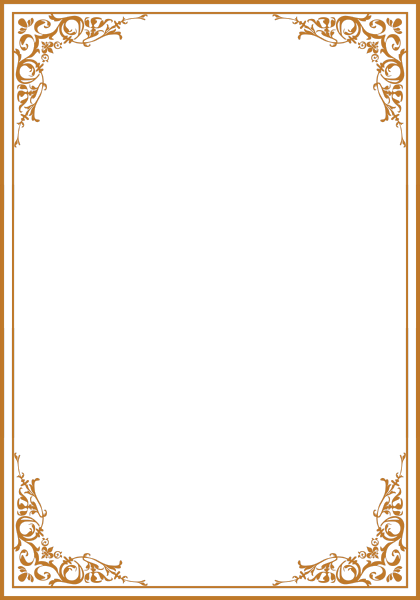<< 10:00~11:00




感情を殺した目で見つめていた。
できることなら三十六時間、そのままでいたかった。それを許さない、一時間ごとの記憶の流入。切り離して記録として処理しても、ここにいる間は残り続けるだろう。三十六時間に対して、“楽しげな姿が多すぎる”。

『……その、さっきは本当に悪かった。アンタを責めようとかそういうつもりじゃなかった。俺も、余裕がなくて、どうしていいかわからなくて、不安だった』
だから興味のない体を装っている。聞き流しているように見えているだろう、きっと。
改善の余地。最善の選択。――歩き続けるしかないということ。歩き続けて、辿り着かねばならないということ。歩き続けて、歩き続けて、どこかにあるはずの出口を見つけなければならない。
『どんな形でもスズヒコは、スズヒコだ。そんな当たり前の事も忘れて、焦ってた。でもきっと、今の状態に一番納得いってないのはアンタだ』
その通りだ。
自分には、お得意の頭脳しかないのだ。三十六時間は、そういう意味でも短すぎる。水の残渣をようやく掴んで、飛び交う火の粉から不滅の火を得る。それだけでは足りないだろう。
短すぎた。けれども、そこに飛び込んでくるあらゆる情報が、己を狂わせる。ごくごく平和に暮らしているだけの人間に、こんなに心乱されることがあっただろうか。
『……なら、俺が出来る事なんて無い。だから、待ってる。アンタが納得出来る形になるまで。アンタの側で』
彼は何かを掴んだのだろうか。
けれど、ああして掴みかかったあとで、それについて聞けるような精神と、覚悟は持ち合わせていなかった。
――ぼくと先生の話をしようと思う。
知っている、あるいは覚えている人はもう誰もいないだろう、秘密の話だ。ぼくはパライバトルマリン、不出来な神の御使いの成れの果て。神のおわす世界から見放され、あとは死ぬだけだったはずの成れの果て。捨てる神あれば拾う神ありとはよく言ったもので、けれどぼくは最低でも二度は捨てられた
ひとつ。生まれ損なったぼくを捨てた“世界”。黎明の世界樹エーオシャフト。世界樹の下に神がおわし、そして枝葉末節それぞれがひとつの世界を構築する大きな世界。
ひとつ。ぼくを外界適応させようと、あらゆる改造を施した人たち。手足どころか目すらない生き物に、彼らは装甲としての被嚢と、腕としての触手を与えた。それまではよかったかもしれない。そこから先に進みすぎ、ぼくの身体はその気になれば人を殺せるようになった。人を殺したくないというぼくを、もう覚えていない誰かが黒いビニール袋に入れて捨ててくれた。名前すらなかった生き物は、そこで一度死を迎えた。ぼくから生み出された他のあまたの“きょうだい”たちが、どうなったのか。御使いの理から弾かれている以上、ぼくに知り用はなかった。
ひとつ。同じ研究所の“変わりものの集まり”。偶然にも誰よりも遅くゴミを捨てに行く彼らは、ぼくの入ったゴミ袋に興味を示した。中を暴き、ぼくを見た彼らは、ぼくに向かって“おもしろいね”と言った。
ぼくの見た目は、どうやったって取り繕えるものではなく、気持ち悪いという分類にカテゴライズされるのが普通だろう。けれど彼らの好奇心の方が上回り、そうしてぼくは“ペット”になった。捨てられていたものをどうしたっていいだろう、という持論の下、彼らはぼくに優しくしてくれた……というより、ぼくの存在を許した。
ぼくはそれだけで優しくされた気になって、元気良く飛び回っていた。
ぼくたちと先生の関係が変わったころ、世界の間の情勢が悪化していた。
黎明の世界樹エーオシャフトの葉の一枚、双極世界バイポーリス。科学の世界シエンティカと自然の世界ネイトリエが融合し、それが混ざり合わないまま存在している世界。それが、ぼくたちと先生のいた世界の名前。バイポーリスという名前はぼくらのような御使いしか知らないし、シエンティカとネイトリエはあくまで二つの国名として扱われていた。――要するに、国と国の間で、一触即発の状態が続いていたころ。先生だけが、別の研究室に異動になった。
先生は自然の世界の出身だった。そして、ぼくたちの研究所は、科学の世界にあった。
先生が来たときは何ともなくて、それでも“変わりものの集まり”に入れられて……要するに、差別だ。けれど“変わりものの集まり”の構成人員は、それを欠片も気にしなかった。先生はむしろあの中ではよっぽど常識があって、絶対午後から出勤してくる人、机の下に強引にマットレスを敷き詰めて眠っている人、その他なんか……とんでもない人々、それらに比べたら本当にマシだった。先生は要するに、別の国の人間だからという理由でここに入れられていた、ということにぼくが気づいたのは、この研究所が跡形もなく燃え尽きてからだった。
大人のやることの方が陰湿だ、と言っていたのは、確か机の下で寝ていた人だったと思う。先生はいじめられている。先生は干されようとしている。その言葉の意味は、今になってようやく分かった。異物を排除しようとしている。そう言えば聞こえは良い。けれど、やっていることはどうしようもなく、個人に負担をかけ、破壊しようとする行為だった。
ぼくたちはどうにか先生を助けられないかと思って(――先生は優秀な人だったので)、いろいろな案を出し合ったりもした。けれど、ぼくたちが“変わりものの集まり”だというのが足を引っ張ってしまって、結局何も出来ないまま、その日を迎えてしまった。
『先生はね、何でも下準備する人。先のことを考えて、用意しなくていいものまで用意する人』
言葉の通り。
学会というものがある。大抵の場合、その研究室での研究課題はひとつの方向を向いていて、同じ学会に皆が出向くことは当たり前といえば、そうだった。出向かなくても、それを理由にして休んだり、早引きをしたり……先生はその日をずっと待っていた。何も信じられなくなりながら。
無敵の人、という言葉がある。これも後から知った言葉だけれど、先生のことをよく表していたと思う。家をもぬけの殻にし、結婚指輪もどこかに隠し、こちらに連れてきていた娘さんは、確か親戚のところに預けていたと思う。全てを断ち切り、一直線にこちら――研究所だけを見つめていた。
そして、研究所には。可燃物が、大量に転がっている。ふつう、そういう火災が起こったときは防火設備が作動するものだ、と、大日向深知……今の持ち主には教わった。たぶん、世界が変わればその基準も変わって、そして今よりは昔のことだったから、そういうものなんじゃないかなあ、と、ぼくは曖昧に答えている。実際どうして、あれだけ火の手が上がったのか、ぼくには分からないでいた。
ぼくには呼吸が必要なかった。だから“嫌な予感がして”飛んでいった。逃げ損なった人が一酸化炭素中毒で倒れている上を乗り越えて、焼け落ちて崩れたドアの向こう側から聞こえる『助けて』という声を無視して、一人の人間だけを助けに行った。
結論から言うと、ぼくは拒絶された。
もっと正確に言えば、先生がぼくの飼い主になっていたことを利用され、娘たちのために働いてくれと頼まれた。そう言われてしまえば、ぼくには抵抗する力はなかった。ただ、その通りに動くしかなかった。
結果的にそれは最善になり、先生と娘さんたちはとある本の世界で再会して――そこでも、いろいろあったのだけれど。先生が今の先生のような状態に限りなく近い、人間ではない何かになったのは、その本の世界だ。だから先生の本体は、本そのもので、そして、燃えることがない。
だからぼくは、先生と何のしがらみもない状態で向き合うのが、初めてだ。
この髪は持ち主の鏡。今はユッカ・ハリカリ――から、間接的に譲渡された大日向深知。彼らは先生のことを“どうでもいいもの”か“利用するもの”としてしか見ていなくて、その認識はぼくにも反映される。
情も何も全てを抜かれたフラットな形で向き合うのは、初めてだった。

「……先生、覚えてる?」
口から発されたのは、女とも男ともつかない声だった。
「……」
「……先生、」
「邪魔をしに来たのか?」
致命的に変わってしまっているなあ、というのを、肌で感じている。何かを見失っていて、それを探すのに必死になっている、そんな声。
見下ろす視線は氷のようだった。それを是としてしまうのは、あまり良くないことのように感じられた。
「……時と場合によるかも。基本的には協力の要請だけど」
「誰から……」
「吉野暁海から。」
見開かれる目。その一言だけで理解されたのだろう、羽織の袖から鋭い爪が伸びてくる。外套は分厚く、セルロース繊維で構成されているからそうやすやすとは切り裂けない。
しばらく爪を引っ掛けていて、どうにもならないことに気づいたのか、“先生”――スズヒコは手を離した。
「何故あんたがその名前を……」
「今の飼い主が大日向深知だからさ。覚えてるよね?」
「……思い出したよ。そういうやつだった」
一歩前に進む。スズヒコの足は動かない。
「ぼくは、大日向深知から……“あなたの力を借りたい”という言伝てを持ってやってきた。けど」
「けど、何」
「今の先生には具体的に何をどうするかについては伝えられない。だって、そういう状態ではないから」
駆け引きだ。それか、爆弾処理だ。
本当に少しだけ冷静になってもらって、他人のことについて考慮できるほどの余裕が生まれたとき、パライバトルマリンは大日向から託されたジョーカーを切ることができる。
そのことについては、もうきっかけは生まれているはずなのだ。
「けれど、ひとつだけ言えることがある」
「……何の取引?」
「ああ、聡い。そうだよね、知ってたよ」
ぼくはもう少し、先生に寄り添うことができたはずだけれど、今の先生はきっとそれを求めていなかった。自分で辿り着いて結果を手繰り寄せたとき、ようやく視界が拓けることを知っているひとだから――先生も、大日向も。
ずっと難しい顔をしていたのを知っている。知っていた。今の顔も、なんとなくそんな気がしていた。記憶としては朧気な眼鏡を掛けた横顔は、今には似ても似つかない。けれど、根本的なものはきっと同じだ。探している人間の目。糸口を求めている目。
「……無駄な時間は使いたくないんだ、できるだけ。話してくれ」
「それは無理だ。ぼくらが求めている状態ではないから。……そうなんでしょう、先生。納得行ってないんでしょう」
見つめる目の色の片方は、知らない色だ。そして、共に歩いている人も、知らない人が二人いる。それがどのような導きなのか、ぼくには推し量ることはできない。できなくなった。
でも、覚えていることはある。あなたがきっと、何の準備もしていないなんてことはありえないということ。死ぬために執拗な準備をするんだから、こうなることも予期しているはずだ。
「……それで」
「分かった。……“こちらには世界転移の技術がある”」
「……!」
果たして大日向深知は、それを知っていたのだろうか。ぼくですら知らなかったようなことを、把握していたのだろうか。ぼくは確かに見た。先生の冷たい顔が鮮やかな驚きに染まるさまを見た。
――否定の世界。罪人の掃き溜め。どうして先生は、こんなところにいるんだろう。



ENo.151 ガズエット とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.20 ひんやりフルーツアイス を食べました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!















ロストのフレディオ・・・のようだ。
周囲に散乱したゾンビを眺め、
こちらの姿をじーっと確認する。
真剣な眼差しで訴える。
考え込むフレディオ。
フレディオは芋焼酎を欲しているようだ。
エロ本と間違えないよう注意しなければならない。



メリーナ(646) に ItemNo.22 ビーフ を送付しました。
魔術LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
メリーナ(646) により ItemNo.9 タイヤ片 から装飾『ルリユールリング』を作製してもらいました!
⇒ ルリユールリング/装飾:強さ170/[効果1]気合15 [効果2]- [効果3]-
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.18 お野菜 から料理『温野菜ピリ辛ソース和え』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.26 良いお肉 から料理『厚切りステーキ野菜添え』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.12 禁断じゃない果実 から料理『マジカルフルーツアイス』をつくりました!
グノウ(909) により ItemNo.12 零度の背表紙 に ItemNo.21 羽 を付加してもらいました!
⇒ 零度の背表紙/防具:強さ100/[効果1]反凍10 [効果2]風柳10 [効果3]-
レイ(525) とカードを交換しました!
ギフトカード (サモン:ビーフ)

クリエイト:モンスター を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:モンスター を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:モンスター を研究しました!(深度2⇒3)
イグニス を習得!
ビッグウェイブ を習得!
イクスプロージョン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は 白詰草 を入手!
スズヒコ(244) は 枝豆 を入手!
スズヒコ(244) は 剛毛 を入手!
スズヒコ(244) は 剛毛 を入手!
フェデルタ(165) は 腐肉 を入手!
スズヒコ(244) は 腐肉 を入手!
フェデルタ(165) は 腐肉 を入手!
スズヒコ(244) は 腐肉 を入手!
フェデルタ(165) は 腐肉 を入手!
スズヒコ(244) は 腐肉 を入手!
フェデルタ(165) は 腐肉 を入手!



ヒノデ区 R-2(草原)に移動!(体調18⇒17)
ヒノデ区 S-2(道路)に移動!(体調17⇒16)
ヒノデ区 T-2(道路)に移動!(体調16⇒15)
マガサ区 A-2(道路)に移動!(体調15⇒14)
マガサ区 B-2(道路)に移動!(体調14⇒13)





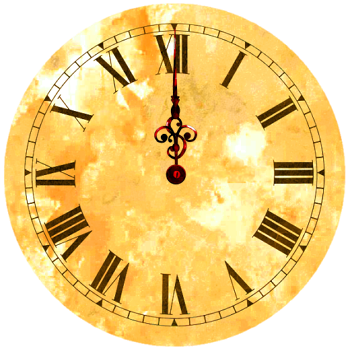
[843 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[396 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[440 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[138 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[272 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[125 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[125 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[24 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。




ロストのふたりがチャットに入り込んできた。
軽蔑の眼差しを向けるエディアン。
ミヨチンを制止する。
フレディオの胸倉をつかみ強く睨みつける!
――ザザッ
チャットが閉じられる――













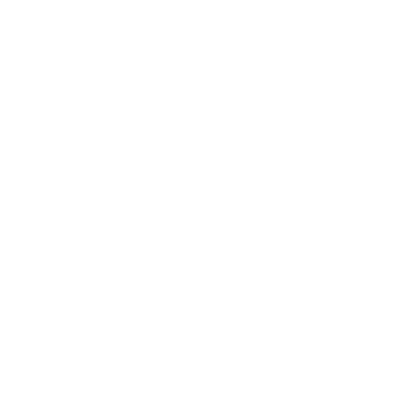
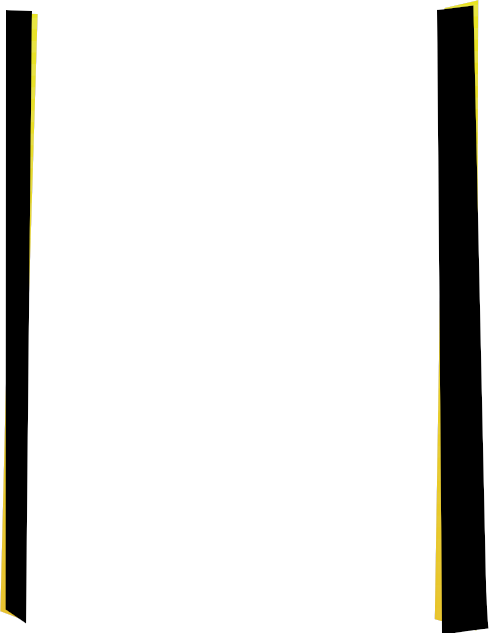
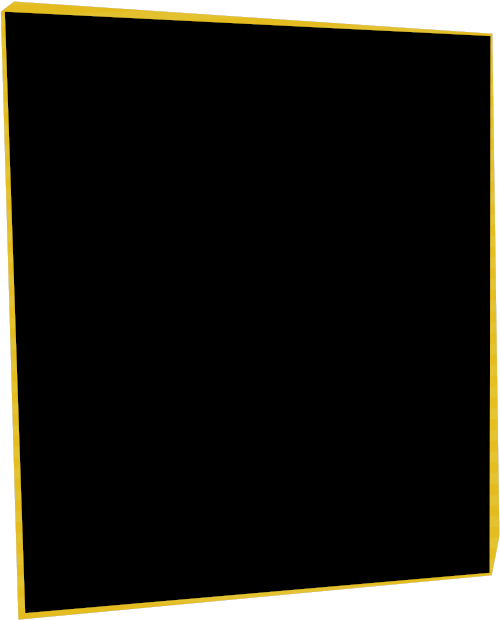





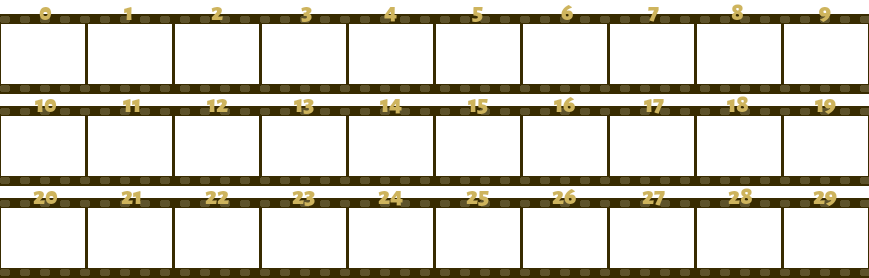









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



感情を殺した目で見つめていた。
できることなら三十六時間、そのままでいたかった。それを許さない、一時間ごとの記憶の流入。切り離して記録として処理しても、ここにいる間は残り続けるだろう。三十六時間に対して、“楽しげな姿が多すぎる”。

『……その、さっきは本当に悪かった。アンタを責めようとかそういうつもりじゃなかった。俺も、余裕がなくて、どうしていいかわからなくて、不安だった』
だから興味のない体を装っている。聞き流しているように見えているだろう、きっと。
改善の余地。最善の選択。――歩き続けるしかないということ。歩き続けて、辿り着かねばならないということ。歩き続けて、歩き続けて、どこかにあるはずの出口を見つけなければならない。
『どんな形でもスズヒコは、スズヒコだ。そんな当たり前の事も忘れて、焦ってた。でもきっと、今の状態に一番納得いってないのはアンタだ』
その通りだ。
自分には、お得意の頭脳しかないのだ。三十六時間は、そういう意味でも短すぎる。水の残渣をようやく掴んで、飛び交う火の粉から不滅の火を得る。それだけでは足りないだろう。
短すぎた。けれども、そこに飛び込んでくるあらゆる情報が、己を狂わせる。ごくごく平和に暮らしているだけの人間に、こんなに心乱されることがあっただろうか。
『……なら、俺が出来る事なんて無い。だから、待ってる。アンタが納得出来る形になるまで。アンタの側で』
彼は何かを掴んだのだろうか。
けれど、ああして掴みかかったあとで、それについて聞けるような精神と、覚悟は持ち合わせていなかった。
――ぼくと先生の話をしようと思う。
知っている、あるいは覚えている人はもう誰もいないだろう、秘密の話だ。ぼくはパライバトルマリン、不出来な神の御使いの成れの果て。神のおわす世界から見放され、あとは死ぬだけだったはずの成れの果て。捨てる神あれば拾う神ありとはよく言ったもので、けれどぼくは最低でも二度は捨てられた
ひとつ。生まれ損なったぼくを捨てた“世界”。黎明の世界樹エーオシャフト。世界樹の下に神がおわし、そして枝葉末節それぞれがひとつの世界を構築する大きな世界。
ひとつ。ぼくを外界適応させようと、あらゆる改造を施した人たち。手足どころか目すらない生き物に、彼らは装甲としての被嚢と、腕としての触手を与えた。それまではよかったかもしれない。そこから先に進みすぎ、ぼくの身体はその気になれば人を殺せるようになった。人を殺したくないというぼくを、もう覚えていない誰かが黒いビニール袋に入れて捨ててくれた。名前すらなかった生き物は、そこで一度死を迎えた。ぼくから生み出された他のあまたの“きょうだい”たちが、どうなったのか。御使いの理から弾かれている以上、ぼくに知り用はなかった。
ひとつ。同じ研究所の“変わりものの集まり”。偶然にも誰よりも遅くゴミを捨てに行く彼らは、ぼくの入ったゴミ袋に興味を示した。中を暴き、ぼくを見た彼らは、ぼくに向かって“おもしろいね”と言った。
ぼくの見た目は、どうやったって取り繕えるものではなく、気持ち悪いという分類にカテゴライズされるのが普通だろう。けれど彼らの好奇心の方が上回り、そうしてぼくは“ペット”になった。捨てられていたものをどうしたっていいだろう、という持論の下、彼らはぼくに優しくしてくれた……というより、ぼくの存在を許した。
ぼくはそれだけで優しくされた気になって、元気良く飛び回っていた。
ぼくたちと先生の関係が変わったころ、世界の間の情勢が悪化していた。
黎明の世界樹エーオシャフトの葉の一枚、双極世界バイポーリス。科学の世界シエンティカと自然の世界ネイトリエが融合し、それが混ざり合わないまま存在している世界。それが、ぼくたちと先生のいた世界の名前。バイポーリスという名前はぼくらのような御使いしか知らないし、シエンティカとネイトリエはあくまで二つの国名として扱われていた。――要するに、国と国の間で、一触即発の状態が続いていたころ。先生だけが、別の研究室に異動になった。
先生は自然の世界の出身だった。そして、ぼくたちの研究所は、科学の世界にあった。
先生が来たときは何ともなくて、それでも“変わりものの集まり”に入れられて……要するに、差別だ。けれど“変わりものの集まり”の構成人員は、それを欠片も気にしなかった。先生はむしろあの中ではよっぽど常識があって、絶対午後から出勤してくる人、机の下に強引にマットレスを敷き詰めて眠っている人、その他なんか……とんでもない人々、それらに比べたら本当にマシだった。先生は要するに、別の国の人間だからという理由でここに入れられていた、ということにぼくが気づいたのは、この研究所が跡形もなく燃え尽きてからだった。
大人のやることの方が陰湿だ、と言っていたのは、確か机の下で寝ていた人だったと思う。先生はいじめられている。先生は干されようとしている。その言葉の意味は、今になってようやく分かった。異物を排除しようとしている。そう言えば聞こえは良い。けれど、やっていることはどうしようもなく、個人に負担をかけ、破壊しようとする行為だった。
ぼくたちはどうにか先生を助けられないかと思って(――先生は優秀な人だったので)、いろいろな案を出し合ったりもした。けれど、ぼくたちが“変わりものの集まり”だというのが足を引っ張ってしまって、結局何も出来ないまま、その日を迎えてしまった。
『先生はね、何でも下準備する人。先のことを考えて、用意しなくていいものまで用意する人』
言葉の通り。
学会というものがある。大抵の場合、その研究室での研究課題はひとつの方向を向いていて、同じ学会に皆が出向くことは当たり前といえば、そうだった。出向かなくても、それを理由にして休んだり、早引きをしたり……先生はその日をずっと待っていた。何も信じられなくなりながら。
無敵の人、という言葉がある。これも後から知った言葉だけれど、先生のことをよく表していたと思う。家をもぬけの殻にし、結婚指輪もどこかに隠し、こちらに連れてきていた娘さんは、確か親戚のところに預けていたと思う。全てを断ち切り、一直線にこちら――研究所だけを見つめていた。
そして、研究所には。可燃物が、大量に転がっている。ふつう、そういう火災が起こったときは防火設備が作動するものだ、と、大日向深知……今の持ち主には教わった。たぶん、世界が変わればその基準も変わって、そして今よりは昔のことだったから、そういうものなんじゃないかなあ、と、ぼくは曖昧に答えている。実際どうして、あれだけ火の手が上がったのか、ぼくには分からないでいた。
ぼくには呼吸が必要なかった。だから“嫌な予感がして”飛んでいった。逃げ損なった人が一酸化炭素中毒で倒れている上を乗り越えて、焼け落ちて崩れたドアの向こう側から聞こえる『助けて』という声を無視して、一人の人間だけを助けに行った。
結論から言うと、ぼくは拒絶された。
もっと正確に言えば、先生がぼくの飼い主になっていたことを利用され、娘たちのために働いてくれと頼まれた。そう言われてしまえば、ぼくには抵抗する力はなかった。ただ、その通りに動くしかなかった。
結果的にそれは最善になり、先生と娘さんたちはとある本の世界で再会して――そこでも、いろいろあったのだけれど。先生が今の先生のような状態に限りなく近い、人間ではない何かになったのは、その本の世界だ。だから先生の本体は、本そのもので、そして、燃えることがない。
だからぼくは、先生と何のしがらみもない状態で向き合うのが、初めてだ。
この髪は持ち主の鏡。今はユッカ・ハリカリ――から、間接的に譲渡された大日向深知。彼らは先生のことを“どうでもいいもの”か“利用するもの”としてしか見ていなくて、その認識はぼくにも反映される。
情も何も全てを抜かれたフラットな形で向き合うのは、初めてだった。

「……先生、覚えてる?」
口から発されたのは、女とも男ともつかない声だった。
「……」
「……先生、」
「邪魔をしに来たのか?」
致命的に変わってしまっているなあ、というのを、肌で感じている。何かを見失っていて、それを探すのに必死になっている、そんな声。
見下ろす視線は氷のようだった。それを是としてしまうのは、あまり良くないことのように感じられた。
「……時と場合によるかも。基本的には協力の要請だけど」
「誰から……」
「吉野暁海から。」
見開かれる目。その一言だけで理解されたのだろう、羽織の袖から鋭い爪が伸びてくる。外套は分厚く、セルロース繊維で構成されているからそうやすやすとは切り裂けない。
しばらく爪を引っ掛けていて、どうにもならないことに気づいたのか、“先生”――スズヒコは手を離した。
「何故あんたがその名前を……」
「今の飼い主が大日向深知だからさ。覚えてるよね?」
「……思い出したよ。そういうやつだった」
一歩前に進む。スズヒコの足は動かない。
「ぼくは、大日向深知から……“あなたの力を借りたい”という言伝てを持ってやってきた。けど」
「けど、何」
「今の先生には具体的に何をどうするかについては伝えられない。だって、そういう状態ではないから」
駆け引きだ。それか、爆弾処理だ。
本当に少しだけ冷静になってもらって、他人のことについて考慮できるほどの余裕が生まれたとき、パライバトルマリンは大日向から託されたジョーカーを切ることができる。
そのことについては、もうきっかけは生まれているはずなのだ。
「けれど、ひとつだけ言えることがある」
「……何の取引?」
「ああ、聡い。そうだよね、知ってたよ」
ぼくはもう少し、先生に寄り添うことができたはずだけれど、今の先生はきっとそれを求めていなかった。自分で辿り着いて結果を手繰り寄せたとき、ようやく視界が拓けることを知っているひとだから――先生も、大日向も。
ずっと難しい顔をしていたのを知っている。知っていた。今の顔も、なんとなくそんな気がしていた。記憶としては朧気な眼鏡を掛けた横顔は、今には似ても似つかない。けれど、根本的なものはきっと同じだ。探している人間の目。糸口を求めている目。
「……無駄な時間は使いたくないんだ、できるだけ。話してくれ」
「それは無理だ。ぼくらが求めている状態ではないから。……そうなんでしょう、先生。納得行ってないんでしょう」
見つめる目の色の片方は、知らない色だ。そして、共に歩いている人も、知らない人が二人いる。それがどのような導きなのか、ぼくには推し量ることはできない。できなくなった。
でも、覚えていることはある。あなたがきっと、何の準備もしていないなんてことはありえないということ。死ぬために執拗な準備をするんだから、こうなることも予期しているはずだ。
「……それで」
「分かった。……“こちらには世界転移の技術がある”」
「……!」
果たして大日向深知は、それを知っていたのだろうか。ぼくですら知らなかったようなことを、把握していたのだろうか。ぼくは確かに見た。先生の冷たい顔が鮮やかな驚きに染まるさまを見た。
――否定の世界。罪人の掃き溜め。どうして先生は、こんなところにいるんだろう。



ENo.151 ガズエット とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.20 ひんやりフルーツアイス を食べました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 12 増加!
影響力が 12 増加!



ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
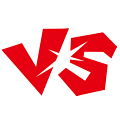 |
立ちはだかるもの
|



ヒノデ区 M-2 周辺:ヒノデコーポレーション
ゾンビを一掃すると、物陰から再び何かが現れる。
フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
ロストのフレディオ・・・のようだ。
 |
フレディオ 「おっ・・・・・チャットは送れていたようだな。 あぁいう類いのはようわからんが、どうにかなるもんだ。」 |
周囲に散乱したゾンビを眺め、
 |
フレディオ 「おぅおぅ、しっかりやってくれたな。おかげで弾が節約できたぜ。」 |
こちらの姿をじーっと確認する。
 |
フレディオ 「・・・どうせなら絶世の美女ちゃんに助けられたかったが、まぁいい。 俺の願いを叶えてくれるっつー話だったな。」 |
 |
フレディオ 「おっと、助けてくれーはノーカンな。俺の願いは、ズバリ・・・・・」 |
 |
フレディオ 「・・・エロ本だ。最高のやつを頼む。」 |
真剣な眼差しで訴える。
 |
フレディオ 「・・・・・・あー・・・いや、やめだ。 これは・・・ジャンルが大事だからな・・・。ぁー・・・・・」 |
考え込むフレディオ。
 |
フレディオ 「・・・・・・・・・酒、だな。」 |
 |
フレディオ 「芋焼酎を、お願いできるか。最高のやつを頼む。」 |
フレディオは芋焼酎を欲しているようだ。
エロ本と間違えないよう注意しなければならない。



メリーナ(646) に ItemNo.22 ビーフ を送付しました。
魔術LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV35⇒40、-5CP)
メリーナ(646) により ItemNo.9 タイヤ片 から装飾『ルリユールリング』を作製してもらいました!
⇒ ルリユールリング/装飾:強さ170/[効果1]気合15 [効果2]- [効果3]-
 |
メリーナ 「おつかれさま。頼まれてたリングを作ってきたよ。サイズは大丈夫かな?」 |
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.18 お野菜 から料理『温野菜ピリ辛ソース和え』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.26 良いお肉 から料理『厚切りステーキ野菜添え』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.12 禁断じゃない果実 から料理『マジカルフルーツアイス』をつくりました!
グノウ(909) により ItemNo.12 零度の背表紙 に ItemNo.21 羽 を付加してもらいました!
⇒ 零度の背表紙/防具:強さ100/[効果1]反凍10 [効果2]風柳10 [効果3]-
 |
グノウ 「私たちはよく羽を拾いますよね。」 |
レイ(525) とカードを交換しました!
ギフトカード (サモン:ビーフ)

クリエイト:モンスター を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:モンスター を研究しました!(深度1⇒2)
クリエイト:モンスター を研究しました!(深度2⇒3)
イグニス を習得!
ビッグウェイブ を習得!
イクスプロージョン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は 白詰草 を入手!
スズヒコ(244) は 枝豆 を入手!
スズヒコ(244) は 剛毛 を入手!
スズヒコ(244) は 剛毛 を入手!
フェデルタ(165) は 腐肉 を入手!
スズヒコ(244) は 腐肉 を入手!
フェデルタ(165) は 腐肉 を入手!
スズヒコ(244) は 腐肉 を入手!
フェデルタ(165) は 腐肉 を入手!
スズヒコ(244) は 腐肉 を入手!
フェデルタ(165) は 腐肉 を入手!



ヒノデ区 R-2(草原)に移動!(体調18⇒17)
ヒノデ区 S-2(道路)に移動!(体調17⇒16)
ヒノデ区 T-2(道路)に移動!(体調16⇒15)
マガサ区 A-2(道路)に移動!(体調15⇒14)
マガサ区 B-2(道路)に移動!(体調14⇒13)





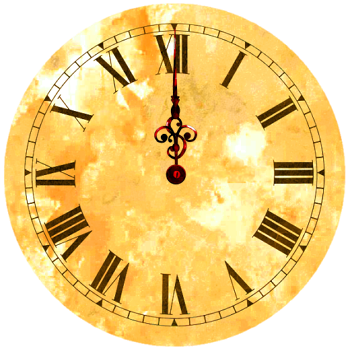
[843 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[396 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[440 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[138 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[272 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[125 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[125 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[24 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
 |
フレディオ 「いよぉ!なるほどこう入んのか、ようやく使えそうだぜ。」 |
 |
ミヨチン 「にゃー!遊びに来たっすよぉ!!」 |
 |
エディアン 「にゃー!いらっしゃいませー!!」 |
 |
白南海 「毎度毎度うっせぇなぁ・・・いやこれ俺絶対この役向いてねぇわ。」 |
ロストのふたりがチャットに入り込んできた。
 |
ミヨチン 「・・・・・?おっさん誰?」 |
 |
フレディオ 「フレディオにゃー。ピッチピチ小娘も大好きにゃん!」 |
 |
ミヨチン 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |
 |
フレディオ 「・・・いやジョークだろジョーク、そんな反応すんなっつーの。」 |
 |
ミヨチン 「大好きなのは嬉しーけど、そのナリでにゃんは痛いっすよぉ! なんすかそれ口癖っすかぁ??まじウケるんですけど。」 |
 |
フレディオ 「え、あぁそっち?・・・ジョークだジョーク。」 |
 |
エディアン 「私はそっちじゃないほうですね。顔がいいだけに残念です。」 |
軽蔑の眼差しを向けるエディアン。
 |
白南海 「・・・別にいいだろーよ。若い女が好きな男なんてむしろ普通だ普通。」 |
 |
フレディオ 「おうおうそうだそうだ!話の分かる兄ちゃんがいて助かるわッ」 |
 |
フレディオ 「・・・っつーわけで、みんなで初めましてのハグしようや!!!!」 |
 |
ミヨチン 「ハグハグー!!」 |
 |
エディアン 「ダメダメやめなさいミヨちゃん、確実にろくでもないおっさんですよあれ。」 |
ミヨチンを制止する。
 |
フレディオ 「・・・ハグしたがってる者を止める権利がお前にはあるのか?」 |
 |
エディアン 「真面目な顔して何言ってんですかフレディオさ・・・・・フレディオ。おい。」 |
 |
白南海 「お堅いねぇ。ハグぐらいしてやりゃえぇでしょうに。」 |
 |
フレディオ 「そうだそうだ!枯れたおっさんのちょっとした願望・・・・・」 |
 |
フレディオ 「・・・・・願望!?そうかその手が!!!!」 |
 |
エディアン 「ゼッッッッタイにやめてください。」 |
フレディオの胸倉をつかみ強く睨みつける!
 |
白南海 「そういえば聞きたかったんすけど、あんたらロストって一体どういう存在――」 |
――ザザッ
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



ミハクサマ親衛隊
|
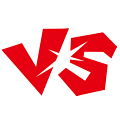 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|


ENo.244
鈴のなる夢
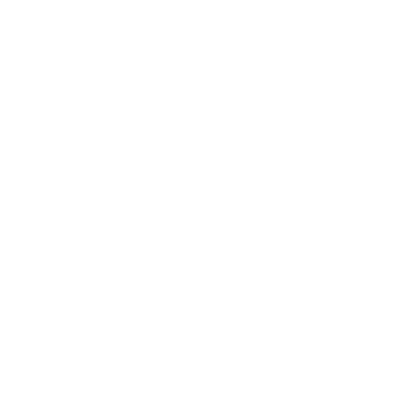
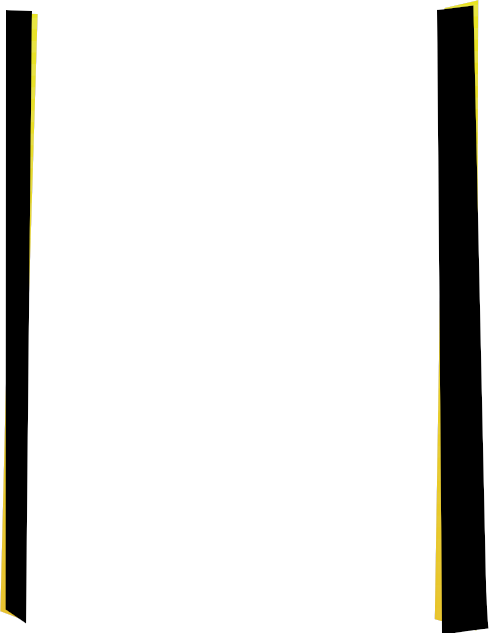
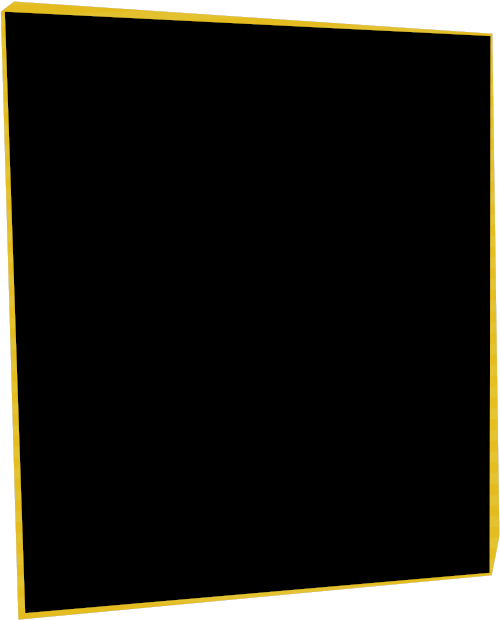
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
13 / 30
945 PS
マガサ区
B-2
B-2







痛撃友の会
4
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
3
アイコン60pxの会
2
#片道切符チャット
#交流歓迎
3
アンジ出身イバラ陣営の集い
8
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
4
カード報告会
6
とりあえず肉食う?
9



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | - | - | 【射程3】 |
| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |
| 5 | ポプラ | 素材 | 25 | [武器]追風15(LV35)[防具]耐災25(LV35)[装飾]風纏25(LV40) | |||
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | - | - | |
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | 風柳10 | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 枝豆 | 食材 | 20 | [効果1]復活15(LV15)[効果2]快癒15(LV25)[効果3]増幅15(LV35) | |||
| 21 | 剛毛 | 素材 | 10 | [武器]放縛15(LV25)[防具]反縛15(LV25)[装飾]強靭15(LV25) | |||
| 22 | 剛毛 | 素材 | 10 | [武器]放縛15(LV25)[防具]反縛15(LV25)[装飾]強靭15(LV25) | |||
| 23 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
| 24 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
| 25 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 20 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 40 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 35 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 8 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| 練3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 練1 | フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| 練3 | マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) |
| 練3 | コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アンダークーリング | 6 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| 練1 | ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| 練1 | カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| 練3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 練1 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| 練2 | ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| 練2 | ブレイブハート | 11 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| 練2 | ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| 練2 | クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| 練2 | サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |
| 練2 | アブソーブ | 6 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 |
| 練2 | ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 |
| 練2 | セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| グレイシア | 6 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 6 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| 練2 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 | |
| イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 | |
| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 練2 | 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 |
| 治癒領域 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練2 |
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| 練2 |
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
| 練2 |
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
| 練2 |
弧 (ファルクス) |
0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 |
|
ギフトカード (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]フレイムインパクト | [ 3 ]イディオータ | [ 3 ]フィアスファング |
| [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]クリエイト:モンスター |
| [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]ブレイブハート |
| [ 3 ]レーヴァテイン | [ 3 ]プチメテオカード | [ 3 ]アブソーブ |

PL / 紙箱みど