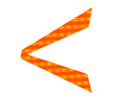<< 9:00~10:00





天を仰いでいる姿があった。赤いコートはいつかと変わらず、相変わらず独特のにおいがする。燃えるにおいと、不快なにおいだ。不快なにおいの出元が『タバコ』という嗜好品からするのも知っていた。
追跡するのは簡単なことだった。力の残渣を追う、たったそれだけでよかった。このハザマという空間では、僅かな力であっても増幅される――そう聞いていた説明は正しかった。
人の少ない方向に向かっているのは、恐らく作戦の一つだろう。研究者はそうするからだ。先駆者のいる分野に立ち入っても意味がないことを知っている。その傘の下に入らない限りは。
その男――フェデルタ・アートルムは、パライバトルマリンも知っていた。先生が懇意にしていた人。それが友情なのか、愛情なのか、それとも別のものなのか、パライバにはあまり分からない。けれども、そうである、という事実のほうが重要だった。
そうであるのなら、接触することでアドバンテージが生まれるのだ。ステルス状態で見上げた顔は、あまりにも辛気臭い。
しばらく観察を続けていた。何本か目のタバコに火をつけ、ふと零すように言った言葉に、返事を返さないという選択肢はなかった。これは確実にチャンスだと思ったのだ。自分の主は今、咲良乃スズヒコではない。利用できるものは全てを利用する、大日向深知という女だ。
「……どの面下げりゃいいんだろうな」
「ほんとだよ。まーそのツラしかないと思うんだけど……」
「!!」
独り言に唐突に返事が来たのだから、それは当たり前の反応だった。吐き捨てられたタバコが狭間の大地でぶすぶすと燃え尽き、代わりに声をかけられた男の警戒心に火が点いている。
少しフランクにしすぎたか、とか、それもどうでもいい。分析するに、咲良乃スズヒコの名前を出すだけでどうにかできそうだったからだ。飼われていた実績がある。
「……誰だ」
「やっほー。ぼくだよ。覚えてる?」
ステルスを解く。ついさっきまでフェデルタが寄りかかっていた瓦礫の影から這い出て、“あのとき”とは毛の色が違うことに気づいた。こればかりは飼い主依存なので仕方ない。
「……覚えてる?」
問いかけた。その方が手っ取り早いと判断した。警戒されている気配を感じながら、どう言ったものか思慮する。覚えてる?と問いかけたからには、その外堀を埋めていくほうがいい。
今の飼い主と、かつての飼い主の思考回路は、比較的似通っている。故に、パライバは考えるのが楽だった。同じことをすればいい。覚えていることの大半が通用する。
「あそこだよほら、本の世界!おじさんもいたでしょ?」
「……、あ、」
具体的な名前まで必要かと思ってライブラリーを漁っていたが、それも不要そうだった。であれば、もう少しで納得してもらえるはずだ。思い出すのを待つ。
「……お前、たしか……なんだっけ、パラ、なんとか」
「ウワッ記憶ガバガバじゃん。パライバだよ!パライバトルマリン!」
「ああ、ああ、そうだ、パライバ」
覚えてくれている、ということを確認したら、そのとき名前を出せばいい。そう言っていたのは大日向も、“先生”も一緒だった。
見つめる先の男――フェデルタのことは、よく聞いていたはずだ。けれど、それはもうほとんどが抜け落ちている。持ち主が変わったとき、残っている力を残すか、それともきれいに洗うか、それは新しい持ち主に全てが託される。パライバトルマリンを捕まえたユッカ・ハリカリという男は、力は抜き出すだけ抜き出して、きれいに洗いはしなかった。その方が有用かもしれないから、どうするかは次の持ち主――大日向深知に一任すると。
結果として、存在と、“先生にとって大事な人であること”ということだけ、覚えている。
「……なんでここに――あ、」
忘れているのなら、疑問は当たり前だろう。“ぼく”をきちんと認識している人は、基本的にそのときの飼い主に限られる。そうでなければ、ゆっくりと記憶から欠けていく。人間の記憶は欠けるもの。それに乗じて神の御使いもまた、存在を消す。
忘れることは、必然だ。そして、忘れていたものを呼び起こすこともまた、同様に。この触角は、そういうことに長けていた。
「……色々思い出せた?」
「ああ」
素直に相対する。あとは、面白おかしく話をしてやるだけだった。
「あーよかった! いや、だって、さっきまであんなよぼよぼふらふらで、ぴえんぴえんしてる感じだったからさあ。お話になるのかなって心配したよね、元気になってよかったよかった!」
「おま、え……いつから?」
「えー……ここにきてから二、三時間くらい?」
正確に数えてはいない。そんな機能は備えられていない。けれども、人々の行動でおおよその予測は立っていた。
フェデルタは片手で顔を覆っている。よっぽど先程の状態が堪えた――あるいは、他人に見られることを想定していない。まあ、それもそうだろう。
「……あー、あ、そう……うん、元気……いや、元気ではねえ」
「で、どうしてあんなにぐだってたわけ?」
元気ではない、ということを明かせるくらいには、こちらには“先生”といたという信用があるのだろう。そっと傍らに寄っていく。
「……スズヒコと、ちょっとな」
「……先生と?」
遊んでいる時間は終わりになった。こちらとしても、情報を聞き出さなければならなかった。
逡巡する様子が見られたが、何もせずとも素直に口を開いてくれる。
「……あの人は、ここに来て少し……いや、大分取り乱してる……それを自分で気付いてないのか、認めたくないのかわかんねえけど、全く直そうとしない。俺は、あれがスズヒコだとは認めたくなかったし、だからこそ目を覚まして欲しくて、色々やろうとした。結果として、ろくな事は出来ずに、お互いがバカみたいに傷ついた」
「……ふうん」
分析。それは恐らく、極限環境下の限界。
分析。それは恐らく、譲れないが故の拒絶。
分析。それは恐らく、とっくに考慮されている。
「俺は、そんな自分に嫌気がさして、あとはご覧の通り――結局、俺はこうして生き続けて……自分でケジメをつける以外はねえって、ようやくわかったけどな」
フェデルタはひとしきりいい終えると、横目でパライバを見る。果たして話してよかったのか、と思わなくはないが、吐き出せた事で少しスッキリしたのも事実だ。
パライバの方が何を考えているかは、その態度や表情――そもそも表情が無いのだが――から読み取る事は出来そうもない。
「先生はね、何でも下準備する人。先のことを考えて、用意しなくていいものまで用意する人。それにはもちろん、自分の死に方も含まれてた」
「……」
それは過去の記録。
忌々しくもなければ、後悔もしていない、ただの事実。咲良乃スズヒコが死ぬ直前、助けようとして火の手の中に飛び込んだ時の記録。――そして、拒否され、別の命令を与えられたときの記録。
「だから、ぼくは先生がなんもしてないわけがないって思うんだよね」
「……準備」
「うん。ポケットとかひっくり返してみたら?」
結果的にそれはより良い結果を生んだ。あれがなければこのような事象はまず間違いなく発生していなかっただろうし、奇跡は奇跡を引き寄せる。
だから、あの人はその時考えられうる最善を常に取ろうとしているはずなのだ。
「じゃ、ぼくそろそろ行くね」
「……ちょっと待て」
「……なに?」
目的はあくまでスズヒコ――先生。それはずっと言われていた。近くにいるものはどうにかしてやる必要はない、恐らく関係があって関わろうとしてくるのはお前の知っている一人だけだ、と。それも大日向は分かっていた。
彼女が一体何なのか、ともすれば彼女のことを何か話す必要があるのか――それについては、本人が“好きにしろ”と言い切っている。
生き物の使い方をよく分かっている人間のやることだ。
「もし、もし万が一お前が――いや、お前をここに寄越した何かが、スズヒコに何かしようと思ってんなら――俺がどうするか、わかるよな?」
風が吹き付けてくる。砂塵と共に火の粉が舞い、その向こうから見える瞳は炎の色。ようやくそう思ったのか、それとも始めから燃えていたのか、それは別にどうでもいい。
持っていけと渡された水の力を握りしめ、高らかに宣言した。
「わかるとも。だから敢えて言うね、“そんな状況でボクたちに勝てると思わないことだ”」
ぼくらが対立するかは、大日向でもまだ分からないという。
であれば、ぼくは今課せられていることを粛々とこなし、それに楯突いてくるようであれば、歯向かうしかない。歯向かうと言っても本当に付け焼き刃のことしかできないというのに、無茶を言ってくれるものだ、と思った。
数値計算用のサーバーがひっきりなしに動いている。
バグ技で彼の世界に送り込まれたパライバトルマリンからの情報は、彼がそれなりの安息の地に辿り着かなければ、再び送信されることはない。要するに、今できることは、あまり多くなかった。
「……そういえば、【哀歌の行進】はともかく、残りのふたつ……」
「【望遠水槽の終点】は彼の世界だ。それは割り出した……いや、関係があるからこそそちらにいる。分からないのは【透翅流星飛行】だ」
三つだ。そのうちひとつは【哀歌の行進】。大日向研が総出でかからなくてはならないもの。そのうちのひとつ、【望遠水槽の終点】は我々の敵にはならないだろうと、大日向は言い切った。
「何か関係があるものがいるはずなんですよね」
「そのはずだ。【望遠水槽の終点】については、今はパライバトルマリンを頼りにする以外にない」
ひとつだけ、まるでイレギュラーのように存在している。
どこからやってきたのかわからない、何とも関連が見られない、イレギュラー存在。研究室の人員を漁ってもなお、まだわからないもの。まだ時間は存在していると言っても、嫌なものは嫌だった。無知な時間が存在しているということが嫌なのだ。痕跡のひとつくらいをもぎ取り、そこから追い立てる時間が欲しい。
「……マジで今更なこと聞いてもいいっすか?センセー」
「いいぞ紀野。ボクはまだ比較的気分がいい」
「はーい。そもそも、自分たちが追っかけてる怪異みたいなのってなんなんスか?」
「ほんとに今更なことが出てきましたね」
「まあ一年生ですから……」
眼鏡の鼻当てを中指で押し、大日向は椅子ごと振り向く。純粋な質問は時に突破口になるのを知っていた。
「そう茶化すな。初心に戻るのは良いことだ……簡単に言えば“ヒトではないもの”だ」
「人魚とか夢喰いとか、そういうのっスよね」
「よろしい。授業の成果があるようだな」
神秘研究科怪異対策類、という名前には意味がある。
まず“ヒトではないもの”は全て『神秘』として扱われるのだ。その中で、様々な頂点に立っているヒトを脅かすようなものがあれば、それを『怪異』として取り扱う。神秘の中に怪異は包含され、神秘研究科には純粋に神秘そのものを研究する類も存在している。
「ボクたちの仕事は要するに狩りだ。神秘の力を適切に扱えぬものも対象となり、あらゆるヒトの害を叩きのめし、狩る。必要があれば殺す。まあ……最低限力を削ぐことができれば数十年安泰という例も――」
「――すいません。ちょっと電話に出ます」
西村がスマートフォンを取り出した。着信を受け、そのまま流れるようにスピーカーモードに切り替え、床に固いものが落ちる音。

『……お前は違ったか。【右手の幸運】はどこにいる?』
『お答えしかねます……!』
息を呑む音。それより早く、大日向が人差し指を立てて口に当てていた。



ENo.426 アストロイェライ とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.5 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












命術LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
アカイホノオ?(1305) により ItemNo.4 鉄板 から防具『ペルガモンカバー』を作製してもらいました!
⇒ ペルガモンカバー/防具:強さ160/[効果1]防御15 [効果2]- [効果3]-
ItemNo.20 不思議な食材 から料理『ひんやりフルーツアイス』をつくりました!
⇒ ひんやりフルーツアイス/料理:強さ45/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.20 ローズクォーツ に ItemNo.21 赤い薔薇 を付加しました!
ItemNo.4 ペルガモンカバー に ItemNo.21 鉄板 を付加しました!
⇒ ペルガモンカバー/防具:強さ160/[効果1]防御15 [効果2]防御15 [効果3]-
闇(273) とカードを交換しました!
弧 (ファルクス)
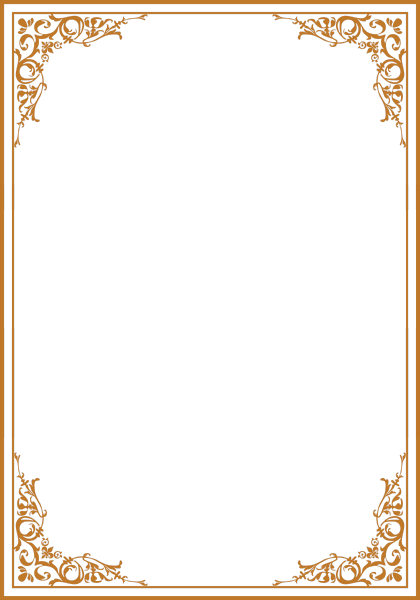
フィアスファング を研究しました!(深度0⇒1)
フィアスファング を研究しました!(深度1⇒2)
フィアスファング を研究しました!(深度2⇒3)
アイシクルランス を習得!
サルベイション を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ポプラ を入手!
スズヒコ(244) は ポプラ を入手!
グノウ(909) は 竹 を入手!
迦楼羅(931) は 竹 を入手!
スズヒコ(244) は 羽 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
迦楼羅(931) は 皮 を入手!
グノウ(909) は 羽 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 皮 を入手!
グノウ(909) は ビーフ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに フェアリー がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに カメレオン が空を見上げなから近づいてきます。



グノウ(909) がパーティから離脱しました!
迦楼羅(931) がパーティから離脱しました!
ヒノデ区 O-2(森林)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 N-2(森林)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 O-2(森林)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 P-2(森林)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 Q-2(草原)に移動!(体調18⇒17)
MISSION!!
ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション が発生!
- フェデルタ(165) が経由した ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション
- スズヒコ(244) が経由した ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション





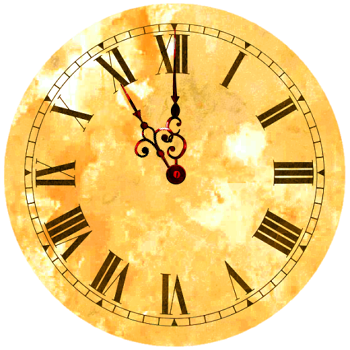
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
チャットが閉じられる――















その施設のほとんどは朽ち果てているようだ。
がさっ・・・・・
物陰から、何かが這い出てきた。


腐敗した者たちが、静かに迫ってくる・・・







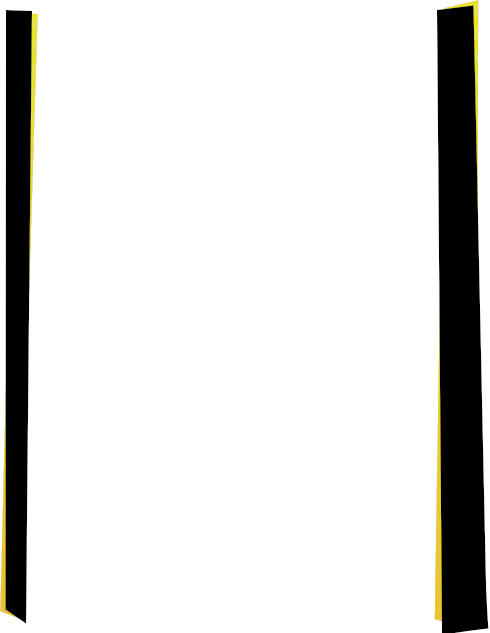
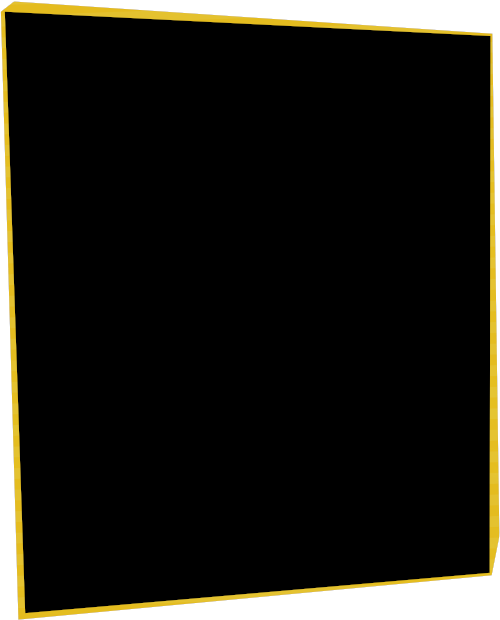





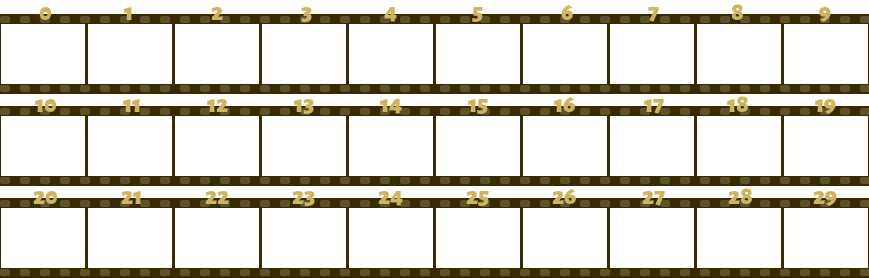









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




天を仰いでいる姿があった。赤いコートはいつかと変わらず、相変わらず独特のにおいがする。燃えるにおいと、不快なにおいだ。不快なにおいの出元が『タバコ』という嗜好品からするのも知っていた。
追跡するのは簡単なことだった。力の残渣を追う、たったそれだけでよかった。このハザマという空間では、僅かな力であっても増幅される――そう聞いていた説明は正しかった。
人の少ない方向に向かっているのは、恐らく作戦の一つだろう。研究者はそうするからだ。先駆者のいる分野に立ち入っても意味がないことを知っている。その傘の下に入らない限りは。
その男――フェデルタ・アートルムは、パライバトルマリンも知っていた。先生が懇意にしていた人。それが友情なのか、愛情なのか、それとも別のものなのか、パライバにはあまり分からない。けれども、そうである、という事実のほうが重要だった。
そうであるのなら、接触することでアドバンテージが生まれるのだ。ステルス状態で見上げた顔は、あまりにも辛気臭い。
しばらく観察を続けていた。何本か目のタバコに火をつけ、ふと零すように言った言葉に、返事を返さないという選択肢はなかった。これは確実にチャンスだと思ったのだ。自分の主は今、咲良乃スズヒコではない。利用できるものは全てを利用する、大日向深知という女だ。
「……どの面下げりゃいいんだろうな」
「ほんとだよ。まーそのツラしかないと思うんだけど……」
「!!」
独り言に唐突に返事が来たのだから、それは当たり前の反応だった。吐き捨てられたタバコが狭間の大地でぶすぶすと燃え尽き、代わりに声をかけられた男の警戒心に火が点いている。
少しフランクにしすぎたか、とか、それもどうでもいい。分析するに、咲良乃スズヒコの名前を出すだけでどうにかできそうだったからだ。飼われていた実績がある。
「……誰だ」
「やっほー。ぼくだよ。覚えてる?」
ステルスを解く。ついさっきまでフェデルタが寄りかかっていた瓦礫の影から這い出て、“あのとき”とは毛の色が違うことに気づいた。こればかりは飼い主依存なので仕方ない。
「……覚えてる?」
問いかけた。その方が手っ取り早いと判断した。警戒されている気配を感じながら、どう言ったものか思慮する。覚えてる?と問いかけたからには、その外堀を埋めていくほうがいい。
今の飼い主と、かつての飼い主の思考回路は、比較的似通っている。故に、パライバは考えるのが楽だった。同じことをすればいい。覚えていることの大半が通用する。
「あそこだよほら、本の世界!おじさんもいたでしょ?」
「……、あ、」
具体的な名前まで必要かと思ってライブラリーを漁っていたが、それも不要そうだった。であれば、もう少しで納得してもらえるはずだ。思い出すのを待つ。
「……お前、たしか……なんだっけ、パラ、なんとか」
「ウワッ記憶ガバガバじゃん。パライバだよ!パライバトルマリン!」
「ああ、ああ、そうだ、パライバ」
覚えてくれている、ということを確認したら、そのとき名前を出せばいい。そう言っていたのは大日向も、“先生”も一緒だった。
見つめる先の男――フェデルタのことは、よく聞いていたはずだ。けれど、それはもうほとんどが抜け落ちている。持ち主が変わったとき、残っている力を残すか、それともきれいに洗うか、それは新しい持ち主に全てが託される。パライバトルマリンを捕まえたユッカ・ハリカリという男は、力は抜き出すだけ抜き出して、きれいに洗いはしなかった。その方が有用かもしれないから、どうするかは次の持ち主――大日向深知に一任すると。
結果として、存在と、“先生にとって大事な人であること”ということだけ、覚えている。
「……なんでここに――あ、」
忘れているのなら、疑問は当たり前だろう。“ぼく”をきちんと認識している人は、基本的にそのときの飼い主に限られる。そうでなければ、ゆっくりと記憶から欠けていく。人間の記憶は欠けるもの。それに乗じて神の御使いもまた、存在を消す。
忘れることは、必然だ。そして、忘れていたものを呼び起こすこともまた、同様に。この触角は、そういうことに長けていた。
「……色々思い出せた?」
「ああ」
素直に相対する。あとは、面白おかしく話をしてやるだけだった。
「あーよかった! いや、だって、さっきまであんなよぼよぼふらふらで、ぴえんぴえんしてる感じだったからさあ。お話になるのかなって心配したよね、元気になってよかったよかった!」
「おま、え……いつから?」
「えー……ここにきてから二、三時間くらい?」
正確に数えてはいない。そんな機能は備えられていない。けれども、人々の行動でおおよその予測は立っていた。
フェデルタは片手で顔を覆っている。よっぽど先程の状態が堪えた――あるいは、他人に見られることを想定していない。まあ、それもそうだろう。
「……あー、あ、そう……うん、元気……いや、元気ではねえ」
「で、どうしてあんなにぐだってたわけ?」
元気ではない、ということを明かせるくらいには、こちらには“先生”といたという信用があるのだろう。そっと傍らに寄っていく。
「……スズヒコと、ちょっとな」
「……先生と?」
遊んでいる時間は終わりになった。こちらとしても、情報を聞き出さなければならなかった。
逡巡する様子が見られたが、何もせずとも素直に口を開いてくれる。
「……あの人は、ここに来て少し……いや、大分取り乱してる……それを自分で気付いてないのか、認めたくないのかわかんねえけど、全く直そうとしない。俺は、あれがスズヒコだとは認めたくなかったし、だからこそ目を覚まして欲しくて、色々やろうとした。結果として、ろくな事は出来ずに、お互いがバカみたいに傷ついた」
「……ふうん」
分析。それは恐らく、極限環境下の限界。
分析。それは恐らく、譲れないが故の拒絶。
分析。それは恐らく、とっくに考慮されている。
「俺は、そんな自分に嫌気がさして、あとはご覧の通り――結局、俺はこうして生き続けて……自分でケジメをつける以外はねえって、ようやくわかったけどな」
フェデルタはひとしきりいい終えると、横目でパライバを見る。果たして話してよかったのか、と思わなくはないが、吐き出せた事で少しスッキリしたのも事実だ。
パライバの方が何を考えているかは、その態度や表情――そもそも表情が無いのだが――から読み取る事は出来そうもない。
「先生はね、何でも下準備する人。先のことを考えて、用意しなくていいものまで用意する人。それにはもちろん、自分の死に方も含まれてた」
「……」
それは過去の記録。
忌々しくもなければ、後悔もしていない、ただの事実。咲良乃スズヒコが死ぬ直前、助けようとして火の手の中に飛び込んだ時の記録。――そして、拒否され、別の命令を与えられたときの記録。
「だから、ぼくは先生がなんもしてないわけがないって思うんだよね」
「……準備」
「うん。ポケットとかひっくり返してみたら?」
結果的にそれはより良い結果を生んだ。あれがなければこのような事象はまず間違いなく発生していなかっただろうし、奇跡は奇跡を引き寄せる。
だから、あの人はその時考えられうる最善を常に取ろうとしているはずなのだ。
「じゃ、ぼくそろそろ行くね」
「……ちょっと待て」
「……なに?」
目的はあくまでスズヒコ――先生。それはずっと言われていた。近くにいるものはどうにかしてやる必要はない、恐らく関係があって関わろうとしてくるのはお前の知っている一人だけだ、と。それも大日向は分かっていた。
彼女が一体何なのか、ともすれば彼女のことを何か話す必要があるのか――それについては、本人が“好きにしろ”と言い切っている。
生き物の使い方をよく分かっている人間のやることだ。
「もし、もし万が一お前が――いや、お前をここに寄越した何かが、スズヒコに何かしようと思ってんなら――俺がどうするか、わかるよな?」
風が吹き付けてくる。砂塵と共に火の粉が舞い、その向こうから見える瞳は炎の色。ようやくそう思ったのか、それとも始めから燃えていたのか、それは別にどうでもいい。
持っていけと渡された水の力を握りしめ、高らかに宣言した。
「わかるとも。だから敢えて言うね、“そんな状況でボクたちに勝てると思わないことだ”」
ぼくらが対立するかは、大日向でもまだ分からないという。
であれば、ぼくは今課せられていることを粛々とこなし、それに楯突いてくるようであれば、歯向かうしかない。歯向かうと言っても本当に付け焼き刃のことしかできないというのに、無茶を言ってくれるものだ、と思った。
数値計算用のサーバーがひっきりなしに動いている。
バグ技で彼の世界に送り込まれたパライバトルマリンからの情報は、彼がそれなりの安息の地に辿り着かなければ、再び送信されることはない。要するに、今できることは、あまり多くなかった。
「……そういえば、【哀歌の行進】はともかく、残りのふたつ……」
「【望遠水槽の終点】は彼の世界だ。それは割り出した……いや、関係があるからこそそちらにいる。分からないのは【透翅流星飛行】だ」
三つだ。そのうちひとつは【哀歌の行進】。大日向研が総出でかからなくてはならないもの。そのうちのひとつ、【望遠水槽の終点】は我々の敵にはならないだろうと、大日向は言い切った。
「何か関係があるものがいるはずなんですよね」
「そのはずだ。【望遠水槽の終点】については、今はパライバトルマリンを頼りにする以外にない」
ひとつだけ、まるでイレギュラーのように存在している。
どこからやってきたのかわからない、何とも関連が見られない、イレギュラー存在。研究室の人員を漁ってもなお、まだわからないもの。まだ時間は存在していると言っても、嫌なものは嫌だった。無知な時間が存在しているということが嫌なのだ。痕跡のひとつくらいをもぎ取り、そこから追い立てる時間が欲しい。
「……マジで今更なこと聞いてもいいっすか?センセー」
「いいぞ紀野。ボクはまだ比較的気分がいい」
「はーい。そもそも、自分たちが追っかけてる怪異みたいなのってなんなんスか?」
「ほんとに今更なことが出てきましたね」
「まあ一年生ですから……」
眼鏡の鼻当てを中指で押し、大日向は椅子ごと振り向く。純粋な質問は時に突破口になるのを知っていた。
「そう茶化すな。初心に戻るのは良いことだ……簡単に言えば“ヒトではないもの”だ」
「人魚とか夢喰いとか、そういうのっスよね」
「よろしい。授業の成果があるようだな」
神秘研究科怪異対策類、という名前には意味がある。
まず“ヒトではないもの”は全て『神秘』として扱われるのだ。その中で、様々な頂点に立っているヒトを脅かすようなものがあれば、それを『怪異』として取り扱う。神秘の中に怪異は包含され、神秘研究科には純粋に神秘そのものを研究する類も存在している。
「ボクたちの仕事は要するに狩りだ。神秘の力を適切に扱えぬものも対象となり、あらゆるヒトの害を叩きのめし、狩る。必要があれば殺す。まあ……最低限力を削ぐことができれば数十年安泰という例も――」
「――すいません。ちょっと電話に出ます」
西村がスマートフォンを取り出した。着信を受け、そのまま流れるようにスピーカーモードに切り替え、床に固いものが落ちる音。

『……お前は違ったか。【右手の幸運】はどこにいる?』
『お答えしかねます……!』
息を呑む音。それより早く、大日向が人差し指を立てて口に当てていた。



ENo.426 アストロイェライ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.5 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





たのしいおともだち
|
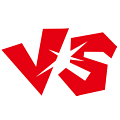 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 9 増加!
影響力が 9 増加!



命術LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
アカイホノオ?(1305) により ItemNo.4 鉄板 から防具『ペルガモンカバー』を作製してもらいました!
⇒ ペルガモンカバー/防具:強さ160/[効果1]防御15 [効果2]- [効果3]-
 |
燃流 「この辺りは人が少ないからな…ッ! 皆で助け合いの精神でいこうッ!! えっと、防具が欲しいんだったねッ!ちょっと待っててくれッ!」 |
ItemNo.20 不思議な食材 から料理『ひんやりフルーツアイス』をつくりました!
⇒ ひんやりフルーツアイス/料理:強さ45/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10
フェデルタ(165) の持つ ItemNo.20 ローズクォーツ に ItemNo.21 赤い薔薇 を付加しました!
ItemNo.4 ペルガモンカバー に ItemNo.21 鉄板 を付加しました!
⇒ ペルガモンカバー/防具:強さ160/[効果1]防御15 [効果2]防御15 [効果3]-
闇(273) とカードを交換しました!
弧 (ファルクス)
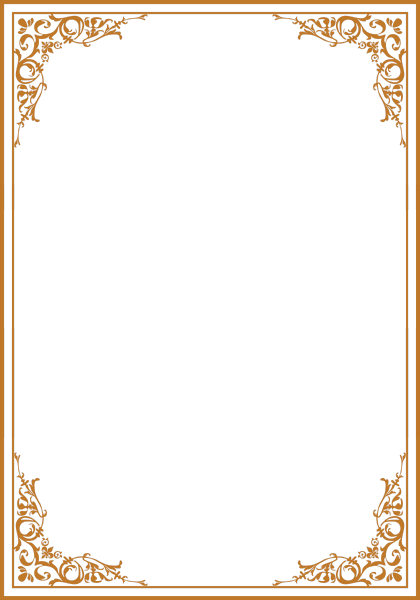
フィアスファング を研究しました!(深度0⇒1)
フィアスファング を研究しました!(深度1⇒2)
フィアスファング を研究しました!(深度2⇒3)
アイシクルランス を習得!
サルベイション を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ポプラ を入手!
スズヒコ(244) は ポプラ を入手!
グノウ(909) は 竹 を入手!
迦楼羅(931) は 竹 を入手!
スズヒコ(244) は 羽 を入手!
スズヒコ(244) は ビーフ を入手!
迦楼羅(931) は 皮 を入手!
グノウ(909) は 羽 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 皮 を入手!
グノウ(909) は ビーフ を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに フェアリー がゆっくりと近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに カメレオン が空を見上げなから近づいてきます。



グノウ(909) がパーティから離脱しました!
迦楼羅(931) がパーティから離脱しました!
ヒノデ区 O-2(森林)に移動!(体調22⇒21)
ヒノデ区 N-2(森林)に移動!(体調21⇒20)
ヒノデ区 O-2(森林)に移動!(体調20⇒19)
ヒノデ区 P-2(森林)に移動!(体調19⇒18)
ヒノデ区 Q-2(草原)に移動!(体調18⇒17)
MISSION!!
ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション が発生!
- フェデルタ(165) が経由した ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション
- スズヒコ(244) が経由した ヒノデ区 M-2:ヒノデコーポレーション





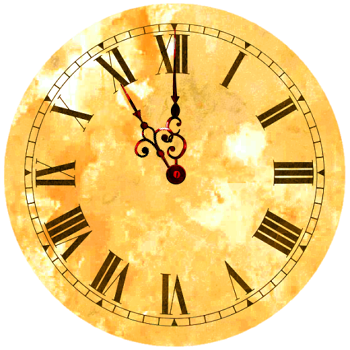
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
白南海 「・・・・・おや、どうしました?まだ恐怖心が拭えねぇんすか?」 |
 |
エディアン 「・・・何を澄ました顔で。窓に勧誘したの、貴方ですよね。」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!! 俺これ嫌っすよぉぉ!!最初は世界を救うカッケー役割とか思ってたっすけどッ!!」 |
 |
エディアン 「わかわかわかわか・・・・・何を今更なっさけない。 そんなにワカが恋しいんです?そんなに頼もしいんです?」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
 |
白南海 「それはもう!若はとんでもねぇ器の持ち主でねぇッ!!」 |
 |
エディアン 「突然元気になった・・・・・」 |
 |
白南海 「俺が頼んだラーメンに若は、若のチャーシューメンのチャーシューを1枚分けてくれたんすよッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・。・・・・他には?」 |
 |
白南海 「俺が501円のを1000円で買おうとしたとき、そっと1円足してくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・あとは?」 |
 |
白南海 「俺が車道側歩いてたら、そっと車道側と代わってくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・うーん。他の、あります?」 |
 |
白南海 「俺がアイスをシングルかダブルかで悩ん――」 |
 |
エディアン 「――あー、もういいです。いいでーす。」 |
 |
白南海 「・・・お分かりいただけましたか?若の素晴らしさ。」 |
 |
エディアン 「えぇぇーとってもーーー。」 |
 |
白南海 「いやー若の話をすると気分が良くなりますァ!」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「・・・あーうるさい。帰りますよ?帰りますからねー。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。







ヒノデ区 M-2 周辺
ヒノデコーポレーション
数々の巨大施設が立ち並ぶ、ヒノデコーポレーション構内。ヒノデコーポレーション
その施設のほとんどは朽ち果てているようだ。
がさっ・・・・・
物陰から、何かが這い出てきた。

ゾンビ
身を崩しながらも歩き回る、腐敗した何か。

ゾンビリーダー
リーダーの風格あふれる、腐敗した何か。
 |
ゾンビリーダー 「・・・・・・・・・」 |
腐敗した者たちが、静かに迫ってくる・・・





ENo.244
鈴のなる夢

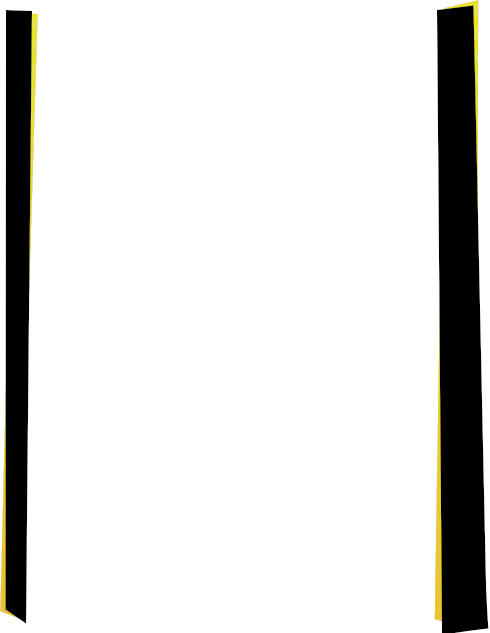
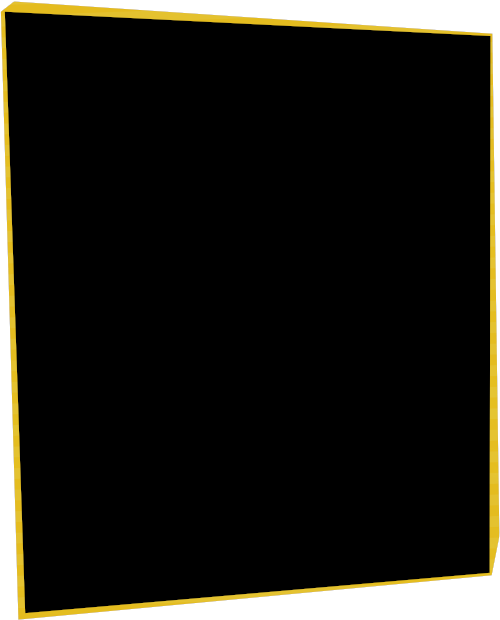
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
17 / 30
602 PS
ヒノデ区
Q-2
Q-2







痛撃友の会
6
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
4
アイコン60pxの会
2
#片道切符チャット
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
4
長文大好きクラブ
自我とか意思とかある異能の交流会
4
カード報告会
8
とりあえず肉食う?
6



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | - | - | 【射程3】 |
| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |
| 5 | ポプラ | 素材 | 25 | [武器]追風15(LV35)[防具]耐災25(LV35)[装飾]風纏25(LV40) | |||
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | タイヤ片 | 素材 | 20 | [武器]増幅15(LV35)[防具]反撃15(LV30)[装飾]気合15(LV35) | |||
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | - | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | ひんやりフルーツアイス | 料理 | 45 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 21 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 22 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 35 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 35 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 8 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アンダークーリング | 6 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| 練3 | プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 10 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 6 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 | |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| グレイシア | 6 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 6 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 | |
| 治癒領域 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
|
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 | |
| 練3 |
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
|
弧 (ファルクス) |
0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]プチメテオカード |
| [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]レーヴァテイン |
| [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]イディオータ |
| [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]フレイムインパクト |

PL / 紙箱みど