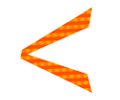<< 8:00~9:00




許せなかった。何もかも許せなかった。自分も、彼も、誰もかも許せなかった。
俺はどうやったって獣以下の何かでしかないのか?それ以下の何かで、それ未満の何かで、ではどうすればいいのか?わからない。わからない。どうして俺は、どうしてあんなことしかできなかったのか、どうして、ここには後悔しかないのか。

例えば心の在処がどこかにあるとして、それはどこになるのか。心の比喩表現として、胸を押さえたり、手を当てたりすることはよくあることだ。
答えは簡単かもしれない。少なくとも胸部にはそんなものはない。ヒトの心の在処を定めるのなら、それは脳だ。思考し、行動指針を定めるのは脳の役目だ。故に心があるとするのなら脳で、心を精神だとするなら、神経系がその一端を担っているということになる。
ヒトの神経は集中神経系であり、そして記憶の集積もまた脳がその役目を担っている。これはあくまでもただの人間の話で、そうではない自分はどうなるのだろう。この頭蓋の中には何が詰まっていて、何があの発言と、動作を齎したのだろう。それについてずっと考えていた。
そもそも俺は本で、本は記述こそあれど思考しない。俺を、俺として思考させているものは、一体何なのだろう。理論上俺に脳はなく、であれば何も言わない獣以下の存在になっているはずだ。けれども、そうではなく、今までもずっとそうではなかった。
俺は何を基準にして、そうではないことを知っているのだろう。俺がヒトだったという確信は、一体どこからやってきているのだろう。
俺はその答えを、きちんと把握している。
俺の表紙を開くと、そこに封筒が貼ってある。その中身が、俺が最後に、まだヒトとして定義されていたころに、印刷されたものだ。俺はそれを識っているのに、それを開ける勇気がないままでいる。なのに、ずっと確信だけは抱いている。不思議なものだと思う。俺の記録は確かにそのように告げてくる。けれど、俺の記憶はそれを拒絶しようとしている。
どうして拒絶しようとしているのかすら分からない。それが罪を重ねた末路だというのなら、甘んじて受け入れる。けれども、分からないのだ。そして、理解するためには己を開かなければならないことすら分かっていて、なお恐れていた。
何を恐れているのだろう。今更恐れるようなことなんて、どこにもありやしないはずなのに。それとも、俺が俺でなくなるということを恐れでもしているのだろうか。俺は、絶対的に、外部記述によって定められている。
だから今まで戦えてきて、だから今まで引き下がることもなく、だから今まで、後ろを振り向かなかった。
――後ろを振り向くことが怖い。
それに気づいてしまったとき、俺はすべてが終わるかと思った。後ろに俺の歩いてきた道は残っているのだろうか。意味は存在しているのだろうか。冷や汗ばかりが顔を伝った。必要のない機能だけ残しやがって、と思った。きっと体温が存在していたら、それどころではなくなっていた。俺に最後まで与えられることがなかったのは熱で、だからこそ冷静でいられるものだと思っていた。そんなことはない、そんなわけはない。今俺を焦らせているのは、もっともっと別のなにかだ。
回顧。追憶。追想。回想。自分の“ひとではない”部分に手を伸ばそうとするたび、手が止まる。そんなことではいけないと分かっていても。
俺はヒトだったもので、今はヒトではない。ヒトを模倣しているだけの怪物で、だからこそヒトのような挙動をするのかもしれない。だから俺の心らしきものは脳に存在していて、恐れる。後悔する。許せなくなる。そうであれば納得はできたし、それが正しいという直感もまたあった。一度足を止めて、顧みなければならないときが来ている。
けれど、後ろを振り向く前にやらなければいけないことがあった。きっと先にそれを済ませてしまわないと、先延ばしにしてしまうと、自分で嫌というほど知っていた。

グノウ・スワロルドという男は、一言で言えばスキのない男だった。ただの従者?そんなわけがない。ただの主従?そんなわけもない。
ただ幸いにして、あの男が主と仰ぐ者がいることだけは、よかったと思う。理由は簡単だ。主の方を人質に取ってしまえば御しやすい。それだけのことだ。
――あくまでそれは最終手段として置いておくとして、グノウ・スワロルドという男には、不可解な点がいくつかあった。ひとつ、イバラシティの土着の人間ではなさそうだと言うこと。それはもうどこででも有り得る話で、別段不可解でもなくなりつつあった。ひとつ。“嗅ぎ慣れたにおいがする”こと。どこで嗅いだものだったろう。けれどそれは、間違いなく同じ世界のにおいで、そしてここではなかった。記録を辿る必要があるだろうか。――できれば開きたくない。
それ以上に、そのにおいは、“腐っている”。良くもならなければあとは悪くなる一方で、どうやっても破滅が待っている。むしろ今まで、どうして開いた傷口で生きていくことができていたのか。そればかりが気になっている。閉じない傷口に起こることがどんなことかくらい、医学を専門にしていなくても知っていた。ずっと負担になり続ける。死んだ細胞が腐り、新たな腐敗を生む。この表記は厳密ではないかもしれないが、とにかく死んだ細胞が溶け出てくることは経験しているはずだ。そんなにおいがした。
「……グノウさん。少しばかりいいですか?」
薄ら笑い。取り繕った笑み。表面だけの付き合い。それらには慣れていた。生前から染み付いていた。どこまで行っても切り離せないということに辟易していたが、使えるものは使うしかなかった。
この男に向かって使うたび、気が気でない。ずっと取り繕っていられるわけでもない。それはきっと、この男のほうが上手だ。
「……何でしょうか」
「端的に言えば、謝罪です」
一日とちょっとだ。それだけで、信用できるような関係にはなりえない。それは確信していた。彼以前に、自分がそうだったからだ。だからこそ、今できることをする。――形ばかりの謝罪。そして開示。それが最善だと、今は言うしかなかった。ベースキャンプに戻らなければ自分たちで何もかもを賄うしかない旅路を、わざわざ人の少ない方に向かって歩いている。
「こちらの都合で……、二人きりにしてしまい、申し訳ない」
「……」
思っていたよりずっと、大人数で歩いている“相手”は少ないらしい。しばらくどころか、一度だけ当てられて、それっきりが続いている。
自分たちが“喧嘩”をしている間に、彼らは目をつけられて、そして襲われた。知っていた襲うものと違って、彼らは何も奪っていかなかったらしい。それはそれでという気持ち。何もなければよかったのではないかという気持ち。それに対抗するように沸いてくる申し訳なさは、どこから来るのか。
「今後、このようなことがないようにお願いします」
冷ややかな視線が浴びせられている。前髪越しでもよく分かった。あれはこちらを信用していない目だ。子供の方から攻めようとして、かなり無理を感じているくらいには――思っている。この二人は純然たるヒトで、その片方を何かが蝕んでいる。
覚えがあるような、ないような、そんな力だった。それはどうしてか、この人間に深く穴を開けている。――血の臭い。嗅ぎつければ盛ろうとするだろう獣は置いてきた。
「……謝罪だけだと、納得いただけないでしょうから。……俺たちのことを、話します。何も包み隠すことなく、今言えるかぎりを」
懐に手を入れる。固い背表紙に指先が当たるまで一秒、それを引きずり出すのにもう数秒。
とても懐から出てくると思えない大きい本に、グノウの眉根がかすかに動く。
「……これは?」
「俺の“本体”です」
手袋を外したのが見える。抵抗する理由は今のところない。
失態の埋め合わせは実利である必要がある。何も生み出せないものに、居場所はない。なかった。だからこうして見せている。
「心臓のようなものですか?あるいは、もっと別の?」
「心臓……とは言い難いですが、限りなく近いものではあります。外付けの脳、それがもっとも正確かもしれません」
触れた手から、邪悪を感じた。邪悪としか呼びようのない何かがいる。思わず視線を向けた。――腹部。人間の柔らかな部分。臓腑を包んでいる部分。
触れられる感触があった。力で干渉される感覚があった。それも一瞬だった。それもそうだ、この本は……、……この本は、何?
疑問は遙か後に置いていかれる。
「俺たちは死人です。広義のアンデッドで、まかり間違えて死を超越してしまった」
「アンデッド……生の理から、外れたのですね」
「理どころではなく。円環から外れてしまった……命は巡るもの。そこで足を止め続けてしまったどころか――」
もう何人殺したか覚えていません、という。事実だ。
罪人の世界なのだからそれくらい許されると思っていた、という。事実だ。
それは本当だったのだろうか。いたずらに罪を重ね、己を縛り付けている要因を作っていただけなのではないか?
「けど、それを終わらせる。……それが、俺の行動理念で、それはあなたたちの行動理念とぶつかることはないはずです」
そう。終わらせるために来た。終わらせるためにやってきた。
終わらせるために。終わらせるためだけに旅をしている。それは何に対してだろうか。思い出せない。何か大切なことを思い出せない。
「俺たちは、何としてでもあのアンジニティという世界を出なければならない。」
「……死人がアンジニティにいることは何の不思議でもなかった。今更疑うことでもないのでは」
「……俺たちは、何としてでも、アンジニティ以外で死ななければならない。」
死ななければならない。それがきっと大切なことだった。
それは正しいと、何も参照しなくても確信が持てた。だからきっと、もっとも大事な部分に刻まれている。自分が自分足り得る部分に深く刻み込んである。
……他人と話しているときは冷静だ。ではどうして、彼にあんなに牙を剥いたのだろう。分からなかった。
「……あなたたちは、何故旅をしていますか?」
ただ、虚空へ向かって指を向けただけに見えただろう。
けれどその先は、腐敗の臭いの元に向いている。指先の示す場所に視線が落ちる。
「俺たちは、終わらせるために旅をしています」
「……事情は分かりました、協力はします」
それは弱点だったのかもしれないし、懸念事項だったのかもしれない。
どちらでもよかった。次の言葉を聞くまでは。
「出来うる限り手を貸しましょう。その代わり貴方たちの手も借ります」
手を貸す、であれば、それは、あまりにも簡単なことだった。続いた言葉は、そうではなかった。
「もし、――」
貼り付けていた微笑みが崩れるような、重く、重く――要石を握らされるような。
けれど、今まで背負ってきたものの数に比べれば、あまりにも軽かったはずなのに、何故だろう。まじまじと見て、ひとつだけ頷いた。
責任を背負うことには慣れていた。責任を背負うのなら他人がいい。責任を放棄するのなら、バケモノの方がもっといい。食い殺してしまえばいいだけだ。
躊躇いはどこからやってくるのだろう。



ENo.151 ガズエット とのやりとり

ENo.548 葵 とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.931 迦楼羅 とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました




フェデルタ(165) から 鉄板 を手渡しされました。
ItemNo.4 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












グノウ(909) に ItemNo.20 触手 を送付しました。
ユキ(424) に ItemNo.9 山査子 を送付しました。
グノウ(909) から 鉄板 を受け取りました。
領域LV を 5 DOWN。(LV25⇒20、+5CP、-5FP)
料理LV を 25 DOWN。(LV60⇒35、+25CP、-25FP)
魔術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
付加LV を 30 UP!(LV0⇒30、-30CP)
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.18 お肉 から料理『揚げたて唐揚げ(塩味)』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.19 お肉 から料理『ビーフ10割肉まん』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.27 夙迎のツバメ に ItemNo.17 腐肉 を付加しました!
ケイ(1357) とカードを交換しました!
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア)
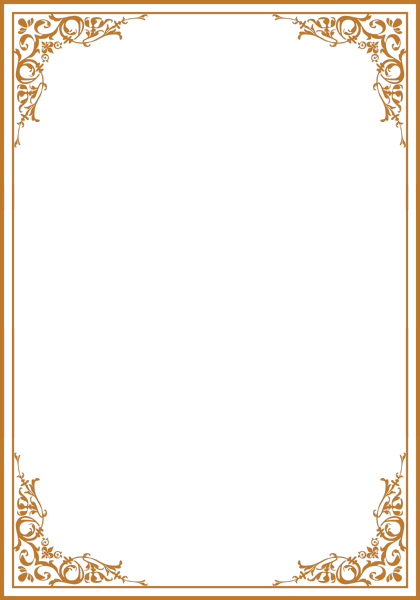
イディオータ を研究しました!(深度0⇒1)
イディオータ を研究しました!(深度1⇒2)
イディオータ を研究しました!(深度2⇒3)
ファイアボルト を習得!
カタラクト を習得!
ヒートイミッター を習得!
クリムゾンスカイ を習得!
上書き付加 を習得!
火の祝福 を習得!
セイクリットファイア を習得!
マナバースト を習得!
大爆発 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ボロ毛布 を入手!
スズヒコ(244) は タイヤ片 を入手!
グノウ(909) は タイヤ片 を入手!
迦楼羅(931) は タイヤ片 を入手!
フェデルタ(165) は 赤い薔薇 を入手!
迦楼羅(931) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 赤い薔薇 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
スズヒコ(244) は 不思議な食材 を入手!
グノウ(909) は 赤い薔薇 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに ホスト が興味津々な様子で近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ネギさん がものすごい勢いで駆け寄ってきます。



ヒノデ区 N-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
ヒノデ区 O-6(草原)に移動!(体調25⇒24)
ヒノデ区 O-5(森林)に移動!(体調24⇒23)
ヒノデ区 O-4(森林)に移動!(体調23⇒22)
ヒノデ区 O-3(森林)に移動!(体調22⇒21)





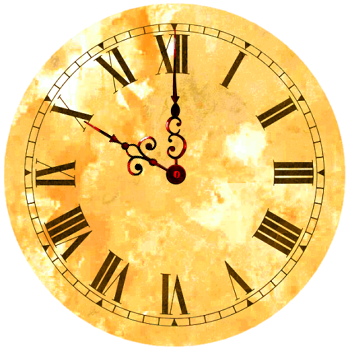
[822 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[375 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[396 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[117 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[185 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。




チャット画面に映る、4人の姿。
少しの間、無音となる。
くんくんと匂いを嗅ぐふたり。
3人の様子を遠目に眺める白南海。
チャットが閉じられる――














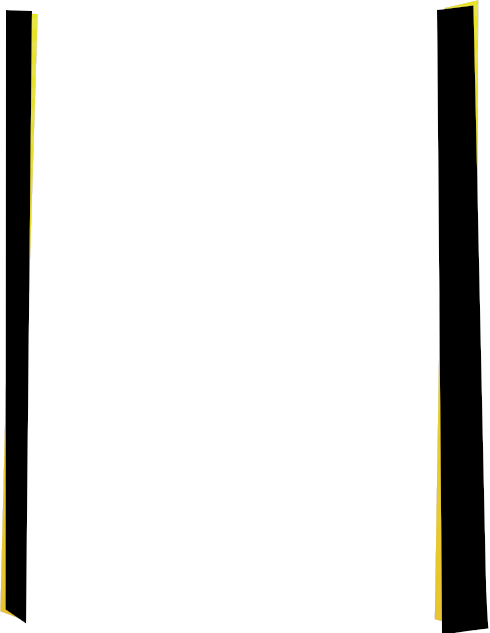
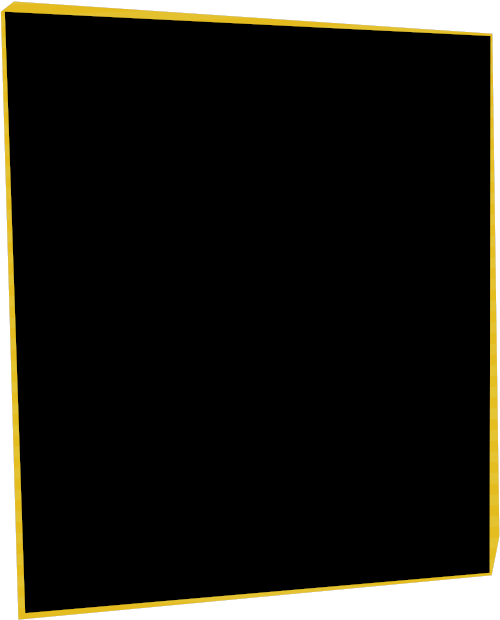





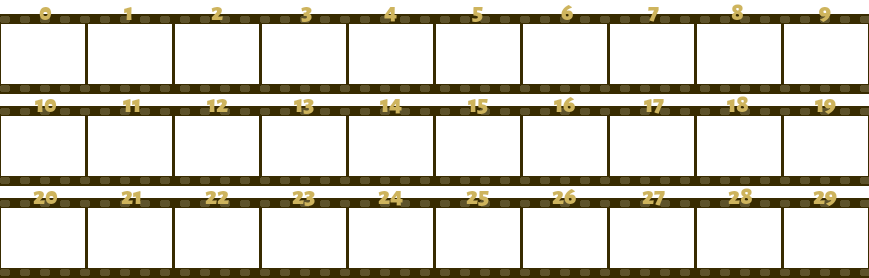









































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



許せなかった。何もかも許せなかった。自分も、彼も、誰もかも許せなかった。
俺はどうやったって獣以下の何かでしかないのか?それ以下の何かで、それ未満の何かで、ではどうすればいいのか?わからない。わからない。どうして俺は、どうしてあんなことしかできなかったのか、どうして、ここには後悔しかないのか。

例えば心の在処がどこかにあるとして、それはどこになるのか。心の比喩表現として、胸を押さえたり、手を当てたりすることはよくあることだ。
答えは簡単かもしれない。少なくとも胸部にはそんなものはない。ヒトの心の在処を定めるのなら、それは脳だ。思考し、行動指針を定めるのは脳の役目だ。故に心があるとするのなら脳で、心を精神だとするなら、神経系がその一端を担っているということになる。
ヒトの神経は集中神経系であり、そして記憶の集積もまた脳がその役目を担っている。これはあくまでもただの人間の話で、そうではない自分はどうなるのだろう。この頭蓋の中には何が詰まっていて、何があの発言と、動作を齎したのだろう。それについてずっと考えていた。
そもそも俺は本で、本は記述こそあれど思考しない。俺を、俺として思考させているものは、一体何なのだろう。理論上俺に脳はなく、であれば何も言わない獣以下の存在になっているはずだ。けれども、そうではなく、今までもずっとそうではなかった。
俺は何を基準にして、そうではないことを知っているのだろう。俺がヒトだったという確信は、一体どこからやってきているのだろう。
俺はその答えを、きちんと把握している。
俺の表紙を開くと、そこに封筒が貼ってある。その中身が、俺が最後に、まだヒトとして定義されていたころに、印刷されたものだ。俺はそれを識っているのに、それを開ける勇気がないままでいる。なのに、ずっと確信だけは抱いている。不思議なものだと思う。俺の記録は確かにそのように告げてくる。けれど、俺の記憶はそれを拒絶しようとしている。
どうして拒絶しようとしているのかすら分からない。それが罪を重ねた末路だというのなら、甘んじて受け入れる。けれども、分からないのだ。そして、理解するためには己を開かなければならないことすら分かっていて、なお恐れていた。
何を恐れているのだろう。今更恐れるようなことなんて、どこにもありやしないはずなのに。それとも、俺が俺でなくなるということを恐れでもしているのだろうか。俺は、絶対的に、外部記述によって定められている。
だから今まで戦えてきて、だから今まで引き下がることもなく、だから今まで、後ろを振り向かなかった。
――後ろを振り向くことが怖い。
それに気づいてしまったとき、俺はすべてが終わるかと思った。後ろに俺の歩いてきた道は残っているのだろうか。意味は存在しているのだろうか。冷や汗ばかりが顔を伝った。必要のない機能だけ残しやがって、と思った。きっと体温が存在していたら、それどころではなくなっていた。俺に最後まで与えられることがなかったのは熱で、だからこそ冷静でいられるものだと思っていた。そんなことはない、そんなわけはない。今俺を焦らせているのは、もっともっと別のなにかだ。
回顧。追憶。追想。回想。自分の“ひとではない”部分に手を伸ばそうとするたび、手が止まる。そんなことではいけないと分かっていても。
俺はヒトだったもので、今はヒトではない。ヒトを模倣しているだけの怪物で、だからこそヒトのような挙動をするのかもしれない。だから俺の心らしきものは脳に存在していて、恐れる。後悔する。許せなくなる。そうであれば納得はできたし、それが正しいという直感もまたあった。一度足を止めて、顧みなければならないときが来ている。
けれど、後ろを振り向く前にやらなければいけないことがあった。きっと先にそれを済ませてしまわないと、先延ばしにしてしまうと、自分で嫌というほど知っていた。

グノウ・スワロルドという男は、一言で言えばスキのない男だった。ただの従者?そんなわけがない。ただの主従?そんなわけもない。
ただ幸いにして、あの男が主と仰ぐ者がいることだけは、よかったと思う。理由は簡単だ。主の方を人質に取ってしまえば御しやすい。それだけのことだ。
――あくまでそれは最終手段として置いておくとして、グノウ・スワロルドという男には、不可解な点がいくつかあった。ひとつ、イバラシティの土着の人間ではなさそうだと言うこと。それはもうどこででも有り得る話で、別段不可解でもなくなりつつあった。ひとつ。“嗅ぎ慣れたにおいがする”こと。どこで嗅いだものだったろう。けれどそれは、間違いなく同じ世界のにおいで、そしてここではなかった。記録を辿る必要があるだろうか。――できれば開きたくない。
それ以上に、そのにおいは、“腐っている”。良くもならなければあとは悪くなる一方で、どうやっても破滅が待っている。むしろ今まで、どうして開いた傷口で生きていくことができていたのか。そればかりが気になっている。閉じない傷口に起こることがどんなことかくらい、医学を専門にしていなくても知っていた。ずっと負担になり続ける。死んだ細胞が腐り、新たな腐敗を生む。この表記は厳密ではないかもしれないが、とにかく死んだ細胞が溶け出てくることは経験しているはずだ。そんなにおいがした。
「……グノウさん。少しばかりいいですか?」
薄ら笑い。取り繕った笑み。表面だけの付き合い。それらには慣れていた。生前から染み付いていた。どこまで行っても切り離せないということに辟易していたが、使えるものは使うしかなかった。
この男に向かって使うたび、気が気でない。ずっと取り繕っていられるわけでもない。それはきっと、この男のほうが上手だ。
「……何でしょうか」
「端的に言えば、謝罪です」
一日とちょっとだ。それだけで、信用できるような関係にはなりえない。それは確信していた。彼以前に、自分がそうだったからだ。だからこそ、今できることをする。――形ばかりの謝罪。そして開示。それが最善だと、今は言うしかなかった。ベースキャンプに戻らなければ自分たちで何もかもを賄うしかない旅路を、わざわざ人の少ない方に向かって歩いている。
「こちらの都合で……、二人きりにしてしまい、申し訳ない」
「……」
思っていたよりずっと、大人数で歩いている“相手”は少ないらしい。しばらくどころか、一度だけ当てられて、それっきりが続いている。
自分たちが“喧嘩”をしている間に、彼らは目をつけられて、そして襲われた。知っていた襲うものと違って、彼らは何も奪っていかなかったらしい。それはそれでという気持ち。何もなければよかったのではないかという気持ち。それに対抗するように沸いてくる申し訳なさは、どこから来るのか。
「今後、このようなことがないようにお願いします」
冷ややかな視線が浴びせられている。前髪越しでもよく分かった。あれはこちらを信用していない目だ。子供の方から攻めようとして、かなり無理を感じているくらいには――思っている。この二人は純然たるヒトで、その片方を何かが蝕んでいる。
覚えがあるような、ないような、そんな力だった。それはどうしてか、この人間に深く穴を開けている。――血の臭い。嗅ぎつければ盛ろうとするだろう獣は置いてきた。
「……謝罪だけだと、納得いただけないでしょうから。……俺たちのことを、話します。何も包み隠すことなく、今言えるかぎりを」
懐に手を入れる。固い背表紙に指先が当たるまで一秒、それを引きずり出すのにもう数秒。
とても懐から出てくると思えない大きい本に、グノウの眉根がかすかに動く。
「……これは?」
「俺の“本体”です」
手袋を外したのが見える。抵抗する理由は今のところない。
失態の埋め合わせは実利である必要がある。何も生み出せないものに、居場所はない。なかった。だからこうして見せている。
「心臓のようなものですか?あるいは、もっと別の?」
「心臓……とは言い難いですが、限りなく近いものではあります。外付けの脳、それがもっとも正確かもしれません」
触れた手から、邪悪を感じた。邪悪としか呼びようのない何かがいる。思わず視線を向けた。――腹部。人間の柔らかな部分。臓腑を包んでいる部分。
触れられる感触があった。力で干渉される感覚があった。それも一瞬だった。それもそうだ、この本は……、……この本は、何?
疑問は遙か後に置いていかれる。
「俺たちは死人です。広義のアンデッドで、まかり間違えて死を超越してしまった」
「アンデッド……生の理から、外れたのですね」
「理どころではなく。円環から外れてしまった……命は巡るもの。そこで足を止め続けてしまったどころか――」
もう何人殺したか覚えていません、という。事実だ。
罪人の世界なのだからそれくらい許されると思っていた、という。事実だ。
それは本当だったのだろうか。いたずらに罪を重ね、己を縛り付けている要因を作っていただけなのではないか?
「けど、それを終わらせる。……それが、俺の行動理念で、それはあなたたちの行動理念とぶつかることはないはずです」
そう。終わらせるために来た。終わらせるためにやってきた。
終わらせるために。終わらせるためだけに旅をしている。それは何に対してだろうか。思い出せない。何か大切なことを思い出せない。
「俺たちは、何としてでもあのアンジニティという世界を出なければならない。」
「……死人がアンジニティにいることは何の不思議でもなかった。今更疑うことでもないのでは」
「……俺たちは、何としてでも、アンジニティ以外で死ななければならない。」
死ななければならない。それがきっと大切なことだった。
それは正しいと、何も参照しなくても確信が持てた。だからきっと、もっとも大事な部分に刻まれている。自分が自分足り得る部分に深く刻み込んである。
……他人と話しているときは冷静だ。ではどうして、彼にあんなに牙を剥いたのだろう。分からなかった。
「……あなたたちは、何故旅をしていますか?」
ただ、虚空へ向かって指を向けただけに見えただろう。
けれどその先は、腐敗の臭いの元に向いている。指先の示す場所に視線が落ちる。
「俺たちは、終わらせるために旅をしています」
「……事情は分かりました、協力はします」
それは弱点だったのかもしれないし、懸念事項だったのかもしれない。
どちらでもよかった。次の言葉を聞くまでは。
「出来うる限り手を貸しましょう。その代わり貴方たちの手も借ります」
手を貸す、であれば、それは、あまりにも簡単なことだった。続いた言葉は、そうではなかった。
「もし、――」
貼り付けていた微笑みが崩れるような、重く、重く――要石を握らされるような。
けれど、今まで背負ってきたものの数に比べれば、あまりにも軽かったはずなのに、何故だろう。まじまじと見て、ひとつだけ頷いた。
責任を背負うことには慣れていた。責任を背負うのなら他人がいい。責任を放棄するのなら、バケモノの方がもっといい。食い殺してしまえばいいだけだ。
躊躇いはどこからやってくるのだろう。



ENo.151 ガズエット とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
ENo.548 葵 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.909 グノウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.931 迦楼羅 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| フェデルタ 「……」 |
フェデルタ(165) から 鉄板 を手渡しされました。
ItemNo.4 エナジー棒 を食べました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|
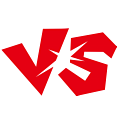 |
鋼響戦隊
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 8 増加!
影響力が 8 増加!



グノウ(909) に ItemNo.20 触手 を送付しました。
ユキ(424) に ItemNo.9 山査子 を送付しました。
グノウ(909) から 鉄板 を受け取りました。
 |
グノウ 「肉が焼けます。」 |
領域LV を 5 DOWN。(LV25⇒20、+5CP、-5FP)
料理LV を 25 DOWN。(LV60⇒35、+25CP、-25FP)
魔術LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)
付加LV を 30 UP!(LV0⇒30、-30CP)
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.18 お肉 から料理『揚げたて唐揚げ(塩味)』をつくりました!
迦楼羅(931) の持つ ItemNo.19 お肉 から料理『ビーフ10割肉まん』をつくりました!
グノウ(909) の持つ ItemNo.27 夙迎のツバメ に ItemNo.17 腐肉 を付加しました!
ケイ(1357) とカードを交換しました!
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア)
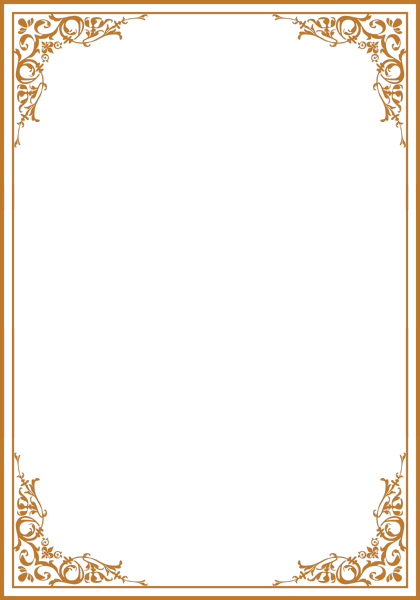
イディオータ を研究しました!(深度0⇒1)
イディオータ を研究しました!(深度1⇒2)
イディオータ を研究しました!(深度2⇒3)
ファイアボルト を習得!
カタラクト を習得!
ヒートイミッター を習得!
クリムゾンスカイ を習得!
上書き付加 を習得!
火の祝福 を習得!
セイクリットファイア を習得!
マナバースト を習得!
大爆発 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



フェデルタ(165) は ボロ毛布 を入手!
スズヒコ(244) は タイヤ片 を入手!
グノウ(909) は タイヤ片 を入手!
迦楼羅(931) は タイヤ片 を入手!
フェデルタ(165) は 赤い薔薇 を入手!
迦楼羅(931) は ビーフ を入手!
グノウ(909) は 赤い薔薇 を入手!
フェデルタ(165) は ビーフ を入手!
スズヒコ(244) は 不思議な食材 を入手!
グノウ(909) は 赤い薔薇 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
迦楼羅(931) のもとに ホスト が興味津々な様子で近づいてきます。
迦楼羅(931) のもとに ネギさん がものすごい勢いで駆け寄ってきます。



ヒノデ区 N-6(道路)に移動!(体調26⇒25)
ヒノデ区 O-6(草原)に移動!(体調25⇒24)
ヒノデ区 O-5(森林)に移動!(体調24⇒23)
ヒノデ区 O-4(森林)に移動!(体調23⇒22)
ヒノデ区 O-3(森林)に移動!(体調22⇒21)





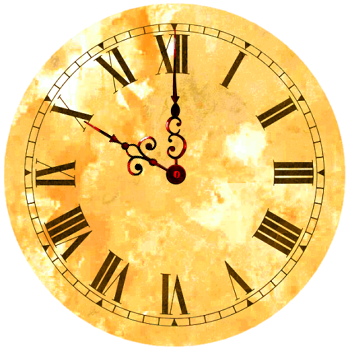
[822 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[375 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[396 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[117 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[185 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
 |
アンドリュウ 「ヘーイ!皆さんオゲンキですかー!!」 |
 |
ロジエッタ 「チャット・・・・・できた。・・・ん、あれ・・・?」 |
 |
エディアン 「あらあら賑やかですねぇ!!」 |
 |
白南海 「・・・ンだこりゃ。既に退室してぇんだが、おい。」 |
チャット画面に映る、4人の姿。
 |
ロジエッタ 「ぁ・・・ぅ・・・・・初めまして。」 |
 |
アンドリュウ 「はーじめまして!!アンドウリュウいいまーすっ!!」 |
 |
エディアン 「はーじめまして!エディアンカーグいいまーすっ!!」 |
 |
白南海 「ロストのおふたりですか。いきなり何用です?」 |
 |
アンドリュウ 「用・・・用・・・・・そうですねー・・・」 |
 |
アンドリュウ 「・・・特にないでーす!!」 |
 |
ロジエッタ 「私も別に・・・・・ ・・・ ・・・暇だったから。」 |
少しの間、無音となる。
 |
エディアン 「えぇえぇ!暇ですよねー!!いいんですよーそれでー。」 |
 |
ロジエッタ 「・・・・・なんか、いい匂いする。」 |
 |
エディアン 「ん・・・?そういえばほんのりと甘い香りがしますねぇ。」 |
くんくんと匂いを嗅ぐふたり。
 |
アンドリュウ 「それはわたくしでございますなぁ! さっきまで少しCookingしていたのです!」 |
 |
エディアン 「・・・!!もしかして甘いものですかーっ!!?」 |
 |
アンドリュウ 「Yes!ほおぼねとろけるスイーツ!!」 |
 |
ロジエッタ 「貴方が・・・?美味しく作れるのかしら。」 |
 |
アンドリュウ 「自信はございまーす!お店、出したいくらいですよー?」 |
 |
ロジエッタ 「プロじゃないのね・・・素人の作るものなんて自己満足レベルでしょう?」 |
 |
アンドリュウ 「ムムム・・・・・厳しいおじょーさん。」 |
 |
アンドリュウ 「でしたら勝負でーすっ!! わたくしのスイーツ、食べ残せるものなら食べ残してごらんなさーい!」 |
 |
エディアン 「・・・・・!!」 |
 |
エディアン 「た、確かに疑わしい!素人ですものね!!!! それは私も審査しますよぉー!!・・・審査しないとですよッ!!」 |
 |
アンドリュウ 「かかってこいでーす! ・・・ともあれ材料集まんないとでーすねー!!」 |
 |
ロジエッタ 「大した自信ですね。私の舌を満足させるのは難しいですわよ。 何せ私の家で出されるデザートといえば――」 |
 |
エディアン 「皆さん急務ですよこれは!急務ですッ!! ハザマはスイーツ提供がやたらと期待できちゃいますねぇ!!」 |
3人の様子を遠目に眺める白南海。
 |
白南海 「まぁ甘いもんの話ばっか、飽きないっすねぇ。 ・・・そもそも毎時強制のわりに、案内することなんてそんな無ぇっつぅ・・・な。」 |
 |
白南海 「・・・・・物騒な情報はノーセンキューですがね。ほんと。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



たのしいおともだち
|
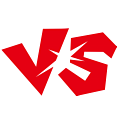 |
痛撃は紳士の嗜みですわよ!
|


ENo.244
鈴のなる夢

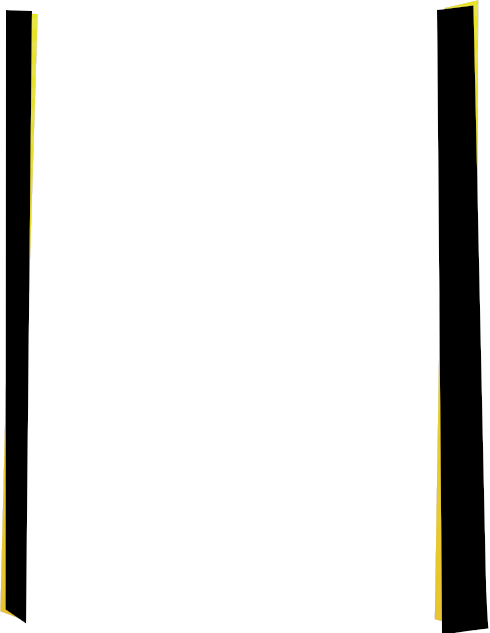
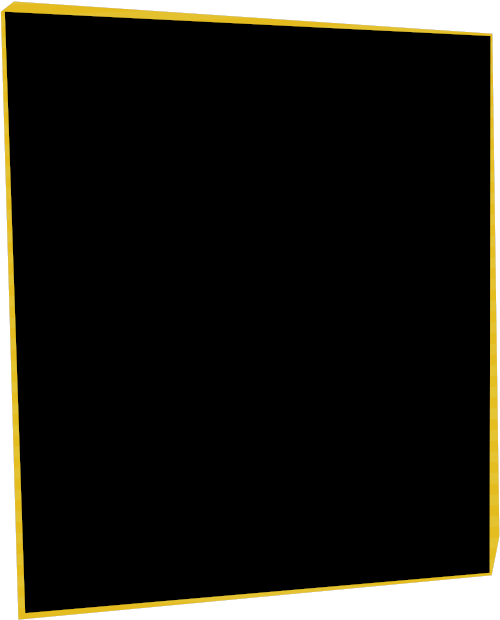
ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
▼Akemi Yoshino / 吉野暁海
創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。
軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。
イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。
ENo165 吉野俊彦は弟。
▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室
名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。
大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。
所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。
特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。
荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。
▼鈴のなる夢
異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。
一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。
関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。
ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。
【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。
この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。
21 / 30
413 PS
ヒノデ区
O-3
O-3







痛撃友の会
5
ログまとめられフリーの会
眼鏡の会
3
アイコン60pxの会
2
#片道切符チャット
#交流歓迎
1
アンジ出身イバラ陣営の集い
7
長文大好きクラブ
1
自我とか意思とかある異能の交流会
2
カード報告会
7
とりあえず肉食う?
4



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |
| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | - | - | 【射程3】 |
| 4 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
| 5 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |
| 7 | 花の護り | 装飾 | 40 | 強靭10 | 回復10 | - | |
| 8 | ハードカバークロウ | 武器 | 35 | 衰弱10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | タイヤ片 | 素材 | 20 | [武器]増幅15(LV35)[防具]反撃15(LV30)[装飾]気合15(LV35) | |||
| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | - | - | |
| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |
| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||
| 20 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 21 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 付加 | 30 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 35 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 8 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 練2 | フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アンダークーリング | 6 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| 練2 | ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ブレイブハート | 10 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 6 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| 練2 | セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |
| グレイシア | 6 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |
| サモン:ビーフ | 6 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 練3 | 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 |
| 治癒領域 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
けだまタックル (ピンポイント) |
0 | 50 | 敵:痛撃 | |
|
アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
《イレイザー》 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
|
注射器 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 練3 |
イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 |
|
ショップカード (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| 練2 |
大爆発 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
| 練2 |
唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
|
プライドファイト (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
|
狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |
5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]イディオータ |
| [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]フレイムインパクト | [ 3 ]フィジカルブースター |
| [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]レーヴァテイン |
| [ 3 ]プチメテオカード |

PL / 紙箱みど